解説記事2009年09月07日 【実務解説】 未曾有の景気悪化に対応する法人税実務 第2回 子会社・関連会社への支援を行う場合および欠損填補のための無償減資を行う場合(2009年9月7日号・№321)
実務解説
未曾有の景気悪化に対応する法人税実務
第2回 子会社・関連会社への支援を行う場合および欠損填補のための無償減資を行う場合
アクタスマネジメントサービス/アクタス税理士法人 加藤幸人
Ⅱ.景気悪化時に起こる特有の税務ポイント(承前)
2.子会社・関連会社への支援を行う場合
(1)概 要 経営環境の悪化によって、子会社・関連会社が経営不振に陥ってしまう場合も多い。この場合、親会社の経営判断として、子会社・関連会社を解散させる、もしくは経営権を売却するなどの整理をすることにより債務の引受け、債権放棄その他の損失負担を行うことがある。また、倒産を防止するため無償貸付けや、低利の貸付け、債権放棄を行うことにより再建させることも考えられる。
このような子会社・関連会社支援を行うことは、税務上の取扱いにおいては、寄附金とみなされる可能性があり、その点を充分に検討する必要がある。
(2)寄附金について 寄附金の額とは、法人税法37条7項において「金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその贈与時又はその供与時の価額」であるとされている。すなわち、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与は寄附とみなされる。
子会社・関連会社を整理もしくは再建させる際には、子会社の債権を放棄したり、通常よりも低い金利で貸付を行うといった行為が想定されるが、これらの取引は、子会社・関連会社に対する「経済的利益の贈与又は無償の供与」と考えられる。このため、寄附金課税の対象といえるが、経済合理性が存する場合には、その贈与または供与した経済的利益の額は、寄附金に該当しない取扱いになる。
(3)子会社・関連会社支援の経済合理性 経済合理性があると判断される場合とは、供与する支援者側からみて、支援による損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかであることや、子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づくことなど相当な理由がある場合となる(図表1参照)。
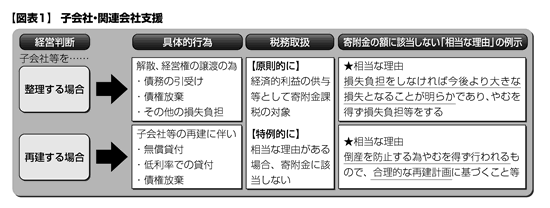
相当な理由の判断基準については、法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)、9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)で概念的に示されているが、具体的には、国税庁ホームページ・タックスアンサーの「No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」でより詳しく公表されている。
(4)質疑応答事例による具体的検討について 子会社等を整理または再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かは、次のような点について、総合的に検討することになる。
① 損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
② 子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
③ 損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
④ 損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
⑤ 整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
⑥ 損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
⑦ 損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし、または免れていないか)。
① 子会社等の範囲について 子会社等については、資本関係のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者も含まれることになる。
② 子会社等は経営危機に陥っているか 経営危機に陥っているか否かの判断は、一般的に、その子会社等が債務超過の状態にあり、資金繰りが逼迫している場合が該当する。
ただし、債務超過の状態にあっても自力再建の可能性がある場合に支援することは、寄附金課税の対象となる。
逆に、許認可事業を行っている法人で、赤字決算のままでは許認可が取り消されるような場合、または、事業譲渡において事業譲受側からの要望で赤字圧縮を求められている場合には、債務超過でなくても、合理的な理由があるとして、寄附金課税の対象とならないこともある。
③ 支援者にとっての相当な理由について 損失負担等を行う相当な理由としては、整理により、今後蒙るであろう大きな損失を回避できる場合、または、再建することにより、残債権の回収可能性が高まったり、支援者の信用が維持される場合などが該当することになる。
④ 支援額の合理性について 損失負担の支援額の合理性は、次の2点から検討することになる。
イ)整理、再建のための必要最低限の金額であるか。
ロ)子会社等の財務内容、営業状況の見直し等および自助努力を加味して検討されているか。
支援金額が過剰と認められる場合、過剰額が寄附金課税の対象となるので、注意しなければならない。
⑤ 再建管理等の有無について 一般に、整理は速やかに行われるものであるため、整理計画の検討を要しないものと考えられている。しかし、整理計画が長期にわたる場合には、整理計画の実施状況に関する管理が的確に行われるか否かの検討が必要となる。
一方、再建においては、再建計画により、再建状況を把握する必要がある。計画より順調に再建が進んだ場合には、計画期間の途中でも支援を打ち切るようにするなどの管理が必要となる。
再建管理の具体的な方法としては、支援者側から役員を派遣することや再建管理状況の報告を定期的(毎年、毎四半期、毎月など)に行わせる方法がある。
⑥ 支援者の範囲の相当性について 支援者の範囲として、関係者が複数いる場合において、子会社等との事業関連性が強い支援者が加わっていないときは、事業関連性の強弱、支援規模、支援能力等の個別事情から判断されることになる。
なお、支援者の範囲は、当事者間の合意により決定されるものである。
⑦ 支援割合の合理性について 上記⑥と関連して、関係者が複数いる場合、支援者ごとの負担割合は、出資状況、経営参加状況、融資状況等の事業関連性の強弱や支援能力からみて合理的に検討されることになる。
具体的には、負担総額を融資残高比で按分した金額としたり、出資比率、融資残高比率、役員派遣割合の総合比率で按分し、個々の負担能力調整を行ったうえで決定する方法がある。
上記検討項目は図表2のチェックシートで確認できる。
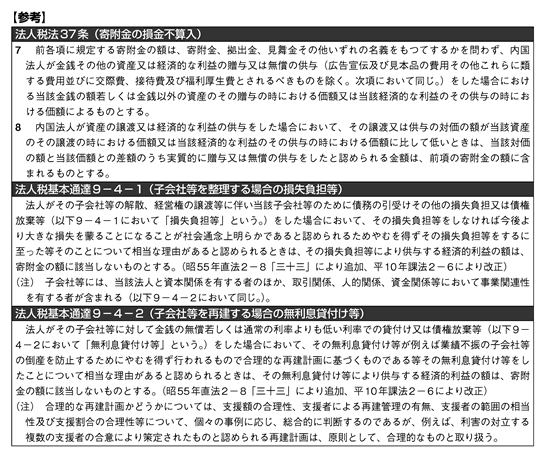
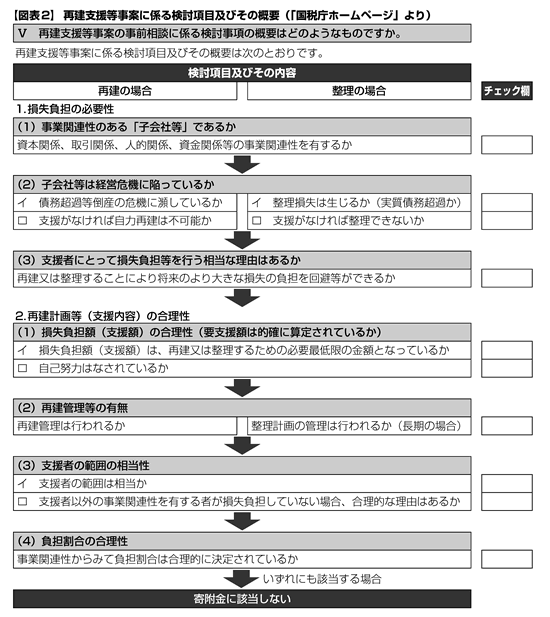
(5)適用にあたっての注意点 子会社・関連会社支援については、支援者にとって、寄附金課税になるのかどうかが所得計算上の大きなポイントとなる。寄附金課税されないためには、支援の合理性が重要となるが、その判断に至った経緯を十分に説明できる資料等を保存しておくことが必要といえる。なお、各国税局においては、相談窓口が設置され事前相談に応じているため、利用を検討するのは有用である。
ただし、この相談は、「事前に許可又は認可をあたえるというようなものではありません。」とあり、支援者が行う損失負担等が寄附金に該当するか否かを検討するもので、法的に効力のあるものではないので、その点は注意する必要がある。
3.欠損填補のための無償減資を行う場合
(1)概 要 損益の悪化により欠損が発生している場合、減資により欠損填補をし、財務体質の強化を検討することがある。減資をする目的としては、純資産の部の改善と、今後の配当財源の確保ということが挙げられる(図表3参照)。
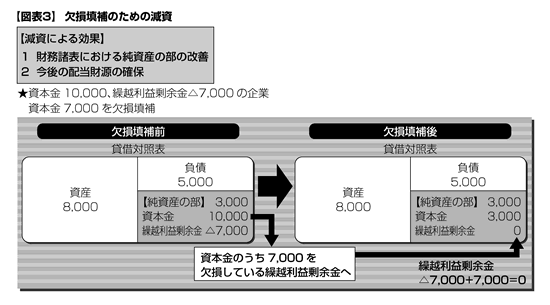
(2)会計上の取扱い 会社法上、無償減資により欠損填補することは、例外的に資本と利益の混同が許され、認められているものであるが、株主資本内部の計数変動であり、会社財産が社外に流出することはない。
資本金の減少額の全額を欠損填補に充当する場合は、効力発生日に「(借方)資本金××× (貸方)繰越利益剰余金×××」と仕訳をすることになる(図表4参照)。
財務諸表への記載については、株主資本等変動計算書の記載がポイントとなり、当期変動額に変動事由の「資本金の減少」を記載し、資本金襴の減少額および繰越利益剰余金の欄の増加額を記載することになる。
(3)税務上の取扱い 法人税の取扱いにおいて、欠損填補の無償減資は、資本金の減少と同額の資本積立金の増加となり、結果的に資本金と資本積立金の合計である資本金等の額に変動は生じない。つまり、欠損填補の無償減資取引は、資本取引になり、この取引から課税関係が生じることはない。
減少した欠損(その他利益剰余金)については欠損填補前の状態に戻す調整を利益積立金額の計算で行うことになる(図表4参照)。
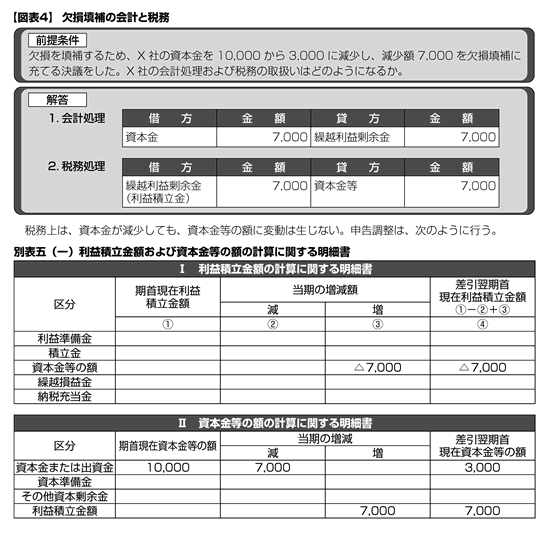 なお、資本金が1億円以下になると法人税において、次のような中小法人の特典がある。
なお、資本金が1億円以下になると法人税において、次のような中小法人の特典がある。
・軽減税率の適用(年800万円以下の所得について30%が18%に)
・交際費課税優遇(年600万円までの定額控除限度額)
・貸倒引当金の特例(法定繰入率の使用)
・留保金課税の停止
・少額減価償却資産の特例(即時償却できる取得価額が30万円未満に)
・教育訓練費の税額控除や試験研究費の税額控除などの特典
一方、地方税である法人事業税の取扱いについては、資本金1億円超の法人が、外形標準課税の対象となるため、無償減資により資本金が1億円以下になった場合には対象から外れる。また、資本割の計算において平成18年5月1日以後に資本金および資本準備金を減少し、剰余金として計上した額を欠損填補に充てた場合、平成18年5月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人事業税に限り、資本金等の額からその欠損填補に充てた金額を控除することができる。
(4)適用にあたっての注意点 減資を行う際は、会社法上の手続として、原則株主総会の特別決議を必要とし、債権者保護手続として、減資の公告と知れている債権者に対し各別に催告する必要があり、利害関係者との関係を考慮し手続を進めることが重要である。
(かとう・ゆきと)
未曾有の景気悪化に対応する法人税実務
第2回 子会社・関連会社への支援を行う場合および欠損填補のための無償減資を行う場合
アクタスマネジメントサービス/アクタス税理士法人 加藤幸人
Ⅱ.景気悪化時に起こる特有の税務ポイント(承前)
2.子会社・関連会社への支援を行う場合
(1)概 要 経営環境の悪化によって、子会社・関連会社が経営不振に陥ってしまう場合も多い。この場合、親会社の経営判断として、子会社・関連会社を解散させる、もしくは経営権を売却するなどの整理をすることにより債務の引受け、債権放棄その他の損失負担を行うことがある。また、倒産を防止するため無償貸付けや、低利の貸付け、債権放棄を行うことにより再建させることも考えられる。
このような子会社・関連会社支援を行うことは、税務上の取扱いにおいては、寄附金とみなされる可能性があり、その点を充分に検討する必要がある。
(2)寄附金について 寄附金の額とは、法人税法37条7項において「金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその贈与時又はその供与時の価額」であるとされている。すなわち、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与は寄附とみなされる。
子会社・関連会社を整理もしくは再建させる際には、子会社の債権を放棄したり、通常よりも低い金利で貸付を行うといった行為が想定されるが、これらの取引は、子会社・関連会社に対する「経済的利益の贈与又は無償の供与」と考えられる。このため、寄附金課税の対象といえるが、経済合理性が存する場合には、その贈与または供与した経済的利益の額は、寄附金に該当しない取扱いになる。
(3)子会社・関連会社支援の経済合理性 経済合理性があると判断される場合とは、供与する支援者側からみて、支援による損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかであることや、子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づくことなど相当な理由がある場合となる(図表1参照)。
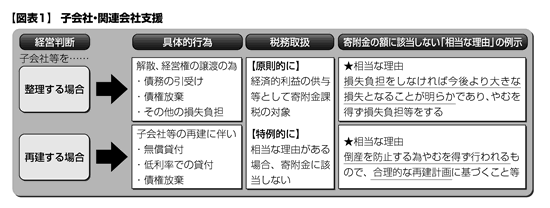
相当な理由の判断基準については、法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)、9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)で概念的に示されているが、具体的には、国税庁ホームページ・タックスアンサーの「No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」でより詳しく公表されている。
(4)質疑応答事例による具体的検討について 子会社等を整理または再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かは、次のような点について、総合的に検討することになる。
① 損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
② 子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
③ 損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
④ 損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
⑤ 整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
⑥ 損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
⑦ 損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし、または免れていないか)。
① 子会社等の範囲について 子会社等については、資本関係のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者も含まれることになる。
② 子会社等は経営危機に陥っているか 経営危機に陥っているか否かの判断は、一般的に、その子会社等が債務超過の状態にあり、資金繰りが逼迫している場合が該当する。
ただし、債務超過の状態にあっても自力再建の可能性がある場合に支援することは、寄附金課税の対象となる。
逆に、許認可事業を行っている法人で、赤字決算のままでは許認可が取り消されるような場合、または、事業譲渡において事業譲受側からの要望で赤字圧縮を求められている場合には、債務超過でなくても、合理的な理由があるとして、寄附金課税の対象とならないこともある。
③ 支援者にとっての相当な理由について 損失負担等を行う相当な理由としては、整理により、今後蒙るであろう大きな損失を回避できる場合、または、再建することにより、残債権の回収可能性が高まったり、支援者の信用が維持される場合などが該当することになる。
④ 支援額の合理性について 損失負担の支援額の合理性は、次の2点から検討することになる。
イ)整理、再建のための必要最低限の金額であるか。
ロ)子会社等の財務内容、営業状況の見直し等および自助努力を加味して検討されているか。
支援金額が過剰と認められる場合、過剰額が寄附金課税の対象となるので、注意しなければならない。
⑤ 再建管理等の有無について 一般に、整理は速やかに行われるものであるため、整理計画の検討を要しないものと考えられている。しかし、整理計画が長期にわたる場合には、整理計画の実施状況に関する管理が的確に行われるか否かの検討が必要となる。
一方、再建においては、再建計画により、再建状況を把握する必要がある。計画より順調に再建が進んだ場合には、計画期間の途中でも支援を打ち切るようにするなどの管理が必要となる。
再建管理の具体的な方法としては、支援者側から役員を派遣することや再建管理状況の報告を定期的(毎年、毎四半期、毎月など)に行わせる方法がある。
⑥ 支援者の範囲の相当性について 支援者の範囲として、関係者が複数いる場合において、子会社等との事業関連性が強い支援者が加わっていないときは、事業関連性の強弱、支援規模、支援能力等の個別事情から判断されることになる。
なお、支援者の範囲は、当事者間の合意により決定されるものである。
⑦ 支援割合の合理性について 上記⑥と関連して、関係者が複数いる場合、支援者ごとの負担割合は、出資状況、経営参加状況、融資状況等の事業関連性の強弱や支援能力からみて合理的に検討されることになる。
具体的には、負担総額を融資残高比で按分した金額としたり、出資比率、融資残高比率、役員派遣割合の総合比率で按分し、個々の負担能力調整を行ったうえで決定する方法がある。
上記検討項目は図表2のチェックシートで確認できる。
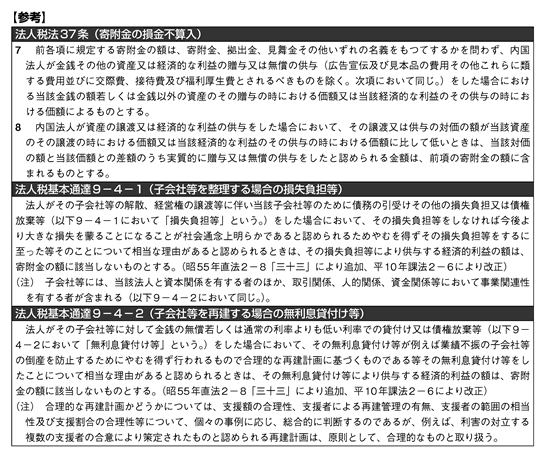
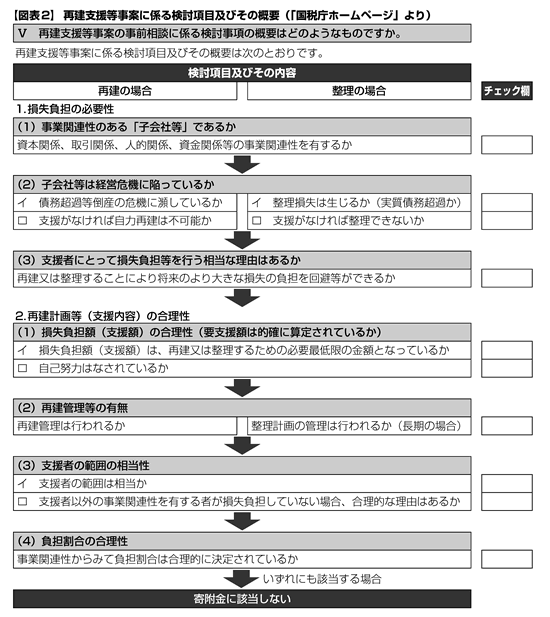
(5)適用にあたっての注意点 子会社・関連会社支援については、支援者にとって、寄附金課税になるのかどうかが所得計算上の大きなポイントとなる。寄附金課税されないためには、支援の合理性が重要となるが、その判断に至った経緯を十分に説明できる資料等を保存しておくことが必要といえる。なお、各国税局においては、相談窓口が設置され事前相談に応じているため、利用を検討するのは有用である。
ただし、この相談は、「事前に許可又は認可をあたえるというようなものではありません。」とあり、支援者が行う損失負担等が寄附金に該当するか否かを検討するもので、法的に効力のあるものではないので、その点は注意する必要がある。
3.欠損填補のための無償減資を行う場合
(1)概 要 損益の悪化により欠損が発生している場合、減資により欠損填補をし、財務体質の強化を検討することがある。減資をする目的としては、純資産の部の改善と、今後の配当財源の確保ということが挙げられる(図表3参照)。
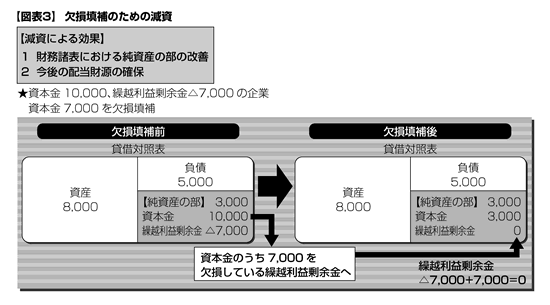
(2)会計上の取扱い 会社法上、無償減資により欠損填補することは、例外的に資本と利益の混同が許され、認められているものであるが、株主資本内部の計数変動であり、会社財産が社外に流出することはない。
資本金の減少額の全額を欠損填補に充当する場合は、効力発生日に「(借方)資本金××× (貸方)繰越利益剰余金×××」と仕訳をすることになる(図表4参照)。
財務諸表への記載については、株主資本等変動計算書の記載がポイントとなり、当期変動額に変動事由の「資本金の減少」を記載し、資本金襴の減少額および繰越利益剰余金の欄の増加額を記載することになる。
(3)税務上の取扱い 法人税の取扱いにおいて、欠損填補の無償減資は、資本金の減少と同額の資本積立金の増加となり、結果的に資本金と資本積立金の合計である資本金等の額に変動は生じない。つまり、欠損填補の無償減資取引は、資本取引になり、この取引から課税関係が生じることはない。
減少した欠損(その他利益剰余金)については欠損填補前の状態に戻す調整を利益積立金額の計算で行うことになる(図表4参照)。
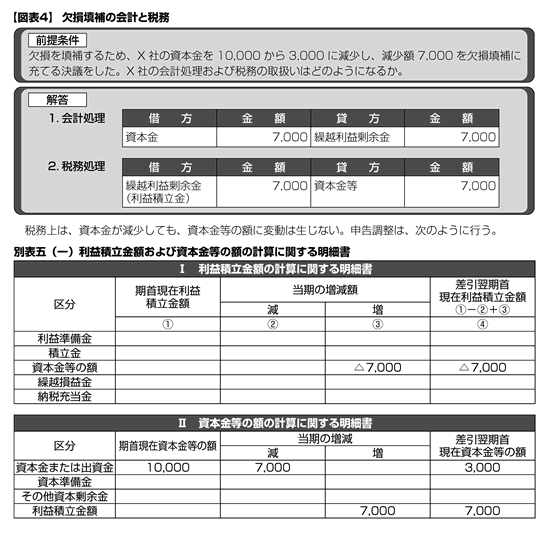 なお、資本金が1億円以下になると法人税において、次のような中小法人の特典がある。
なお、資本金が1億円以下になると法人税において、次のような中小法人の特典がある。・軽減税率の適用(年800万円以下の所得について30%が18%に)
・交際費課税優遇(年600万円までの定額控除限度額)
・貸倒引当金の特例(法定繰入率の使用)
・留保金課税の停止
・少額減価償却資産の特例(即時償却できる取得価額が30万円未満に)
・教育訓練費の税額控除や試験研究費の税額控除などの特典
一方、地方税である法人事業税の取扱いについては、資本金1億円超の法人が、外形標準課税の対象となるため、無償減資により資本金が1億円以下になった場合には対象から外れる。また、資本割の計算において平成18年5月1日以後に資本金および資本準備金を減少し、剰余金として計上した額を欠損填補に充てた場合、平成18年5月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人事業税に限り、資本金等の額からその欠損填補に充てた金額を控除することができる。
(4)適用にあたっての注意点 減資を行う際は、会社法上の手続として、原則株主総会の特別決議を必要とし、債権者保護手続として、減資の公告と知れている債権者に対し各別に催告する必要があり、利害関係者との関係を考慮し手続を進めることが重要である。
(かとう・ゆきと)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















