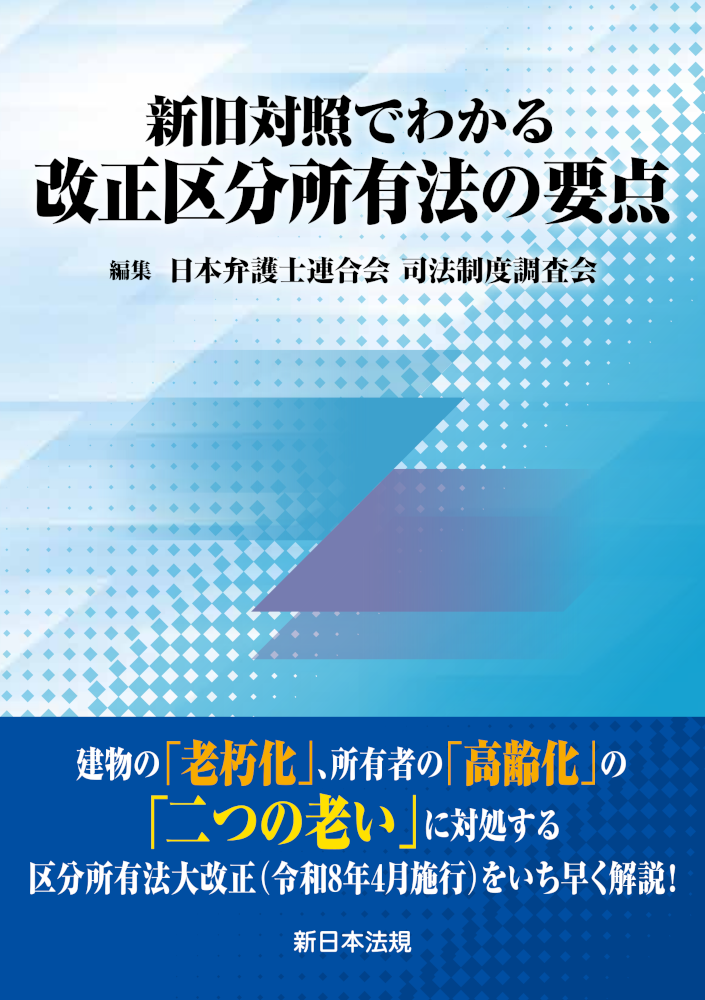解説記事2010年10月11日 【実務解説】 清算所得課税の廃止と欠損金─債務免除を受ける場合の問題点(2010年10月11日号・№373)
実務解説
清算所得課税の廃止と欠損金
─債務免除を受ける場合の問題点
さくら綜合事務所 公認会計士・不動産鑑定士・税理士 杉本 茂
さくら綜合事務所 シニアアソシエイト 林 達男
Ⅰ.はじめに
平成22年税制改正における大きな改正点の一つに清算所得課税の廃止がある。これは、法人税の計算について、清算事業年度は従来、財産計算で課税していたものを、通常の事業年度と同様の所得計算により課税するというものである。詳細は後段にて説明するが、これにより、いわゆる第二会社方式(脚注1)を含む事業の再生・再編の実務上、赤字会社の再編・再生実務において多額の納税が発生するケースが懸念されることとなっただけでなく、継続企業の前提を欠く解散後の法人に公正妥当会計基準を適用するというこれまでにない新たな次元の問題に直面することとなった。
Ⅱ.解散・清算手続の種類と事業年度の概要
清算所得課税の改正の前に、まず、本改正は平成22年10月1日以降解散する事業年度から適用されることから、基本的な事業年度の仕組みについて確認することとする。
法人の基本的な倒産手続は、①通常清算、②特別清算、③破産、の3種類に分けられるが、いずれについても、税務申告の原則的な仕組みは同じであり、解散事業年度と清算事業年度の少なくとも2回の申告が必要である。なお、会社更生や民事再生手続の開始または認可決定では、解散したものとされないが、破産手続の開始は法人税法上の解散に含まれ(会社法471五、最高判平成4年10月20日他、窪田悟嗣編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会)23頁参照)、解散の手続は無いが、破産手続開始決定日が税務上は解散事業年度の末日となる。
なお、内国法人の事業年度については、解散した場合には、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間となっており、また、清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間となっている(法法14)。
つまり、解散後、残余財産が確定するまでの間に、事業年度が終了した場合には、別途その事業年度末日までの税務申告が必要となる。なお、国税庁の法令解釈通達によると、株式会社等が解散した場合には、会社法494条における清算株式会社の清算事務年度の規定に従い、法人税上の事業年度も解散日の1年後に終了することとなる(法基通1-2-9)が、破産や持分会社の解散の場合には清算事務年度の規定がそもそもないことから、定款上の事業年度のままとなる(例えば、定款上の事業年度が4月1日から3月31日の法人が2月末に破産手続開始決定を受けた場合には、同年の3月に事業年度が終了することとなる。)。
平成22年度税制改正で課税方式が変わり、問題となるのは、清算中の事業年度における確定申告である。
Ⅲ.清算所得課税の廃止
1.従来の課税方式 従来の清算確定申告においては、下記の算式でいわゆる財産法的な手法により清算所得の計算を行っていた。この方法により解散時に所有していた残余財産の時価について、過年度に資本金等に対応する部分、過年度に課税された、或いは、非課税の部分である利益積立金を控除した残額に対して(清算年度に課される事業税が損金算入されないことを考慮した税率である。)27.1%の税率を乗じて法人税を計算する仕組みである。
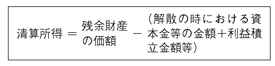
2.税制改正における基本的な考え方 今回の改正においてこの清算所得課税の制度が廃止された結果、平成22年10月1日以降解散した法人については、清算時の課税も財産法ではなくいわゆる損益法、すなわち益金の額から損金の額を控除して所得金額を算出し、解散前と同様に各事業年度の所得に対する法人税が課せられることとなった(事業税の取扱い等相違点もある。)。
(1)損益法と財産法で所得が異なる場面 損益法により通常の所得計算を行ったとしても、図表1の通り、税務調整が入らないシンプルなケースの場合、その課税標準は従来の清算所得と異ならないはずである(脚注2)。
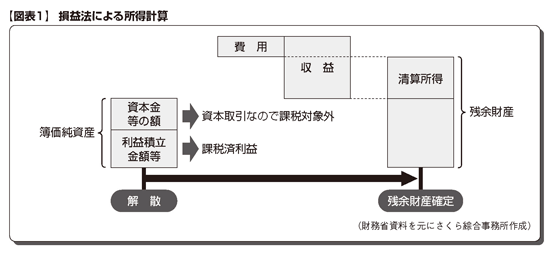
では、どのような時に大きな問題が発生するかというと、その原因は主として二つ考えられる。第一は、欠損金と債務免除益等清算期の所得が相殺できない場合であり、もう一つは、過年度に計上した架空資産や貸付金等の評価損又は清算中に支払った退職金(脚注3)や交際費等(脚注4)が清算期に損金に計上できない場合である。
前者については、例えば債務超過の会社等で清算期に債務免除等を受ける会社の場合、従来の計算では残余財産(資産-負債)の時価を計算する際に資産から差し引く負債の金額が減少する結果、残余財産額が多くなるものの、残余財産の額が控除する資本金等及び利益積立金等の範囲内であれば清算所得はゼロであって課税が発生しなかった。しかし、改正後の計算方法では、その事業年度に発生した債務免除益等による収益を、青色欠損金を含む損金で充当できない場合、残余財産がないのに課税所得が発生してしまう場合があるが、結論から言うと、今回の改正で一定の場合に期限切れ欠損金を充当することで手当てされている。
しかし、後者の場合については手当てされていない。後者の場合に関しては、従来の課税方法では問題があるケースもありえたので、今回改めてクローズアップされたと言うこともできよう。
(2)期限切れ欠損金の利用 例えば、解散時において資産簿価(=時価)10、負債50、資本金等がない場合に清算期に負債を40債務免除したとしよう。従来の計算方法では、残余財産はなくなり、清算所得の課税はなくなる。しかし、改正後は清算期の債務免除益40に対して、充当する欠損金がなければ課税が発生してしまうのである。
もっとも、前述のような財務状況の場合、資本金等に相当する繰越欠損金があるはずであるが、当該欠損金が、青色欠損金として事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のものである等の要件を満たさなければ、損金算入できない(法法57、57の2)。
つまり、従来の課税方法によれば、過去の欠損金と清算事業年度の所得とが自動的に相殺される結果となっていたのであるが、今回の改正のより、期限切れ欠損金相当額が相殺されずに、課税所得が残るケースが想定されることとなったものである。
したがって図表2のような場合で、期限切れ欠損金を使用できないとすると、清算中の事業年度において課税所得が発生することになるが、今回の改正で一定の手当てがなされている。それは、青色欠損金を控除して、なお課税所得が発生するときは、残余財産がないと見込まれることを要件として期限切れ欠損金が損金の額に算入できるという手当てであり、青色欠損金控除後の所得を限度として損金に算入できることとなった(法法59③)。
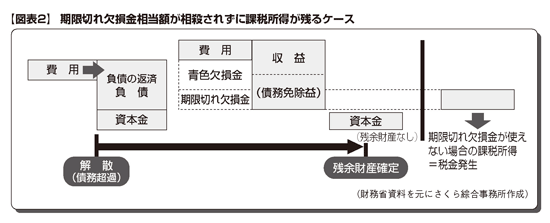
なお期限切れ欠損金とは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額であり、下記①から②を控除した金額である(法令118、法基通12-3-2)。
① 当該事業年度の確定申告書に添付する別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」の合計額がマイナスである場合のその値
② 青色欠損金・災害損失欠損金(損金算入額)
3.具体的な取扱い
(1)残余財産のないことの疎明方法及び破産時における継続的な申告が困難な場合の期限切れ欠損金の額 期限切れ欠損金の使用が認められる要件は「残余財産がないと見込まれるとき」であり、「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による(法基通12-3-7)。
この規定の適用を受けようとする場合には、「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」を確定申告書に添付することとされている(法規26の6①三)ため、事業年度末の時点での実態貸借対照表を添付(法基通12-3-9)し、残余財産がないことを示す必要がある。その場合の時価は財務省主税局の「平成22年度税制改正の解説」(277頁参照)では単に「通常の時価ではなく処分価額によることになると考えられます」としているが、法人税基本通達12-3-9(注)では事業譲渡の場合には通常の使用収益価額によるものとしている。
制度上の特例を受ける納税者に疎明させることはやむを得ないかもしれないが、破産を始め、倒産・事業再生の局面では帳簿記録が散逸していることも多く、課税の回避のための資料収集の時間・費用が膨大となる可能性もある。この点について、法人税基本通達12-3-8において、解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当するとされおり、財務省主税局の「平成22年度税制改正の解説」(277頁参照)においても、破産手続開始の決定による解散の場合には通常残余財産が無い場合に該当するとされていることから、破産手続等の場合には、実態貸借対照表の添付は不要になると考えられる。また、事業再生研究機構より公表されている「平成22年度税制改正後の清算中の法人税申告における実務上の取扱いについて」(脚注5)(以下、「事業再生研究機構報告書」という。)においても、下記のように述べられている。これは倒産や事業再生の実務上妥当な見解と考えられる。
なお、従来の破産手続を見ると、破産会社では、破産前の法人税申告を適切に行っていなかったり、従業員を申立時等に解雇した結果、会計帳簿が散逸しているなどして、通常の継続的な申告を行うことが困難な状態となっている場合が多く存在する。そのため、開始決定時点以降の情報のみで申告書の作成をせざるを得ないこととなるが、従来は財産計算であったことから、最終的に資産と負債がどれだけあるかで計算できたため、支障はなかった。しかし、上記のとおり、期限切れ欠損金を使う必要があるケースが想定され、期限切れ欠損金を使用する場合には、確定申告書に明細の添付、つまり、確定申告を行うことが要件となっていることから、今後の破産手続においては、清算中の確定申告に当たり、過去の累積値である、期限切れ欠損金の額を把握する必要がある(仮に期限切れ欠損金を使わない場合にも、申告書に記載箇所があることから、いずれにせよ金額は把握しなければならない。)。
このような場合の対応方法についても、事業再生研究機構報告書において、簡便な計算方法が述べられている。
(2)仮装経理等について、還付手続を行った場合の期限切れ欠損金
過去に過大納付があり、更正により過大納付額が還付された場合には、期限切れ欠損金の計上の根拠となる別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」も更正されるため、期限切れ欠損金の額は通常多くなる。したがって、残余財産がないと見込まれることが疎明できる場合には、清算期の債務免除益等の課税の可能性はあまりないだろう。
但し、その過大納付が仮装経理等による場合、損金算入要件が課される減価償却、引当金や多くの評価損等の未計上は、通常減額更正の対象とならずに解散法人に残り、また、更正の期間制限を徒過した等の理由により税務署長の職権更正が適わなかったそれ以外の要素も解散法人に残留することになる。更には、法人税基本通達9-6-2(実質基準の貸倒損失)のように事実が発生した事業年度での損金計上が求められる(計上時期に制限のある)場合には、清算期間中に評価損の損金計上が認められないということも考えられる。
なお、資産に係る評価損等の未計上は清算手続中に資産の譲渡損等として解消するものもあるが、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行い、同法に基づく財産価額の評定の準備を始めていた事案において、過年度棚卸資産廃棄損の額は、「過年度の棚卸資産に係る粉飾額を計上したものにすぎず、その全額が本件事業年度において生じたものでないことが明らかである」として、過年度棚卸資産廃棄損が否認された事例(脚注7)もある。
この仮装経理の問題は企業再生事由が生じているような場合に発生するだけではなく、健全な会社においても発生する。特に残余財産がある通常清算の場合では、仮装経理を理由とする青色申告の承認の取り消し(脚注8)の可能性も考慮する必要がある。
このように、これら「実在性のない資産」に関しては、清算中も損金に計上することは困難な場合がありうるが、かかる場合には、事業再生研究機構報告書で次のように述べられている。
以上のような要件を満たす場合には、最も古い期間の期首の利益積立金を更正する(期限切れ欠損金とする。)ことが妥当と考える。
(3)通常清算とするための債務免除の額 解散時点においては債務超過の状態におかれていても、債務免除をした結果、残余財産が残ってしまう場合は「残余財産がないと見込まれる」ことにはならないので、免除益をいくら計上するかという点には注意が必要である。債務超過の場合でも、債権者が少数の関係者であるときなどは、債務免除により通常清算手続により清算させることもあると思われる(債務超過のまま株式会社を清算する場合には、原則として特別清算手続によることになる(会社法510)。)。このような場合において、残余財産確定時には債務免除が完了している状態であるので、この時点においては債務超過という状態はなくなるが、「残余財産がないと見込まれる」状態にあるか否かという問題がある。
この点については、法人税基本通達12-3-8を反対解釈して「債務超過状態でなければ残余財産があると見込まれる」とまで解釈する必要はないだろう。つまり、法人税法上の要件が「残余財産がないと見込まれるとき」であるため、残余財産がゼロになるように債務免除を行い、資産=負債の状態で残余財産を確定させることで期限切れ欠損金の額を損金算入できることになると考えられる。
なお、債務の弁済に充当可能な資産が残っているにもかかわらず、債務免除を受けた場合は、債権者側で寄付金課税の問題が生じるおそれもあるので、法人税基本通達9-4-1や9-4-2等を勘案してその経済的合理性を検証する必要がある。
(4)残余財産がわずかに見込まれる資本欠損の会社の場合 清算事業年度において、残余財産がゼロではないものの、資本金が毀損している場合、従来の財産計算においては、原則的には課税所得は発生することはないが、平成22年10月1日以降の損益計算においては、その期の損益から欠損金等を控除して、なお所得が残れば課税所得が発生することとなる。
更に、このような場合で期限切れ欠損金があるときについても、残余財産があるため期限切れ欠損金を使用することができず、その結果、残余財産を超える課税が発生する可能性がある。
(5)その他の期限切れ欠損金の利用特例(特例欠損金)との関係 法人税法59条3項の期限切れ欠損金の損金算入の制度は、法人税法59条1項及び2項に規定される「更生手続き開始の決定」があった場合及び「再生手続開始の決定があったこと」その他一定の事実が生じた場合の期限切れ欠損金の損金算入制度の適用とは別個のものであり、計算方法も異なる(法法59①②、法令117、法基通12-3-1)。これらの制度の適用を受ける事業年度には、清算による期限切れ欠損金の特例を重ねて受けることはできない(法法59③)が、それ以外の年度なら適用を受けることができる。
(6)第二会社方式による場合 事業再生において新会社に優良な事業を移転し、旧会社を不採算部門と合わせて清算してしまう、いわゆる第二会社方式による場合も、通常、清算する会社は債務超過であり、債務免除の問題は生じることとなる。
しかし、第二会社方式の場合、債権者の損金算入の要件を充足させることや、金融機関等が積極的に債務放棄を行うことが難しいことなどもあり、裁判所が介在する特別清算手続をとることが多く、上記の取り扱いを勘案すると、特別清算手続であれば、今回の税制改正が直接的な原因となるような問題は生じないものと考えられる。
Ⅳ.完全支配関係のある親会社からの債務免除
上記のとおり、債務免除がある場合には、赤字会社でも納税の懸念があるが、グループ法人税制の施行に伴い、平成22年10月1日以降の完全支配関係がある会社間での寄付金の額については、支出側で全額損金不算入(法法37②)になるとともに、受入側では益金不算入となる(法法25の2①)。
よって、完全支配関係がある親会社からの債務免除については、そもそも益金の額に算入されないことから、債務免除による納税額の発生の懸念は不要である。
但し、子会社等を整理する場合の損失負担等として、支出側で損金算入する場合(法基通9-4-1、9-4-2)には、受入側においては益金算入になると考えられるため、注意が必要である(図表3参照)。
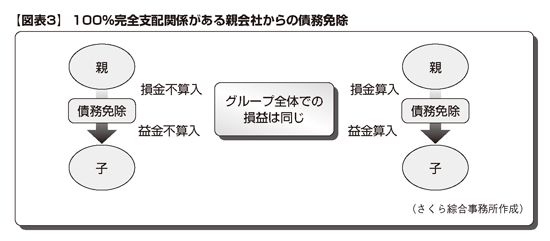
脚注
1 財務状況が悪化している企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また、不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることにより事業の再生を図る手法をいう。中小企業については一定の要件を満たして認定を受ければ、許認可承継等の特典を得ることもできる産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画の認定制度が平成21年度に創設された。
2 但し、通常の事業年度と清算中の事業年度の取扱が異なる点の一つに事業税の損金算入時期がある。通常の事業年度に係る事業税は支払った期の損金算入となるが、清算期間中の事業税のうち、残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金算入ができることとされている(法法62の5⑤)。
3 法基通9-2-28但し書参照。
4 改正前の制度では、通常の所得計算では損金算入が制限される交際費や過大役員報酬や退職金等についても財産法計算上特に制限なく、全額控除が可能であった。
5 http://www.shojihomu.co.jp/jabr/jabr.html又は事業再生研究機構税務問題委員会編『清算法人税申告の実務』(商事法務)を参照。
6 実際の報告書の別紙の計算部分のみ抜粋。
7 裁決事例集No.72-404頁(平成18年11月21日裁決)。本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例。なお、東京地裁において、粉飾決算による棚卸資産の過大計上に関する判決も平成22年9月10日に行われている(平成21年(行ウ)第380号)。
8 法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)[平成12年7月3日課法2-10、課料3-15、査調4-12査察1-31]では、次のいずれかに該当する場合には、原則として、青色申告の承認を取り消すものとしているが、経営責任がとられた事案での減額更正の場合には寛大な取扱いが望まれる。
イ 無申告のために所得金額の決定をした場合又は所得金額の更正をした場合において、その事業年度の当該決定又は更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、当該更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)。
ロ 欠損金額を減額する更正(所得金額があることとなる更正を含む。)をした場合において、その事業年度の当該更正により減少した部分の欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正欠損金額」という。)が、当初の申告に係る欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額。以下「申告欠損金額」という。)の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正欠損金額が500万円に満たないときを除く。)。
ハ 帳簿書類への記載等が不十分である等のため、法第131条(法第147条において準用する場合を含む。)の規定による推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合。
清算所得課税の廃止と欠損金
─債務免除を受ける場合の問題点
さくら綜合事務所 公認会計士・不動産鑑定士・税理士 杉本 茂
さくら綜合事務所 シニアアソシエイト 林 達男
Ⅰ.はじめに
平成22年税制改正における大きな改正点の一つに清算所得課税の廃止がある。これは、法人税の計算について、清算事業年度は従来、財産計算で課税していたものを、通常の事業年度と同様の所得計算により課税するというものである。詳細は後段にて説明するが、これにより、いわゆる第二会社方式(脚注1)を含む事業の再生・再編の実務上、赤字会社の再編・再生実務において多額の納税が発生するケースが懸念されることとなっただけでなく、継続企業の前提を欠く解散後の法人に公正妥当会計基準を適用するというこれまでにない新たな次元の問題に直面することとなった。
Ⅱ.解散・清算手続の種類と事業年度の概要
清算所得課税の改正の前に、まず、本改正は平成22年10月1日以降解散する事業年度から適用されることから、基本的な事業年度の仕組みについて確認することとする。
法人の基本的な倒産手続は、①通常清算、②特別清算、③破産、の3種類に分けられるが、いずれについても、税務申告の原則的な仕組みは同じであり、解散事業年度と清算事業年度の少なくとも2回の申告が必要である。なお、会社更生や民事再生手続の開始または認可決定では、解散したものとされないが、破産手続の開始は法人税法上の解散に含まれ(会社法471五、最高判平成4年10月20日他、窪田悟嗣編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会)23頁参照)、解散の手続は無いが、破産手続開始決定日が税務上は解散事業年度の末日となる。
なお、内国法人の事業年度については、解散した場合には、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間となっており、また、清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間となっている(法法14)。
つまり、解散後、残余財産が確定するまでの間に、事業年度が終了した場合には、別途その事業年度末日までの税務申告が必要となる。なお、国税庁の法令解釈通達によると、株式会社等が解散した場合には、会社法494条における清算株式会社の清算事務年度の規定に従い、法人税上の事業年度も解散日の1年後に終了することとなる(法基通1-2-9)が、破産や持分会社の解散の場合には清算事務年度の規定がそもそもないことから、定款上の事業年度のままとなる(例えば、定款上の事業年度が4月1日から3月31日の法人が2月末に破産手続開始決定を受けた場合には、同年の3月に事業年度が終了することとなる。)。
平成22年度税制改正で課税方式が変わり、問題となるのは、清算中の事業年度における確定申告である。
Ⅲ.清算所得課税の廃止
1.従来の課税方式 従来の清算確定申告においては、下記の算式でいわゆる財産法的な手法により清算所得の計算を行っていた。この方法により解散時に所有していた残余財産の時価について、過年度に資本金等に対応する部分、過年度に課税された、或いは、非課税の部分である利益積立金を控除した残額に対して(清算年度に課される事業税が損金算入されないことを考慮した税率である。)27.1%の税率を乗じて法人税を計算する仕組みである。
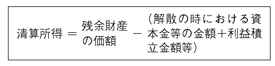
2.税制改正における基本的な考え方 今回の改正においてこの清算所得課税の制度が廃止された結果、平成22年10月1日以降解散した法人については、清算時の課税も財産法ではなくいわゆる損益法、すなわち益金の額から損金の額を控除して所得金額を算出し、解散前と同様に各事業年度の所得に対する法人税が課せられることとなった(事業税の取扱い等相違点もある。)。
(1)損益法と財産法で所得が異なる場面 損益法により通常の所得計算を行ったとしても、図表1の通り、税務調整が入らないシンプルなケースの場合、その課税標準は従来の清算所得と異ならないはずである(脚注2)。
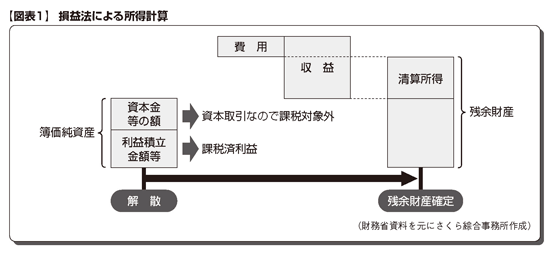
では、どのような時に大きな問題が発生するかというと、その原因は主として二つ考えられる。第一は、欠損金と債務免除益等清算期の所得が相殺できない場合であり、もう一つは、過年度に計上した架空資産や貸付金等の評価損又は清算中に支払った退職金(脚注3)や交際費等(脚注4)が清算期に損金に計上できない場合である。
前者については、例えば債務超過の会社等で清算期に債務免除等を受ける会社の場合、従来の計算では残余財産(資産-負債)の時価を計算する際に資産から差し引く負債の金額が減少する結果、残余財産額が多くなるものの、残余財産の額が控除する資本金等及び利益積立金等の範囲内であれば清算所得はゼロであって課税が発生しなかった。しかし、改正後の計算方法では、その事業年度に発生した債務免除益等による収益を、青色欠損金を含む損金で充当できない場合、残余財産がないのに課税所得が発生してしまう場合があるが、結論から言うと、今回の改正で一定の場合に期限切れ欠損金を充当することで手当てされている。
しかし、後者の場合については手当てされていない。後者の場合に関しては、従来の課税方法では問題があるケースもありえたので、今回改めてクローズアップされたと言うこともできよう。
(2)期限切れ欠損金の利用 例えば、解散時において資産簿価(=時価)10、負債50、資本金等がない場合に清算期に負債を40債務免除したとしよう。従来の計算方法では、残余財産はなくなり、清算所得の課税はなくなる。しかし、改正後は清算期の債務免除益40に対して、充当する欠損金がなければ課税が発生してしまうのである。
もっとも、前述のような財務状況の場合、資本金等に相当する繰越欠損金があるはずであるが、当該欠損金が、青色欠損金として事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のものである等の要件を満たさなければ、損金算入できない(法法57、57の2)。
つまり、従来の課税方法によれば、過去の欠損金と清算事業年度の所得とが自動的に相殺される結果となっていたのであるが、今回の改正のより、期限切れ欠損金相当額が相殺されずに、課税所得が残るケースが想定されることとなったものである。
したがって図表2のような場合で、期限切れ欠損金を使用できないとすると、清算中の事業年度において課税所得が発生することになるが、今回の改正で一定の手当てがなされている。それは、青色欠損金を控除して、なお課税所得が発生するときは、残余財産がないと見込まれることを要件として期限切れ欠損金が損金の額に算入できるという手当てであり、青色欠損金控除後の所得を限度として損金に算入できることとなった(法法59③)。
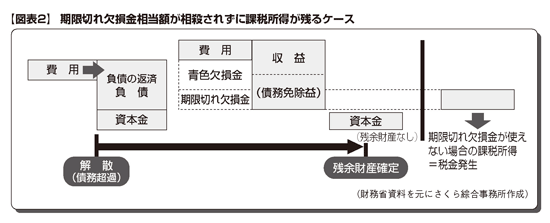
なお期限切れ欠損金とは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額であり、下記①から②を控除した金額である(法令118、法基通12-3-2)。
① 当該事業年度の確定申告書に添付する別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」の合計額がマイナスである場合のその値
② 青色欠損金・災害損失欠損金(損金算入額)
3.具体的な取扱い
(1)残余財産のないことの疎明方法及び破産時における継続的な申告が困難な場合の期限切れ欠損金の額 期限切れ欠損金の使用が認められる要件は「残余財産がないと見込まれるとき」であり、「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による(法基通12-3-7)。
この規定の適用を受けようとする場合には、「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」を確定申告書に添付することとされている(法規26の6①三)ため、事業年度末の時点での実態貸借対照表を添付(法基通12-3-9)し、残余財産がないことを示す必要がある。その場合の時価は財務省主税局の「平成22年度税制改正の解説」(277頁参照)では単に「通常の時価ではなく処分価額によることになると考えられます」としているが、法人税基本通達12-3-9(注)では事業譲渡の場合には通常の使用収益価額によるものとしている。
制度上の特例を受ける納税者に疎明させることはやむを得ないかもしれないが、破産を始め、倒産・事業再生の局面では帳簿記録が散逸していることも多く、課税の回避のための資料収集の時間・費用が膨大となる可能性もある。この点について、法人税基本通達12-3-8において、解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当するとされおり、財務省主税局の「平成22年度税制改正の解説」(277頁参照)においても、破産手続開始の決定による解散の場合には通常残余財産が無い場合に該当するとされていることから、破産手続等の場合には、実態貸借対照表の添付は不要になると考えられる。また、事業再生研究機構より公表されている「平成22年度税制改正後の清算中の法人税申告における実務上の取扱いについて」(脚注5)(以下、「事業再生研究機構報告書」という。)においても、下記のように述べられている。これは倒産や事業再生の実務上妥当な見解と考えられる。
| 【抜粋1】 例えば、裁判所又は公的機関が関与する手続又は、一定の準則により独立した第三者が関与する手続において、債務超過であるなど破産手続の開始決定の原因があることなどを裁判所、公的機関又は独立した第三者が確認している場合には「残余財産がないと見込まれる」ことを確認しているといえ、当該手続における清算期間中は「残余財産がないと見込まれるとき」に該当すると考えられる。具体的には、 (1)清算型の法的整理手続である破産又は特別清算の開始決定がなされた場合 (2)再生型の法的整理手続である民事再生又は会社更生の開始決定後、清算手続が行われる場合 (3)公的機関が関与し、又は、一定の準則に基づき独立した第三者が関与して策定された事業再生計画に基づいて清算手続が行われる場合 が該当するものと考えられる。 |
このような場合の対応方法についても、事業再生研究機構報告書において、簡便な計算方法が述べられている。
| 【抜粋2】 まず、開始決定時点の財産の総額、資本金の額及び債務総額をもって簡易な貸借対照表を作成し、債務超過額を算出する。債務超過額に資本金の額を加えた額は、期限切れ欠損金の額となると考えられる。 これらの情報をもとに申告書を作成する。具体的には別紙(脚注6)のとおり。 また、申告書には、清算B/S(又は財産目録若しくは財産目録に準ずるものと、債務総額を示す書類)、開始決定後の財産の換価状況等を添付する。 【別紙(抜粋)】 例)①開始時点の財産の価額 500 ②債務総額1000 ③資本金の額 200 ①-②=△500→500(絶対値)……債務超過額 500+③=700 ⇒ 期限切れ欠損金額 |
但し、その過大納付が仮装経理等による場合、損金算入要件が課される減価償却、引当金や多くの評価損等の未計上は、通常減額更正の対象とならずに解散法人に残り、また、更正の期間制限を徒過した等の理由により税務署長の職権更正が適わなかったそれ以外の要素も解散法人に残留することになる。更には、法人税基本通達9-6-2(実質基準の貸倒損失)のように事実が発生した事業年度での損金計上が求められる(計上時期に制限のある)場合には、清算期間中に評価損の損金計上が認められないということも考えられる。
なお、資産に係る評価損等の未計上は清算手続中に資産の譲渡損等として解消するものもあるが、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行い、同法に基づく財産価額の評定の準備を始めていた事案において、過年度棚卸資産廃棄損の額は、「過年度の棚卸資産に係る粉飾額を計上したものにすぎず、その全額が本件事業年度において生じたものでないことが明らかである」として、過年度棚卸資産廃棄損が否認された事例(脚注7)もある。
この仮装経理の問題は企業再生事由が生じているような場合に発生するだけではなく、健全な会社においても発生する。特に残余財産がある通常清算の場合では、仮装経理を理由とする青色申告の承認の取り消し(脚注8)の可能性も考慮する必要がある。
このように、これら「実在性のない資産」に関しては、清算中も損金に計上することは困難な場合がありうるが、かかる場合には、事業再生研究機構報告書で次のように述べられている。
| 【抜粋3】 ① 過去の帳簿書類を調査した結果、実在性のない資産の計上根拠等が判明した場合 実在性のない資産の計上根拠等が判明しているため、適正な処理に修正をすることが適当であると考えられる。 このうち、更正期限内のものについては、適正な処理に修正を行い、更正手続を経て当該原因の生じた事業年度の欠損金(その事業年度が青色申告の場合は青色欠損金、青色申告でない場合は期限切れ欠損金)とする。 また、更正期限を超えるものについては適正な処理に修正して当該原因の生じた事業年度の欠損金(その事業年度が青色申告であるかどうかにかかわらず期限切れ欠損金)とする。 ② 過去の帳簿書類を調査した結果、実在性のない資産の計上根拠等が判明しなかった場合 裁判所または独立した第三者等が関与する手続(上記【抜粋1】の(1)(2)(3)の破産等の手続)を経て実在性のないことが確認された場合、実在性のない資産の帳簿価額を期限切れ欠損金とする。 |
(3)通常清算とするための債務免除の額 解散時点においては債務超過の状態におかれていても、債務免除をした結果、残余財産が残ってしまう場合は「残余財産がないと見込まれる」ことにはならないので、免除益をいくら計上するかという点には注意が必要である。債務超過の場合でも、債権者が少数の関係者であるときなどは、債務免除により通常清算手続により清算させることもあると思われる(債務超過のまま株式会社を清算する場合には、原則として特別清算手続によることになる(会社法510)。)。このような場合において、残余財産確定時には債務免除が完了している状態であるので、この時点においては債務超過という状態はなくなるが、「残余財産がないと見込まれる」状態にあるか否かという問題がある。
この点については、法人税基本通達12-3-8を反対解釈して「債務超過状態でなければ残余財産があると見込まれる」とまで解釈する必要はないだろう。つまり、法人税法上の要件が「残余財産がないと見込まれるとき」であるため、残余財産がゼロになるように債務免除を行い、資産=負債の状態で残余財産を確定させることで期限切れ欠損金の額を損金算入できることになると考えられる。
なお、債務の弁済に充当可能な資産が残っているにもかかわらず、債務免除を受けた場合は、債権者側で寄付金課税の問題が生じるおそれもあるので、法人税基本通達9-4-1や9-4-2等を勘案してその経済的合理性を検証する必要がある。
(4)残余財産がわずかに見込まれる資本欠損の会社の場合 清算事業年度において、残余財産がゼロではないものの、資本金が毀損している場合、従来の財産計算においては、原則的には課税所得は発生することはないが、平成22年10月1日以降の損益計算においては、その期の損益から欠損金等を控除して、なお所得が残れば課税所得が発生することとなる。
更に、このような場合で期限切れ欠損金があるときについても、残余財産があるため期限切れ欠損金を使用することができず、その結果、残余財産を超える課税が発生する可能性がある。
(5)その他の期限切れ欠損金の利用特例(特例欠損金)との関係 法人税法59条3項の期限切れ欠損金の損金算入の制度は、法人税法59条1項及び2項に規定される「更生手続き開始の決定」があった場合及び「再生手続開始の決定があったこと」その他一定の事実が生じた場合の期限切れ欠損金の損金算入制度の適用とは別個のものであり、計算方法も異なる(法法59①②、法令117、法基通12-3-1)。これらの制度の適用を受ける事業年度には、清算による期限切れ欠損金の特例を重ねて受けることはできない(法法59③)が、それ以外の年度なら適用を受けることができる。
(6)第二会社方式による場合 事業再生において新会社に優良な事業を移転し、旧会社を不採算部門と合わせて清算してしまう、いわゆる第二会社方式による場合も、通常、清算する会社は債務超過であり、債務免除の問題は生じることとなる。
しかし、第二会社方式の場合、債権者の損金算入の要件を充足させることや、金融機関等が積極的に債務放棄を行うことが難しいことなどもあり、裁判所が介在する特別清算手続をとることが多く、上記の取り扱いを勘案すると、特別清算手続であれば、今回の税制改正が直接的な原因となるような問題は生じないものと考えられる。
Ⅳ.完全支配関係のある親会社からの債務免除
上記のとおり、債務免除がある場合には、赤字会社でも納税の懸念があるが、グループ法人税制の施行に伴い、平成22年10月1日以降の完全支配関係がある会社間での寄付金の額については、支出側で全額損金不算入(法法37②)になるとともに、受入側では益金不算入となる(法法25の2①)。
よって、完全支配関係がある親会社からの債務免除については、そもそも益金の額に算入されないことから、債務免除による納税額の発生の懸念は不要である。
但し、子会社等を整理する場合の損失負担等として、支出側で損金算入する場合(法基通9-4-1、9-4-2)には、受入側においては益金算入になると考えられるため、注意が必要である(図表3参照)。
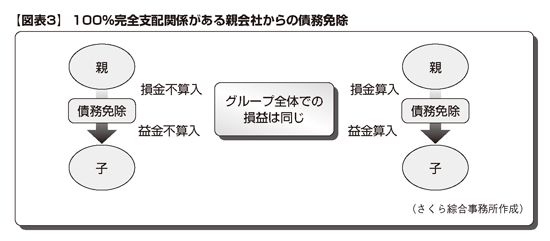
脚注
1 財務状況が悪化している企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また、不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることにより事業の再生を図る手法をいう。中小企業については一定の要件を満たして認定を受ければ、許認可承継等の特典を得ることもできる産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画の認定制度が平成21年度に創設された。
2 但し、通常の事業年度と清算中の事業年度の取扱が異なる点の一つに事業税の損金算入時期がある。通常の事業年度に係る事業税は支払った期の損金算入となるが、清算期間中の事業税のうち、残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金算入ができることとされている(法法62の5⑤)。
3 法基通9-2-28但し書参照。
4 改正前の制度では、通常の所得計算では損金算入が制限される交際費や過大役員報酬や退職金等についても財産法計算上特に制限なく、全額控除が可能であった。
5 http://www.shojihomu.co.jp/jabr/jabr.html又は事業再生研究機構税務問題委員会編『清算法人税申告の実務』(商事法務)を参照。
6 実際の報告書の別紙の計算部分のみ抜粋。
7 裁決事例集No.72-404頁(平成18年11月21日裁決)。本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例。なお、東京地裁において、粉飾決算による棚卸資産の過大計上に関する判決も平成22年9月10日に行われている(平成21年(行ウ)第380号)。
8 法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)[平成12年7月3日課法2-10、課料3-15、査調4-12査察1-31]では、次のいずれかに該当する場合には、原則として、青色申告の承認を取り消すものとしているが、経営責任がとられた事案での減額更正の場合には寛大な取扱いが望まれる。
イ 無申告のために所得金額の決定をした場合又は所得金額の更正をした場合において、その事業年度の当該決定又は更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、当該更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)。
ロ 欠損金額を減額する更正(所得金額があることとなる更正を含む。)をした場合において、その事業年度の当該更正により減少した部分の欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正欠損金額」という。)が、当初の申告に係る欠損金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額。以下「申告欠損金額」という。)の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正欠損金額が500万円に満たないときを除く。)。
ハ 帳簿書類への記載等が不十分である等のため、法第131条(法第147条において準用する場合を含む。)の規定による推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.