解説記事2010年11月01日 【税務マエストロ】 海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)(2010年11月1日号・№376)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)
#03 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職(平成22年10月現在)。
次回のテーマ
#04 経営戦略に応える企業再編成税制
税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設に携わった著者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説
昨今、法人税率の引下げの議論が盛んになっている。現在の高い法人税率を嫌って日本企業およびその事業活動が海外へ流失してしまっているのではないかとの危惧から、これを引下げ、日本国内における企業活動を活性化させ、景気の浮揚を図ろうとする議論である(脚注1)。事実、日本の法律上の法人税率は30%であり、地方税等の負担を加えた実効税率は、諸外国、特にアジア近隣諸国と比べて格段に高い(図表1参照)。また、諸外国には、多くの税制優遇措置を設け、外国企業の誘致を図るところも多い。しかし、日本企業の海外進出は、こうした高い法人税率や外国の税制優遇措置のみが原因ではなく、その他にも多くの要因が考えられるところである。安価な労働力が活用できる国であれば製造拠点として進出する価値があるであろうし、域内に購買意欲が旺盛な市場があるのであれば、新たな販売拠点を設けることも当然の企業行動である。つまり、日本企業の海外事業展開は、税率の議論とは別に、事業上の要請からも生ずる動きであり、これは今後も続くことが予想されるのである。
こうした日本企業の海外事業展開に際しては、税務上の影響を常に考えておく必要があるが、ここでは2つの側面から検討を行う必要がある。1つは進出先の税制である。進出先の法人税率は何%なのか、優遇措置はあるのか、日本に配当を行う場合には何%の源泉税がかかるのかといった論点である。また、もう1つは、日本の税制で、これは日本企業であるゆえに常に検討していなくてはならない論点である。具体的にはタックスヘイブン対策税制や移転価格税制の問題である。本稿においては、こうした国際税務を総論的に俯瞰し、今後順次、その他の個別論点を解説することとしたい。
1.進出先国の税制(源泉徴収、恒久的施設) 日本企業が海外進出(アウトバウンド投資)をし、そのリターン(対価)を得る場合には、一般的には、その外国で源泉徴収されることとなる。通常考えられるリターンは、使用料、配当や貸付金利息であるが、これらは日本において通常の利益(所得)であり、日本で課税対象となると同時に、その外国でも源泉徴収されることとなる。これは、日本の企業が外国企業に対して、利子や配当を支払う場合に日本で源泉徴収することと同様の仕組みであるが、その源泉徴収の金額(税率)、時期、納付方法は、外国それぞれであり、その国ごとに考える必要がある。
また、外国に駐在員事務所を作った場合に、恒久的施設に該当するかどうかといった問題も、その国の税法に従うこととなり、また、その場合も必ずしも日本と同じ結果になるとは言い切れないといえよう。たとえば、日本以上に、恒久的施設の範囲を広く捉えている国も多くあり、こうした場合には、日本では恒久的施設に該当しない場合でもその国では恒久的施設に該当することもあるのである。
2.租税条約 租税条約は、通常、ある国と他の国の2国間で、自国の個人や企業が、相手国で何らかの所得を得た場合に、その相手国でどのように課税されるかについて取り決めた国家間の取り決めである。上記1のごとく、国ごとに制度が異なる部分について、ある一定の共通概念を与えることとなる。その結果、租税条約が締結されている国への投資は、相手国での課税という面で、一定の安定性が確保されると理解することができよう。
具体的に日本とアメリカの租税条約を例にとれば、日本企業がアメリカに支店を開設した場合に、アメリカでどのように課税されるか(法人税課税)、日本企業がアメリカ企業から配当を受ける場合に、アメリカでどのような税金がかかるか(源泉徴収)などについて、その基本的事項が定められている。たとえば、アメリカ法人から日本企業(親会社)に対する配当についての源泉徴収は、原則的な税率(通常30%)ではなく、租税条約に定める軽減税率(脚注2)によることとなる。なお、租税条約は2国間で締結するもので、かつ相互主義を原則としているため、アメリカの企業が日本で課税を受ける場合も同様の対応、結果となる。
また、租税条約には、この他にも、それぞれの税務当局間の協力についても定められており、移転価格課税の問題が起きた後の「相互協議」もその1つである。
このように、相手国へ投資した場合に、その成果(リターン)に対する課税については、相手国の法律を考えているだけでは、正確な課税関係とはいえず、租税条約を併せて検討しなければ最終的な課税関係には至らないのである。そして、これら租税条約の存在によって、相手国に投資をし、その成果を得た場合の課税関係が明確になることになり、投資がしやすくなる効果が期待されるところでもある。同様に、相手国からの投資を誘導する効果も生じることとなろう。
3.外国税額控除 日本企業(内国法人)や日本人(居住者)が海外進出(アウトバウンド投資)を行った際には、原則として、投資先の国において何らかの課税を受けることとなる。支店(PE)を設置して事業を行っていれば、一般的な法人税の対象となり、利子、配当等を受け取るのであれば、源泉徴収されることとなる。これは、この外国で生じた所得(その国に源泉がある)があるため、これらの外国が課税するところとなるのである。一方、外国で課税されたこれらの所得は、日本においても、その内国法人、居住者の課税所得に含まれることになる。つまり、こうした所得は、その発生地である外国と日本で二重に課税されることになるのである。
こうした二重課税は、非常に重い税負担となり、事業活動の妨げになるのは明らかである。したがって、一般的には、本国において何らかの二重課税排除措置が施されている。日本の場合には、外国税額控除が定められているが、これは、一定の限度のもと、外国で課された税金を日本の算出税額から控除する制度である。
この結果、アウトバウンド投資を行って、海外で税金が課された場合でも、日本国内で投資を行い、それに対して納税する場合との均衡が保たれることとなる。
4.タックスヘイブン対策税制 タックスヘイブン対策税制は、日本企業が、海外の子会社に利益を留保する租税回避を防止する税制である。アウトバウンド投資(海外に子会社設立)に関する国際税務でのきわめて重要な留意点といえる。
日本企業が、自ら日本を拠点にビジネスをし、その結果獲得された利益は、当然のことながらその日本企業の所得として日本で課税される。一方、同様のビジネスを、海外の子会社名義で行えば、形式的には、その海外の子会社の利益となり、日本では課税されないこととなる。
このような海外の子会社を利用した、日本の税金に関する租税回避が成り立つためには、2つの要素が必要となる。1つめの要素は、ビジネスそのものを実質的に本社である日本企業がコントロールできること、極端に言えば、海外の子会社がペーパーカンパニーのような状態であること、2つめの要素は、その子会社が設立された国における納付税額が日本の税額よりも少なくなることである。
こうした租税回避と認定できる場合には、その海外の子会社の所得を親会社の所得として合算する制度がタックスヘイブン対策税制である(図表2参照)。このタックスヘイブン対策税制の適用を受ける場合には、その子会社の所得に日本の税金が課せられることとなる(合算課税)。
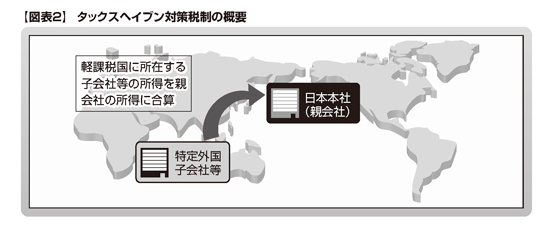
タックスヘイブン対策税制では、実質的に日本企業のコントロール下にあるか否かという論点については「適用除外基準」で、外国での納付税額が日本の税額より少なくなるか否かという論点については「20%基準」によって判定している。実務上は、これらの2つの論点が非常に重要と考えられる。
5.移転価格税制 移転価格税制は、海外の関連企業との取引価格が、独立の企業間における取引価格(独立企業間価格)と異なる場合に、これを独立企業間価格で行われたものとみなして、課税所得を計算しなおす制度であり、関連者との取引価格を利用した海外への所得移転を防止するための制度といわれている。つまり、具体的に考えれば、たとえば日本の子会社が海外の親会社から製品を輸入し、それを日本国内で販売していたとする。その際の親子法人間の取引が関連者間の取引に該当し、その取引価格(輸入価格)が独立企業間であれば100万円で輸入することとなるところ、親子間取引であるゆえ200万円で輸入していると仮定する。つまり仕入価格が高いことになり、日本の子会社の所得がその分圧迫されていることになろう。移転価格税制は、こうした価格(200万円)を課税所得の計算上独立企業間価格(100万円)に調整(仕入価格の減少)する制度で、その結果、日本における課税所得が100万円増加することとなる。
昨今は、多くの高額な課税案件が報道されていることから、何か極めて複雑な制度と誤解されることが多いようであるが、基本的には、いかにして独立企業間価格を把握するかということが論点になる。法律上は、独立価格比準法や利益分割法などいくつかの方法が定められているところであるが、対象となった取引についてどの方法が適用可能か、そもそも独立企業間価格が算定できるのかといったことが、実務上の論点となる。
移転価格税制のポイントは課税後の相互協議のプロセスにもある。取引価格の調整による課税であるため、取引の相手方の所得金額も調整しなければ二重課税が発生することとなる。この二重課税を排除するシステムが相互協議である。
移転価格税制は、アウトバウンド投資の場合と同様にインバウンド投資においても重要な項目といえる。つまり2つの国の観点から考える必要がある。日本企業が海外の子会社等のグループ企業との取引を独立企業間価格以外の価格で行い、その結果、日本企業の所得であるはずの所得が海外の子会社に流失してしまうケースについては、日本の課税当局が問題視することとなろう。その結果、日本の税務調査等で指摘され、追徴課税という事態になることも予想される。一方、そのグループ企業が所在する外国も、取引価格が独立企業間価格でないため、本来その子会社等が得られるべき所得が計上されていないという判断を行うことも考えられる。この場合は、外国の移転価格税制により、その外国で課税されるところとなる。このように、移転価格税制は、日本のみならず、グループ企業が所在する国の税制、執行状況を同時に勘案しなければならない制度となっている。特に、一旦どちらかの国で課税された場合に、二重課税を排除するための相互協議や、事前に独立企業間価格等について課税当局間で承認、合意を行う「事前確認」などは、両国の税務当局を巻き込んで行うこととなる。
脚注
1 一方、法人税率引下げにより、外国企業の対日投資を促進させようとの議論もある。
2 租税条約での取り決めは、原則として、国内税法による内容よりも優先すると理解されている。つまり、わが国の所得税法では、外国法人に支払う配当に対する源泉税の税率は原則20%とされているが、通常、租税条約では5%ないし10%と定められており、そうした租税条約を締結している国の外国企業(株主)に対する配当については、20%ではなく5%(ないしは10%)で源泉徴収することとなる。これが租税条約の限度税率(制限税率)である。
この記事に関するご意見・お問合せは編集部 03(5281)0020または ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
今週のマエストロ&テーマ
海外へ事業展開する場合における税務上の留意点(総論)
#03 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職(平成22年10月現在)。
次回のテーマ
#04 経営戦略に応える企業再編成税制
税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設に携わった著者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説
昨今、法人税率の引下げの議論が盛んになっている。現在の高い法人税率を嫌って日本企業およびその事業活動が海外へ流失してしまっているのではないかとの危惧から、これを引下げ、日本国内における企業活動を活性化させ、景気の浮揚を図ろうとする議論である(脚注1)。事実、日本の法律上の法人税率は30%であり、地方税等の負担を加えた実効税率は、諸外国、特にアジア近隣諸国と比べて格段に高い(図表1参照)。また、諸外国には、多くの税制優遇措置を設け、外国企業の誘致を図るところも多い。しかし、日本企業の海外進出は、こうした高い法人税率や外国の税制優遇措置のみが原因ではなく、その他にも多くの要因が考えられるところである。安価な労働力が活用できる国であれば製造拠点として進出する価値があるであろうし、域内に購買意欲が旺盛な市場があるのであれば、新たな販売拠点を設けることも当然の企業行動である。つまり、日本企業の海外事業展開は、税率の議論とは別に、事業上の要請からも生ずる動きであり、これは今後も続くことが予想されるのである。
こうした日本企業の海外事業展開に際しては、税務上の影響を常に考えておく必要があるが、ここでは2つの側面から検討を行う必要がある。1つは進出先の税制である。進出先の法人税率は何%なのか、優遇措置はあるのか、日本に配当を行う場合には何%の源泉税がかかるのかといった論点である。また、もう1つは、日本の税制で、これは日本企業であるゆえに常に検討していなくてはならない論点である。具体的にはタックスヘイブン対策税制や移転価格税制の問題である。本稿においては、こうした国際税務を総論的に俯瞰し、今後順次、その他の個別論点を解説することとしたい。
1.進出先国の税制(源泉徴収、恒久的施設) 日本企業が海外進出(アウトバウンド投資)をし、そのリターン(対価)を得る場合には、一般的には、その外国で源泉徴収されることとなる。通常考えられるリターンは、使用料、配当や貸付金利息であるが、これらは日本において通常の利益(所得)であり、日本で課税対象となると同時に、その外国でも源泉徴収されることとなる。これは、日本の企業が外国企業に対して、利子や配当を支払う場合に日本で源泉徴収することと同様の仕組みであるが、その源泉徴収の金額(税率)、時期、納付方法は、外国それぞれであり、その国ごとに考える必要がある。
また、外国に駐在員事務所を作った場合に、恒久的施設に該当するかどうかといった問題も、その国の税法に従うこととなり、また、その場合も必ずしも日本と同じ結果になるとは言い切れないといえよう。たとえば、日本以上に、恒久的施設の範囲を広く捉えている国も多くあり、こうした場合には、日本では恒久的施設に該当しない場合でもその国では恒久的施設に該当することもあるのである。
2.租税条約 租税条約は、通常、ある国と他の国の2国間で、自国の個人や企業が、相手国で何らかの所得を得た場合に、その相手国でどのように課税されるかについて取り決めた国家間の取り決めである。上記1のごとく、国ごとに制度が異なる部分について、ある一定の共通概念を与えることとなる。その結果、租税条約が締結されている国への投資は、相手国での課税という面で、一定の安定性が確保されると理解することができよう。
具体的に日本とアメリカの租税条約を例にとれば、日本企業がアメリカに支店を開設した場合に、アメリカでどのように課税されるか(法人税課税)、日本企業がアメリカ企業から配当を受ける場合に、アメリカでどのような税金がかかるか(源泉徴収)などについて、その基本的事項が定められている。たとえば、アメリカ法人から日本企業(親会社)に対する配当についての源泉徴収は、原則的な税率(通常30%)ではなく、租税条約に定める軽減税率(脚注2)によることとなる。なお、租税条約は2国間で締結するもので、かつ相互主義を原則としているため、アメリカの企業が日本で課税を受ける場合も同様の対応、結果となる。
また、租税条約には、この他にも、それぞれの税務当局間の協力についても定められており、移転価格課税の問題が起きた後の「相互協議」もその1つである。
このように、相手国へ投資した場合に、その成果(リターン)に対する課税については、相手国の法律を考えているだけでは、正確な課税関係とはいえず、租税条約を併せて検討しなければ最終的な課税関係には至らないのである。そして、これら租税条約の存在によって、相手国に投資をし、その成果を得た場合の課税関係が明確になることになり、投資がしやすくなる効果が期待されるところでもある。同様に、相手国からの投資を誘導する効果も生じることとなろう。
3.外国税額控除 日本企業(内国法人)や日本人(居住者)が海外進出(アウトバウンド投資)を行った際には、原則として、投資先の国において何らかの課税を受けることとなる。支店(PE)を設置して事業を行っていれば、一般的な法人税の対象となり、利子、配当等を受け取るのであれば、源泉徴収されることとなる。これは、この外国で生じた所得(その国に源泉がある)があるため、これらの外国が課税するところとなるのである。一方、外国で課税されたこれらの所得は、日本においても、その内国法人、居住者の課税所得に含まれることになる。つまり、こうした所得は、その発生地である外国と日本で二重に課税されることになるのである。
こうした二重課税は、非常に重い税負担となり、事業活動の妨げになるのは明らかである。したがって、一般的には、本国において何らかの二重課税排除措置が施されている。日本の場合には、外国税額控除が定められているが、これは、一定の限度のもと、外国で課された税金を日本の算出税額から控除する制度である。
この結果、アウトバウンド投資を行って、海外で税金が課された場合でも、日本国内で投資を行い、それに対して納税する場合との均衡が保たれることとなる。
4.タックスヘイブン対策税制 タックスヘイブン対策税制は、日本企業が、海外の子会社に利益を留保する租税回避を防止する税制である。アウトバウンド投資(海外に子会社設立)に関する国際税務でのきわめて重要な留意点といえる。
日本企業が、自ら日本を拠点にビジネスをし、その結果獲得された利益は、当然のことながらその日本企業の所得として日本で課税される。一方、同様のビジネスを、海外の子会社名義で行えば、形式的には、その海外の子会社の利益となり、日本では課税されないこととなる。
このような海外の子会社を利用した、日本の税金に関する租税回避が成り立つためには、2つの要素が必要となる。1つめの要素は、ビジネスそのものを実質的に本社である日本企業がコントロールできること、極端に言えば、海外の子会社がペーパーカンパニーのような状態であること、2つめの要素は、その子会社が設立された国における納付税額が日本の税額よりも少なくなることである。
こうした租税回避と認定できる場合には、その海外の子会社の所得を親会社の所得として合算する制度がタックスヘイブン対策税制である(図表2参照)。このタックスヘイブン対策税制の適用を受ける場合には、その子会社の所得に日本の税金が課せられることとなる(合算課税)。
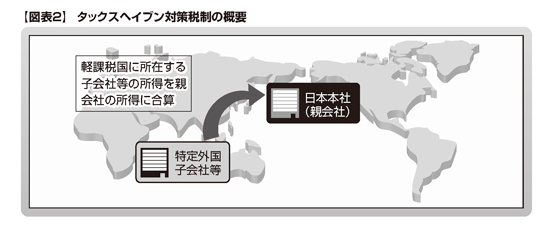
タックスヘイブン対策税制では、実質的に日本企業のコントロール下にあるか否かという論点については「適用除外基準」で、外国での納付税額が日本の税額より少なくなるか否かという論点については「20%基準」によって判定している。実務上は、これらの2つの論点が非常に重要と考えられる。
5.移転価格税制 移転価格税制は、海外の関連企業との取引価格が、独立の企業間における取引価格(独立企業間価格)と異なる場合に、これを独立企業間価格で行われたものとみなして、課税所得を計算しなおす制度であり、関連者との取引価格を利用した海外への所得移転を防止するための制度といわれている。つまり、具体的に考えれば、たとえば日本の子会社が海外の親会社から製品を輸入し、それを日本国内で販売していたとする。その際の親子法人間の取引が関連者間の取引に該当し、その取引価格(輸入価格)が独立企業間であれば100万円で輸入することとなるところ、親子間取引であるゆえ200万円で輸入していると仮定する。つまり仕入価格が高いことになり、日本の子会社の所得がその分圧迫されていることになろう。移転価格税制は、こうした価格(200万円)を課税所得の計算上独立企業間価格(100万円)に調整(仕入価格の減少)する制度で、その結果、日本における課税所得が100万円増加することとなる。
昨今は、多くの高額な課税案件が報道されていることから、何か極めて複雑な制度と誤解されることが多いようであるが、基本的には、いかにして独立企業間価格を把握するかということが論点になる。法律上は、独立価格比準法や利益分割法などいくつかの方法が定められているところであるが、対象となった取引についてどの方法が適用可能か、そもそも独立企業間価格が算定できるのかといったことが、実務上の論点となる。
移転価格税制のポイントは課税後の相互協議のプロセスにもある。取引価格の調整による課税であるため、取引の相手方の所得金額も調整しなければ二重課税が発生することとなる。この二重課税を排除するシステムが相互協議である。
移転価格税制は、アウトバウンド投資の場合と同様にインバウンド投資においても重要な項目といえる。つまり2つの国の観点から考える必要がある。日本企業が海外の子会社等のグループ企業との取引を独立企業間価格以外の価格で行い、その結果、日本企業の所得であるはずの所得が海外の子会社に流失してしまうケースについては、日本の課税当局が問題視することとなろう。その結果、日本の税務調査等で指摘され、追徴課税という事態になることも予想される。一方、そのグループ企業が所在する外国も、取引価格が独立企業間価格でないため、本来その子会社等が得られるべき所得が計上されていないという判断を行うことも考えられる。この場合は、外国の移転価格税制により、その外国で課税されるところとなる。このように、移転価格税制は、日本のみならず、グループ企業が所在する国の税制、執行状況を同時に勘案しなければならない制度となっている。特に、一旦どちらかの国で課税された場合に、二重課税を排除するための相互協議や、事前に独立企業間価格等について課税当局間で承認、合意を行う「事前確認」などは、両国の税務当局を巻き込んで行うこととなる。
脚注
1 一方、法人税率引下げにより、外国企業の対日投資を促進させようとの議論もある。
2 租税条約での取り決めは、原則として、国内税法による内容よりも優先すると理解されている。つまり、わが国の所得税法では、外国法人に支払う配当に対する源泉税の税率は原則20%とされているが、通常、租税条約では5%ないし10%と定められており、そうした租税条約を締結している国の外国企業(株主)に対する配当については、20%ではなく5%(ないしは10%)で源泉徴収することとなる。これが租税条約の限度税率(制限税率)である。
この記事に関するご意見・お問合せは編集部 03(5281)0020または ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























