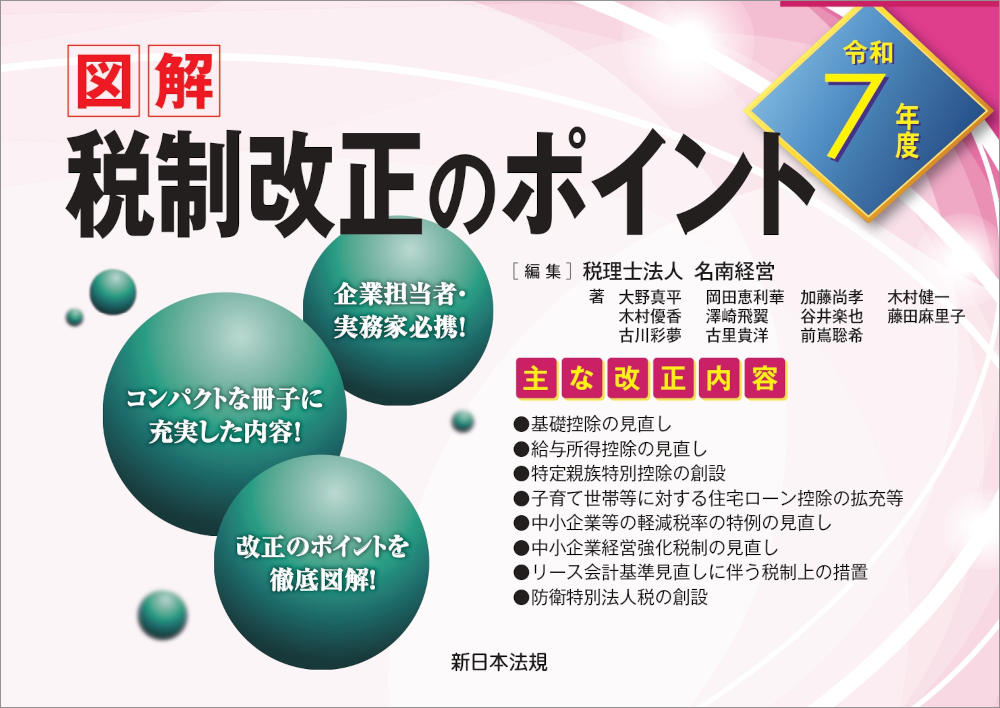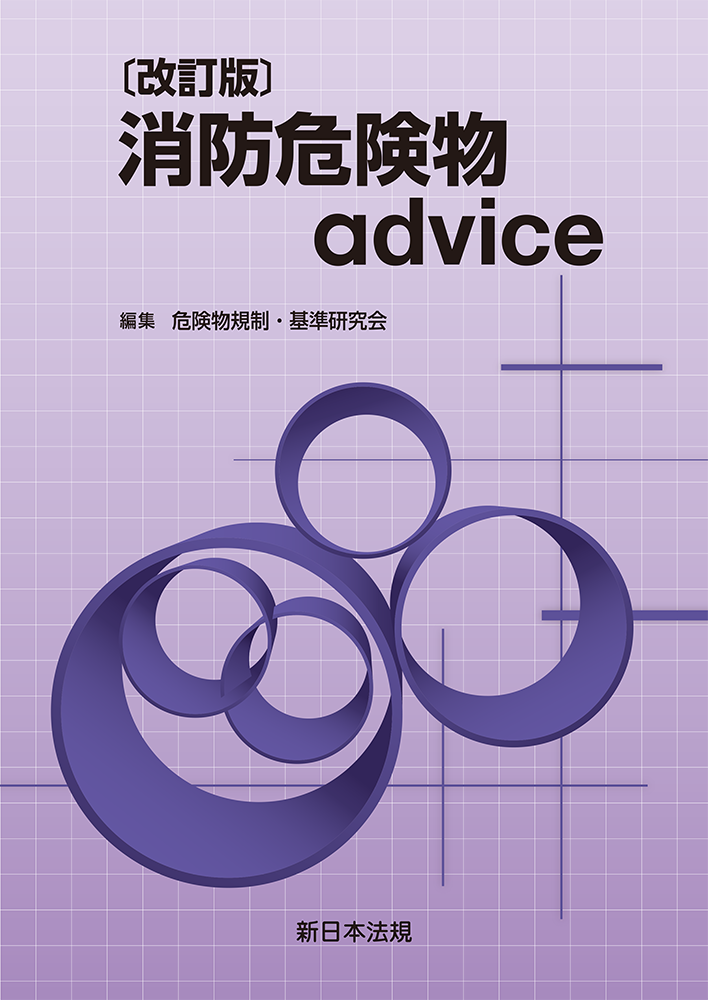解説記事2011年02月07日 【実務解説】 税制から見た新公益法人制度の留意点(1)(2011年2月7日号・№389)
実務解説
税制から見た新公益法人制度の留意点(1)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.はじめに
公益法人制度改革関連三法(脚注1)(以下「公益三法」という)が平成20年12月1日より施行され、新しい公益法人制度がスタートしたが、平成25年11月までの5年間の移行期間も残すところあと3年をきっている。
内閣府によれば、100年以上公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなってきたこと、民間による非営利の活動を活発にし、民(みん)による公益を増進するとともに、官庁ごとに法人の設立・運営にばらつきがあったことなどの問題解決を目的としているとされている。
また新しい公益法人会計基準(いわゆる20年改正基準)が公表され、平成20年度税制改正による新たな税制も明らかになっているところである。
しかし、全国で2万5千あったといわれている社団法人・財団法人(民法34条法人)(脚注2)のうち、新公益法人制度への移行申請を行った法人数はいまだ10%に満たない(図表1参照)。
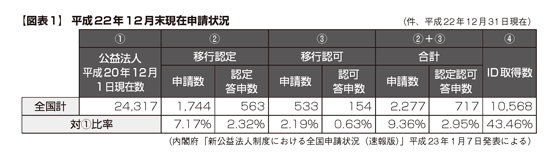
公益三法等法制の複雑さ、法人内部の意思決定に時間のかかること、同業種他法人の様子伺い等の事情もさることながら、会計制度及び税制がわかりづらい面も移行申請を遅らせている一因であると思われる。なお、移行申請にあたりIDを取得した法人は40%以上にのぼり、準備が進んでいることが伺われる。
公益社団・財団法人は、公益目的事業であればたとえ従来型の法人税法上の収益事業であっても課税されない(法令5②)。一方、一般社団・財団法人のうち、非営利型法人は収益事業課税(法法4①)、非営利型法人以外のものは、法人税法上、普通法人として全所得課税となるなど、公益社団・財団法人については各種の税制が優遇(脚注3)され、他方、一般社団・財団法人に関しては課税強化となっている。
そこで本稿では、誌面の都合上、新公益法人制度の公益三法上の留意点(脚注4)は割愛し、主として税制上の課題や留意点をまとめてみた。
Ⅱ.法人区分と定款記載
1.定款記載パターンは6区分 既存の社団法人・財団法人は公益法人改革の中で、その施行日である平成20年12月1日以降は特例民法法人である一般社団・財団法人として存続(整備法40)し、平成25年11月までの5年間の移行期間中に、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請をしなければ解散したものとみなされる(整備法44~46)。
平成20年度税制改正では、公益認定等委員会で行う公益性の認定及び公益目的事業の判断を税制上もそのまま受け入れ、公益法人等として法人税法別表二に掲げる法人から民法34条法人を削除(但し、移行期間中は特例民法法人である一般社団・財団法人は、税法上の措置も含めて現在の地位がそのまま維持される(平成20年改正法附則10))し、公益社団・財団法人、非営利型法人に該当する一般社団・財団法人を追加した(図表2参照)。
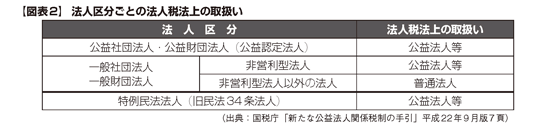
このように、平成20年度税制改正による新たな税制の枠組みが存在することから、法人のステータスの選択とそれに伴う定款変更にあたっては、税制を十分理解しておく必要がある。
公益三法では公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人の2区分であるが、税制を当てはめると、定款の定めの区分は次の図表3-1のパターン1から6のとおり、6区分になるので、自らの特例民法法人の移行時の定款変更にあたっては、留意が必要である。
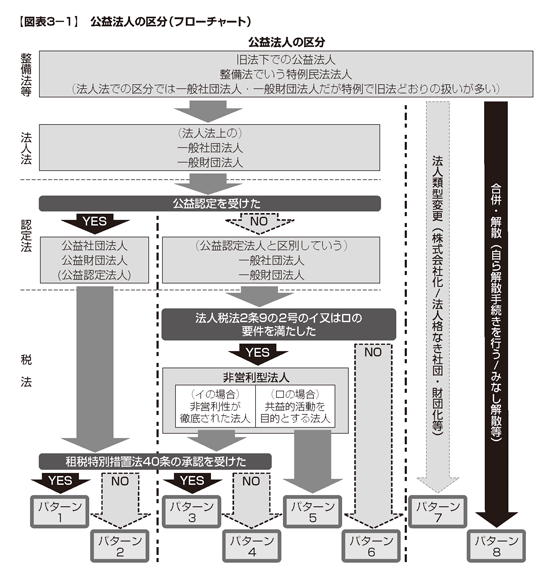
2.法人区分と税務の取扱いの概要 図表3-1の区分に従うと、税務の取扱いがどのように変わるかを概観すると次の図表3-2のとおりとなる。また税務の取扱いの概要は以下のとおりである(下記①~⑦は図表3-2に対応する)。
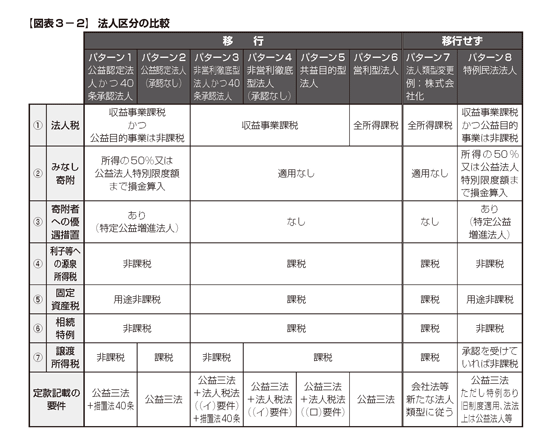
① 公益社団・財団法人は、認定法に規定する公益目的事業であればたとえ従来の収益事業であっても課税としない(法令5②)。一般社団・財団法人については非営利型法人は「公益法人等」として収益事業課税となり、営利型法人は「普通法人」として全所得課税となる(法法4①)。
② 公益社団・財団法人については、みなし寄附金制度が大幅拡充された(法法37⑤、法令77の3)。一般社団・財団法人については、みなし寄附を認めずに課税ベースが拡大されている。
③ 公益社団・財団法人をすべて特定公益増進法人とし、寄附金優遇措置の対象とする(法令77三)。平成23年度税制改正大綱においてさらに拡充される。
④ 公益社団・財団法人については、利子・配当等についての所得税非課税法人とする(所法別表一)。
なお、公益社団・財団法人については非課税、一般社団・財団法人については課税という原則論だけで対応することは余りにも問題が大きく、平成23年度税制改正大綱において、特例民法法人から一般社団・財団法人に移行した特定退職金共済団体について一部緩和されている。
⑤ 公益社団・財団法人が設置する、幼稚園、医療関係者養成所、図書館、博物館、一定の社会福祉事業、学術研究等の用途に直接供する固定資産の固定資産税については、特例民法法人同様、非課税とする(地法348②九、九の二、十二、二十六ほか)。一般社団・財団法人に移行した法人については平成25年度分まで非課税。但し、医療関係者養成所については、非営利型の一般社団・財団法人に非課税規定がある(地法348②九の二)。
なお、平成23年度税制改正大綱においては、特例民法法人から一般社団・財団法人へ移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、平成23年度中の調査、検討を行うことが記載されている。一般社団・財団法人については課税という原則論だけで対応することは余りにも問題が大きい。博物館、幼稚園は博物館法や学校教育法で設置法人も限定され、ガバナンスも効いているのであるから、経過措置を設けるべきである。
⑥ 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税措置の適用対象となる法人の範囲から、旧民法34条法人が除外され、代わりに公益社団・財団法人が追加された(措置法70①)。なお、特例民法法人については所要の経過措置が講じられている。
⑦ 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の適用対象となる法人の範囲が旧民法34条法人から公益社団・財団法人及び非営利型の一般社団・財団法人のうち非営利徹底法人に改められた(措置法40)。
なお、譲渡所得等の非課税の特例承認を継続する場合には、公益三法により記載すべき事項に加えて定款記載事項を追加しなければならない(次号以降掲載予定の「Ⅱ7.公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」参照)。
3.法人税率 現行では、移行後の一般社団・財団法人並びに公益社団・財団法人の各事業年度の所得に対する法人税は30%の税率(法法66①)、所得の金額のうち年800万円以下の金額については、22%の税率によることとされている(法法66②)。
平成23年度税制改正大綱では、法人実効税率(国税と地方税を合わせた表面税率)が5%引き下げられ、現在30%である普通法人に係る国税の法人税率(法法66①)は25.5%に引き下げられ、中小法人等に係る軽減税率18%についても、15%に引き下げることとされている。また、法人税法における軽減税率22%についても19%に引き下げることとされている。
現行では、特例民法法人に対して課する各事業年度の所得に対しては22%の税率という経過措置となっている(法法66③)。一般社団・財団法人へ移行する場合には、前述した図表3-2で述べた各種税制上の措置、なかでもみなし寄附金が認められずに課税ベースが拡大され、かつ税率が22%から30%に引き上げられることとなり、税率構造においても増税となることに留意が必要である。
この税率の改正経過及び公益法人の類型別の法人税率は図表4のとおりである。
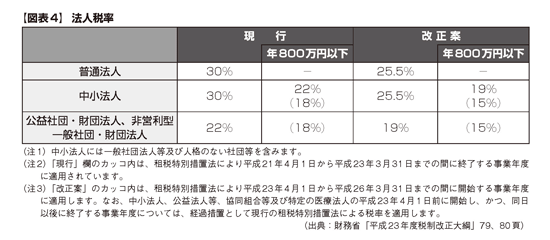
4.人格のない社団等と支部 現在、支部を持つ特例民法法人が、支部の扱いをどうするかという課題に直面している。支部を人格のない社団として別会計・別組織として扱っているものが多く、移行申請に際して、上部組織(いわゆる「支部」に対して「本会」)と連結するのか、連結する場合には資産や組織規定をどうするのか、また別の一般社団法人へ移行させるか、従来どおり人格のない社団として存続するのか、その他の選択をするのか議論が進行している。
人格のない社団等(脚注5)は収益事業課税であり(法法4①)、収益事業以外の所得については法人税は課されない(法法5、7)。結果的に課税所得の範囲は非営利型法人に該当する一般社団・財団法人と同じであり、税率も同じである(図表4参照)。なお、法人法により制約を受ける営利型の一般社団・財団法人(普通法人)は、全所得課税であるので、人格のない社団等に比較して不均衡かつ不合理である。
公益認定は法人全体について行うものであり、人格のない社団等となっている支部についても、法人の一部として公益認定を受けるのであれば人格のない社団を定款上も明らかにしなければならない。人格のない社団を定款上、支部と定めずに公益認定を受けた場合には、認定法9条の名称の使用独占の規定に反することとなる(公益認定等委員会FAQⅢ-1-①参照)。
なお、従来、法人格を異にする団体が支部を名乗ることについては慎重に取り扱われていたが、以下のような扱いとなった(脚注6)。
① 任意団体や個人を法人の支部として位置づけている場合、移行認定申請にあたっては、その支部は法人の“中”なのか(法人の一部なのか)、それとも“外”なのか(法人格を異にするのか)を整理する必要がある。
② 支部を法人の“外”と位置づけた場合でも、法人支部を名乗ることについて、不正目的での名称使用(認定法9⑤)に該当しないことが確認できるのであれば、当該支部が「○○協会××支部」を名乗ることは可能。
※但し、特例社団法人でないものが「社団法人」を、公益社団法人でないものが「公益社団法人」を、その名称に冠することはできない(認定法9④、整備法42⑤⑥)。
また公益法人会計基準(いわゆる20年改正基準)においても「支部を有する法人については支部の活動等を勘案して内訳表(正味財産増減計算書、貸借対照表内訳表をいう)を作成するものとする」としている(脚注7)。
人格のない社団等となっている支部については、税務上も会計上も、さらには名称も含めて公益三法上の取扱いを充分に留意しなければならない。
5.非営利型法人と営利型法人
(1)非営利型法人の2類型 一般社団・財団法人については、法人税法上、非営利型法人と営利型法人の区分(図表3-1、3-2のパターン3~6参照)を設けた。さらに譲渡所得等の非課税の特例(措法40)適用の適否により定款の定め方が異なってくるので留意が必要である。
そもそも、①法人法239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とあり、剰余金の分配が完全に遮断されているわけではないこと、②行う事業の範囲に制約がなく、公益性を担保する制度上の仕組みを有していないことから、図表5のとおり、法人税法により独自の要件を定めている。
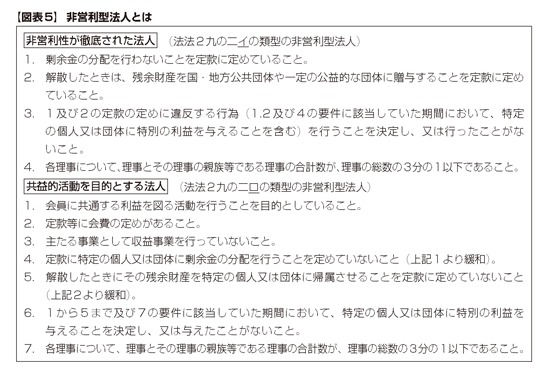
なお、共益的活動を目的とする法人の要件中、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定にあたっては、合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるか否かで判定すること(法基通1-1-10)(脚注8)、及び実費弁償方式による業務等はここでの収益事業に当たらないこと(法基通1-1-11)(脚注9)が明らかにされている。
(2)定款記載事項の比較 一般社団・財団法人については法人税法上さらに非営利型法人と営利型法人の区分を設けられていることは上記(1)のとおりであり、したがって、定款を単に公益三法の定めだけで規律してはいけないこととなる(図表6参照)。
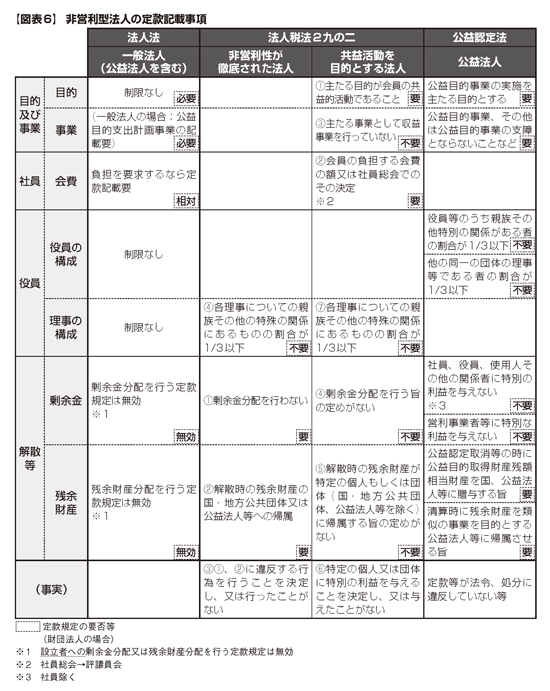
(イ)非営利性が徹底された法人と(ロ)共益的活動を目的とする法人の要件は図表6のとおり異なっている。
特徴的なのは、①剰余金の配当、残余財産の帰属について、非営利徹底型法人は積極的に定款規定が必要であり、これに対して、共益的法人では消極的に定款規定がないことが要件となっている点で異なっていること、②非営利徹底型法人においては収益事業の規模に制限がないこと、これに対して共益的法人では主たる事業として収益事業を行っていないことという制限があるので、個々の法人の性格に応じて選択をする必要があることに留意が必要である。
(3)非営利型法人の税務リスク 非営利型法人の要件のすべてに該当する一般社団・財団法人は、特段の手段を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となり、非営利型法人が、その要件のうち、1つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となる(図表7参照)。
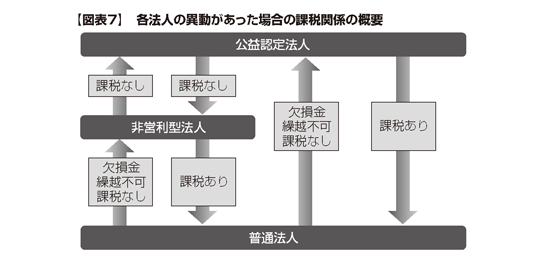
なお、特例民法法人が公益認定法人、非営利型法人又は普通法人になった場合、及び普通法人が公益認定法人又は非営利型法人になったときは速やかに所轄税務署へ「異動届出書」(書式1参照)の提出をすることとなる。
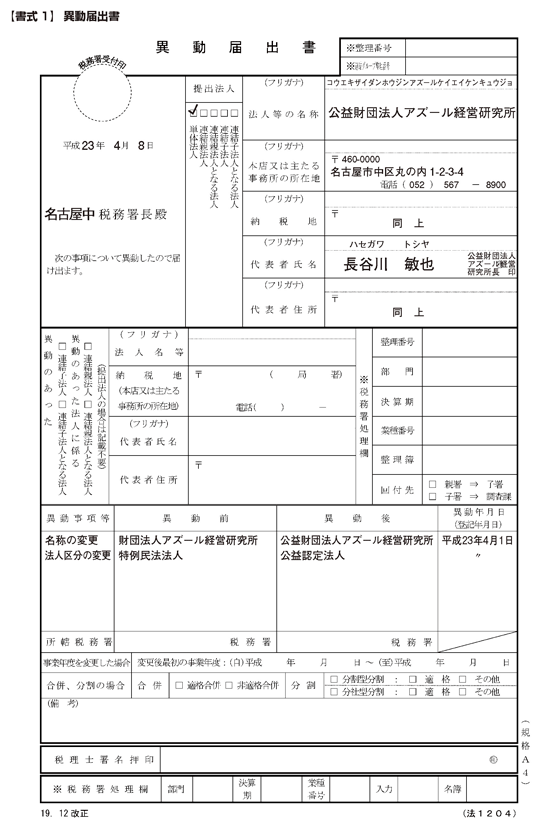
異動届出書では、法人区分は、①公益認定を受けているものを「公益認定法人」、②法人税法上の非営利型法人に該当しているものを「非営利型法人」、③①及び②以外のもので行政庁の認可を受けているものを「普通法人」とし、④行政庁の認定又は認可を受ける前の社団法人又は財団法人を「特例民法法人」としている。
また、法人税申告書別表一(一)においても「非営利型法人」「普通法人」の区分しかない。非営利が徹底された法人なのか共益的活動を目的としている法人なのか(法法2九の二でいうイなのかロなのか)の宣言場所はない。
ここでの留意点は、非営利型法人が、剰余金の分配を行うことを決定し、又は行った場合や、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたこと(法基通1-1-8)(脚注10)により普通法人となった場合、その後は永久に同類型の非営利型法人になることはできない(法基通1-1-9)こと、理事の死亡等で、やむを得ず親族関係にある者などについての割合の要件を充足できなくなる場合などがあるということである。
特例民法法人から非営利型法人に移行できたとしても、その後の税務調査によりこれらの点が指摘され、要件のうち1つでも満たさないと、普通法人(全課税法人)とみなされて多額の税負担が発生する場合がある(脚注11)ので、特段の留意が必要である。
(4)営利型法人 非営利型法人以外の法人(普通法人)の課税については既に概説した(図表3-2、4等参照)ところであるが、持分のない法人であるので、株式会社の税制とはたとえば次の点が異なる。
① 資本金を有しないので、「中小企業者」の判定は従業員数1,000人基準のみ(措令27の4⑩)。
② 資本金を有しないので、交際費等の定額控除限度額は純資産額の60%相当金額(措令37の4一)。
③ 資本金等の額を有しないので、法人住民税均等割標準税率は最低(道府県民税年額2万円、市町村民税5万円)(地法52、312)。
④ 同族会社ではないので留保金課税の適用や非常勤役員の定期同額給与制限はない(法法2①十、34、67、法基通9-2-12(脚注12))。
脚注
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)の三法をいう。
2 公益法人インフォメーションにリンクされている平成21年度『特例民法法人に関する年次報告』(内閣府)によれば、平成20年12月1日現在、公益法人の総数は24,317法人だった。
3 認定法では、「公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする(認定法58)」という明文の規定を置いている。
4 拙著(共著)『Q&A新公益法人の実務ハンドブック~移行・設立・運営・会計・税務』(清文社、2009年3月)に詳しい記載がある。
5 【法人税基本通達1-1-1(法人でない社団の範囲)(抜粋)】
人格のない社団等の意義に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいう。
【法人税基本通達1-1-2(法人でない財団の範囲)(抜粋)】
人格のない社団等の意義に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。
【法人税基本通達1-1-3(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)(抜粋)】
法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
6 内閣府公益認定等委員会事務局「公益認定等委員会だより(その5)」(平成23年1月1日)参照。
7 「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)13「様式について」に明記されている。
8 【法人税基本通達1-1-10(主たる事業の判定)】
令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》に規定する「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当するかどうかは、原則として、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において、主たる事業であるかどうかは、法人の事業の態様に応じて、例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し、当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。
ただし、その法人の行う事業の内容に変更があるなど、収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き、当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには、その法人は、当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加)
(注)本文後段の判定を行った結果、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても、そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。
9 【法人税基本通達1-1-11(収益事業を行っていないことの判定)】
一般社団法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとし、当該一般社団法人等の収益事業としないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。(平21年課法2-5「二」により追加)
10 【法人税基本通達1-1-8 (非営利型法人における特別の利益の意義)】
令第3条第1項第3号及び第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する「特別の利益を与えること」とは、例えば、次に掲げるような経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう。
(1)法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。
(2)法人が、特定の個人又は団体に対し、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けていること。
(3)法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。
(4)法人が、特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借していること又は通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。
(5)法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲り受けていること又は法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。
(6)法人が、特定の個人に対し、過大な給与等を支給していること。
なお、「特別の利益を与えること」には、収益事業に限らず、収益事業以外の事業において行われる経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。
11 本稿第4回で詳述する。
12 【法人税基本通達9-2-12(定期同額給与の意義)】
法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
(注)非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1)同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2)同族会社が支給する給与で令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
税制から見た新公益法人制度の留意点(1)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.はじめに
公益法人制度改革関連三法(脚注1)(以下「公益三法」という)が平成20年12月1日より施行され、新しい公益法人制度がスタートしたが、平成25年11月までの5年間の移行期間も残すところあと3年をきっている。
内閣府によれば、100年以上公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなってきたこと、民間による非営利の活動を活発にし、民(みん)による公益を増進するとともに、官庁ごとに法人の設立・運営にばらつきがあったことなどの問題解決を目的としているとされている。
また新しい公益法人会計基準(いわゆる20年改正基準)が公表され、平成20年度税制改正による新たな税制も明らかになっているところである。
しかし、全国で2万5千あったといわれている社団法人・財団法人(民法34条法人)(脚注2)のうち、新公益法人制度への移行申請を行った法人数はいまだ10%に満たない(図表1参照)。
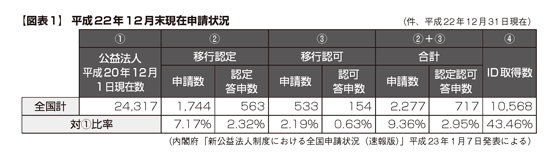
公益三法等法制の複雑さ、法人内部の意思決定に時間のかかること、同業種他法人の様子伺い等の事情もさることながら、会計制度及び税制がわかりづらい面も移行申請を遅らせている一因であると思われる。なお、移行申請にあたりIDを取得した法人は40%以上にのぼり、準備が進んでいることが伺われる。
公益社団・財団法人は、公益目的事業であればたとえ従来型の法人税法上の収益事業であっても課税されない(法令5②)。一方、一般社団・財団法人のうち、非営利型法人は収益事業課税(法法4①)、非営利型法人以外のものは、法人税法上、普通法人として全所得課税となるなど、公益社団・財団法人については各種の税制が優遇(脚注3)され、他方、一般社団・財団法人に関しては課税強化となっている。
そこで本稿では、誌面の都合上、新公益法人制度の公益三法上の留意点(脚注4)は割愛し、主として税制上の課題や留意点をまとめてみた。
Ⅱ.法人区分と定款記載
1.定款記載パターンは6区分 既存の社団法人・財団法人は公益法人改革の中で、その施行日である平成20年12月1日以降は特例民法法人である一般社団・財団法人として存続(整備法40)し、平成25年11月までの5年間の移行期間中に、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請をしなければ解散したものとみなされる(整備法44~46)。
平成20年度税制改正では、公益認定等委員会で行う公益性の認定及び公益目的事業の判断を税制上もそのまま受け入れ、公益法人等として法人税法別表二に掲げる法人から民法34条法人を削除(但し、移行期間中は特例民法法人である一般社団・財団法人は、税法上の措置も含めて現在の地位がそのまま維持される(平成20年改正法附則10))し、公益社団・財団法人、非営利型法人に該当する一般社団・財団法人を追加した(図表2参照)。
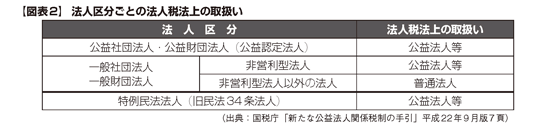
このように、平成20年度税制改正による新たな税制の枠組みが存在することから、法人のステータスの選択とそれに伴う定款変更にあたっては、税制を十分理解しておく必要がある。
公益三法では公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人の2区分であるが、税制を当てはめると、定款の定めの区分は次の図表3-1のパターン1から6のとおり、6区分になるので、自らの特例民法法人の移行時の定款変更にあたっては、留意が必要である。
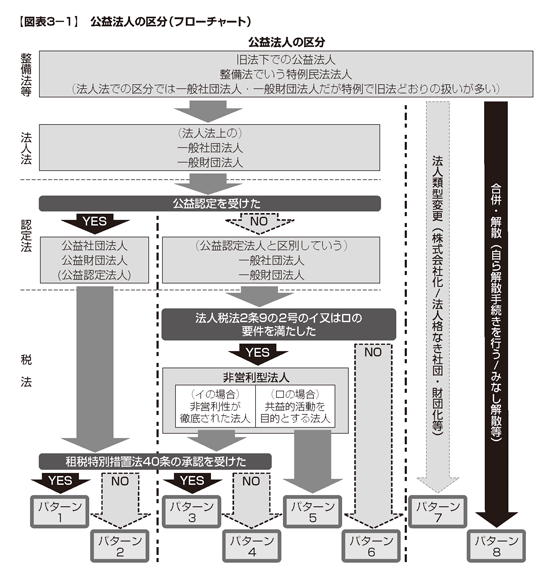
2.法人区分と税務の取扱いの概要 図表3-1の区分に従うと、税務の取扱いがどのように変わるかを概観すると次の図表3-2のとおりとなる。また税務の取扱いの概要は以下のとおりである(下記①~⑦は図表3-2に対応する)。
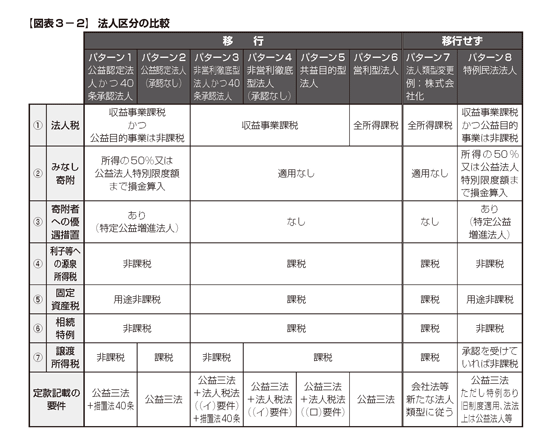
① 公益社団・財団法人は、認定法に規定する公益目的事業であればたとえ従来の収益事業であっても課税としない(法令5②)。一般社団・財団法人については非営利型法人は「公益法人等」として収益事業課税となり、営利型法人は「普通法人」として全所得課税となる(法法4①)。
② 公益社団・財団法人については、みなし寄附金制度が大幅拡充された(法法37⑤、法令77の3)。一般社団・財団法人については、みなし寄附を認めずに課税ベースが拡大されている。
③ 公益社団・財団法人をすべて特定公益増進法人とし、寄附金優遇措置の対象とする(法令77三)。平成23年度税制改正大綱においてさらに拡充される。
④ 公益社団・財団法人については、利子・配当等についての所得税非課税法人とする(所法別表一)。
なお、公益社団・財団法人については非課税、一般社団・財団法人については課税という原則論だけで対応することは余りにも問題が大きく、平成23年度税制改正大綱において、特例民法法人から一般社団・財団法人に移行した特定退職金共済団体について一部緩和されている。
⑤ 公益社団・財団法人が設置する、幼稚園、医療関係者養成所、図書館、博物館、一定の社会福祉事業、学術研究等の用途に直接供する固定資産の固定資産税については、特例民法法人同様、非課税とする(地法348②九、九の二、十二、二十六ほか)。一般社団・財団法人に移行した法人については平成25年度分まで非課税。但し、医療関係者養成所については、非営利型の一般社団・財団法人に非課税規定がある(地法348②九の二)。
なお、平成23年度税制改正大綱においては、特例民法法人から一般社団・財団法人へ移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、平成23年度中の調査、検討を行うことが記載されている。一般社団・財団法人については課税という原則論だけで対応することは余りにも問題が大きい。博物館、幼稚園は博物館法や学校教育法で設置法人も限定され、ガバナンスも効いているのであるから、経過措置を設けるべきである。
⑥ 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税措置の適用対象となる法人の範囲から、旧民法34条法人が除外され、代わりに公益社団・財団法人が追加された(措置法70①)。なお、特例民法法人については所要の経過措置が講じられている。
⑦ 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の適用対象となる法人の範囲が旧民法34条法人から公益社団・財団法人及び非営利型の一般社団・財団法人のうち非営利徹底法人に改められた(措置法40)。
なお、譲渡所得等の非課税の特例承認を継続する場合には、公益三法により記載すべき事項に加えて定款記載事項を追加しなければならない(次号以降掲載予定の「Ⅱ7.公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」参照)。
3.法人税率 現行では、移行後の一般社団・財団法人並びに公益社団・財団法人の各事業年度の所得に対する法人税は30%の税率(法法66①)、所得の金額のうち年800万円以下の金額については、22%の税率によることとされている(法法66②)。
平成23年度税制改正大綱では、法人実効税率(国税と地方税を合わせた表面税率)が5%引き下げられ、現在30%である普通法人に係る国税の法人税率(法法66①)は25.5%に引き下げられ、中小法人等に係る軽減税率18%についても、15%に引き下げることとされている。また、法人税法における軽減税率22%についても19%に引き下げることとされている。
現行では、特例民法法人に対して課する各事業年度の所得に対しては22%の税率という経過措置となっている(法法66③)。一般社団・財団法人へ移行する場合には、前述した図表3-2で述べた各種税制上の措置、なかでもみなし寄附金が認められずに課税ベースが拡大され、かつ税率が22%から30%に引き上げられることとなり、税率構造においても増税となることに留意が必要である。
この税率の改正経過及び公益法人の類型別の法人税率は図表4のとおりである。
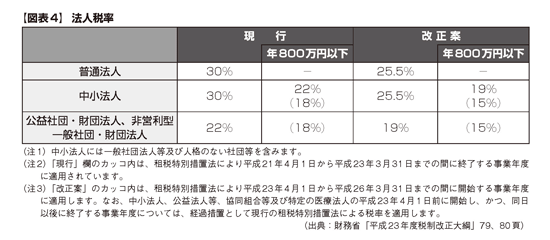
4.人格のない社団等と支部 現在、支部を持つ特例民法法人が、支部の扱いをどうするかという課題に直面している。支部を人格のない社団として別会計・別組織として扱っているものが多く、移行申請に際して、上部組織(いわゆる「支部」に対して「本会」)と連結するのか、連結する場合には資産や組織規定をどうするのか、また別の一般社団法人へ移行させるか、従来どおり人格のない社団として存続するのか、その他の選択をするのか議論が進行している。
人格のない社団等(脚注5)は収益事業課税であり(法法4①)、収益事業以外の所得については法人税は課されない(法法5、7)。結果的に課税所得の範囲は非営利型法人に該当する一般社団・財団法人と同じであり、税率も同じである(図表4参照)。なお、法人法により制約を受ける営利型の一般社団・財団法人(普通法人)は、全所得課税であるので、人格のない社団等に比較して不均衡かつ不合理である。
公益認定は法人全体について行うものであり、人格のない社団等となっている支部についても、法人の一部として公益認定を受けるのであれば人格のない社団を定款上も明らかにしなければならない。人格のない社団を定款上、支部と定めずに公益認定を受けた場合には、認定法9条の名称の使用独占の規定に反することとなる(公益認定等委員会FAQⅢ-1-①参照)。
なお、従来、法人格を異にする団体が支部を名乗ることについては慎重に取り扱われていたが、以下のような扱いとなった(脚注6)。
① 任意団体や個人を法人の支部として位置づけている場合、移行認定申請にあたっては、その支部は法人の“中”なのか(法人の一部なのか)、それとも“外”なのか(法人格を異にするのか)を整理する必要がある。
② 支部を法人の“外”と位置づけた場合でも、法人支部を名乗ることについて、不正目的での名称使用(認定法9⑤)に該当しないことが確認できるのであれば、当該支部が「○○協会××支部」を名乗ることは可能。
※但し、特例社団法人でないものが「社団法人」を、公益社団法人でないものが「公益社団法人」を、その名称に冠することはできない(認定法9④、整備法42⑤⑥)。
また公益法人会計基準(いわゆる20年改正基準)においても「支部を有する法人については支部の活動等を勘案して内訳表(正味財産増減計算書、貸借対照表内訳表をいう)を作成するものとする」としている(脚注7)。
人格のない社団等となっている支部については、税務上も会計上も、さらには名称も含めて公益三法上の取扱いを充分に留意しなければならない。
5.非営利型法人と営利型法人
(1)非営利型法人の2類型 一般社団・財団法人については、法人税法上、非営利型法人と営利型法人の区分(図表3-1、3-2のパターン3~6参照)を設けた。さらに譲渡所得等の非課税の特例(措法40)適用の適否により定款の定め方が異なってくるので留意が必要である。
そもそも、①法人法239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とあり、剰余金の分配が完全に遮断されているわけではないこと、②行う事業の範囲に制約がなく、公益性を担保する制度上の仕組みを有していないことから、図表5のとおり、法人税法により独自の要件を定めている。
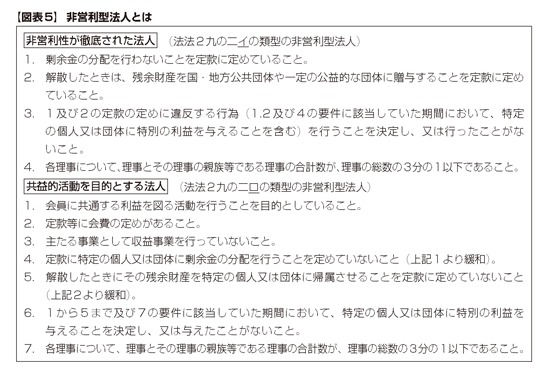
なお、共益的活動を目的とする法人の要件中、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定にあたっては、合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるか否かで判定すること(法基通1-1-10)(脚注8)、及び実費弁償方式による業務等はここでの収益事業に当たらないこと(法基通1-1-11)(脚注9)が明らかにされている。
(2)定款記載事項の比較 一般社団・財団法人については法人税法上さらに非営利型法人と営利型法人の区分を設けられていることは上記(1)のとおりであり、したがって、定款を単に公益三法の定めだけで規律してはいけないこととなる(図表6参照)。
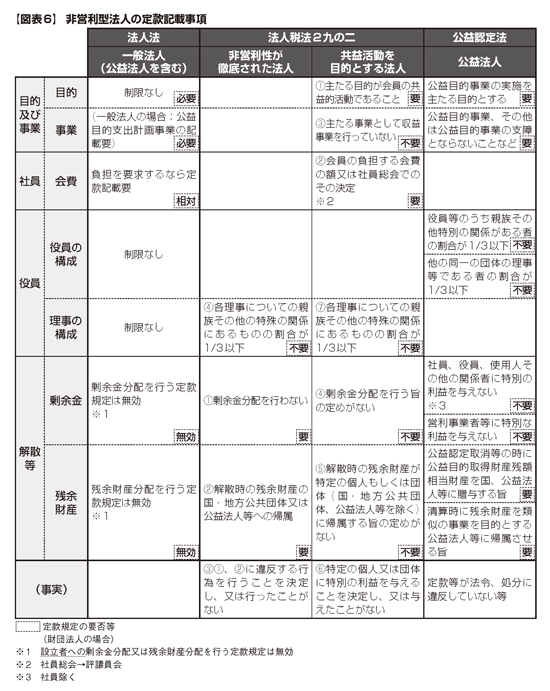
(イ)非営利性が徹底された法人と(ロ)共益的活動を目的とする法人の要件は図表6のとおり異なっている。
特徴的なのは、①剰余金の配当、残余財産の帰属について、非営利徹底型法人は積極的に定款規定が必要であり、これに対して、共益的法人では消極的に定款規定がないことが要件となっている点で異なっていること、②非営利徹底型法人においては収益事業の規模に制限がないこと、これに対して共益的法人では主たる事業として収益事業を行っていないことという制限があるので、個々の法人の性格に応じて選択をする必要があることに留意が必要である。
(3)非営利型法人の税務リスク 非営利型法人の要件のすべてに該当する一般社団・財団法人は、特段の手段を踏むことなく公益法人等である非営利型法人となり、非営利型法人が、その要件のうち、1つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となる(図表7参照)。
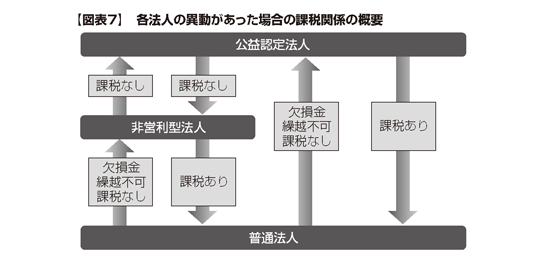
なお、特例民法法人が公益認定法人、非営利型法人又は普通法人になった場合、及び普通法人が公益認定法人又は非営利型法人になったときは速やかに所轄税務署へ「異動届出書」(書式1参照)の提出をすることとなる。
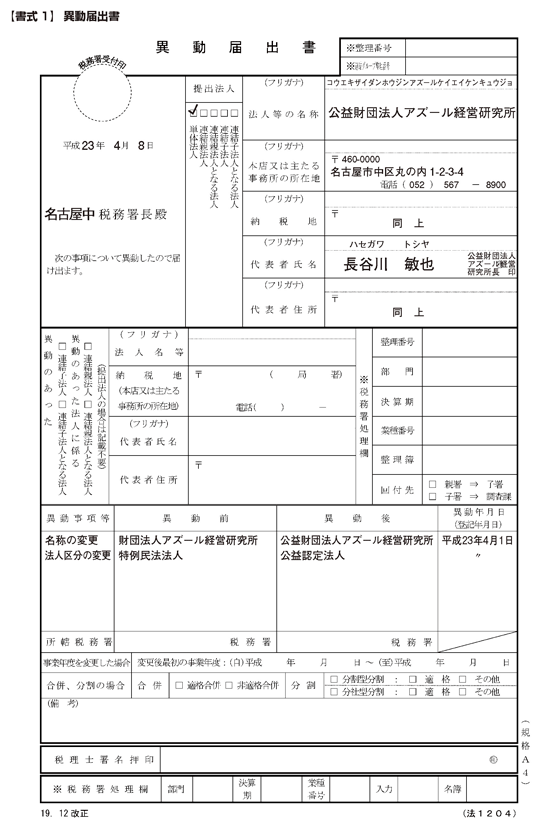
異動届出書では、法人区分は、①公益認定を受けているものを「公益認定法人」、②法人税法上の非営利型法人に該当しているものを「非営利型法人」、③①及び②以外のもので行政庁の認可を受けているものを「普通法人」とし、④行政庁の認定又は認可を受ける前の社団法人又は財団法人を「特例民法法人」としている。
また、法人税申告書別表一(一)においても「非営利型法人」「普通法人」の区分しかない。非営利が徹底された法人なのか共益的活動を目的としている法人なのか(法法2九の二でいうイなのかロなのか)の宣言場所はない。
ここでの留意点は、非営利型法人が、剰余金の分配を行うことを決定し、又は行った場合や、特定の個人や団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたこと(法基通1-1-8)(脚注10)により普通法人となった場合、その後は永久に同類型の非営利型法人になることはできない(法基通1-1-9)こと、理事の死亡等で、やむを得ず親族関係にある者などについての割合の要件を充足できなくなる場合などがあるということである。
特例民法法人から非営利型法人に移行できたとしても、その後の税務調査によりこれらの点が指摘され、要件のうち1つでも満たさないと、普通法人(全課税法人)とみなされて多額の税負担が発生する場合がある(脚注11)ので、特段の留意が必要である。
(4)営利型法人 非営利型法人以外の法人(普通法人)の課税については既に概説した(図表3-2、4等参照)ところであるが、持分のない法人であるので、株式会社の税制とはたとえば次の点が異なる。
① 資本金を有しないので、「中小企業者」の判定は従業員数1,000人基準のみ(措令27の4⑩)。
② 資本金を有しないので、交際費等の定額控除限度額は純資産額の60%相当金額(措令37の4一)。
③ 資本金等の額を有しないので、法人住民税均等割標準税率は最低(道府県民税年額2万円、市町村民税5万円)(地法52、312)。
④ 同族会社ではないので留保金課税の適用や非常勤役員の定期同額給与制限はない(法法2①十、34、67、法基通9-2-12(脚注12))。
脚注
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)の三法をいう。
2 公益法人インフォメーションにリンクされている平成21年度『特例民法法人に関する年次報告』(内閣府)によれば、平成20年12月1日現在、公益法人の総数は24,317法人だった。
3 認定法では、「公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする(認定法58)」という明文の規定を置いている。
4 拙著(共著)『Q&A新公益法人の実務ハンドブック~移行・設立・運営・会計・税務』(清文社、2009年3月)に詳しい記載がある。
5 【法人税基本通達1-1-1(法人でない社団の範囲)(抜粋)】
人格のない社団等の意義に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいう。
【法人税基本通達1-1-2(法人でない財団の範囲)(抜粋)】
人格のない社団等の意義に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。
【法人税基本通達1-1-3(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)(抜粋)】
法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
6 内閣府公益認定等委員会事務局「公益認定等委員会だより(その5)」(平成23年1月1日)参照。
7 「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)13「様式について」に明記されている。
8 【法人税基本通達1-1-10(主たる事業の判定)】
令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》に規定する「主たる事業として収益事業を行つていない」場合に該当するかどうかは、原則として、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において、主たる事業であるかどうかは、法人の事業の態様に応じて、例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し、当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。
ただし、その法人の行う事業の内容に変更があるなど、収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き、当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには、その法人は、当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加)
(注)本文後段の判定を行った結果、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても、そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。
9 【法人税基本通達1-1-11(収益事業を行っていないことの判定)】
一般社団法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとし、当該一般社団法人等の収益事業としないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。(平21年課法2-5「二」により追加)
10 【法人税基本通達1-1-8 (非営利型法人における特別の利益の意義)】
令第3条第1項第3号及び第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する「特別の利益を与えること」とは、例えば、次に掲げるような経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう。
(1)法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。
(2)法人が、特定の個人又は団体に対し、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けていること。
(3)法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。
(4)法人が、特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借していること又は通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。
(5)法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲り受けていること又は法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。
(6)法人が、特定の個人に対し、過大な給与等を支給していること。
なお、「特別の利益を与えること」には、収益事業に限らず、収益事業以外の事業において行われる経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。
11 本稿第4回で詳述する。
12 【法人税基本通達9-2-12(定期同額給与の意義)】
法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
(注)非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1)同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2)同族会社が支給する給与で令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.