解説記事2011年02月21日 【ニュース特集】 動き出したグループ法人税制最新実務からのQ&A(2011年2月21日号・№391)
出資関係図の範囲から親会社株式の現物分配とみなし配当の関係まで
動き出したグループ法人税制最新実務からのQ&A
昨年10月1日よりグループ法人税制が適用開始となってからおよそ5か月が経過したが、実務上の疑問点は尽きないようだ。
本特集では、出資関係図の記載範囲から親会社株式の現物分配とみなし配当規定の関係まで、実務家の間で挙がっている疑問をピックアップし、Q&A形式でお届けする。
Q1 グループ法人税制の適用法人
一般社団法人や特定目的会社、合同会社はグループ法人税制(譲渡損益の繰延べ、寄附金の損金・益金不算入等)の適用対象になりますか?
A 特定目的会社、合同会社は適用対象となります。一般社団法人については、グループの頂点に立つ場合には適用対象になります。 グループ法人税制(※)の適用を受けるためには、法人間の「完全支配関係」が求められることになります。法人税法上、完全支配関係とは「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(当事者間の完全支配の関係)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」とされていることから(法法2十二の七の六)、完全支配関係とは「株式または出資」を通じてはじめて成立し得るものであることがわかります。
一般社団法人(および一般財団法人。以下同じ)とは、設立者が300万円以上の財産を拠出して設立する法人ですが、株式会社等とは異なり、財産を拠出した者には剰余金の配当請求権や株主総会の議決権もなければ、財産の返還請求権もありません。すなわち、一般社団法人には株式や出資の概念がないことになりますので、完全支配関係を構成することができず、グループ税制の適用対象とはなりません(図1左参照)。ただし、一般社団法人が株式や出資を通じて他法人を支配することは可能であり、また、一般社団法人は法人税法上は普通法人に該当しますので、一般社団法人が100%グループの頂点に立つ場合には100%グループの一部を構成する法人として、グループ法人税制の適用対象となります(図1右参照)。
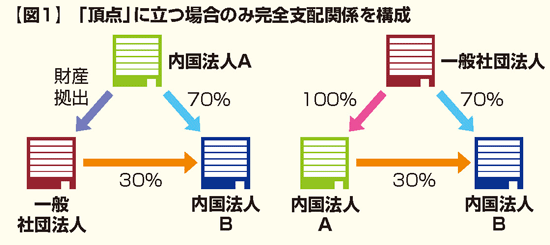
これに対し、合同会社、特定目的会社は出資を受けることができるため、100%グループの頂点に立つか否かにかかわらず、グループ法人税制の適用対象となります。
※ 100%グループ内の法人間における資産の譲渡に係る譲渡損益の繰延べ(法法61の13)、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度(法法25の2、37②、81の6②)、現物分配(法2十二の六、十二の十五、62の5③)、100%グループ内の法人間の非適格株式交換(法法62の9①)。
Q2 出資関係図への記載範囲
当社は外国に100%子会社を有しています。この100%子会社は内国法人の株式を一切保有していないのですが、課税当局への提出が求められる「出資関係図」に当該外国法人を記載する必要はありますか?
A 記載する必要はありません。 法人税法上、グループ法人税制が適用される法人に対しては「完全支配関係を系統的に示す図」(以下「出資関係図」)を申告書に添付することが求められます(法規35、37の12)。
ただ、図2左における外国法人Cのように、内国法人から出資を「受ける」だけで、内国法人への出資を行っていない法人については、グループ法人税制の適用範囲に何ら影響を及ぼさないことから、課税当局は、出資関係図への記載を求めない方針です。
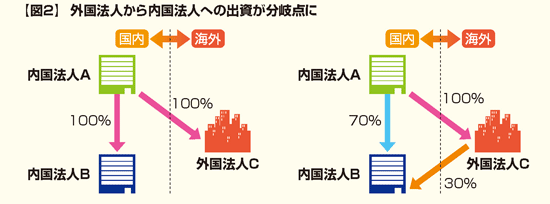
これに対し、図2右においては、外国法人Cが内国法人Bに出資していることに起因して内国法人Aと内国法人Bの間に完全支配関係が生じ、AB間の取引がグループ法人税制の適用対象となり得るため、出資関係図に記載する必要があります。
Q3 税務調査で認定された受贈益の益金不算入
完全支配関係にある法人間で「寄附」の認識のないまま行われた取引について、後の税務調査により寄附金課税が行われた場合であっても、寄附を受けた法人において計上される受贈益は益金不算入とできるのでしょうか?
A はい、できます。 課税当局より、当該受贈益は「当然に職権での減額更正が行われる」ものであって、「納税者側からの更正請求は不要」である旨の見解が示されています。ただし、寄附を行った法人への税務調査がきっかけで寄附金課税が行われた場合、寄附を受けた法人に対して職権更正が行われるのは、寄附を行った法人における処理が完了してからとなるため、実際に職権更正が行われるまでには多少の時間を要することも想定されます。もしあまり時間がかかるようであれば、確認の意味でも、調査官に対して職権更正を求めてみてもよいでしょう(本誌388号7頁参照)。
Q4 債権放棄と新寄附金税制の関係
100%子会社の経営悪化に伴い、当該子会社を解散するとともに、当該子会社に対する貸付金を放棄しようと考えています。この場合、貸付金の放棄に伴い子会社において発生する債務免除益は、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度により益金不算入となるのでしょうか?
A 当該貸付金の放棄が「寄附」に該当しなければ、債務免除益は益金不算入とはなりません。 完全支配関係にある子会社の経営が悪化したため、子会社を解散させるとともに、子会社に対する貸付金を放棄するといったケースは少なくありませんが、ここで1つの論点となるのが寄附金課税の問題です。こうしたケースの場合、貸付金を放棄しなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らかであれば、当該貸付金の放棄は法人税法上「寄附」とはなりません(法基通9-4-1)。この点、グループ法人税制の導入に伴い寄附金税制は見直されましたが、寄附金の概念そのものには何の変更もありません。
法人税基本通達9-4-1によって当該債権放棄が寄附とならなかった場合、親会社および子会社は下記のような処理をすることになりますが、ここで注意したいのは、子会社においては「債務免除益」が立ち、これは課税対象となる(益金不算入とはならない)ということです。
逆にいうと、「債権放棄をしなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らか」でない場合には、当該債権放棄は寄附に該当するとともに子会社には受贈益が立ち、この受贈益は、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度により益金不算入となります。
親会社にとって「経済合理性がある債権放棄(すなわち寄附金課税の対象とならない債権放棄)」が子会社において債務免除益を発生させ課税対象となる一方、「経済合理性のない債権放棄」は寄附となり、新しい寄附金税制によって子会社への受贈益が益金不算入となる点、不合理に感じるかも知れませんが、実際にこのような取扱いとなっていますので注意が必要です。
もっとも、解散する会社は多額の欠損金を有しているのが通常ですので、当該債務免除益に対して課税が行われるケースは少ないと思われます。
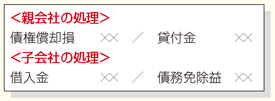
Q5 親会社株式の現物分配とみなし配当規定の関係
親会社株式を剰余金として親会社に配当した場合、親会社にとっては「自己株式」の取得となり、みなし配当に係る規定が適用されますか?
A いいえ、みなし配当に係る規定が適用されることはありません。 会社法上、子会社による親会社株式の取得は原則禁止ですが、たとえば子会社と合併した被合併法人が親会社の株式を保有していた場合、子会社は親会社株式を保有することになります。こうした場合、子会社は相当の時期に親会社株式を処分しなければなりませんが、処分の方法として、当該親会社株式を剰余金として親会社に「現物分配」するやり方があります。そして、当該現物分配が税制適格であれば、現物分配法人(子会社)は譲渡損益を認識する必要がないうえ、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰延措置も適用されず、配当に係る源泉徴収も不要です。
ただ、子会社から親会社に対する親会社株式の現物分配は、親会社の立場からすれば「自己株式の取得」にもみえるため、みなし配当に係る法人税法24条も適用されるのではないかとの指摘があります。
しかし、自己株式を取得した場合にはその対価を支払うのが通常であるにもかかわらず、剰余金の配当として自己株式を取得した場合には、一方的に配当(この場合は自己株式)を受け取るだけであって、対価を支払うことはありません。このように対価自体が存在しないため、みなし配当の計算もしようがなく、したがって、法人税法24条の規定も適用されません。
Q6 親族が保有する会社の合併における対価
親族で保有する兄弟会社を合併させたいと考えています。当該合併を無対価で行った場合でも、税制適格合併となりますか?
A いいえ、税制非適格となります。税制適格とするためには、合併対価を交付する必要があります。 税制適格となる無対価合併は、100%子会社との合併をはじめ4つの類型があり(法令4の3②二イ~ニ)、その1つが兄弟会社の合併です。ここでいう兄弟会社とは、正確には「一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係」とされています(法令4の3②二ロ)。
「一の者」というと、グループ法人税制の完全支配関係の定義を思い浮かべる人も多いと思います。すなわち、「その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人(6親等内の血族、3親等内の姻族等。法令4①)」です(法令4の2②カッコ書き)。
一方、税制適格となる無対価合併の類型における「一の者」(法令4の3②二ロ)とは、文字どおり「1人(社)」を指しています。これは、法令4条の3第2項2号ロにいう「一の者」には、法令4条の2第2項における「一の者」に付されているカッコ書きがないことからも明らかです。仮に法令4条の3第2項2号ロにいう「一の者」が、法令4条の2第2項における「一の者」と同様の意味(特殊関係にある個人を一の者とする)を持つのであれば、法令4条の2第2項のカッコ書き内に「次条において同じ」との文言が入らなければなりません。
したがって、株主が2人いる(一の者でない)図3のような合併を無対価で行った場合には、税制非適格となります。税制適格とするためには、兄弟に対し合併対価を交付する必要があります。
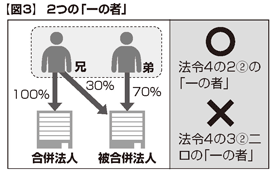
Column
「Q&A」の法的拘束力 近年、新たな制度の導入や影響の大きい改正が実施されるたび、国税庁から必ずといってよいほど出されるようになったのが「Q&A」だ。税制が複雑化するなか、納税者利便の向上を図ろうというのが課税当局側の狙いと思われるが、気になるのはその法的拘束力であり、これまでは法令や通達との関係における位置付けもあやふやだったといえる。
この点について、昨夏以降出されたQ&Aから1つの変化がみられる。昨夏以降に出された3つのQ&A(「外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例について」「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)」)をみると、いずれも法人課税課情報、審理室情報、調査課情報といった形で「情報」への“格上げ”が行われ、課税当局の職員に対し「処分執行の参考にされたい」とのメッセージとともに周知された後に、国税庁ホームページ上で公表されている。これは、Q&Aが基本通達と同様に「国税庁の正式見解、解釈指針」であり、課税当局の職員もこれに沿った執行を行うことを示しているといえる。
また、Q&Aを巡っては、「Q&Aは所詮個別事例に過ぎないので、これにぴったり当てはまらなければ使えないのではないか?」との指摘もあるが、たとえ自分の事例と完全に一致しなくても、Q&Aから課税当局の考え方を読み取り、それに沿った解釈をすることで、課税リスクを減少させることができよう。
動き出したグループ法人税制最新実務からのQ&A
昨年10月1日よりグループ法人税制が適用開始となってからおよそ5か月が経過したが、実務上の疑問点は尽きないようだ。
本特集では、出資関係図の記載範囲から親会社株式の現物分配とみなし配当規定の関係まで、実務家の間で挙がっている疑問をピックアップし、Q&A形式でお届けする。
Q1 グループ法人税制の適用法人
一般社団法人や特定目的会社、合同会社はグループ法人税制(譲渡損益の繰延べ、寄附金の損金・益金不算入等)の適用対象になりますか?
A 特定目的会社、合同会社は適用対象となります。一般社団法人については、グループの頂点に立つ場合には適用対象になります。 グループ法人税制(※)の適用を受けるためには、法人間の「完全支配関係」が求められることになります。法人税法上、完全支配関係とは「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(当事者間の完全支配の関係)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」とされていることから(法法2十二の七の六)、完全支配関係とは「株式または出資」を通じてはじめて成立し得るものであることがわかります。
一般社団法人(および一般財団法人。以下同じ)とは、設立者が300万円以上の財産を拠出して設立する法人ですが、株式会社等とは異なり、財産を拠出した者には剰余金の配当請求権や株主総会の議決権もなければ、財産の返還請求権もありません。すなわち、一般社団法人には株式や出資の概念がないことになりますので、完全支配関係を構成することができず、グループ税制の適用対象とはなりません(図1左参照)。ただし、一般社団法人が株式や出資を通じて他法人を支配することは可能であり、また、一般社団法人は法人税法上は普通法人に該当しますので、一般社団法人が100%グループの頂点に立つ場合には100%グループの一部を構成する法人として、グループ法人税制の適用対象となります(図1右参照)。
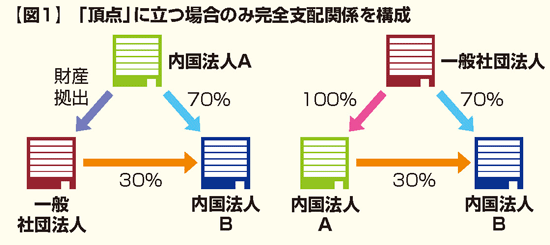
これに対し、合同会社、特定目的会社は出資を受けることができるため、100%グループの頂点に立つか否かにかかわらず、グループ法人税制の適用対象となります。
※ 100%グループ内の法人間における資産の譲渡に係る譲渡損益の繰延べ(法法61の13)、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度(法法25の2、37②、81の6②)、現物分配(法2十二の六、十二の十五、62の5③)、100%グループ内の法人間の非適格株式交換(法法62の9①)。
Q2 出資関係図への記載範囲
当社は外国に100%子会社を有しています。この100%子会社は内国法人の株式を一切保有していないのですが、課税当局への提出が求められる「出資関係図」に当該外国法人を記載する必要はありますか?
A 記載する必要はありません。 法人税法上、グループ法人税制が適用される法人に対しては「完全支配関係を系統的に示す図」(以下「出資関係図」)を申告書に添付することが求められます(法規35、37の12)。
ただ、図2左における外国法人Cのように、内国法人から出資を「受ける」だけで、内国法人への出資を行っていない法人については、グループ法人税制の適用範囲に何ら影響を及ぼさないことから、課税当局は、出資関係図への記載を求めない方針です。
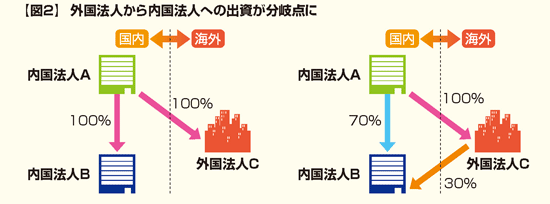
これに対し、図2右においては、外国法人Cが内国法人Bに出資していることに起因して内国法人Aと内国法人Bの間に完全支配関係が生じ、AB間の取引がグループ法人税制の適用対象となり得るため、出資関係図に記載する必要があります。
Q3 税務調査で認定された受贈益の益金不算入
完全支配関係にある法人間で「寄附」の認識のないまま行われた取引について、後の税務調査により寄附金課税が行われた場合であっても、寄附を受けた法人において計上される受贈益は益金不算入とできるのでしょうか?
A はい、できます。 課税当局より、当該受贈益は「当然に職権での減額更正が行われる」ものであって、「納税者側からの更正請求は不要」である旨の見解が示されています。ただし、寄附を行った法人への税務調査がきっかけで寄附金課税が行われた場合、寄附を受けた法人に対して職権更正が行われるのは、寄附を行った法人における処理が完了してからとなるため、実際に職権更正が行われるまでには多少の時間を要することも想定されます。もしあまり時間がかかるようであれば、確認の意味でも、調査官に対して職権更正を求めてみてもよいでしょう(本誌388号7頁参照)。
Q4 債権放棄と新寄附金税制の関係
100%子会社の経営悪化に伴い、当該子会社を解散するとともに、当該子会社に対する貸付金を放棄しようと考えています。この場合、貸付金の放棄に伴い子会社において発生する債務免除益は、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度により益金不算入となるのでしょうか?
A 当該貸付金の放棄が「寄附」に該当しなければ、債務免除益は益金不算入とはなりません。 完全支配関係にある子会社の経営が悪化したため、子会社を解散させるとともに、子会社に対する貸付金を放棄するといったケースは少なくありませんが、ここで1つの論点となるのが寄附金課税の問題です。こうしたケースの場合、貸付金を放棄しなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らかであれば、当該貸付金の放棄は法人税法上「寄附」とはなりません(法基通9-4-1)。この点、グループ法人税制の導入に伴い寄附金税制は見直されましたが、寄附金の概念そのものには何の変更もありません。
法人税基本通達9-4-1によって当該債権放棄が寄附とならなかった場合、親会社および子会社は下記のような処理をすることになりますが、ここで注意したいのは、子会社においては「債務免除益」が立ち、これは課税対象となる(益金不算入とはならない)ということです。
逆にいうと、「債権放棄をしなければ親会社が今後より大きな損失を被ることが社会通念上明らか」でない場合には、当該債権放棄は寄附に該当するとともに子会社には受贈益が立ち、この受贈益は、100%グループ内の法人間における寄附金の損金・益金不算入制度により益金不算入となります。
親会社にとって「経済合理性がある債権放棄(すなわち寄附金課税の対象とならない債権放棄)」が子会社において債務免除益を発生させ課税対象となる一方、「経済合理性のない債権放棄」は寄附となり、新しい寄附金税制によって子会社への受贈益が益金不算入となる点、不合理に感じるかも知れませんが、実際にこのような取扱いとなっていますので注意が必要です。
もっとも、解散する会社は多額の欠損金を有しているのが通常ですので、当該債務免除益に対して課税が行われるケースは少ないと思われます。
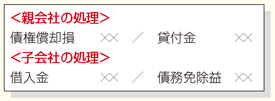
Q5 親会社株式の現物分配とみなし配当規定の関係
親会社株式を剰余金として親会社に配当した場合、親会社にとっては「自己株式」の取得となり、みなし配当に係る規定が適用されますか?
A いいえ、みなし配当に係る規定が適用されることはありません。 会社法上、子会社による親会社株式の取得は原則禁止ですが、たとえば子会社と合併した被合併法人が親会社の株式を保有していた場合、子会社は親会社株式を保有することになります。こうした場合、子会社は相当の時期に親会社株式を処分しなければなりませんが、処分の方法として、当該親会社株式を剰余金として親会社に「現物分配」するやり方があります。そして、当該現物分配が税制適格であれば、現物分配法人(子会社)は譲渡損益を認識する必要がないうえ、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰延措置も適用されず、配当に係る源泉徴収も不要です。
ただ、子会社から親会社に対する親会社株式の現物分配は、親会社の立場からすれば「自己株式の取得」にもみえるため、みなし配当に係る法人税法24条も適用されるのではないかとの指摘があります。
しかし、自己株式を取得した場合にはその対価を支払うのが通常であるにもかかわらず、剰余金の配当として自己株式を取得した場合には、一方的に配当(この場合は自己株式)を受け取るだけであって、対価を支払うことはありません。このように対価自体が存在しないため、みなし配当の計算もしようがなく、したがって、法人税法24条の規定も適用されません。
Q6 親族が保有する会社の合併における対価
親族で保有する兄弟会社を合併させたいと考えています。当該合併を無対価で行った場合でも、税制適格合併となりますか?
A いいえ、税制非適格となります。税制適格とするためには、合併対価を交付する必要があります。 税制適格となる無対価合併は、100%子会社との合併をはじめ4つの類型があり(法令4の3②二イ~ニ)、その1つが兄弟会社の合併です。ここでいう兄弟会社とは、正確には「一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係」とされています(法令4の3②二ロ)。
「一の者」というと、グループ法人税制の完全支配関係の定義を思い浮かべる人も多いと思います。すなわち、「その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人(6親等内の血族、3親等内の姻族等。法令4①)」です(法令4の2②カッコ書き)。
一方、税制適格となる無対価合併の類型における「一の者」(法令4の3②二ロ)とは、文字どおり「1人(社)」を指しています。これは、法令4条の3第2項2号ロにいう「一の者」には、法令4条の2第2項における「一の者」に付されているカッコ書きがないことからも明らかです。仮に法令4条の3第2項2号ロにいう「一の者」が、法令4条の2第2項における「一の者」と同様の意味(特殊関係にある個人を一の者とする)を持つのであれば、法令4条の2第2項のカッコ書き内に「次条において同じ」との文言が入らなければなりません。
したがって、株主が2人いる(一の者でない)図3のような合併を無対価で行った場合には、税制非適格となります。税制適格とするためには、兄弟に対し合併対価を交付する必要があります。
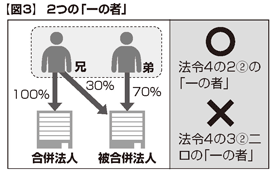
Column
「Q&A」の法的拘束力 近年、新たな制度の導入や影響の大きい改正が実施されるたび、国税庁から必ずといってよいほど出されるようになったのが「Q&A」だ。税制が複雑化するなか、納税者利便の向上を図ろうというのが課税当局側の狙いと思われるが、気になるのはその法的拘束力であり、これまでは法令や通達との関係における位置付けもあやふやだったといえる。
この点について、昨夏以降出されたQ&Aから1つの変化がみられる。昨夏以降に出された3つのQ&A(「外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例について」「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)」「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)」)をみると、いずれも法人課税課情報、審理室情報、調査課情報といった形で「情報」への“格上げ”が行われ、課税当局の職員に対し「処分執行の参考にされたい」とのメッセージとともに周知された後に、国税庁ホームページ上で公表されている。これは、Q&Aが基本通達と同様に「国税庁の正式見解、解釈指針」であり、課税当局の職員もこれに沿った執行を行うことを示しているといえる。
また、Q&Aを巡っては、「Q&Aは所詮個別事例に過ぎないので、これにぴったり当てはまらなければ使えないのではないか?」との指摘もあるが、たとえ自分の事例と完全に一致しなくても、Q&Aから課税当局の考え方を読み取り、それに沿った解釈をすることで、課税リスクを減少させることができよう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























