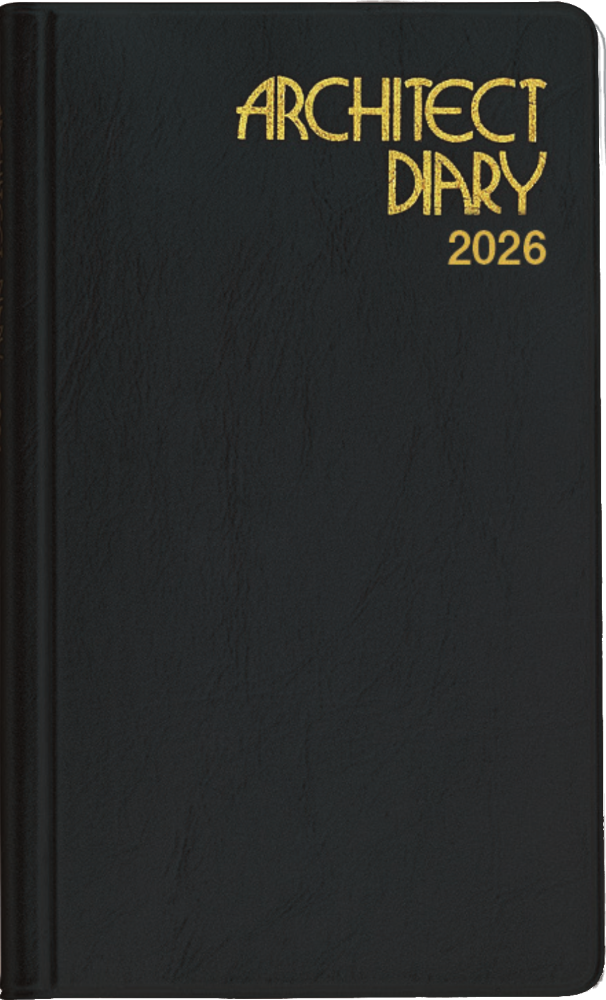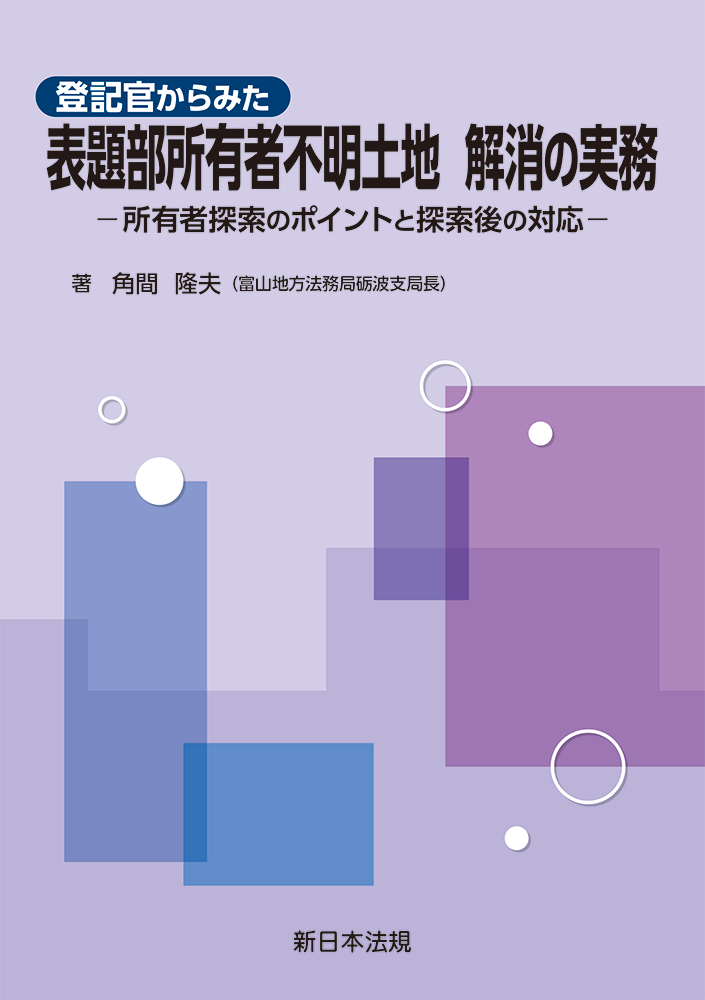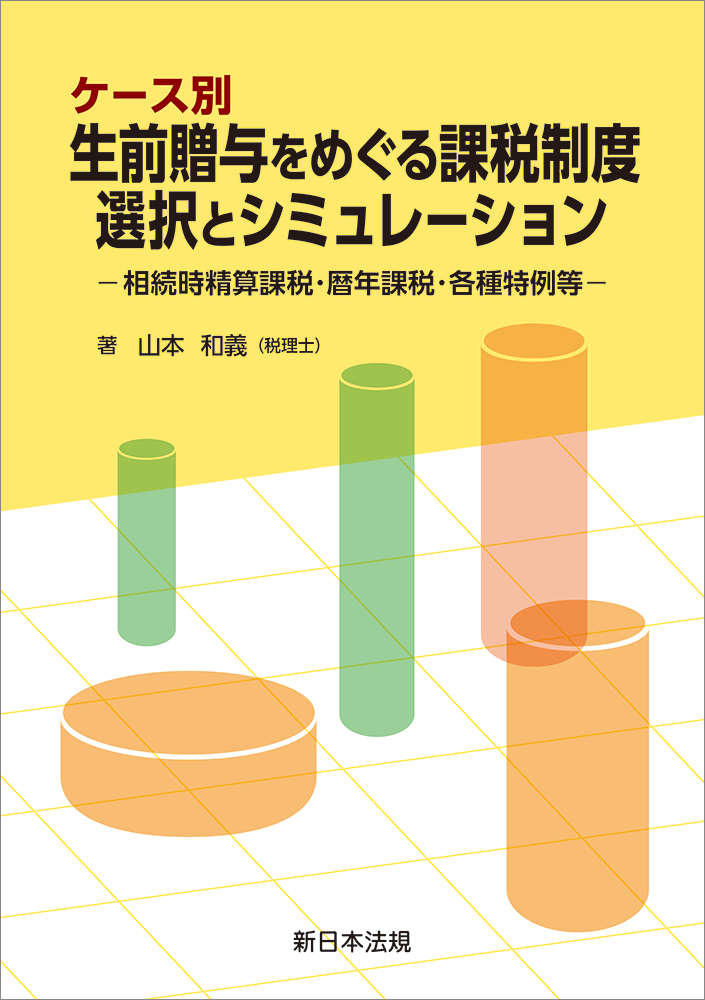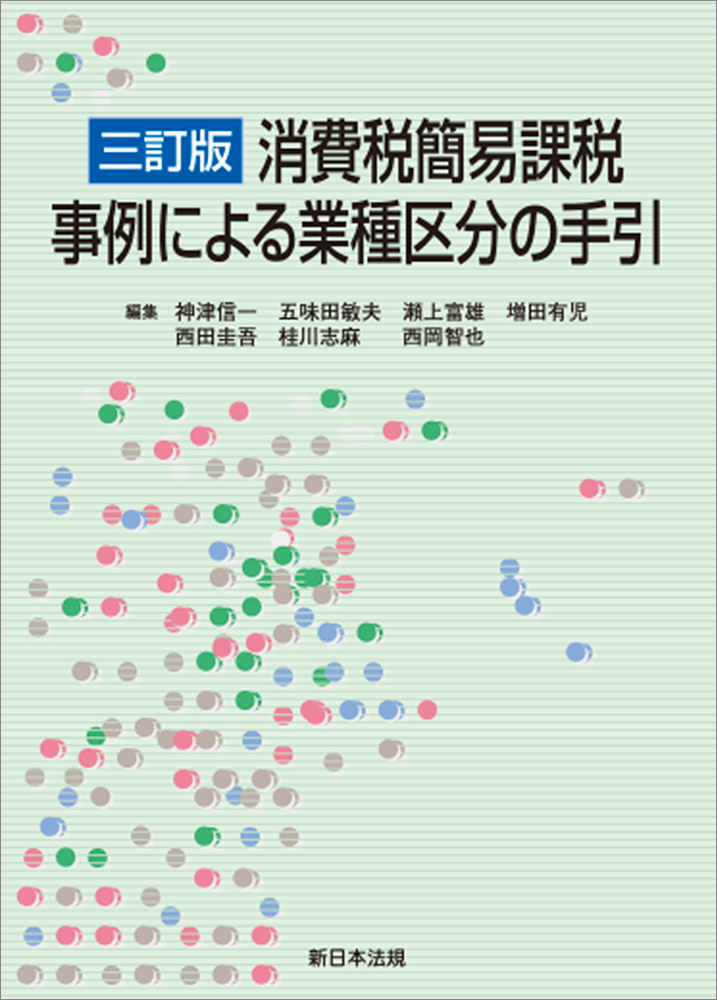解説記事2012年01月30日 【判決評釈】 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制──近時の裁判例の検討と課題──(2012年1月30日号・№436)
判決評釈
来料加工とタックス・ヘイブン対策税制──近時の裁判例の検討と課題──
西村あさひ法律事務所 弁護士・公認会計士 北村導人
Ⅰ はじめに
来料加工(脚注1)を利用した日本企業に対してタックス・ヘイブン対策税制が適用された事案に関して、その更正処分の取消しを求めた裁判が複数係属している(以下、当該裁判を「来料加工裁判」という)。
来料加工裁判における裁判所の判断は、日本電産ニッシン事件平成21年5月28日東京地裁判決(以下「東京地判平成21年5月28日」という)で初めて示されたところであるが、昨年、同事件に関する控訴審判決である平成23年8月30日東京高裁判決(以下「東京高判平成23年8月30日」という)および別の事件である船井電機事件平成23年6月24日大阪地裁判決(以下「大阪地判平成23年6月24日」という)が相次いで出された(なお、これら3件の裁判例はいずれも納税者の請求を棄却した(脚注2))。
来料加工裁判は来料加工という特殊性のある取引に係る更正処分の取消訴訟であるが、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件に係る解釈に関する重要な争点を含んでおり、裁判所が示した判断枠組みや解釈は今後他の事案における同税制の適用に関しても影響を及ぼし得る。
そこで、本稿では、日本電産ニッシン事件に係る裁判例(以下「本裁判例」という)について検討し、その課題を指摘する(脚注3・4)。
Ⅱ 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制に係る争点
日本企業A社の香港子会社B社は、中国の郷鎮企業C公司との間で長安工場における来料加工を内容とする1995年5月29日付「協議書」(以下「本件協議書」という)を作成した(以下を含め、図参照)。その後、B社は、2003年3月31日付で、中国企業D社との間で工場・宿舎等を賃借する本件借用契約書を、2004年7月8日付で、B社がD社から長安工場の経営を請け負うという本件経営契約書をそれぞれ締結した。
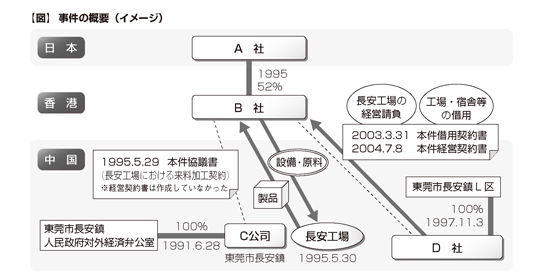
B社は、これらの契約書に基づき、長安工場に設備や原材料を無償で提供し、長安工場で加工組立を行った製品を全量引き取り、当該製品を第三者に売却する事業を行っていた。
課税当局は、A社に対して、①B社の主たる事業は「製造業」であること、②B社は当該「製造業」を「主として」本店所在地である香港で行っていないことを理由に、租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第3項(旧第4項)の適用除外要件(所在地国基準)を満たさず、B社の課税対象(留保)金額相当額をA社の益金の額に算入すべきであるとして、更正処分をした。これに対して、A社が更正処分の取消しを求めて不服申立ておよび訴訟を提起した。
本裁判例における争点は、表のとおりである(ただし、争点4は控訴審における争点である)。
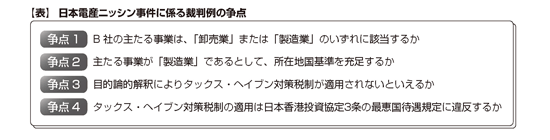
Ⅲ 争点1(「主たる事業」に係る業種認定)について
1 争点のポイント 来料加工裁判では、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである非関連者基準または所在地国基準のいずれが適用されるかが問題となっている。
措置法66条の6第3項(旧第4項)1号は、特定外国子会社が営む「主たる事業」が卸売業等の列挙された事業に該当する場合には非関連者基準が、それ以外の事業の場合には所在地国基準が適用されると定めている。
本事件では、「卸売業」とされる場合には非関連者基準を充足するが、「製造業」とされる場合には所在地国基準の充足性に争いが存するため、「主たる事業」がいずれの業種に該当するかが争点とされた。
2 裁判所の判断 裁判所は、「特定外国子会社等の『主たる事業』の判定……は、現実の当該事業の経済活動としての実質・実体がどのようなものであるかという観点から、事業実態の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって、当該事業の目的、内容、態様等の諸般の事情(関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容を含む。)を社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行われるべき」であるという判断を示した。
そのうえで、「一般的にみて、製造業が、自ら製品を製造した上で販売する事業であるのに対して、卸売業は、……自ら製品を製造するものではなく、他社が製造した製品(委託加工製品を含む。)を購入した上で販売する事業であると解される」として、卸売業と製造業は、「販売する製品の製造を自ら行っているか否か」により区別されるとし、その判断は、次の要素を、社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行われるべきとしている。
ア 製品製造のための、①生産設備の整備、②人員の配置、③原材料・補助材料等の調達等への当該特定外国子会社等の関与の状況等
イ (A)当該特定外国子会社等の設立の目的、(B)製品製造のための(a)人員の組織化、(b)事業計画の策定、(c)生産管理の策定・実施、(d)生産設備の投資計画の策定、(e)財務管理の実施、(f)人事・労務管理の実施等への当該特定外国子会社等の関与の状況等
ウ 関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容
本裁判例では、上記の考慮要素に沿って詳細に事実を認定し、社会通念上、B社は実質的に長安工場において製品の製造を自ら行っていたと認定した。なお、争点1ないし争点3に関する東京高判平成23年8月30日の判断は東京地判平成21年5月28日と同旨である。
3 争点1に関する判断に係る検討 まず、租税法上「卸売業」等の業種の定義がない(また、私法上の概念を借用する借用概念でもない)以上、各事業の意義について、本裁判例が採用した、社会通念上の意義を基礎として、規定の趣旨目的に照らして、解釈するというアプローチ自体は妥当と考えられる。もっとも、本裁判例は、「一般的にみて」として「卸売業」および「製造業」の意義を述べているに過ぎず、何故当該意義が社会通念に合致しているのか、その根拠を示しておらず、この点において論理の不明確さが残る。
次に、「卸売業」と「製造業」の各意義から区別基準として導かれた製造主体性の判断枠組みに関する判示については、課税は私法上の法律関係に則して行われるべきであり、これを軽視している等の批判がある。この点、たしかに、当事者の真意に基づく契約関係が成立している場合には、これを尊重して「主たる事業」を判定すべきであり、かかる私法上の法律関係を軽視して、徒に経済的実質・実体を強調した判断を行うべきではない。
しかしながら、本事案では、本件協議書にC公司はB社のために工場建物等を提供して加工生産を行う旨の定めがあるものの、他方で、本件経営請負契約書および本件借用契約書では、C社とは別の中国法人D社から長安工場を借り受け、またD社からB社が長安工場の経営を請け負うものとされており、これらの契約書からは、B社、C社およびD社の相互の法律関係は必ずしも明確ではなく、むしろB社が締結した各契約間に矛盾が生じているように思われる。さらに、本件協議書が規定するB社からC公司に対する加工費の支払いの事実はない等の認定がなされており、本件協議書等の規定と実際の運用に齟齬が存することが認められている。
かかる認定からすれば、本事案では、契約書の記載内容のみに依拠して業種を認定することはできず、実態を踏まえて判断するというアプローチを採らざるを得なかったと考えられよう。
もっとも、本裁判例では、結論として、B社の法人格の外に位置付けられる長安工場が営む事業を、B社の事業の一部と認定しているようであるが、かかる認定の理論的根拠(香港子会社の中国におけるPEと認定しているのか、実質主義を用いているのか、法人格否認の法理を用いているのか等)が必ずしも明確でないという点、また、裁判例が示した基準では、特定外国子会社等が他の事業体に対してどの程度関与すれば、製造行為の主体性が認められるのか一義的に明らかではなく、予測可能性および法的安定性の観点から問題があるという点でなお課題が残っているものと考えられる。
Ⅳ 争点2(所在地国基準の充足性)について
1 争点のポイント 所在地国基準は、主たる事業を主として本店の所在する国または地域において行っているか否かを判定する基準であるところ、①香港は、タックス・ヘイブン対策税制の適用上、中国とは異なる「地域」に該当するか、さらに、①で香港が中国とは異なる「地域」に該当するとしても、②香港子会社は、「主として」香港において主たる事業を行っているか否かが問題となる。
2 裁判所の判断 裁判所は、争点①について、香港は一国二制度が適用されており、独自の租税制度を有していることから、中国とは異なる「地域」に該当するとし、争点②について、B社は、その「人員及び資本の大半」を長安工場における製造業務に集中的に投下していることから、その主たる事業である製造業を主として行っているのは中国のうち香港以外の地域であり、所在地国基準を満たさないと判示した。
3 争点2に関する判断に係る検討 裁判所は、「人員及び資本の大半」を長安工場における製造業務に集中的に投下していることから、「主たる事業」である「製造業」を「主として」行っているのは中国のうち香港以外の地域であると認定している。
しかしながら、そもそも所在地国基準を判定する前提としての「主たる事業」の捉え方に関して問題がある。すなわち、措置法66条の6第3項2号は、1号列挙事業以外の事業について所在地国基準を適用すると定めていることからすれば、来料加工事業を「製造業」として整理する必要はなく、1号列挙事業には該当しない事業と整理すれば足りる。
つまり、「製造業」という枠組みにとらわれ、製造行為という事業の一部のみに着目するのではなく、「主たる事業」を「来料加工事業」と捉えて、営業活動、原材料等の調達、加工組立、製品の販売、その過程における生産管理、人事管理、財務管理、投資計画等の管理業務を含む一連の「来料加工事業に係る行為」が「主として」どこで行われているかというアプローチが採られるべきであると考えられる。
また、本裁判例は、「主として」の判定基準として「人員及び資本」を用いているが、本店所在地国の経済と密接に関連して事業活動を行っていれば、その地に所在することについて十分な経済合理性が推認し得るという所在地国基準の趣旨からすれば、必ずしも「人員及び資本」という要素のみでもって同基準充足性を判定すべきということは論理的に導かれない。
むしろ、上記趣旨からは、上記で述べた一連の「来料加工事業に係る行為」がいずれの地で行われたかを分析的に検討すべきであると考える。特に、争点1に関する裁判所の判断において、事業計画、生産管理、生産設備の投資計画、財務管理、人事・労務管理等の策定・実施等を考慮要素として製造行為の主体性を認定していることからすれば、これらの管理業務が香港と中国のいずれで行われているかという点は当然に重要な考慮要素とすべきである。
さらに、具体的な判定方法として、来料加工事業に係る香港における事業(管理事業も含む)と中国における事業について、定性的な面から分析するとともに、定量的な観点から、各事業の機能およびリスクに照らして、それぞれが生み出す付加価値等を定量化し、これを判定基準として用いることも合理的であると考えられる(脚注5)。
Ⅴ 争点3(目的論的解釈に係る主張)について
1 争点のポイント 措置法66条の6第1項および第3項の立法趣旨〔租税回避の防止および経済合理性ある事業活動の尊重〕に鑑みれば、特定外国子会社等がその地で経済合理性のある活動を行っている場合には、上記各規定の目的論的解釈により当該規定の適用の射程範囲外と解すべきであるとの納税者の主張が認められるかが問題となる。
2 裁判所の判断 裁判所は、納税者の主張は「要するに、措置法の条文にはない独自の適用除外要件を創設して同条3項の適用除外の範囲を拡大すべき旨を主張するものであって、……しかも、原告が主張する同条1項への付加要件……と考えられるから、……租税法規の解釈の在り方に照らし、措置法66条の6の解釈論として所論を採用することはできない」として、その主張を排斥した。
3 争点3に関する判断に係る検討 本裁判例における納税者の主張の排斥理由からすると、納税者の主張は裁判所に必ずしも正確に理解されていないのではないかと思われる。
すなわち、納税者の主張は、ある銀行の取引を、「外国税額控除の制度を濫用するものであり、これに基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることはできない」として、同制度の趣旨・目的に照らして規定の限定解釈を行ったと理解される、外国税額控除余裕枠事件最高裁判決(最判平成17年12月19日判時1918号3頁、最判平成18年2月23日判時1926号57頁)等の判例や、一定の政策目的を実現させるための規定に形式的には該当する行為や取引であっても、その本来の政策目的の実現とは無縁であるという場合には、「その規定がもともと予定している行為や取引には当たらないと考えて、その規定の縮小解釈ないし限定解釈によって、その適用を否定することができる」とする金子宏教授の見解(脚注6)および「政策目的の課税減免規定のみならず、課税規定であるタックス・ヘイブン対策税制も理論的には、目的的解釈(制度の趣旨・目的からの限定解釈)は可能であるはず」とする中里実教授の見解(脚注7)などの有力な学説と同様の論理に基づき、政策税制に係る規定の解釈にあたり当該税制の趣旨・目的を勘案してその規定の射程範囲を限定すると主張しているところであり、上記排斥理由のように適用除外の範囲拡大や要件の「付加」を主張するものではない。
したがって、上記裁判所の判断は納税者の主張を正解していないと考えられ、今後の裁判においては上記論理をいかに裁判官に対して説得的かつ分かりやすく主張(説明)することができるかが本争点の成否の鍵を握ると考えられる。
Ⅵ 争点4(日本香港投資協定違反の有無)について
1 争点のポイント 日本香港投資協定3条は、「いずれの一方の締約政府の投資家も、他方の締約政府の地域内において、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、当該他方の締約政府又は両締約政府以外の政府の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。」として、いわゆる最恵国待遇を規定している。
納税者は、①タックス・ヘイブン対策税制を含め、締約国と第三国の間の租税条約に規定されていない租税事項は、同協定の適用対象となる、②同協定3条は「投資に関連する事業活動」がどこで行われるかについて地理的な制限を加えていないから、香港子会社が中国で行う第三国向け投資についても同協定の適用がある、③タックス・ヘイブン対策税制の適用を避けるために香港子会社が親会社に対して配当を行うとすれば、事業資金の減少を来すのであり、香港子会社に対して、同協定3条にいう「不利な待遇」を与えるものであるから、同税制は同協定に違反し、本件更正処分は違法であると主張する。
2 裁判所(控訴審)の判断 まず、裁判所は、タックス・ヘイブン対策税制を設けることは国家主権の中核に属する課税権の内容に含まれ、租税条約その他国際約束等によってこのような税制を設けるわが国の権能が制約されるのは,当該国際約束におけるその旨の明文規定その他の十分な解釈上の根拠が存する場合でなければならない(グラクソ事件最二小判平成21年10月29日の判示を引用)とした。
そのうえで、同税制はわが国内国法人に対する課税権の行使であり、日本香港投資協定3条は、同税制の適用を排除する規定とは解されないこと、同協定前文および2条から、同協定が日本・香港双方の「地域内」での投資促進を目指したものと看取できること、同協定3条は、香港子会社が中国(第三国)で行う第三国向け投資について何ら規定していないこと等から、十分な解釈上の根拠はないとしている。
3 争点4に関する判断に係る検討 一般に、投資協定には租税事項は除外されているところ、日本香港投資協定はあえてこれを除外していないという点が議論の出発点となっている。
この点は、あえて租税事項が除外されなかった背景等を探ることは重要であるものの、裁判例が示すとおり、日本香港投資協定3条違反の納税者の主張が論理的に成り立つか、なお検討の必要があろう。
Ⅶ おわりに
来料加工については、近時、中国政府が、製品加工のハイエンド化等の方向に政策転換し、種々の優遇税制を廃止しているところであるが、現状においても、わが国の多数の企業が利用しているため、来料加工裁判における裁判所の判断が実務に与える影響はなお大きい。
これまでの裁判例ではいずれも納税者の請求が棄却されているが、その判断には本稿で指摘した本裁判例の判断に係る問題点と同様の問題点が存する。特に、これまでの裁判における当事者の主張の大半は業種認定の争点に充てられ、所在地国基準における「主として」の判定基準については十分な主張がなされてこなかったように思われる。
今後の来料加工裁判においては、後者の「主として」の判断基準に関して新たな判断が示され、来料加工を利用する企業が救済されることを期待するところである。
北村導人 きたむら みちと
1994年慶應義塾大学卒業、1992年会計士補登録、1996年公認会計士登録、2000年弁護士登録、2007年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in International Tax)。現在、西村あさひ法律事務所パートナーとして、多数の税務争訟、税法解釈に関する助言、税務調査対応等に従事している。その他、租税訴訟学会理事、一橋大学国際・公共政策大学院(国際租税政策)講師、経済産業省外国事業体課税研究会委員等。
脚注
1 来料加工は、1978年以来の中国における改革開放政策のもとで発展してきた三来一補といわれる加工貿易形態の1つであり、特に、中国華南地方の珠江デルタ(深圳、東莞等)と香港とで構成される「華南経済圏」を拠点として1990年代に発展したものである。来料加工とは、①香港企業などの外国企業が中国国内の工場に対して原材料、部材、補助材料などのほか生産に必要な機械設備を無償で提供し、②中国側は委託者である香港企業の要求に基づき製品を製造し、③香港企業がその製品の全量を引き取る形態の取引であり、外国企業が、中国への直接投資による中国法規制等を含むローカルリスクを回避しながら、中国の大量かつ安価な労働力を利用し、他方で、香港における、英語力のある人材、多通貨決済、邦銀からの資金調達可能性、物流の優位性(在庫期間の短縮)等のインフラの優位性を利用することができる、1つのビジネスモデルである。来料加工に関しては、中国において、税関に取引形態を登録することで、来料加工工場に輸入する原材料、加工設備等に係る関税や増値税および製品の輸出時の関税が免除される(ただし、近時の改正あり)ほか、香港においても、来料加工に係る利益の50%は国外源泉所得として非課税とされるなどの税制上のメリットも有している。来料加工裁判を提起した部品メーカー等の納税者の大半は、大手メーカーのアジア進出等に伴い自らもコスト・ダウンを図らざるを得ないというbusiness orientedな背景のもとで当該事業形態を選択している。納税者の不服はこのような事業上の背景があるにも拘わらず、租税回避防止を趣旨とするタックス・ヘイブン対策税制が適用されたという点、すなわち同税制の趣旨と実際に同税制が適用される範囲との間に齟齬が生じているという点にあるといえよう。
2 日本電産ニッシン事件では上告受理申立てが行われており、船井電機事件は控訴審係属中である。
3 本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的意見であり、筆者の属する事務所の見解ではない。
4 紙幅の関係上、大阪地判平成23年6月24日の検討は他日を期すこととしたい。
5 その他、来料加工工場を香港子会社のPEと考え、OECDのAOA(Authorized OECD Approach)における所得の帰属判定基準を参考とし、重要な人的資源(significant people function)が香港または中国のいずれに帰属するかという点に着目して、「主として」を判断する方法も考え得る。
6 金子宏『租税法第16版』(弘文堂、2011年)121頁。
7 中里実「金融取引をめぐる最近の課税問題(45)政策税制の政策目的に沿った限定解釈」税研129号(2006年9月)75頁。
来料加工とタックス・ヘイブン対策税制──近時の裁判例の検討と課題──
西村あさひ法律事務所 弁護士・公認会計士 北村導人
Ⅰ はじめに
来料加工(脚注1)を利用した日本企業に対してタックス・ヘイブン対策税制が適用された事案に関して、その更正処分の取消しを求めた裁判が複数係属している(以下、当該裁判を「来料加工裁判」という)。
来料加工裁判における裁判所の判断は、日本電産ニッシン事件平成21年5月28日東京地裁判決(以下「東京地判平成21年5月28日」という)で初めて示されたところであるが、昨年、同事件に関する控訴審判決である平成23年8月30日東京高裁判決(以下「東京高判平成23年8月30日」という)および別の事件である船井電機事件平成23年6月24日大阪地裁判決(以下「大阪地判平成23年6月24日」という)が相次いで出された(なお、これら3件の裁判例はいずれも納税者の請求を棄却した(脚注2))。
来料加工裁判は来料加工という特殊性のある取引に係る更正処分の取消訴訟であるが、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件に係る解釈に関する重要な争点を含んでおり、裁判所が示した判断枠組みや解釈は今後他の事案における同税制の適用に関しても影響を及ぼし得る。
そこで、本稿では、日本電産ニッシン事件に係る裁判例(以下「本裁判例」という)について検討し、その課題を指摘する(脚注3・4)。
Ⅱ 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制に係る争点
日本企業A社の香港子会社B社は、中国の郷鎮企業C公司との間で長安工場における来料加工を内容とする1995年5月29日付「協議書」(以下「本件協議書」という)を作成した(以下を含め、図参照)。その後、B社は、2003年3月31日付で、中国企業D社との間で工場・宿舎等を賃借する本件借用契約書を、2004年7月8日付で、B社がD社から長安工場の経営を請け負うという本件経営契約書をそれぞれ締結した。
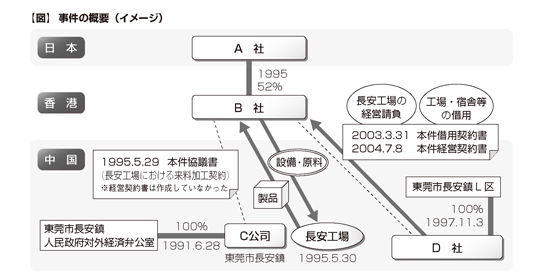
B社は、これらの契約書に基づき、長安工場に設備や原材料を無償で提供し、長安工場で加工組立を行った製品を全量引き取り、当該製品を第三者に売却する事業を行っていた。
課税当局は、A社に対して、①B社の主たる事業は「製造業」であること、②B社は当該「製造業」を「主として」本店所在地である香港で行っていないことを理由に、租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第3項(旧第4項)の適用除外要件(所在地国基準)を満たさず、B社の課税対象(留保)金額相当額をA社の益金の額に算入すべきであるとして、更正処分をした。これに対して、A社が更正処分の取消しを求めて不服申立ておよび訴訟を提起した。
本裁判例における争点は、表のとおりである(ただし、争点4は控訴審における争点である)。
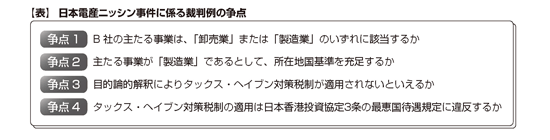
Ⅲ 争点1(「主たる事業」に係る業種認定)について
1 争点のポイント 来料加工裁判では、タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準の1つである非関連者基準または所在地国基準のいずれが適用されるかが問題となっている。
措置法66条の6第3項(旧第4項)1号は、特定外国子会社が営む「主たる事業」が卸売業等の列挙された事業に該当する場合には非関連者基準が、それ以外の事業の場合には所在地国基準が適用されると定めている。
本事件では、「卸売業」とされる場合には非関連者基準を充足するが、「製造業」とされる場合には所在地国基準の充足性に争いが存するため、「主たる事業」がいずれの業種に該当するかが争点とされた。
2 裁判所の判断 裁判所は、「特定外国子会社等の『主たる事業』の判定……は、現実の当該事業の経済活動としての実質・実体がどのようなものであるかという観点から、事業実態の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって、当該事業の目的、内容、態様等の諸般の事情(関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容を含む。)を社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行われるべき」であるという判断を示した。
そのうえで、「一般的にみて、製造業が、自ら製品を製造した上で販売する事業であるのに対して、卸売業は、……自ら製品を製造するものではなく、他社が製造した製品(委託加工製品を含む。)を購入した上で販売する事業であると解される」として、卸売業と製造業は、「販売する製品の製造を自ら行っているか否か」により区別されるとし、その判断は、次の要素を、社会通念に照らして総合的に考慮して個別具体的に行われるべきとしている。
ア 製品製造のための、①生産設備の整備、②人員の配置、③原材料・補助材料等の調達等への当該特定外国子会社等の関与の状況等
イ (A)当該特定外国子会社等の設立の目的、(B)製品製造のための(a)人員の組織化、(b)事業計画の策定、(c)生産管理の策定・実施、(d)生産設備の投資計画の策定、(e)財務管理の実施、(f)人事・労務管理の実施等への当該特定外国子会社等の関与の状況等
ウ 関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容
本裁判例では、上記の考慮要素に沿って詳細に事実を認定し、社会通念上、B社は実質的に長安工場において製品の製造を自ら行っていたと認定した。なお、争点1ないし争点3に関する東京高判平成23年8月30日の判断は東京地判平成21年5月28日と同旨である。
3 争点1に関する判断に係る検討 まず、租税法上「卸売業」等の業種の定義がない(また、私法上の概念を借用する借用概念でもない)以上、各事業の意義について、本裁判例が採用した、社会通念上の意義を基礎として、規定の趣旨目的に照らして、解釈するというアプローチ自体は妥当と考えられる。もっとも、本裁判例は、「一般的にみて」として「卸売業」および「製造業」の意義を述べているに過ぎず、何故当該意義が社会通念に合致しているのか、その根拠を示しておらず、この点において論理の不明確さが残る。
次に、「卸売業」と「製造業」の各意義から区別基準として導かれた製造主体性の判断枠組みに関する判示については、課税は私法上の法律関係に則して行われるべきであり、これを軽視している等の批判がある。この点、たしかに、当事者の真意に基づく契約関係が成立している場合には、これを尊重して「主たる事業」を判定すべきであり、かかる私法上の法律関係を軽視して、徒に経済的実質・実体を強調した判断を行うべきではない。
しかしながら、本事案では、本件協議書にC公司はB社のために工場建物等を提供して加工生産を行う旨の定めがあるものの、他方で、本件経営請負契約書および本件借用契約書では、C社とは別の中国法人D社から長安工場を借り受け、またD社からB社が長安工場の経営を請け負うものとされており、これらの契約書からは、B社、C社およびD社の相互の法律関係は必ずしも明確ではなく、むしろB社が締結した各契約間に矛盾が生じているように思われる。さらに、本件協議書が規定するB社からC公司に対する加工費の支払いの事実はない等の認定がなされており、本件協議書等の規定と実際の運用に齟齬が存することが認められている。
かかる認定からすれば、本事案では、契約書の記載内容のみに依拠して業種を認定することはできず、実態を踏まえて判断するというアプローチを採らざるを得なかったと考えられよう。
もっとも、本裁判例では、結論として、B社の法人格の外に位置付けられる長安工場が営む事業を、B社の事業の一部と認定しているようであるが、かかる認定の理論的根拠(香港子会社の中国におけるPEと認定しているのか、実質主義を用いているのか、法人格否認の法理を用いているのか等)が必ずしも明確でないという点、また、裁判例が示した基準では、特定外国子会社等が他の事業体に対してどの程度関与すれば、製造行為の主体性が認められるのか一義的に明らかではなく、予測可能性および法的安定性の観点から問題があるという点でなお課題が残っているものと考えられる。
Ⅳ 争点2(所在地国基準の充足性)について
1 争点のポイント 所在地国基準は、主たる事業を主として本店の所在する国または地域において行っているか否かを判定する基準であるところ、①香港は、タックス・ヘイブン対策税制の適用上、中国とは異なる「地域」に該当するか、さらに、①で香港が中国とは異なる「地域」に該当するとしても、②香港子会社は、「主として」香港において主たる事業を行っているか否かが問題となる。
2 裁判所の判断 裁判所は、争点①について、香港は一国二制度が適用されており、独自の租税制度を有していることから、中国とは異なる「地域」に該当するとし、争点②について、B社は、その「人員及び資本の大半」を長安工場における製造業務に集中的に投下していることから、その主たる事業である製造業を主として行っているのは中国のうち香港以外の地域であり、所在地国基準を満たさないと判示した。
3 争点2に関する判断に係る検討 裁判所は、「人員及び資本の大半」を長安工場における製造業務に集中的に投下していることから、「主たる事業」である「製造業」を「主として」行っているのは中国のうち香港以外の地域であると認定している。
しかしながら、そもそも所在地国基準を判定する前提としての「主たる事業」の捉え方に関して問題がある。すなわち、措置法66条の6第3項2号は、1号列挙事業以外の事業について所在地国基準を適用すると定めていることからすれば、来料加工事業を「製造業」として整理する必要はなく、1号列挙事業には該当しない事業と整理すれば足りる。
つまり、「製造業」という枠組みにとらわれ、製造行為という事業の一部のみに着目するのではなく、「主たる事業」を「来料加工事業」と捉えて、営業活動、原材料等の調達、加工組立、製品の販売、その過程における生産管理、人事管理、財務管理、投資計画等の管理業務を含む一連の「来料加工事業に係る行為」が「主として」どこで行われているかというアプローチが採られるべきであると考えられる。
また、本裁判例は、「主として」の判定基準として「人員及び資本」を用いているが、本店所在地国の経済と密接に関連して事業活動を行っていれば、その地に所在することについて十分な経済合理性が推認し得るという所在地国基準の趣旨からすれば、必ずしも「人員及び資本」という要素のみでもって同基準充足性を判定すべきということは論理的に導かれない。
むしろ、上記趣旨からは、上記で述べた一連の「来料加工事業に係る行為」がいずれの地で行われたかを分析的に検討すべきであると考える。特に、争点1に関する裁判所の判断において、事業計画、生産管理、生産設備の投資計画、財務管理、人事・労務管理等の策定・実施等を考慮要素として製造行為の主体性を認定していることからすれば、これらの管理業務が香港と中国のいずれで行われているかという点は当然に重要な考慮要素とすべきである。
さらに、具体的な判定方法として、来料加工事業に係る香港における事業(管理事業も含む)と中国における事業について、定性的な面から分析するとともに、定量的な観点から、各事業の機能およびリスクに照らして、それぞれが生み出す付加価値等を定量化し、これを判定基準として用いることも合理的であると考えられる(脚注5)。
Ⅴ 争点3(目的論的解釈に係る主張)について
1 争点のポイント 措置法66条の6第1項および第3項の立法趣旨〔租税回避の防止および経済合理性ある事業活動の尊重〕に鑑みれば、特定外国子会社等がその地で経済合理性のある活動を行っている場合には、上記各規定の目的論的解釈により当該規定の適用の射程範囲外と解すべきであるとの納税者の主張が認められるかが問題となる。
2 裁判所の判断 裁判所は、納税者の主張は「要するに、措置法の条文にはない独自の適用除外要件を創設して同条3項の適用除外の範囲を拡大すべき旨を主張するものであって、……しかも、原告が主張する同条1項への付加要件……と考えられるから、……租税法規の解釈の在り方に照らし、措置法66条の6の解釈論として所論を採用することはできない」として、その主張を排斥した。
3 争点3に関する判断に係る検討 本裁判例における納税者の主張の排斥理由からすると、納税者の主張は裁判所に必ずしも正確に理解されていないのではないかと思われる。
すなわち、納税者の主張は、ある銀行の取引を、「外国税額控除の制度を濫用するものであり、これに基づいて生じた所得に対する外国法人税を法人税法69条の定める外国税額控除の対象とすることはできない」として、同制度の趣旨・目的に照らして規定の限定解釈を行ったと理解される、外国税額控除余裕枠事件最高裁判決(最判平成17年12月19日判時1918号3頁、最判平成18年2月23日判時1926号57頁)等の判例や、一定の政策目的を実現させるための規定に形式的には該当する行為や取引であっても、その本来の政策目的の実現とは無縁であるという場合には、「その規定がもともと予定している行為や取引には当たらないと考えて、その規定の縮小解釈ないし限定解釈によって、その適用を否定することができる」とする金子宏教授の見解(脚注6)および「政策目的の課税減免規定のみならず、課税規定であるタックス・ヘイブン対策税制も理論的には、目的的解釈(制度の趣旨・目的からの限定解釈)は可能であるはず」とする中里実教授の見解(脚注7)などの有力な学説と同様の論理に基づき、政策税制に係る規定の解釈にあたり当該税制の趣旨・目的を勘案してその規定の射程範囲を限定すると主張しているところであり、上記排斥理由のように適用除外の範囲拡大や要件の「付加」を主張するものではない。
したがって、上記裁判所の判断は納税者の主張を正解していないと考えられ、今後の裁判においては上記論理をいかに裁判官に対して説得的かつ分かりやすく主張(説明)することができるかが本争点の成否の鍵を握ると考えられる。
Ⅵ 争点4(日本香港投資協定違反の有無)について
1 争点のポイント 日本香港投資協定3条は、「いずれの一方の締約政府の投資家も、他方の締約政府の地域内において、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、当該他方の締約政府又は両締約政府以外の政府の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。」として、いわゆる最恵国待遇を規定している。
納税者は、①タックス・ヘイブン対策税制を含め、締約国と第三国の間の租税条約に規定されていない租税事項は、同協定の適用対象となる、②同協定3条は「投資に関連する事業活動」がどこで行われるかについて地理的な制限を加えていないから、香港子会社が中国で行う第三国向け投資についても同協定の適用がある、③タックス・ヘイブン対策税制の適用を避けるために香港子会社が親会社に対して配当を行うとすれば、事業資金の減少を来すのであり、香港子会社に対して、同協定3条にいう「不利な待遇」を与えるものであるから、同税制は同協定に違反し、本件更正処分は違法であると主張する。
2 裁判所(控訴審)の判断 まず、裁判所は、タックス・ヘイブン対策税制を設けることは国家主権の中核に属する課税権の内容に含まれ、租税条約その他国際約束等によってこのような税制を設けるわが国の権能が制約されるのは,当該国際約束におけるその旨の明文規定その他の十分な解釈上の根拠が存する場合でなければならない(グラクソ事件最二小判平成21年10月29日の判示を引用)とした。
そのうえで、同税制はわが国内国法人に対する課税権の行使であり、日本香港投資協定3条は、同税制の適用を排除する規定とは解されないこと、同協定前文および2条から、同協定が日本・香港双方の「地域内」での投資促進を目指したものと看取できること、同協定3条は、香港子会社が中国(第三国)で行う第三国向け投資について何ら規定していないこと等から、十分な解釈上の根拠はないとしている。
3 争点4に関する判断に係る検討 一般に、投資協定には租税事項は除外されているところ、日本香港投資協定はあえてこれを除外していないという点が議論の出発点となっている。
この点は、あえて租税事項が除外されなかった背景等を探ることは重要であるものの、裁判例が示すとおり、日本香港投資協定3条違反の納税者の主張が論理的に成り立つか、なお検討の必要があろう。
Ⅶ おわりに
来料加工については、近時、中国政府が、製品加工のハイエンド化等の方向に政策転換し、種々の優遇税制を廃止しているところであるが、現状においても、わが国の多数の企業が利用しているため、来料加工裁判における裁判所の判断が実務に与える影響はなお大きい。
これまでの裁判例ではいずれも納税者の請求が棄却されているが、その判断には本稿で指摘した本裁判例の判断に係る問題点と同様の問題点が存する。特に、これまでの裁判における当事者の主張の大半は業種認定の争点に充てられ、所在地国基準における「主として」の判定基準については十分な主張がなされてこなかったように思われる。
今後の来料加工裁判においては、後者の「主として」の判断基準に関して新たな判断が示され、来料加工を利用する企業が救済されることを期待するところである。
北村導人 きたむら みちと
1994年慶應義塾大学卒業、1992年会計士補登録、1996年公認会計士登録、2000年弁護士登録、2007年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in International Tax)。現在、西村あさひ法律事務所パートナーとして、多数の税務争訟、税法解釈に関する助言、税務調査対応等に従事している。その他、租税訴訟学会理事、一橋大学国際・公共政策大学院(国際租税政策)講師、経済産業省外国事業体課税研究会委員等。
脚注
1 来料加工は、1978年以来の中国における改革開放政策のもとで発展してきた三来一補といわれる加工貿易形態の1つであり、特に、中国華南地方の珠江デルタ(深圳、東莞等)と香港とで構成される「華南経済圏」を拠点として1990年代に発展したものである。来料加工とは、①香港企業などの外国企業が中国国内の工場に対して原材料、部材、補助材料などのほか生産に必要な機械設備を無償で提供し、②中国側は委託者である香港企業の要求に基づき製品を製造し、③香港企業がその製品の全量を引き取る形態の取引であり、外国企業が、中国への直接投資による中国法規制等を含むローカルリスクを回避しながら、中国の大量かつ安価な労働力を利用し、他方で、香港における、英語力のある人材、多通貨決済、邦銀からの資金調達可能性、物流の優位性(在庫期間の短縮)等のインフラの優位性を利用することができる、1つのビジネスモデルである。来料加工に関しては、中国において、税関に取引形態を登録することで、来料加工工場に輸入する原材料、加工設備等に係る関税や増値税および製品の輸出時の関税が免除される(ただし、近時の改正あり)ほか、香港においても、来料加工に係る利益の50%は国外源泉所得として非課税とされるなどの税制上のメリットも有している。来料加工裁判を提起した部品メーカー等の納税者の大半は、大手メーカーのアジア進出等に伴い自らもコスト・ダウンを図らざるを得ないというbusiness orientedな背景のもとで当該事業形態を選択している。納税者の不服はこのような事業上の背景があるにも拘わらず、租税回避防止を趣旨とするタックス・ヘイブン対策税制が適用されたという点、すなわち同税制の趣旨と実際に同税制が適用される範囲との間に齟齬が生じているという点にあるといえよう。
2 日本電産ニッシン事件では上告受理申立てが行われており、船井電機事件は控訴審係属中である。
3 本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的意見であり、筆者の属する事務所の見解ではない。
4 紙幅の関係上、大阪地判平成23年6月24日の検討は他日を期すこととしたい。
5 その他、来料加工工場を香港子会社のPEと考え、OECDのAOA(Authorized OECD Approach)における所得の帰属判定基準を参考とし、重要な人的資源(significant people function)が香港または中国のいずれに帰属するかという点に着目して、「主として」を判断する方法も考え得る。
6 金子宏『租税法第16版』(弘文堂、2011年)121頁。
7 中里実「金融取引をめぐる最近の課税問題(45)政策税制の政策目的に沿った限定解釈」税研129号(2006年9月)75頁。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -