解説記事2012年04月23日 【判決評釈】 デラウェア州LPSの法人等該当性に関する裁判例の検討(2012年4月23日号・№448)
判決評釈
デラウェア州LPSの法人等該当性に関する裁判例の検討
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 手塚崇史
Ⅰ はじめに
平成23年12月14日、名古屋地方裁判所は、米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)を、我が国の租税法に規定する法人及び人格のない社団のいずれにも該当しないとする判決(以下「名古屋地判」という。)を下した(脚注1)。
本判決は、東京地裁平成23年7月29日判決(脚注2)(以下「東京地判」という。)、大阪地裁平成22年12月17日判決(脚注3)(以下「大阪地判」という。)に続いて、ほぼ同様の事案において、LPSの法人該当性ないし人格のない社団該当性について判断したものである。東京地判は、LPSの法人ないし人格のない社団該当性をいずれも否定したが、大阪地判は法人に該当すると判断した。
本稿では、これら一連の裁判例のうち、適宜、必要に応じて東京地判や大阪地判にも言及しつつ、最新の裁判例である名古屋地判について検討することとする。
なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する法律事務所の見解ではないことを念のため申し添える。
Ⅱ 事案の概要
事案の概要は、名古屋地判、東京地判及び大阪地判ともいずれもほぼ同様である。すなわち、原告ら投資家が、外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPSが行った米国所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得(損失)が、所得税法26条1項所定の不動産所得(損失)に該当するものとして、その減価償却等による損失と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をしたところ、税務当局から、当該所得は不動産所得に該当しないことから損益通算はできないとして、所得税の更正処分ないし更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分等を受け、これらを不服として原告ら投資家がこれら各処分の取消しを求めたものである。より詳細には、以下のとおりである。
(1)いずれも我が国の居住者たる個人である原告らは、米国所在の中古集合住宅である建物(以下「本件建物」という。)を対象とした、投資金額を1口2000万円とする不動産賃貸事業(以下「本件各不動産賃貸事業」という。)に投資するため、A銀行との間で、自己を委託者兼受益者、A銀行を受託者とする信託契約(以下「本件各信託契約」という。)を締結し、同契約に基づいて、A銀行に開設された口座に現金を拠出した。
(2)A銀行は、米国デラウェア州の複数のリミテッド・ライアビリティ・カンパニーとの間で、それらのリミテッド・ライアビリティ・カンパニーをジェネラル・パートナー(以下「本件各GP」という。)、A銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ契約(脚注4)を締結し(以下、A銀行と本件各GPが締結したリミテッド・パートナーシップ契約を「本件各LPS契約」、本件各LPS契約により組成されたLPSを「本件各LPS」という。)、本件各LPS契約に基づき、原告らが拠出した現金を本件各LPSに出資した。
(3)本件各LPSは、第三者から本件建物を購入し、本件建物の敷地を賃借して、本件建物を別の第三者に対して賃貸した。
(4)原告らは、本件各不動産賃貸事業による損益が不動産所得に該当することを前提に、本件各不動産賃貸事業によって生じた各損失(以下「本件各損失」という。本件各損失の内容は、本件建物の減価償却費等である。)をもって、原告らの他の所得と損益通算をして所得税の申告をし又は更正の請求をした。
以上の取引関係を図示すると、図のようになる。
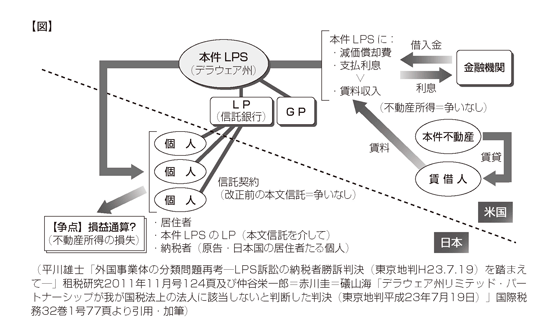
(5)所轄税務署長は、本件各不動産賃貸事業による損益は不動産所得に該当せず、本件各損失の損益通算は許されないとして、原告らに対し、所得税の更正、過少申告加算税賦課決定及び更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知をした(以下「本件各処分」という。)。
(6)原告らは、異議申立て及び審査請求を経た後、本件各処分の取消しを求め、出訴した。
(7)なお、本件各LPSは、米国財務省規則のチェック・ザ・ボックス規則の下で、連邦課税上、コーポレーション(corporation)として事業体課税を受けるか、又はパートナーシップ(partnership)として構成員課税を受けるかを選択することができる適格事業体であるところ、本件各LPSは、同規則によって、連邦課税上、パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされていることから、米国租税法上の納税義務者となっておらず、原告ら各構成員が納税義務者となった。
(8)名古屋地判によれば、上記のスキームにおいては、1口2000万円の出資に対し、我が国において投資家が本来負担すべき所得税額及び住民税額が合計2350万5000円減額されるとともに、7年間における本件各不動産賃貸事業による現金収入360万3000円及び7年後の本件建物の売却による現金収入541万8000円が得られることにより、合計約3258万2000円の利益及び税負担の軽減という税効果があるものと想定されている、とのことである(脚注5)。判示では明示されていないものの、上記のようなスキームは、不動産所得の損失と損益通算できる高額の所得を有する者に対する節税商品であったということができる。
Ⅲ 主な争点と判示の概要
1.主な争点 本件における究極的な争点は、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が「原告らの」不動産所得(所得税法26条1項)に該当するか否かである。もし、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が原告らの不動産所得に該当するのであれば、本件各不動産賃貸事業から生じる純損失を他の不動産所得から減算できる上に、不動産所得全体の純損失が生じれば、損益通算(所得税法69条1項)により他の各種所得の金額からも控除できる(脚注6)ところ、逆に、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が「原告らの」不動産所得の損益に該当しなければ、本件各不動産賃貸事業から生じる純損失を、他の不動産所得からも他の各種所得からも控除することができないことになる(脚注7)。
そして、本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当すれば、本件各不動産賃貸事業から生じる損益は原告らではなく本件各LPSに帰属すると考えられるため、本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当するか否かが問題となった(脚注8)。
その他にも争点はあるが、本稿では、上記の点のみを検討する。
2.判示の概要 名古屋地判は、まず、判断の枠組みとして、「ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において構成員課税がされるか否かは、第1次的には当該事業体が法人に該当するか否かにより判断され、これに該当しない場合に人格のない社団等に該当するか否かが問題となり、いずれも否定される場合に初めて構成員課税がされることになる」(脚注9)と判示し、これに加えて、「ある事業体が法人税の納税義務者になるか否か(逆にいえば構成員課税を行うか否か)の実質は、当該事業体がその事業の損益の帰属主体となり得る実態を有するか否かにあるということができる」とし、本件各LPSの法人該当性及び人格のない社団該当性を順次判断し、結論としてそのいずれも否定して、構成員課税がされること、すなわち本件各不動産賃貸事業から生じた損益が原告らの不動産所得に該当すると認めた。
名古屋地判による法人該当性否定の理由、人格のない社団該当性否定の理由は、概要以下のとおりである。
(1)我が国の租税法が、特段の定義なく私法上の概念を用いている場合には、租税法律主義や法的安定性確保の観点から、本来的に私法上の概念と同じ意義に解するのが相当である。民法上の「外国法人」とは、外国の法令に準拠して法人として成立した団体、すなわち、外国の法令に準拠して法人格を付与された団体をいうと解されるので、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かも、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきである。
(2)もっとも、諸外国の法制・法体系は様々であり、我が国の「法人」に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であると考えられることから、当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあり、結局、そのような場合も含めて、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、より実質的な観点から、当該事業体を当該外国の法令が規定する内容を踏まえて我が国法人と同様に損益の帰属する主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要があり、この点が肯定されて初めて、我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきである。
(3)州LPS法の規定によれば、①州LPS法に基づき組織されたLPSは、独立した法的主体となる。②LPSは、州LPS法若しくはその他の法律又は当該LPSのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(当該LPSの事業、目的、活動の実行、促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。)を保有し、それを行使することができる。③パートナーは、特定のLPS財産に対していかなる持分も所有しない。
(4)そして、日米租税条約によれば、米国における我が国租税法上の「法人」に該当する概念は、「company」や「corporation」であると解することができる。さらに、米国の連邦所得税の課税においても、corporationとpartnershipとは区分されており、前者は事業体課税がなされていること、entityといった用語の使用状況、州LPS法の制定経緯、等に照らせば、州LPS法に準拠して組成されたLPSを法人とする旨を定めたものと解することはできない。
(5)さらに、「念のために」実質的にみて、本件各LPSが我が国租税法上の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否かについて検討してみると、州LPS法の規定、本件各LPS契約の定めからは、本件各LPSがデラウェア州法上、当然に損益の帰属主体となるとまで認めることはできないし、実質的にみても、州LPS法に準拠して組成されたLPSは、パートナー間の契約関係を本質として、その事業の損益をパートナーに直接帰属させることを目的とするものであると解することができる。
(6)続いて、本件各LPSが我が国租税法上の人格のない社団に該当するか否かについて、租税法上の人格のない社団とは、民事実体法における権利能力のない社団(法人でない社団)と同義であると解されるから、ある団体(事業体)が租税法上の人格のない社団に該当するというためには、(要件①)団体としての組織を備え、(要件②)多数決の原則が行われ、(要件③)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、(要件④)代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないとの最高裁判例(脚注10)の基準に照らして検討すると、本件各LPSは構成員による意思決定のための内部組織を備えているとはいえないから、上記要件①を満たさず、また、団体としての組織を備えていない以上、本件各LPS契約の定めをもって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているということもできず、上記要件④も欠いているので、本件各LPSは我が国租税法上の人格のない社団にも該当しない。
Ⅳ 判示の検討
1.法人該当性についての判断 (1)外国事業体の我が国租税法上における法人該当性については、次のような見解があるとされる(脚注11)。
① 設立準拠法がその事業体に法人格を認めているか否かに従う(以下「設立地私法説」と呼称する。)。
② 設立地の租税法がその事業体を法人として課税しているか否かに従う(以下「設立地税法説」と呼称する。)。
③ 我が国の私法からみて、その事業体が法人と判断されるか否かにより判断する(以下「国内私法説」と呼称する。)。
④ 我が国の租税法からみて、その事業体が法人として課税されるか否かにより判断する(以下「国内税法説」と呼称する。)。
上記のうち、名古屋地判は「外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かも、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきである」とした上で、「当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあり、結局、そのような場合も含めて、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、より実質的な観点から、当該事業体を当該外国の法令が規定する内容を踏まえて我が国法人と同様に損益の帰属する主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要がある」としていることから、設立地私法説によりつつ、副次的に損益帰属主体性を参照して我が国の税法独自の立場での検討を行う国内税法説との複合的な立場であると考えられる(脚注12)。
(2)このように名古屋地判は、設立地私法説によりつつ、副次的に損益帰属主体性を基準とする国内税法説を採用するという複合的な立場を採ったものであると考えられるところ、名古屋地判が判示するように、諸外国の法制・法体系は様々であり、我が国の「法人」に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であると考えられることから、当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは、当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあると想定されるところであり、そのような場合には、設立地私法が法人格を付与しているか否かを適切に判断できるのか、といった問題があり得よう(脚注13)。また、仮に判別ができたとしても、それが妥当な結論を導くとは限らないとも考えられる。
そこで、名古屋地判は、そのような場合に備えて副次的に損益帰属主体性を基準として国内税法独自の基準を採用しているものと考えられる。しかし、そもそも、法人格の有無が争われる案件では、設立地私法の観点だけからでは、法人格の有無を明確に判別できない場合の方が多いのではないかと推測される。とするならば、損益帰属主体性を端的に法人該当性判断の主要な要素とすることも考えられるのではなかろうか。すなわち、損益帰属主体性に基づく判断基準は、必ずしも副次的な基準として機能するのではなく、むしろ一次的に機能させるということも考えられるのではなかろうかとも思われるところである。ただし、このような考え方を採ったとしても、損益帰属主体性については未だ十分な検討がなされておらず、概念として変動し得、具体性や明確性に乏しいとの問題点を指摘し得よう。
(3)また、本件各LPSの法人該当性の検討において、日米租税条約における「法人」や「corporation」といった用語を検討しているが、そもそも日米租税条約は、高度の自治権を有する米国の各州の租税法規を含む法令は、その対象外にあると基本的に考えることができ、しかも、米国では我が国と異なって条約の解釈が法令に優位するとする法制度も採られていない。これらのことからすると、日米租税条約における文言の検討は、適切な検討であるといい得るのかも疑問がないわけではない。
(4)以上のように、名古屋地判によっても、如何なる基準によって外国事業体の法人該当性を判断するかについては、その射程も含めて、必ずしも明確とはなっていない。この点については、米国は、周知のとおり、米国連邦租税法上、法人として取り扱われる外国事業体を87カ国にわたって列挙し、それ以外の事業体については、事業体課税とするか、あるいは、構成員課税とするかを選択することができるとしている(脚注14)。このような制度は、一方で租税回避的なスキームの構築を可能としているという面もあり、一定の制限や例外について検討する必要は大きいと思われるが、そのような手当をした上で課税関係を明確にするための割り切った立法論としては、あり得ないものではないものと思われる。
2.人格のない社団該当性について 人格のない社団に、本件各LPSが該当するかについては、最高裁判所昭和39年10月15日判決に基づいて、州LPS法の規定、本件各LPS契約の定め等を検討している。これは国内私法説を採用したものといえよう。しかしながら、この点についても、上記の法人該当性と同じく、外国の私法基準(上記1(1)①に相当)、外国の税法基準(上記1(1)②に相当)、国内税法基準(上記1(1)④に相当)等の考え方があり得るように考えられる。名古屋地判が、最高裁判所昭和39年10月15日判決で定立された基準を用いた理由は必ずしも明らかではないが、この点については、今後、検討されるべき点であろうと考えられる(脚注15)。
Ⅴ おわりに 名古屋地判は、東京地判とほぼ同様の考え方の枠組みに従って、東京地判と同様の判決を下したが、大阪地判は異なる判決となっている。これら3つの地裁判決は、いずれも高裁に審理の場を移して検討がなされることとなっている。高裁の判断に注目したい。
手塚崇史 てづか たかし
1996年3月東京大学法学部卒業、1996年4月自治省(現総務省)入省、2000年6月ハーバード大学ロースクール修了(International Tax Program)、2000年5月ニューヨーク州弁護士登録、2002年10月弁護士登録、2010年6月アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。租税法、特に国際課税と地方税を中心的な業務分野とし、多数の案件に従事。『国際租税訴訟の最前線』(有斐閣 2010年7月)(共著)ほか著作多数。その他、九州大学法科大学院講師(租税法実務担当)を務める。
脚注
1 TAINS番号Z888-1630。
2 TAINS番号Z888-1616。
3 判時2126号28頁。
4 名古屋地判においては、「パートナーシップとは、米国各州の立法で認められている2名以上の者により組成される事業活動や投資活動を営むための組織形態であり、パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有する2名以上のジェネラル・パートナー(GP)のみによって構成されるジェネラル・パートナーシップ(GPS)と、パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権限を有する1名以上のジェネラル・パートナー(GP)とパートナーシップ債務に対して、原則として出資額を限度とする有限責任を負い、当該事業活動に対する限定的な経営参加権を有する1名以上のリミテッド・パートナー(LP)によって構成されるリミテッド・パートナーシップ(LPS)の2種類がある」と判示されている。
5 大阪地判でも、同様の認定がなされている。
6 本件各LPS契約は、特定組合員の不動産所得に係る損益通算を制限した租税特別措置法41条の4の2の施行前のものであるため、同条は適用されない。
7 大阪地判においては、「本件各不動産賃貸事業から生じた損益自体が所得税法26条1項の不動産所得に該当すること、本件各信託契約が所得税法13条1項本文に規定する信託に該当すること(同項ただし書に規定する投資信託に該当しないこと)については、当事者間に争いがない」とされている。東京地判においても同様であったようである。なお、仮に本件各LPSが「法人」又は「人格のない社団」に該当しないとしても、本件各不動産賃貸事業から生じた損益が本件各LPSを通じて原告らに分配される段階で、所得区分が変わるのではないかという点も問題になり、名古屋地判、東京地判及び大阪地判においてはこの点も争点となっているが、本稿ではこれに立ち入らない。この点につき、仲谷栄一郎=藤田耕司「海外事業体の課税上の扱い」金子宏編著『租税法の発展』646頁以下(有斐閣、2010)。名古屋地判は、本件各LPSが行った本件各不動産賃貸事業により原告らに直接帰属することとなった損益は、本件各建物を賃貸することによって生じたものであり、事業所得や譲渡所得には該当しない、と認定している。
8 名古屋地判、東京地判及び大阪地判において、仮に損益通算が許されない場合、原告らに過少申告加算税が課されない「正当な理由」(国税通則法65条4項)があるか否かという点も争点となった。大阪地判は、損益通算が許されないとした上で、原告らには「正当な理由」も認められないと判断した。名古屋地判及び東京地判は、損益通算は許されると判断したため、「正当な理由」の有無について判断しなかった。
9 この判示部分は東京地判と全く同じである。
10 最高裁判所昭和39年10月15日判決(民集18巻8号1671頁)
11 仲谷栄一郎=赤川圭=礒山海「デラウェア州リミテッド・パートナーシップが我が国税法上の法人に該当しないと判断した判決(東京地判平成23年7月19日)」国際税務32巻1号83頁及び太田洋=佐藤修二「我が国の租税法規と外国私法の交錯」中里実ほか編著『国際租税訴訟の最前線』345頁以下(有斐閣2010)参照。
12 東京地判も同様の考え方に立っているものと考えられる。大阪地判は、国内私法説によりつつ、我が国の私法上の法人であるといい得るための基準を権利義務の帰属主体となるか検討するために用いるとする立場を採っているものと考えられる。前掲注11仲谷ほか85頁参照。
13 前掲注11仲谷ほか87頁参照。
14 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdfの末尾の頁を参照。我が国の株式会社もここに掲げられており、米国連邦租税法上、法人として取り扱われることとなる。
15 同旨前掲注11仲谷ほか89頁以下。
デラウェア州LPSの法人等該当性に関する裁判例の検討
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 手塚崇史
Ⅰ はじめに
平成23年12月14日、名古屋地方裁判所は、米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)を、我が国の租税法に規定する法人及び人格のない社団のいずれにも該当しないとする判決(以下「名古屋地判」という。)を下した(脚注1)。
本判決は、東京地裁平成23年7月29日判決(脚注2)(以下「東京地判」という。)、大阪地裁平成22年12月17日判決(脚注3)(以下「大阪地判」という。)に続いて、ほぼ同様の事案において、LPSの法人該当性ないし人格のない社団該当性について判断したものである。東京地判は、LPSの法人ないし人格のない社団該当性をいずれも否定したが、大阪地判は法人に該当すると判断した。
本稿では、これら一連の裁判例のうち、適宜、必要に応じて東京地判や大阪地判にも言及しつつ、最新の裁判例である名古屋地判について検討することとする。
なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者の所属する法律事務所の見解ではないことを念のため申し添える。
Ⅱ 事案の概要
事案の概要は、名古屋地判、東京地判及び大阪地判ともいずれもほぼ同様である。すなわち、原告ら投資家が、外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPSが行った米国所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得(損失)が、所得税法26条1項所定の不動産所得(損失)に該当するものとして、その減価償却等による損失と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をしたところ、税務当局から、当該所得は不動産所得に該当しないことから損益通算はできないとして、所得税の更正処分ないし更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分等を受け、これらを不服として原告ら投資家がこれら各処分の取消しを求めたものである。より詳細には、以下のとおりである。
(1)いずれも我が国の居住者たる個人である原告らは、米国所在の中古集合住宅である建物(以下「本件建物」という。)を対象とした、投資金額を1口2000万円とする不動産賃貸事業(以下「本件各不動産賃貸事業」という。)に投資するため、A銀行との間で、自己を委託者兼受益者、A銀行を受託者とする信託契約(以下「本件各信託契約」という。)を締結し、同契約に基づいて、A銀行に開設された口座に現金を拠出した。
(2)A銀行は、米国デラウェア州の複数のリミテッド・ライアビリティ・カンパニーとの間で、それらのリミテッド・ライアビリティ・カンパニーをジェネラル・パートナー(以下「本件各GP」という。)、A銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ契約(脚注4)を締結し(以下、A銀行と本件各GPが締結したリミテッド・パートナーシップ契約を「本件各LPS契約」、本件各LPS契約により組成されたLPSを「本件各LPS」という。)、本件各LPS契約に基づき、原告らが拠出した現金を本件各LPSに出資した。
(3)本件各LPSは、第三者から本件建物を購入し、本件建物の敷地を賃借して、本件建物を別の第三者に対して賃貸した。
(4)原告らは、本件各不動産賃貸事業による損益が不動産所得に該当することを前提に、本件各不動産賃貸事業によって生じた各損失(以下「本件各損失」という。本件各損失の内容は、本件建物の減価償却費等である。)をもって、原告らの他の所得と損益通算をして所得税の申告をし又は更正の請求をした。
以上の取引関係を図示すると、図のようになる。
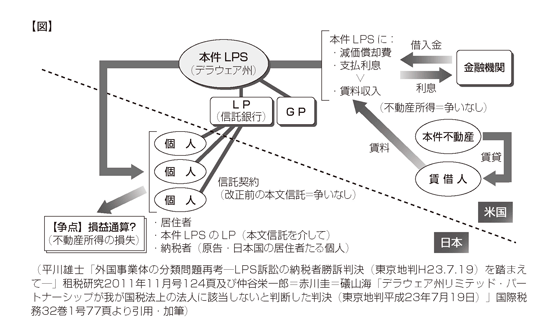
(5)所轄税務署長は、本件各不動産賃貸事業による損益は不動産所得に該当せず、本件各損失の損益通算は許されないとして、原告らに対し、所得税の更正、過少申告加算税賦課決定及び更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知をした(以下「本件各処分」という。)。
(6)原告らは、異議申立て及び審査請求を経た後、本件各処分の取消しを求め、出訴した。
(7)なお、本件各LPSは、米国財務省規則のチェック・ザ・ボックス規則の下で、連邦課税上、コーポレーション(corporation)として事業体課税を受けるか、又はパートナーシップ(partnership)として構成員課税を受けるかを選択することができる適格事業体であるところ、本件各LPSは、同規則によって、連邦課税上、パートナーシップとしての課税を選択したものとみなされていることから、米国租税法上の納税義務者となっておらず、原告ら各構成員が納税義務者となった。
(8)名古屋地判によれば、上記のスキームにおいては、1口2000万円の出資に対し、我が国において投資家が本来負担すべき所得税額及び住民税額が合計2350万5000円減額されるとともに、7年間における本件各不動産賃貸事業による現金収入360万3000円及び7年後の本件建物の売却による現金収入541万8000円が得られることにより、合計約3258万2000円の利益及び税負担の軽減という税効果があるものと想定されている、とのことである(脚注5)。判示では明示されていないものの、上記のようなスキームは、不動産所得の損失と損益通算できる高額の所得を有する者に対する節税商品であったということができる。
Ⅲ 主な争点と判示の概要
1.主な争点 本件における究極的な争点は、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が「原告らの」不動産所得(所得税法26条1項)に該当するか否かである。もし、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が原告らの不動産所得に該当するのであれば、本件各不動産賃貸事業から生じる純損失を他の不動産所得から減算できる上に、不動産所得全体の純損失が生じれば、損益通算(所得税法69条1項)により他の各種所得の金額からも控除できる(脚注6)ところ、逆に、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が「原告らの」不動産所得の損益に該当しなければ、本件各不動産賃貸事業から生じる純損失を、他の不動産所得からも他の各種所得からも控除することができないことになる(脚注7)。
そして、本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当すれば、本件各不動産賃貸事業から生じる損益は原告らではなく本件各LPSに帰属すると考えられるため、本件各LPSが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない社団」に該当するか否かが問題となった(脚注8)。
その他にも争点はあるが、本稿では、上記の点のみを検討する。
2.判示の概要 名古屋地判は、まず、判断の枠組みとして、「ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において構成員課税がされるか否かは、第1次的には当該事業体が法人に該当するか否かにより判断され、これに該当しない場合に人格のない社団等に該当するか否かが問題となり、いずれも否定される場合に初めて構成員課税がされることになる」(脚注9)と判示し、これに加えて、「ある事業体が法人税の納税義務者になるか否か(逆にいえば構成員課税を行うか否か)の実質は、当該事業体がその事業の損益の帰属主体となり得る実態を有するか否かにあるということができる」とし、本件各LPSの法人該当性及び人格のない社団該当性を順次判断し、結論としてそのいずれも否定して、構成員課税がされること、すなわち本件各不動産賃貸事業から生じた損益が原告らの不動産所得に該当すると認めた。
名古屋地判による法人該当性否定の理由、人格のない社団該当性否定の理由は、概要以下のとおりである。
(1)我が国の租税法が、特段の定義なく私法上の概念を用いている場合には、租税法律主義や法的安定性確保の観点から、本来的に私法上の概念と同じ意義に解するのが相当である。民法上の「外国法人」とは、外国の法令に準拠して法人として成立した団体、すなわち、外国の法令に準拠して法人格を付与された団体をいうと解されるので、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かも、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきである。
(2)もっとも、諸外国の法制・法体系は様々であり、我が国の「法人」に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であると考えられることから、当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあり、結局、そのような場合も含めて、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、より実質的な観点から、当該事業体を当該外国の法令が規定する内容を踏まえて我が国法人と同様に損益の帰属する主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要があり、この点が肯定されて初めて、我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきである。
(3)州LPS法の規定によれば、①州LPS法に基づき組織されたLPSは、独立した法的主体となる。②LPSは、州LPS法若しくはその他の法律又は当該LPSのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限(当該LPSの事業、目的、活動の実行、促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。)を保有し、それを行使することができる。③パートナーは、特定のLPS財産に対していかなる持分も所有しない。
(4)そして、日米租税条約によれば、米国における我が国租税法上の「法人」に該当する概念は、「company」や「corporation」であると解することができる。さらに、米国の連邦所得税の課税においても、corporationとpartnershipとは区分されており、前者は事業体課税がなされていること、entityといった用語の使用状況、州LPS法の制定経緯、等に照らせば、州LPS法に準拠して組成されたLPSを法人とする旨を定めたものと解することはできない。
(5)さらに、「念のために」実質的にみて、本件各LPSが我が国租税法上の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否かについて検討してみると、州LPS法の規定、本件各LPS契約の定めからは、本件各LPSがデラウェア州法上、当然に損益の帰属主体となるとまで認めることはできないし、実質的にみても、州LPS法に準拠して組成されたLPSは、パートナー間の契約関係を本質として、その事業の損益をパートナーに直接帰属させることを目的とするものであると解することができる。
(6)続いて、本件各LPSが我が国租税法上の人格のない社団に該当するか否かについて、租税法上の人格のない社団とは、民事実体法における権利能力のない社団(法人でない社団)と同義であると解されるから、ある団体(事業体)が租税法上の人格のない社団に該当するというためには、(要件①)団体としての組織を備え、(要件②)多数決の原則が行われ、(要件③)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、(要件④)代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないとの最高裁判例(脚注10)の基準に照らして検討すると、本件各LPSは構成員による意思決定のための内部組織を備えているとはいえないから、上記要件①を満たさず、また、団体としての組織を備えていない以上、本件各LPS契約の定めをもって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているということもできず、上記要件④も欠いているので、本件各LPSは我が国租税法上の人格のない社団にも該当しない。
Ⅳ 判示の検討
1.法人該当性についての判断 (1)外国事業体の我が国租税法上における法人該当性については、次のような見解があるとされる(脚注11)。
① 設立準拠法がその事業体に法人格を認めているか否かに従う(以下「設立地私法説」と呼称する。)。
② 設立地の租税法がその事業体を法人として課税しているか否かに従う(以下「設立地税法説」と呼称する。)。
③ 我が国の私法からみて、その事業体が法人と判断されるか否かにより判断する(以下「国内私法説」と呼称する。)。
④ 我が国の租税法からみて、その事業体が法人として課税されるか否かにより判断する(以下「国内税法説」と呼称する。)。
上記のうち、名古屋地判は「外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かも、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきである」とした上で、「当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあり、結局、そのような場合も含めて、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、より実質的な観点から、当該事業体を当該外国の法令が規定する内容を踏まえて我が国法人と同様に損益の帰属する主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要がある」としていることから、設立地私法説によりつつ、副次的に損益帰属主体性を参照して我が国の税法独自の立場での検討を行う国内税法説との複合的な立場であると考えられる(脚注12)。
(2)このように名古屋地判は、設立地私法説によりつつ、副次的に損益帰属主体性を基準とする国内税法説を採用するという複合的な立場を採ったものであると考えられるところ、名古屋地判が判示するように、諸外国の法制・法体系は様々であり、我が国の「法人」に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であると考えられることから、当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは、当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあると想定されるところであり、そのような場合には、設立地私法が法人格を付与しているか否かを適切に判断できるのか、といった問題があり得よう(脚注13)。また、仮に判別ができたとしても、それが妥当な結論を導くとは限らないとも考えられる。
そこで、名古屋地判は、そのような場合に備えて副次的に損益帰属主体性を基準として国内税法独自の基準を採用しているものと考えられる。しかし、そもそも、法人格の有無が争われる案件では、設立地私法の観点だけからでは、法人格の有無を明確に判別できない場合の方が多いのではないかと推測される。とするならば、損益帰属主体性を端的に法人該当性判断の主要な要素とすることも考えられるのではなかろうか。すなわち、損益帰属主体性に基づく判断基準は、必ずしも副次的な基準として機能するのではなく、むしろ一次的に機能させるということも考えられるのではなかろうかとも思われるところである。ただし、このような考え方を採ったとしても、損益帰属主体性については未だ十分な検討がなされておらず、概念として変動し得、具体性や明確性に乏しいとの問題点を指摘し得よう。
(3)また、本件各LPSの法人該当性の検討において、日米租税条約における「法人」や「corporation」といった用語を検討しているが、そもそも日米租税条約は、高度の自治権を有する米国の各州の租税法規を含む法令は、その対象外にあると基本的に考えることができ、しかも、米国では我が国と異なって条約の解釈が法令に優位するとする法制度も採られていない。これらのことからすると、日米租税条約における文言の検討は、適切な検討であるといい得るのかも疑問がないわけではない。
(4)以上のように、名古屋地判によっても、如何なる基準によって外国事業体の法人該当性を判断するかについては、その射程も含めて、必ずしも明確とはなっていない。この点については、米国は、周知のとおり、米国連邦租税法上、法人として取り扱われる外国事業体を87カ国にわたって列挙し、それ以外の事業体については、事業体課税とするか、あるいは、構成員課税とするかを選択することができるとしている(脚注14)。このような制度は、一方で租税回避的なスキームの構築を可能としているという面もあり、一定の制限や例外について検討する必要は大きいと思われるが、そのような手当をした上で課税関係を明確にするための割り切った立法論としては、あり得ないものではないものと思われる。
2.人格のない社団該当性について 人格のない社団に、本件各LPSが該当するかについては、最高裁判所昭和39年10月15日判決に基づいて、州LPS法の規定、本件各LPS契約の定め等を検討している。これは国内私法説を採用したものといえよう。しかしながら、この点についても、上記の法人該当性と同じく、外国の私法基準(上記1(1)①に相当)、外国の税法基準(上記1(1)②に相当)、国内税法基準(上記1(1)④に相当)等の考え方があり得るように考えられる。名古屋地判が、最高裁判所昭和39年10月15日判決で定立された基準を用いた理由は必ずしも明らかではないが、この点については、今後、検討されるべき点であろうと考えられる(脚注15)。
Ⅴ おわりに 名古屋地判は、東京地判とほぼ同様の考え方の枠組みに従って、東京地判と同様の判決を下したが、大阪地判は異なる判決となっている。これら3つの地裁判決は、いずれも高裁に審理の場を移して検討がなされることとなっている。高裁の判断に注目したい。
手塚崇史 てづか たかし
1996年3月東京大学法学部卒業、1996年4月自治省(現総務省)入省、2000年6月ハーバード大学ロースクール修了(International Tax Program)、2000年5月ニューヨーク州弁護士登録、2002年10月弁護士登録、2010年6月アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。租税法、特に国際課税と地方税を中心的な業務分野とし、多数の案件に従事。『国際租税訴訟の最前線』(有斐閣 2010年7月)(共著)ほか著作多数。その他、九州大学法科大学院講師(租税法実務担当)を務める。
脚注
1 TAINS番号Z888-1630。
2 TAINS番号Z888-1616。
3 判時2126号28頁。
4 名古屋地判においては、「パートナーシップとは、米国各州の立法で認められている2名以上の者により組成される事業活動や投資活動を営むための組織形態であり、パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有する2名以上のジェネラル・パートナー(GP)のみによって構成されるジェネラル・パートナーシップ(GPS)と、パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権限を有する1名以上のジェネラル・パートナー(GP)とパートナーシップ債務に対して、原則として出資額を限度とする有限責任を負い、当該事業活動に対する限定的な経営参加権を有する1名以上のリミテッド・パートナー(LP)によって構成されるリミテッド・パートナーシップ(LPS)の2種類がある」と判示されている。
5 大阪地判でも、同様の認定がなされている。
6 本件各LPS契約は、特定組合員の不動産所得に係る損益通算を制限した租税特別措置法41条の4の2の施行前のものであるため、同条は適用されない。
7 大阪地判においては、「本件各不動産賃貸事業から生じた損益自体が所得税法26条1項の不動産所得に該当すること、本件各信託契約が所得税法13条1項本文に規定する信託に該当すること(同項ただし書に規定する投資信託に該当しないこと)については、当事者間に争いがない」とされている。東京地判においても同様であったようである。なお、仮に本件各LPSが「法人」又は「人格のない社団」に該当しないとしても、本件各不動産賃貸事業から生じた損益が本件各LPSを通じて原告らに分配される段階で、所得区分が変わるのではないかという点も問題になり、名古屋地判、東京地判及び大阪地判においてはこの点も争点となっているが、本稿ではこれに立ち入らない。この点につき、仲谷栄一郎=藤田耕司「海外事業体の課税上の扱い」金子宏編著『租税法の発展』646頁以下(有斐閣、2010)。名古屋地判は、本件各LPSが行った本件各不動産賃貸事業により原告らに直接帰属することとなった損益は、本件各建物を賃貸することによって生じたものであり、事業所得や譲渡所得には該当しない、と認定している。
8 名古屋地判、東京地判及び大阪地判において、仮に損益通算が許されない場合、原告らに過少申告加算税が課されない「正当な理由」(国税通則法65条4項)があるか否かという点も争点となった。大阪地判は、損益通算が許されないとした上で、原告らには「正当な理由」も認められないと判断した。名古屋地判及び東京地判は、損益通算は許されると判断したため、「正当な理由」の有無について判断しなかった。
9 この判示部分は東京地判と全く同じである。
10 最高裁判所昭和39年10月15日判決(民集18巻8号1671頁)
11 仲谷栄一郎=赤川圭=礒山海「デラウェア州リミテッド・パートナーシップが我が国税法上の法人に該当しないと判断した判決(東京地判平成23年7月19日)」国際税務32巻1号83頁及び太田洋=佐藤修二「我が国の租税法規と外国私法の交錯」中里実ほか編著『国際租税訴訟の最前線』345頁以下(有斐閣2010)参照。
12 東京地判も同様の考え方に立っているものと考えられる。大阪地判は、国内私法説によりつつ、我が国の私法上の法人であるといい得るための基準を権利義務の帰属主体となるか検討するために用いるとする立場を採っているものと考えられる。前掲注11仲谷ほか85頁参照。
13 前掲注11仲谷ほか87頁参照。
14 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdfの末尾の頁を参照。我が国の株式会社もここに掲げられており、米国連邦租税法上、法人として取り扱われることとなる。
15 同旨前掲注11仲谷ほか89頁以下。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























