解説記事2012年08月13日 【ニュース特集】 貸倒引当金廃止による実務への影響(2012年8月13日号・№463)
今後は「事実上の貸倒れ」がクローズアップも
貸倒引当金廃止による実務への影響
平成24年度税制改正により、特定の法人以外は貸倒引当金の損金算入が認められなくなったが、これにより、従来の貸倒実務は大きな影響を受けることになる。
平成21年度の通達改正で創設された金銭債権の減額分の貸倒引当金繰入れを認める規定が存在意義を失う一方で、今後は「事実上の貸倒損失」が実務上重要になるものと考えられる。
「貸倒引当金廃止後」の貸倒実務の留意点をまとめた。
貸倒引当金廃止で、3年前に創設した通達の存在意義が消失 平成24年度税制改正により、中小法人や銀行など特定の法人を除き、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金の損金算入が制限されることになった。具体的には、中小法人や銀行、保険会社等については現行制度のまま貸倒引当金が維持されたほか、リース会社や証券会社、クレジット会社等の「リース債権を有する法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する法人」については、貸倒引当金への繰入対象が“本業”に係る特定の金銭債権に限定されることとなった(改正法法52条①一~三、改正法令96条、97条、改正法規25条の4の2、25条の5)。リース会社を例にとると、「リース債権」のみが貸倒引当金の対象となる。
これ以外の法人については、3年間の経過措置を経て、(経過措置が切れる)27年4月1日以降に開始する事業年度からは一切損金算入ができなくなる(改正法附則13条①、図表参照)。
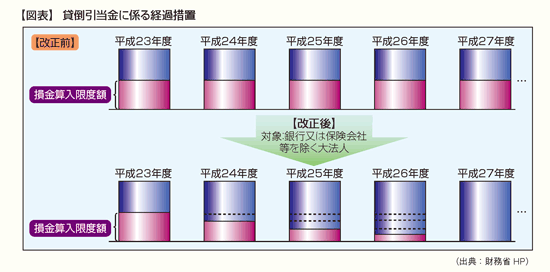
これに伴い、今後、金銭債権については、①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)、②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(法基通9-6-3)―――により、「貸倒損失」の計上可否のみを判断することになる。
ただ、貸倒引当金は会計慣行として定着してきただけに、税務における貸倒引当金の廃止は、しばらく実務に混乱をもたらすことになる可能性がありそうだ。
例えば、法的整理の事実が生じた場合における金銭債権の取扱いである(法基通9-1-3の2、次ページ下参照)。
法人税基本通達9-1-3の2は、今から約3年前の平成21年度の通達改正により創設されたものであるが、平成24年度税制改正における貸倒引当金の廃止によって、貸倒実務における重要な取扱いの一つであった同通達の(注)の趣旨は根底から崩れることになる。
そもそも同通達が創設された背景には、法人税法上、金銭債権について評価損計上が認められるのかどうか、はっきりしなかったということがある。法人税法では、特定の要件を満たす場合には資産の評価損の計上が認められており(法法33条②)、評価損の計上が認められる資産は法人税法施行令68条に規定されているが、ここに金銭債権は入っていない。一方、法人税法33条3項、4項で「法的整理によって資産の切り捨てがなされた場合には評価損の計上を認める」旨規定されているにもかかわらず、この場合に評価損の計上が認められる資産は、法人税法施行令68条のように具体的に規定されてない。
このため、金銭債権について評価損計上が認められるのかどうか、解釈に疑義が生じていた。
そこで課税当局は、平成21年度の通達改正により法人税基本通達9-1-3の2を新設、金銭債権の評価損計上は認めないことを明確にする一方、同通達の(注)では、更生手続きや再生手続きの開始決定がなされた場合(法的整理の事実が生じた場合)においては、「貸倒引当金」への繰入れにより、簿価を減額した分の損金計上を認めることとしたところだ。
しかし、平成24年度税制改正により特定の法人以外は貸倒引当金が認められなくなったことで、特定の法人以外にとっては、同通達の(注)は意味をなさない規定となった(経過措置の適用期間を除く)。すなわち、前述の通り、今後金銭債権については「貸倒損失」の計上可否のみが判断されることになる。
あれから7年余り、興銀事件で「事実上の貸倒れ」の適用範囲は広がったか 課税当局は、貸倒損失の計上について「考え方はこれまでと何も変わらない」と述べているが、貸倒損失が計上される3つのパターン――①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)、②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(法基通9-6-3)――のうち、もっとも課税当局との見解の相違が生じやすいのが「事実上の貸倒れ」であろう。
事実上の貸倒れについてまず気になるのが、その「判定要素」だ。
法人税基本通達9-6-2(下記参照)では、回収不能かどうかは「債務者」の資産状況、支払能力等をみて判断する旨規定しているが、この点についていわゆる興銀事件(平成16年12月24日 最高裁判所第二小法廷判決)で最高裁は、債務者側の事情のみならず「債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等」といった「債権者側の事情」「経済的環境等」も考慮する必要があると判断、法人税基本通達9-6-2を形式的に適用して興銀の貸倒損失計上を否認した国側の全面敗訴という判決をもたらしたのは、いまだに記憶に新しい。
すなわち、最高裁判決は、法人税基本通達9-6-2に規定する貸倒損失計上の判定要素に「債権者側の事情」「経済的環境等」を加えることで、貸倒損失の計上範囲を広げたものと言える。
ただ、最高裁判決の後、現在まで法人税基本通達9-6-2は改正されていない。この点について課税当局は、最高裁判決を踏まえ、「債権者側の事情等を考慮する必要があることは認識している」という。
とはいえ、最高裁判決の後に「貸倒損失の損金算入に係る事前照会窓口」を設けたにもかかわらず、照会がほとんどなかったことから、「最高裁判決で指摘された課税上の弊害は実際には存在していない」というのが課税当局の認識であり、通達改正を行わなかった理由もそこにある。
したがって、税務調査等においては、今後も引き続き「債務者側の事情」のみを考慮して、回収可能か否かが判断されることになると言っていいだろう。
常にチェックされる貸倒損失の計上時期 「事実上の貸倒れ」による貸倒損失を巡り、税務調査で常にチェックされることになると言ってよいのが、その計上時期だ。特に、赤字申告の翌期が黒字となったタイミングで貸倒引当金を計上した場合、調査官の注目度が一段と高まることは間違いない。税務調査でのトラブルを避けるためには、なぜその時点で回収不能と判断したのかについて、調査官を納得させるだけの理由を用意しておく必要がある。
また、債務者の行方が分からなくなった場合も「事実上の貸倒れ」に該当し得るが、この場合、どの程度債務者の行方を確認をした上で「行方不明」と判断したのかも問われることになる。例えば、単に「電話をかけても通じなかった」といった程度の確認では貸倒損失の計上が否認される可能性もあるので要注意だ。貸倒損失の計上が認められるためには、債務者の行方を捜すために相応の努力を払ったことを具体的に調査官に示す必要があろう。
貸倒引当金廃止による実務への影響
平成24年度税制改正により、特定の法人以外は貸倒引当金の損金算入が認められなくなったが、これにより、従来の貸倒実務は大きな影響を受けることになる。
平成21年度の通達改正で創設された金銭債権の減額分の貸倒引当金繰入れを認める規定が存在意義を失う一方で、今後は「事実上の貸倒損失」が実務上重要になるものと考えられる。
「貸倒引当金廃止後」の貸倒実務の留意点をまとめた。
貸倒引当金廃止で、3年前に創設した通達の存在意義が消失 平成24年度税制改正により、中小法人や銀行など特定の法人を除き、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金の損金算入が制限されることになった。具体的には、中小法人や銀行、保険会社等については現行制度のまま貸倒引当金が維持されたほか、リース会社や証券会社、クレジット会社等の「リース債権を有する法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する法人」については、貸倒引当金への繰入対象が“本業”に係る特定の金銭債権に限定されることとなった(改正法法52条①一~三、改正法令96条、97条、改正法規25条の4の2、25条の5)。リース会社を例にとると、「リース債権」のみが貸倒引当金の対象となる。
これ以外の法人については、3年間の経過措置を経て、(経過措置が切れる)27年4月1日以降に開始する事業年度からは一切損金算入ができなくなる(改正法附則13条①、図表参照)。
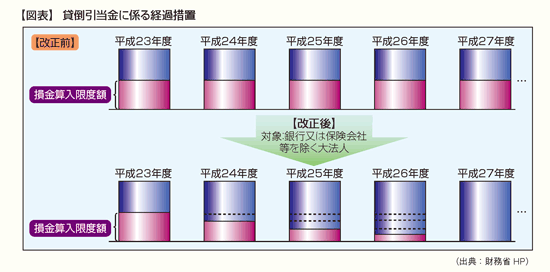
これに伴い、今後、金銭債権については、①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)、②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(法基通9-6-3)―――により、「貸倒損失」の計上可否のみを判断することになる。
ただ、貸倒引当金は会計慣行として定着してきただけに、税務における貸倒引当金の廃止は、しばらく実務に混乱をもたらすことになる可能性がありそうだ。
例えば、法的整理の事実が生じた場合における金銭債権の取扱いである(法基通9-1-3の2、次ページ下参照)。
法人税基本通達9-1-3の2は、今から約3年前の平成21年度の通達改正により創設されたものであるが、平成24年度税制改正における貸倒引当金の廃止によって、貸倒実務における重要な取扱いの一つであった同通達の(注)の趣旨は根底から崩れることになる。
そもそも同通達が創設された背景には、法人税法上、金銭債権について評価損計上が認められるのかどうか、はっきりしなかったということがある。法人税法では、特定の要件を満たす場合には資産の評価損の計上が認められており(法法33条②)、評価損の計上が認められる資産は法人税法施行令68条に規定されているが、ここに金銭債権は入っていない。一方、法人税法33条3項、4項で「法的整理によって資産の切り捨てがなされた場合には評価損の計上を認める」旨規定されているにもかかわらず、この場合に評価損の計上が認められる資産は、法人税法施行令68条のように具体的に規定されてない。
このため、金銭債権について評価損計上が認められるのかどうか、解釈に疑義が生じていた。
そこで課税当局は、平成21年度の通達改正により法人税基本通達9-1-3の2を新設、金銭債権の評価損計上は認めないことを明確にする一方、同通達の(注)では、更生手続きや再生手続きの開始決定がなされた場合(法的整理の事実が生じた場合)においては、「貸倒引当金」への繰入れにより、簿価を減額した分の損金計上を認めることとしたところだ。
しかし、平成24年度税制改正により特定の法人以外は貸倒引当金が認められなくなったことで、特定の法人以外にとっては、同通達の(注)は意味をなさない規定となった(経過措置の適用期間を除く)。すなわち、前述の通り、今後金銭債権については「貸倒損失」の計上可否のみが判断されることになる。
| ▶法人税基本通達9-1-3の2(評価換えの対象となる資産の範囲) |
| 法人の有する金銭債権は、法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の評価換えの対象とならないことに留意する。 (注)令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」が生じた場合において、法人の有する金銭債権の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額については、法第52条《貸倒引当金》の貸倒引当金勘定に繰り入れた金額として取り扱う。(平21年課法2-5「七」により追加) |
あれから7年余り、興銀事件で「事実上の貸倒れ」の適用範囲は広がったか 課税当局は、貸倒損失の計上について「考え方はこれまでと何も変わらない」と述べているが、貸倒損失が計上される3つのパターン――①法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)、②事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)、③一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(法基通9-6-3)――のうち、もっとも課税当局との見解の相違が生じやすいのが「事実上の貸倒れ」であろう。
事実上の貸倒れについてまず気になるのが、その「判定要素」だ。
法人税基本通達9-6-2(下記参照)では、回収不能かどうかは「債務者」の資産状況、支払能力等をみて判断する旨規定しているが、この点についていわゆる興銀事件(平成16年12月24日 最高裁判所第二小法廷判決)で最高裁は、債務者側の事情のみならず「債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等」といった「債権者側の事情」「経済的環境等」も考慮する必要があると判断、法人税基本通達9-6-2を形式的に適用して興銀の貸倒損失計上を否認した国側の全面敗訴という判決をもたらしたのは、いまだに記憶に新しい。
すなわち、最高裁判決は、法人税基本通達9-6-2に規定する貸倒損失計上の判定要素に「債権者側の事情」「経済的環境等」を加えることで、貸倒損失の計上範囲を広げたものと言える。
ただ、最高裁判決の後、現在まで法人税基本通達9-6-2は改正されていない。この点について課税当局は、最高裁判決を踏まえ、「債権者側の事情等を考慮する必要があることは認識している」という。
とはいえ、最高裁判決の後に「貸倒損失の損金算入に係る事前照会窓口」を設けたにもかかわらず、照会がほとんどなかったことから、「最高裁判決で指摘された課税上の弊害は実際には存在していない」というのが課税当局の認識であり、通達改正を行わなかった理由もそこにある。
したがって、税務調査等においては、今後も引き続き「債務者側の事情」のみを考慮して、回収可能か否かが判断されることになると言っていいだろう。
| ▶法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ) |
| 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。 (注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。 |
常にチェックされる貸倒損失の計上時期 「事実上の貸倒れ」による貸倒損失を巡り、税務調査で常にチェックされることになると言ってよいのが、その計上時期だ。特に、赤字申告の翌期が黒字となったタイミングで貸倒引当金を計上した場合、調査官の注目度が一段と高まることは間違いない。税務調査でのトラブルを避けるためには、なぜその時点で回収不能と判断したのかについて、調査官を納得させるだけの理由を用意しておく必要がある。
また、債務者の行方が分からなくなった場合も「事実上の貸倒れ」に該当し得るが、この場合、どの程度債務者の行方を確認をした上で「行方不明」と判断したのかも問われることになる。例えば、単に「電話をかけても通じなかった」といった程度の確認では貸倒損失の計上が否認される可能性もあるので要注意だ。貸倒損失の計上が認められるためには、債務者の行方を捜すために相応の努力を払ったことを具体的に調査官に示す必要があろう。
| 興銀事件とは? |
| バブル崩壊後の住専処理策の一環として、日本興業銀行(現みずほコーポレート銀行)が、傘下の住専(日本ハウジングローン株式会社。以下JHL社)に対する貸付金について、解除条件付債権放棄を行ったによる貸倒損失の計上時期を主な争点とする訴訟。一審の東京地裁では、「社会通念上全額回収不能、仮に回収不能でないとしても、本件債権放棄によって全額を損金に算入すべきもの」として興銀勝訴の判決が下されたが、続く控訴審の東京高裁では一転、「住専処理の流動的な事実関係の下において、解除条件付きの債権放棄による損失を対象事業年度の損金に算入することはできない」として、国勝訴の判決が下された。 そして最高裁判決では、金銭債権の全額が回収不能であることについて、「当該事業年度の損金の額に算入するためには、金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される。そして、その全額が回収不能であることは、客観的に明らかでなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生じる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきもの」と判示し、「興銀が債権額に応じた損失の平等負担を主張することは、平成8年3月末までの間に社会通念上不可能となっており、当時のJHL社の資産等の状況からすると、本件債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかになっていたというべきである。そして、このことは、本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではない」として、本件債権相当額3,760億5,500万円を対象事業年度(平成8年3月期)の損金に算入することとした。この結果、還付加算金を含め、3,000億円を超える金額が還付されるに至っている。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























