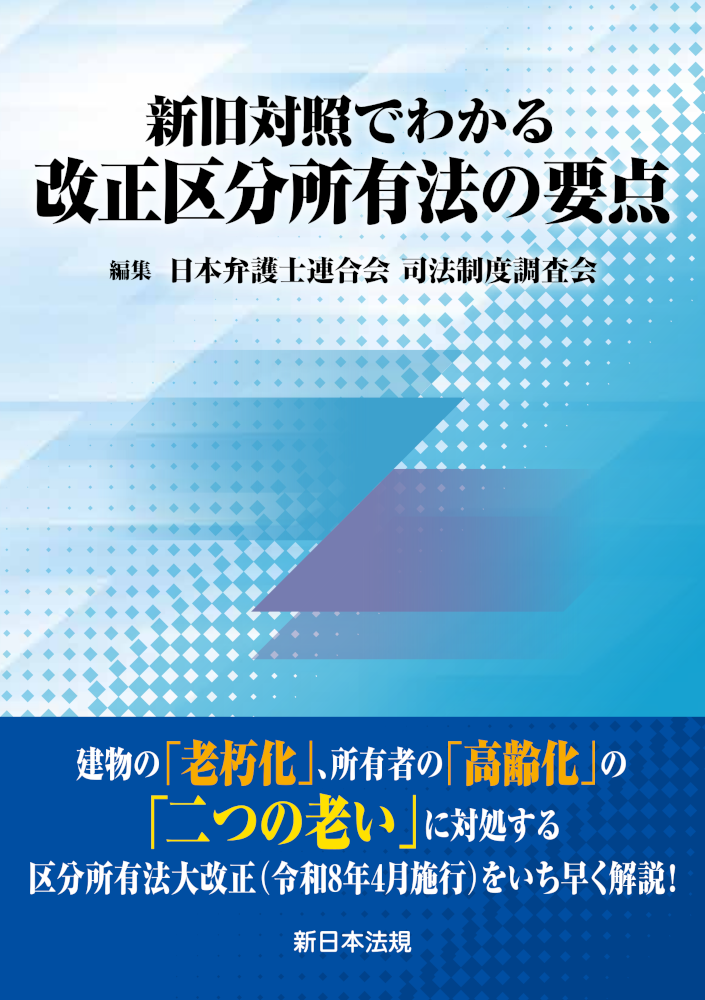解説記事2012年11月26日 【実務解説】 事業再生実務の法務-事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント-(2012年11月26日号・№476)
実務解説
事業再生実務の法務
-事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント-
弁護士・公認会計士 鈴木規央
Ⅰ 序 論
平成21年11月30日に成立し、12月4日に施行された中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」という。)が、平成25年3月31日をもって、いよいよ終了する。
この中小企業金融円滑化法は、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、金融機関はできる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを定めているため、多くの中小企業が金融機関に対し、条件変更を申し入れ、条件変更に応じてもらった企業は多いと聞く。しかし、中小企業円滑化法終了後は、このような条件変更を申し入れても、金融機関が容易には応じないということが想定され、今まで問題を先送りにしてきた中小企業の多くが、倒産せざるを得ないのではないかということが危惧されている。
かかる事態を回避すべく、現在、官民一体型ファンドを立ち上げ、救済しようという動きがあるが、すべての企業がファンドによる救済を得られるとは到底考えられず、負債を抱えた企業は、自力で事業再建の手法を考える必要がある。それには、どのような事業再建の手続や財務リストラの手法があるのか、ある程度知っておくことが有益である。
そこで、本稿では、事業再建の手続について説明するとともに、財務リストラの手法について言及する。
Ⅱ 私的整理と法的整理
事業再建の手続は、大きく分けて、私的整理と法的整理の二種類がある。私的整理とは、裁判所が関与しない再建手続であり、法的整理(脚注1)とは裁判所が関与する再建手続である。
私的整理は、再建手続に入ったことについて公表されないため、「倒産」のレッテルが貼られることを回避できるといったメリットや、取引業者に対する債権を債務整理の対象としないこともできるので、取引業者との関係を円満に保つことができるというメリットがある。しかし、私的整理は、債務処理について対象債権者全員の同意が必要となるため、合意形成が困難であるというデメリットがある。
これに対し、法的整理は、多数決原理により再生計画案が可決され、裁判所の認可決定が得られれば、債権者全員に対して効力が及ぶという強制的効果があるため、債権者調整が比較的容易であるというメリットがある。しかし、法的整理は、「倒産」のレッテルが貼られ、事業価値が毀損するおそれが高いというデメリットや、取引先の債権も整理の対象となるので、取引業者との関係が悪化する可能性が高いというデメリットがある。
債権者からの同意が得られないなどの理由により私的整理での事業再建が困難な場合、法的整理に移行し、再建手続を進めることは可能である。例えば、日本航空は、平成21年10月29日、国土交通大臣直轄のJAL再生タスクフォースによる再建計画を策定し、同年11月13日、事業再生ADRを申請したが金融機関からの同意が得られず、平成22年1月19日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、同日、開始決定を受けた。また、ウィルコムも平成21年9月24日、事業再生ADRの申請をしたが、平成22年2月18日、会社更生手続開始の申立てをした。最近では、三光汽船が平成24年3月9日、事業再生ADRの申請をしたが、担保権者による権利行使が止まらず、同年7月2日、会社更生手続開始の申立てをした。このように、私的整理での事業再建が困難な場合に法的整理に移行し、再建手続を進める例は多い。
これに対し、法的整理での事業再建が困難となった場合、他の法的整理手続に移行することはできるが、私的整理手続に移行することはできない。法的整理で事業再建が困難となり、他の法的整理での事業再建もできない場合には、破産手続に移行する。そのため、通常は、私的整理手続での事業再建の可能性を先に探るのが、事業再建の専門家の思考である。
Ⅲ 私的整理の種類
私的整理は、債権者との個別協議により進める方法、私的整理ガイドラインに沿って進める方法、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会の調整を得て進める方法(以下「中小企業再生支援協議会スキーム」という。)、株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)の調整を得て進める方法(以下「RCC企業再生スキーム」という。)、企業再生支援機構の支援を得て進める方法(以下「企業再生支援機構スキーム」という。)等がある。
債権者との個別協議による方法及び私的整理ガイドラインによる方法は関係当事者間で進める私的整理であるが、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会スキーム、RCCスキーム、企業再生支援機構スキームは、第三者が介入して進める私的整理である。
1 債権者との個別協議により進める方法 私的整理のうち、債権者との個別協議により進める私的整理は、最も基本的な方法である。
しかし、債権者との個別協議により進める私的整理は、債務整理をしなければならない事態を招いたのは他ならぬ債務者であることから、債務者の説明では債権者から信用を得られにくいこと、対象となる債権者が複数存在する場合には、公平性や透明性の確保が強く求められるところ、こうした公平性や透明性を確保することが困難であること等から、債権者からの同意が得られにくい。
そこで、債権者との個別協議による私的整理を行う場合、特定調停を利用することが考えられる。特定調停は、個人・法人を問わず、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資するため、裁判所の主催する調停手続により、債権者と債務者との間で、債務の減免、弁済期限の猶予、担保権の変更等を合意する手続である(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1条)。
特定調停は、多重債務者個人が金融債権者を相手方として、利息制限法に基づき計算し直した借入金残金をリスケジュールして、毎月分割弁済することを求める場合、また、中堅ゼネコン、都道府県の住宅供給公社、第三セクター等の企業等が金融債権者等を相手方として申し立てる場合に多く利用されている(脚注2)。
特定調停は、非公開手続であることから、債務者は調停の相手方とする債権者を選択でき、事実上秘密裏に手続を進めることが可能である。また、特定調停は裁判所が選任した特定調停委員会が手続を進めるので、手続の公正性や透明性が確保されている。さらに、労働債権を除き広く民事執行手続の停止が認められるため、事業継続に必要な重要な資産に対する強制執行を停止しつつ調停を進めることができる。そして、特定調停の中で債権者が債権放棄を行う場合、税法上も合理的な再建計画に基づくものと判断され、損金算入が認められる可能性が高いため、債権者も債務の減免等に応じやすい。したがって、債権者との個別協議による私的整理を行う場合、特定調停を利用することは、非常に有効な手段といえる。
しかし、特定調停は、各債権者が債務の減免等に納得して債務者との合意に至らなければ、その債権者との調停手続は不調で終了するので、債務の減免等に強く反対している債権者に対しては、調停手続の対象としても無意味である。また、多数の債権者がいる場合には、特定調停を利用することは困難である。そこで、このように特定調停を利用しても話し合いでの解決が不可能な場合には、他の手続を選択すべきである。
2 私的整理ガイドラインにより進める方法 「私的整理に関するガイドライン」(以下「私的整理ガイドライン」という。)は、債務者と多数の債権者との間に公正かつ公平な私的整理を円滑に成立させるためにとりまとめられた指針をいう。
私的整理は、もともと法律上定められた手続があるわけではないから、その進め方についても特に決まったものはない。そのため、柔軟に運用することが可能な反面、従うべき準則が明確でなく、かえって合意に至りにくいということがあった。こうした点を踏まえ、平成13年6月、全国銀行協会や日本経団連、学識経験者等が中心となった「私的整理ガイドライン研究会」が発足し、協議を重ねた結果、「私的整理ガイドライン」として策定されたものが平成13年9月に採択された。私的整理ガイドラインは、その後、平成16年度の税制改正を受けた改正を経て現在に至っている。
私的整理ガイドラインによる手続は、複数の金融債権者からの借入のある債務者が、原則として商取引債権者に負担を求めることなく、金融債務に関する条件変更や免除といった支援要請を含む事業再生計画を策定し、債務者がメインバンクとの連名で対象債権者に一時停止通知を発して事業再生計画を共同提案するという点に特徴がある。
しかし、債務者がメインバンクと共同で事業再生を行う手続であるため、大半の事例において、金融債権者全員がプロラタでの負担ではなく、メインバンクにより多くの負担を負わせるメイン寄せが行われている。そのため、メイン銀行が私的整理ガイドラインを利用して再建することに消極的であり、あまり利用されていない。
3 事業再生ADR 事業再生ADR(特定認証紛争手続)とは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき法務大臣による認証を受け、かつ「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(以下「産活法」という。)に基づいて経済産業大臣による認定を受けた民間機関である特定認証ADRが実施する、私的整理に関する協議の仲介手続をいう。現在、事業再生実務家協会が、特定認証ADR事業者として活動している。
事業再生ADRは、私的整理ガイドラインと同様、複数の金融債権者から借入のある債務者が、商取引債権者に負担を求めることなく、金融債務に関する条件変更や免除といった支援要請を含む事業再生計画を策定することが可能である。また、中立的な第三者である特定認証ADR事業者及びその選定する手続実施者の指導・助言を受けて手続が進められるため、手続の公平性が担保されており、私的整理ガイドラインで問題とされていたメイン寄せのおそれもない。さらに、一定の条件をもとに私的整理手続中に行われたつなぎ融資(プレDIPファイナンス)を既存の債務よりも優先的に取り扱うことが認められているため、つなぎ融資が受けられやすくなっている。加えて、事業再生ADR手続が不調に終わり、特定調停又は法的整理に移行する場合には、裁判所がADRでの調整を引き継ぐため、迅速な手続が可能となる。
このようなメリットがある事業再生ADRではあるが、デュー・ディリジェンス等の調査費用、再建計画案その他の書類の作成費用などが高額な上、特定認証ADR機関への申請費用も高額なため、十分な資金がなければ利用することはできないことから、資金繰りの厳しい中小企業には利用しにくい手続であると思われる。実際、公表されている事案をみると、手続を利用した企業の多くは、十分な資金を持った上場企業のようである。
4 RCC企業再生スキーム RCCは、もともと住宅金融専門会社の処理のために設立された株式会社住宅金融債権管理機構と破綻金融機関の不良債権等の処理のために設立された株式会社整理回収銀行が合併して誕生した株式会社である。
RCCは、平成10年に成立した金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融再生法」という。)53条に基づいて、預金保険機構の委託を受けて、不良債権の買取業務を行うこととなったが、平成13年の同法の改正により、預金保険機構との協定の内容として、買い取った不良債権の債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めることを定めるべきものとされた。この結果、RCCは、企業の再生をその任務の一つとすることになった。
その後も政府からRCCによる企業再生機能の活用が推進され、これを受けてRCCは、自らが債権者ではない場合も含めて企業再生に携わることとなり、その際の一般的な準則を「RCC企業再生スキーム」として公表した。
RCC企業再生スキームは、公的な性格を有する主体が公表した準則に従い、中立的な立場から調整するものであることから、債権者からの納得が得られやすく、合意形成が容易になることが期待できる。また、RCC企業再生スキームに基づいて策定された再生計画により債権放棄が行われた場合には、原則として法人税基本通達9-4-2の合理的な再建計画に基づく債権放棄であると扱われ、債権者は損金算入することができるので、債権放棄に応じやすくなっている。さらに、債務者としても、資産評価損の計上の特例が認められるので、債務免除益課税が回避しやすくなっている。
しかし、RCC企業再生スキームは、RCCが主要債権者である場合、または主要債権者の一人である金融機関がRCCに手続を委託する場合における再生可能な債務者の私的再生を対象とするので、RCCや主要債権者である金融機関に利用する意思がないと利用できない。また、RCCに対する手続費用や、デュー・ディリジェンス等の調査費用、再建計画案その他の書類の作成費用などの費用を負担しなければならないので、資金的に余裕がないと利用しづらい面がある。
5 中小企業再生支援協議会スキーム 中小企業再生支援協議会とは、平成11年に制定された産活法41条に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関に設置された再生支援組織である。中小企業再生支援協議会は、平成15年2月から全国47都道府県に順次設置され、現在も全国47都道府県に1か所ずつ設置されている。中小企業再生支援協議会による再生支援事業は、当初、平成20年3月31日を期限とする時限立法であったが、平成19年の産活法改正により、平成28年3月31日までその期間が延長された。
中小企業再生支援協議会スキームは、大きく窓口対応(第1次対応)と再生計画策定支援(第2次対応)の2つの対応に分けられる。
窓口相談では、常駐専門家である統括責任者(プロジェクトマネージャー)又は統括責任者補佐(サブマネージャー)が債務者の持参した資料を分析し、ヒアリングや面談によって、債務者の経営状況や財務状況の把握を行い、経営課題の洗い出しを行う。窓口相談の結果として、課題の解決に向けた助言を行い、場合によっては支援施策・支援機関や弁護士を紹介することもある。事業性が認められるなど一定の要件を満たす場合には、再生計画策定支援に移行する。
再生計画策定支援では、常駐専門家である統括責任者、統括責任者補佐、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の外部専門家によって構成される個別支援チームが財務デュー・ディリジェンス、事業デュー・ディリジェンスを実施し、デュー・ディリジェンスの結果把握された債務者の財務及び事業の状況に基づいて、債務者による再生計画案の作成を支援する。個別支援チームは、再生計画案の作成過程で、債務者と主要債権者との会議を適宜開催し、デュー・ディリジェンスの結果の報告や再生計画案の内容についての検討を行い、債権者・債務者間での合意形成を図っていく。
中小企業再生支援協議会は、全国47都道府県に1か所ずつあるので、事業再生ADRやRCCスキームと比べ、地方にある企業にとっては、相談、打ち合わせが容易である。また、相談料等の利用料がかからず、財務・事業デュー・ディリジェンス費用についても国から一定の補助があるので、再生に要する費用負担が軽減される。さらに、信用保証協会や中小企業整備基盤機構の保証を利用できるため、プレDIPファイナンスを受けられやすく、私的整理手続中の資金繰りの安定を図ることが可能となる。そして、中小企業再生支援協議会は、公正中立な立場から債権者などの利害関係人の調整を図るので、債権者からの同意も得られやすい。
しかし、中小企業再生支援協議会の調整による手続は、対象が中小企業者(脚注3)に限定されているため、上場企業等の大企業や医療法人、学校法人は利用できない。また、地方の中小企業再生支援協議会によっては、その債権者調整力が十分ではないとの指摘もなされている。
6 企業再生支援機構スキーム 株式会社企業再生支援機構(以下「企業再生支援機構」という。)は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅・中小企業その他の事業者の事業再生を支援することなどを目的として平成21年10月14日に株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された官民出資の企業である。
当初、設立から5年間で業務を完了するよう努める時限的な組織であり、設立から2年までに支援先を決定することとされていたが、平成24年3月31日に法改正がなされ、業務は平成28年3月31日までに完了するよう努めるものとされ、支援決定については、平成25年3月31日までに行うものとされた。
企業再生支援機構による支援は、対象事業者に対する融資を実行することができること、非メイン金融機関から時価で債権買取等をすることも可能なこと、対象事業者に対して出資することができる、といった特徴があり、事業再生に対する支援は、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会の調整手続よりも積極的である。
デュー・ディリジェンスの費用等は、対象事業者が負担するのが原則であるが、支援決定に至った場合には、事業者の規模に応じて一部機構が負担し、支援決定に至らなかった場合には、全額支援機構が負担することとなっている。
この企業再生支援機構による事業再生手続は、申込み後、支援決定までに時間がかかるといった問題点が一部で指摘されている。
Ⅳ 私的整理における財務リストラの手法
私的整理における財務リストラの手法としては、リスケジュール、債権放棄、デッド・エクイティ・スワップ(DES)、デッド・デッド・スワップ(DDS)、事業譲渡、会社分割等が考えられる。
1 リスケジュール リスケジュールとは、金融機関等からの借入金の返済条件を変更して、分割返済額の減額や元本返済猶予(その間、利息のみ支払う)期間を置くなどにより、債務者のキャッシュ・フローを改善させるものである。
リスケジュールは、単に返済条件を変更するものであり、債権そのものを減額するものではないので、金融機関としても応じやすい。しかし、元本返済猶予期間内にキャッシュ・フローを改善できる見込みがなく、改善後のフリー・キャッシュ・フローで合理的期間内(通常、10年程度)に借入金を返済することができないようであれば、リスケジュールによる事業再生は困難であり、単に、問題を先送りしただけとなる。したがって、リスケジュールによる事業再生を図る場合、キャッシュ・フローの改善策及び今後見込まれるフリー・キャッシュ・フローを検討し、今後のフリー・キャッシュ・フローで合理的期間内に借入金を返済できる見込みが立たないようであれば、より抜本的な他の手法を検討する必要がある。
2 債務免除 債務免除とは、債権者が債務者に対して債権を免除するとの意思表示をすることにより債務を消滅させ、もって債務者のキャッシュ・フロー及び財務内容を改善させるという再生手法である。
債務者とすれば、債務免除の対象となった債権の元本及び利息の返済の必要がなくなり、負担が大幅に軽減されるので、債務免除は抜本的な再生手法といえる。しかし、債権者にとっては、負担が大きいことから、私的整理では債務免除を得ることは容易ではない。そのため、債務者としては、十分な情報開示をするとともに、債務免除の合理性について、十分説明する必要がある。
また、債務免除を受けると債務免除益が生じることになるため、繰越欠損金等が十分でない等の理由により損金算入できる金額が少ない場合には、課税が生ずることになることになるので、注意が必要である。
3 DES DESとは、債権者が債務者に対して有する債権を、債務者の株式と交換することをいう。
会社法ではDESについての規定はないため、一般的には、債権者が債務者に対する債権を債務者に現物出資し、債権の現物出資の対価として株式を取得し、現物出資の対象となった債権自体は、債務者と債権者が一致することから混同により消滅するので、事実上、債務が株式に代わるという手法がとられる。
DESを行うと、債権者が株主になることから経営の安定化が図られないことと、銀行は企業の議決権の5%までしか株式を持つことができないことから、DESにより発行する株式は普通株式ではなく無議決権株式であることが多い。
DESは、債務者にとっては、債務を圧縮するというメリットがあり、債権者としても、将来企業の再建が成功した場合にはキャピタルゲインを期待できるというメリットがある。
しかし、DESは債権の現物出資という手続をとるため、検査役の検査(会社法33条4項)を受けなければならず、手続が煩雑であることや、非上場株式の場合、キャピタルゲインは期待できない等のデメリットがあることから、中小企業がこの手法を用いることは、少ないと思われる。
4 DDS DDSとは、債権者が、債務者に対して有する債権を、他の債権よりも弁済順位について劣後する債権に変更することをいう。
具体的には、債権者と債務者との間で、金融検査マニュアルを踏まえ、返済順位の劣後条項、表明・保証、コベナンツ(数値目標、財務制限条項、情報開示、モニタリング)、期限の利益喪失条項等を定めた条件変更契約を締結することとなる。
DDSを行った場合、債権が劣後化されている間は元本の返済の必要はないので、債務者はその間に資金繰りを改善することができる。また、DDSは、対象債権を他の債権よりも弁済順位について劣後する債権に変更するものであるから、実質上債務超過が解消されることとなり、債務者の信用力が増しやすくなる。さらに、DDSは、DESと異なり、債務者と債権者との間で変更契約を締結すれば済むという点で手続が容易であるし、医療法人や学校法人など株式を発行しない法人でも用いることができる。
しかし、DDSは、実質的には支払期間が延期されただけであるから、その間に資金繰りを改善することができなければ、事業再生は困難となる。
5 事業譲渡・会社分割 事業譲渡とは、株式会社が事業を取引行為として他に譲渡する行為をいい、会社分割とは、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社又は分割により設立する会社に承継させることを目的とする会社の行為をいう。なお、事業譲渡又は会社分割後、旧会社である譲渡会社・分割会社を消滅させる場合を、第二会社方式と呼ぶこともある。
事業譲渡も会社分割も、もともと事業再生の手段として規定されたものではないが、会社の収益性のある事業と不採算部門を分けて、不採算部門を旧会社に残し、収益性のある事業を切り離して他の会社に承継させることで事業再生を図ったり(事業譲渡・会社分割の場合)、逆に、不採算部門を切り離して他の会社に承継させ、旧会社に収益性のある事業を残すことで、事業再生を図ることが可能である(会社分割の場合)ことから、事業再生の一手法として広く利用されている。
事業譲渡や会社分割は、収益性のある事業部門のみを承継したいというスポンサーの意向や、債務免除をすると多額の債務免除益が発生し、繰越欠損金等の損金算入が十分できず課税が生じる場合に、これを回避することができるというメリットがある。
しかし、事業譲渡や会社分割を行うには、株主総会の特別決議による承認を要することから(会社法467条1項1号・2号)、多くの株主から反対される場合には、私的整理で事業譲渡や会社分割を行うことはできない。また、債務者の事業継続に債務者所有の不動産が必要である場合には、不動産の所有権の移転に登録免許税や不動産取得税等のコストがかかるといったデメリットもある(脚注4)。さらに、営業上必要な許認可等については承継できない可能性があるといったデメリットもある(脚注5)。
なお、事業譲渡や会社分割は、債権者保護手続を経ずに行うことが可能であるため、債権者に知れぬよう事業譲渡や会社分割を行い、収益性のある事業と不採算部門を切り分け、多額の債権を不採算部門のある会社に残すといった手法が広く行われている。
しかし、債権者の意向をまったく無視した濫用的な事業譲渡や会社分割については、かねてから批判がなされており、近時、株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると判断した最高裁判例も出ている(最高裁判所平成24年10月12日第二小法廷判決(平成22年(受)第622号))。また、平成24年9月7日に法制審議会総会で決定された「会社法制の見直しに関する要綱」でも、詐害的な会社分割等により不採算部門に残された債権者は、承継会社に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することや、各別の催告を受けずに承継会社に対する債権とされてしまった債権者は、分割会社に対し、分割時に有していた財産を限度として債務の履行を請求することが規定されている。したがって、今後は、債権者に知られないように事業譲渡や会社分割を実行して、収益性のある事業を切り離すという主張は、事業再生の手法としては採りづらくなると思われる。
Ⅴ 法的整理の種類
私的整理での事業再生が困難ということになれば、次に、法的整理での事業再生を検討することとなる。
法的整理には、再生手続と更生手続がある。再生手続は、大正11年に公布された和議法(脚注6)に代わるものとして、平成11年に公布され、平成12年4月1日から施行された民事再生法に基づく再建型の倒産手続であり、更生手続は、平成27年に成立した旧会社更生法を全面改正し、新しい法律として平成14年に公布され、平成15年4月1日から施行された会社更生法に基づく更生型の倒産手続である。民事再生法と会社更生法は、前者が一般法、後者が特別法という位置づけであるが、再生手続と更生手続の違いは、以下のとおりである。
1 適用対象 再生手続は、適用対象に限定がなく、すべての法人及び自然人を対象としているのに対し(民事再生法1条)、更生手続の適用対象は、株式会社に限定されている(会社更生法1条)。
したがって、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等株式会社以外の法人及び個人が法的整理での事業再生を行う場合には、再生手続を利用することとなる。
なお、再生手続は、手続の簡便性等から、主として中小規模の企業の再建に利用され、更生手続は大規模企業の再建に利用されることが想定されていたが、上場企業でも再生手続が利用されており、規模により手続を分けるという意味は、あまりなくなってきている。
2 管理処分権の帰属主体 再生手続は、原則として再生債務者が業務の遂行権限や財産の管理処分権限を維持した形で手続が進められるDIP(Debtor In Possession)型であるのに対し(民事再生法38条1項)、更生手続は、原則として裁判所の選任した管財人にこれらの権限を専属させる形で手続が進行する管理型である(会社更生法72条1項)。
企業の内容を把握した現経営陣が手続を進めたほうが効率よく的確に再建を進められる可能性が高いので、原則的には、再生手続を選択することが再建可能性をより高くするものといえるが、現経営陣が不正行為を行っていた場合など、債権者から最低限度の信頼も得られないような場合には、裁判所に選任された管財人という中立・公平な第三者の下で再建を行っていく更生手続で事業再建を進めた方が再建可能性は高くなる。
もっとも、更生手続においても、更正会社の現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がない場合には、現経営陣の中から管財人を選任することができるとされており(会社更生法67条3項)、実質的にはDIP型の手続として運用することが可能である。近時は、DIP型の更生手続も利用され、運用として定着しつつある。
また、再生手続においても、再生債務者が法人の場合には、再生債務者による財産の管理処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認められるときには、管理命令を発令して管財人を選任することができるものとされており(民事再生法64条)、近時、管理型で再生手続が進められる事例も出てきている。
3 担保権や租税債権等の権利行使に対する制約 再生手続においては、抵当権等の担保権を有する債権は別除権として、租税債権(国税、地方税、社会保険料等)や労働債権等の優先権のある債権は一般優先債権として、再生手続外での権利行使が可能である(民事再生法53条、122条)。
これに対し、更生手続では、担保権を有する債権及び租税債権等の優先権のある債権のいずれについても更生手続に取り込まれ、手続外での権利行使はできず(会社更生法2条10項、47条1項、50条1項、135条1項)、更生計画に従った弁済を受けることになる(会社更生法167条1項1号、168条、169条)。
したがって、強硬な担保権者がいる場合には、再生手続よりも更生手続を利用した方が適切な場合が多い。
4 組織再編 再生手続では、事業譲渡については、株主総会の特別決議による承認に代わる代替許可の制度が設けられ(民事再生法43条1項)、自己株式の取得、株式の併合、資本金の額の減少、授権資本に関する定款の変更についても再生計画によって行うことができるとされているが(同法154条3項、183条)、新株発行(増資)を行うには、再生計画の定めだけでは足りず、取締役会の決議等が必要であるとされており(同法154条4項、183条の2)、事業譲渡以外の組織上の行為を行う場合にも、会社法の規定に従って株主総会の決議その他会社の機関決定を経る必要がある。
これに対し、更生手続においては、再生手続でできることに加え、新株発行(増資)や社債の発行、更には合併、会社分割、株式交換、株式移転等のような会社組織の再編に亘る行為についても会社法の規定によることなく更生計画によって行うことが可能である(会社更生法167条2項、203条1項、210条以下)。
また、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を承継させることができるうえ(会社更生法231条)、更生会社から新会社へ不動産・船舶を承継させる場合の移転登記の登録免許税が大幅に軽減され(会社更生法264条7項・8項)、更生会社から新会社への不動産を移転する場合の不動産取得税が非課税扱いとなる(地方税法73条の7第2号の4)。
このように、更生手続では、本来的に組織再編行為が予定されているため、組織再編行為を容易にするための規定が多く設けられている。
5 計画案の可決要件 再生手続では、再生計画案の可決のためには、議決権者の議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意に加え、債権者集会に出席し又は書面投票をした議決権者の過半数の同意(いわゆる頭数要件)が必要である(民事再生法172条の3第1項)。
他方、更生手続においては、更生計画案の可決のためには、①更生債権については、議決権の2分の1を超える議決権を有する者の同意、②更生担保権については、期限の猶予を定める場合には議決権総額の3分の2以上、減免その他期限の猶予以外の方法による権利変更を定める場合には議決権総額の4分の3以上、事業全部の廃止を内容とする場合には議決権総額の10分の9以上の同意、③株主については、議決権総数の過半数の同意(ただし、更生会社が債務超過である場合には、株主は議決権を有しない)が必要である(会社更生法196条5項)が、再生手続と異なり頭数要件は必要とされていない。したがって、大口の債権者は再生計画案に賛成しているが、零細な債権者が再生計画案に反対しており、その数が多い場合には、更生手続を選択することになろう。
6 手続の終了 再生手続においては、再生計画認可決定の確定後3年が経過した時は、再生計画の履行が未了であったとしても、再生手続終結の決定をしなければならない(民事再生法188条2項)。
これに対し、更生手続の場合には、このような期間制限はなく、少なくとも更生計画の遂行が確実であると認められるまでは、更生手続終結の決定をすることはできず(会社更生法239条)、裁判所による監督が継続する。再生手続と比較すると、更生手続では、計画遂行の確実性を期すためにより厳格な監督体制が採られている。
Ⅵ 法的整理における再生計画(更生計画)
1 法的整理における財務リストラの手法 法的整理における財務リストラは、一般的には再生計画又は更生計画における権利変更という形で行われる。
法的整理では、全債権者の合意ではなく、多数決原理が採られるために、債権者調整が私的整理に比べ容易であることと、通常、財務状態が大きく毀損していることが多いことから、その財務リストラのほとんどが債権放棄であり、リスケジュール、DDS、DESといった手法はとられない(脚注7)。
しかし、平成22年5月に東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てをし、平成23年2月に手続を終結した株式会社プロパストの再生計画では、上場を維持するために、一部の債権についてDESが行われている。法的整理でも、事案に応じて柔軟に財務リストラの手法を検討することが重要である。
2 民事再生・会社更生とM&A 再生手続又は更生手続を行った株式会社の多くは、信用を維持するため、手続中の資金援助を受けるため、弁済原資を得て債権者に対する早期弁済をするため、株主責任・経営者責任を果たすためにスポンサーからの支援を受けている。スポンサーからの支援を受ける場合、通常、M&Aが行われるが、民事再生法及び会社更生法は、M&Aが行いやすいよう、会社法の規定を一部修正している。
再生手続及び更生手続で通常行われるM&Aの手法としては、①増減資スキーム、②事業譲渡、③会社分割、の3つが挙げられる。
そこで、以下、上記3つの手法について説明する。
(1)増減資スキーム 増減資スキームとは、再生会社・更生会社が一定の減資をすると同時に株式を消却し、スポンサー企業に第三者割当増資を行う手法である。
再生手続の場合、再生会社が債務超過である場合には、会社法の規定による資本減少の手続(会社法447条以下)、株式取得の手続(会社法156条等)によらずに、あらかじめ裁判所の許可を得た上で、再生計画において資本の減少に関する条項、株式の取得に関する条項を定めることで(民事再生法166条1項・154条3項)、会社法所定の株主総会の特別決議や債権者保護手続が不要となる(民事再生法183条)。
更生手続の場合、資本の再構成を本来的に予定しているため、裁判所の許可を得なくとも、更生計画において資本の減少に関する条項(会社更生法174条3号)、株式の取得に関する条項(会社更生法174条の2)、株式の消却に関する条項(会社更生法174条1号)を定めることで、会社法所定の株主総会の特別決議や債権者保護手続が不要となる(会社更生法212条、214条、215条)。
増減資スキームは、承継する資産・負債、契約関係の取捨選択や資産等を個別移転させる手続が不要であり、手続が簡便であること、また、許認可の移転手続や再取得の必要がないこと、資産の移転に伴うコスト(不動産取得税や登録免許税など)が発生しないといったメリットがある。
しかし、多額の債務免除益が発生した場合、それを打ち消すだけの資産評価損や繰越欠損金がない場合には、債務免除益課税の問題が生じるし、スポンサーにとっては不採算事業まで承継する可能性が残るという問題もある。
(2)事業譲渡 事業譲渡とは、株式会社が事業を取引行為として他に譲渡する行為をいう。
再生手続では、再生計画で事業譲渡を行うこともできるが、再生手続開始決定後であれば、再生計画案提出前までに、裁判所の許可を得て事業の全部または重要な一部を譲渡することができる(民事再生法42条1項)。
再生手続において事業譲渡をする場合にも、原則として株主総会の特別決議による承認が必要となるが(会社法467条1項1号・2号)、再生会社が債務超過である場合には、裁判所は、債務者の申立により、株主総会の特別決議による承認に代わる許可を与えることができる(民事再生法43条1項)。再生会社の多くは債務超過であると思われるから、事実上、株主総会の特別決議による承認は不要となる。
更生手続でも、事業譲渡は更生計画によって行うことを原則としつつも(会社更生法46条1項本文)、開始決定後更生計画案の付議決定がなされるまでの間であれば、裁判所の許可を得て、事業の全部または重要な一部の譲渡を行うことができる(同条2項)。更生手続で事業譲渡する場合には、株主総会の特別決議による承認は不要であるが、更生会社が債務超過でなく、かつ、譲渡先が更生会社の特別支配会社(会社法468条1項)でない場合には、事業譲渡を行うに当たり、あらかじめ所定の株主保護手続を採らなければならない(会社更生法46条4項ないし6項)。
事業譲渡は、再生計画案・更生計画案作成前に実行することが可能であり、株主総会の特別決議による承認も不要なので、迅速に行うことができる。また、スポンサーにとっては、必要な事業だけを譲り受けることができる上、偶発債務や簿外債務を承継するリスクを最小化できるというメリットがある。さらに、清算所得課税制度は廃止されたものの、残余財産がないと見込まれるときには、法人税法59条3項において期限切れ欠損金の利用が認められるので、債務免除益と同額の損金算入が可能となるから、事業譲渡を行い、その後再生計画・更生計画により債務免除の権利変更がなされた譲渡会社を清算させれば、債務免除益課税の問題も生じない。
しかし、事業譲渡は、資産の移転コスト(不動産取得税や登録免許税等)が発生すること(脚注8)、個々の資産の譲渡ごとに対抗要件を具備することが必要であること、契約上の地位の譲渡の場合、相手方の承諾を得ることが必要であること、従業員を移籍させる場合、個別の同意が必要であること、許認可を承継させることが困難であること(脚注9)、といったデメリットがある。
(3)会社分割 会社分割とは、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社又は分割により設立する会社に承継させることを目的とする会社の行為をいう。
会社分割については、民事再生法上、特別の規定は設けられていないため、再生手続と絡めて会社分割を行う場合は、再生会社において、会社法に定める手続を履践する必要がある。
更生手続で会社分割を行う場合には、会社法所定の手続を履践することなく、更生手続の中で会社分割を行うことができる。
会社分割は、スポンサーにとって必要な事業だけを譲り受けることができる上、包括承継なので、契約の相手方の個別の同意を要することなく契約関係を移転することが可能であり、事務手続を大幅に簡略化できるので、承継すべき契約関係が多数あるときに多く利用される。また、会社分割では、権利の承継・移転についての登録免許税等が軽減されており、不動産取得税も一定の要件を満たした場合には、非課税となる。
しかし、会社分割の場合、行政上の許認可等について、主務大臣の許認可が必要なものがあり、当然に承継することはできない。また、再生手続では、会社分割を行う場合、会社法上の手続を履銭しなければならず、労働者保護手続、株主保護手続、債権者保護手続きを行うことが必要である。
鈴木規央 すずき のりお
シティユーワ法律事務所 弁護士・公認会計士。太田昭和監査法人(新日本有限責任監査法人)、パートナーズ国際会計事務所を経て、2006年弁護士登録し、同年からシティユーワ法律事務所。日本公認会計士協会租税調査会国際租税専門部会専門委員、日本公認会計士協会東京会税務第二委員会委員。著作として、『公認会計士による税務判例の分析と実務対応』(共著、日本公認会計士協会東京会編、日本公認会計士協会出版局、2012年)、『問答別 企業提携の法律実務』(共著、新日本法規)など。
脚注
1 なお、法的整理といった場合、一般的には清算型の倒産手続である破産手続や特別清算手続も含まれるが、本稿では事業再生について論じるものであるから、ここでは清算型の法的整理は含めないものとする。
2 「裁判外事業再生」実務研究会編「裁判外事業再生の実務」(商事法務)28頁。
3 「中小企業者」とは、①資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を営むもの、②資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの、③資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの、④資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの、⑤資本金の額又は出資の総額がその業種毎に政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの、⑥企業組合、⑦協業組合、⑧事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの、をいう(産活法2条17項)。
4 なお、産活法に基づき、事業継続が困難であるが収益性のある事業を有している中小企業に対して第二会社方式による中小企業承継事業再生計画の認定を受けることができれば、登録免許税、不動産取得税の軽減等の税負担の軽減措置等を受けることができる(租税特別措置法80条、地方税法附則11条45号)。
5 なお、産活法に基づき、事業継続が困難であるが収益性のある事業を有している中小企業に対して第二会社方式による中小企業承継事業再生計画の認定を受けることができれば、特定の種類の営業上必要な許認可等を承継することができる(産活法39条の4)。また、会社分割では、保険業、登録電機工事業者等のように届出等しなくても承継できる許認可、飲食店業、液化石油ガス販売業者、アルコール製造業者等のように会社分割の届出だけで承継できる許認可、ホテル、旅館業、一般貨物自動車運送事業者等のように承継に所轄官庁の承認が必要な許認可もある。
6 和議法は、我が国で最初の再建型手続法として、オーストリア和議法を模範として制定されたものであったが、開始原因が狭すぎること、担保権の行使が制約されないこと、和議の可決要件が厳しいこと、和議の履行が十分に確保できないことなどから再建型手続としてその機能を十分に発揮し得なかった。
7 会社更生法の理念としては、DESを利用した再建手法が用いられることが想定されているようであるが(山本・中西・笠井・沖野・水元「倒産法概説(第2版)」(弘文堂)32頁)、実際にDESが利用されている事例は少ない。
8 ただし、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を承継させることができる(会社更生法231条)。
9 ただし、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、更生会社から新会社へ不動産・船舶を承継させる場合の移転登記の登録免許税が大幅に軽減され(会社更生法264条7項・8項)、更生会社から新会社への不動産を移転する場合の不動産取得税が非課税扱いとなる(地方税法73条の7第2号の4)。
事業再生実務の法務
-事業再建の手続と財務リストラの手法の選択のポイント-
弁護士・公認会計士 鈴木規央
Ⅰ 序 論
平成21年11月30日に成立し、12月4日に施行された中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」という。)が、平成25年3月31日をもって、いよいよ終了する。
この中小企業金融円滑化法は、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、金融機関はできる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを定めているため、多くの中小企業が金融機関に対し、条件変更を申し入れ、条件変更に応じてもらった企業は多いと聞く。しかし、中小企業円滑化法終了後は、このような条件変更を申し入れても、金融機関が容易には応じないということが想定され、今まで問題を先送りにしてきた中小企業の多くが、倒産せざるを得ないのではないかということが危惧されている。
かかる事態を回避すべく、現在、官民一体型ファンドを立ち上げ、救済しようという動きがあるが、すべての企業がファンドによる救済を得られるとは到底考えられず、負債を抱えた企業は、自力で事業再建の手法を考える必要がある。それには、どのような事業再建の手続や財務リストラの手法があるのか、ある程度知っておくことが有益である。
そこで、本稿では、事業再建の手続について説明するとともに、財務リストラの手法について言及する。
Ⅱ 私的整理と法的整理
事業再建の手続は、大きく分けて、私的整理と法的整理の二種類がある。私的整理とは、裁判所が関与しない再建手続であり、法的整理(脚注1)とは裁判所が関与する再建手続である。
私的整理は、再建手続に入ったことについて公表されないため、「倒産」のレッテルが貼られることを回避できるといったメリットや、取引業者に対する債権を債務整理の対象としないこともできるので、取引業者との関係を円満に保つことができるというメリットがある。しかし、私的整理は、債務処理について対象債権者全員の同意が必要となるため、合意形成が困難であるというデメリットがある。
これに対し、法的整理は、多数決原理により再生計画案が可決され、裁判所の認可決定が得られれば、債権者全員に対して効力が及ぶという強制的効果があるため、債権者調整が比較的容易であるというメリットがある。しかし、法的整理は、「倒産」のレッテルが貼られ、事業価値が毀損するおそれが高いというデメリットや、取引先の債権も整理の対象となるので、取引業者との関係が悪化する可能性が高いというデメリットがある。
債権者からの同意が得られないなどの理由により私的整理での事業再建が困難な場合、法的整理に移行し、再建手続を進めることは可能である。例えば、日本航空は、平成21年10月29日、国土交通大臣直轄のJAL再生タスクフォースによる再建計画を策定し、同年11月13日、事業再生ADRを申請したが金融機関からの同意が得られず、平成22年1月19日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、同日、開始決定を受けた。また、ウィルコムも平成21年9月24日、事業再生ADRの申請をしたが、平成22年2月18日、会社更生手続開始の申立てをした。最近では、三光汽船が平成24年3月9日、事業再生ADRの申請をしたが、担保権者による権利行使が止まらず、同年7月2日、会社更生手続開始の申立てをした。このように、私的整理での事業再建が困難な場合に法的整理に移行し、再建手続を進める例は多い。
これに対し、法的整理での事業再建が困難となった場合、他の法的整理手続に移行することはできるが、私的整理手続に移行することはできない。法的整理で事業再建が困難となり、他の法的整理での事業再建もできない場合には、破産手続に移行する。そのため、通常は、私的整理手続での事業再建の可能性を先に探るのが、事業再建の専門家の思考である。
Ⅲ 私的整理の種類
私的整理は、債権者との個別協議により進める方法、私的整理ガイドラインに沿って進める方法、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会の調整を得て進める方法(以下「中小企業再生支援協議会スキーム」という。)、株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)の調整を得て進める方法(以下「RCC企業再生スキーム」という。)、企業再生支援機構の支援を得て進める方法(以下「企業再生支援機構スキーム」という。)等がある。
債権者との個別協議による方法及び私的整理ガイドラインによる方法は関係当事者間で進める私的整理であるが、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会スキーム、RCCスキーム、企業再生支援機構スキームは、第三者が介入して進める私的整理である。
1 債権者との個別協議により進める方法 私的整理のうち、債権者との個別協議により進める私的整理は、最も基本的な方法である。
しかし、債権者との個別協議により進める私的整理は、債務整理をしなければならない事態を招いたのは他ならぬ債務者であることから、債務者の説明では債権者から信用を得られにくいこと、対象となる債権者が複数存在する場合には、公平性や透明性の確保が強く求められるところ、こうした公平性や透明性を確保することが困難であること等から、債権者からの同意が得られにくい。
そこで、債権者との個別協議による私的整理を行う場合、特定調停を利用することが考えられる。特定調停は、個人・法人を問わず、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資するため、裁判所の主催する調停手続により、債権者と債務者との間で、債務の減免、弁済期限の猶予、担保権の変更等を合意する手続である(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1条)。
特定調停は、多重債務者個人が金融債権者を相手方として、利息制限法に基づき計算し直した借入金残金をリスケジュールして、毎月分割弁済することを求める場合、また、中堅ゼネコン、都道府県の住宅供給公社、第三セクター等の企業等が金融債権者等を相手方として申し立てる場合に多く利用されている(脚注2)。
特定調停は、非公開手続であることから、債務者は調停の相手方とする債権者を選択でき、事実上秘密裏に手続を進めることが可能である。また、特定調停は裁判所が選任した特定調停委員会が手続を進めるので、手続の公正性や透明性が確保されている。さらに、労働債権を除き広く民事執行手続の停止が認められるため、事業継続に必要な重要な資産に対する強制執行を停止しつつ調停を進めることができる。そして、特定調停の中で債権者が債権放棄を行う場合、税法上も合理的な再建計画に基づくものと判断され、損金算入が認められる可能性が高いため、債権者も債務の減免等に応じやすい。したがって、債権者との個別協議による私的整理を行う場合、特定調停を利用することは、非常に有効な手段といえる。
しかし、特定調停は、各債権者が債務の減免等に納得して債務者との合意に至らなければ、その債権者との調停手続は不調で終了するので、債務の減免等に強く反対している債権者に対しては、調停手続の対象としても無意味である。また、多数の債権者がいる場合には、特定調停を利用することは困難である。そこで、このように特定調停を利用しても話し合いでの解決が不可能な場合には、他の手続を選択すべきである。
2 私的整理ガイドラインにより進める方法 「私的整理に関するガイドライン」(以下「私的整理ガイドライン」という。)は、債務者と多数の債権者との間に公正かつ公平な私的整理を円滑に成立させるためにとりまとめられた指針をいう。
私的整理は、もともと法律上定められた手続があるわけではないから、その進め方についても特に決まったものはない。そのため、柔軟に運用することが可能な反面、従うべき準則が明確でなく、かえって合意に至りにくいということがあった。こうした点を踏まえ、平成13年6月、全国銀行協会や日本経団連、学識経験者等が中心となった「私的整理ガイドライン研究会」が発足し、協議を重ねた結果、「私的整理ガイドライン」として策定されたものが平成13年9月に採択された。私的整理ガイドラインは、その後、平成16年度の税制改正を受けた改正を経て現在に至っている。
私的整理ガイドラインによる手続は、複数の金融債権者からの借入のある債務者が、原則として商取引債権者に負担を求めることなく、金融債務に関する条件変更や免除といった支援要請を含む事業再生計画を策定し、債務者がメインバンクとの連名で対象債権者に一時停止通知を発して事業再生計画を共同提案するという点に特徴がある。
しかし、債務者がメインバンクと共同で事業再生を行う手続であるため、大半の事例において、金融債権者全員がプロラタでの負担ではなく、メインバンクにより多くの負担を負わせるメイン寄せが行われている。そのため、メイン銀行が私的整理ガイドラインを利用して再建することに消極的であり、あまり利用されていない。
3 事業再生ADR 事業再生ADR(特定認証紛争手続)とは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき法務大臣による認証を受け、かつ「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(以下「産活法」という。)に基づいて経済産業大臣による認定を受けた民間機関である特定認証ADRが実施する、私的整理に関する協議の仲介手続をいう。現在、事業再生実務家協会が、特定認証ADR事業者として活動している。
事業再生ADRは、私的整理ガイドラインと同様、複数の金融債権者から借入のある債務者が、商取引債権者に負担を求めることなく、金融債務に関する条件変更や免除といった支援要請を含む事業再生計画を策定することが可能である。また、中立的な第三者である特定認証ADR事業者及びその選定する手続実施者の指導・助言を受けて手続が進められるため、手続の公平性が担保されており、私的整理ガイドラインで問題とされていたメイン寄せのおそれもない。さらに、一定の条件をもとに私的整理手続中に行われたつなぎ融資(プレDIPファイナンス)を既存の債務よりも優先的に取り扱うことが認められているため、つなぎ融資が受けられやすくなっている。加えて、事業再生ADR手続が不調に終わり、特定調停又は法的整理に移行する場合には、裁判所がADRでの調整を引き継ぐため、迅速な手続が可能となる。
このようなメリットがある事業再生ADRではあるが、デュー・ディリジェンス等の調査費用、再建計画案その他の書類の作成費用などが高額な上、特定認証ADR機関への申請費用も高額なため、十分な資金がなければ利用することはできないことから、資金繰りの厳しい中小企業には利用しにくい手続であると思われる。実際、公表されている事案をみると、手続を利用した企業の多くは、十分な資金を持った上場企業のようである。
4 RCC企業再生スキーム RCCは、もともと住宅金融専門会社の処理のために設立された株式会社住宅金融債権管理機構と破綻金融機関の不良債権等の処理のために設立された株式会社整理回収銀行が合併して誕生した株式会社である。
RCCは、平成10年に成立した金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融再生法」という。)53条に基づいて、預金保険機構の委託を受けて、不良債権の買取業務を行うこととなったが、平成13年の同法の改正により、預金保険機構との協定の内容として、買い取った不良債権の債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めることを定めるべきものとされた。この結果、RCCは、企業の再生をその任務の一つとすることになった。
その後も政府からRCCによる企業再生機能の活用が推進され、これを受けてRCCは、自らが債権者ではない場合も含めて企業再生に携わることとなり、その際の一般的な準則を「RCC企業再生スキーム」として公表した。
RCC企業再生スキームは、公的な性格を有する主体が公表した準則に従い、中立的な立場から調整するものであることから、債権者からの納得が得られやすく、合意形成が容易になることが期待できる。また、RCC企業再生スキームに基づいて策定された再生計画により債権放棄が行われた場合には、原則として法人税基本通達9-4-2の合理的な再建計画に基づく債権放棄であると扱われ、債権者は損金算入することができるので、債権放棄に応じやすくなっている。さらに、債務者としても、資産評価損の計上の特例が認められるので、債務免除益課税が回避しやすくなっている。
しかし、RCC企業再生スキームは、RCCが主要債権者である場合、または主要債権者の一人である金融機関がRCCに手続を委託する場合における再生可能な債務者の私的再生を対象とするので、RCCや主要債権者である金融機関に利用する意思がないと利用できない。また、RCCに対する手続費用や、デュー・ディリジェンス等の調査費用、再建計画案その他の書類の作成費用などの費用を負担しなければならないので、資金的に余裕がないと利用しづらい面がある。
5 中小企業再生支援協議会スキーム 中小企業再生支援協議会とは、平成11年に制定された産活法41条に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関に設置された再生支援組織である。中小企業再生支援協議会は、平成15年2月から全国47都道府県に順次設置され、現在も全国47都道府県に1か所ずつ設置されている。中小企業再生支援協議会による再生支援事業は、当初、平成20年3月31日を期限とする時限立法であったが、平成19年の産活法改正により、平成28年3月31日までその期間が延長された。
中小企業再生支援協議会スキームは、大きく窓口対応(第1次対応)と再生計画策定支援(第2次対応)の2つの対応に分けられる。
窓口相談では、常駐専門家である統括責任者(プロジェクトマネージャー)又は統括責任者補佐(サブマネージャー)が債務者の持参した資料を分析し、ヒアリングや面談によって、債務者の経営状況や財務状況の把握を行い、経営課題の洗い出しを行う。窓口相談の結果として、課題の解決に向けた助言を行い、場合によっては支援施策・支援機関や弁護士を紹介することもある。事業性が認められるなど一定の要件を満たす場合には、再生計画策定支援に移行する。
再生計画策定支援では、常駐専門家である統括責任者、統括責任者補佐、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の外部専門家によって構成される個別支援チームが財務デュー・ディリジェンス、事業デュー・ディリジェンスを実施し、デュー・ディリジェンスの結果把握された債務者の財務及び事業の状況に基づいて、債務者による再生計画案の作成を支援する。個別支援チームは、再生計画案の作成過程で、債務者と主要債権者との会議を適宜開催し、デュー・ディリジェンスの結果の報告や再生計画案の内容についての検討を行い、債権者・債務者間での合意形成を図っていく。
中小企業再生支援協議会は、全国47都道府県に1か所ずつあるので、事業再生ADRやRCCスキームと比べ、地方にある企業にとっては、相談、打ち合わせが容易である。また、相談料等の利用料がかからず、財務・事業デュー・ディリジェンス費用についても国から一定の補助があるので、再生に要する費用負担が軽減される。さらに、信用保証協会や中小企業整備基盤機構の保証を利用できるため、プレDIPファイナンスを受けられやすく、私的整理手続中の資金繰りの安定を図ることが可能となる。そして、中小企業再生支援協議会は、公正中立な立場から債権者などの利害関係人の調整を図るので、債権者からの同意も得られやすい。
しかし、中小企業再生支援協議会の調整による手続は、対象が中小企業者(脚注3)に限定されているため、上場企業等の大企業や医療法人、学校法人は利用できない。また、地方の中小企業再生支援協議会によっては、その債権者調整力が十分ではないとの指摘もなされている。
6 企業再生支援機構スキーム 株式会社企業再生支援機構(以下「企業再生支援機構」という。)は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅・中小企業その他の事業者の事業再生を支援することなどを目的として平成21年10月14日に株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された官民出資の企業である。
当初、設立から5年間で業務を完了するよう努める時限的な組織であり、設立から2年までに支援先を決定することとされていたが、平成24年3月31日に法改正がなされ、業務は平成28年3月31日までに完了するよう努めるものとされ、支援決定については、平成25年3月31日までに行うものとされた。
企業再生支援機構による支援は、対象事業者に対する融資を実行することができること、非メイン金融機関から時価で債権買取等をすることも可能なこと、対象事業者に対して出資することができる、といった特徴があり、事業再生に対する支援は、事業再生ADRや中小企業再生支援協議会の調整手続よりも積極的である。
デュー・ディリジェンスの費用等は、対象事業者が負担するのが原則であるが、支援決定に至った場合には、事業者の規模に応じて一部機構が負担し、支援決定に至らなかった場合には、全額支援機構が負担することとなっている。
この企業再生支援機構による事業再生手続は、申込み後、支援決定までに時間がかかるといった問題点が一部で指摘されている。
Ⅳ 私的整理における財務リストラの手法
私的整理における財務リストラの手法としては、リスケジュール、債権放棄、デッド・エクイティ・スワップ(DES)、デッド・デッド・スワップ(DDS)、事業譲渡、会社分割等が考えられる。
1 リスケジュール リスケジュールとは、金融機関等からの借入金の返済条件を変更して、分割返済額の減額や元本返済猶予(その間、利息のみ支払う)期間を置くなどにより、債務者のキャッシュ・フローを改善させるものである。
リスケジュールは、単に返済条件を変更するものであり、債権そのものを減額するものではないので、金融機関としても応じやすい。しかし、元本返済猶予期間内にキャッシュ・フローを改善できる見込みがなく、改善後のフリー・キャッシュ・フローで合理的期間内(通常、10年程度)に借入金を返済することができないようであれば、リスケジュールによる事業再生は困難であり、単に、問題を先送りしただけとなる。したがって、リスケジュールによる事業再生を図る場合、キャッシュ・フローの改善策及び今後見込まれるフリー・キャッシュ・フローを検討し、今後のフリー・キャッシュ・フローで合理的期間内に借入金を返済できる見込みが立たないようであれば、より抜本的な他の手法を検討する必要がある。
2 債務免除 債務免除とは、債権者が債務者に対して債権を免除するとの意思表示をすることにより債務を消滅させ、もって債務者のキャッシュ・フロー及び財務内容を改善させるという再生手法である。
債務者とすれば、債務免除の対象となった債権の元本及び利息の返済の必要がなくなり、負担が大幅に軽減されるので、債務免除は抜本的な再生手法といえる。しかし、債権者にとっては、負担が大きいことから、私的整理では債務免除を得ることは容易ではない。そのため、債務者としては、十分な情報開示をするとともに、債務免除の合理性について、十分説明する必要がある。
また、債務免除を受けると債務免除益が生じることになるため、繰越欠損金等が十分でない等の理由により損金算入できる金額が少ない場合には、課税が生ずることになることになるので、注意が必要である。
3 DES DESとは、債権者が債務者に対して有する債権を、債務者の株式と交換することをいう。
会社法ではDESについての規定はないため、一般的には、債権者が債務者に対する債権を債務者に現物出資し、債権の現物出資の対価として株式を取得し、現物出資の対象となった債権自体は、債務者と債権者が一致することから混同により消滅するので、事実上、債務が株式に代わるという手法がとられる。
DESを行うと、債権者が株主になることから経営の安定化が図られないことと、銀行は企業の議決権の5%までしか株式を持つことができないことから、DESにより発行する株式は普通株式ではなく無議決権株式であることが多い。
DESは、債務者にとっては、債務を圧縮するというメリットがあり、債権者としても、将来企業の再建が成功した場合にはキャピタルゲインを期待できるというメリットがある。
しかし、DESは債権の現物出資という手続をとるため、検査役の検査(会社法33条4項)を受けなければならず、手続が煩雑であることや、非上場株式の場合、キャピタルゲインは期待できない等のデメリットがあることから、中小企業がこの手法を用いることは、少ないと思われる。
4 DDS DDSとは、債権者が、債務者に対して有する債権を、他の債権よりも弁済順位について劣後する債権に変更することをいう。
具体的には、債権者と債務者との間で、金融検査マニュアルを踏まえ、返済順位の劣後条項、表明・保証、コベナンツ(数値目標、財務制限条項、情報開示、モニタリング)、期限の利益喪失条項等を定めた条件変更契約を締結することとなる。
DDSを行った場合、債権が劣後化されている間は元本の返済の必要はないので、債務者はその間に資金繰りを改善することができる。また、DDSは、対象債権を他の債権よりも弁済順位について劣後する債権に変更するものであるから、実質上債務超過が解消されることとなり、債務者の信用力が増しやすくなる。さらに、DDSは、DESと異なり、債務者と債権者との間で変更契約を締結すれば済むという点で手続が容易であるし、医療法人や学校法人など株式を発行しない法人でも用いることができる。
しかし、DDSは、実質的には支払期間が延期されただけであるから、その間に資金繰りを改善することができなければ、事業再生は困難となる。
5 事業譲渡・会社分割 事業譲渡とは、株式会社が事業を取引行為として他に譲渡する行為をいい、会社分割とは、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社又は分割により設立する会社に承継させることを目的とする会社の行為をいう。なお、事業譲渡又は会社分割後、旧会社である譲渡会社・分割会社を消滅させる場合を、第二会社方式と呼ぶこともある。
事業譲渡も会社分割も、もともと事業再生の手段として規定されたものではないが、会社の収益性のある事業と不採算部門を分けて、不採算部門を旧会社に残し、収益性のある事業を切り離して他の会社に承継させることで事業再生を図ったり(事業譲渡・会社分割の場合)、逆に、不採算部門を切り離して他の会社に承継させ、旧会社に収益性のある事業を残すことで、事業再生を図ることが可能である(会社分割の場合)ことから、事業再生の一手法として広く利用されている。
事業譲渡や会社分割は、収益性のある事業部門のみを承継したいというスポンサーの意向や、債務免除をすると多額の債務免除益が発生し、繰越欠損金等の損金算入が十分できず課税が生じる場合に、これを回避することができるというメリットがある。
しかし、事業譲渡や会社分割を行うには、株主総会の特別決議による承認を要することから(会社法467条1項1号・2号)、多くの株主から反対される場合には、私的整理で事業譲渡や会社分割を行うことはできない。また、債務者の事業継続に債務者所有の不動産が必要である場合には、不動産の所有権の移転に登録免許税や不動産取得税等のコストがかかるといったデメリットもある(脚注4)。さらに、営業上必要な許認可等については承継できない可能性があるといったデメリットもある(脚注5)。
なお、事業譲渡や会社分割は、債権者保護手続を経ずに行うことが可能であるため、債権者に知れぬよう事業譲渡や会社分割を行い、収益性のある事業と不採算部門を切り分け、多額の債権を不採算部門のある会社に残すといった手法が広く行われている。
しかし、債権者の意向をまったく無視した濫用的な事業譲渡や会社分割については、かねてから批判がなされており、近時、株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができると判断した最高裁判例も出ている(最高裁判所平成24年10月12日第二小法廷判決(平成22年(受)第622号))。また、平成24年9月7日に法制審議会総会で決定された「会社法制の見直しに関する要綱」でも、詐害的な会社分割等により不採算部門に残された債権者は、承継会社に対し、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することや、各別の催告を受けずに承継会社に対する債権とされてしまった債権者は、分割会社に対し、分割時に有していた財産を限度として債務の履行を請求することが規定されている。したがって、今後は、債権者に知られないように事業譲渡や会社分割を実行して、収益性のある事業を切り離すという主張は、事業再生の手法としては採りづらくなると思われる。
Ⅴ 法的整理の種類
私的整理での事業再生が困難ということになれば、次に、法的整理での事業再生を検討することとなる。
法的整理には、再生手続と更生手続がある。再生手続は、大正11年に公布された和議法(脚注6)に代わるものとして、平成11年に公布され、平成12年4月1日から施行された民事再生法に基づく再建型の倒産手続であり、更生手続は、平成27年に成立した旧会社更生法を全面改正し、新しい法律として平成14年に公布され、平成15年4月1日から施行された会社更生法に基づく更生型の倒産手続である。民事再生法と会社更生法は、前者が一般法、後者が特別法という位置づけであるが、再生手続と更生手続の違いは、以下のとおりである。
1 適用対象 再生手続は、適用対象に限定がなく、すべての法人及び自然人を対象としているのに対し(民事再生法1条)、更生手続の適用対象は、株式会社に限定されている(会社更生法1条)。
したがって、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等株式会社以外の法人及び個人が法的整理での事業再生を行う場合には、再生手続を利用することとなる。
なお、再生手続は、手続の簡便性等から、主として中小規模の企業の再建に利用され、更生手続は大規模企業の再建に利用されることが想定されていたが、上場企業でも再生手続が利用されており、規模により手続を分けるという意味は、あまりなくなってきている。
2 管理処分権の帰属主体 再生手続は、原則として再生債務者が業務の遂行権限や財産の管理処分権限を維持した形で手続が進められるDIP(Debtor In Possession)型であるのに対し(民事再生法38条1項)、更生手続は、原則として裁判所の選任した管財人にこれらの権限を専属させる形で手続が進行する管理型である(会社更生法72条1項)。
企業の内容を把握した現経営陣が手続を進めたほうが効率よく的確に再建を進められる可能性が高いので、原則的には、再生手続を選択することが再建可能性をより高くするものといえるが、現経営陣が不正行為を行っていた場合など、債権者から最低限度の信頼も得られないような場合には、裁判所に選任された管財人という中立・公平な第三者の下で再建を行っていく更生手続で事業再建を進めた方が再建可能性は高くなる。
もっとも、更生手続においても、更正会社の現経営陣に不正行為等の違法な経営責任の問題がない場合には、現経営陣の中から管財人を選任することができるとされており(会社更生法67条3項)、実質的にはDIP型の手続として運用することが可能である。近時は、DIP型の更生手続も利用され、運用として定着しつつある。
また、再生手続においても、再生債務者が法人の場合には、再生債務者による財産の管理処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認められるときには、管理命令を発令して管財人を選任することができるものとされており(民事再生法64条)、近時、管理型で再生手続が進められる事例も出てきている。
3 担保権や租税債権等の権利行使に対する制約 再生手続においては、抵当権等の担保権を有する債権は別除権として、租税債権(国税、地方税、社会保険料等)や労働債権等の優先権のある債権は一般優先債権として、再生手続外での権利行使が可能である(民事再生法53条、122条)。
これに対し、更生手続では、担保権を有する債権及び租税債権等の優先権のある債権のいずれについても更生手続に取り込まれ、手続外での権利行使はできず(会社更生法2条10項、47条1項、50条1項、135条1項)、更生計画に従った弁済を受けることになる(会社更生法167条1項1号、168条、169条)。
したがって、強硬な担保権者がいる場合には、再生手続よりも更生手続を利用した方が適切な場合が多い。
4 組織再編 再生手続では、事業譲渡については、株主総会の特別決議による承認に代わる代替許可の制度が設けられ(民事再生法43条1項)、自己株式の取得、株式の併合、資本金の額の減少、授権資本に関する定款の変更についても再生計画によって行うことができるとされているが(同法154条3項、183条)、新株発行(増資)を行うには、再生計画の定めだけでは足りず、取締役会の決議等が必要であるとされており(同法154条4項、183条の2)、事業譲渡以外の組織上の行為を行う場合にも、会社法の規定に従って株主総会の決議その他会社の機関決定を経る必要がある。
これに対し、更生手続においては、再生手続でできることに加え、新株発行(増資)や社債の発行、更には合併、会社分割、株式交換、株式移転等のような会社組織の再編に亘る行為についても会社法の規定によることなく更生計画によって行うことが可能である(会社更生法167条2項、203条1項、210条以下)。
また、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を承継させることができるうえ(会社更生法231条)、更生会社から新会社へ不動産・船舶を承継させる場合の移転登記の登録免許税が大幅に軽減され(会社更生法264条7項・8項)、更生会社から新会社への不動産を移転する場合の不動産取得税が非課税扱いとなる(地方税法73条の7第2号の4)。
このように、更生手続では、本来的に組織再編行為が予定されているため、組織再編行為を容易にするための規定が多く設けられている。
5 計画案の可決要件 再生手続では、再生計画案の可決のためには、議決権者の議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意に加え、債権者集会に出席し又は書面投票をした議決権者の過半数の同意(いわゆる頭数要件)が必要である(民事再生法172条の3第1項)。
他方、更生手続においては、更生計画案の可決のためには、①更生債権については、議決権の2分の1を超える議決権を有する者の同意、②更生担保権については、期限の猶予を定める場合には議決権総額の3分の2以上、減免その他期限の猶予以外の方法による権利変更を定める場合には議決権総額の4分の3以上、事業全部の廃止を内容とする場合には議決権総額の10分の9以上の同意、③株主については、議決権総数の過半数の同意(ただし、更生会社が債務超過である場合には、株主は議決権を有しない)が必要である(会社更生法196条5項)が、再生手続と異なり頭数要件は必要とされていない。したがって、大口の債権者は再生計画案に賛成しているが、零細な債権者が再生計画案に反対しており、その数が多い場合には、更生手続を選択することになろう。
6 手続の終了 再生手続においては、再生計画認可決定の確定後3年が経過した時は、再生計画の履行が未了であったとしても、再生手続終結の決定をしなければならない(民事再生法188条2項)。
これに対し、更生手続の場合には、このような期間制限はなく、少なくとも更生計画の遂行が確実であると認められるまでは、更生手続終結の決定をすることはできず(会社更生法239条)、裁判所による監督が継続する。再生手続と比較すると、更生手続では、計画遂行の確実性を期すためにより厳格な監督体制が採られている。
Ⅵ 法的整理における再生計画(更生計画)
1 法的整理における財務リストラの手法 法的整理における財務リストラは、一般的には再生計画又は更生計画における権利変更という形で行われる。
法的整理では、全債権者の合意ではなく、多数決原理が採られるために、債権者調整が私的整理に比べ容易であることと、通常、財務状態が大きく毀損していることが多いことから、その財務リストラのほとんどが債権放棄であり、リスケジュール、DDS、DESといった手法はとられない(脚注7)。
しかし、平成22年5月に東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てをし、平成23年2月に手続を終結した株式会社プロパストの再生計画では、上場を維持するために、一部の債権についてDESが行われている。法的整理でも、事案に応じて柔軟に財務リストラの手法を検討することが重要である。
2 民事再生・会社更生とM&A 再生手続又は更生手続を行った株式会社の多くは、信用を維持するため、手続中の資金援助を受けるため、弁済原資を得て債権者に対する早期弁済をするため、株主責任・経営者責任を果たすためにスポンサーからの支援を受けている。スポンサーからの支援を受ける場合、通常、M&Aが行われるが、民事再生法及び会社更生法は、M&Aが行いやすいよう、会社法の規定を一部修正している。
再生手続及び更生手続で通常行われるM&Aの手法としては、①増減資スキーム、②事業譲渡、③会社分割、の3つが挙げられる。
そこで、以下、上記3つの手法について説明する。
(1)増減資スキーム 増減資スキームとは、再生会社・更生会社が一定の減資をすると同時に株式を消却し、スポンサー企業に第三者割当増資を行う手法である。
再生手続の場合、再生会社が債務超過である場合には、会社法の規定による資本減少の手続(会社法447条以下)、株式取得の手続(会社法156条等)によらずに、あらかじめ裁判所の許可を得た上で、再生計画において資本の減少に関する条項、株式の取得に関する条項を定めることで(民事再生法166条1項・154条3項)、会社法所定の株主総会の特別決議や債権者保護手続が不要となる(民事再生法183条)。
更生手続の場合、資本の再構成を本来的に予定しているため、裁判所の許可を得なくとも、更生計画において資本の減少に関する条項(会社更生法174条3号)、株式の取得に関する条項(会社更生法174条の2)、株式の消却に関する条項(会社更生法174条1号)を定めることで、会社法所定の株主総会の特別決議や債権者保護手続が不要となる(会社更生法212条、214条、215条)。
増減資スキームは、承継する資産・負債、契約関係の取捨選択や資産等を個別移転させる手続が不要であり、手続が簡便であること、また、許認可の移転手続や再取得の必要がないこと、資産の移転に伴うコスト(不動産取得税や登録免許税など)が発生しないといったメリットがある。
しかし、多額の債務免除益が発生した場合、それを打ち消すだけの資産評価損や繰越欠損金がない場合には、債務免除益課税の問題が生じるし、スポンサーにとっては不採算事業まで承継する可能性が残るという問題もある。
(2)事業譲渡 事業譲渡とは、株式会社が事業を取引行為として他に譲渡する行為をいう。
再生手続では、再生計画で事業譲渡を行うこともできるが、再生手続開始決定後であれば、再生計画案提出前までに、裁判所の許可を得て事業の全部または重要な一部を譲渡することができる(民事再生法42条1項)。
再生手続において事業譲渡をする場合にも、原則として株主総会の特別決議による承認が必要となるが(会社法467条1項1号・2号)、再生会社が債務超過である場合には、裁判所は、債務者の申立により、株主総会の特別決議による承認に代わる許可を与えることができる(民事再生法43条1項)。再生会社の多くは債務超過であると思われるから、事実上、株主総会の特別決議による承認は不要となる。
更生手続でも、事業譲渡は更生計画によって行うことを原則としつつも(会社更生法46条1項本文)、開始決定後更生計画案の付議決定がなされるまでの間であれば、裁判所の許可を得て、事業の全部または重要な一部の譲渡を行うことができる(同条2項)。更生手続で事業譲渡する場合には、株主総会の特別決議による承認は不要であるが、更生会社が債務超過でなく、かつ、譲渡先が更生会社の特別支配会社(会社法468条1項)でない場合には、事業譲渡を行うに当たり、あらかじめ所定の株主保護手続を採らなければならない(会社更生法46条4項ないし6項)。
事業譲渡は、再生計画案・更生計画案作成前に実行することが可能であり、株主総会の特別決議による承認も不要なので、迅速に行うことができる。また、スポンサーにとっては、必要な事業だけを譲り受けることができる上、偶発債務や簿外債務を承継するリスクを最小化できるというメリットがある。さらに、清算所得課税制度は廃止されたものの、残余財産がないと見込まれるときには、法人税法59条3項において期限切れ欠損金の利用が認められるので、債務免除益と同額の損金算入が可能となるから、事業譲渡を行い、その後再生計画・更生計画により債務免除の権利変更がなされた譲渡会社を清算させれば、債務免除益課税の問題も生じない。
しかし、事業譲渡は、資産の移転コスト(不動産取得税や登録免許税等)が発生すること(脚注8)、個々の資産の譲渡ごとに対抗要件を具備することが必要であること、契約上の地位の譲渡の場合、相手方の承諾を得ることが必要であること、従業員を移籍させる場合、個別の同意が必要であること、許認可を承継させることが困難であること(脚注9)、といったデメリットがある。
(3)会社分割 会社分割とは、株式会社又は合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、分割後他の会社又は分割により設立する会社に承継させることを目的とする会社の行為をいう。
会社分割については、民事再生法上、特別の規定は設けられていないため、再生手続と絡めて会社分割を行う場合は、再生会社において、会社法に定める手続を履践する必要がある。
更生手続で会社分割を行う場合には、会社法所定の手続を履践することなく、更生手続の中で会社分割を行うことができる。
会社分割は、スポンサーにとって必要な事業だけを譲り受けることができる上、包括承継なので、契約の相手方の個別の同意を要することなく契約関係を移転することが可能であり、事務手続を大幅に簡略化できるので、承継すべき契約関係が多数あるときに多く利用される。また、会社分割では、権利の承継・移転についての登録免許税等が軽減されており、不動産取得税も一定の要件を満たした場合には、非課税となる。
しかし、会社分割の場合、行政上の許認可等について、主務大臣の許認可が必要なものがあり、当然に承継することはできない。また、再生手続では、会社分割を行う場合、会社法上の手続を履銭しなければならず、労働者保護手続、株主保護手続、債権者保護手続きを行うことが必要である。
鈴木規央 すずき のりお
シティユーワ法律事務所 弁護士・公認会計士。太田昭和監査法人(新日本有限責任監査法人)、パートナーズ国際会計事務所を経て、2006年弁護士登録し、同年からシティユーワ法律事務所。日本公認会計士協会租税調査会国際租税専門部会専門委員、日本公認会計士協会東京会税務第二委員会委員。著作として、『公認会計士による税務判例の分析と実務対応』(共著、日本公認会計士協会東京会編、日本公認会計士協会出版局、2012年)、『問答別 企業提携の法律実務』(共著、新日本法規)など。
脚注
1 なお、法的整理といった場合、一般的には清算型の倒産手続である破産手続や特別清算手続も含まれるが、本稿では事業再生について論じるものであるから、ここでは清算型の法的整理は含めないものとする。
2 「裁判外事業再生」実務研究会編「裁判外事業再生の実務」(商事法務)28頁。
3 「中小企業者」とは、①資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を営むもの、②資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの、③資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの、④資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの、⑤資本金の額又は出資の総額がその業種毎に政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの、⑥企業組合、⑦協業組合、⑧事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの、をいう(産活法2条17項)。
4 なお、産活法に基づき、事業継続が困難であるが収益性のある事業を有している中小企業に対して第二会社方式による中小企業承継事業再生計画の認定を受けることができれば、登録免許税、不動産取得税の軽減等の税負担の軽減措置等を受けることができる(租税特別措置法80条、地方税法附則11条45号)。
5 なお、産活法に基づき、事業継続が困難であるが収益性のある事業を有している中小企業に対して第二会社方式による中小企業承継事業再生計画の認定を受けることができれば、特定の種類の営業上必要な許認可等を承継することができる(産活法39条の4)。また、会社分割では、保険業、登録電機工事業者等のように届出等しなくても承継できる許認可、飲食店業、液化石油ガス販売業者、アルコール製造業者等のように会社分割の届出だけで承継できる許認可、ホテル、旅館業、一般貨物自動車運送事業者等のように承継に所轄官庁の承認が必要な許認可もある。
6 和議法は、我が国で最初の再建型手続法として、オーストリア和議法を模範として制定されたものであったが、開始原因が狭すぎること、担保権の行使が制約されないこと、和議の可決要件が厳しいこと、和議の履行が十分に確保できないことなどから再建型手続としてその機能を十分に発揮し得なかった。
7 会社更生法の理念としては、DESを利用した再建手法が用いられることが想定されているようであるが(山本・中西・笠井・沖野・水元「倒産法概説(第2版)」(弘文堂)32頁)、実際にDESが利用されている事例は少ない。
8 ただし、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を承継させることができる(会社更生法231条)。
9 ただし、更生手続では、更生計画で新会社を設立し、更生会社の事業の全部または一部を新会社に譲渡する場合には、更生会社から新会社へ不動産・船舶を承継させる場合の移転登記の登録免許税が大幅に軽減され(会社更生法264条7項・8項)、更生会社から新会社への不動産を移転する場合の不動産取得税が非課税扱いとなる(地方税法73条の7第2号の4)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.