解説記事2013年01月07日 【税務マエストロ】 税務行政執行共助条約-徴収共助①(2013年1月7日号・№481)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
税務行政執行共助条約-徴収共助①
#64 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#65 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設を主導した筆者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 平成23年11月、日本は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」(脚注1))に署名した。この条約は、署名した締結国間で税金に関する行政支援、具体的には「情報交換」、「徴収共助」、「送達共助」を相互に行うことを定めるもので、国税庁等の税務当局間で協力して国際的な脱税および租税回避行為に対処していくことを目的としている。つまり納税者が意図的に納税せず、滞納処分を逃れるために資産を国外に移転するリスクに対応するものとして認識されているが、一方で、その内容としては日本国内の税務調査や滞納処分の制度の根幹に関係するものが多く、結果として、日本国内の一般納税者にも多大な影響を与える条約と言えよう。
1 署名に至るまでの経緯 税務行政執行共助条約は、2国間条約である一般的な租税条約と異なり、多国間租税条約に位置づけられるが、もともとはヨーロッパ、つまりEU内の政策協調の一端としての発想から生まれてきたものである。OECDおよび欧州評議会(Council of Europe)で草案作成の検討が行われ、1988年に参加署名のために開放されたが(原条約)、国内制度との齟齬を理由に当初の参加国は限定されていた。こうした状況下、昨今の一般的な情報交換や徴収共助の精緻化の議論に合わせ、税務行政執行共助条約(原条約)も改正され、徐々に参加国が増加してきたものである。
我が国においては、税制調査会の議論(脚注2)を踏まえ、平成23年度税制改正大綱(平成22年12月16日閣議決定)で、「欧州評議会・OECD税務行政執行共助条約などの国際的な取り組み等を踏まえつつ、具体的な検討を行います。」とされた。それを受け、平成23年11月3日、G20カンヌサミットにおいて、税務行政執行共助条約に署名したものである。
我が国の国内手続きとして、署名後、第180回国会に提出されたが、承認を得る前に国会が閉会してしまい、現在のところ我が国において税務行政執行共助条約は発効していない。今後の国会で承認を得られれば、その批准書等をOECD事務局等に寄託し、寄託の日の後3カ月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に発効することになる。
2 徴収共助の基本的仕組み 徴収共助は、「租税債権の徴収において執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が互いに条約相手国の租税債権を徴収していこうとする枠組み」(税制調査会資料)であり、税務行政執行共助条約で定める共助事項の中で最も重要な制度の一つと言える。具体的には、たとえば、自国の納税を滞納している納税者が、国内ではなく外国に財産を有する場合に、外国の主権(執行管轄権)による制約から、直接的にその在外資産に対して自国の法令に基づく滞納処分を行うことができないこととなる。こうした場合に、相手国(財産所在地国)の法令に基づき、相手国で滞納処分等を行い、その徴収額を自国に送付してもらう制度である(脚注3)。たとえば、滞納中の日本企業について、国内に主だった資産がなく、外国に多額の売上債権を有するような場合、その売上債権から共助により徴収することが考えられる(図参照)。
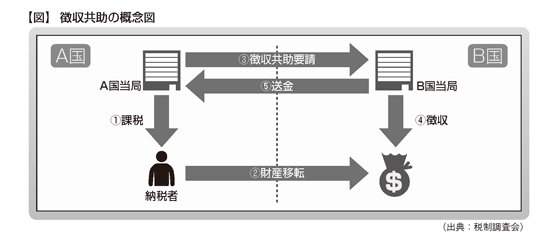
なお、条約に署名し徴収共助を行うということは、こちらから依頼、要請するケースのみならず、当然のことながら他の条約参加国から徴収の依頼、要請を受けることも想定しなくてはならない。こうした場合、だれが、どのようにして滞納処分を行い、徴収額を送金するのかといった国内手続きおよびその法的根拠が論点となる。こうした法的根拠の整備の観点から、平成24年度改正において、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(条約実施特例法)および関連政省令が大幅に改正されたのである。
3 基本的論点―主な改正点
(1)改正前の法的根拠 徴収共助については税務行政執行共助条約のみならず、これまで我が国が締結した2国間租税条約にもその定めがある。租税条約の相手国から租税の徴収の嘱託をうけた場合には、日本国政府として、なんらかのアクションをとることを約束していたと言える。国内法的にも平成24年の改正以前の租税条約実施特例法第11条に、「政府は、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の租税につき当該相手国等の政府から徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。この場合において、当該租税及び滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税及びその滞納処分費と同順位とする。」とされていた。この規定は、基本的に国税徴収の手続きに準じて外国の租税の徴収を行うことを定めているが、徴収共助の一連の手続きをすべて準用するには不十分な規定である。具体的に、だれが(たとえばどこの税務署か)、どのように(たとえば換価処分など)行うかといった根本的問題すら解決策(準用の仕方)がないといえる。したがって、これまでに租税条約の相手国から徴収共助の要請を受け、それに対応できたケースはないと推測される。
また、そもそも、「租税条約実施特例法」は主に租税条約の規定を適用するための手続きを定める法律、規定である。「国税徴収の例により」という規定のみで、国税の徴収を担当する国税職員に、我が国では国税でない(つまり一般債権と同じ)外国の租税を徴収するという職務権限が与えられているとは考え難い。こうした国税職員の職務権限の観点からの法整備も必要であったと考えられる。
(2)徴収共助の対象となる外国租税 我が国の税務当局が税務行政執行共助条約の参加国から徴収共助の要請を受けた場合、国税を徴収する例にならい、外国の租税の徴収を日本国内で行うこととなる。これは、外国の租税のために私人の財産権を制約することになり、憲法第29条(脚注4)の精神に反することになりかねない。したがって、こうした憲法上の要請との関連性を踏まえれば、我が国の国益に悪影響が及ぶような場合にまで徴収共助を行うことには合理的な理由を見いだせないばかりか、法的な観点で問題なしとしない。つまり、相手国から要請を受けた場合、相手国の言うがまま、自動的に徴収共助に応じるのではなく、我が国の国益、法制に照らして、徴収共助に応じることが適当かどうかの検討、判断を行うことが必要となるのである。こうしたことから、徴収共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるときなど、徴収共助に応じることが適当でない場合として、いくつかの除外事由が定められた(実特法11)。
(3)徴収共助の実施方法 徴収共助の要請を受けた場合、実際に徴収を行うのは、「所轄国税局長等」とされた。これは原則として、共助対象者(通常は徴収共助の対象となる租税債務を有する者)の住所等または財産の所在地を所轄する国税局長となる。
実際の徴収の手続きは、我が国の国税と同様に行うことになるのであるが、その過程では国税の「優先権」という大きな問題がある。我が国の国税には国税徴収法により優先権が与えられている。つまり、国税債権が他の私債権と競合した場合、国税債権が優先的に回収されることとなる。これは、国税が憲法で要請された租税法律主義に基づく債権債務であることに加え、納税証明制度により、私債権者が競合しうる国税を予測する手段が保障されているためである。一方、徴収共助の対象となった租税については、我が国の憲法等と関係のないものであり、また、必ずしも私債権者の予見可能性が保障されているとは言い難いと考えられる。したがって、こうした外国の租税に対し、我が国の国税に与えられる優先権を認めることは適当ではなく、その結果、私債権者と競合した場合に、私債権者より優先的に回収されないような手当がされた。
(次号において、上記(2)、(3)を詳解予定)
(参考)税務行政執行共助条約の署名国は次の35ヶ国(2012年3月末) 日、米、英、仏、独、伊、加、韓、メキシコ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、アイルランド、ポーランド、スロベニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、グルジア、モルドバ、トルコ、豪、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、ロシア、インドネシア、インド、コスタリカ、ギリシャ
脚注
1 正式英文名は「Convention on Mutual Administrative Assistance In Tax Matters」
2 平成22年11月の税制調査会専門家委員会で取りまとめられた「国際課税に関する論点整理」において、「外国との間で租税債権につき徴収の共助を行うことのできる仕組みを整える必要がある」とされ、「欧州評議会・OECD税務執行共助条約といった、①情報交換、②徴収の共助、③文書送達に関する税務執行共助に係る多国間条約に、より多くの国が参加するようになっており、我が国も税務執行に関する多国間協力のアプローチを検討の対象とすべき」とされていた。
3 我が国から他国に対して徴収の共助を依頼する場合、国外の財産から徴収することを可能にするよう、国税徴収法および国税通則法が改正されている。また、国外財産の把握のため、平成24年度改正で創設された「国外財産調書制度」が効力を持つと考えられる。
4 憲法第29条第1項財産権は、これを侵してはならない。第2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。第3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
税務行政執行共助条約-徴収共助①
#64 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#65 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設を主導した筆者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 平成23年11月、日本は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」(脚注1))に署名した。この条約は、署名した締結国間で税金に関する行政支援、具体的には「情報交換」、「徴収共助」、「送達共助」を相互に行うことを定めるもので、国税庁等の税務当局間で協力して国際的な脱税および租税回避行為に対処していくことを目的としている。つまり納税者が意図的に納税せず、滞納処分を逃れるために資産を国外に移転するリスクに対応するものとして認識されているが、一方で、その内容としては日本国内の税務調査や滞納処分の制度の根幹に関係するものが多く、結果として、日本国内の一般納税者にも多大な影響を与える条約と言えよう。
1 署名に至るまでの経緯 税務行政執行共助条約は、2国間条約である一般的な租税条約と異なり、多国間租税条約に位置づけられるが、もともとはヨーロッパ、つまりEU内の政策協調の一端としての発想から生まれてきたものである。OECDおよび欧州評議会(Council of Europe)で草案作成の検討が行われ、1988年に参加署名のために開放されたが(原条約)、国内制度との齟齬を理由に当初の参加国は限定されていた。こうした状況下、昨今の一般的な情報交換や徴収共助の精緻化の議論に合わせ、税務行政執行共助条約(原条約)も改正され、徐々に参加国が増加してきたものである。
我が国においては、税制調査会の議論(脚注2)を踏まえ、平成23年度税制改正大綱(平成22年12月16日閣議決定)で、「欧州評議会・OECD税務行政執行共助条約などの国際的な取り組み等を踏まえつつ、具体的な検討を行います。」とされた。それを受け、平成23年11月3日、G20カンヌサミットにおいて、税務行政執行共助条約に署名したものである。
我が国の国内手続きとして、署名後、第180回国会に提出されたが、承認を得る前に国会が閉会してしまい、現在のところ我が国において税務行政執行共助条約は発効していない。今後の国会で承認を得られれば、その批准書等をOECD事務局等に寄託し、寄託の日の後3カ月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に発効することになる。
2 徴収共助の基本的仕組み 徴収共助は、「租税債権の徴収において執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が互いに条約相手国の租税債権を徴収していこうとする枠組み」(税制調査会資料)であり、税務行政執行共助条約で定める共助事項の中で最も重要な制度の一つと言える。具体的には、たとえば、自国の納税を滞納している納税者が、国内ではなく外国に財産を有する場合に、外国の主権(執行管轄権)による制約から、直接的にその在外資産に対して自国の法令に基づく滞納処分を行うことができないこととなる。こうした場合に、相手国(財産所在地国)の法令に基づき、相手国で滞納処分等を行い、その徴収額を自国に送付してもらう制度である(脚注3)。たとえば、滞納中の日本企業について、国内に主だった資産がなく、外国に多額の売上債権を有するような場合、その売上債権から共助により徴収することが考えられる(図参照)。
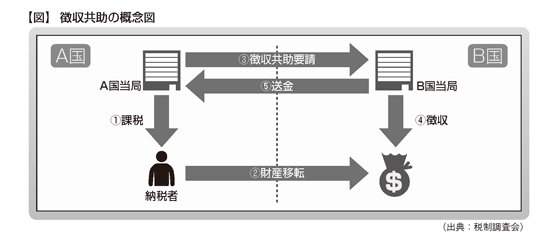
なお、条約に署名し徴収共助を行うということは、こちらから依頼、要請するケースのみならず、当然のことながら他の条約参加国から徴収の依頼、要請を受けることも想定しなくてはならない。こうした場合、だれが、どのようにして滞納処分を行い、徴収額を送金するのかといった国内手続きおよびその法的根拠が論点となる。こうした法的根拠の整備の観点から、平成24年度改正において、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(条約実施特例法)および関連政省令が大幅に改正されたのである。
3 基本的論点―主な改正点
(1)改正前の法的根拠 徴収共助については税務行政執行共助条約のみならず、これまで我が国が締結した2国間租税条約にもその定めがある。租税条約の相手国から租税の徴収の嘱託をうけた場合には、日本国政府として、なんらかのアクションをとることを約束していたと言える。国内法的にも平成24年の改正以前の租税条約実施特例法第11条に、「政府は、租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の租税につき当該相手国等の政府から徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例によりこれを徴収する。この場合において、当該租税及び滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税及びその滞納処分費と同順位とする。」とされていた。この規定は、基本的に国税徴収の手続きに準じて外国の租税の徴収を行うことを定めているが、徴収共助の一連の手続きをすべて準用するには不十分な規定である。具体的に、だれが(たとえばどこの税務署か)、どのように(たとえば換価処分など)行うかといった根本的問題すら解決策(準用の仕方)がないといえる。したがって、これまでに租税条約の相手国から徴収共助の要請を受け、それに対応できたケースはないと推測される。
また、そもそも、「租税条約実施特例法」は主に租税条約の規定を適用するための手続きを定める法律、規定である。「国税徴収の例により」という規定のみで、国税の徴収を担当する国税職員に、我が国では国税でない(つまり一般債権と同じ)外国の租税を徴収するという職務権限が与えられているとは考え難い。こうした国税職員の職務権限の観点からの法整備も必要であったと考えられる。
(2)徴収共助の対象となる外国租税 我が国の税務当局が税務行政執行共助条約の参加国から徴収共助の要請を受けた場合、国税を徴収する例にならい、外国の租税の徴収を日本国内で行うこととなる。これは、外国の租税のために私人の財産権を制約することになり、憲法第29条(脚注4)の精神に反することになりかねない。したがって、こうした憲法上の要請との関連性を踏まえれば、我が国の国益に悪影響が及ぶような場合にまで徴収共助を行うことには合理的な理由を見いだせないばかりか、法的な観点で問題なしとしない。つまり、相手国から要請を受けた場合、相手国の言うがまま、自動的に徴収共助に応じるのではなく、我が国の国益、法制に照らして、徴収共助に応じることが適当かどうかの検討、判断を行うことが必要となるのである。こうしたことから、徴収共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるときなど、徴収共助に応じることが適当でない場合として、いくつかの除外事由が定められた(実特法11)。
(3)徴収共助の実施方法 徴収共助の要請を受けた場合、実際に徴収を行うのは、「所轄国税局長等」とされた。これは原則として、共助対象者(通常は徴収共助の対象となる租税債務を有する者)の住所等または財産の所在地を所轄する国税局長となる。
実際の徴収の手続きは、我が国の国税と同様に行うことになるのであるが、その過程では国税の「優先権」という大きな問題がある。我が国の国税には国税徴収法により優先権が与えられている。つまり、国税債権が他の私債権と競合した場合、国税債権が優先的に回収されることとなる。これは、国税が憲法で要請された租税法律主義に基づく債権債務であることに加え、納税証明制度により、私債権者が競合しうる国税を予測する手段が保障されているためである。一方、徴収共助の対象となった租税については、我が国の憲法等と関係のないものであり、また、必ずしも私債権者の予見可能性が保障されているとは言い難いと考えられる。したがって、こうした外国の租税に対し、我が国の国税に与えられる優先権を認めることは適当ではなく、その結果、私債権者と競合した場合に、私債権者より優先的に回収されないような手当がされた。
(次号において、上記(2)、(3)を詳解予定)
(参考)税務行政執行共助条約の署名国は次の35ヶ国(2012年3月末) 日、米、英、仏、独、伊、加、韓、メキシコ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、アイルランド、ポーランド、スロベニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、グルジア、モルドバ、トルコ、豪、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、ロシア、インドネシア、インド、コスタリカ、ギリシャ
脚注
1 正式英文名は「Convention on Mutual Administrative Assistance In Tax Matters」
2 平成22年11月の税制調査会専門家委員会で取りまとめられた「国際課税に関する論点整理」において、「外国との間で租税債権につき徴収の共助を行うことのできる仕組みを整える必要がある」とされ、「欧州評議会・OECD税務執行共助条約といった、①情報交換、②徴収の共助、③文書送達に関する税務執行共助に係る多国間条約に、より多くの国が参加するようになっており、我が国も税務執行に関する多国間協力のアプローチを検討の対象とすべき」とされていた。
3 我が国から他国に対して徴収の共助を依頼する場合、国外の財産から徴収することを可能にするよう、国税徴収法および国税通則法が改正されている。また、国外財産の把握のため、平成24年度改正で創設された「国外財産調書制度」が効力を持つと考えられる。
4 憲法第29条第1項財産権は、これを侵してはならない。第2項財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。第3項私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















