解説記事2013年04月01日 【ニュース特集】 米国LPS訴訟の要点をQ&Aで読み解く(2013年4月1日号・№493)
法人該当性の判断基準は他の外国事業体に影響
米国LPS訴訟の要点をQ&Aで読み解く
米国デラウェア州のLPS(リミテッド・パートナーシップ)が日本の租税法上、法人に該当するか否かが争われた一連の訴訟で、控訴審の判断が相次いで示された。名古屋高裁(平成25年1月24日判決)は、同州LPSは法人に該当しないと判断し、納税者に軍配を上げた。一方、東京高裁(平成25年3月13日判決)は、同州LPSは法人に該当すると判断し、国側逆転勝訴の判決を言い渡した。地裁レベルで判断が分かれた同州LPS訴訟は、控訴審でも判断が分かれることとなり、最終的な決着は最高裁に委ねられることとなった。特集では、各裁判所が示した法人該当性の判断基準や他の外国事業体への影響などをQ&A形式で解説する。
Q1
米国デラウェア州のLPSとは? 米国LPS訴訟で問題となっているLPSとはどのようなものなのでしょうか。
A LPSとは、個人や法人が共同出資者となって組成される事業体(共同出資組織)のことです。LPSは、不動産投資などに用いられることが多く、米国租税法では、LPSの出資者に対して課税が行われています(パススルー課税)。日本の組合と類似していますが、日本には存在しない法概念です。米国LPS訴訟を巡る一連の事案では、LPSが行う不動産賃貸業から発生した損失が、納税者(出資者)に帰属するか否かが問題となりました(事案の概要は今号7頁の参考、スキームの全体像は本誌437号5頁参照)。
Q2
米国LPS訴訟の最大の争点 米国LPS訴訟では、デラウェア州のLPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっているそうですが、法人か否かで納税者の課税関係にどのような違いが生じるのでしょうか。具体的に教えて下さい。
A デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当しないのであれば、LPSから生じた損失は、出資者である納税者に直接帰属(パススルー課税)するため、たとえば納税者の給与所得等と損益通算することにより、納税者は節税メリットを享受することができます。
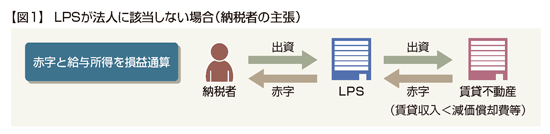
一方で、LPSが法人に該当するのであれば、LPSから生じた損失は、LPS本体に帰属するため、納税者側での損失計上は認められません。
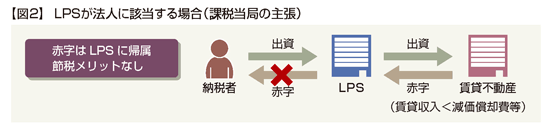 節税メリットを享受できる否かは、LPSが法人に該当するか否かにより決定されるため、一連の事案では、デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっていました。
節税メリットを享受できる否かは、LPSが法人に該当するか否かにより決定されるため、一連の事案では、デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっていました。
Q3
各裁判所が示した法人該当性の判断基準 デラウェア州のLPSが法人に該当するか否かについて、裁判所はどのような判断を示したのでしょうか。
A まず、大阪地裁判決(平成22年12月17日)が、国側が主張する法人該当性の判断基準(①独自の財産を有するか否か、②権利義務の帰属主体となるか否か、③訴訟当事者となりえるか否か)を採用し、デラウェア州LPSは法人に該当すると判断しました。
しかし、その後に言い渡された東京地裁判決(平成23年7月19日)と名古屋地裁判決(平成23年12月14日)は、国側の判断基準を一蹴し、新たに「①外国法令により法人格を付与する旨が規定されているか否か、②損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否か」という判断基準を示し、デラウェア州LPSは法人に該当しないと判断しました。この判断基準は、名古屋地裁判決の控訴審である名古屋高裁判決(平成25年1月24日)においても支持されています。
ところが、先日言い渡された東京高裁判決(平成25年3月13日)は、原審の東京地裁判決が示した「判断基準② 損益の帰属すべき主体か否か」は不要であると指摘し、新たに、「外国法令で法人格を付与する旨を規定されているかどうかだけでなく、外国法令が事業体の設立、組織、運営、管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきである」という判断基準を示しました。そのうえで東京高裁判決は、デラウェア州LPSは法人に該当するとの判断を示しました(次頁表参照)。
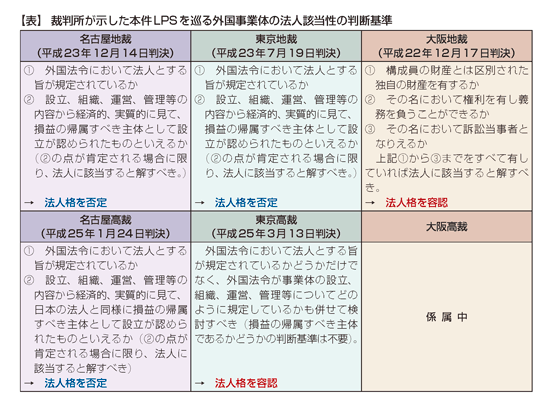
Q4
デラウェア州LPSとニューヨーク州LCCの相違点 米国ニューヨーク州のLLCについて、さいたま地裁判決(平成19年5月16日)とその控訴審である東京高裁判決(平成19年10月10日)は、ニューヨーク州LCCは法人に該当するとの判断を示しています。ニューヨーク州LCCと今回問題となったデラウェア州LPSの相違点を教えてください。
A ニューヨーク州LCC法のLCC(Limited Liability Company)は、パートナーシップ(Pertnership)という言葉が含まれず、外形的には「Company」に類するものとされています。また、デラウェア州LPSとの相違点として、ニューヨーク州LCCは、LCCから生じた損益が構成員に直ちに帰属せず、一定の部分のみが構成員に対する分配の対象になることを予定している点が挙げられます。
Q5
他の外国事業体への影響 外国法を準拠法とする事業体は、デラウェア州LPS以外にも存在します。各裁判所が示した法人該当性の判断基準は、他の外国事業体にも影響するのでしょうか。
A 米国LPSを巡る東京地裁判決(平成23年7月19日)と同様の判断基準(損益の帰属主体であるか否かなど)は、英国領バミューダ諸島の法律により組成されたLPSが法人に該当するか否かが争われた訴訟(平成24年8月30日判決)で採用されています。同訴訟の東京地裁は、バミューダ法に基づき組成されたLPSが日本の租税法上、法人に該当しないと判断しています(本誌472号40頁参照)。ただ、バミューダLPSを巡る訴訟は現在、東京高裁に係属中です。東京地裁判決(平成23年7月19日)の判断基準が控訴審(平成25年3月13日判決)で否定されていることを踏まえると、バミューダLPSの法人該当性を巡る控訴審の行方に注目が集まります。
Q6
海外LPS節税スキームは現在も有効か? 今回問題となった不動産投資事業を行う海外LPSを利用した節税スキームは、現在も有効なのでしょうか。
A 平成17年度税制改正により、民法上の組合契約、投資事業有限責任組合契約、外国におけるこれらに類似する契約に係る事業により発生した損失は、個人組合員の不動産所得の金額の計算上、その損失金額はなかったものとみなされる措置が講じられました(措法41条の4の2)。これにより、本事案のような海外LPSから発生した不動産損失を納税者の他の所得と損益通算する節税スキームは、封じ込められています。
なお、一連の訴訟では、改正措置法が適用される前の事案について、損益通算の可否ができるか否かが争われています。
米国LPS訴訟の要点をQ&Aで読み解く
米国デラウェア州のLPS(リミテッド・パートナーシップ)が日本の租税法上、法人に該当するか否かが争われた一連の訴訟で、控訴審の判断が相次いで示された。名古屋高裁(平成25年1月24日判決)は、同州LPSは法人に該当しないと判断し、納税者に軍配を上げた。一方、東京高裁(平成25年3月13日判決)は、同州LPSは法人に該当すると判断し、国側逆転勝訴の判決を言い渡した。地裁レベルで判断が分かれた同州LPS訴訟は、控訴審でも判断が分かれることとなり、最終的な決着は最高裁に委ねられることとなった。特集では、各裁判所が示した法人該当性の判断基準や他の外国事業体への影響などをQ&A形式で解説する。
Q1
米国デラウェア州のLPSとは? 米国LPS訴訟で問題となっているLPSとはどのようなものなのでしょうか。
A LPSとは、個人や法人が共同出資者となって組成される事業体(共同出資組織)のことです。LPSは、不動産投資などに用いられることが多く、米国租税法では、LPSの出資者に対して課税が行われています(パススルー課税)。日本の組合と類似していますが、日本には存在しない法概念です。米国LPS訴訟を巡る一連の事案では、LPSが行う不動産賃貸業から発生した損失が、納税者(出資者)に帰属するか否かが問題となりました(事案の概要は今号7頁の参考、スキームの全体像は本誌437号5頁参照)。
Q2
米国LPS訴訟の最大の争点 米国LPS訴訟では、デラウェア州のLPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっているそうですが、法人か否かで納税者の課税関係にどのような違いが生じるのでしょうか。具体的に教えて下さい。
A デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当しないのであれば、LPSから生じた損失は、出資者である納税者に直接帰属(パススルー課税)するため、たとえば納税者の給与所得等と損益通算することにより、納税者は節税メリットを享受することができます。
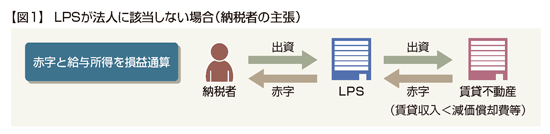
一方で、LPSが法人に該当するのであれば、LPSから生じた損失は、LPS本体に帰属するため、納税者側での損失計上は認められません。
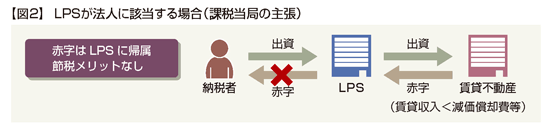 節税メリットを享受できる否かは、LPSが法人に該当するか否かにより決定されるため、一連の事案では、デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっていました。
節税メリットを享受できる否かは、LPSが法人に該当するか否かにより決定されるため、一連の事案では、デラウェア州LPSが日本の租税法上、法人に該当するか否かが最大の争点となっていました。Q3
各裁判所が示した法人該当性の判断基準 デラウェア州のLPSが法人に該当するか否かについて、裁判所はどのような判断を示したのでしょうか。
A まず、大阪地裁判決(平成22年12月17日)が、国側が主張する法人該当性の判断基準(①独自の財産を有するか否か、②権利義務の帰属主体となるか否か、③訴訟当事者となりえるか否か)を採用し、デラウェア州LPSは法人に該当すると判断しました。
しかし、その後に言い渡された東京地裁判決(平成23年7月19日)と名古屋地裁判決(平成23年12月14日)は、国側の判断基準を一蹴し、新たに「①外国法令により法人格を付与する旨が規定されているか否か、②損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否か」という判断基準を示し、デラウェア州LPSは法人に該当しないと判断しました。この判断基準は、名古屋地裁判決の控訴審である名古屋高裁判決(平成25年1月24日)においても支持されています。
ところが、先日言い渡された東京高裁判決(平成25年3月13日)は、原審の東京地裁判決が示した「判断基準② 損益の帰属すべき主体か否か」は不要であると指摘し、新たに、「外国法令で法人格を付与する旨を規定されているかどうかだけでなく、外国法令が事業体の設立、組織、運営、管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきである」という判断基準を示しました。そのうえで東京高裁判決は、デラウェア州LPSは法人に該当するとの判断を示しました(次頁表参照)。
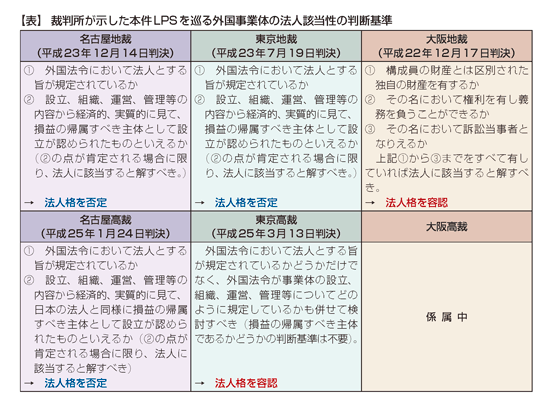
Q4
デラウェア州LPSとニューヨーク州LCCの相違点 米国ニューヨーク州のLLCについて、さいたま地裁判決(平成19年5月16日)とその控訴審である東京高裁判決(平成19年10月10日)は、ニューヨーク州LCCは法人に該当するとの判断を示しています。ニューヨーク州LCCと今回問題となったデラウェア州LPSの相違点を教えてください。
A ニューヨーク州LCC法のLCC(Limited Liability Company)は、パートナーシップ(Pertnership)という言葉が含まれず、外形的には「Company」に類するものとされています。また、デラウェア州LPSとの相違点として、ニューヨーク州LCCは、LCCから生じた損益が構成員に直ちに帰属せず、一定の部分のみが構成員に対する分配の対象になることを予定している点が挙げられます。
Q5
他の外国事業体への影響 外国法を準拠法とする事業体は、デラウェア州LPS以外にも存在します。各裁判所が示した法人該当性の判断基準は、他の外国事業体にも影響するのでしょうか。
A 米国LPSを巡る東京地裁判決(平成23年7月19日)と同様の判断基準(損益の帰属主体であるか否かなど)は、英国領バミューダ諸島の法律により組成されたLPSが法人に該当するか否かが争われた訴訟(平成24年8月30日判決)で採用されています。同訴訟の東京地裁は、バミューダ法に基づき組成されたLPSが日本の租税法上、法人に該当しないと判断しています(本誌472号40頁参照)。ただ、バミューダLPSを巡る訴訟は現在、東京高裁に係属中です。東京地裁判決(平成23年7月19日)の判断基準が控訴審(平成25年3月13日判決)で否定されていることを踏まえると、バミューダLPSの法人該当性を巡る控訴審の行方に注目が集まります。
Q6
海外LPS節税スキームは現在も有効か? 今回問題となった不動産投資事業を行う海外LPSを利用した節税スキームは、現在も有効なのでしょうか。
A 平成17年度税制改正により、民法上の組合契約、投資事業有限責任組合契約、外国におけるこれらに類似する契約に係る事業により発生した損失は、個人組合員の不動産所得の金額の計算上、その損失金額はなかったものとみなされる措置が講じられました(措法41条の4の2)。これにより、本事案のような海外LPSから発生した不動産損失を納税者の他の所得と損益通算する節税スキームは、封じ込められています。
なお、一連の訴訟では、改正措置法が適用される前の事案について、損益通算の可否ができるか否かが争われています。
| 【参考】事案の概要 |
| 納税者(居住者)は、外国信託銀行との信託契約を介して、米国デラウェア州のLPSに対して現金等を出資。LPSは、出資された資金と借入金を元手に米国内の不動産(中古集合住宅)を取得し、その賃貸業を営んでいた。 賃貸業は、当初の数年間は取得した不動産の減価償却費、借入金に係る支払利息が賃貸収入を上回ることから損失が発生。その発生した損失について、納税者は、LPSへの出資持分に応じた損失額が、LPSを介さずに納税者に直接帰属するとの前提のもと、給与所得等と損益通算をして確定申告を行っていた。これに対して、原処分庁は、LPSは日本の租税法上の法人に該当するため、LPSが行った不動産賃貸業の損益は、原告に直接帰属するものではないことなどを理由に、本件損失は、不動産所得の計算上生じた損失に該当せず、損益通算はできないとして、所得税の更正処分等を行っていた。 本事案では、この損益通算を否定した原処分庁の更正処分の適法性が争われるなかで、LPSが法人に該当するか否かが最大の争点となっている。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















