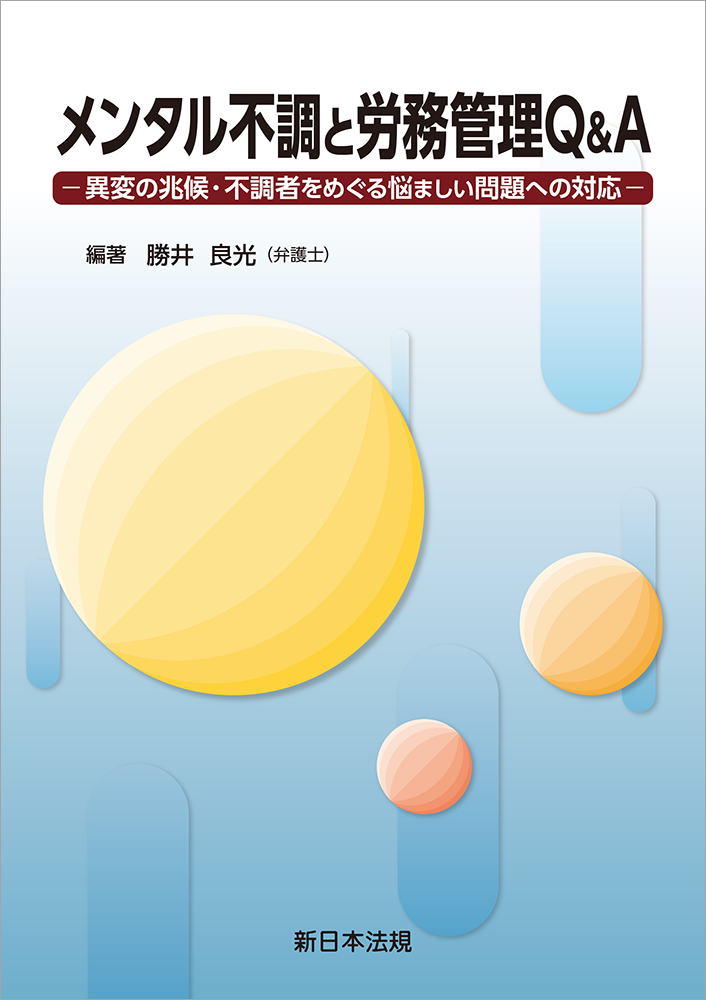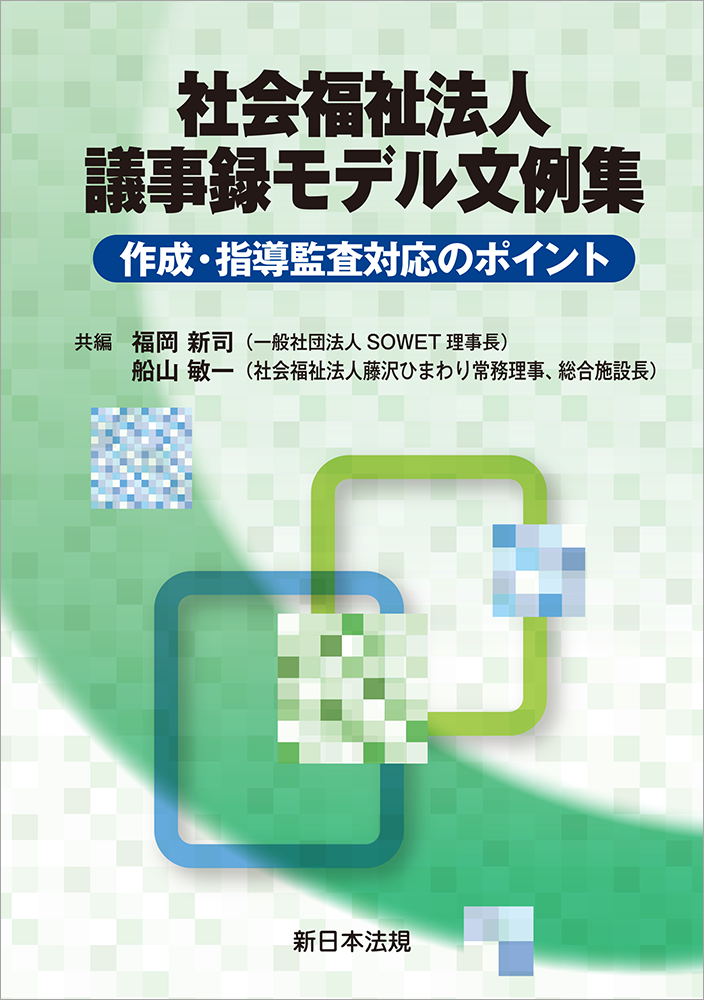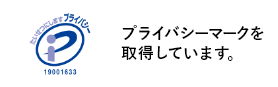解説記事2013年04月29日 【事例で学ぶ資産税】 「土地の無償返還届出書」と20%相当額の処理(2013年4月29日号・№497)
事例で学ぶ資産税
第3回
「土地の無償返還届出書」と20%相当額の処理
税理士 塩野入文雄
はじめに 今回は、「土地の無償返還に関する届出書」(以下、単に「届出書」とします)に関連した事例を取り上げます。具体的には、権利金などの一時金の授受がなく、通常の地代の授受により土地の賃貸借を行い、かつ、届出書を提出している場合における20%相当額の処理に関する2つの事例を設定しています(脚注1)。
ところで、本誌No.494(2013.4.8号)「ニュース特集」(4頁)に、今回のテーマに関連した裁決〔未公表〕に関する記事が掲載されています(脚注2)。Q1についての問題の所在は、その裁決の争点と同様のものと思われますが、少し視点を変えて、より日常的に多発していると思われる(また、看過されていることが少なくないと思われる)、別の事例により、20%相当額の処理に関する検討を行うこととします。
なお、事務処理に関する事例として、届出書が税務署に提出されているかどうかが不確実である場合における対応方法についても、Q3として触れています。
Q1 甲は、その同族会社であるA社に対して、通常の地代の授受により甲所有の宅地をA社の貸ビル建築のための敷地として賃貸し、かつ、税務署に届出書を提出した。甲が死亡したため、相続税の申告をすることになったが、甲が所有していたA社株式の純資産価額(相評)の算定に当たり、同社の資産に計上することとされている対象地の20%相当額から、貸ビルの敷地(貸家建付借地権)としての評価減を行うことはできますか。
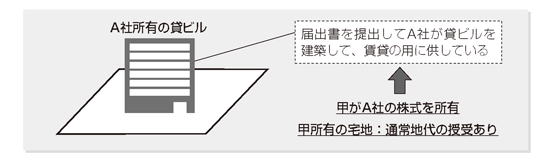
Q2 乙は、その同族会社であるB社に対して、通常の地代の授受により乙所有の雑種地をB社の資材置場の用に供するために賃貸し、かつ、税務署に届出書を提出した。乙が死亡したため、相続税の申告をすることになったが、対象地の評価に当たって、20%の減額を行うことができますか(相続開始時における賃貸借の残存期間は15年でした)。

Q3 税理士Xは、被相続人丙に関する相続税の申告を依頼された。Xが、丙の同族会社であるC社の決算書等を点検したところ、昭和50年代から、丙所有の宅地に係るC社から丙に対する通常の地代の支払があったが、C社に借地権等の資産計上はなく、また、権利金の認定課税を受けたような記録等も残っていない。届出書の税務署への提出の有無については、後継者(相続人)や社員の記憶も定かではなく、また、C社の従来からの関与税理士の事務所も代替わりをしており、事実関係を確認できなかった。
このような状況にあることから、Xは、丙所有の宅地を底地評価として申告することに不安を感じているが、届出書の提出の有無を税務署に確認できる方法はありませんか。
A1 A社の純資産価額(相評)に計上される20%相当額については、貸家(貸しビル)の敷地としての評価減はできないものと考えます〔20%相当額のままで、A社の株式評価額の算定を行うことになると考えます〕。
なお、前記裁決の詳細は不明ですが、20%相当額について、課税庁側の主張等に沿うと貸家建付借地権としての評価減を行うこととなり、納税者側の主張等に沿うと評価減を行わないことになるものと思われます。
A2 20%の評価減は出来ないと考えます。その雑種地を自用地(100%)として評価して申告を行うことになると考えます。
A3 「申告書等の閲覧サービス」を利用することによって、税務署の窓口において届出書の提出の有無を確認できます。なお、届出書が提出されている場合には、届出書を閲覧することができます。
解説 Q1について
1.問題の所在 対象地の賃貸借に当たって、通常の地代の授受があり(権利金等の授受なし)、かつ、届出書が提出されている場合には、昭和60年6月5日付の個別通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(以下、「相当地代通達」とします)の8項の定めによって、対象地の自用地(更地)評価額から20%減を行います。この際、その賃借人が土地所有者にとっての同族会社である場合には、その同族会社の株式評価における純資産価額(相評)の計算において、対象地の評価額から減額された20%相当額を資産に計上して算定することとされています。その資産への計上に当たって、A社が通常の借地権を保有している場合(脚注3)と同様に、「貸家建付借地権」として評価を行えるのか、すなわち、前記裁決の争点と同様に、その20%相当額の賃借権をどのように位置づけるのかとの問題があります(脚注4)。
2.前提整理―通達の定め― 相当地代通達の8項は、次のとおり定められています。
(注)アンダーラインは筆者が付したものです(以下の法令等の引用部分も同じです)。
また、昭和60年6月に相当地代通達が整備される前に、相当地代を授受している課税案件について、昭和43年10月28日付の個別通達「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(脚注5)(以下「昭和43年個別通達」とします)によって、その評価等の取扱いが定められ、その取扱いを定めた「理由」が、同通達に次のとおり示されています。
なお、この昭和43年個別通達は、上記相当地代通達において引用されていることから、相当地代通達8における80%評価(20%減)も同じ考え方に基づくものとして判断することになります。
Q1の事例に則して、この2つの個別通達について注視すべき点は、次の3点にあると考えます。
① 相当地代が授受されていることによって、課税上(法令137の趣旨)、借地権の価額が本来的には0である場合であっても、土地の賃貸借に伴う制約等を勘案して80%評価(20%減)を行うこと<昭和43年個別通達>(脚注7)。
② 当該評価を行うことの条件が、(a)借地権の設定と(b)届出書の提出という2つの事実関係に基づいていること<相当地代通達8>。
なお、この点については、Q2において検討を行います。
③ 80%評価(20%減)を行うことは土地評価上の問題(斟酌)であるところ、100%の顕現については、「課税の公平」の見地によるものであること<昭和43年個別通達>。
3.検 討 まず、事例検討の前提となる「基本的な考え方」として、筆者は、評価のあり方(時価の測定方法)と課税のあり方(課税の公平や妥当性の確保)とは、別の位相にあるものであって、区分して捉えるべきものと考えます(極論を述べるならば、両者を混同してしまうと、対象財産の時価測定が、どのようにでも行い得るものとなってしまうと考えられます(脚注8))。
このような視点でQ1の事例を検討すると、まず、A社が対象地の借地権を有しているという事実は揺るぎないものであり、その借地権の価額をどのように測定するかという視点に移行することになります。
この場合において、届出書の前提となっている対象地の賃貸借契約(借地契約書等)において、将来における無償返還が約されていることなどから(脚注9)、その土地の部分的譲渡に相当するような通常の借地権に比して、賃借人(A社)が有する権利は、極めて弱いものとなっています。しかしながら、甲所有の対象地にA社の賃借権が存すること、その「利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。」(昭和43年個別通達の上記「理由」)として、評価のあり方の視点に立った対象地に係る20%減が講じられているところです。
一方、A社の株式評価における純資産価額(相評)の算定における20%相当額のA社の資産への計上は、「課税の公平上適当」(昭和43年個別通達の上記「理由」)とされているものであって、被相続人甲に係る相続税の課税のあり方として措置されたもので、評価のあり方とは異なる位相にあるものとして捉えることになります。すなわち、A社が甲にとって、同族会社に該当しない場合には、20%相当額のA社の資産への計上は「無用」となっているところであり、賃借人が同族会社であるか否かによって、その処理を区々にすることは、評価のあり方として妥当でないものとして捉えられると考えられます(脚注10)。
また、20%相当額の計上は、甲とA社の同族関係に着目したものであり、評価のあり方の範疇に留まっているとの考え方もあり得ると思われます。しかしながら、然りであるとするならば、むしろ、そこで想定される取引は、A社の有する借地権を0としたものになると考えられます。また、財産評価基本通達1(2)の時価の意義における「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい」との定めにも合致しないことからも、評価のあり方の範疇にはなく、課税のあり方の範疇にあることが首肯されるものと考えられます〔このような視点からは、昭和43年個別通達の「理由」における前段は評価のあり方の範疇にあるものであり、後段は課税のあり方の範疇にあるものとして捉えられ、二者が併存している個別通達として認識されます〕。
4.結 論 上記のような意味において、相当地代通達8に定める20%相当額の評価会社の資産への計上については、文字どおり課税のあり方の見地から創出(付与)された価額であると認識することになると考えられます。
したがって、A社の資産に計上される20%相当額は、評価の範疇にはないものであり、例え、貸ビルの敷地であったとしても、貸家建付借地権としての評価減を織り込むことはできないものであると筆者は考えます〔すなわち、乙が所有している対象地の評価額が「個人と法人を通じて100%顕現する」(昭和43年個別通達の上記「理由」)との考えが維持されることになります〕。
Q2について
1.問題の所在―相続税と法人税における「借地権」の意義― 周知のように、相続税と法人税における「借地権」の意義が異なっています。
法人税においては、法人税法施行令137条に借地権の意義を「地上権又は土地の賃貸借をいう」との直接的な意義(定義)規定が設けられています(脚注11)。
一方、相続税においては、相続税法23条における地上権から「借地借家法(……)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(……)の地上権に該当するものを除く」とする間接的規定(地上権の法定評価からの適用除外規定)が設けられているにすぎません。しかしながら、この間接的規定を受けたものとなるのでしょうが、相続税の実務においては、借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」(借地借家法2一)(脚注12)ものと捉えられているところです。
したがって、このような両者の相違を受けて、相当地代通達における20%減は、届出書の対象地となっていた乙所有の雑種地の評価にも適用があるのではないかとの疑問が生じることになります。言い換えると、相当地代通達等において、借地権の意義は定められていないのであるから、届出書を定めた法人税基本通達(及び法人税法)における借地権の意義に沿って、20%の評価減をすべきではないかとの疑問が生じることになります。
2.検 討
(1)相当地代通達の解釈 相当地代通達における「借地権」の意義については、建物所有目的の賃借権等に限られるのか、それとも雑種地に係る賃借権も含まれるのか(雑種地の賃借権も法人税法施行令137条に定める「土地の賃借権」ではないか)という論点があります〔文理解釈上の議論としては、やや「水かけ論」となる一面があるものと思われます〕。
この場合、法人税における借地権については、相当に幅のあるものとなっている点に注視する必要があると考えます。すなわち、法人税法施行令137条は、いわゆる権利金等の認定課税に関して、次のとおり規定しています。
○ 法人税法施行令
このように、法人税におけるいわゆる認定課税の対象となり得るのは、権利金を収受する取引上の慣行がある場合に限られています。
しかしながら、前述したとおり、借地権のそのものの直接的な意義としては(権利金等の認定課税の有無の問題とは別に)、土地の所有権のいわば部分的譲渡にも相当するような建物所有目的の賃借権等から、一時的な土地の利用をもカバーしているものとなっています。このため、法人税基本通達13-1-5には、土地の使用目的が物品置場などの通常権利金の授受を行わない場合には権利金の認定課税を行わないとする留意の定めが設けられ、また、同通達13-1-14にも、借地権の無償返還を認容するケースとして、土地の使用目的が単に物品置場などとして土地を更地のまま使用している場合などが例示されています。
したがって、Q2において、乙及びB社が届出書を提出した背景は、おそらく、その賃貸借期間が長いなどの点を考慮した税務上の安全性を確保することを企図したものであるとは思われますが、結果論とはなってしまうものの、果たして、届出書の提出が必要なケースであったのかという疑問も生じてきます。換言すると、法人税においても、土地の賃貸借をする際などには、必ずしも全てのケースにおいて、届出書の提出を要するものとはなっていない、幅のある「借地権」として、その意義を捉える必要があると考えます(脚注13)。
(2)相続税評価(論)の見地から 一方、このような文理解釈(論)とは別に、相続税における評価バランスの視点からも、届出書が提出されている一事をもって、20%減額を行えるとの結論を出すことは早計であると考えます。
すなわち、賃借権の目的となっている雑種地の評価は、財産評価基本通達86の定めによることになりますが、同項(1)のロには、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権以外の目的となっている雑種地の評価について、Q2のように、残存期間15年であるならば、7.5%(※)の評価減を行うものとされています。
(※)評基通86(1)のロの定めによります。
① 評基通87の(2)による賃借権の価額
残存期間15年の法定地上権割合10%(相法23)×1/2=5%
② 評基通86(1)のイの(ロ)による割合
15%×1/2=7.5%
③ 「5%<7.5%」につき、7.5%を採用
したがって、借地権の意義を雑種地に係る賃借権を含み、また、届出書の提出があるとの事実のみをもって、20%減の対象とすることは、その結果が、「7.5%<20%」となることから見ても不適切なものと考えます。
もっとも、筆者は、このようなケースについては〔事実上、届出書の提出が無意味となっているケースについては〕、土地の賃貸借の事実があることを考慮した何らかの斟酌(若干の評価減)が必要ではないかとの議論はあり得るものと考えます(脚注14)。
3.その他 ところで、上記のような議論とは別に、対象地に係る借地権(狭義)の存否について検討する必要があるケースも想定されます。すなわち、それぞれの具体的な契約内容や対象地の利用状況に応じて、借地権が及んでいる範囲はどこまでなのかなどという検討が必要となる課税場面も想定されることに注意が必要です。
なお、対象地における借地権の存否が問題とされた事例を表1に取りまとめておきます(表1の「結果」欄の表示は、対象地に借地権が存することに関する結論を示しています)。

Q3について
1.問題意識 筆者が仄聞した事例としても、Q3のようなケースへの対応に当たって、税理士が届出書の提出が行われていなものと判断し、対象地を底地評価して相続税の申告を行ったところ、税務署側から届出書が提出されているとの指摘を受け、修正申告の必要に迫られたケースがあります。
税理士事務所や会社の管理態勢にもよりますが、継続的な関与先の事案であるならば、基本的には、このようなトラブルが生じることは稀であると思われます。しかしながら、相続税の申告については、いわゆる単発(飛び込み)で受任する場合も少なくないことから、このようなケースには慎重に対応することが必要と考えます。
2.税務署による資料情報の開示 厳格な守秘義務と公文書管理が行われていると思われる税務署が保有している資料情報について、納税者が開示を受ける方法としては、表2のとおり、①個人情報開示請求と②申告書等閲覧サービスの2つのものがあります(脚注16)。
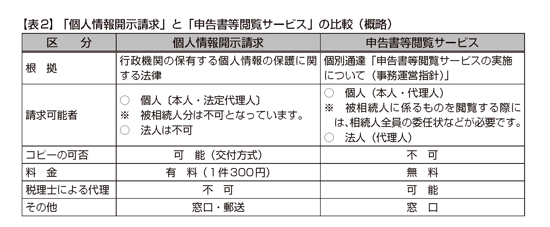
3.具体的な対応 Q3の事例においては、既に丙が亡くなっていますので、個人情報開示請求を行うことができません。したがって、丙の相続人としての立場、あるいはC社の立場から、申告書等閲覧サービスを利用して、届出書の提出の有無や記載内容等を確認することになります。
ちなみに、丙の生前であれば、個人情報開示請求制度を利用し、届出書が提出されていた場合、その写しを入手することができたところです(脚注17)。
脚注
1 借地権の課税関係については、最近ではやや沈静化しているものと思われますが、かっては、活発な議論が交わされていました。
白崎浅吉「借地権の税制をめぐる若干の考察(承前)」(税大論叢8号・昭和49.9月)、同「借地権の税制をめぐる若干の考察」(税大論叢7号・昭和48.3月)、同「借地権課税80年のあゆみ」(税大論叢6号・昭和47.7月:税大HPに掲載あり)などを参照してください。
2 上記の本誌の記事によると、土地保有特定会社の判定における土地の保有割合を算定する際に、通常の地代の授受があり、かつ、届出書が提出されていたケースにおける株式評価の純資産価額(相評)の計算上、20%相当額をその計算の基礎に織り込むべきか否かを争点とするものです。
3 厳密には、A社が有する借地権についての通常の借地権価額ということになります。
4 筆者が仄聞したところ(限られた範囲ですが)、20%相当額を基礎として貸家建付借地権評価を行って申告しているケースも少なからずあるようであり、また、税務署側も株式の所有割合の影響もあったのか、問題視されないケースがあるようです。
5 この昭和43年個別通達は、東京国税局長からの上申(照会)に対する国税庁長官の指示通達となっています。
6 現在の路線価図等においても、10%きざみで決定されている借地権割合の最低割合は、30%となっています。
7 このような控除項目(減額)に関する最低保障は、評基通86(1)のただし書きなどにも定められています。
8 換言すると、相続税法22条の規定から逸脱することになります。
無論、筆者も財産評価基本通達に基づく評価方法が、純粋な意味における時価測定であるとは考えていませんが、「課税評価」の範疇にはあるべきものと考えます。
9 法基通13-1-7参照
10 例えば、株式評価にける同族会社、同族株主か否かによって、株主の態様が区分され、適用される評価方式が原則的評価方式によるか配当還元方式によるのかとの判定(評基通188)とも異なるものであると考えられます。
11 法人税法施行令138条における借地権の意義は、「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」とされています。
12 旧借地法第1条においても、「本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ」と規定されていました。
13 建物所有を目的とするような土地の賃貸借などは別として、必ずしも「権利金等の支払いなしの通常地代による土地の賃貸借=要届出書の提出」とはならない点に注意が必要と考えます。
14 しかしながら、実際的な対応としては、税務署側が、届出書が提出されているという一事をもって(納税者側における100%評価のアグリーメントがあったなど)、そのような申告を否認してくることが十分に予想されます。
15 神谷光春「判例・裁決例に見る 土地評価の実務」191頁(新日本法規)参照
16 具体的内容や手続などについては、国税庁HPの掲載情報を参照してください。
① 個人情報開示請求:調達・その他情報>個人情報の保護>個人情報の保護に関する手続等について
② 申告書等閲覧サービス:税について調べる>事務運営指針>申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
17 届出書の提出とは別の事例ですが、筆者が仄聞したケースを参考までに付記しておきます。
(a)過去の所得税の申告書の控から今回売却しようとしている物件が買換え特例を適用して取得したものであることが明らかであった。しかしながら、保存されている資料では、引継取得価額の計算がどのように行われたのかが不詳であった。
(b)このため、関与税理士は、納税者本人に依頼して、旧物件を譲渡した際に申告書を提出した当時の所轄税務署と現在の所轄税務署に対して、引継取得価額に関する資料情報の開示請求をそれぞれに行った。
(c)両税務署長から、「開示請求に係る個人情報は作成しておらず、保有していないため、不開示とした。」との通知を受けた。
(d)このような通知を税務署側から受けたが、当該税理士は、実際の取得価額によることなく、一部不明な事項も踏まえつつ、引継取得価額を再計算して、買換え特例を適用して取得した物件の売却としての申告を行った。
第3回
「土地の無償返還届出書」と20%相当額の処理
税理士 塩野入文雄
はじめに 今回は、「土地の無償返還に関する届出書」(以下、単に「届出書」とします)に関連した事例を取り上げます。具体的には、権利金などの一時金の授受がなく、通常の地代の授受により土地の賃貸借を行い、かつ、届出書を提出している場合における20%相当額の処理に関する2つの事例を設定しています(脚注1)。
ところで、本誌No.494(2013.4.8号)「ニュース特集」(4頁)に、今回のテーマに関連した裁決〔未公表〕に関する記事が掲載されています(脚注2)。Q1についての問題の所在は、その裁決の争点と同様のものと思われますが、少し視点を変えて、より日常的に多発していると思われる(また、看過されていることが少なくないと思われる)、別の事例により、20%相当額の処理に関する検討を行うこととします。
なお、事務処理に関する事例として、届出書が税務署に提出されているかどうかが不確実である場合における対応方法についても、Q3として触れています。
Q1 甲は、その同族会社であるA社に対して、通常の地代の授受により甲所有の宅地をA社の貸ビル建築のための敷地として賃貸し、かつ、税務署に届出書を提出した。甲が死亡したため、相続税の申告をすることになったが、甲が所有していたA社株式の純資産価額(相評)の算定に当たり、同社の資産に計上することとされている対象地の20%相当額から、貸ビルの敷地(貸家建付借地権)としての評価減を行うことはできますか。
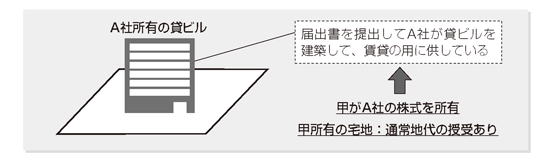
Q2 乙は、その同族会社であるB社に対して、通常の地代の授受により乙所有の雑種地をB社の資材置場の用に供するために賃貸し、かつ、税務署に届出書を提出した。乙が死亡したため、相続税の申告をすることになったが、対象地の評価に当たって、20%の減額を行うことができますか(相続開始時における賃貸借の残存期間は15年でした)。

Q3 税理士Xは、被相続人丙に関する相続税の申告を依頼された。Xが、丙の同族会社であるC社の決算書等を点検したところ、昭和50年代から、丙所有の宅地に係るC社から丙に対する通常の地代の支払があったが、C社に借地権等の資産計上はなく、また、権利金の認定課税を受けたような記録等も残っていない。届出書の税務署への提出の有無については、後継者(相続人)や社員の記憶も定かではなく、また、C社の従来からの関与税理士の事務所も代替わりをしており、事実関係を確認できなかった。
このような状況にあることから、Xは、丙所有の宅地を底地評価として申告することに不安を感じているが、届出書の提出の有無を税務署に確認できる方法はありませんか。
A1 A社の純資産価額(相評)に計上される20%相当額については、貸家(貸しビル)の敷地としての評価減はできないものと考えます〔20%相当額のままで、A社の株式評価額の算定を行うことになると考えます〕。
なお、前記裁決の詳細は不明ですが、20%相当額について、課税庁側の主張等に沿うと貸家建付借地権としての評価減を行うこととなり、納税者側の主張等に沿うと評価減を行わないことになるものと思われます。
A2 20%の評価減は出来ないと考えます。その雑種地を自用地(100%)として評価して申告を行うことになると考えます。
A3 「申告書等の閲覧サービス」を利用することによって、税務署の窓口において届出書の提出の有無を確認できます。なお、届出書が提出されている場合には、届出書を閲覧することができます。
解説 Q1について
1.問題の所在 対象地の賃貸借に当たって、通常の地代の授受があり(権利金等の授受なし)、かつ、届出書が提出されている場合には、昭和60年6月5日付の個別通達「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(以下、「相当地代通達」とします)の8項の定めによって、対象地の自用地(更地)評価額から20%減を行います。この際、その賃借人が土地所有者にとっての同族会社である場合には、その同族会社の株式評価における純資産価額(相評)の計算において、対象地の評価額から減額された20%相当額を資産に計上して算定することとされています。その資産への計上に当たって、A社が通常の借地権を保有している場合(脚注3)と同様に、「貸家建付借地権」として評価を行えるのか、すなわち、前記裁決の争点と同様に、その20%相当額の賃借権をどのように位置づけるのかとの問題があります(脚注4)。
2.前提整理―通達の定め― 相当地代通達の8項は、次のとおり定められています。
| (「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価) 8 借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。 なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。 (注)使用貸借に係る土地について無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額によって評価するのであるから留意する。 |
(注)アンダーラインは筆者が付したものです(以下の法令等の引用部分も同じです)。
また、昭和60年6月に相当地代通達が整備される前に、相当地代を授受している課税案件について、昭和43年10月28日付の個別通達「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(脚注5)(以下「昭和43年個別通達」とします)によって、その評価等の取扱いが定められ、その取扱いを定めた「理由」が、同通達に次のとおり示されています。
なお、この昭和43年個別通達は、上記相当地代通達において引用されていることから、相当地代通達8における80%評価(20%減)も同じ考え方に基づくものとして判断することになります。
| (理由) 地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である(脚注6)。 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有するⅠ株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである。 |
Q1の事例に則して、この2つの個別通達について注視すべき点は、次の3点にあると考えます。
① 相当地代が授受されていることによって、課税上(法令137の趣旨)、借地権の価額が本来的には0である場合であっても、土地の賃貸借に伴う制約等を勘案して80%評価(20%減)を行うこと<昭和43年個別通達>(脚注7)。
② 当該評価を行うことの条件が、(a)借地権の設定と(b)届出書の提出という2つの事実関係に基づいていること<相当地代通達8>。
なお、この点については、Q2において検討を行います。
③ 80%評価(20%減)を行うことは土地評価上の問題(斟酌)であるところ、100%の顕現については、「課税の公平」の見地によるものであること<昭和43年個別通達>。
3.検 討 まず、事例検討の前提となる「基本的な考え方」として、筆者は、評価のあり方(時価の測定方法)と課税のあり方(課税の公平や妥当性の確保)とは、別の位相にあるものであって、区分して捉えるべきものと考えます(極論を述べるならば、両者を混同してしまうと、対象財産の時価測定が、どのようにでも行い得るものとなってしまうと考えられます(脚注8))。
このような視点でQ1の事例を検討すると、まず、A社が対象地の借地権を有しているという事実は揺るぎないものであり、その借地権の価額をどのように測定するかという視点に移行することになります。
この場合において、届出書の前提となっている対象地の賃貸借契約(借地契約書等)において、将来における無償返還が約されていることなどから(脚注9)、その土地の部分的譲渡に相当するような通常の借地権に比して、賃借人(A社)が有する権利は、極めて弱いものとなっています。しかしながら、甲所有の対象地にA社の賃借権が存すること、その「利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。」(昭和43年個別通達の上記「理由」)として、評価のあり方の視点に立った対象地に係る20%減が講じられているところです。
一方、A社の株式評価における純資産価額(相評)の算定における20%相当額のA社の資産への計上は、「課税の公平上適当」(昭和43年個別通達の上記「理由」)とされているものであって、被相続人甲に係る相続税の課税のあり方として措置されたもので、評価のあり方とは異なる位相にあるものとして捉えることになります。すなわち、A社が甲にとって、同族会社に該当しない場合には、20%相当額のA社の資産への計上は「無用」となっているところであり、賃借人が同族会社であるか否かによって、その処理を区々にすることは、評価のあり方として妥当でないものとして捉えられると考えられます(脚注10)。
また、20%相当額の計上は、甲とA社の同族関係に着目したものであり、評価のあり方の範疇に留まっているとの考え方もあり得ると思われます。しかしながら、然りであるとするならば、むしろ、そこで想定される取引は、A社の有する借地権を0としたものになると考えられます。また、財産評価基本通達1(2)の時価の意義における「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい」との定めにも合致しないことからも、評価のあり方の範疇にはなく、課税のあり方の範疇にあることが首肯されるものと考えられます〔このような視点からは、昭和43年個別通達の「理由」における前段は評価のあり方の範疇にあるものであり、後段は課税のあり方の範疇にあるものとして捉えられ、二者が併存している個別通達として認識されます〕。
4.結 論 上記のような意味において、相当地代通達8に定める20%相当額の評価会社の資産への計上については、文字どおり課税のあり方の見地から創出(付与)された価額であると認識することになると考えられます。
したがって、A社の資産に計上される20%相当額は、評価の範疇にはないものであり、例え、貸ビルの敷地であったとしても、貸家建付借地権としての評価減を織り込むことはできないものであると筆者は考えます〔すなわち、乙が所有している対象地の評価額が「個人と法人を通じて100%顕現する」(昭和43年個別通達の上記「理由」)との考えが維持されることになります〕。
Q2について
1.問題の所在―相続税と法人税における「借地権」の意義― 周知のように、相続税と法人税における「借地権」の意義が異なっています。
法人税においては、法人税法施行令137条に借地権の意義を「地上権又は土地の賃貸借をいう」との直接的な意義(定義)規定が設けられています(脚注11)。
一方、相続税においては、相続税法23条における地上権から「借地借家法(……)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(……)の地上権に該当するものを除く」とする間接的規定(地上権の法定評価からの適用除外規定)が設けられているにすぎません。しかしながら、この間接的規定を受けたものとなるのでしょうが、相続税の実務においては、借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」(借地借家法2一)(脚注12)ものと捉えられているところです。
したがって、このような両者の相違を受けて、相当地代通達における20%減は、届出書の対象地となっていた乙所有の雑種地の評価にも適用があるのではないかとの疑問が生じることになります。言い換えると、相当地代通達等において、借地権の意義は定められていないのであるから、届出書を定めた法人税基本通達(及び法人税法)における借地権の意義に沿って、20%の評価減をすべきではないかとの疑問が生じることになります。
2.検 討
(1)相当地代通達の解釈 相当地代通達における「借地権」の意義については、建物所有目的の賃借権等に限られるのか、それとも雑種地に係る賃借権も含まれるのか(雑種地の賃借権も法人税法施行令137条に定める「土地の賃借権」ではないか)という論点があります〔文理解釈上の議論としては、やや「水かけ論」となる一面があるものと思われます〕。
この場合、法人税における借地権については、相当に幅のあるものとなっている点に注視する必要があると考えます。すなわち、法人税法施行令137条は、いわゆる権利金等の認定課税に関して、次のとおり規定しています。
○ 法人税法施行令
| 第137条 ……その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあっては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(……)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。 |
このように、法人税におけるいわゆる認定課税の対象となり得るのは、権利金を収受する取引上の慣行がある場合に限られています。
しかしながら、前述したとおり、借地権のそのものの直接的な意義としては(権利金等の認定課税の有無の問題とは別に)、土地の所有権のいわば部分的譲渡にも相当するような建物所有目的の賃借権等から、一時的な土地の利用をもカバーしているものとなっています。このため、法人税基本通達13-1-5には、土地の使用目的が物品置場などの通常権利金の授受を行わない場合には権利金の認定課税を行わないとする留意の定めが設けられ、また、同通達13-1-14にも、借地権の無償返還を認容するケースとして、土地の使用目的が単に物品置場などとして土地を更地のまま使用している場合などが例示されています。
したがって、Q2において、乙及びB社が届出書を提出した背景は、おそらく、その賃貸借期間が長いなどの点を考慮した税務上の安全性を確保することを企図したものであるとは思われますが、結果論とはなってしまうものの、果たして、届出書の提出が必要なケースであったのかという疑問も生じてきます。換言すると、法人税においても、土地の賃貸借をする際などには、必ずしも全てのケースにおいて、届出書の提出を要するものとはなっていない、幅のある「借地権」として、その意義を捉える必要があると考えます(脚注13)。
(2)相続税評価(論)の見地から 一方、このような文理解釈(論)とは別に、相続税における評価バランスの視点からも、届出書が提出されている一事をもって、20%減額を行えるとの結論を出すことは早計であると考えます。
すなわち、賃借権の目的となっている雑種地の評価は、財産評価基本通達86の定めによることになりますが、同項(1)のロには、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権以外の目的となっている雑種地の評価について、Q2のように、残存期間15年であるならば、7.5%(※)の評価減を行うものとされています。
(※)評基通86(1)のロの定めによります。
① 評基通87の(2)による賃借権の価額
残存期間15年の法定地上権割合10%(相法23)×1/2=5%
② 評基通86(1)のイの(ロ)による割合
15%×1/2=7.5%
③ 「5%<7.5%」につき、7.5%を採用
したがって、借地権の意義を雑種地に係る賃借権を含み、また、届出書の提出があるとの事実のみをもって、20%減の対象とすることは、その結果が、「7.5%<20%」となることから見ても不適切なものと考えます。
もっとも、筆者は、このようなケースについては〔事実上、届出書の提出が無意味となっているケースについては〕、土地の賃貸借の事実があることを考慮した何らかの斟酌(若干の評価減)が必要ではないかとの議論はあり得るものと考えます(脚注14)。
3.その他 ところで、上記のような議論とは別に、対象地に係る借地権(狭義)の存否について検討する必要があるケースも想定されます。すなわち、それぞれの具体的な契約内容や対象地の利用状況に応じて、借地権が及んでいる範囲はどこまでなのかなどという検討が必要となる課税場面も想定されることに注意が必要です。
なお、対象地における借地権の存否が問題とされた事例を表1に取りまとめておきます(表1の「結果」欄の表示は、対象地に借地権が存することに関する結論を示しています)。

Q3について
1.問題意識 筆者が仄聞した事例としても、Q3のようなケースへの対応に当たって、税理士が届出書の提出が行われていなものと判断し、対象地を底地評価して相続税の申告を行ったところ、税務署側から届出書が提出されているとの指摘を受け、修正申告の必要に迫られたケースがあります。
税理士事務所や会社の管理態勢にもよりますが、継続的な関与先の事案であるならば、基本的には、このようなトラブルが生じることは稀であると思われます。しかしながら、相続税の申告については、いわゆる単発(飛び込み)で受任する場合も少なくないことから、このようなケースには慎重に対応することが必要と考えます。
2.税務署による資料情報の開示 厳格な守秘義務と公文書管理が行われていると思われる税務署が保有している資料情報について、納税者が開示を受ける方法としては、表2のとおり、①個人情報開示請求と②申告書等閲覧サービスの2つのものがあります(脚注16)。
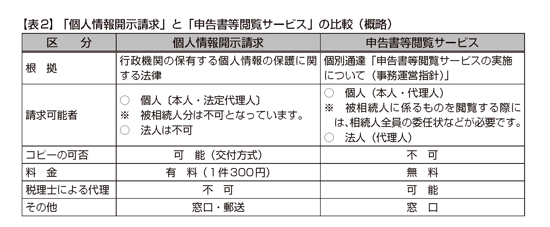
3.具体的な対応 Q3の事例においては、既に丙が亡くなっていますので、個人情報開示請求を行うことができません。したがって、丙の相続人としての立場、あるいはC社の立場から、申告書等閲覧サービスを利用して、届出書の提出の有無や記載内容等を確認することになります。
ちなみに、丙の生前であれば、個人情報開示請求制度を利用し、届出書が提出されていた場合、その写しを入手することができたところです(脚注17)。
脚注
1 借地権の課税関係については、最近ではやや沈静化しているものと思われますが、かっては、活発な議論が交わされていました。
白崎浅吉「借地権の税制をめぐる若干の考察(承前)」(税大論叢8号・昭和49.9月)、同「借地権の税制をめぐる若干の考察」(税大論叢7号・昭和48.3月)、同「借地権課税80年のあゆみ」(税大論叢6号・昭和47.7月:税大HPに掲載あり)などを参照してください。
2 上記の本誌の記事によると、土地保有特定会社の判定における土地の保有割合を算定する際に、通常の地代の授受があり、かつ、届出書が提出されていたケースにおける株式評価の純資産価額(相評)の計算上、20%相当額をその計算の基礎に織り込むべきか否かを争点とするものです。
3 厳密には、A社が有する借地権についての通常の借地権価額ということになります。
4 筆者が仄聞したところ(限られた範囲ですが)、20%相当額を基礎として貸家建付借地権評価を行って申告しているケースも少なからずあるようであり、また、税務署側も株式の所有割合の影響もあったのか、問題視されないケースがあるようです。
5 この昭和43年個別通達は、東京国税局長からの上申(照会)に対する国税庁長官の指示通達となっています。
6 現在の路線価図等においても、10%きざみで決定されている借地権割合の最低割合は、30%となっています。
7 このような控除項目(減額)に関する最低保障は、評基通86(1)のただし書きなどにも定められています。
8 換言すると、相続税法22条の規定から逸脱することになります。
無論、筆者も財産評価基本通達に基づく評価方法が、純粋な意味における時価測定であるとは考えていませんが、「課税評価」の範疇にはあるべきものと考えます。
9 法基通13-1-7参照
10 例えば、株式評価にける同族会社、同族株主か否かによって、株主の態様が区分され、適用される評価方式が原則的評価方式によるか配当還元方式によるのかとの判定(評基通188)とも異なるものであると考えられます。
11 法人税法施行令138条における借地権の意義は、「建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」とされています。
12 旧借地法第1条においても、「本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ」と規定されていました。
13 建物所有を目的とするような土地の賃貸借などは別として、必ずしも「権利金等の支払いなしの通常地代による土地の賃貸借=要届出書の提出」とはならない点に注意が必要と考えます。
14 しかしながら、実際的な対応としては、税務署側が、届出書が提出されているという一事をもって(納税者側における100%評価のアグリーメントがあったなど)、そのような申告を否認してくることが十分に予想されます。
15 神谷光春「判例・裁決例に見る 土地評価の実務」191頁(新日本法規)参照
16 具体的内容や手続などについては、国税庁HPの掲載情報を参照してください。
① 個人情報開示請求:調達・その他情報>個人情報の保護>個人情報の保護に関する手続等について
② 申告書等閲覧サービス:税について調べる>事務運営指針>申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
17 届出書の提出とは別の事例ですが、筆者が仄聞したケースを参考までに付記しておきます。
(a)過去の所得税の申告書の控から今回売却しようとしている物件が買換え特例を適用して取得したものであることが明らかであった。しかしながら、保存されている資料では、引継取得価額の計算がどのように行われたのかが不詳であった。
(b)このため、関与税理士は、納税者本人に依頼して、旧物件を譲渡した際に申告書を提出した当時の所轄税務署と現在の所轄税務署に対して、引継取得価額に関する資料情報の開示請求をそれぞれに行った。
(c)両税務署長から、「開示請求に係る個人情報は作成しておらず、保有していないため、不開示とした。」との通知を受けた。
(d)このような通知を税務署側から受けたが、当該税理士は、実際の取得価額によることなく、一部不明な事項も踏まえつつ、引継取得価額を再計算して、買換え特例を適用して取得した物件の売却としての申告を行った。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -