コラム2013年11月04日 【SCOPE】 特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟で税理士が一部敗訴(2013年11月4日号・№522)
過少申告加算税・延滞税を損害と認定
特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟で税理士が一部敗訴
個人の特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟で税理士が一部敗訴する事案があった(東京地裁平成25年9月9日判決)。買換資産を取得期限までに取得できなかった場合に必要とされる修正申告書の提出を税理士(被告)が怠ったため、過少申告加算税など約90万円が原告(納税者)に賦課されたことが発端となった事案だ。裁判所は、税理士の過失を一部認めたうえで、税理士に対して約90万円の損害賠償を命じている。なお、本事案では、法人の特定資産の買換特例を巡り、原告が代表取締役を務める原告会社の買換特例に係る修正申告についても、税理士に対して税賠訴訟が提起されていたが、こちらは税理士が勝訴する結果となっている。スコープでは、特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟を紹介する。
買換資産の取得が間に合わない場合の修正申告、顧問税理士が失念
個人が、含み益のある特定資産を譲渡して、一定の要件に該当する土地、建物などを取得して事業の用に供した場合には、その譲渡益の80%相当額の課税を将来に繰り延べることができる(措置法37条①、④参照)。
ただ、買換資産は、特定資産を譲渡した日の属する年の翌年中に取得し、その取得日から1年以内に事業の用に供しなければならない。
この期限内に買換資産を取得できない場合は、含み益のある特定資産の譲渡について、譲渡益の課税を繰り延べることができず、修正申告書を提出したうえ、繰り延べられた所得税を納付しなければならない。
今回紹介する事案は、納税者(原告)が、顧問税理士(被告)に対して、取得期限までに買換資産を取得できなかったことについて、修正申告書を提出すべき義務があったのにもかかわらずこれを怠ったとして、修正申告の結果生じた過少申告加算税など約90万円の損害賠償を求めていたものだ(修正申告までの経緯は図1参照)。
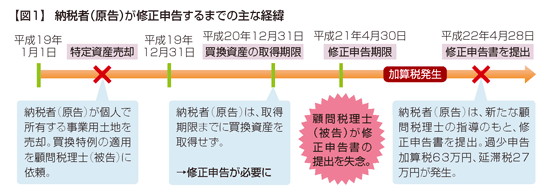 過少申告加算税など約90万円の賠償命令
納税者(原告)の主張に対して、裁判所は、被告であるが税理士が修正申告を失念したことを訴訟のなかで認めているため、税理士は修正申告に係る過少申告加算税・延滞税に相当する約90万円を支払う義務あるとの判断を示した。この点、顧問税理士の過失を裁判所が認めた格好となった。
過少申告加算税など約90万円の賠償命令
納税者(原告)の主張に対して、裁判所は、被告であるが税理士が修正申告を失念したことを訴訟のなかで認めているため、税理士は修正申告に係る過少申告加算税・延滞税に相当する約90万円を支払う義務あるとの判断を示した。この点、顧問税理士の過失を裁判所が認めた格好となった。
法定外の再延長申請、顧問税理士は認められない可能性が高いと説明
また、今回の事案では、特定資産の買換特例を巡り、原告個人だけでなく、原告が代表取締役を務める原告会社の買換特例に係る修正申告についても、顧問税理士(被告)に対して税賠訴訟が提起されていた。
具体的にみると、顧問税理士は、原告会社が買換資産を延長後の取得期限までに取得できない見込みであったことから、取得期限の再延長を税務署に対して申請していた。
ただ、顧問税理士は、この再延長の申請が法令に基づくものではないため、原告会社に対して再延長の申請は認められない可能性がある旨の説明を行っていた(その後、顧問税理士は原告会社との税務顧問委任契約を平成21年6月4日付で解約している)。
申請を受け、税務署は、再延長の申請を認めない旨の連絡を原告会社と後任の税理士に対して行った。その後、原告会社と後任の税理士は、税務署の指導のもと、買換資産を延長後の取得期限までに取得したものとした修正申告書を提出していたが、このとき過少申告加算税等が約500万円発生していた(修正申告までの経緯は図2参照)。
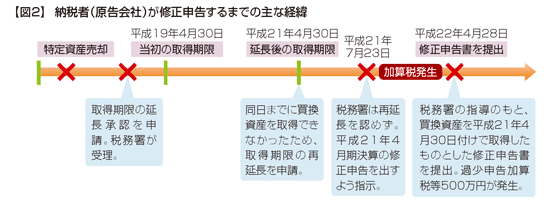
顧問税理士に説明義務違反は認められない 原告会社は、修正申告により発生した約500万円の過少申告加算税等について、再延長の申請が認められない場合の具体的な事後処理を連絡すべき義務を怠ったとして、顧問税理士(被告)に対して損害賠償を請求していた。
しかし、裁判所は、顧問税理士(被告)は原告会社に対して、再延長の申請が認められない可能性があることおよび修正申告が必要となるので、その場合は新しい税理士に相談するよう説明していたことなどを指摘。顧問税理士(被告)に説明義務違反は認められないとして、原告会社の請求を斥けた。
特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟で税理士が一部敗訴
個人の特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟で税理士が一部敗訴する事案があった(東京地裁平成25年9月9日判決)。買換資産を取得期限までに取得できなかった場合に必要とされる修正申告書の提出を税理士(被告)が怠ったため、過少申告加算税など約90万円が原告(納税者)に賦課されたことが発端となった事案だ。裁判所は、税理士の過失を一部認めたうえで、税理士に対して約90万円の損害賠償を命じている。なお、本事案では、法人の特定資産の買換特例を巡り、原告が代表取締役を務める原告会社の買換特例に係る修正申告についても、税理士に対して税賠訴訟が提起されていたが、こちらは税理士が勝訴する結果となっている。スコープでは、特定資産の買換特例を巡る税賠訴訟を紹介する。
買換資産の取得が間に合わない場合の修正申告、顧問税理士が失念
個人が、含み益のある特定資産を譲渡して、一定の要件に該当する土地、建物などを取得して事業の用に供した場合には、その譲渡益の80%相当額の課税を将来に繰り延べることができる(措置法37条①、④参照)。
ただ、買換資産は、特定資産を譲渡した日の属する年の翌年中に取得し、その取得日から1年以内に事業の用に供しなければならない。
この期限内に買換資産を取得できない場合は、含み益のある特定資産の譲渡について、譲渡益の課税を繰り延べることができず、修正申告書を提出したうえ、繰り延べられた所得税を納付しなければならない。
今回紹介する事案は、納税者(原告)が、顧問税理士(被告)に対して、取得期限までに買換資産を取得できなかったことについて、修正申告書を提出すべき義務があったのにもかかわらずこれを怠ったとして、修正申告の結果生じた過少申告加算税など約90万円の損害賠償を求めていたものだ(修正申告までの経緯は図1参照)。
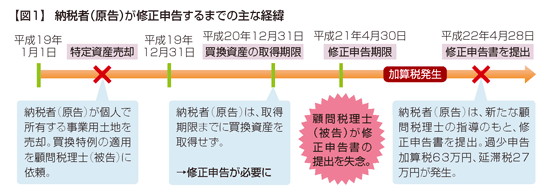 過少申告加算税など約90万円の賠償命令
納税者(原告)の主張に対して、裁判所は、被告であるが税理士が修正申告を失念したことを訴訟のなかで認めているため、税理士は修正申告に係る過少申告加算税・延滞税に相当する約90万円を支払う義務あるとの判断を示した。この点、顧問税理士の過失を裁判所が認めた格好となった。
過少申告加算税など約90万円の賠償命令
納税者(原告)の主張に対して、裁判所は、被告であるが税理士が修正申告を失念したことを訴訟のなかで認めているため、税理士は修正申告に係る過少申告加算税・延滞税に相当する約90万円を支払う義務あるとの判断を示した。この点、顧問税理士の過失を裁判所が認めた格好となった。法定外の再延長申請、顧問税理士は認められない可能性が高いと説明
また、今回の事案では、特定資産の買換特例を巡り、原告個人だけでなく、原告が代表取締役を務める原告会社の買換特例に係る修正申告についても、顧問税理士(被告)に対して税賠訴訟が提起されていた。
具体的にみると、顧問税理士は、原告会社が買換資産を延長後の取得期限までに取得できない見込みであったことから、取得期限の再延長を税務署に対して申請していた。
ただ、顧問税理士は、この再延長の申請が法令に基づくものではないため、原告会社に対して再延長の申請は認められない可能性がある旨の説明を行っていた(その後、顧問税理士は原告会社との税務顧問委任契約を平成21年6月4日付で解約している)。
申請を受け、税務署は、再延長の申請を認めない旨の連絡を原告会社と後任の税理士に対して行った。その後、原告会社と後任の税理士は、税務署の指導のもと、買換資産を延長後の取得期限までに取得したものとした修正申告書を提出していたが、このとき過少申告加算税等が約500万円発生していた(修正申告までの経緯は図2参照)。
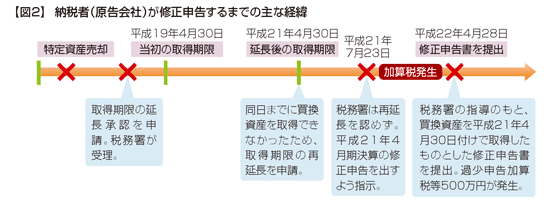
顧問税理士に説明義務違反は認められない 原告会社は、修正申告により発生した約500万円の過少申告加算税等について、再延長の申請が認められない場合の具体的な事後処理を連絡すべき義務を怠ったとして、顧問税理士(被告)に対して損害賠償を請求していた。
しかし、裁判所は、顧問税理士(被告)は原告会社に対して、再延長の申請が認められない可能性があることおよび修正申告が必要となるので、その場合は新しい税理士に相談するよう説明していたことなどを指摘。顧問税理士(被告)に説明義務違反は認められないとして、原告会社の請求を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























