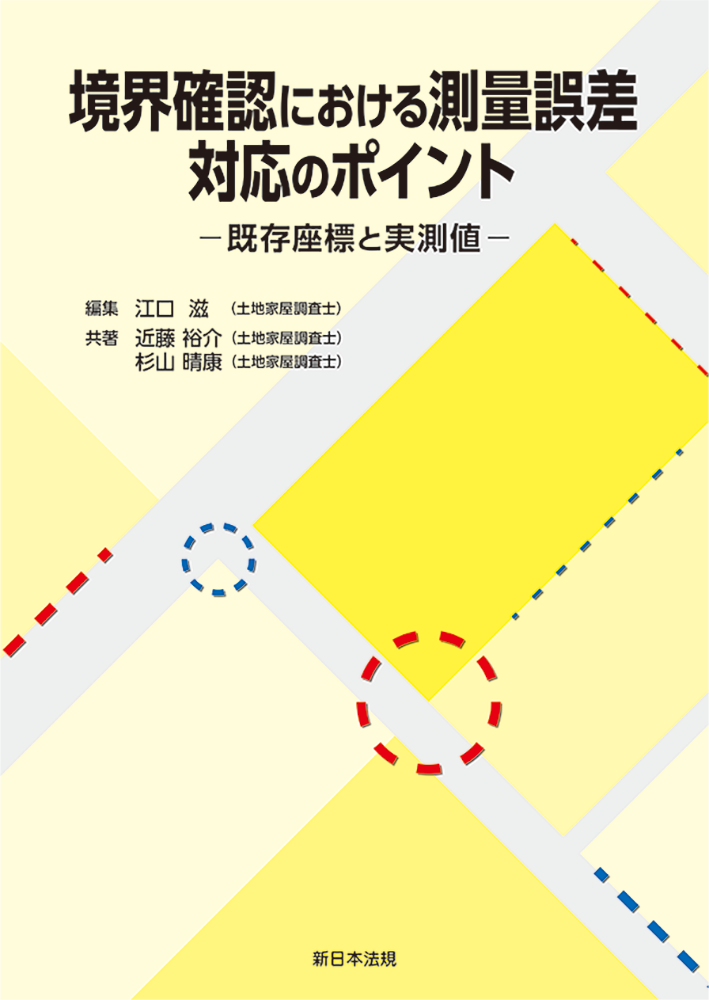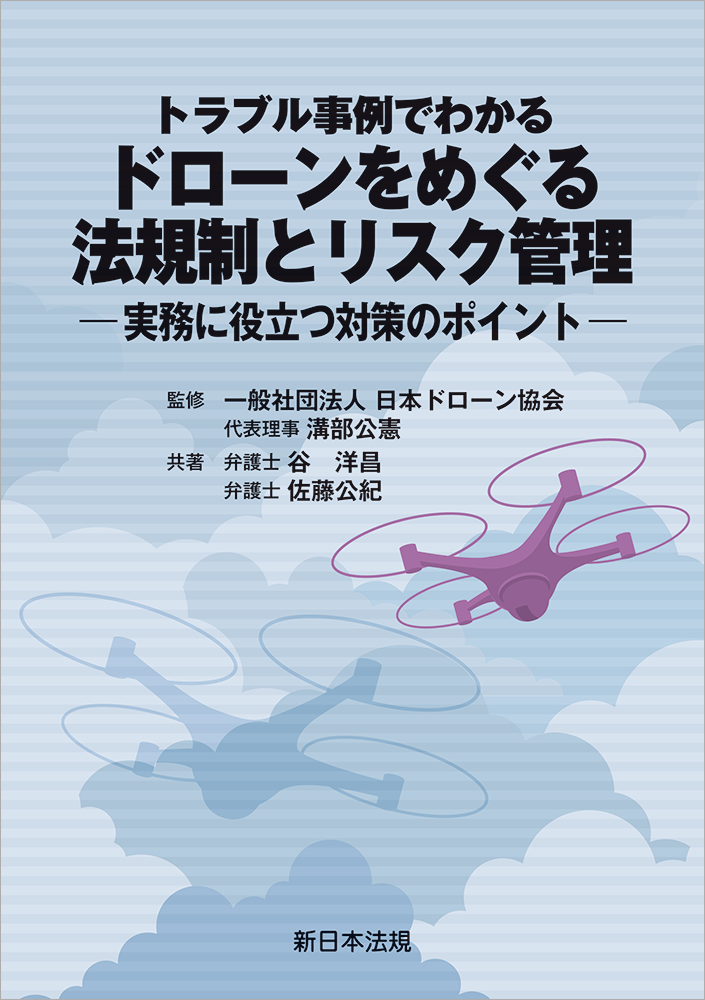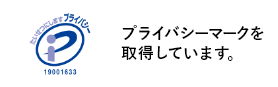解説記事2014年02月03日 【実務解説】 公益法人の税務の留意点(1)~一般法人へ移行した法人を中心として~(2014年2月3日号・№533)
実務解説
公益法人の税務の留意点(1)~一般法人へ移行した法人を中心として~
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.公益法人の税制上の取扱いの概要
特例民法法人は、公益社団法人・公益財団法人(以下「公益認定法人」という。)又は一般社団法人・一般財団法人(以下「一般法人」という。)のいずれかに移行しなければならず、平成25年11月30日をもってこの移行期間が終了した。
平成20年、民法の一部の廃止といわゆる公益三法(三つの法は、それぞれ「一般法人法」、「公益認定法」、「整備法」と通称される。)が施行され、実に110年ぶりに公益法人制度が改正されたが、これと同時に、公益法人に対する税制も改正された。
新制度では、法定の手続きを踏めばベースとなる法人(一般法人)を自由に設立できることになり(準則主義)、それらが公益性に応じて公益認定を受けて「公益社団法人」・「公益財団法人」(以下、「公益認定法人」と総称する。)になるというように、幅のある取扱いがなされることとなった。
税制においても、それぞれの法人に関する取扱いが整備された。
税制上の取扱い新旧の概要は、表1の通りである。
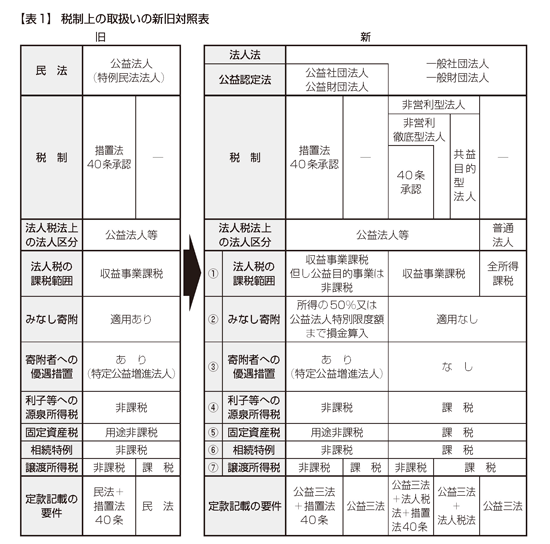
従来の取扱いと比較すると、新たな取扱いには多様性があることが分かる。これは、各法人が公益を担う法人であって優遇されるのにふさわしい法人であるのか否かということについて個別に審査を受けるという公益認定制度に対応して、税制においても、法人ごとに優遇の程度に変化を持たせた仕組みとしたことに因るものと考えてよい。
税制上の取扱いを判定する基準としては、公益認定法人となる基準(18項目がある。以下「公益認定基準」という。)や法人税法上の非営利型法人の基準、租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条による譲渡所得税の優遇等についての承認基準がある。
公益認定基準は、特に財務三基準といわれる「収支相償」「公益目的事業比率」「遊休財産保有制限」の基準、運営体制(役員の員数・構成など)や経理的基礎の適正さを判定する基準など、多岐に亘る基準となっている。
移行後の法人の内訳は、公益認定法人44.4%、一般法人55.6%(脚注1)というように、二分されることとなったが、寄附優遇税制の対象である特定公益増進法人にも該当し、税法上の収益事業であっても非課税という公益事業に非常に有利な枠組みが用意されているにもかかわらず、半分以上の移行法人が公益認定法人への移行を選択しなかった理由は、税制以外の上記の多岐に亘る基準の存在に拠るものと思われる。
本稿では、公益法人の税務上の留意点について、一般法人へ移行した法人を中心として、改めて考えてみたい。
Ⅱ.一般法人の位置付け
1 全所得課税と非営利型の区分 一般法人については、法人税法上、全所得課税が原則であるが、一定の要件に該当するものは非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業の所得のみが課税されるという特例が設けられている。
一般法人法239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とされており、剰余金の分配が完全に遮断されているわけではないこと、そして、事業の範囲に制約がなく、公益性を担保する制度上の仕組みを有していないことから、表2の通り、法人税法においては、非営利型法人に関して独自の要件を定めている。
表2の中の共益的活動を目的とする法人の要件の「主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定に関しては、法人税基本通達1-1-10(主たる事業の判定)において次のような解釈が示されている。
法人税申告書別表1(1)においては、「非営利型法人」と「普通法人」の区分しか設けられていない。非営利が徹底された法人であるのかあるいは共益的活動を目的としている法人であるのか(法法2九の二イに該当するのかあるいは同号ロに該当するのか)ということを示す別表等はないため、法人自身において、この判断の根拠を明確にしておく必要がある。
2 非営利型法人の問題点 非営利型法人に該当するのか否かについては、非営利徹底型法人と共益目的型法人の区分ごとに判断の基準が設けられているが、いずれの基準にも共通するものとして「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」という要件が設けられている(法令3①三、②六)。
この「特別の利益」とは範囲が広いものであり、具体的な事例として、法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けている場合や、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けている場合、通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借している場合、特定の個人に対し、過大な給与等を支給している場合などが挙げられている(法基通1-1-8)。
これらの取引に関しては、特別な利益を与える意思は問われていない。
この要件に該当して非営利型法人から外れることとなった場合には、その後、永久に同類型の非営利型法人になることはできないものとされている(法基通1-1-9)(注)。
(注)この要件に関してのみ、一旦、抵触した場合には、永久に要件を満たさないこととするという他に例を見ない基準となっているが、この要件に関してのみ、そのような基準とする理由は、明らかでない。
また、いずれの類型にも共通する要件として、「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。」(法令3①四、②七)という要件も設けられている。
この要件の判定は、原則として、判定される時の現況によることとされている。ただし、例えば、非営利型法人が理事の退任に基因してこの要件に該当しなくなった場合において、該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度、要件に該当していると認められるときには、継続してこの要件に該当しているものと取り扱って差し支えないとされている(法基通1-1-12)。
非営利型法人に移行したとしても、その後の税務調査により、要件の内の一つでも満たさないということになれば、普通法人(全所得課税)とされて多額の税負担が発生することがあるため、要件に該当するのか否かの判断に関しては、十分に注意する必要がある。
3 営利型法人 非営利型法人以外の法人(普通法人)は、全所得課税となるが、持分のない法人であるため、株式会社の課税と比べると、次のような点が異なる。
① 資本金を有しないため、中小会社の判定は、従業員数のみで行う(措令27の4⑩)。
② 資本金を有しないため、交際費等の定額控除額は、純資産額の60%相当額となる(措令37の4一)。
③ 資本金等の額を有しないため、法人住民税均等割額は、最低額(道府県民税年額2万円、市町村民税5万円)となる(地法52、312)。
④ 同族会社ではないため、留保金課税や非常勤役員の定期同額給与制限はない(法法2①十、34、67、法基通9-2-12)。
Ⅲ.法人区分の変更に伴う累積所得金額の益金算入
1 累積所得金額の課税 公益法人等が普通法人等(非営利型法人以外の法人)に移行する場合には、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税となるが、この場合には、公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる。
そこで、このように非課税とされていた前提が存在しなくなった場合には、その時点で、全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分について、益金に算入して課税を行うこととされている。
ところで、公益法人等である法人が普通法人となるとはいっても、法人税法4条と7条において収益事業以外の事業から生じた所得に対しては法人税を課さないこととしてきたわけであり、公益法人制度が変わったからといって、過去の公益法人等の時代の収益事業以外の事業から生じた利益の留保額に対して、法人設立時まで遡って遡及的に所得課税を行うというのは、理論的ではなく、立法論としても疑問なしとしない(脚注3)。
ただし、現行の法制度上、課税が行われることとなっていることは事実であり、実務に当たっては、期せずして巨額の課税を受けることのないように、十分に注意する必要がある。
2 普通法人(営利型法人)となる場合の課税問題 特例民法法人が普通法人に移行するケース、そして、非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となるケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下、「当初調整公益目的財産残額」という。)を累積所得金額から控除することとされており、累積所得金額から控除しきれない場合には、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととされている(法法64の4③、法令131の5①三・②)。
この「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。
整備法上の「公益目的財産額」は、時価に基づく金額であり、退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められているため、法人税法上の上記の累積所得金額の計算において、そのまま用いることはできない。
上記の計算に当たっては、法人税法上の帳簿価額に修正する(元に戻す)処理を行って控除することとなるため、「修正公益目的財産残額」という用語が用いられているわけである。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上で認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上で認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)、これに関しても差異が生ずることとなる。
法人の区分の変更に際しては、これらの点にも十分に注意する必要がある。
公益法人会計基準では、例えば、賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これらの引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
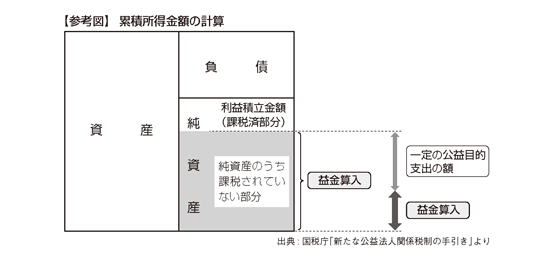
Ⅳ.公益目的支出超過額の損金不算入
営利型法人である移行法人(普通法人)は、全所得課税となる。
したがって、会費収入、資産の譲渡収入や寄附金収入も含めて、全て課税対象となる。
移行法人は、上記Ⅲで述べたとおり、移行に伴う累積所得金額の課税を受けることとなるわけであるが、その課税の後に普通法人と同じように課税を受けることになるのかというと、そうではない。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く。)の公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える場合には、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされており(法令131の5⑤)、実施事業収入の額が公益目的支出を超える場合には、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)。
なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのかというと、上記Ⅲで述べたとおり、普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」がゼロになればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、ゼロになるまでの期間は、この法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があるため、公益目的支出計画実施中の各事業年度においては申告書の作成漏れがないように注意する必要がある。
また、上記Ⅲ2で述べた通り、整備法上の「公益目的財産残額」は時価に基づく金額であり、法人税法上は法人税法上の帳簿価額に修正して「修正公益目的財産残額」を計算することとなる。そして、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させることとなる。
さらに、整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制が続くこととなる。
このため、公益目的支出計画の実施期間と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間が異なる場合があることにも、注意が必要である。
脚注
1 内閣府「新公益法人制度における全国申請状況(速報版)」(2013.10.31)では、移行認定申請8,940件、移行認可申請11,183件で、合計申請件数は20,123件である。
2 平成26年度税制改正大綱
3 朝長英樹『精説公益法人の税務』(公益法人協会)186頁に同趣旨。
公益法人の税務の留意点(1)~一般法人へ移行した法人を中心として~
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.公益法人の税制上の取扱いの概要
特例民法法人は、公益社団法人・公益財団法人(以下「公益認定法人」という。)又は一般社団法人・一般財団法人(以下「一般法人」という。)のいずれかに移行しなければならず、平成25年11月30日をもってこの移行期間が終了した。
平成20年、民法の一部の廃止といわゆる公益三法(三つの法は、それぞれ「一般法人法」、「公益認定法」、「整備法」と通称される。)が施行され、実に110年ぶりに公益法人制度が改正されたが、これと同時に、公益法人に対する税制も改正された。
新制度では、法定の手続きを踏めばベースとなる法人(一般法人)を自由に設立できることになり(準則主義)、それらが公益性に応じて公益認定を受けて「公益社団法人」・「公益財団法人」(以下、「公益認定法人」と総称する。)になるというように、幅のある取扱いがなされることとなった。
税制においても、それぞれの法人に関する取扱いが整備された。
税制上の取扱い新旧の概要は、表1の通りである。
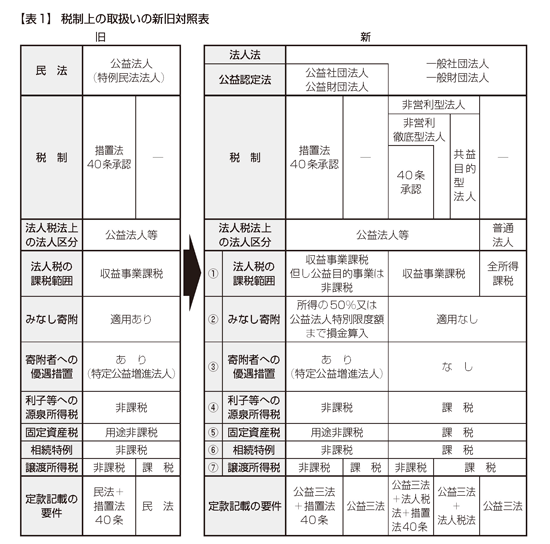
| 【表1】の内容については、次の通りである。 ① 公益認定法人は、公益認定法に規定する公益目的事業であれば例え従来の収益事業であっても課税しない(法令5②)。一般法人は、非営利型法人にあっては「公益法人等」として収益事業課税となり、営利型法人にあっては「普通法人」として全所得課税となる(法法4①)。 ② 公益認定法人については、みなし寄附金制度が大幅に拡充された(法法37⑤、法令77の3)。一般法人については、みなし寄附金制度の適用を認めずに課税ベースが拡大されている。 ③ 公益認定法人をすべて特定公益増進法人とし、寄附金優遇措置の対象としている(法令77三)。平成23年度税制改正で更に優遇策が拡充された。 ④ 公益認定法人については、利子・配当等に対する所得税の非課税法人とされている(所法別表第一)。 公益認定法人については非課税とし一般法人については課税とするという原則論だけで対応することでは余りにも大きな問題があるため、平成23年度税制改正において、特例民法法人から一般法人に移行した特定退職金共済団体について一部緩和されているが、その他の一般法人は取り残された状態となっており、結果的に源泉所得税が課税されて手取り額が減少することとなっている。 もっとも、全所得課税となれば、法人税の申告において源泉所得税や法人県民税の利子割額の還付を受けることは可能である。 ⑤ 公益認定法人が設置する幼稚園、図書館、博物館等の固定資産税については、従来どおり非課税であるが、一般法人に移行した法人については、平成25年度分で非課税措置が終了する(脚注2)。 なお、一般法人(非営利型法人のみ)が設置する医療関係者の養成所については、非課税のままである。 ⑥ 国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税措置の適用対象となる法人の範囲から、旧民法34条法人が除外され、代わりに公益認定法人が追加された(措法70①)。 ⑦ 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の適用対象となる法人の範囲が旧民法34条法人から公益認定法人及び非営利型の一般法人のうち非営利徹底法人に改められた(措法40)。 |
税制上の取扱いを判定する基準としては、公益認定法人となる基準(18項目がある。以下「公益認定基準」という。)や法人税法上の非営利型法人の基準、租税特別措置法(以下「措置法」という。)40条による譲渡所得税の優遇等についての承認基準がある。
公益認定基準は、特に財務三基準といわれる「収支相償」「公益目的事業比率」「遊休財産保有制限」の基準、運営体制(役員の員数・構成など)や経理的基礎の適正さを判定する基準など、多岐に亘る基準となっている。
移行後の法人の内訳は、公益認定法人44.4%、一般法人55.6%(脚注1)というように、二分されることとなったが、寄附優遇税制の対象である特定公益増進法人にも該当し、税法上の収益事業であっても非課税という公益事業に非常に有利な枠組みが用意されているにもかかわらず、半分以上の移行法人が公益認定法人への移行を選択しなかった理由は、税制以外の上記の多岐に亘る基準の存在に拠るものと思われる。
本稿では、公益法人の税務上の留意点について、一般法人へ移行した法人を中心として、改めて考えてみたい。
Ⅱ.一般法人の位置付け
1 全所得課税と非営利型の区分 一般法人については、法人税法上、全所得課税が原則であるが、一定の要件に該当するものは非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業の所得のみが課税されるという特例が設けられている。
一般法人法239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とされており、剰余金の分配が完全に遮断されているわけではないこと、そして、事業の範囲に制約がなく、公益性を担保する制度上の仕組みを有していないことから、表2の通り、法人税法においては、非営利型法人に関して独自の要件を定めている。
| 【表2】非営利型法人 |
| 非営利性が徹底された法人 (法法2九の二イの類型の非営利型法人) |
| 1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 3.1及び2の定款の定めに違反する行為(1、2及び4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 4.理事(清算人を含む。以下、同じ。)とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 |
| 共益的活動を目的とする法人 (法法2九の二ロの類型の非営利型法人) |
| 1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。 2.定款等に会費の定めがあること。 3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。 4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。(上記1より緩和) 5.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと(上記2より緩和)。 6.1から5まで及び7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 7.理事(清算人を含む。以下、同じ。)とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 |
表2の中の共益的活動を目的とする法人の要件の「主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定に関しては、法人税基本通達1-1-10(主たる事業の判定)において次のような解釈が示されている。
| 令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》に規定する「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当するかどうかは、原則として、その法人が主たる事業として収益事業を行うことが常態となっていないかどうかにより判定する。この場合において、主たる事業であるかどうかは、法人の事業の態様に応じて、例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標(以下1-1-10において「合理的指標」という。)を総合的に勘案し、当該合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定することとなる。 ただし、その法人の行う事業の内容に変更があるなど、収益事業の割合と収益事業以外の事業の割合の比に大きな変動を生ずる場合を除き、当該事業年度の前事業年度における合理的指標による収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるときには、その法人は、当該事業年度の開始の日において「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しているものと判定して差し支えない。 (注)本文後段の判定を行った結果、収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えないとしても、そのことのみをもって「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当しないことにはならないことに留意する。 |
2 非営利型法人の問題点 非営利型法人に該当するのか否かについては、非営利徹底型法人と共益目的型法人の区分ごとに判断の基準が設けられているが、いずれの基準にも共通するものとして「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」という要件が設けられている(法令3①三、②六)。
この「特別の利益」とは範囲が広いものであり、具体的な事例として、法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けている場合や、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けている場合、通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借している場合、特定の個人に対し、過大な給与等を支給している場合などが挙げられている(法基通1-1-8)。
これらの取引に関しては、特別な利益を与える意思は問われていない。
この要件に該当して非営利型法人から外れることとなった場合には、その後、永久に同類型の非営利型法人になることはできないものとされている(法基通1-1-9)(注)。
(注)この要件に関してのみ、一旦、抵触した場合には、永久に要件を満たさないこととするという他に例を見ない基準となっているが、この要件に関してのみ、そのような基準とする理由は、明らかでない。
また、いずれの類型にも共通する要件として、「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。」(法令3①四、②七)という要件も設けられている。
この要件の判定は、原則として、判定される時の現況によることとされている。ただし、例えば、非営利型法人が理事の退任に基因してこの要件に該当しなくなった場合において、該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度、要件に該当していると認められるときには、継続してこの要件に該当しているものと取り扱って差し支えないとされている(法基通1-1-12)。
非営利型法人に移行したとしても、その後の税務調査により、要件の内の一つでも満たさないということになれば、普通法人(全所得課税)とされて多額の税負担が発生することがあるため、要件に該当するのか否かの判断に関しては、十分に注意する必要がある。
3 営利型法人 非営利型法人以外の法人(普通法人)は、全所得課税となるが、持分のない法人であるため、株式会社の課税と比べると、次のような点が異なる。
① 資本金を有しないため、中小会社の判定は、従業員数のみで行う(措令27の4⑩)。
② 資本金を有しないため、交際費等の定額控除額は、純資産額の60%相当額となる(措令37の4一)。
③ 資本金等の額を有しないため、法人住民税均等割額は、最低額(道府県民税年額2万円、市町村民税5万円)となる(地法52、312)。
④ 同族会社ではないため、留保金課税や非常勤役員の定期同額給与制限はない(法法2①十、34、67、法基通9-2-12)。
Ⅲ.法人区分の変更に伴う累積所得金額の益金算入
1 累積所得金額の課税 公益法人等が普通法人等(非営利型法人以外の法人)に移行する場合には、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税となるが、この場合には、公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる。
そこで、このように非課税とされていた前提が存在しなくなった場合には、その時点で、全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分について、益金に算入して課税を行うこととされている。
| 益金に算入すべき金額 =資産の帳簿価額-負債帳簿価額-利益積 立金額-当初調整公益目的財産残額 |
ただし、現行の法制度上、課税が行われることとなっていることは事実であり、実務に当たっては、期せずして巨額の課税を受けることのないように、十分に注意する必要がある。
2 普通法人(営利型法人)となる場合の課税問題 特例民法法人が普通法人に移行するケース、そして、非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となるケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下、「当初調整公益目的財産残額」という。)を累積所得金額から控除することとされており、累積所得金額から控除しきれない場合には、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととされている(法法64の4③、法令131の5①三・②)。
この「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)。
整備法上の「公益目的財産額」は、時価に基づく金額であり、退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められているため、法人税法上の上記の累積所得金額の計算において、そのまま用いることはできない。
上記の計算に当たっては、法人税法上の帳簿価額に修正する(元に戻す)処理を行って控除することとなるため、「修正公益目的財産残額」という用語が用いられているわけである。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上で認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上で認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)、これに関しても差異が生ずることとなる。
法人の区分の変更に際しては、これらの点にも十分に注意する必要がある。
公益法人会計基準では、例えば、賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これらの引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
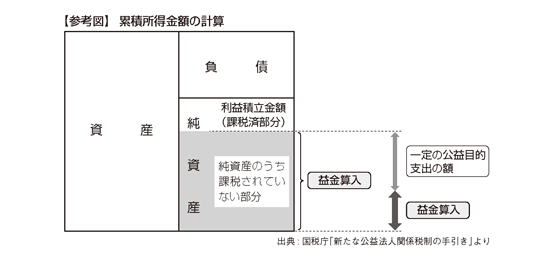
具体例
公益法人等が普通法人に移行することとなった場合の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入に関する計算は、法人税別表十四(七)にて行うこととなる。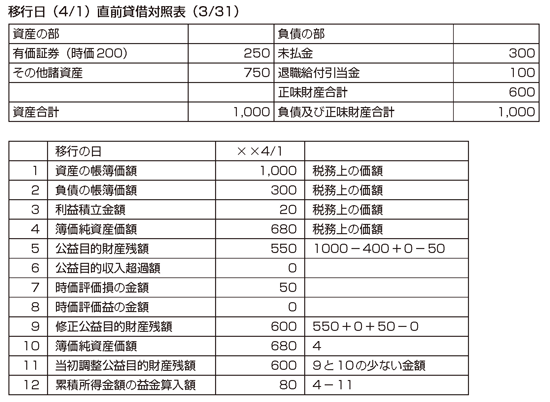 |
Ⅳ.公益目的支出超過額の損金不算入
営利型法人である移行法人(普通法人)は、全所得課税となる。
したがって、会費収入、資産の譲渡収入や寄附金収入も含めて、全て課税対象となる。
移行法人は、上記Ⅲで述べたとおり、移行に伴う累積所得金額の課税を受けることとなるわけであるが、その課税の後に普通法人と同じように課税を受けることになるのかというと、そうではない。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く。)の公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える場合には、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされており(法令131の5⑤)、実施事業収入の額が公益目的支出を超える場合には、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)。
なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのかというと、上記Ⅲで述べたとおり、普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」がゼロになればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、ゼロになるまでの期間は、この法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があるため、公益目的支出計画実施中の各事業年度においては申告書の作成漏れがないように注意する必要がある。
また、上記Ⅲ2で述べた通り、整備法上の「公益目的財産残額」は時価に基づく金額であり、法人税法上は法人税法上の帳簿価額に修正して「修正公益目的財産残額」を計算することとなる。そして、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させることとなる。
さらに、整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制が続くこととなる。
このため、公益目的支出計画の実施期間と法人税法上の調整公益目的財産残額がゼロになる期間が異なる場合があることにも、注意が必要である。
脚注
1 内閣府「新公益法人制度における全国申請状況(速報版)」(2013.10.31)では、移行認定申請8,940件、移行認可申請11,183件で、合計申請件数は20,123件である。
2 平成26年度税制改正大綱
3 朝長英樹『精説公益法人の税務』(公益法人協会)186頁に同趣旨。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -