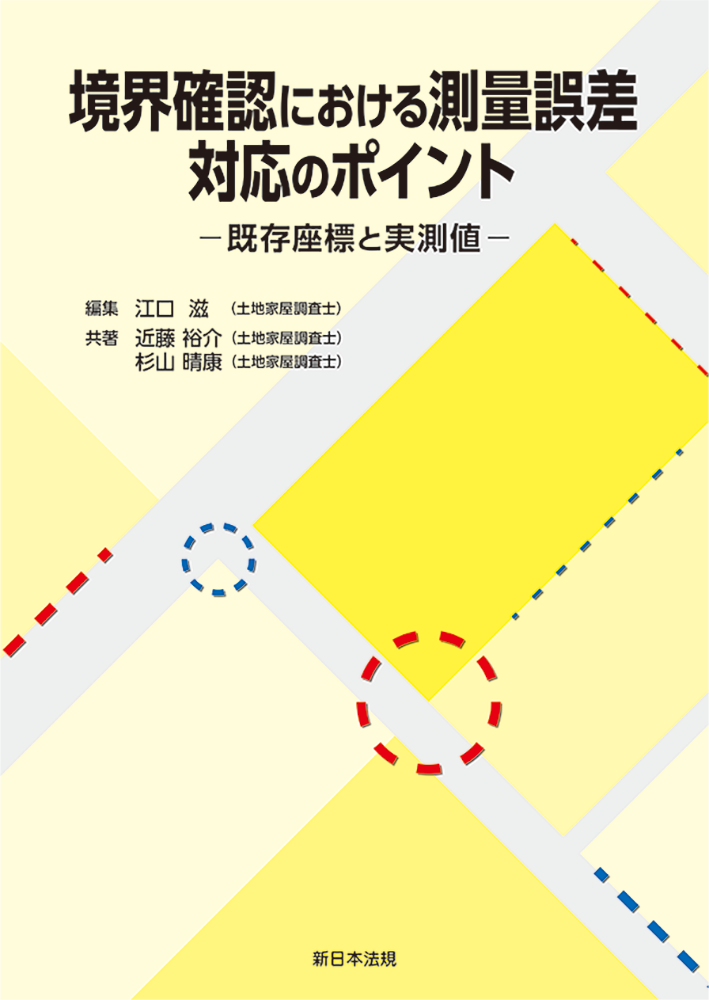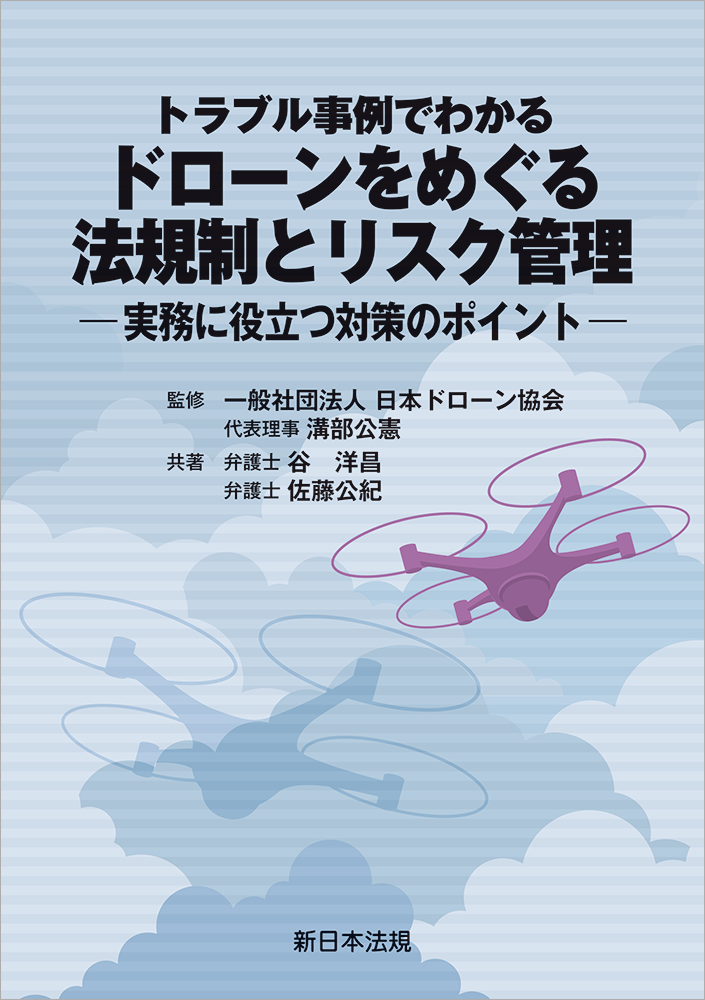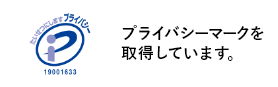解説記事2014年02月10日 【実務解説】 公益法人の税務の留意点(2)~公益認定法人を中心として~(2014年2月10日号・№534)
実務解説
公益法人の税務の留意点(2)~公益認定法人を中心として~
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.公益法人等に寄附をした場合の譲渡所得税等の非課税制度の見直し
1 制度の概要 公益認定法人(脚注1)及び非営利徹底型の一般法人への財産の贈与又は遺贈があった場合には、一定の要件を満たして手続きを行えば、所得税法上、その贈与又は遺贈がなかったものとみなされる(措法40①後段)。つまり贈与者又は遺贈者に対してみなし譲渡課税が行われない。
これは、贈与等をした者に有利な制度であり、これによって公益的事業への寄附を促そうという趣旨(脚注2)である。
この非課税の特例は、平成20年度税制改正により、次のとおり改正されている。
① 公益認定法人及び特例一般法人(非営利型法人のうち非営利性が徹底された法人)が特例の対象法人とされた。
② 寄附財産が対象法人の公益目的事業の用に直接供されなくなったことなどの一定の事由により非課税承認が取り消された場合には、その対象法人に対して、法人を個人とみなして寄附時の譲渡所得等に係る所得税が課されることとなった(措法40②・③)。
この取扱いは、公益法人等がその贈与又は遺贈を受けた資産を一旦その公益目的事業の用に供した後にその用に供しなくなるといった、いわば後発的事由により承認が取り消される場合には、その事情を考慮して、その贈与又は遺贈をした者ではなく贈与又は遺贈を受けた公益法人等に対して課税することとしたものである。
寄贈財産が公益法人等の公益目的事業の用に供される前にその承認が取り消されたときは、その寄贈者に対して、その公益法人等の公益目的事業の用に供された後にその承認が取り消されたときは、その公益法人等に対して、その取消日の属する年分の所得税が課される。
また、その寄贈者が死亡している場合には、それぞれの者に対してその贈与者の死亡日の属する年分の所得税が課されるが、その申告期限から時効が進行するため、この承認の取消しが、その贈与者の死亡日の属する年分の法定納期限から5年を経過した日後に行われた場合には、その公益法人等に対して課される所得税の徴収権が時効となるため(通法72①)、結果として、その公益法人等に対して所得税が課されることはない。
非課税承認取消しに係る公益法人等への所得税の課税は、平成20年12月1日以後にされる承認の取消しについて適用される。つまり、平成20年12月1日前に受けた非課税承認であってもその取消しが平成20年12月1日以後であれば、この公益法人等への所得税の規定が適用される(措法附則50①・②)。
措置法40条が適用されるためには、大きく分けて、①承認要件=個別の贈与等について非課税承認を受ける、②事業供用要件=贈与等を受けた財産を直接に一定の事業に用いる、という二つの要件がある。
このうち「事業供用要件」では、贈与等を受けた後、2年以内に直接に一定の公益目的事業に贈与財産を用いなくてはならない。この「直接」という意味は、建物や機材などの事業を行う上で用いることのできる物はその事業を行う中で用いること、ということである。正当な理由がある場合には、2年間という期限を延長したり、代替物をもって供用したりすることもできるが、そのためには、別途、贈与等を受けた法人による届出が必要である。
そして、この供用がなされなくなってしまった場合には、この事業供用要件を満たさなくなり、課税されることとなる。
この事業供用要件に関連した裁判例(脚注3)では、「株式の場合は配当金を公益目的事業に供与することが直接供用に当たり、換価をそもそも目的としていたとしても株式が換価されれば供用がなくなったことになり、特例は認められず課税される」としている。判決文の中では、非課税要件規定の厳格解釈がうたわれており、今後の参考事案として留意しておく必要がある。
また、法人が寄附を受け入れることがあった場合のために事前にすべき準備のうち、定款規定の整備も必要不可欠である(脚注4)。
2 平成26年度改正による緩和措置 平成26年度税制改正により、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置が講じられることとなった(脚注5)。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
公益認定基準においては、株式保有の制限(脚注6)があり、他の団体の意思決定に関与することができる株式を保有しないことが求められている。このこととの均衡を受けて、認定法上の議決権ベース(支配権)ではなく、所得税法上は、発行済株式数ベースにおいて2分の1が上限とされた。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用する。
③ 公益法人等は、買換え又は合併等により寄附財産を移転する場合に事前届出により非課税特例を継続できる措置の適用を受けるため、寄附財産を特定して申請を行うこと等一定の要件の下で、非課税承認対象財産に該当するかの確認を国税庁長官に求めることができることとする。
④ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③及び④の改正は、平成26年4月1日以後に行われる申請又は届出について適用する。
⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、当該公益法人等が当該取消しのあった年以前に合併又は解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分及び確定申告期間については、次のとおりとする。
イ 納税義務の成立時期 合併の日の前日又は解散の日(現行:非課税承認が取り消された日(以下「承認取消日」という。)の属する年の終了の時)
ロ 課税年分 上記イに定める日の属する年分(現行:承認取消日の属する年分)
ハ 確定申告期間 合併の日又は解散の日の翌日から2月以内(現行:承認取消日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで)
(注)上記⑤の改正は、平成26年4月1日以後に公益法人等が合併又は解散を行う場合について適用する。
Ⅱ.寄附金税制
1 公益認定法人の寄附金の損金算入限度額 公益認定法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなし、その寄附金の額とみなした金額(以下、「みなし寄附金額」という。)を通常の寄附金の額に含めて寄附金の損金算入限度額の計算を行う特例制度が平成20年度税制改正により創設されている(法法37⑤)。
公益認定法人は、その公益目的事業の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(その金額がみなし寄附金額を超える場合には、みなし寄附金額に相当する金額。以下、「公益法人特別限度額」という。)が所得金額の50%相当額を超える場合には、公益法人特別限度額に相当する金額を損金に算入できる(法令73の2)。
この特例制度を適用しない場合の寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%相当額とされている(法令73①三イ)。
みなし寄附金額については、正味財産増減計算書の収益事業等会計から公益目的事業会計へ「他会計振替額」科目にて経理することになる。
なお、一般法人に移行した場合には、収益事業課税制度が適用される非営利型一般法人であっても、みなし寄附金額に関する制度の適用はない(法法37④)。
2 みなし寄附金額の「支出」とは みなし寄附金額については、「公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして」(法法37⑤)と規定されており、また、公益認定法人にあっては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で認定法上の公益目的事業のために支出した金額も含まれる(法令77の3)とされており、いずれも「支出」という文言が用いられているため、この「支出」とは何か、という疑問が生ずることとなる。
これについては、法人税法施行令6条(収益事業を行う法人の経理の区分)により「収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない」とされており、法人税基本通達15-1-7(収益事業の所得の運用)、15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)においては、この「支出」を「経理」と解釈して、優先的にみなし寄附金額に関する規定を適用することが明らかにされている。
また、国税庁の質疑応答事例では、社会福祉法人の「収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて」において、「内部振り替えの金額は一般の寄附金とはみなされますが、指定寄附金として拠出されたものとまでみなされるものではなく、損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。」と回答し、明確に「内部振替」も寄附金とみなすこととしている。
ただし、「収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業に受け入れた場合には、法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分したことにはならないから、本件における当該収益事業から公益事業への支出額(公益事業から収益事業への元入金)は、みなし寄付金には該当しない。」とされた裁決事例(脚注7)があるため、元入金という経理は、慎重に行う必要がある。
また、「支出時期」の判定についても、疑問がある。
公益認定法上、公益認定法人は、収益事業等から生じた利益の50%以上を公益目的事業財産に繰り入れなければならないとされており(認定法18四)、この繰入れ金額の確定のために、みなし寄附金額は、事業年度終了後の決算整理仕訳の一つとして「経理」されることにならざるを得ない。
現実には、このような状況となっているわけであるが、このような状況下で、法人税の取扱いにおいて、この決算整理日付(経理した日付)を無視して、みなし寄附金の「支出」日を決算日としてよいのか否かということが、必ずしも明確になっていない。
3 公益認定法との関係 公益認定法上、公益認定法人は、収益事業等(収益事業、相互扶助等のその他事業)から生じた利益の50%は公益目的事業財産に繰り入れなければならず(認定法18四)、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には、自発的に50%を超えて繰り入れることができる(認定法規則26七、八)。
そして、収益事業等から生じた利益の繰入額が、50%丁度か、50%超かによって、収支相償の計算方法が異なる(公益認定等ガイドラインⅠ.5.参照)。
法人税法では、公益認定法上の各種概念をそのまま受け入れ、税額計算に反映させており、公益目的事業の財源確保のために必要な額の具体的な算出方法は、収支相償の判定方法の計算と基本的に類似している(法規22の5)が、法人税法上は「収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額」を寄附金の額とみなし、損金算入限度額以内の金額を損金とする(法法37⑤、法令73①三イ、73の2①)とされているため、その差異には、注意が必要である。
4 公益認定法人に寄附をした個人・法人に対する優遇措置 公益認定法人は、全て特定公益増進法人となり、寄附金優遇措置の対象となる(法37④、令77三、所法78②三、所令217三)。
(1)個人が支出する寄附金
① 寄附金控除(所得控除) 個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し寄附金を支出した場合には、それらの寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除される(所法78①)。
② 公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除) 個人が、運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たす公益認定法人等に対し寄附金を支出した場合には、①との選択により、それらの寄附金の額の合計額(原則として所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額の40%相当額(その年分の所得税額の25%が上限)が公益社団法人等寄附金特別控除としてその年分の所得税額から控除される(措法41の18の3①)。
(2)法人が支出する寄附金 法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額が設けられている(法令77の2)。
Ⅲ.公益認定の取消しにより普通法人に該当することとなった場合
1 「公益目的取得財産残額」の贈与 公益認定法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②)、公益認定法人自らが一般法人となるべく申請した場合、役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合等に公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じ(認定法29①)、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与が強制され(認定法30)、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、取消しの日から1か月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与する必要があるとしており、取消しの日における金額の確定を3か月以内としている(認定法規50)。
なお、1か月以内に贈与契約が成立していない場合には、国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているため、注意する必要がある(認定法30①)。
2 「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 「公益目的取得財産残額」は、法人の意思と宣言によって確定するため、その範囲及び計算については、十分な注意が必要となる。
この公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額であって、毎事業年度末、計算を行った上で、行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規48)。
3 公益認定の取消しにより普通法人に該当することとなった場合の課税上の取扱い 公益認定法人が行政庁から公益認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の一般法人(普通法人)に該当することとなった場合において、その該当することとなった日(以下、「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額(以下、「累積所得金額」という。)は、移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされている(法法64の4①・③)。
取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額は、累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。累積所得金額から控除しきれない場合には、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法令131の5①三・②)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生ずるため、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引くこととなる。
この贈与により生じた損失の額は、損金に算入されず(法令131の5④)、寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、1の贈与に加えて、一時に多額の課税が生ずることとなる(次の計算式参照)。
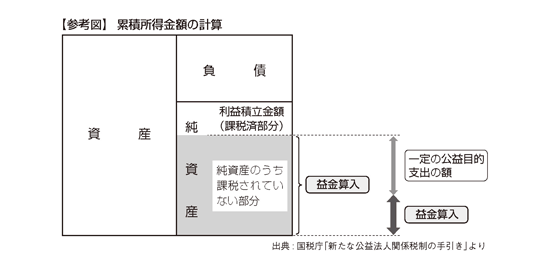
Ⅳ.公益法人の会計と法人税法上の区分経理
1 公益法人会計基準 公益法人は「平成20年基準」又は「平成16年基準」と言われている公益法人の会計基準に従って会計処理を行うこととなる。
公益法人会計基準における公益法人は、次に掲げた法人である。
① 認定法2条3号に定めのある公益法人(以下、「公益社団・財団法人」という。)
② 整備法123条1項に定めのある移行法人(以下、「移行法人」という。)
③ 整備法60条に定めのある特例民法法人(以下、「申請法人」という。)(整備法44条、45条の申請をする際の計算書類を作成する場合)
④ 認定法7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人(以下、「一般社団・財団法人」という。)
なお、公益法人は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計の慣行によることが求められるが、(公益法人認定法施行規則12条)、これは、特定の会計基準の適用を義務付けるものではなく、平成16年基準を適用することも可能である(脚注8)。そして、原則として、公益認定法人であれば「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」、「法人会計」ごとに、一般法人のうち移行法人であれば公益目的支出計画の対象となる「実施事業等会計」、「その他会計」、「法人会計」ごとに貸借対照表、正味財産増減計算書(損益計算書)の内訳表の作成が求められている。
2 法人税法上の区分経理 公益認定法人及び一般法人のうち非営利型法人は、収益事業課税であるため、法人税法施行令6条(収益事業を行う法人の経理の区分)により、「収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない」とされている。
そして、法人税基本通達15-2-5(費用又は損失の区分経理)では、「収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する」とされており、法人税基本通達15-2-1(所得に関する経理)では、「一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経理する」ことも認められている。
以上のように、会計上の経理区分と法人税法上の経理区分、共通経費の扱いが異なることから、公益法人では、会計とは別に、法人税法における税額計算を行うために収益事業に係る収益と費用を抽出して損益計算書を作成しているケースが多くなっている。このようなケースにおいては、別途作成した収益事業分を集計した損益計算書の前期繰越利益・次期繰越利益を用いて法人税申告書別表五(一)を作成している。
そして、貸借対照表に至っては、期首の勘定科目から誘導的に作成されることなく、収益事業に属する資産・負債科目との差額を元入金として経理し、この差額については、資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないものと取り扱っているのが実情である。
結果的に、元入金は資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないものとされることになるため、負債とする以外には処理のしようがないこととなる(脚注9)。
(了)
脚注
1 本稿では、公益社団法人・公益財団法人を「公益認定法人」といい、一般社団法人・一般財団法人を「一般法人」という。
2 相続税法にも類似の相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税規定があるが(措法70)、公益認定法人のみであること、寄附財産の事業供用は必要だが間接的でもよい点等に差異がある。
3 東京高裁平成22年8月25日判決(平成22年(行コ)第103号)
4 措置法40条の承認の要件には、例えば「運営組織が適正である」必要があり、その判定は「定款又は規則において、一定の事項が定められていること」など、詳細に定められている(40条通達18)。
5 平成26年度税制改正大綱40頁
6 公益法人認定等委員会FAQ問Ⅵ-4-①(会計基準)
7 平成12年3月7日裁決。裁決事例集No.59。143頁
8 公益法人認定等委員会FAQ問Ⅵ-4-①(会計基準)
9 朝長英樹『公益法人税制』(法令出版)94頁
公益法人の税務の留意点(2)~公益認定法人を中心として~
公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅰ.公益法人等に寄附をした場合の譲渡所得税等の非課税制度の見直し
1 制度の概要 公益認定法人(脚注1)及び非営利徹底型の一般法人への財産の贈与又は遺贈があった場合には、一定の要件を満たして手続きを行えば、所得税法上、その贈与又は遺贈がなかったものとみなされる(措法40①後段)。つまり贈与者又は遺贈者に対してみなし譲渡課税が行われない。
これは、贈与等をした者に有利な制度であり、これによって公益的事業への寄附を促そうという趣旨(脚注2)である。
この非課税の特例は、平成20年度税制改正により、次のとおり改正されている。
① 公益認定法人及び特例一般法人(非営利型法人のうち非営利性が徹底された法人)が特例の対象法人とされた。
② 寄附財産が対象法人の公益目的事業の用に直接供されなくなったことなどの一定の事由により非課税承認が取り消された場合には、その対象法人に対して、法人を個人とみなして寄附時の譲渡所得等に係る所得税が課されることとなった(措法40②・③)。
この取扱いは、公益法人等がその贈与又は遺贈を受けた資産を一旦その公益目的事業の用に供した後にその用に供しなくなるといった、いわば後発的事由により承認が取り消される場合には、その事情を考慮して、その贈与又は遺贈をした者ではなく贈与又は遺贈を受けた公益法人等に対して課税することとしたものである。
寄贈財産が公益法人等の公益目的事業の用に供される前にその承認が取り消されたときは、その寄贈者に対して、その公益法人等の公益目的事業の用に供された後にその承認が取り消されたときは、その公益法人等に対して、その取消日の属する年分の所得税が課される。
また、その寄贈者が死亡している場合には、それぞれの者に対してその贈与者の死亡日の属する年分の所得税が課されるが、その申告期限から時効が進行するため、この承認の取消しが、その贈与者の死亡日の属する年分の法定納期限から5年を経過した日後に行われた場合には、その公益法人等に対して課される所得税の徴収権が時効となるため(通法72①)、結果として、その公益法人等に対して所得税が課されることはない。
非課税承認取消しに係る公益法人等への所得税の課税は、平成20年12月1日以後にされる承認の取消しについて適用される。つまり、平成20年12月1日前に受けた非課税承認であってもその取消しが平成20年12月1日以後であれば、この公益法人等への所得税の規定が適用される(措法附則50①・②)。
措置法40条が適用されるためには、大きく分けて、①承認要件=個別の贈与等について非課税承認を受ける、②事業供用要件=贈与等を受けた財産を直接に一定の事業に用いる、という二つの要件がある。
このうち「事業供用要件」では、贈与等を受けた後、2年以内に直接に一定の公益目的事業に贈与財産を用いなくてはならない。この「直接」という意味は、建物や機材などの事業を行う上で用いることのできる物はその事業を行う中で用いること、ということである。正当な理由がある場合には、2年間という期限を延長したり、代替物をもって供用したりすることもできるが、そのためには、別途、贈与等を受けた法人による届出が必要である。
そして、この供用がなされなくなってしまった場合には、この事業供用要件を満たさなくなり、課税されることとなる。
この事業供用要件に関連した裁判例(脚注3)では、「株式の場合は配当金を公益目的事業に供与することが直接供用に当たり、換価をそもそも目的としていたとしても株式が換価されれば供用がなくなったことになり、特例は認められず課税される」としている。判決文の中では、非課税要件規定の厳格解釈がうたわれており、今後の参考事案として留意しておく必要がある。
また、法人が寄附を受け入れることがあった場合のために事前にすべき準備のうち、定款規定の整備も必要不可欠である(脚注4)。
2 平成26年度改正による緩和措置 平成26年度税制改正により、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置が講じられることとなった(脚注5)。
① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
公益認定基準においては、株式保有の制限(脚注6)があり、他の団体の意思決定に関与することができる株式を保有しないことが求められている。このこととの均衡を受けて、認定法上の議決権ベース(支配権)ではなく、所得税法上は、発行済株式数ベースにおいて2分の1が上限とされた。
(注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用する。
③ 公益法人等は、買換え又は合併等により寄附財産を移転する場合に事前届出により非課税特例を継続できる措置の適用を受けるため、寄附財産を特定して申請を行うこと等一定の要件の下で、非課税承認対象財産に該当するかの確認を国税庁長官に求めることができることとする。
④ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
(注)上記③及び④の改正は、平成26年4月1日以後に行われる申請又は届出について適用する。
⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、当該公益法人等が当該取消しのあった年以前に合併又は解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分及び確定申告期間については、次のとおりとする。
イ 納税義務の成立時期 合併の日の前日又は解散の日(現行:非課税承認が取り消された日(以下「承認取消日」という。)の属する年の終了の時)
ロ 課税年分 上記イに定める日の属する年分(現行:承認取消日の属する年分)
ハ 確定申告期間 合併の日又は解散の日の翌日から2月以内(現行:承認取消日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで)
(注)上記⑤の改正は、平成26年4月1日以後に公益法人等が合併又は解散を行う場合について適用する。
Ⅱ.寄附金税制
1 公益認定法人の寄附金の損金算入限度額 公益認定法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなし、その寄附金の額とみなした金額(以下、「みなし寄附金額」という。)を通常の寄附金の額に含めて寄附金の損金算入限度額の計算を行う特例制度が平成20年度税制改正により創設されている(法法37⑤)。
公益認定法人は、その公益目的事業の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(その金額がみなし寄附金額を超える場合には、みなし寄附金額に相当する金額。以下、「公益法人特別限度額」という。)が所得金額の50%相当額を超える場合には、公益法人特別限度額に相当する金額を損金に算入できる(法令73の2)。
この特例制度を適用しない場合の寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%相当額とされている(法令73①三イ)。
みなし寄附金額については、正味財産増減計算書の収益事業等会計から公益目的事業会計へ「他会計振替額」科目にて経理することになる。
なお、一般法人に移行した場合には、収益事業課税制度が適用される非営利型一般法人であっても、みなし寄附金額に関する制度の適用はない(法法37④)。
2 みなし寄附金額の「支出」とは みなし寄附金額については、「公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして」(法法37⑤)と規定されており、また、公益認定法人にあっては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で認定法上の公益目的事業のために支出した金額も含まれる(法令77の3)とされており、いずれも「支出」という文言が用いられているため、この「支出」とは何か、という疑問が生ずることとなる。
これについては、法人税法施行令6条(収益事業を行う法人の経理の区分)により「収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない」とされており、法人税基本通達15-1-7(収益事業の所得の運用)、15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)においては、この「支出」を「経理」と解釈して、優先的にみなし寄附金額に関する規定を適用することが明らかにされている。
また、国税庁の質疑応答事例では、社会福祉法人の「収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて」において、「内部振り替えの金額は一般の寄附金とはみなされますが、指定寄附金として拠出されたものとまでみなされるものではなく、損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。」と回答し、明確に「内部振替」も寄附金とみなすこととしている。
ただし、「収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業に受け入れた場合には、法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分したことにはならないから、本件における当該収益事業から公益事業への支出額(公益事業から収益事業への元入金)は、みなし寄付金には該当しない。」とされた裁決事例(脚注7)があるため、元入金という経理は、慎重に行う必要がある。
また、「支出時期」の判定についても、疑問がある。
公益認定法上、公益認定法人は、収益事業等から生じた利益の50%以上を公益目的事業財産に繰り入れなければならないとされており(認定法18四)、この繰入れ金額の確定のために、みなし寄附金額は、事業年度終了後の決算整理仕訳の一つとして「経理」されることにならざるを得ない。
現実には、このような状況となっているわけであるが、このような状況下で、法人税の取扱いにおいて、この決算整理日付(経理した日付)を無視して、みなし寄附金の「支出」日を決算日としてよいのか否かということが、必ずしも明確になっていない。
3 公益認定法との関係 公益認定法上、公益認定法人は、収益事業等(収益事業、相互扶助等のその他事業)から生じた利益の50%は公益目的事業財産に繰り入れなければならず(認定法18四)、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には、自発的に50%を超えて繰り入れることができる(認定法規則26七、八)。
そして、収益事業等から生じた利益の繰入額が、50%丁度か、50%超かによって、収支相償の計算方法が異なる(公益認定等ガイドラインⅠ.5.参照)。
法人税法では、公益認定法上の各種概念をそのまま受け入れ、税額計算に反映させており、公益目的事業の財源確保のために必要な額の具体的な算出方法は、収支相償の判定方法の計算と基本的に類似している(法規22の5)が、法人税法上は「収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額」を寄附金の額とみなし、損金算入限度額以内の金額を損金とする(法法37⑤、法令73①三イ、73の2①)とされているため、その差異には、注意が必要である。
4 公益認定法人に寄附をした個人・法人に対する優遇措置 公益認定法人は、全て特定公益増進法人となり、寄附金優遇措置の対象となる(法37④、令77三、所法78②三、所令217三)。
(1)個人が支出する寄附金
① 寄附金控除(所得控除) 個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し寄附金を支出した場合には、それらの寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除される(所法78①)。
② 公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除) 個人が、運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たす公益認定法人等に対し寄附金を支出した場合には、①との選択により、それらの寄附金の額の合計額(原則として所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額の40%相当額(その年分の所得税額の25%が上限)が公益社団法人等寄附金特別控除としてその年分の所得税額から控除される(措法41の18の3①)。
(2)法人が支出する寄附金 法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額が設けられている(法令77の2)。
Ⅲ.公益認定の取消しにより普通法人に該当することとなった場合
1 「公益目的取得財産残額」の贈与 公益認定法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②)、公益認定法人自らが一般法人となるべく申請した場合、役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合等に公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じ(認定法29①)、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与が強制され(認定法30)、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、取消しの日から1か月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与する必要があるとしており、取消しの日における金額の確定を3か月以内としている(認定法規50)。
なお、1か月以内に贈与契約が成立していない場合には、国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているため、注意する必要がある(認定法30①)。
2 「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 「公益目的取得財産残額」は、法人の意思と宣言によって確定するため、その範囲及び計算については、十分な注意が必要となる。
この公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額であって、毎事業年度末、計算を行った上で、行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規48)。
3 公益認定の取消しにより普通法人に該当することとなった場合の課税上の取扱い 公益認定法人が行政庁から公益認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の一般法人(普通法人)に該当することとなった場合において、その該当することとなった日(以下、「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額(以下、「累積所得金額」という。)は、移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされている(法法64の4①・③)。
取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額は、累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。累積所得金額から控除しきれない場合には、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法令131の5①三・②)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生ずるため、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引くこととなる。
この贈与により生じた損失の額は、損金に算入されず(法令131の5④)、寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、1の贈与に加えて、一時に多額の課税が生ずることとなる(次の計算式参照)。
| 益金に算入すべき金額 =資産の帳簿価額-負債帳簿価額-利益積立金額-公益目的取得財産残額 |
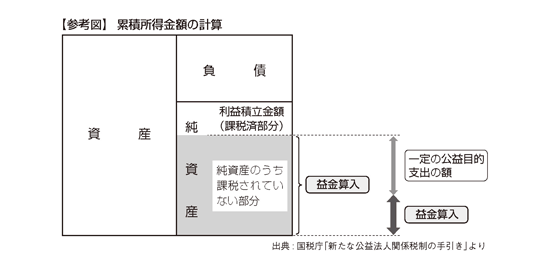
Ⅳ.公益法人の会計と法人税法上の区分経理
1 公益法人会計基準 公益法人は「平成20年基準」又は「平成16年基準」と言われている公益法人の会計基準に従って会計処理を行うこととなる。
公益法人会計基準における公益法人は、次に掲げた法人である。
① 認定法2条3号に定めのある公益法人(以下、「公益社団・財団法人」という。)
② 整備法123条1項に定めのある移行法人(以下、「移行法人」という。)
③ 整備法60条に定めのある特例民法法人(以下、「申請法人」という。)(整備法44条、45条の申請をする際の計算書類を作成する場合)
④ 認定法7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人(以下、「一般社団・財団法人」という。)
なお、公益法人は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計の慣行によることが求められるが、(公益法人認定法施行規則12条)、これは、特定の会計基準の適用を義務付けるものではなく、平成16年基準を適用することも可能である(脚注8)。そして、原則として、公益認定法人であれば「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」、「法人会計」ごとに、一般法人のうち移行法人であれば公益目的支出計画の対象となる「実施事業等会計」、「その他会計」、「法人会計」ごとに貸借対照表、正味財産増減計算書(損益計算書)の内訳表の作成が求められている。
2 法人税法上の区分経理 公益認定法人及び一般法人のうち非営利型法人は、収益事業課税であるため、法人税法施行令6条(収益事業を行う法人の経理の区分)により、「収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない」とされている。
そして、法人税基本通達15-2-5(費用又は損失の区分経理)では、「収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する」とされており、法人税基本通達15-2-1(所得に関する経理)では、「一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経理する」ことも認められている。
以上のように、会計上の経理区分と法人税法上の経理区分、共通経費の扱いが異なることから、公益法人では、会計とは別に、法人税法における税額計算を行うために収益事業に係る収益と費用を抽出して損益計算書を作成しているケースが多くなっている。このようなケースにおいては、別途作成した収益事業分を集計した損益計算書の前期繰越利益・次期繰越利益を用いて法人税申告書別表五(一)を作成している。
そして、貸借対照表に至っては、期首の勘定科目から誘導的に作成されることなく、収益事業に属する資産・負債科目との差額を元入金として経理し、この差額については、資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないものと取り扱っているのが実情である。
結果的に、元入金は資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないものとされることになるため、負債とする以外には処理のしようがないこととなる(脚注9)。
(了)
脚注
1 本稿では、公益社団法人・公益財団法人を「公益認定法人」といい、一般社団法人・一般財団法人を「一般法人」という。
2 相続税法にも類似の相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税規定があるが(措法70)、公益認定法人のみであること、寄附財産の事業供用は必要だが間接的でもよい点等に差異がある。
3 東京高裁平成22年8月25日判決(平成22年(行コ)第103号)
4 措置法40条の承認の要件には、例えば「運営組織が適正である」必要があり、その判定は「定款又は規則において、一定の事項が定められていること」など、詳細に定められている(40条通達18)。
5 平成26年度税制改正大綱40頁
6 公益法人認定等委員会FAQ問Ⅵ-4-①(会計基準)
7 平成12年3月7日裁決。裁決事例集No.59。143頁
8 公益法人認定等委員会FAQ問Ⅵ-4-①(会計基準)
9 朝長英樹『公益法人税制』(法令出版)94頁
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -