税務ニュース2003年02月10日 自社株軽減特例の拡充措置が明らかに すべての小規模宅地特例との限度内併用案実現へ
自社株軽減特例の拡充措置が明らかに
すべての小規模宅地特例との限度内併用案実現へ
平成15年度税制改正で注目されていた「自社株に対する軽減措置に係る所要の規定の整備」の内容が固まってきた。
これらの改正(図1参照)では、自社株軽減の対象範囲を広げる効果と、軽減額自体を拡充させる効果が見込まれている。
自社株軽減の対象範囲を広げるものとして1軽減対象の上限見直し2被相続人要件の見直し3対象会社要件の見直しが行われる。
1軽減対象の上限見直しは、発行済み株式総数の1/3までの上限を2/3までに引き上げるものである。自社株は、特別決議に必要な2/3を保有するのが通常であり、これまで軽減対象は1/3までに制限されていたが、範囲が広がることになる。軽減対象の上限見直しでは、発行済み株式総額に対する軽減額を拡充する効果も見込まれている(図2参照)。
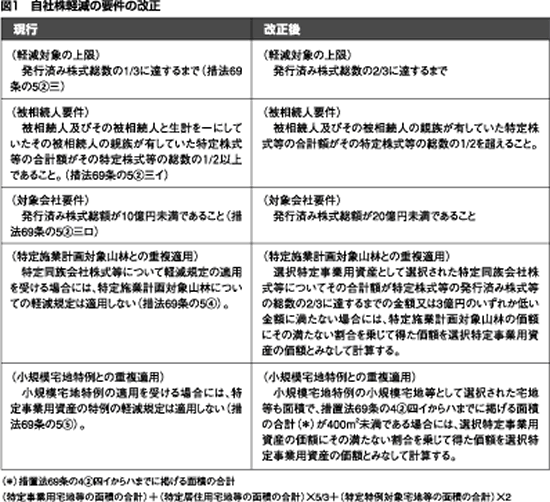
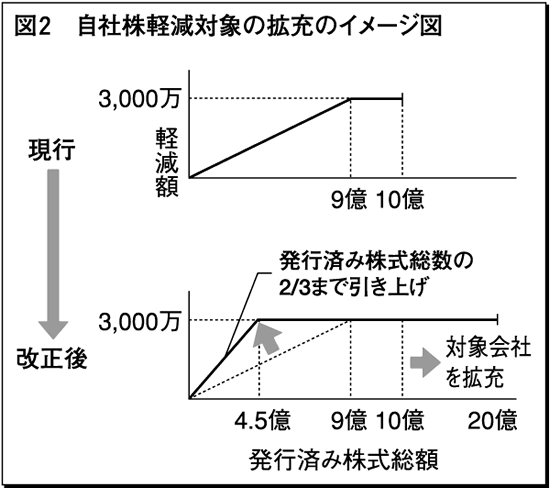
2被相続人要件の見直しは、現行制度では本人とこれと生計を一にする者とだけで50%以上を保有していないと特例を利用できなかったが、生計を一にする者との限定を外して、同族関係者で50%超保有していれば特例が利用できるように要件緩和を行うものである。
3対象会社要件の見直しは、現行制度では発行済み株式総額10億円超(相続税評価額ベ-ス)の会社は特例を利用できないが、発行済み総額20億円以下の会社まで利用できるよう対象を拡充するものである。
使い勝手改善にはほど遠いが
自社株軽減を利用することができる範囲は広がるが、自社株軽減制度の使い勝手改善にはほど遠い。自社株軽減は、現行どおり3億円部分までを対象とし、軽減率も変わらない。軽減額は、最大で3億円×10%=3,000万円である。小規模宅地の評価減特例には金額的な頭打ちはない。小規模宅地特例に対する自社株特例の使い勝手の悪さが、抜本的に改善されたものとはいいがたい。自社株特例を抜本的に見直すのであれば、1)3億円の枠の拡大、2)軽減率のアップ、3)小規模宅地特例との重複適用禁止規定の見直しが不可避である。
今回の改正は、上記1)2)に手をつけたものではなく、3)小規模宅地特例との重複適用禁止規定の見直しを限度余裕部分についてだけ行った(図3参照)きわめて小ぶりなものである。しかし、併用される小規模宅地特例については、対象を限定せずに割合計算を行っているので、小規模宅地特例を限度一杯に利用できない場合には、広く減税効果が期待できそうだ。
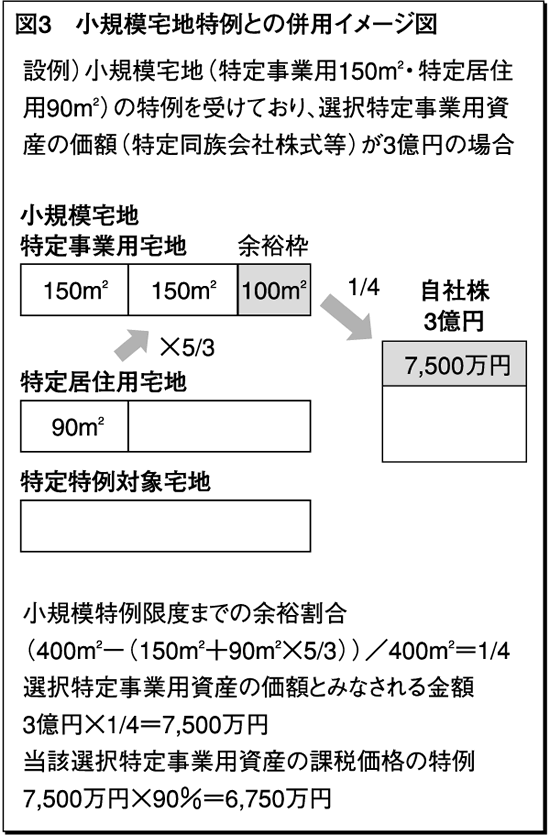
すべての小規模宅地特例との限度内併用案実現へ
平成15年度税制改正で注目されていた「自社株に対する軽減措置に係る所要の規定の整備」の内容が固まってきた。
これらの改正(図1参照)では、自社株軽減の対象範囲を広げる効果と、軽減額自体を拡充させる効果が見込まれている。
自社株軽減の対象範囲を広げるものとして1軽減対象の上限見直し2被相続人要件の見直し3対象会社要件の見直しが行われる。
1軽減対象の上限見直しは、発行済み株式総数の1/3までの上限を2/3までに引き上げるものである。自社株は、特別決議に必要な2/3を保有するのが通常であり、これまで軽減対象は1/3までに制限されていたが、範囲が広がることになる。軽減対象の上限見直しでは、発行済み株式総額に対する軽減額を拡充する効果も見込まれている(図2参照)。
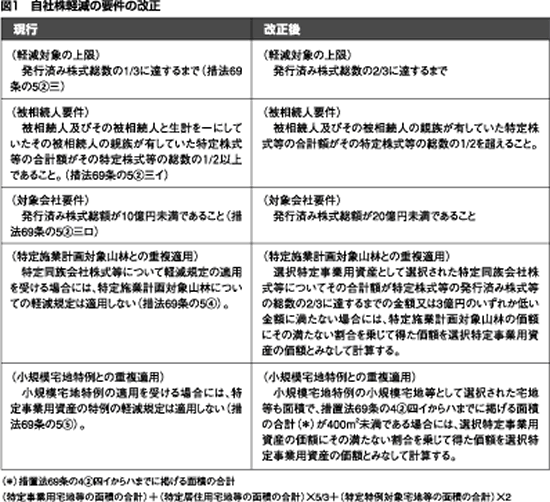
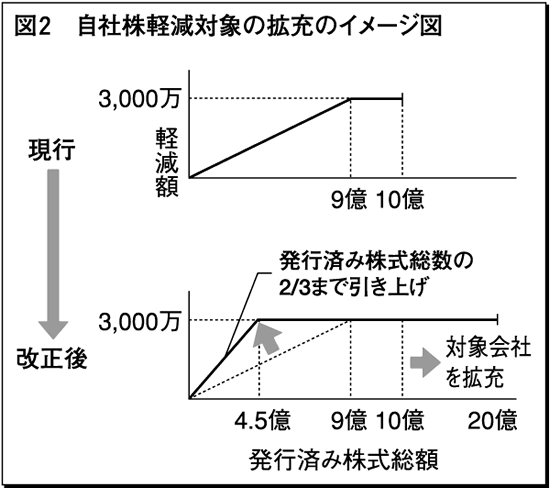
2被相続人要件の見直しは、現行制度では本人とこれと生計を一にする者とだけで50%以上を保有していないと特例を利用できなかったが、生計を一にする者との限定を外して、同族関係者で50%超保有していれば特例が利用できるように要件緩和を行うものである。
3対象会社要件の見直しは、現行制度では発行済み株式総額10億円超(相続税評価額ベ-ス)の会社は特例を利用できないが、発行済み総額20億円以下の会社まで利用できるよう対象を拡充するものである。
使い勝手改善にはほど遠いが
自社株軽減を利用することができる範囲は広がるが、自社株軽減制度の使い勝手改善にはほど遠い。自社株軽減は、現行どおり3億円部分までを対象とし、軽減率も変わらない。軽減額は、最大で3億円×10%=3,000万円である。小規模宅地の評価減特例には金額的な頭打ちはない。小規模宅地特例に対する自社株特例の使い勝手の悪さが、抜本的に改善されたものとはいいがたい。自社株特例を抜本的に見直すのであれば、1)3億円の枠の拡大、2)軽減率のアップ、3)小規模宅地特例との重複適用禁止規定の見直しが不可避である。
今回の改正は、上記1)2)に手をつけたものではなく、3)小規模宅地特例との重複適用禁止規定の見直しを限度余裕部分についてだけ行った(図3参照)きわめて小ぶりなものである。しかし、併用される小規模宅地特例については、対象を限定せずに割合計算を行っているので、小規模宅地特例を限度一杯に利用できない場合には、広く減税効果が期待できそうだ。
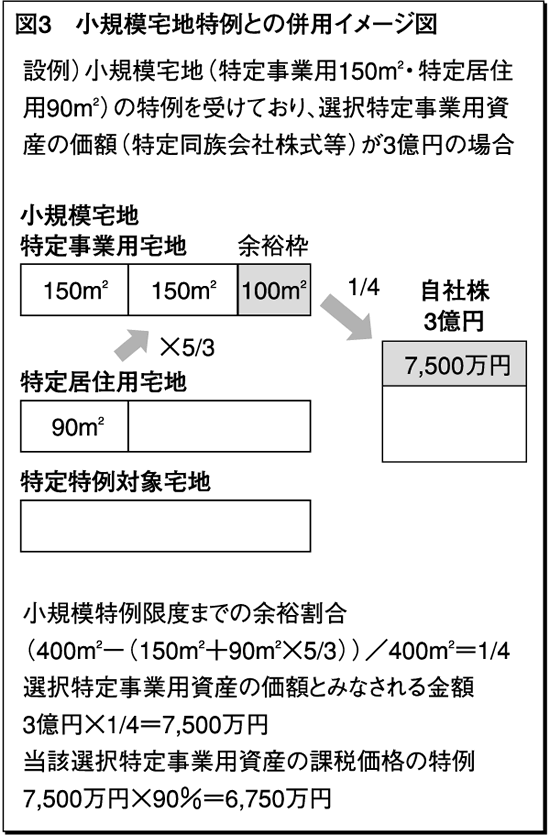
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















