コラム2014年03月03日 【SCOPE】 会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず(2014年3月3日号・№537)
課徴金を命じた金融庁と異なる判断を示す
会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず
課徴金の納付命令を受けたビックカメラをめぐり、同社の株主が提起していた株主代表訴訟で、役員らが勝訴する判決が下された(東京地裁平成25年12月26日判決)。本件では、ビックカメラが信託受益権の譲渡取引を「売却取引」と判断したことが適法か否かが問題となっていた。この点、裁判所は、ビックカメラの会計処理は違法とはいえないと判断し、株主側の役員らに対する損害賠償請求を斥けている。この裁判所の判断は、会計処理(売却取引)を違法と判断した金融庁の課徴金納付命令と異なるもの。本事案の株主側は、課徴金の是非を審判手続きで争わないことを選択した点について、役員らに対して損害賠償を求めていたが、裁判所はこれも棄却している。なお、敗訴した株主側は、控訴している。
裁判所、「売却取引」とした会計処理は流動化実務指針に違反せず
本事案では、東証1部上場企業のビックカメラが上場前に行っていたSPCを利用した不動産流動化を伴う信託受益権の譲渡取引が、「売却取引」と「金融取引(≠売却)」のいずれかであるかが問題となっていた。
流動化実務指針では、譲渡人のリスク負担割合が5%を超えると、「金融取引」として取り扱われることとなる(5項、13項)。また、譲渡人の子会社が負担するリスクを譲渡人が負担するリスクに加える旨が規定さている(16項)。
これを本事案でみると、SPCへの出資(総額290億円)は、譲渡人であるビックカメラが約15億円、A社(ビックカメラ創業者かつ大株主である被告役員Yが100%支配)が約75億円であった(図参照)。このとき、ビックカメラ単体でみた場合のリスク負担割合は5%である。ただ、A社がビックカメラの子会社に該当するのであれば、ビックカメラのリスク負担割合は約31%になり、信託受益権の譲渡は「金融取引」となる。
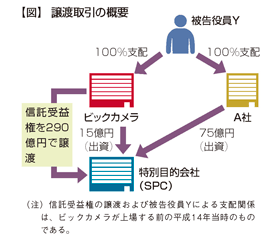
証取委は金融取引と判断、課徴金の納付命令 ビックカメラは、信託受益権の譲渡について、A社は子会社に該当しないため、「売却取引」と判断していた。しかし、証取委がA社は子会社に該当する旨を指摘したことを受け、譲渡取引を「金融取引」に変更する過年度決算訂正を行った。このとき、ビックカメラは、約2億円の課徴金納付命令を受けている。
この処分を受け、ビックカメラの株主は、会計処理につき任務懈怠があったとして、同社の役員らに対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起していた。
売却取引は適法、役員の任務懈怠を認めず 株主の訴えに対して、裁判所は、ビックカメラがその大株主である被告役員Yを通じてA社の意思決定機関を支配しているということはできないなどと指摘し、A社はビックカメラの子会社には該当しないと判断した。
また、仮にA社が子会社に該当するとしても、ビックカメラとA社を実質的に支配していた被告役員Yは、両社の親会社類似の立場にあり、A社が負担するリスクは、被告役員Yが最終的に負担することになると指摘。A社が負担するリスクをビックカメラが負担するリスクに加算しないことも、流動化実務指針上、許容されていると判断した。
そのうえで、信託受益権の譲渡を「売却取引」とした会計処理は、流動化実務指針に反する違法なものとは認められないため、役員らに会計処理の違法を根拠とした任務懈怠は認められないと結論付けた。
課徴金の是非を審判手続きで争わなかった役員らの責任は?
ビックカメラは、当初は信託受益権の譲渡を「売却取引」と処理していたが、証取委の指導を踏まえ、「金融取引」とする内容の過年度決算訂正を行っている。このとき、ビックカメラは、売却取引とした会計処理が適法か否かを課徴金の審判手続き(今号42頁参照)で争うことはなかった。
今回の判決は、信託受益権の譲渡を「売却取引」としたビックカメラの会計処理を適法と判断している。これは、会計処理(売却取引)を違法と判断した金融庁の課徴金納付命令と異なるものだ。
この点、本事案の株主側は、課徴金の是非を審判手続きで争わないことを選択した取締役らに対して、課徴金相当額の損害賠償を求める主張も行っていた。
しかし、裁判所は、会計監査人の辞任や上場廃止のリスクがあると考えたうえで課徴金を支払うことにより問題の早期終結を図った役員らの判断に著しい不合理があったとまではいえないと指摘し、役員への賠償責任を求める株主側の主張を斥けている。
会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず
課徴金の納付命令を受けたビックカメラをめぐり、同社の株主が提起していた株主代表訴訟で、役員らが勝訴する判決が下された(東京地裁平成25年12月26日判決)。本件では、ビックカメラが信託受益権の譲渡取引を「売却取引」と判断したことが適法か否かが問題となっていた。この点、裁判所は、ビックカメラの会計処理は違法とはいえないと判断し、株主側の役員らに対する損害賠償請求を斥けている。この裁判所の判断は、会計処理(売却取引)を違法と判断した金融庁の課徴金納付命令と異なるもの。本事案の株主側は、課徴金の是非を審判手続きで争わないことを選択した点について、役員らに対して損害賠償を求めていたが、裁判所はこれも棄却している。なお、敗訴した株主側は、控訴している。
裁判所、「売却取引」とした会計処理は流動化実務指針に違反せず
本事案では、東証1部上場企業のビックカメラが上場前に行っていたSPCを利用した不動産流動化を伴う信託受益権の譲渡取引が、「売却取引」と「金融取引(≠売却)」のいずれかであるかが問題となっていた。
流動化実務指針では、譲渡人のリスク負担割合が5%を超えると、「金融取引」として取り扱われることとなる(5項、13項)。また、譲渡人の子会社が負担するリスクを譲渡人が負担するリスクに加える旨が規定さている(16項)。
これを本事案でみると、SPCへの出資(総額290億円)は、譲渡人であるビックカメラが約15億円、A社(ビックカメラ創業者かつ大株主である被告役員Yが100%支配)が約75億円であった(図参照)。このとき、ビックカメラ単体でみた場合のリスク負担割合は5%である。ただ、A社がビックカメラの子会社に該当するのであれば、ビックカメラのリスク負担割合は約31%になり、信託受益権の譲渡は「金融取引」となる。
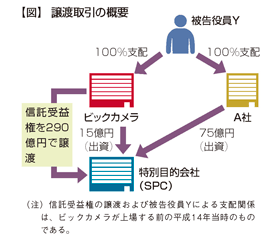
証取委は金融取引と判断、課徴金の納付命令 ビックカメラは、信託受益権の譲渡について、A社は子会社に該当しないため、「売却取引」と判断していた。しかし、証取委がA社は子会社に該当する旨を指摘したことを受け、譲渡取引を「金融取引」に変更する過年度決算訂正を行った。このとき、ビックカメラは、約2億円の課徴金納付命令を受けている。
この処分を受け、ビックカメラの株主は、会計処理につき任務懈怠があったとして、同社の役員らに対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起していた。
売却取引は適法、役員の任務懈怠を認めず 株主の訴えに対して、裁判所は、ビックカメラがその大株主である被告役員Yを通じてA社の意思決定機関を支配しているということはできないなどと指摘し、A社はビックカメラの子会社には該当しないと判断した。
また、仮にA社が子会社に該当するとしても、ビックカメラとA社を実質的に支配していた被告役員Yは、両社の親会社類似の立場にあり、A社が負担するリスクは、被告役員Yが最終的に負担することになると指摘。A社が負担するリスクをビックカメラが負担するリスクに加算しないことも、流動化実務指針上、許容されていると判断した。
そのうえで、信託受益権の譲渡を「売却取引」とした会計処理は、流動化実務指針に反する違法なものとは認められないため、役員らに会計処理の違法を根拠とした任務懈怠は認められないと結論付けた。
| 【参考】「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」 (日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号) |
| 第5項 ……リスクと経済価値のほとんどすべてが、譲受人である特別目的会社を通じて他の者に移転していると認められる場合には、譲渡人は不動産の譲渡取引を売却取引として会計処理する。 第13項 ……リスク負担割合がおおむね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取扱う。 第16項 ……リスク負担割合の算定に当たっては、譲渡人の子会社または関連会社が負担するリスクを譲渡人が負担するリスクに加えてリスク負担割合を算定して判断する。 第40項 ……なお、譲渡人の親会社及び子会社がリスクを負担する場合には、当該リスクを含めないで算定する。 ※ 一部省略化したうえで抜粋 |
課徴金の是非を審判手続きで争わなかった役員らの責任は?
ビックカメラは、当初は信託受益権の譲渡を「売却取引」と処理していたが、証取委の指導を踏まえ、「金融取引」とする内容の過年度決算訂正を行っている。このとき、ビックカメラは、売却取引とした会計処理が適法か否かを課徴金の審判手続き(今号42頁参照)で争うことはなかった。
今回の判決は、信託受益権の譲渡を「売却取引」としたビックカメラの会計処理を適法と判断している。これは、会計処理(売却取引)を違法と判断した金融庁の課徴金納付命令と異なるものだ。
この点、本事案の株主側は、課徴金の是非を審判手続きで争わないことを選択した取締役らに対して、課徴金相当額の損害賠償を求める主張も行っていた。
しかし、裁判所は、会計監査人の辞任や上場廃止のリスクがあると考えたうえで課徴金を支払うことにより問題の早期終結を図った役員らの判断に著しい不合理があったとまではいえないと指摘し、役員への賠償責任を求める株主側の主張を斥けている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























