解説記事2014年09月08日 【ニュース特集】 27年度税制改正要望 世代間の資産移転を促進(2014年9月8日号・№561)
ジュニアNISA創設・教育・住宅資金非課税の拡充etc.
27年度税制改正要望 世代間の資産移転を促進
各省庁等の平成27年度税制改正要望が出揃った。高齢者層から若年者層等への世代間の資産移転を促すための要望が目立つ内容だ。金融庁は、ジュニアNISAの創設を要望。文部科学省は金融庁と共同で教育資金一括贈与非課税制度の拡充を求める。国土交通省は、住宅取得等資金の贈与税非課税措置の拡充を要望する。また、経済産業省は、事業承継税制の拡充として、2代目から3代目への再贈与にも贈与税の納税猶予を要望している。本特集では、各省庁が27年度改正で要望する世代間の資産移転を促す制度を中心にその概要を紹介する。
ジュニアNISA創設で高齢者の金融資産を移転
金融庁が平成27年度税制改正で要望するのが、ジュニアNISA(仮称)の創設だ。平成25年度税制改正で創設された現行の(成人)NISAは、総口座数が約650万口座、総買付資金は約1兆円に達している。しかし、口座開設者の6割を60代以上が占めることから、金融庁は、高齢者から若年層へと金融資金を移転することで経済成長・長期投資を促進するため、ジュニアNISAの創設を求める。
ジュニアNISAは、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とし、親や祖父母などが資金を拠出するもの。ただし、資金拠出者には親族などの制限はなく誰でも資金を拠出することができる。投資上限額は年間80万円であり、現行NISA(年間100万円)と比べて若干少額に設定されている。ジュニアNISAが未成年者向けの制度であることが理由だ。
口座の管理・運用は、親権者等が未成年者を代理して行うが、災害などやむを得ない場合を除いて子や孫などが18歳になるまで払い出しが制限される。これは、払い出した資金を子や孫などのために使用することを担保するための措置であり、18歳までに払い出した場合は、過去の利益に対して課税される。
なお、口座からの資金の払出しを18歳以降可能としたのは、子や孫などが大学に進学するケースを想定したものだが、ジュニアNISAでは、払い出した資金の使用目的が教育に限定はされていない。
現行NISAの投資上限額拡大 金融庁は、ジュニアNISAの創設に加えて、現行NISAの年間投資上限額の引上げも要望。毎月一定額の積立てに適した金額として、120万円(毎月10万円×12か月)とすることを求める。この改正が実現した場合、ジュニアNISAと合わせた年間投資上限額は200万円となり、現行NISAの上限額から倍増することになる。
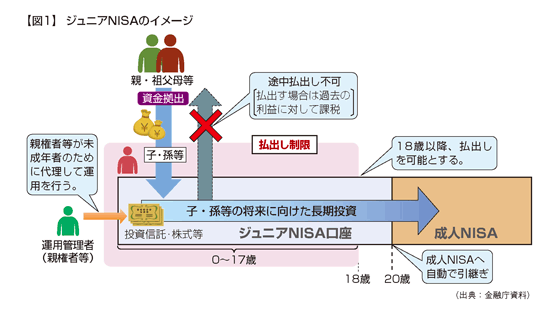
非課税対象となる「教育費」、贈与者範囲を拡充
文部科学省は、金融庁と共同で、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充を要望する。この制度は、平成25年度税制改正で創設されたもの。信託協会の集計では、今年6月末現在で、口座数7万6,851口座、信託財産設定額5,193億円となっている。
文科省は、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限が来年末までとされていることから、制度の恒久化を要望する。また、現行制度では、贈与税が非課税となる「教育費」の範囲が、学校等の入学金や授業料、塾やスポーツまたは文化芸術をはじめとする習い事とされていることから、教育に密接に関連するものとして、通学定期券などの交通費等を「教育費」に加えることなどを求める。さらに、直系尊属に限定されている「贈与者」の範囲について、叔父や叔母、篤志家などからの贈与も贈与税非課税の対象とすることも要望する。なお、この点、金融庁は、贈与税非課税の対象となる「受贈者」の範囲の拡大(直系卑属限定の廃止)を要望している(図2参照)。
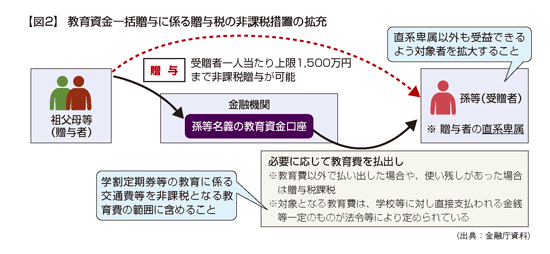
住宅取得等資金非課税制度を延長・拡充
国土交通省が要望するのは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充だ。この制度は、直系尊属からの贈与により、家屋の新築・増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合、以下の表に示した非課税限度額までの金額について、贈与税を非課税とするもの。
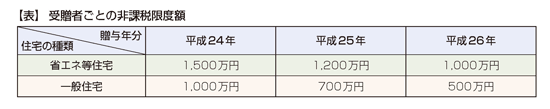
国交省は、①住宅の一次取得者層である30歳代の住宅取得資金が大幅に不足している一方、60歳以上の高齢者世帯の4分の1が3,000万円以上の貯蓄残高を有しており、高齢者層が保有する資産を現役世代に移転させて住宅取得を促進し、経済活性化を図る必要がある。②消費税率10%引上げ時の住宅着工の反動減への対応も必要などと指摘。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の3年間の延長、非課税枠を最大3,000万円まで拡充することを要望する。
2代目から3代目への株式再贈与に納税猶予
経済産業省は、事業承継税制(非上場株式等の贈与税の納税猶予制度)の拡充を要望する。事業承継税制については、平成25年度税制改正で適用要件の大幅な見直しが行われている。具体的には、①雇用確保要件の緩和(5年間平均で8割以上)、②後継者の親族間承継要件の廃止(親族外への承継が可能)、③先代経営者の役員退任要件の緩和(代表者を退任すれば役員の退任までは不要)などが手当てされている。
ただし、経産省は、事業承継税制の活用を促進するため、さらに拡充を行う必要があると指摘。贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者(2代目)が、一定の要件の下で株式を3代目に再贈与した場合に、その再贈与に係る贈与税に対して贈与税の納税猶予制度が適用できるよう求めている(図3参照)。
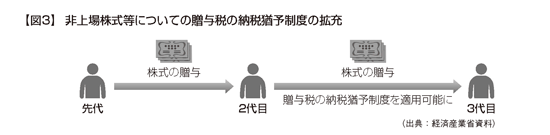
現行の事業承継税制では、事業を承継した後継者(2代目)が、その後、3代目の後継者に事業を承継する場合、先代が健在(相続税の納税猶予制度へ未切替)であれば3代目に株式を贈与した時点で納税猶予が打切りとなり、2代目に猶予されていた贈与税に納税義務が生じることになる。この点を問題視した経産省が、2代目から3代目への株式の再贈与に事業承継税制の適用を要望したものだ。
個人事業者版の事業承継税制を また、経産省は、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設も要望している。具体的には、①経産大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税について、相続時精算課税を適用する。②当該贈与から5年間(または贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経産大臣の確認を受け続けた場合、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算で贈与時の課税価格を軽減するというものだ。
診療報酬対応か、課税化(ゼロ税率)実現か
そのほか、平成27年度税制改正要望で注目されるのが、厚生労働省の「医療に係る消費税の課税のあり方の検討」だ。
消費税率8%引上げ時、医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬とは別建ての高額投資対応を行わず、診療報酬上乗せのみで対応した(図4参照)。しかし、中医協の議論では、診療側が税率10%引上げ時における税制による抜本的な措置での対応を強く要望していた。また、与党税制協議会の消費税軽減税率ヒアリングにおいても、日本医師会が社会保険診療の課税化(軽減税率の適用)を主張している。税率10%引上げ時の対応が焦点となりそうだ。
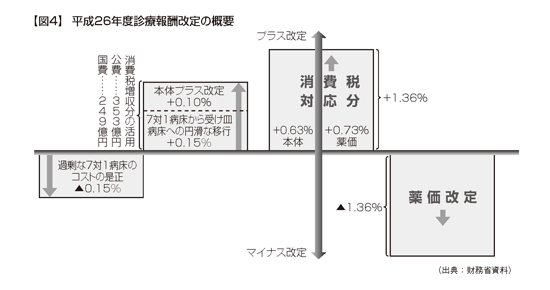
27年度税制改正要望 世代間の資産移転を促進
各省庁等の平成27年度税制改正要望が出揃った。高齢者層から若年者層等への世代間の資産移転を促すための要望が目立つ内容だ。金融庁は、ジュニアNISAの創設を要望。文部科学省は金融庁と共同で教育資金一括贈与非課税制度の拡充を求める。国土交通省は、住宅取得等資金の贈与税非課税措置の拡充を要望する。また、経済産業省は、事業承継税制の拡充として、2代目から3代目への再贈与にも贈与税の納税猶予を要望している。本特集では、各省庁が27年度改正で要望する世代間の資産移転を促す制度を中心にその概要を紹介する。
ジュニアNISA創設で高齢者の金融資産を移転
金融庁が平成27年度税制改正で要望するのが、ジュニアNISA(仮称)の創設だ。平成25年度税制改正で創設された現行の(成人)NISAは、総口座数が約650万口座、総買付資金は約1兆円に達している。しかし、口座開設者の6割を60代以上が占めることから、金融庁は、高齢者から若年層へと金融資金を移転することで経済成長・長期投資を促進するため、ジュニアNISAの創設を求める。
ジュニアNISAは、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とし、親や祖父母などが資金を拠出するもの。ただし、資金拠出者には親族などの制限はなく誰でも資金を拠出することができる。投資上限額は年間80万円であり、現行NISA(年間100万円)と比べて若干少額に設定されている。ジュニアNISAが未成年者向けの制度であることが理由だ。
口座の管理・運用は、親権者等が未成年者を代理して行うが、災害などやむを得ない場合を除いて子や孫などが18歳になるまで払い出しが制限される。これは、払い出した資金を子や孫などのために使用することを担保するための措置であり、18歳までに払い出した場合は、過去の利益に対して課税される。
なお、口座からの資金の払出しを18歳以降可能としたのは、子や孫などが大学に進学するケースを想定したものだが、ジュニアNISAでは、払い出した資金の使用目的が教育に限定はされていない。
現行NISAの投資上限額拡大 金融庁は、ジュニアNISAの創設に加えて、現行NISAの年間投資上限額の引上げも要望。毎月一定額の積立てに適した金額として、120万円(毎月10万円×12か月)とすることを求める。この改正が実現した場合、ジュニアNISAと合わせた年間投資上限額は200万円となり、現行NISAの上限額から倍増することになる。
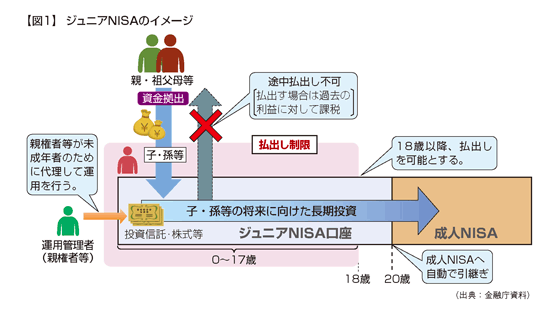
非課税対象となる「教育費」、贈与者範囲を拡充
文部科学省は、金融庁と共同で、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充を要望する。この制度は、平成25年度税制改正で創設されたもの。信託協会の集計では、今年6月末現在で、口座数7万6,851口座、信託財産設定額5,193億円となっている。
文科省は、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限が来年末までとされていることから、制度の恒久化を要望する。また、現行制度では、贈与税が非課税となる「教育費」の範囲が、学校等の入学金や授業料、塾やスポーツまたは文化芸術をはじめとする習い事とされていることから、教育に密接に関連するものとして、通学定期券などの交通費等を「教育費」に加えることなどを求める。さらに、直系尊属に限定されている「贈与者」の範囲について、叔父や叔母、篤志家などからの贈与も贈与税非課税の対象とすることも要望する。なお、この点、金融庁は、贈与税非課税の対象となる「受贈者」の範囲の拡大(直系卑属限定の廃止)を要望している(図2参照)。
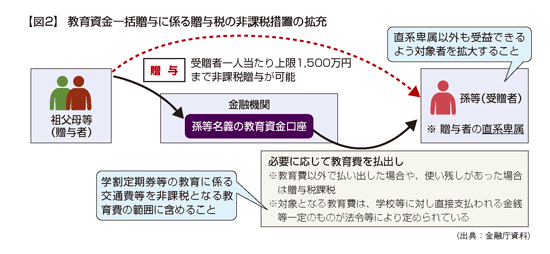
住宅取得等資金非課税制度を延長・拡充
国土交通省が要望するのは、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充だ。この制度は、直系尊属からの贈与により、家屋の新築・増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合、以下の表に示した非課税限度額までの金額について、贈与税を非課税とするもの。
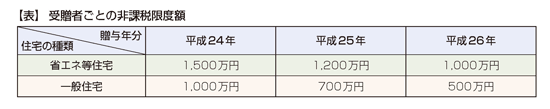
国交省は、①住宅の一次取得者層である30歳代の住宅取得資金が大幅に不足している一方、60歳以上の高齢者世帯の4分の1が3,000万円以上の貯蓄残高を有しており、高齢者層が保有する資産を現役世代に移転させて住宅取得を促進し、経済活性化を図る必要がある。②消費税率10%引上げ時の住宅着工の反動減への対応も必要などと指摘。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の3年間の延長、非課税枠を最大3,000万円まで拡充することを要望する。
2代目から3代目への株式再贈与に納税猶予
経済産業省は、事業承継税制(非上場株式等の贈与税の納税猶予制度)の拡充を要望する。事業承継税制については、平成25年度税制改正で適用要件の大幅な見直しが行われている。具体的には、①雇用確保要件の緩和(5年間平均で8割以上)、②後継者の親族間承継要件の廃止(親族外への承継が可能)、③先代経営者の役員退任要件の緩和(代表者を退任すれば役員の退任までは不要)などが手当てされている。
ただし、経産省は、事業承継税制の活用を促進するため、さらに拡充を行う必要があると指摘。贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者(2代目)が、一定の要件の下で株式を3代目に再贈与した場合に、その再贈与に係る贈与税に対して贈与税の納税猶予制度が適用できるよう求めている(図3参照)。
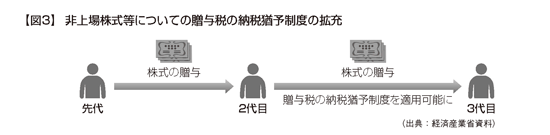
現行の事業承継税制では、事業を承継した後継者(2代目)が、その後、3代目の後継者に事業を承継する場合、先代が健在(相続税の納税猶予制度へ未切替)であれば3代目に株式を贈与した時点で納税猶予が打切りとなり、2代目に猶予されていた贈与税に納税義務が生じることになる。この点を問題視した経産省が、2代目から3代目への株式の再贈与に事業承継税制の適用を要望したものだ。
個人事業者版の事業承継税制を また、経産省は、個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設も要望している。具体的には、①経産大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税について、相続時精算課税を適用する。②当該贈与から5年間(または贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経産大臣の確認を受け続けた場合、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算で贈与時の課税価格を軽減するというものだ。
診療報酬対応か、課税化(ゼロ税率)実現か
そのほか、平成27年度税制改正要望で注目されるのが、厚生労働省の「医療に係る消費税の課税のあり方の検討」だ。
消費税率8%引上げ時、医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬とは別建ての高額投資対応を行わず、診療報酬上乗せのみで対応した(図4参照)。しかし、中医協の議論では、診療側が税率10%引上げ時における税制による抜本的な措置での対応を強く要望していた。また、与党税制協議会の消費税軽減税率ヒアリングにおいても、日本医師会が社会保険診療の課税化(軽減税率の適用)を主張している。税率10%引上げ時の対応が焦点となりそうだ。
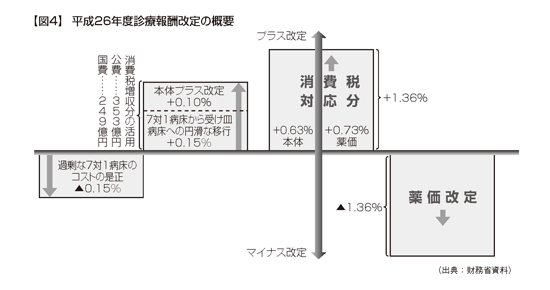
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























