解説記事2014年12月22日 【ニュース特集】 貸付金利息の収入時期、履行期に確定は誤り(2014年12月22日号・№576)
審判所、期間対応に拠らない解釈を一蹴
貸付金利息の収入時期、履行期に確定は誤り
貸付金利息の“収入すべき時期”が争点となった審査請求で、原処分庁による所得税法、所基通に関する解釈が退けられ、更正処分の一部が取り消される事案があった。原処分庁は、利息債権は履行期が到来すれば、権利が確定し、所法36条1項規定の「収入すべき金額」に当たるものとなり、所基通36-8(7)における「その年に対応するもの」は、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの主張を展開したが、審判所は法令等の解釈に基づきこれを一蹴している。
生前贈与のために資金を貸し付け
所得税法は、いわゆる権利確定主義を採用しており、現実の収入がなくても、収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったものとして、その年分の課税所得を計算することになる。また、所基通36-8(7)は、貸付金利息のその年に対応するものに係る収入すべき時期について、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)によるものとしている(下掲参照)。
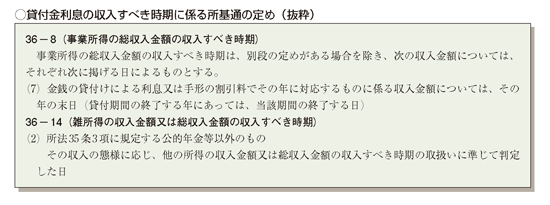
今回の事案では、貸付金利息に係る「収入すべき時期」が争点となった。
事案の内容をみていこう。
請求人(歯科医師)および母Aは、平成3年頃、①母Aが請求人の弟Bおよびその家族に対して生前贈与を行うための金銭を請求人が母Aに対して貸し付けること、②母Aが所有する不動産を売却して現金化したとき、または母Aの死亡に係る相続のときにその借入金を返済することで基本合意をした。請求人は、この基本合意に基づき母Aに対して、平成4年に1,240万円、平成5年に約1,118万500円、平成6年に約438万円、平成7年に240万円、平成8年に240万円、平成9年に800万円をそれぞれ貸し付けた。
請求人および母Aは、平成7年11月1日、①母Aが請求人の弟Bおよびその家族に対して生前贈与を行うために、請求人が母Aに金銭を貸し付けること、②この貸付けに関する利息は年2%とし、返済時にまとめて精算することなどを記載した確認書を作成した。
母Aは、平成23年2月13日、所有する土地(本件土地)について、不動産売買契約を締結。平成23年3月18日、本件土地を買主に引き渡したことにより、本件土地が現金化され、母Aが貸付金を返済することとなったため、貸付金の貸付期間が平成23年3月18日に終了した。
なお、請求人は利息について、記帳等の経理処理を一切行っていない。
履行期が到来すれば権利確定と主張
上記の事実関係から、原処分庁は、本件貸付金に係る利息は、貸付当初からその履行に至るまでに生じた利息の全額が、履行期の到来する平成23年分の収入すべき金額であるなどとして、所得税の更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
注目されるのは、原処分庁による所法36条1項、所基通36-8(7)の解釈だ。
原処分庁は、権利確定主義のもとでは、利息債権の履行期が到来すれば、権利が確定し、所法36条1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものとなり、所基通36-8における「その年に対応するもの」は、その年に権利が確定したものをいうとの解釈を展開(図1参照)。
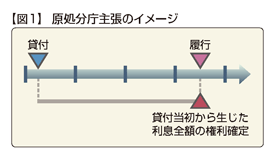
本事案では、母Aが本件土地を売却した平成23年3月18日が利息の履行期であり、この日に利息の全額が確定したと主張した(前頁下掲参照)。
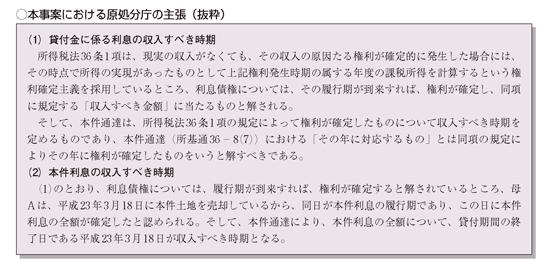
「その年に対応するもの」=計算期間の経過に対応
原処分庁の主張に対し、審判所は、貸付金利息について、(1)元本が返還されるまで日々発生するもので、期間の経過により直ちに利息債権が発生して権利が確定する。(2)所基通36-8(7)の定めは、一般の企業会計慣行に従い、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言は、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であると指摘(図2・下掲参照)。
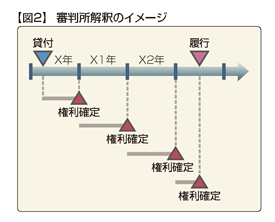
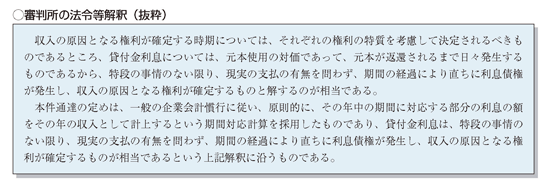
そのうえで、本事案で貸付金から生じる利息は、請求人の営む事業に係る活動とは関係なく請求人と母Aとの親子関係に由来して個人的に貸し付けられたものであるから、雑所得に該当し、その利息が期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因とる権利が確定するものといはいえないような特段の事情は見当たらないから、所基通36-8(7)により収入すべき時期を判断するのが相当と認定。
本事案における利息の収入すべき時期については、利息に関する合意がなされた平成7年から平成22年までの各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期はそれぞれの年の末日、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年3月18日であると判断した。なお、請求人の平成23年分の当該利息に係る雑所得の金額は、17万1,975円(4,076万500円×0.02×77/365)となる。
貸付金利息の収入時期、履行期に確定は誤り
貸付金利息の“収入すべき時期”が争点となった審査請求で、原処分庁による所得税法、所基通に関する解釈が退けられ、更正処分の一部が取り消される事案があった。原処分庁は、利息債権は履行期が到来すれば、権利が確定し、所法36条1項規定の「収入すべき金額」に当たるものとなり、所基通36-8(7)における「その年に対応するもの」は、同項の規定によりその年に権利が確定したものをいうとの主張を展開したが、審判所は法令等の解釈に基づきこれを一蹴している。
生前贈与のために資金を貸し付け
所得税法は、いわゆる権利確定主義を採用しており、現実の収入がなくても、収入の原因となる権利が確定した時点で所得の実現があったものとして、その年分の課税所得を計算することになる。また、所基通36-8(7)は、貸付金利息のその年に対応するものに係る収入すべき時期について、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)によるものとしている(下掲参照)。
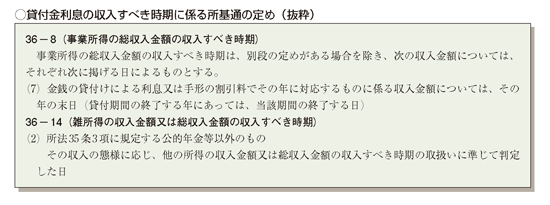
今回の事案では、貸付金利息に係る「収入すべき時期」が争点となった。
事案の内容をみていこう。
請求人(歯科医師)および母Aは、平成3年頃、①母Aが請求人の弟Bおよびその家族に対して生前贈与を行うための金銭を請求人が母Aに対して貸し付けること、②母Aが所有する不動産を売却して現金化したとき、または母Aの死亡に係る相続のときにその借入金を返済することで基本合意をした。請求人は、この基本合意に基づき母Aに対して、平成4年に1,240万円、平成5年に約1,118万500円、平成6年に約438万円、平成7年に240万円、平成8年に240万円、平成9年に800万円をそれぞれ貸し付けた。
請求人および母Aは、平成7年11月1日、①母Aが請求人の弟Bおよびその家族に対して生前贈与を行うために、請求人が母Aに金銭を貸し付けること、②この貸付けに関する利息は年2%とし、返済時にまとめて精算することなどを記載した確認書を作成した。
母Aは、平成23年2月13日、所有する土地(本件土地)について、不動産売買契約を締結。平成23年3月18日、本件土地を買主に引き渡したことにより、本件土地が現金化され、母Aが貸付金を返済することとなったため、貸付金の貸付期間が平成23年3月18日に終了した。
なお、請求人は利息について、記帳等の経理処理を一切行っていない。
履行期が到来すれば権利確定と主張
上記の事実関係から、原処分庁は、本件貸付金に係る利息は、貸付当初からその履行に至るまでに生じた利息の全額が、履行期の到来する平成23年分の収入すべき金額であるなどとして、所得税の更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
注目されるのは、原処分庁による所法36条1項、所基通36-8(7)の解釈だ。
原処分庁は、権利確定主義のもとでは、利息債権の履行期が到来すれば、権利が確定し、所法36条1項に規定する「収入すべき金額」に当たるものとなり、所基通36-8における「その年に対応するもの」は、その年に権利が確定したものをいうとの解釈を展開(図1参照)。
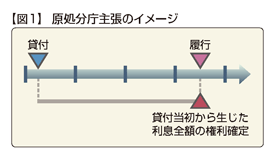
本事案では、母Aが本件土地を売却した平成23年3月18日が利息の履行期であり、この日に利息の全額が確定したと主張した(前頁下掲参照)。
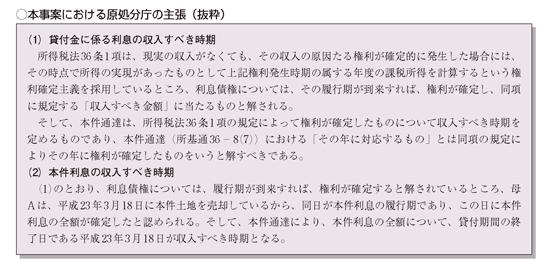
「その年に対応するもの」=計算期間の経過に対応
原処分庁の主張に対し、審判所は、貸付金利息について、(1)元本が返還されるまで日々発生するもので、期間の経過により直ちに利息債権が発生して権利が確定する。(2)所基通36-8(7)の定めは、一般の企業会計慣行に従い、期間対応計算を採用したものであるから、「その年に対応するもの」との文言は、その年における利息の計算期間の経過に対応するものと解するのが相当であると指摘(図2・下掲参照)。
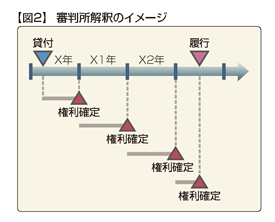
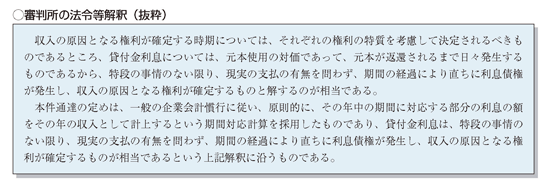
そのうえで、本事案で貸付金から生じる利息は、請求人の営む事業に係る活動とは関係なく請求人と母Aとの親子関係に由来して個人的に貸し付けられたものであるから、雑所得に該当し、その利息が期間の経過により直ちに利息債権が発生し、収入の原因とる権利が確定するものといはいえないような特段の事情は見当たらないから、所基通36-8(7)により収入すべき時期を判断するのが相当と認定。
本事案における利息の収入すべき時期については、利息に関する合意がなされた平成7年から平成22年までの各年中の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期はそれぞれの年の末日、貸付期間の終了した平成23年の期間に対応する部分の金額に係る収入すべき時期は、貸付期間の終了した平成23年3月18日であると判断した。なお、請求人の平成23年分の当該利息に係る雑所得の金額は、17万1,975円(4,076万500円×0.02×77/365)となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















