解説記事2015年05月18日 【新会計基準解説】 改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の概要(2015年5月18日号・№594)
新会計基準解説
改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の概要
企業会計基準委員会 専門研究員 北村幸子
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成27年3月26日に改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本適用指針の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 改正の概要
1 改正の経緯 平成24年1月31日付で厚生労働省から、厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正及び特例的扱いについて」及び「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」及び「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について」(以下合わせて「平成24年厚生労働省通知」という。)が発出され、厚生年金基金及び確定給付企業年金の財務諸表の表示方法の変更が行われた。また、厚生年金基金における財務諸表の表示方法については、平成26年3月24日付で発出された厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正等について」(以下「平成26年厚生労働省通知」という。)による変更も行われた。ASBJにおいては、これらの表示方法の変更に伴い、本適用指針について必要と考えられる改正を行ったものである。
2 厚生年金基金及び確定給付企業年金における財務諸表の表示方法の変更の概要 平成24年厚生労働省通知により、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表について、変更前は、「数理債務」(負債)及び「未償却過去勤務債務残高」(資産)が表示されていたが、変更後は、「数理債務」から「未償却過去勤務債務残高」を控除した純額が、厚生年金基金の場合は「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)として、確定給付企業年金の場合は「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。「数理債務」の額と「未償却過去勤務債務残高」の額は、原則として、貸借対照表の欄外に注記されることとなった(脚注2)。
また、厚生年金基金の場合は、変更前は、「数理債務」(負債)と代行部分に該当する「最低責任準備金(継続基準)」(負債)を合計した額が貸借対照表に「給付債務」(負債)として表示されていたが、平成24年厚生労働省通知による変更に伴い、「給付債務」(負債)は貸借対照表には表示されなくなった。さらに、平成24年厚生労働省通知により「最低責任準備金(継続基準)」(負債)が、「最低責任準備金」(負債)及び「最低責任準備金調整額」(負債)に変更され、平成26年厚生労働省通知により「最低責任準備金」(負債)及び「最低責任準備金調整額」(負債)が、「最低責任準備金」(負債)に変更されている。これらの結果、「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)と「最低責任準備金」(負債)を合計した額が「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。
厚生年金基金及び確定給付企業年金の変更後の表示方法における貸借対照表の表示科目と欄外注記との関係は、次のとおりである。
(1)厚生年金基金の場合 ① 「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)=「数理債務」(欄外注記の額)-「未償却過去勤務債務残高」(欄外注記の額)
② 「責任準備金」(負債)=「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)+「最低責任準備金」(負債)
(2)確定給付企業年金の場合
「責任準備金」(負債)=「数理債務」(欄外注記の額)-「未償却過去勤務債務残高」(欄外注記の額)
変更前と変更後の厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表のイメージはそれぞれ図表1及び図表2のとおりである。
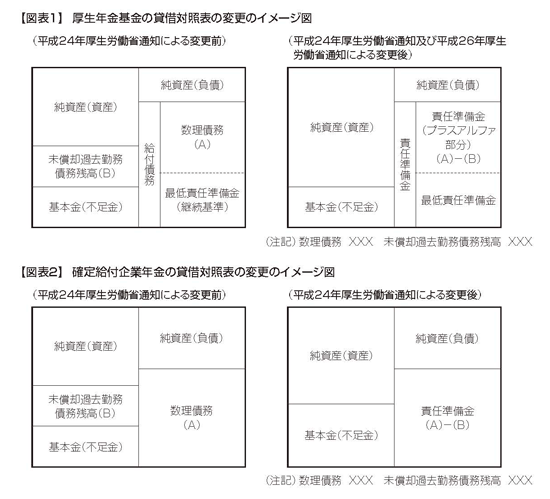
3 本適用指針の改正の概要 上記の厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の表示方法の変更を踏まえ、本適用指針において、以下の点について改正又は留意事項の記載の追加を行った。
(1)複数事業主制度の会計処理及び開示(確定拠出制度に準じた場合の開示) 複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度を採用している場合の取扱いは、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。)において、以下のように規定されている(退職給付会計基準第33項)。
① 合理的な基準により自社の負担に属する年金資産等の計算をしたうえで、確定給付制度の会計処理及び開示を行う。
② 自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行う。この場合、当該年金制度全体の直近の積立状況等についても注記する。
複数事業主制度を採用し、②の確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行うときの注記事項である「直近の積立状況等」とは、改正前の退職給付適用指針において、「年金制度全体の直近の積立状況等(年金資産の額、年金財政計算上の給付債務の額及びその差引額)及び年金制度全体の掛金等に占める自社の割合並びにこれらに関する補足説明をいうものとする。」とされていた。このうち、「年金財政計算上の給付債務の額」について、厚生年金基金の貸借対照表の表示方法の変更により、「給付債務」(負債)は厚生年金基金の貸借対照表に表示されなくなったため、今回必要と考えられる改正を行ったものである。本適用指針では、当該注記は将来の負担額の見込みに関する目安としての開示である(本適用指針第125項)ことに鑑み、従来と実質的に同じ内容の注記を求めることとし、名称を「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」と変更して、注記すべき金額を明らかにすることとした(本適用指針第65項及び第126-2項)。
当該注記の額を計算するにあたっては、年金財政計算上の数理債務の額は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず欄外に注記されているため、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額に基づき注記の額を計算することに留意する必要がある(本適用指針第126-2項)。
なお、「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」について、厚生年金基金の場合は両者の合計額となるが、確定給付企業年金の場合は代行部分の給付がないため、年金財政計算上の数理債務の額のみとなる。したがって、注記対象が確定給付企業年金のみの場合には、注記において使用する名称を「年金財政計算上の数理債務の額」とすることが考えられる(本適用指針第126-2項)。
本適用指針による、確定拠出制度に準じた場合の開示例は、本適用指針の[開示例3]で示された図表3が参考となる。当該開示例は、厚生年金基金の場合の開示例である。
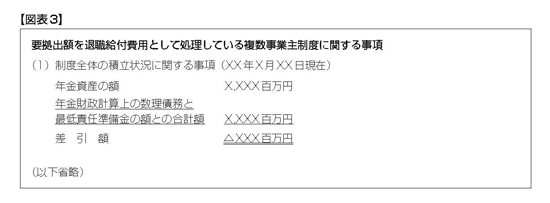
(2)簡便法による退職給付債務の計算 退職給付会計基準第26項では、従業員数が比較的少ない小規模な企業等においては、簡便な方法を用いて退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算することができるとされている。この簡便な方法(以下「簡便法」という。)を適用する場合の企業年金制度の退職給付債務の計算にあたっては、年金財政計算上の数理債務の額を用いる計算方法が本適用指針の第50項(2)及び同第51項(2)に示されている。年金財政計算上の数理債務の額は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず、欄外に注記されることとなったため、簡便法を適用する場合の企業年金制度の退職給付債務に年金財政計算上の数理債務の額を用いる場合の計算は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額(厚生年金基金の場合は当該「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額の合計額)を勘案して計算することに留意する必要がある(本適用指針第112-2項)。
(3)複数事業主制度の会計処理及び開示(自社の負担に属する年金資産等の計算に用いる合理的な基準) 複数事業主制度の会計処理において、自社の負担に属する年金資産等の計算を行うときの合理的な基準(退職給付会計基準第33項(1))の例示が、本適用指針第63項に示されている。このうち、年金財政計算における数理債務の額及び未償却過去勤務債務の額を用いる場合(本適用指針第63項(2)及び(3))においては、年金財政計算上の数理債務の額及び未償却過去勤務債務残高は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず、欄外に注記されることとなったため、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額(厚生年金基金の場合は当該「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額の合計額)及び「未償却過去勤務債務残高」の額を勘案して制度全体の額を算定し、自社の負担に属する年金資産等を計算することに留意する必要がある(本適用指針第119-2項参照)。
4 適用時期 厚生年金基金及び確定給付企業年金の財務諸表はすでに変更後の表示方法により作成されていることから、本適用指針は、公表日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する(本適用指針第129-2項)。
Ⅲ おわりに
本適用指針の適用については、表示方法の変更として取り扱うこととされているため、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定めに従って、表示する過去の期間における本適用指針第65項の注記についても新たな表示方法を適用することとなる。
なお、本適用指針の改正は厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の表示方法の変更を踏まえて行われたものであり、注記される金額や計算結果は実質的に従来と変更がない点に留意いただきたい。
脚注
1 本適用指針の全文はASBJのウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu2015/)を参照のこと。
2 貸借対照表の欄外に、数理債務と未償却過去勤務債務残高が注記されていない場合には、基金又は制度の受託者がそれらの数値を把握しているものと考えられる。
改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の概要
企業会計基準委員会 専門研究員 北村幸子
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成27年3月26日に改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)を公表した(脚注1)。本稿では、本適用指針の概要を紹介する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 改正の概要
1 改正の経緯 平成24年1月31日付で厚生労働省から、厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正及び特例的扱いについて」及び「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」及び「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について」(以下合わせて「平成24年厚生労働省通知」という。)が発出され、厚生年金基金及び確定給付企業年金の財務諸表の表示方法の変更が行われた。また、厚生年金基金における財務諸表の表示方法については、平成26年3月24日付で発出された厚生労働省通知「厚生年金基金の財政運営について等の一部改正等について」(以下「平成26年厚生労働省通知」という。)による変更も行われた。ASBJにおいては、これらの表示方法の変更に伴い、本適用指針について必要と考えられる改正を行ったものである。
2 厚生年金基金及び確定給付企業年金における財務諸表の表示方法の変更の概要 平成24年厚生労働省通知により、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表について、変更前は、「数理債務」(負債)及び「未償却過去勤務債務残高」(資産)が表示されていたが、変更後は、「数理債務」から「未償却過去勤務債務残高」を控除した純額が、厚生年金基金の場合は「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)として、確定給付企業年金の場合は「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。「数理債務」の額と「未償却過去勤務債務残高」の額は、原則として、貸借対照表の欄外に注記されることとなった(脚注2)。
また、厚生年金基金の場合は、変更前は、「数理債務」(負債)と代行部分に該当する「最低責任準備金(継続基準)」(負債)を合計した額が貸借対照表に「給付債務」(負債)として表示されていたが、平成24年厚生労働省通知による変更に伴い、「給付債務」(負債)は貸借対照表には表示されなくなった。さらに、平成24年厚生労働省通知により「最低責任準備金(継続基準)」(負債)が、「最低責任準備金」(負債)及び「最低責任準備金調整額」(負債)に変更され、平成26年厚生労働省通知により「最低責任準備金」(負債)及び「最低責任準備金調整額」(負債)が、「最低責任準備金」(負債)に変更されている。これらの結果、「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)と「最低責任準備金」(負債)を合計した額が「責任準備金」(負債)として表示されることとなった。
厚生年金基金及び確定給付企業年金の変更後の表示方法における貸借対照表の表示科目と欄外注記との関係は、次のとおりである。
(1)厚生年金基金の場合 ① 「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)=「数理債務」(欄外注記の額)-「未償却過去勤務債務残高」(欄外注記の額)
② 「責任準備金」(負債)=「責任準備金(プラスアルファ部分)」(負債)+「最低責任準備金」(負債)
(2)確定給付企業年金の場合
「責任準備金」(負債)=「数理債務」(欄外注記の額)-「未償却過去勤務債務残高」(欄外注記の額)
変更前と変更後の厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表のイメージはそれぞれ図表1及び図表2のとおりである。
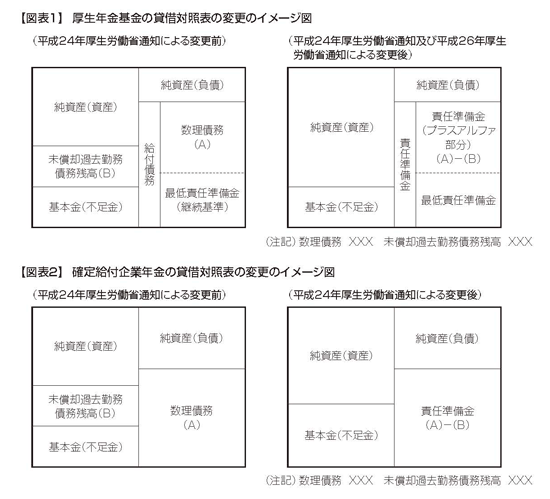
3 本適用指針の改正の概要 上記の厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の表示方法の変更を踏まえ、本適用指針において、以下の点について改正又は留意事項の記載の追加を行った。
(1)複数事業主制度の会計処理及び開示(確定拠出制度に準じた場合の開示) 複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度を採用している場合の取扱いは、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。)において、以下のように規定されている(退職給付会計基準第33項)。
① 合理的な基準により自社の負担に属する年金資産等の計算をしたうえで、確定給付制度の会計処理及び開示を行う。
② 自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないときには、確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行う。この場合、当該年金制度全体の直近の積立状況等についても注記する。
複数事業主制度を採用し、②の確定拠出制度に準じた会計処理及び開示を行うときの注記事項である「直近の積立状況等」とは、改正前の退職給付適用指針において、「年金制度全体の直近の積立状況等(年金資産の額、年金財政計算上の給付債務の額及びその差引額)及び年金制度全体の掛金等に占める自社の割合並びにこれらに関する補足説明をいうものとする。」とされていた。このうち、「年金財政計算上の給付債務の額」について、厚生年金基金の貸借対照表の表示方法の変更により、「給付債務」(負債)は厚生年金基金の貸借対照表に表示されなくなったため、今回必要と考えられる改正を行ったものである。本適用指針では、当該注記は将来の負担額の見込みに関する目安としての開示である(本適用指針第125項)ことに鑑み、従来と実質的に同じ内容の注記を求めることとし、名称を「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」と変更して、注記すべき金額を明らかにすることとした(本適用指針第65項及び第126-2項)。
当該注記の額を計算するにあたっては、年金財政計算上の数理債務の額は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず欄外に注記されているため、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額に基づき注記の額を計算することに留意する必要がある(本適用指針第126-2項)。
なお、「年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額」について、厚生年金基金の場合は両者の合計額となるが、確定給付企業年金の場合は代行部分の給付がないため、年金財政計算上の数理債務の額のみとなる。したがって、注記対象が確定給付企業年金のみの場合には、注記において使用する名称を「年金財政計算上の数理債務の額」とすることが考えられる(本適用指針第126-2項)。
本適用指針による、確定拠出制度に準じた場合の開示例は、本適用指針の[開示例3]で示された図表3が参考となる。当該開示例は、厚生年金基金の場合の開示例である。
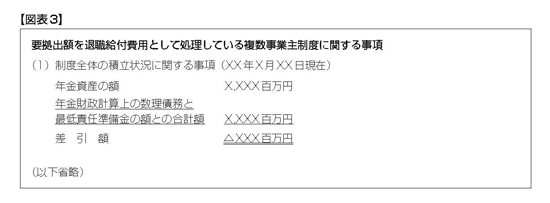
(2)簡便法による退職給付債務の計算 退職給付会計基準第26項では、従業員数が比較的少ない小規模な企業等においては、簡便な方法を用いて退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算することができるとされている。この簡便な方法(以下「簡便法」という。)を適用する場合の企業年金制度の退職給付債務の計算にあたっては、年金財政計算上の数理債務の額を用いる計算方法が本適用指針の第50項(2)及び同第51項(2)に示されている。年金財政計算上の数理債務の額は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず、欄外に注記されることとなったため、簡便法を適用する場合の企業年金制度の退職給付債務に年金財政計算上の数理債務の額を用いる場合の計算は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額(厚生年金基金の場合は当該「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額の合計額)を勘案して計算することに留意する必要がある(本適用指針第112-2項)。
(3)複数事業主制度の会計処理及び開示(自社の負担に属する年金資産等の計算に用いる合理的な基準) 複数事業主制度の会計処理において、自社の負担に属する年金資産等の計算を行うときの合理的な基準(退職給付会計基準第33項(1))の例示が、本適用指針第63項に示されている。このうち、年金財政計算における数理債務の額及び未償却過去勤務債務の額を用いる場合(本適用指針第63項(2)及び(3))においては、年金財政計算上の数理債務の額及び未償却過去勤務債務残高は、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表には表示されず、欄外に注記されることとなったため、厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の欄外に注記されている「数理債務」の額(厚生年金基金の場合は当該「数理債務」の額と貸借対照表に表示されている「最低責任準備金」(負債)の額の合計額)及び「未償却過去勤務債務残高」の額を勘案して制度全体の額を算定し、自社の負担に属する年金資産等を計算することに留意する必要がある(本適用指針第119-2項参照)。
4 適用時期 厚生年金基金及び確定給付企業年金の財務諸表はすでに変更後の表示方法により作成されていることから、本適用指針は、公表日以後最初に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する(本適用指針第129-2項)。
Ⅲ おわりに
本適用指針の適用については、表示方法の変更として取り扱うこととされているため、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定めに従って、表示する過去の期間における本適用指針第65項の注記についても新たな表示方法を適用することとなる。
なお、本適用指針の改正は厚生年金基金及び確定給付企業年金の貸借対照表の表示方法の変更を踏まえて行われたものであり、注記される金額や計算結果は実質的に従来と変更がない点に留意いただきたい。
脚注
1 本適用指針の全文はASBJのウェブサイト(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu2015/)を参照のこと。
2 貸借対照表の欄外に、数理債務と未償却過去勤務債務残高が注記されていない場合には、基金又は制度の受託者がそれらの数値を把握しているものと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















