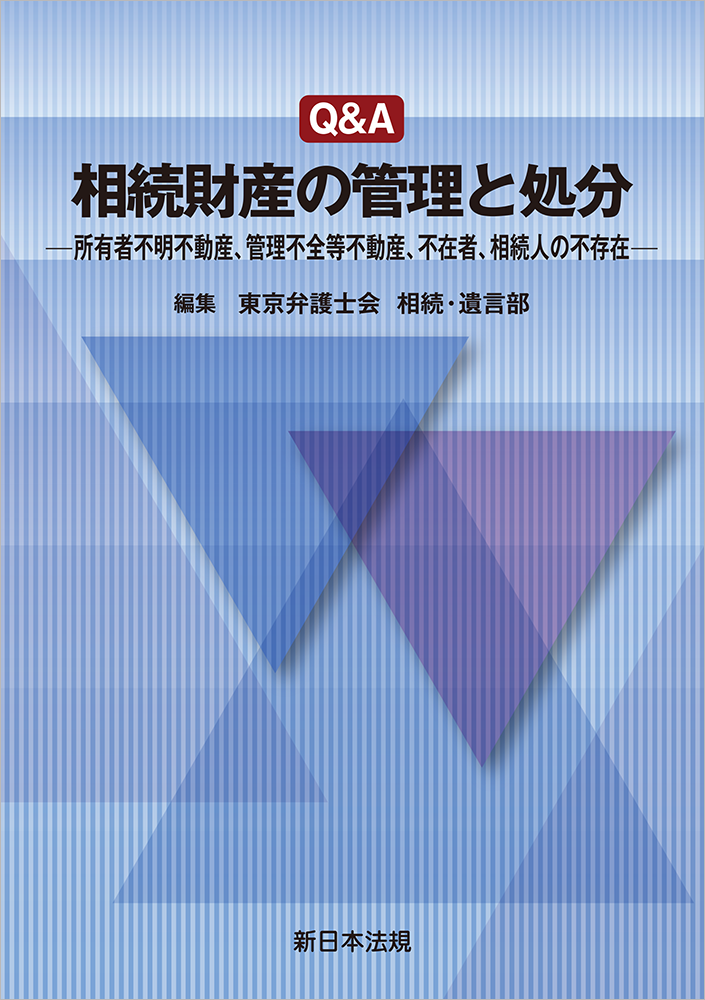資料2015年08月10日 【重要資料】 財産債務調書の提出制度(FAQ)(1)(2015年8月10日号・№606)
重要資料
財産債務調書の提出制度(FAQ)(1)
平成27年6月
国税庁
Ⅰ 通則
【制度の概要等】
(答)
○ 財産債務調書制度は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない方が、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上の財産又は価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する場合に、財産の種類、数量、価額並びに債務の金額などを記載した「財産債務調書」を、翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出していただく制度です(国外送金等調書法6の2①本文)。
財産債務調書を提出しなければならない方の詳細についてはQ2を、財産債務調書の記載事項についてはQ4~Q18をご参照ください。
(答)
○ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がある方で、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、財産債務調書を提出しなければなりません(国外送金等調書法6の2①本文)。
(1)その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超えること
(2)その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産(注2)又はその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産(注3)を有すること
(注1)申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です(国外送金等調書令12の2⑤)。
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
・ 純損失や雑損失の繰越控除
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(注2)国内に所在する財産のほか、国外に所在する財産を含みます。
(注3)国外転出特例対象財産とは、国外転出時課税制度(所得税法60の2、60の3)の対象となる次の財産をいいます(国内に所在するか国外に所在するかを問いません。)(国外送金等調書法6の2①本文、所得税法60の2①~③)。
① 所得税法第2条第1項第17号に規定する有価証券又は所得税法第174条第9号に規定する匿名組合契約の出資の持分
② 決済していない金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項に規定する信用取引又は所得税法施行規則第23条の4に規定する発行日取引に係る権利
③ 決済していない金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利
[参考]所得税の確定申告をする必要がある方の例
○ なお、財産債務調書の提出期限までの間(その年の翌年の3月15日までの間)に、財産債務調書を提出しないで死亡したときは、財産債務調書の提出を要しないこととされています(国外送金等調書法6の2①ただし書)。
また、年の中途で死亡した場合には、その死亡した年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がある場合であっても、その死亡した年の12月31日分の財産債務調書を提出する必要はありません。
(答)
○ その年の12月31日において保有する財産の価額の合計額が3億円以上であるかどうかを判定するに当たっては、含み損のあるデリバティブ取引や信用取引等に係る権利の価額を含めて判定します。
○ なお、その年の12月31日において決済していない信用取引等又はデリバティブ取引に係る権利の価額については、見積価額として、その年の12月31日において決済したとみなして算出した利益の額又は損失の額とすることができます(Q21をご確認ください。)。
この場合、含み損のある信用取引等又はデリバティブ取引に係る権利について、その価額(見積価額)が負(マイナス)となる場合には、財産の価額の合計額を算定する際に、他の財産の価額と通算して計算します。
○ これは、その年の12月31日において保有する国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上であるかどうかを判定するに当たっても同様です。
Ⅱ 財産債務調書の記載事項等
【基本的な考え方】
(答)
○ 財産債務調書には、財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされています。
具体的には、国外送金等調書規則別表第三上欄に規定する財産債務の区分に応じて、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に、その財産の「数量」及び「価額」又はその債務の「金額」を記入します(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
なお、「事業用」とは、この財産債務調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。
また、財産債務の区分のうち、「(六)有価証券」、「(七)匿名組合契約の出資の持分」、「(八)未決済信用取引等に係る権利」及び「(九)未決済デリバティブ取引に係る権利」に区分される財産については、「取得価額」の記入も必要です(取得価額の例については、Q26をご参照ください。)。
(注)個人番号の記載は、平成29年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から必要とされていますので、平成27年12月31日における財産債務について平成28年3月15日までに提出すべき財産債務調書には個人番号を記載する必要はありません(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則101④)。
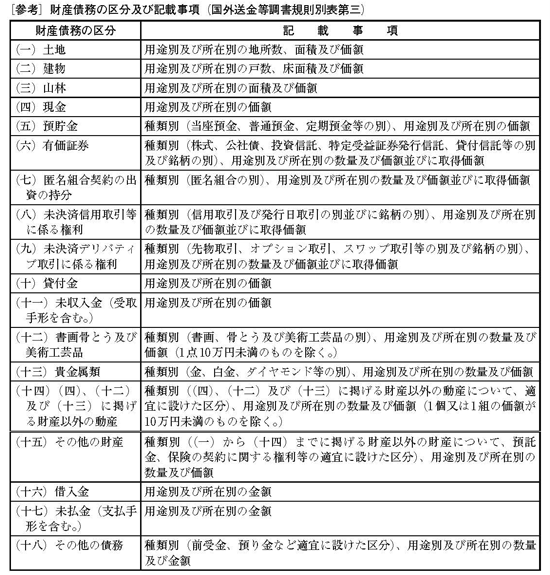
○ また、国外送金等調書規則別表第三上欄に規定する財産債務の区分のうち、次に掲げる財産債務の区分に該当する財産債務の「所在」の記載に当たっては、「その他必要な事項」として、所在地のほか、債務者等の氏名又は名称を記載してください(国外送金等調書法6の2①本文、通達6の2-4、6の2-6、6の2-7)。
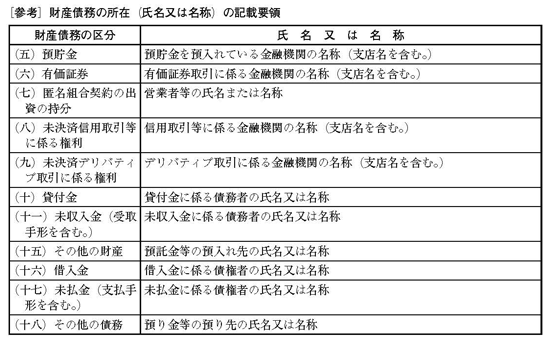
○ 財産の所在の判定についての詳細は、Q12をご確認ください。
○ 財産債務調書の記載例については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の≪申請・届出様式(法定調書関係)≫に掲載していますのでご覧ください。
(答)
○ 財産債務調書に記載すべき財産債務の用途が「一般用」であるのか、「事業用」であるのかについては、次のとおり判定します。
○ 事業用の財産債務とは、その財産債務を、財産債務調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供している財産債務をいいます。
また、一般用の財産債務とは、当該事業又は業務の用に供する以外の財産債務をいいます(国外送金等調書規則別表第三備考一)。
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産債務の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
○ なお、財産債務調書に記載すべき財産債務の用途が、「一般用」及び「事業用」の兼用である場合には、財産債務調書を提出する方の事務負担を軽減する観点から、一般用部分と事業用部分とを区分することなく、財産債務調書に記載することができます(通達6の2-4、6の2-6)。
○ したがって、財産債務調書の記載に当たり、「用途」欄には「一般用、事業用」と記載し、「価額」欄は、用途別に区分することなく算定した財産の価額又は債務の金額を記載して差し支えありません。
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
○ なお、財産債務調書に記載すべき財産が同別表に規定する2以上の財産の区分からなる財産で、それぞれの財産の区分に分けて財産の価額を算定することが困難な場合には、財産債務調書を提出される方の事務負担を軽減する観点から、これらの財産は一体のものとしてその財産の価額を算定し、いずれかの財産の区分にまとめて記載することができます(通達6の2-4)。
○ お尋ねのリゾートマンション(土地付建物)については、財産債務調書の各欄に次のとおり記載してください。
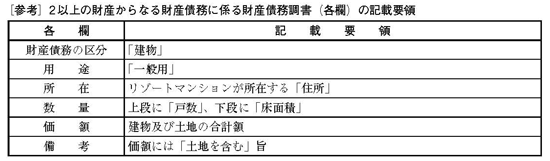
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
また、有価証券に区分される財産については、「種類別」は「株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別」とすることとされています(国外送金等調書規則別表第三)。
○ しかしながら、特定口座内に保有する上場株式等については、「種類別」のうち「銘柄の別」の記載をせず、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載して差し支えありません(通達6の2-4(4))。
○ なお、特定口座内で上場株式等の信用取引又は発行日取引を行っている場合で、その年の12月31日において決済していないものについては、財産債務の区分のうち「未決済信用取引等に係る権利」に区分される財産に該当しますが、当該口座内の当該信用取引等に係る権利についても、「種類別」のうち「銘柄の別」の記載をせず、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載して差し支えありません。
(答)
○ 非課税口座内に保有する上場株式等については、「種類別」のうち「銘柄の別」に記載せず、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載して差し支えありません(通達6の2-4(4))。
【事業用の財産の価額及び債務の金額の記載】
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
○ したがって、財産債務調書の記載にあたり、売掛金など事業上の債権についてはその所在別(相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在)にその価額を記載することとなります。
○ しかしながら、財産債務調書を提出する方の事務負担を軽減する観点から、「未収入金」又は「その他の財産」に区分される財産のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債権であり、かつ、その年の12月31日における価額が100万円未満のものについては、所在別に記載をせず、その件数と総額を記載することとして差し支えありません(通達6の2-4(5))。
(答)
○ 財産債務調書に記載する債務の金額等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する債務の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
○ したがって、財産債務調書の記載にあたり、未払金や預り保証金など事業上の債務についてはその所在別(相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在)にその金額を記載することとなります。
○ しかしながら、「未払金」又は「その他の債務」に区分される債務のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債務であり、かつ、その年の12月31日における金額が100万円未満のものについては、所在別に記載をせず、その件数と総額を記載することとして差し支えありません(通達6の2-6(2))。
【財産の所在の記載事項】
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の所在については、基本的には財産の所在の判定について定める相続税法第10条の規定によることとされ、同条第1項及び第2項に掲げる財産については、これらの規定の定めるところによることとされています(国外送金等調書法6の2③、国外送金等調書令10、12の2①)。
○ なお、有価証券等(注1)が、金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿(注2)に記載等がされているものである場合等におけるその有価証券等の所在については、相続税法第10条第1項及び第2項等の規定にかかわらず、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在によることとされています(国外送金等調書令10②、12の2①、国外送金等調書規則12③ただし書・④、15③、通達6の2-5)。
(注1)「有価証券等」とは具体的には次のものをいいます。
① 貸付金債権(相続税法第10条第1項第7号に掲げる財産)に係る有価証券
② 社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券(相続税法第10条第1項第8号に掲げる財産)
③ 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利(相続税法第10条第1項第9号に掲げる財産)に係る有価証券
④ 国債又は地方債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑤ 外国等の発行する公債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑥ 抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書(国外送金等調書規則第12条第3項第2号に規定する財産)
⑦ 組合契約等に基づく出資(国外送金等調書規則第12条第3項第3号に規定する財産)に係る有価証券
⑧ 信託に関する権利(国外送金等調書規則第12条第3項第4号に規定する財産)に係る有価証券
(注2)「金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいい、外国におけるこれに類するものを含みます。
○ その年の12月31日において保有する各財産の所在の具体的な記載については、その財産の現況により、次表により記載します。
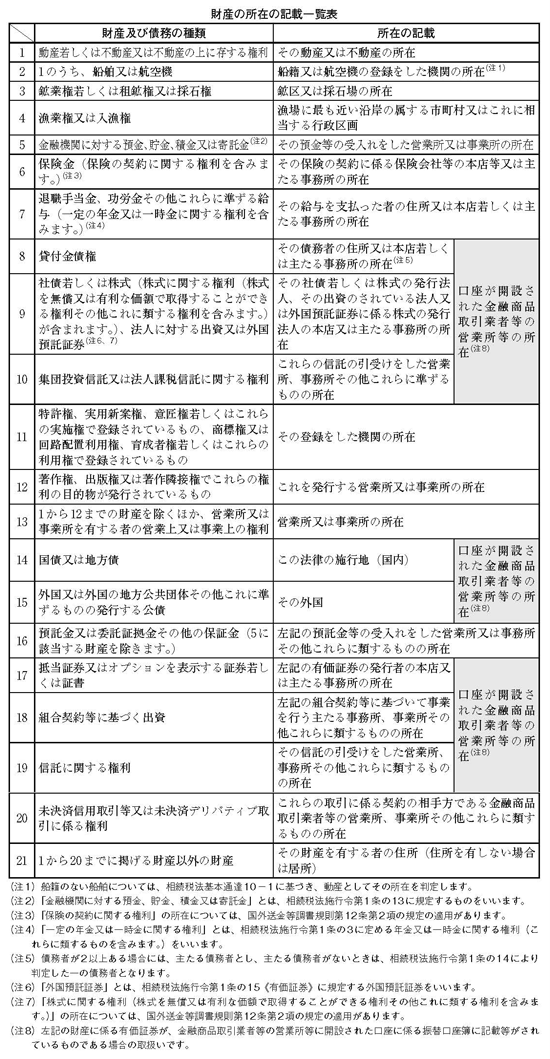
(答)
○ 相続税法に規定する社債、株式等の有価証券等のうち一定のものについては、相続税法第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、国外送金等調書令第12条の2第1項が準用する同第10条第2項の規定により所在を記載します(詳細はQ14を参照)。
○ また、相続税法第10条第1項及び第2項に規定する財産以外の財産で、次に掲げる財産については、国外送金等調書規則第12条第3項の規定により、それぞれ次によりその所在を記載します(国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則12③、15②)。
(1)預託金又は委託証拠金その他の保証金
預託金又は委託証拠金その他の保証金の受入れをした営業所又は事務所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③一)。
(2)抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書等
これらの有価証券の発行者の本店又は主たる事務所の所在(国外送金等調書規則12③二)。
(3)組合契約等に基づく出資
これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③三)。
(4)信託に関する権利(集団投資信託又は法人課税信託に関する権利及び上記(1)から(3)までの財産に該当するものを除きます。)
その信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③四)。
(5)未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に係る権利
これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事業所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③五)。
(6)上記以外の財産
その財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在(国外送金等調書規則12③六)。
○ なお、上記(2)から(4)の財産に係る有価証券のうち一定のものについては、国外送金等調書規則第12条第3項ただし書の規定により所在を記載します(詳細はQ12を参照)。
(答)
○ 財産の所在の記載については、基本的には財産の所在について定める相続税法第10条第1項及び第2項の規定によることとされ、これらの項に規定する財産については、これらの項の定めるところによることとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令10①、12の2①)。
○ ただし、社債、株式等の有価証券等(以下「有価証券等」といいます。)が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等の所在については、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在により記載することとされています(国外送金等調書令10②、12の2①、国外送金等調書規則12③ただし書、通達6の2-5)。
【土地の記載事項】
(答)
○ 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在等については、国外送金等調書規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に記載することとされています(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
○ お尋ねの借地権については、「財産債務の区分」のうち「土地」に該当するものとして記載してください。
【委託証拠金の記載事項】
(答)
○ 先物取引、オプション取引などのデリバティブ取引や、信用取引等を行う際に、委託証拠金その他の保証金として現金又は有価証券を証券会社等に預託することがあります。
○ この委託証拠金その他の保証金として預託した現金又は有価証券については、次のように取り扱います。
(1)預託した現金
財産の区分のうち「その他の財産」に該当し、財産債務調書には、種類別、用途別、所在別の数量及び価額を記載します。
(2)預託した有価証券(いわゆる代用有価証券)
財産の区分のうち「有価証券」に該当し、財産債務調書には、種類別、用途別、所在別の数量及び価額(注)並びに取得価額を記載します(通達6の2-2(1)イ)。
(注)価額は、委託証拠金その他の保証金として取り扱われた金額(いわゆる代用価格に基づく金額)ではなく、当該有価証券の時価又は見積価額を記載します。
○ したがって、ご質問の委託証拠金として預託した株式については、区分欄には「有価証券」と、種類欄には「上場株式(A社)」と記載します。
【債務に係る所在】
(答)
○ 債務に係る所在については、次のとおり記載することとされています(通達6の2-7)。
(1)その債務の相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在を記載します。
(2)所在は、所在地のほか、氏名又は名称を記載します。
【国外財産調書との関係】
(答)
○ 「国外財産調書」の提出が必要な方であっても、所得金額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において価額の合計額が3億円以上である財産又は価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産を有する方は、財産債務調書の提出も必要になります(国外送金等調書法6の2①本文)。
財産債務調書の提出基準の詳細については、Q2をご確認ください。
○ この場合、「財産債務調書」には国外財産に係る事項(国外財産の価額を除く。)の記載を要しないこととされていますので(国外送金等調書法6の2②)、「財産債務調書」及び「財産債務調書合計表」には、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外財産のうち国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載してください(18頁[参考]「財産債務調書」に係る国外財産の記載例及び19頁[参考]「財産債務調書合計表」に係る国外財産の価額の記載例を参照ください。(編注:略))。
なお、国外に存する債務については、「財産債務調書」に記載する必要があります。
[参考]「財産債務調書」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)(編注:略)
[参考]「財産債務調書合計表」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)(編注:略)
財産債務調書の提出制度(FAQ)(1)
平成27年6月
国税庁
Ⅰ 通則
【制度の概要等】
| Q1 財産債務調書の提出制度の概要について教えてください。 |
財産債務調書を提出しなければならない方の詳細についてはQ2を、財産債務調書の記載事項についてはQ4~Q18をご参照ください。
| Q2 財産債務調書を提出しなければならない場合について、具体的に教えてください。 |
(1)その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超えること
(2)その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産(注2)又はその価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産(注3)を有すること
(注1)申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です(国外送金等調書令12の2⑤)。
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
・ 純損失や雑損失の繰越控除
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
(注2)国内に所在する財産のほか、国外に所在する財産を含みます。
(注3)国外転出特例対象財産とは、国外転出時課税制度(所得税法60の2、60の3)の対象となる次の財産をいいます(国内に所在するか国外に所在するかを問いません。)(国外送金等調書法6の2①本文、所得税法60の2①~③)。
① 所得税法第2条第1項第17号に規定する有価証券又は所得税法第174条第9号に規定する匿名組合契約の出資の持分
② 決済していない金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項に規定する信用取引又は所得税法施行規則第23条の4に規定する発行日取引に係る権利
③ 決済していない金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利
[参考]所得税の確定申告をする必要がある方の例
| ○ その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方は、原則として確定申告をしなければなりません。 ただし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。 ○ このほか、所得税の申告義務の有無に関しては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の≪パンフレット・手引き「確定申告に関する手引き等」≫をご覧ください。 |
また、年の中途で死亡した場合には、その死亡した年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がある場合であっても、その死亡した年の12月31日分の財産債務調書を提出する必要はありません。
| Q3 12月31日において保有する財産の価額の合計額が3億円以上であるかどうか又は国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上であるかどうかを判定するに当たって、含み損があるデリバティブ取引に係る権利の価額も含める必要がありますか。 |
○ なお、その年の12月31日において決済していない信用取引等又はデリバティブ取引に係る権利の価額については、見積価額として、その年の12月31日において決済したとみなして算出した利益の額又は損失の額とすることができます(Q21をご確認ください。)。
この場合、含み損のある信用取引等又はデリバティブ取引に係る権利について、その価額(見積価額)が負(マイナス)となる場合には、財産の価額の合計額を算定する際に、他の財産の価額と通算して計算します。
○ これは、その年の12月31日において保有する国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上であるかどうかを判定するに当たっても同様です。
Ⅱ 財産債務調書の記載事項等
【基本的な考え方】
| Q4 財産債務調書には、氏名、住所(又は居所等)及び個人番号(注)のほか、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされていますが、記載事項を具体的に教えてください。 |
具体的には、国外送金等調書規則別表第三上欄に規定する財産債務の区分に応じて、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)及び「所在別」に、その財産の「数量」及び「価額」又はその債務の「金額」を記入します(国外送金等調書法6の2①本文、国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則15①)。
なお、「事業用」とは、この財産債務調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。
また、財産債務の区分のうち、「(六)有価証券」、「(七)匿名組合契約の出資の持分」、「(八)未決済信用取引等に係る権利」及び「(九)未決済デリバティブ取引に係る権利」に区分される財産については、「取得価額」の記入も必要です(取得価額の例については、Q26をご参照ください。)。
(注)個人番号の記載は、平成29年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から必要とされていますので、平成27年12月31日における財産債務について平成28年3月15日までに提出すべき財産債務調書には個人番号を記載する必要はありません(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則101④)。
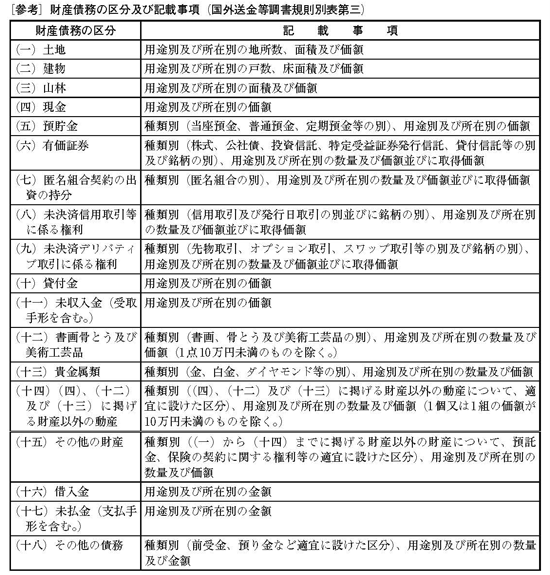
○ また、国外送金等調書規則別表第三上欄に規定する財産債務の区分のうち、次に掲げる財産債務の区分に該当する財産債務の「所在」の記載に当たっては、「その他必要な事項」として、所在地のほか、債務者等の氏名又は名称を記載してください(国外送金等調書法6の2①本文、通達6の2-4、6の2-6、6の2-7)。
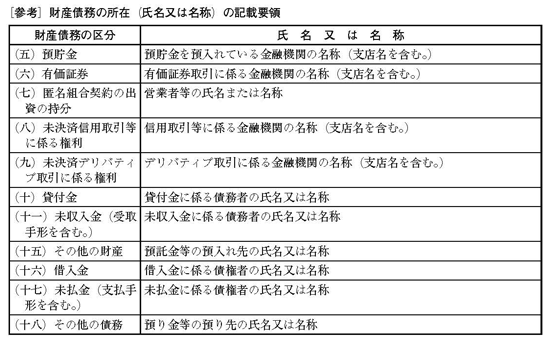
○ 財産の所在の判定についての詳細は、Q12をご確認ください。
○ 財産債務調書の記載例については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の≪申請・届出様式(法定調書関係)≫に掲載していますのでご覧ください。
| Q5 財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等は、その財産債務の用途別(一般用及び事業用の別)に記載することとされています。 保有する財産債務の用途が「一般用」であるのか、「事業用」であるのかについては、どのように判定すればよいのですか。 |
○ 事業用の財産債務とは、その財産債務を、財産債務調書を提出する方の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供している財産債務をいいます。
また、一般用の財産債務とは、当該事業又は業務の用に供する以外の財産債務をいいます(国外送金等調書規則別表第三備考一)。
| Q6 財産債務の用途が「一般用」及び「事業用」の兼用である場合、財産債務調書にはどのように記載すればよいのですか。 |
○ なお、財産債務調書に記載すべき財産債務の用途が、「一般用」及び「事業用」の兼用である場合には、財産債務調書を提出する方の事務負担を軽減する観点から、一般用部分と事業用部分とを区分することなく、財産債務調書に記載することができます(通達6の2-4、6の2-6)。
○ したがって、財産債務調書の記載に当たり、「用途」欄には「一般用、事業用」と記載し、「価額」欄は、用途別に区分することなく算定した財産の価額又は債務の金額を記載して差し支えありません。
| Q7 避暑用のリゾートマンション(土地付建物)を保有しています。売買契約書を確認しても「土地」と「建物」の価額に区分することができません。このような財産の場合、財産債務調書にはどのように記載すればよいのですか。 |
○ なお、財産債務調書に記載すべき財産が同別表に規定する2以上の財産の区分からなる財産で、それぞれの財産の区分に分けて財産の価額を算定することが困難な場合には、財産債務調書を提出される方の事務負担を軽減する観点から、これらの財産は一体のものとしてその財産の価額を算定し、いずれかの財産の区分にまとめて記載することができます(通達6の2-4)。
○ お尋ねのリゾートマンション(土地付建物)については、財産債務調書の各欄に次のとおり記載してください。
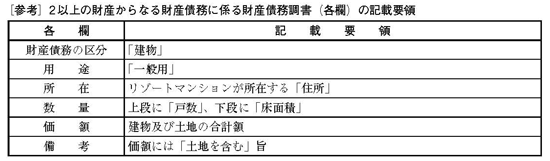
| Q8 証券会社に特定口座を開設しています。この口座内で保有する上場株式等については、財産債務調書にどのように記載すればよいのですか。 |
また、有価証券に区分される財産については、「種類別」は「株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別」とすることとされています(国外送金等調書規則別表第三)。
○ しかしながら、特定口座内に保有する上場株式等については、「種類別」のうち「銘柄の別」の記載をせず、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載して差し支えありません(通達6の2-4(4))。
○ なお、特定口座内で上場株式等の信用取引又は発行日取引を行っている場合で、その年の12月31日において決済していないものについては、財産債務の区分のうち「未決済信用取引等に係る権利」に区分される財産に該当しますが、当該口座内の当該信用取引等に係る権利についても、「種類別」のうち「銘柄の別」の記載をせず、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載して差し支えありません。
| Q9 証券会社に非課税口座を開設しています。この口座内で保有する上場株式等については、財産債務調書にどのように記載すればよいのですか。 |
【事業用の財産の価額及び債務の金額の記載】
| Q10 個人で事業を営んでいます。12月31日現在の事業上の売掛金が多数あります。この売掛金についても所在別に記載する必要がありますか。 |
○ したがって、財産債務調書の記載にあたり、売掛金など事業上の債権についてはその所在別(相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在)にその価額を記載することとなります。
○ しかしながら、財産債務調書を提出する方の事務負担を軽減する観点から、「未収入金」又は「その他の財産」に区分される財産のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債権であり、かつ、その年の12月31日における価額が100万円未満のものについては、所在別に記載をせず、その件数と総額を記載することとして差し支えありません(通達6の2-4(5))。
| Q11 不動産賃貸業を営んでいます。12月31日現在の未払金や預り保証金が多数あります。これらの債務についても所在別に記載する必要がありますか。 |
○ したがって、財産債務調書の記載にあたり、未払金や預り保証金など事業上の債務についてはその所在別(相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在)にその金額を記載することとなります。
○ しかしながら、「未払金」又は「その他の債務」に区分される債務のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供する債務であり、かつ、その年の12月31日における金額が100万円未満のものについては、所在別に記載をせず、その件数と総額を記載することとして差し支えありません(通達6の2-6(2))。
【財産の所在の記載事項】
| Q12 財産債務調書に記載する「財産」の所在は、どのように判定するのですか。 |
○ なお、有価証券等(注1)が、金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿(注2)に記載等がされているものである場合等におけるその有価証券等の所在については、相続税法第10条第1項及び第2項等の規定にかかわらず、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在によることとされています(国外送金等調書令10②、12の2①、国外送金等調書規則12③ただし書・④、15③、通達6の2-5)。
(注1)「有価証券等」とは具体的には次のものをいいます。
① 貸付金債権(相続税法第10条第1項第7号に掲げる財産)に係る有価証券
② 社債若しくは株式、法人に対する出資又は外国預託証券(相続税法第10条第1項第8号に掲げる財産)
③ 集団投資信託又は法人課税信託に関する権利(相続税法第10条第1項第9号に掲げる財産)に係る有価証券
④ 国債又は地方債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑤ 外国等の発行する公債(相続税法第10条第2項に規定する財産)
⑥ 抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書(国外送金等調書規則第12条第3項第2号に規定する財産)
⑦ 組合契約等に基づく出資(国外送金等調書規則第12条第3項第3号に規定する財産)に係る有価証券
⑧ 信託に関する権利(国外送金等調書規則第12条第3項第4号に規定する財産)に係る有価証券
(注2)「金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿をいい、外国におけるこれに類するものを含みます。
○ その年の12月31日において保有する各財産の所在の具体的な記載については、その財産の現況により、次表により記載します。
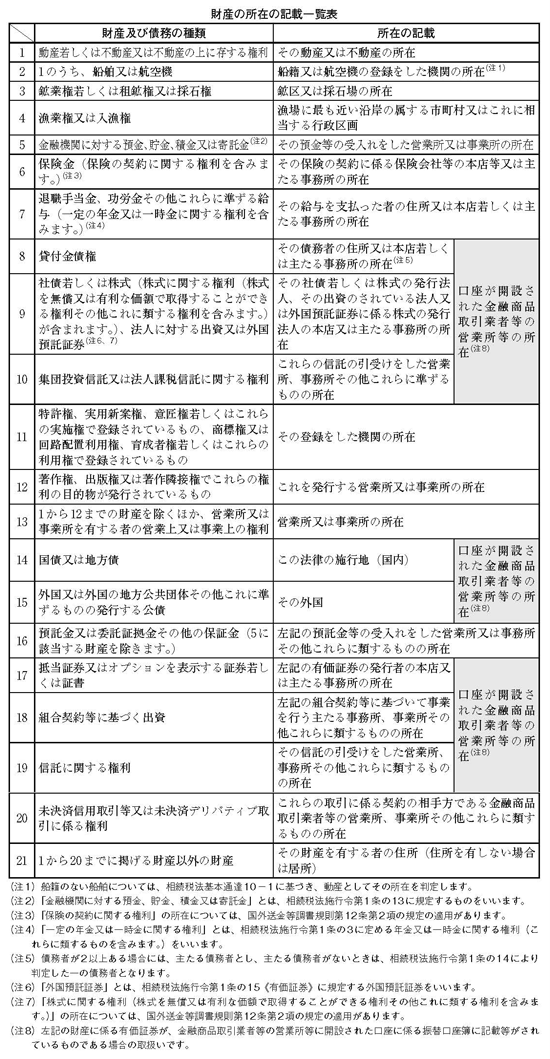
| Q13 財産の所在について、基本的には相続税法第10条第1項及び第2項の規定により判定するとのことですが、相続税法以外の規定により所在を判定する財産もあるのですか。 |
○ また、相続税法第10条第1項及び第2項に規定する財産以外の財産で、次に掲げる財産については、国外送金等調書規則第12条第3項の規定により、それぞれ次によりその所在を記載します(国外送金等調書令12の2⑥、国外送金等調書規則12③、15②)。
(1)預託金又は委託証拠金その他の保証金
預託金又は委託証拠金その他の保証金の受入れをした営業所又は事務所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③一)。
(2)抵当証券又はオプションを表示する証券若しくは証書等
これらの有価証券の発行者の本店又は主たる事務所の所在(国外送金等調書規則12③二)。
(3)組合契約等に基づく出資
これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③三)。
(4)信託に関する権利(集団投資信託又は法人課税信託に関する権利及び上記(1)から(3)までの財産に該当するものを除きます。)
その信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③四)。
(5)未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に係る権利
これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事業所その他これらに類するものの所在(国外送金等調書規則12③五)。
(6)上記以外の財産
その財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在(国外送金等調書規則12③六)。
○ なお、上記(2)から(4)の財産に係る有価証券のうち一定のものについては、国外送金等調書規則第12条第3項ただし書の規定により所在を記載します(詳細はQ12を参照)。
| Q14 社債、株式等の有価証券等の所在は、具体的にどのように記載するのですか。 |
○ ただし、社債、株式等の有価証券等(以下「有価証券等」といいます。)が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等の所在については、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在により記載することとされています(国外送金等調書令10②、12の2①、国外送金等調書規則12③ただし書、通達6の2-5)。
【土地の記載事項】
| Q15 借地権を保有していますが、財産債務調書にはこの借地権をどのように記載すればよいのですか。 |
○ お尋ねの借地権については、「財産債務の区分」のうち「土地」に該当するものとして記載してください。
【委託証拠金の記載事項】
| Q16 先物取引を行うに当たり、保有するA社の株式(上場株式)を委託証拠金として証券会社に預託しました。この預託した株式について、財産債務調書にはどのように記載すればよいのですか。 |
○ この委託証拠金その他の保証金として預託した現金又は有価証券については、次のように取り扱います。
(1)預託した現金
財産の区分のうち「その他の財産」に該当し、財産債務調書には、種類別、用途別、所在別の数量及び価額を記載します。
(2)預託した有価証券(いわゆる代用有価証券)
財産の区分のうち「有価証券」に該当し、財産債務調書には、種類別、用途別、所在別の数量及び価額(注)並びに取得価額を記載します(通達6の2-2(1)イ)。
(注)価額は、委託証拠金その他の保証金として取り扱われた金額(いわゆる代用価格に基づく金額)ではなく、当該有価証券の時価又は見積価額を記載します。
○ したがって、ご質問の委託証拠金として預託した株式については、区分欄には「有価証券」と、種類欄には「上場株式(A社)」と記載します。
【債務に係る所在】
| Q17 「債務」に係る所在については、財産債務調書にどのように記載するのですか。 |
(1)その債務の相手方の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在を記載します。
(2)所在は、所在地のほか、氏名又は名称を記載します。
【国外財産調書との関係】
| Q18 「国外財産調書」には国外財産を記載して提出することとされていますが、「国外財産調書」を提出する場合でも、所得金額が2千万円を超え、かつ、保有する財産の価額の合計額が3億円以上又は国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上である場合は、財産債務調書を提出する必要があるのですか。 |
財産債務調書の提出基準の詳細については、Q2をご確認ください。
○ この場合、「財産債務調書」には国外財産に係る事項(国外財産の価額を除く。)の記載を要しないこととされていますので(国外送金等調書法6の2②)、「財産債務調書」及び「財産債務調書合計表」には、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外財産のうち国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載してください(18頁[参考]「財産債務調書」に係る国外財産の記載例及び19頁[参考]「財産債務調書合計表」に係る国外財産の価額の記載例を参照ください。(編注:略))。
なお、国外に存する債務については、「財産債務調書」に記載する必要があります。
[参考]「財産債務調書」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)(編注:略)
[参考]「財産債務調書合計表」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)(編注:略)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.