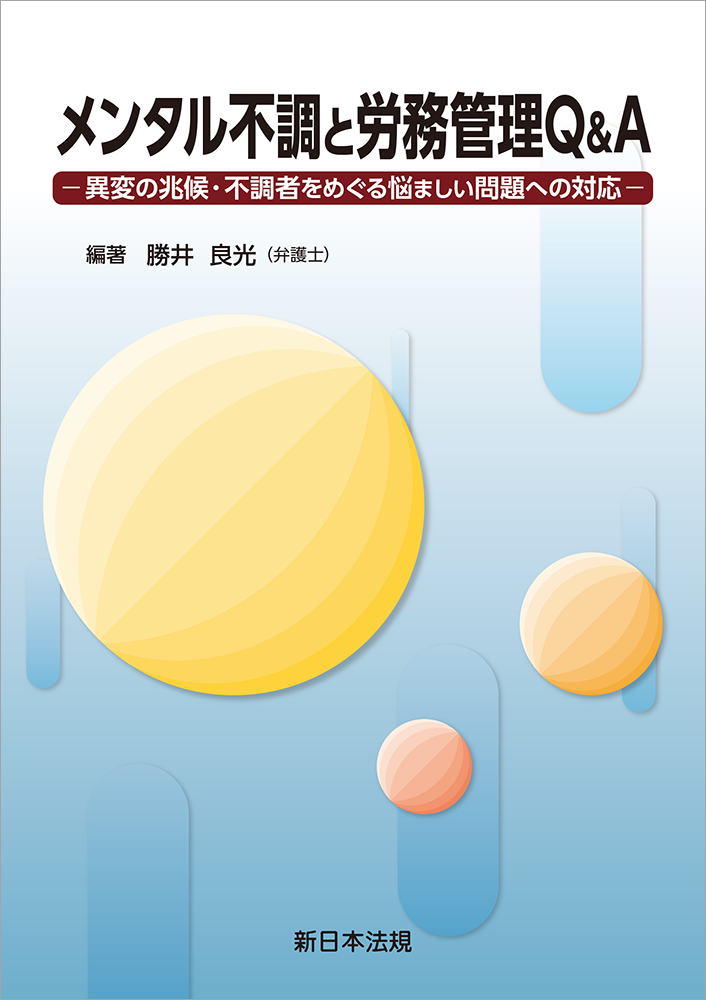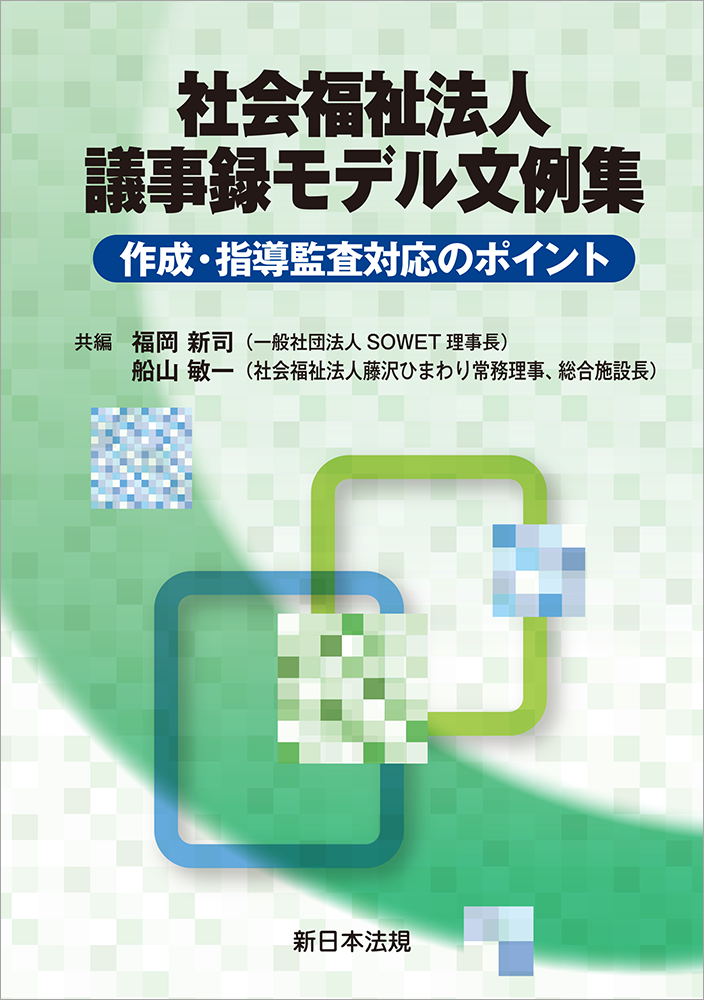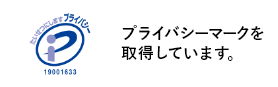解説記事2015年10月19日 【論考】 「租税回避」概念の混迷と否認の限界(2015年10月19日号・№614)
論考
「租税回避」概念の混迷と否認の限界
中央大学名誉教授・税理士 大淵博義
Ⅰ はじめに
本誌では、組織再編成税制の立案に携わったとされる担当者(税理士)が、ヤフー事件判決及びIBM事件判決を取り上げて、数回に亘り、組織再編成の行為計算や同族会社の行為計算における租税回避否認規定(法法132・法法132の2)の適用の是非についての所見を述べられている。しかしながら、そこでは、同担当者がいかなる「租税回避」概念を観念し論じているのか必ずしも明確ではないために、同規定により否認される範囲が不明確であり予測可能性が担保されていないという問題がある。
また、「租税回避」の概念は時代の変遷によって変化するものであるという趣旨のことを述べている論者もいるが、以下に述べる「租税回避」の講学上の意義自体が時代の変遷によって変容することはあり得ないことである。租税回避に関して、時代の推移、変化によって変わることがあるとすれば、それは租税回避の行為の異常性、不自然性が多様化して変化することはありえないことではなかろう。しかして、従前の節税行為が時代の変遷に応じて「租税回避行為」に変質するという論者は、いかなる時代の推移、変化によって、節税行為が不自然、不合理な租税回避行為に変容をもたらすのかについての相関関係を論証する必要がある。
本稿では、このような問題認識に立って、あるべき租税回避否認論における解釈の整合性と不整合性に焦点を当てて、IBM事件等、従前の判例等の問題点を検証したいと考えている(脚注1)。
Ⅱ「租税回避」の意義と否認論
1 学説・判例にみる「租税回避」の意義とその否認の意味 同族会社の行為計算の否認規定(法人税法132条1項)は、租税回避行為の否認規定と理解されているが、そこでの伝統的な講学上の「租税回避」とは、金子宏東大名誉教授及び清永敬次京大名誉教授が論じておられるように、「①不自然、不合理な行為計算により、②通常の合理的行為による経済的成果とほぼ同一の成果を得ているにもかかわらず、③その租税負担が減免されている場合」として理解されている。ドイツ租税法における「経済事象に相応する租税負担を免れることはできない」という租税回避行為の一般否認規定も同様の趣旨である。
ここで重要なことは、顕現されている経済事象(成果)に対して、それに相応する課税がなされるべきであり、それを不合理な行為を選択して、租税負担を回避した行為計算を否認して課税の公平を図るというのが前提となっているという点である。一部の論者(脚注2)を除けば、表現は異なるものの、その意味しているところは上記の講学上の「狭義の租税回避」の概念と同旨と考えられる。
すなわち、同族会社の行為計算の否認規定にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは」(以下、本稿ではこの事象を「不当減少」ともいう。)とは、納税者が通常の合理的な行為計算を選択して得た経済的成果の租税負担に比較して、不合理な法形式を選択した納税者が得た同様の経済的成果の租税負担が減免されていることを意味している。しかして、同族会社の行為計算の否認が争点とされた過去の事件の判決の大半が、一般論として租税回避行為による「不当減少」を否認する意義について、次のように判示しているところである。
「法人税法132条1項は、内国法人である同族会社は、少数の株主又は社員によって支配され、当該会社の法人税負担を不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことに鑑み、税負担の公平を維持すべく、そのような行為又は計算が行われた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して更正等を行う権限を税務署長に認めるものである。そして、同族会社のある行為又は計算が法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるかどうかは、それが純経済人の行為として不自然、かつ不合理な行為又は計算であって、それによって法人税の負担が減少したかどうかによって決すべきである。」(長崎地裁平成21年3月10日判決)
この判示の意義を図解すると上記の図のとおりである。
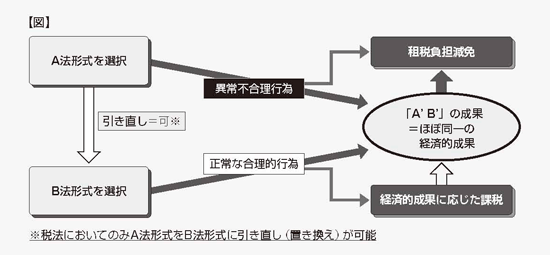
これに適合するのが、「逆さ合併」の否認事例である。その否認は、真実行われた合併による法的効果(経済的成果)を前提として(これを不変のものとして)、税法上においてのみ、合併法人(赤字法人、事業停止・廃止)を被合併法人、被合併法人(黒字法人)を合併法人として行われた合併に引き直すというものであり、「合併」という真実行なわれた法律行為により現実に顕現されている客観的な実体を否認することは許されないということに留意すべきである(脚注3)。
ところが、留学生の子息の役員に役員報酬を支給して損金の額に算入した前記長崎地裁判決の事例において、課税庁は子息の役員は役員としての業務を行っていないとして、法人税法132条1項を適用して、その役員報酬を損金不算入とする課税処分を行ない、同判決はこれを支持している。当該判決は引直し論を総論では示してはいるものの、現実の適用においては、行為計算の引き直しではなく、役員報酬を損金不算入とする根拠規定にしたものにすぎない。
ここでの同族会社の行為計算の否認規定の「税務署長の認めるところにより」、課税標準等を計算することができる、という意味は、納税者が損金控除した支出を、損金不算入として課税することを意味するものではない。それは、税務署長が、納税者の行った不自然、不合理な行為計算について、自然かつ合理的な行為計算を採用したと認定(擬制)して引き直すことが、ここでの「税務署長の認めるところにより」という意味である。しかして、この場合の引き直しとは、次のようなものとなる。
役員の業務を行っていない子息の扶養義務を負っている父親(代表取締役)が、個人として、子息の留学費用等を負担すべきところ、子息を役員に登用して役員給与を支給して法人税等の軽減を図ったものと認定し、その子息の役員給与は、代表取締役(父親)に対する役員給与の支給とフィクション(引き直し)した上、父親として子息に留学費用等の生活資金を贈与したもの、と引き直して、課税関係を形成すべきものである(脚注4)。
このような引直しが失念されているのが、現在の多くの論説や判例であるといえよう。そして、このことが、「租税回避行為の否認」の理解の混迷をもたらしている主たる要因であると考えている。
2 組織再編成の行為計算の否認法理と「租税回避」 組織再編成の税制の創設に際して、租税回避防止規定を措置すべき規定として、法人税法132条の2が創設されたものであるが、その改正当時、主税局担当者と思われる解説において、組織再編成を利用した租税回避行為の例の一つとして、「④株式の譲渡損を計上したり、株式の評価を下げるために、分割等を行う。」という事例が挙げられており、それに続けて、「これらの組織再編成を利用した租税回避行為は、上記のようなものに止まらず、その行為の形態や方法が多様なものとなると考えられることから、これに適正な課税を行うことができるように包括的な組織再編成に係る租税回避行為防止規定が設けられました(法法132の2)。」と解説されている。
当時、この解説を見て驚いたことを記憶している。それは、ここで論じた伝統的な講学上(本来)の「狭義の租税回避」の概念について捨象して言及されていないからである。すなわち、組織再編成について、広く適正な課税を行うことができるように法人税法132条の2が創設されたという説明によると、ヤフー事件判決の課税処分に見られるように、特定役員の就任が短期間等、制度の趣旨目的に反すると認められる場合には、当該規定により、組織再編成税制の課税の特例の適用事例にとどまらず、特例適用の「適格要件外し」も不合理として否認される余地があるからである。
すなわち、適格合併要件を充足するために、株式を買収して完全子会社化とした直後に合併する場合等の「適格づくり」や、非適格組織再編として譲渡損を計上するために、株式交付の他に金銭を交付して「適格要件外し」をする場合も、課税庁が適正な課税を行うために、法人税法132条の2により否認されかねないという危惧があるということである。
そこで、上記の「株式の評価額を引き下げるため」の組織再編成が租税回避として否認されるという説明に関連して、その論理の疑問又は誤謬を指摘しておきたい。
①「個人甲が全株式を所有する黒字法人A社(純資産10億円)及び赤字法人B社(債務超過10億円)を合併して、その株式評価額をゼロとした後に、甲が死亡した場合、その合併法人A社の株式の相続税評価額をゼロとして、その相続人乙が相続税申告をした場合、組織再編成による行為計算の否認規定(相法64③)によりその合併が否認されるか」 この事例について、「税制改正の雑誌解説」及び本誌に掲載された組織再編成税制の担当者のヤフー事件及びIBM事件の一連の論考(本誌592号他)によれば、この組織再編は租税回避として否認されるように思われる。
この場合、法人税法132条の2により当該合併を否認するというのは、合併後のA社株式の評価額(純資産ゼロ円)を合併前の同社株式の評価額10億円と評価して相続税の更正処分を行うということであろう。かかる更正処分がなされると、合併が適法になされ、現実に、相続人乙が相続した株式は合併後のA社株式(純資産0円)であるにもかかわらず、合併前の存在しない10億円のA社株式を相続したという虚構の課税要件事実に基づいて相続税課税がなされるということになる。このことは、真実発生している事実とは異なる事実をフィクションして課税するという、実質課税の原則に違背した「財産なきところに課税する」という、租税原則の根幹を逸脱した課税を行うことになる。かかる否認が許されないことはいうまでもないことである。
ちなみに、乙がA社株式を相続税の物納に供する場合の収納価額は10億円として収納されると考えざるを得ないが、そうとすると、当該A社株式の客観的交換価額はゼロ円であるにもかかわらず、物納の収納価額10億円として物納が許可されるという説明できない矛盾を招来する。このことに鑑みても、かかる租税回避の否認が誤謬であることが明らかになる。
続いて、②「上記合併後のA社株式を相続により取得した当該相続人乙が死亡し、その子の相続人丙が同株式を相続した場合の相続税の評価額はどのようになるか」。さらに、甲が死亡前にA社株式を他に贈与した場合、その贈与税の株式評価額はゼロ円か、10億円か、また、甲が法人にA社株式をゼロ円で譲渡(贈与)した場合、所得税法157条3項が適用され、59条1項と同様の10億円のみなし譲渡課税がなされるのか、等々の多くの説明困難な疑問が発生する。かかる疑問は、租税回避行為の否認により私法上の真実の事実関係を歪めて、客観的事実(経済的成果)とは異なる事実関係(経済事象)にフィクションして課税することの誤謬、つまり、実質課税の原則に違背した課税を行うということが誤謬であるということである。
Ⅲ 課税実務と判例の租税回避否認論の素朴な疑問
以上の論点について、さらに、その問題点を浮き彫りにするために、いくつかの否認事例における問題点(誤謬)を指摘しておきたい。
1 過大管理料等の支払い 株主の同族会社に対する過大管理料の支払いは、現在、所得税法157条1項を適用して過大部分の管理料の必要経費性が否認されているが(脚注5)、かかる否認論によれば、その過大管理料を非同族会社又は個人(親族)に支払った場合には否認できないことになりかねない。しかしながら、この場合の過大部分の管理料は、法人が、法人又は個人に対して過大な経費支出を行った場合に寄附金と認定(個人は一時所得)して寄附金として課税しているのと同様に、私法上の事実認定の実質主義により、過大管理料部分の金員の拠出は個人(株主)から非同族会社又は個人に対する贈与と認定すること(寄附金課税・個人は贈与税課税)により、不動産所得の必要経費性を否認することができるのである。
そうであれば、これと同様に、個人株主から同族会社に対する過大な管理料部分の支払いは贈与と認定して(脚注6)、不動産所得の必要経費控除を否認すれば足りるのである。税務署長の更正権の発動として、同族会社に限定して適用される所得税法157条1項を適用するまでもないということである。このことが失念されているために、租税回避概念を不純化させ混迷に至らしめていると考えている。
2 個人株主の高価買取 個人株主が同族会社の土地建物(時価1,000・取得価額3,000)を取得価額3,000で高価買い取りした後に当該株主に相続が発生した場合、①相続開始前に株主が代金3,000を現金で同族会社に支払っているケース、②売買代金の決済として同族会社の銀行債務3,000を株主が引き受けたケース、③株主は買受代金(3,000)を未払金としたケース、の課税問題を考えてみよう。
被相続人の相続直前の高価な資産の取得は不自然、不合理であるとしても、その高価買取は事実認定の実質主義により、①の3,000の高価買取は、時価1,000による売買と2,000の贈与と認定することができる(脚注7)。その場合、その2,000の贈与は特段の個別規定がない以上、相続税法64条1項(同族会社の行為計算の否認)を適用して金銭の贈与はなかったものとフィクションして、贈与の2,000を相続財産に加算して課税することは、「財産なきところに課税する」ことであり許されない。そして、相続開始前に高額部分の金銭を贈与すれば相続財産は減少し、それに応じた相続税額の減少は、もとより当然の事理であるから、その相続については、課税上何らの問題も発生しない。
これと同様に、②の銀行債務の引受についても、それが虚偽でない以上、被相続人は銀行債務を負うことになるから、これを相続した相続人の課税価格の計算上、銀行債務を債務控除すべきことは当然であり、その債務控除を否認することは許されない(脚注8)。③の場合も、同族会社に対する土地建物の高価買取の支払債務の存在が虚偽であることが証明できない以上、相続税法64条1項により、未払金の債務控除を否認することは許されない(脚注9)。
3 個人の無償の役務提供等─平和事件 個人が10億円の土地を法人(同族会社)に6億円で譲渡した場合、所得税法59条1項の低額譲渡には該当しないからみなし譲渡課税はできない。また、個人が個人に又は株主がその非同族会社に無利息融資をした場合、所得税法157条1項による利息認定も許されない。しかるに、これとの整合性に照らせば、個人株主の同族会社に対する無利息貸付(3,450億円)につき、発生していない550億円(3年間)近い利息を収受したものと擬制(フィクション)して雑所得課税した平和事件最高裁判決等は疑問というほかはない(脚注10)。
何故ならば、現実に取得していない利息を収受したとして、真の客観的事実(収入ゼロ)とは異なる法的、経済的実質をフィクションして、実質課税の原則に反する課税が行われたからである。敢えて、否認のプロセスを探るとすれば、私法上、当該株主の利息収入ゼロの実質(経済事象)に引き直すためには、先ず、①利息収入の収受をフィクションし、②他方で、そのフィクションしたものと同額の利息相当額を借主の同族会社(株主とその妻で100%支配)に贈与したとフィクションして、初めて利息収入がゼロという、現実の私法上の経済的成果(実質)に引き直すことができる。そして、その上で、そのフィクションされた利息収入は、株主の雑所得であり、その贈与した部分は、当該所得金額の計算上、必要経費には含まれないとして、課税するということ以外には考えられない。
ところが、このような迂遠な二段階のフィクションが(脚注11)、果たして、営利追求主体の法人とは異なり、ボランティアが尊重される自然人の個人として、しかも、同族会社を完全支配する法人所有者たる株主(一人株主の場合)は、無利息に伴う同族会社の利益増加はすべて当該株主に還元されるにもかかわらず、かかる二段階の取引を行うことは、個人(株主)として、むしろ、迂遠な不自然な行為であるということができるのである。
加えて、前述したように、個人が個人に、個人株主が非同族会社に同様の無利息貸付を行った場合には、その利息収入は認定できないという課税上の不公平等、多くの矛盾を招来し、論理的に矛盾した解決できない問題が派生することになる。
このような点からみても、ボランティアが尊重される自然人たる個人の無利息貸付等による支援は、社会的に広く許容されていたところであり、殊に、同族会社のすべての財産を支配しその利益を享受している当該個人株主の同族会社に対する無利息貸付は正常な取引条件の下での合理的な行為であるから(脚注12)、これを所得税法157条1項を適用して、私法上、存在しない利息収入を認定することは許されない。
かかる精緻な整合性の視座からの検証がなされると、平和事件最高裁判決等の疑問が浮き彫りにされたであろう。かかる二段階のフィクションを失念し、私法上、存在しない利息収入が存在するという真実に反する擬制(認定)をして課税した最高裁判決は疑問といわざるを得ない。
4 IBM事件判決 米国IBM社の子会社の米国T社は、買収した日本の中間持株会社Ⅹ社(原告)に対して、日本IBM社株式の全てを売却(米国税制・チェックザ・ボックスにより、X社はT社の支店として国内取引として取り扱われその譲渡益につき課税繰延べ)、その後、X社は当該株式を買取価額と同額で日本IBM社に自社株として譲渡したところ、その譲渡収益の内、自社株の譲渡に係るみなし配当部分(益金不算入)が株式の譲渡対価から控除されることから、その配当相当額の株式譲渡損(約4,000億円)が算出され、その譲渡損失を日本IBM社との連結納税申告により相殺したという事例である(脚注13)。
この事件の課税処分の違法性は、控訴審判決の次の判示に集約されているといえよう。
「控訴人は、本件各譲渡が独立当事者間の通常の取引と異なると主張しているにもかかわらず、独立当事者間の通常の取引であれば、どのような譲渡価額で各譲渡がされたはずであるかについて、何ら具体的な主張立証をしていない。控訴人の主張は、親子関係にない独立当事者の内国法人であれば、取得価額と同じ譲渡価額で日本IBMによる自己株式の取得に応じるという取引があり得なかったと認めることもできないというべきである。以上によれば、被控訴人がした本件各譲渡が、それ自体で独立当事者間の通常の取引と異なるものであり経済的合理性を欠くとの控訴人の主張は採用できない。」(要旨)。
中間持株会社としての原告X社の事業活動等の一連の取引が虚偽であり、その法人としての実体が不存在といえるものであれば格別、本件X社は多額な日本IBM社の株式を取得する等、真に実在して事業活動を展開している以上、X社の存在自体を否定することは許されない。しかも、原告X社の日本IBM社に対する当該自己株式の譲渡価額が不適正であることが証明できない以上、経済的、合理的な行為(独立当事者間取引)として容認せざるを得ない。
仮に、課税庁が中間持株会社のX社の設立又は存在自体が不自然、不合理というのであれば、我が国で典型的な節税会社である不動産管理会社や一人芸能法人の設立(存在)自体も不自然、不合理として否認すべきことになろう。しかし、かかる法人の設立(存在)による事業活動の展開自体が合理的な経済行為であるから、その法人の設立自体を租税回避行為として否認することは許されない。このことは、同族会社の行為計算の否認規定創設当初からの前提であり、それは現在に至るも変わることはない。
何故ならば、仮に、節税対策であるとしても、法人の設立自体、つまり、法人組織による事業活動自体が合理的な企業行動と認識されるからである。仮に、節税会社の設立が不合理であるとしても、税法上においてのみ法人による事業活動を当該個人株主の事業活動として引き直すことは真実の法的、経済的実体としての「確定した事実」に反することになるから、これを否認することはできないということである。
この事件の問題の本質は、自己株式としての譲渡によるみなし配当金額を譲渡対価から除かれるとともに、当該みなし配当が益金不算入とされている制度の下においては当然の株式譲渡による損失の発生であり、これを否定するためには税制改正による以外にはないということである。その意味では、この点に関する制度の不備が、本件事案の株式譲渡損の計上とみなし配当の益金不算入という二重の控除をもたらしたということができる(脚注14)。しかるに、その制度の不備と税制改正の遅れを同族会社の行為計算の否認規定により否認して補正することが許されないことは当然のことである。
これと同様に、組織再編成税制の制度不備を租税回避行為の否認規定(法法132の2)により補充、補正して否認したのがヤフー事件である。
Ⅳ 結びに代えて
1 ヤフー事件判決の租税回避否認論
すでに周知のヤフー事件判決(東京地裁平成26年3月18日判決・東京高裁平成26年11月5日判決)は、法人税法132条の2が法人税法132条(同族会社の行為計算の否認)の枝番として規定され、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」と同一の課税要件規定が措置されているにもかかわらず、法人税法132条の2の規定による租税回避否認の射程は、法人税法132条により否認される「経済行為の不合理・不自然である場合」のほか、「一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものを含む」という新しい解釈を示した。
しかしながら、その判示は、すでに論じたことから明らかなように、法人税法132条1項の「不当減少」の意義・範囲(つまり、「講学上の租税回避」)とは異なるものであり、その判示する趣旨目的論による否認は、税法の個別規定の解釈領域の問題として解決すべき問題である。それを租税回避行為の否認規定により否認することは、租税回避行為否認の法理のさらなる混迷をもたらすことになるというべきである。
すなわち、平成13年度改正税法当時の主税局(担当者と思われる執筆者)の解説では、同族会社の行為計算の否認規定の「不当減少」とは異なる意義・概念として規定されたのが法人税法132条の2の「不当減少」であるという趣旨の解説が皆無であることに照らしても、制度創設に当たっては、両否認規定の「不当減少」の意味内容は同義として観念して立法されていたことは容易に推測できよう。
仮に、趣旨目的論による否認を念頭においたのであれば、法人税法132条の枝番ではなく、組織再編成税制の固有の個別規定(法法62)の一つとして法定すべきであり、そして、その規定の中で、当該否認の射程範囲が予測可能な課税要件規定を法定すべきことはいうまでもないことである。
すでに論じたことから明らかなように、租税回避の否認は、現実の経済的成果又は経済事象に相応した課税関係を形成することにある。ところが、ヤフー事件はみなし共同事業要件の充足の有無という課税要件規定の解釈適用の問題であり、租税回避行為の否認論とは異質の問題といえよう。
本判決の背景には、ヤフーの代表取締役の被合併法人の副社長就任が正式な機関で承認、選任された以上、特定役員就任の法的事実を虚偽として否認することが困難であることから(脚注15)、判決は、当該就任期間が短期間で無報酬であること等の当該役員の業務実態に焦点を当て、その現実の問題点を指摘して、それを根拠に組織再編成や個別規定の趣旨目的に違背するとして、この場合には法人税法132条の2の租税回避行為として否認できるという、これまでに議論されたこともない奇抜な論理を採用したものである。
私法上、被合併法人の副社長就任という真の事実につき、税法上においてのみ、副社長就任の事実を否定することは、前述したように、租税回避の否認の法理を逸脱したものであり許されないことが理解されるべきである(脚注16)。
本件において、仮に、当該役員の被合併法人又は合併法人の職務執行が短期間であるという事実をもって、特定役員引継要件の充足性を否定すべきというのであれば、個別の規定により、具体的期間を法定して対処すべきことは立法の基本である。そのような立法的対応によることなく、制度の趣旨目的に違背するという制度の解釈論の領域の問題を租税回避行為否認論の問題にすり替えた本判決は疑問といわざるを得ない。換言すれば、ヤフー事件の更正処分及び判決は、前記IBM事件と同様に、税法上の制度創設に際しての立法の不備を、「伝家の宝刀」の租税回避行為の否認規定(法法132の2)を適用して課税したものという批判を甘受しなければならない。
2 おわりに 以上、論じたことから明らかなように、これまでの租税回避行為の否認事例からみる「租税回避」の意義の理解は区々であり、最近の判決では、古い時代には見られなかった、「真実発生している事実」を発生していないとフィクションし、また、「発生していない事実」を発生しているとフィクションする誤った否認事例が発生している。特に、他の一般規定による否認が可能であるにもかかわらず(過大管理料の否認)、租税回避行為の否認規定により否認しているものがみられるのは、反省すべき点である。
IBM事件及びヤフー事件は、立法的手当により解決すべき問題であり、かかる法的手当てによることなく、租税回避行為の包括的否認規定によって、法の不備を是正することは許されないことを指摘しておきたい。
脚注
1 紙幅の関係もあって、本稿での引用は可能な限り省略することとする。なお、本稿に関連した租税回避行為の否認の筆者の著作として、『法人税法解釈の検証と実践的展開Ⅱ』税務経理協会(2014年)第1章・第2章及び最近の拙稿として「学説・判例理論の租税回避否認論の検証と問題点」租税研究2015年1月号~同3月号参照。
2 この「伝統的な租税回避の概念は狭すぎる」と指摘しているものとして、今村隆「租税回避とは何か」(税務大学論叢40周年記念論文集(2008年6月)57頁)がある。
3 参照・「税法上の実質主義・租税回避防止等如何なる理由からでも、私法上全く有効に形成された法律効果自体はこれを絶対に否定できない」(渡辺伸平「税法上の所得を巡る諸問題」『司法研究報告書』第19輯1号(1967年)28頁)。
4 その結果、代表取締役の加算後の役員給与に係る源泉徴収所得税の納税告知処分、そして、加算した後の代表取締役の役員給与の形式・実質基準からの過大役員給与否認の是非を検討することになる。また、子息が役員給与として取得した金員は、扶養義務者の父親(代表取締役)からの贈与によるものとして非課税(源泉所得税の還付)とされることになる。この場合、法人からの資金支出・子息の役員報酬相当額の金員の取得という経済的意義(成果)を前提とした引き直しであることに留意。
5 課税実務において、否認した過大管理料部分を同族会社(管理会社)の所得から減額する対応的調整が行われているかどうかは不明である。
6 この場合の過大管理料の認定は,同族会社の行為計算の否認規定による平均値課税ではなく、最も類似する事例の管理料を採用するか、類似事例の最高額の管理料を採用すべきである。他方で、所得税法157条1項による否認の場合には、対応的調整により同族会社で減額されるのであろうが、そうであれば、対応的調整の機能しない非同族会社や個人に対する同額の過大管理料の支払いとの不整合・不公平が発生することになる。このことをみても、すべての場合に、同一の課税の根拠(事実認定の実質主義)を採用して課税の公平を図ることの合理性が理解できよう。
7 法基通7-3-1(固定資産の取得価額)では、資産の高価買取の高額部分の金額は、取得価額に含まれない(一般には寄附金)と規定しているが、これは、講学上の租税回避行為の否認ではなく、「事実認定の実質主義」により広く適用される私法上の否認である。
8 これに対して、相続税法64条1項により、銀行債務の引受けを否認できるという論者もいるが、被相続人の債務引受の真否は私法上の事実認定の問題であり、この真の事実(債務引受)を同規定により否認し、高価部分の銀行債務の引受けは存在しないという真実と異なる事実をフィクションすることは、租税回避行為の否認の領域の問題ではなく許されない。
9 ちなみに、この場合の未払金のうち、高価部分の2,000万円の支払債務の実質は、株主から同族会社に対する贈与契約による債務であり、したがって、書面による贈与は契約時に贈与債務が確定し、当該同族会社には受贈益が発生することになるから、当該株主(被相続人)の相続税の課税価格の計算上債務控除が認められることになる。大阪地裁平成18年10月25日判決は相続税法64条1項の否認規定により、未払金債務の債務控除を否認した課税処分を適法として支持しているが、判決は、租税回避行為の否認の本質を理解せず誤っている。真実存在する当該贈与債務を相続人が履行すれば、承継した相続財産が減少する以上、その債務控除は許容すべきことになる。この問題は、私法上の事実認定の問題であり、税法上においてのみフィクションする同族会社の行為計算の否認の問題ではないということである。
10 仄聞するところによると、10億円未満の無利息貸付金の利息認定が行われている事例もあるようである。
11 昭和40年前の法人税法では、二段階説・有償取引同視説により収益と贈与(寄附金)認定を行っていたが、それは営利法人の特質と合わせて、無償の役務提供等による寄附金課税の潜脱を否認するものであることに留意。
12 日本子会社従業員等の精勤による子会社の業績向上は親会社の業績に反映されるから、それがその精勤に対する対価的関係と認定して、親会社と子会社従業員等は雇用契約類似の関係があるとし、親会社からの当該従業員等のストックオプションの権利行使益を給与所得とした最高裁判決の論旨に照らせば、正に、株主の同族会社に対する無利息貸付が正常な取引であるということが理解できよう。
13 この事例の判決は一審東京地裁平成26.5.9判決、控訴審平成27.3.25判決で納税者が勝訴し、現在上告申立て及び上告受理申立中である。
14 平成13年度改正では、法人株主に株式譲渡損が発生しない限度においてのみ、みなし配当として取り扱うこととする規定が廃止され、当該譲渡損の計上とみなし配当の益金不算入制度が併用されることとされたが、その後、平成22年度税制改正において、自己株式の取得を予定して株式を取得した場合のみなし配当は益金不算入の適用を排除する制度が創設された。このような改正の狭間の事業年度であるにもかからず、行為計算の否認ができるという朝長英樹氏の論説の紹介とそれに対する詳細で的確な批判的指摘については、太田洋・伊藤剛志共編著『企業取引と税務否認の実務』大蔵財務協会(2015年)164頁~182頁に詳しい。
15 適法に取締役に選任された役員が、現実には役員の業務執行に携わっていないとしても、法人税上は役員として取り扱われること、また、単なる「名刺専務」である場合を除き、正式な機関で選任された専務取締役等が平取締役の仕事にのみ従事しているとしても、専務であることを否定することは許されないし、したがって、当該専務等は、使用人兼務役員になれない専務等の役付役員として取り扱われている課税実務に留意。
16 株主(被相続人)が同族会社に対する貸付金の全部又は一部を契約により免除することにより、相続財産を減らす行為が、相続税法64条1項(同族会社の行為計算の否認)の不当減少として債務免除の事実を否認して消滅し存在しない貸付金を相続財産として課税する誤謬と同様である。
「租税回避」概念の混迷と否認の限界
中央大学名誉教授・税理士 大淵博義
Ⅰ はじめに
本誌では、組織再編成税制の立案に携わったとされる担当者(税理士)が、ヤフー事件判決及びIBM事件判決を取り上げて、数回に亘り、組織再編成の行為計算や同族会社の行為計算における租税回避否認規定(法法132・法法132の2)の適用の是非についての所見を述べられている。しかしながら、そこでは、同担当者がいかなる「租税回避」概念を観念し論じているのか必ずしも明確ではないために、同規定により否認される範囲が不明確であり予測可能性が担保されていないという問題がある。
また、「租税回避」の概念は時代の変遷によって変化するものであるという趣旨のことを述べている論者もいるが、以下に述べる「租税回避」の講学上の意義自体が時代の変遷によって変容することはあり得ないことである。租税回避に関して、時代の推移、変化によって変わることがあるとすれば、それは租税回避の行為の異常性、不自然性が多様化して変化することはありえないことではなかろう。しかして、従前の節税行為が時代の変遷に応じて「租税回避行為」に変質するという論者は、いかなる時代の推移、変化によって、節税行為が不自然、不合理な租税回避行為に変容をもたらすのかについての相関関係を論証する必要がある。
本稿では、このような問題認識に立って、あるべき租税回避否認論における解釈の整合性と不整合性に焦点を当てて、IBM事件等、従前の判例等の問題点を検証したいと考えている(脚注1)。
Ⅱ「租税回避」の意義と否認論
1 学説・判例にみる「租税回避」の意義とその否認の意味 同族会社の行為計算の否認規定(法人税法132条1項)は、租税回避行為の否認規定と理解されているが、そこでの伝統的な講学上の「租税回避」とは、金子宏東大名誉教授及び清永敬次京大名誉教授が論じておられるように、「①不自然、不合理な行為計算により、②通常の合理的行為による経済的成果とほぼ同一の成果を得ているにもかかわらず、③その租税負担が減免されている場合」として理解されている。ドイツ租税法における「経済事象に相応する租税負担を免れることはできない」という租税回避行為の一般否認規定も同様の趣旨である。
ここで重要なことは、顕現されている経済事象(成果)に対して、それに相応する課税がなされるべきであり、それを不合理な行為を選択して、租税負担を回避した行為計算を否認して課税の公平を図るというのが前提となっているという点である。一部の論者(脚注2)を除けば、表現は異なるものの、その意味しているところは上記の講学上の「狭義の租税回避」の概念と同旨と考えられる。
すなわち、同族会社の行為計算の否認規定にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは」(以下、本稿ではこの事象を「不当減少」ともいう。)とは、納税者が通常の合理的な行為計算を選択して得た経済的成果の租税負担に比較して、不合理な法形式を選択した納税者が得た同様の経済的成果の租税負担が減免されていることを意味している。しかして、同族会社の行為計算の否認が争点とされた過去の事件の判決の大半が、一般論として租税回避行為による「不当減少」を否認する意義について、次のように判示しているところである。
「法人税法132条1項は、内国法人である同族会社は、少数の株主又は社員によって支配され、当該会社の法人税負担を不当に減少させるような行為又は計算が行われやすいことに鑑み、税負担の公平を維持すべく、そのような行為又は計算が行われた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して更正等を行う権限を税務署長に認めるものである。そして、同族会社のある行為又は計算が法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるかどうかは、それが純経済人の行為として不自然、かつ不合理な行為又は計算であって、それによって法人税の負担が減少したかどうかによって決すべきである。」(長崎地裁平成21年3月10日判決)
この判示の意義を図解すると上記の図のとおりである。
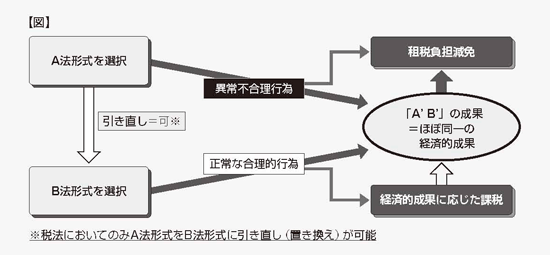
これに適合するのが、「逆さ合併」の否認事例である。その否認は、真実行われた合併による法的効果(経済的成果)を前提として(これを不変のものとして)、税法上においてのみ、合併法人(赤字法人、事業停止・廃止)を被合併法人、被合併法人(黒字法人)を合併法人として行われた合併に引き直すというものであり、「合併」という真実行なわれた法律行為により現実に顕現されている客観的な実体を否認することは許されないということに留意すべきである(脚注3)。
ところが、留学生の子息の役員に役員報酬を支給して損金の額に算入した前記長崎地裁判決の事例において、課税庁は子息の役員は役員としての業務を行っていないとして、法人税法132条1項を適用して、その役員報酬を損金不算入とする課税処分を行ない、同判決はこれを支持している。当該判決は引直し論を総論では示してはいるものの、現実の適用においては、行為計算の引き直しではなく、役員報酬を損金不算入とする根拠規定にしたものにすぎない。
ここでの同族会社の行為計算の否認規定の「税務署長の認めるところにより」、課税標準等を計算することができる、という意味は、納税者が損金控除した支出を、損金不算入として課税することを意味するものではない。それは、税務署長が、納税者の行った不自然、不合理な行為計算について、自然かつ合理的な行為計算を採用したと認定(擬制)して引き直すことが、ここでの「税務署長の認めるところにより」という意味である。しかして、この場合の引き直しとは、次のようなものとなる。
役員の業務を行っていない子息の扶養義務を負っている父親(代表取締役)が、個人として、子息の留学費用等を負担すべきところ、子息を役員に登用して役員給与を支給して法人税等の軽減を図ったものと認定し、その子息の役員給与は、代表取締役(父親)に対する役員給与の支給とフィクション(引き直し)した上、父親として子息に留学費用等の生活資金を贈与したもの、と引き直して、課税関係を形成すべきものである(脚注4)。
このような引直しが失念されているのが、現在の多くの論説や判例であるといえよう。そして、このことが、「租税回避行為の否認」の理解の混迷をもたらしている主たる要因であると考えている。
2 組織再編成の行為計算の否認法理と「租税回避」 組織再編成の税制の創設に際して、租税回避防止規定を措置すべき規定として、法人税法132条の2が創設されたものであるが、その改正当時、主税局担当者と思われる解説において、組織再編成を利用した租税回避行為の例の一つとして、「④株式の譲渡損を計上したり、株式の評価を下げるために、分割等を行う。」という事例が挙げられており、それに続けて、「これらの組織再編成を利用した租税回避行為は、上記のようなものに止まらず、その行為の形態や方法が多様なものとなると考えられることから、これに適正な課税を行うことができるように包括的な組織再編成に係る租税回避行為防止規定が設けられました(法法132の2)。」と解説されている。
当時、この解説を見て驚いたことを記憶している。それは、ここで論じた伝統的な講学上(本来)の「狭義の租税回避」の概念について捨象して言及されていないからである。すなわち、組織再編成について、広く適正な課税を行うことができるように法人税法132条の2が創設されたという説明によると、ヤフー事件判決の課税処分に見られるように、特定役員の就任が短期間等、制度の趣旨目的に反すると認められる場合には、当該規定により、組織再編成税制の課税の特例の適用事例にとどまらず、特例適用の「適格要件外し」も不合理として否認される余地があるからである。
すなわち、適格合併要件を充足するために、株式を買収して完全子会社化とした直後に合併する場合等の「適格づくり」や、非適格組織再編として譲渡損を計上するために、株式交付の他に金銭を交付して「適格要件外し」をする場合も、課税庁が適正な課税を行うために、法人税法132条の2により否認されかねないという危惧があるということである。
そこで、上記の「株式の評価額を引き下げるため」の組織再編成が租税回避として否認されるという説明に関連して、その論理の疑問又は誤謬を指摘しておきたい。
①「個人甲が全株式を所有する黒字法人A社(純資産10億円)及び赤字法人B社(債務超過10億円)を合併して、その株式評価額をゼロとした後に、甲が死亡した場合、その合併法人A社の株式の相続税評価額をゼロとして、その相続人乙が相続税申告をした場合、組織再編成による行為計算の否認規定(相法64③)によりその合併が否認されるか」 この事例について、「税制改正の雑誌解説」及び本誌に掲載された組織再編成税制の担当者のヤフー事件及びIBM事件の一連の論考(本誌592号他)によれば、この組織再編は租税回避として否認されるように思われる。
この場合、法人税法132条の2により当該合併を否認するというのは、合併後のA社株式の評価額(純資産ゼロ円)を合併前の同社株式の評価額10億円と評価して相続税の更正処分を行うということであろう。かかる更正処分がなされると、合併が適法になされ、現実に、相続人乙が相続した株式は合併後のA社株式(純資産0円)であるにもかかわらず、合併前の存在しない10億円のA社株式を相続したという虚構の課税要件事実に基づいて相続税課税がなされるということになる。このことは、真実発生している事実とは異なる事実をフィクションして課税するという、実質課税の原則に違背した「財産なきところに課税する」という、租税原則の根幹を逸脱した課税を行うことになる。かかる否認が許されないことはいうまでもないことである。
ちなみに、乙がA社株式を相続税の物納に供する場合の収納価額は10億円として収納されると考えざるを得ないが、そうとすると、当該A社株式の客観的交換価額はゼロ円であるにもかかわらず、物納の収納価額10億円として物納が許可されるという説明できない矛盾を招来する。このことに鑑みても、かかる租税回避の否認が誤謬であることが明らかになる。
続いて、②「上記合併後のA社株式を相続により取得した当該相続人乙が死亡し、その子の相続人丙が同株式を相続した場合の相続税の評価額はどのようになるか」。さらに、甲が死亡前にA社株式を他に贈与した場合、その贈与税の株式評価額はゼロ円か、10億円か、また、甲が法人にA社株式をゼロ円で譲渡(贈与)した場合、所得税法157条3項が適用され、59条1項と同様の10億円のみなし譲渡課税がなされるのか、等々の多くの説明困難な疑問が発生する。かかる疑問は、租税回避行為の否認により私法上の真実の事実関係を歪めて、客観的事実(経済的成果)とは異なる事実関係(経済事象)にフィクションして課税することの誤謬、つまり、実質課税の原則に違背した課税を行うということが誤謬であるということである。
Ⅲ 課税実務と判例の租税回避否認論の素朴な疑問
以上の論点について、さらに、その問題点を浮き彫りにするために、いくつかの否認事例における問題点(誤謬)を指摘しておきたい。
1 過大管理料等の支払い 株主の同族会社に対する過大管理料の支払いは、現在、所得税法157条1項を適用して過大部分の管理料の必要経費性が否認されているが(脚注5)、かかる否認論によれば、その過大管理料を非同族会社又は個人(親族)に支払った場合には否認できないことになりかねない。しかしながら、この場合の過大部分の管理料は、法人が、法人又は個人に対して過大な経費支出を行った場合に寄附金と認定(個人は一時所得)して寄附金として課税しているのと同様に、私法上の事実認定の実質主義により、過大管理料部分の金員の拠出は個人(株主)から非同族会社又は個人に対する贈与と認定すること(寄附金課税・個人は贈与税課税)により、不動産所得の必要経費性を否認することができるのである。
そうであれば、これと同様に、個人株主から同族会社に対する過大な管理料部分の支払いは贈与と認定して(脚注6)、不動産所得の必要経費控除を否認すれば足りるのである。税務署長の更正権の発動として、同族会社に限定して適用される所得税法157条1項を適用するまでもないということである。このことが失念されているために、租税回避概念を不純化させ混迷に至らしめていると考えている。
2 個人株主の高価買取 個人株主が同族会社の土地建物(時価1,000・取得価額3,000)を取得価額3,000で高価買い取りした後に当該株主に相続が発生した場合、①相続開始前に株主が代金3,000を現金で同族会社に支払っているケース、②売買代金の決済として同族会社の銀行債務3,000を株主が引き受けたケース、③株主は買受代金(3,000)を未払金としたケース、の課税問題を考えてみよう。
被相続人の相続直前の高価な資産の取得は不自然、不合理であるとしても、その高価買取は事実認定の実質主義により、①の3,000の高価買取は、時価1,000による売買と2,000の贈与と認定することができる(脚注7)。その場合、その2,000の贈与は特段の個別規定がない以上、相続税法64条1項(同族会社の行為計算の否認)を適用して金銭の贈与はなかったものとフィクションして、贈与の2,000を相続財産に加算して課税することは、「財産なきところに課税する」ことであり許されない。そして、相続開始前に高額部分の金銭を贈与すれば相続財産は減少し、それに応じた相続税額の減少は、もとより当然の事理であるから、その相続については、課税上何らの問題も発生しない。
これと同様に、②の銀行債務の引受についても、それが虚偽でない以上、被相続人は銀行債務を負うことになるから、これを相続した相続人の課税価格の計算上、銀行債務を債務控除すべきことは当然であり、その債務控除を否認することは許されない(脚注8)。③の場合も、同族会社に対する土地建物の高価買取の支払債務の存在が虚偽であることが証明できない以上、相続税法64条1項により、未払金の債務控除を否認することは許されない(脚注9)。
3 個人の無償の役務提供等─平和事件 個人が10億円の土地を法人(同族会社)に6億円で譲渡した場合、所得税法59条1項の低額譲渡には該当しないからみなし譲渡課税はできない。また、個人が個人に又は株主がその非同族会社に無利息融資をした場合、所得税法157条1項による利息認定も許されない。しかるに、これとの整合性に照らせば、個人株主の同族会社に対する無利息貸付(3,450億円)につき、発生していない550億円(3年間)近い利息を収受したものと擬制(フィクション)して雑所得課税した平和事件最高裁判決等は疑問というほかはない(脚注10)。
何故ならば、現実に取得していない利息を収受したとして、真の客観的事実(収入ゼロ)とは異なる法的、経済的実質をフィクションして、実質課税の原則に反する課税が行われたからである。敢えて、否認のプロセスを探るとすれば、私法上、当該株主の利息収入ゼロの実質(経済事象)に引き直すためには、先ず、①利息収入の収受をフィクションし、②他方で、そのフィクションしたものと同額の利息相当額を借主の同族会社(株主とその妻で100%支配)に贈与したとフィクションして、初めて利息収入がゼロという、現実の私法上の経済的成果(実質)に引き直すことができる。そして、その上で、そのフィクションされた利息収入は、株主の雑所得であり、その贈与した部分は、当該所得金額の計算上、必要経費には含まれないとして、課税するということ以外には考えられない。
ところが、このような迂遠な二段階のフィクションが(脚注11)、果たして、営利追求主体の法人とは異なり、ボランティアが尊重される自然人の個人として、しかも、同族会社を完全支配する法人所有者たる株主(一人株主の場合)は、無利息に伴う同族会社の利益増加はすべて当該株主に還元されるにもかかわらず、かかる二段階の取引を行うことは、個人(株主)として、むしろ、迂遠な不自然な行為であるということができるのである。
加えて、前述したように、個人が個人に、個人株主が非同族会社に同様の無利息貸付を行った場合には、その利息収入は認定できないという課税上の不公平等、多くの矛盾を招来し、論理的に矛盾した解決できない問題が派生することになる。
このような点からみても、ボランティアが尊重される自然人たる個人の無利息貸付等による支援は、社会的に広く許容されていたところであり、殊に、同族会社のすべての財産を支配しその利益を享受している当該個人株主の同族会社に対する無利息貸付は正常な取引条件の下での合理的な行為であるから(脚注12)、これを所得税法157条1項を適用して、私法上、存在しない利息収入を認定することは許されない。
かかる精緻な整合性の視座からの検証がなされると、平和事件最高裁判決等の疑問が浮き彫りにされたであろう。かかる二段階のフィクションを失念し、私法上、存在しない利息収入が存在するという真実に反する擬制(認定)をして課税した最高裁判決は疑問といわざるを得ない。
4 IBM事件判決 米国IBM社の子会社の米国T社は、買収した日本の中間持株会社Ⅹ社(原告)に対して、日本IBM社株式の全てを売却(米国税制・チェックザ・ボックスにより、X社はT社の支店として国内取引として取り扱われその譲渡益につき課税繰延べ)、その後、X社は当該株式を買取価額と同額で日本IBM社に自社株として譲渡したところ、その譲渡収益の内、自社株の譲渡に係るみなし配当部分(益金不算入)が株式の譲渡対価から控除されることから、その配当相当額の株式譲渡損(約4,000億円)が算出され、その譲渡損失を日本IBM社との連結納税申告により相殺したという事例である(脚注13)。
この事件の課税処分の違法性は、控訴審判決の次の判示に集約されているといえよう。
「控訴人は、本件各譲渡が独立当事者間の通常の取引と異なると主張しているにもかかわらず、独立当事者間の通常の取引であれば、どのような譲渡価額で各譲渡がされたはずであるかについて、何ら具体的な主張立証をしていない。控訴人の主張は、親子関係にない独立当事者の内国法人であれば、取得価額と同じ譲渡価額で日本IBMによる自己株式の取得に応じるという取引があり得なかったと認めることもできないというべきである。以上によれば、被控訴人がした本件各譲渡が、それ自体で独立当事者間の通常の取引と異なるものであり経済的合理性を欠くとの控訴人の主張は採用できない。」(要旨)。
中間持株会社としての原告X社の事業活動等の一連の取引が虚偽であり、その法人としての実体が不存在といえるものであれば格別、本件X社は多額な日本IBM社の株式を取得する等、真に実在して事業活動を展開している以上、X社の存在自体を否定することは許されない。しかも、原告X社の日本IBM社に対する当該自己株式の譲渡価額が不適正であることが証明できない以上、経済的、合理的な行為(独立当事者間取引)として容認せざるを得ない。
仮に、課税庁が中間持株会社のX社の設立又は存在自体が不自然、不合理というのであれば、我が国で典型的な節税会社である不動産管理会社や一人芸能法人の設立(存在)自体も不自然、不合理として否認すべきことになろう。しかし、かかる法人の設立(存在)による事業活動の展開自体が合理的な経済行為であるから、その法人の設立自体を租税回避行為として否認することは許されない。このことは、同族会社の行為計算の否認規定創設当初からの前提であり、それは現在に至るも変わることはない。
何故ならば、仮に、節税対策であるとしても、法人の設立自体、つまり、法人組織による事業活動自体が合理的な企業行動と認識されるからである。仮に、節税会社の設立が不合理であるとしても、税法上においてのみ法人による事業活動を当該個人株主の事業活動として引き直すことは真実の法的、経済的実体としての「確定した事実」に反することになるから、これを否認することはできないということである。
この事件の問題の本質は、自己株式としての譲渡によるみなし配当金額を譲渡対価から除かれるとともに、当該みなし配当が益金不算入とされている制度の下においては当然の株式譲渡による損失の発生であり、これを否定するためには税制改正による以外にはないということである。その意味では、この点に関する制度の不備が、本件事案の株式譲渡損の計上とみなし配当の益金不算入という二重の控除をもたらしたということができる(脚注14)。しかるに、その制度の不備と税制改正の遅れを同族会社の行為計算の否認規定により否認して補正することが許されないことは当然のことである。
これと同様に、組織再編成税制の制度不備を租税回避行為の否認規定(法法132の2)により補充、補正して否認したのがヤフー事件である。
Ⅳ 結びに代えて
1 ヤフー事件判決の租税回避否認論
すでに周知のヤフー事件判決(東京地裁平成26年3月18日判決・東京高裁平成26年11月5日判決)は、法人税法132条の2が法人税法132条(同族会社の行為計算の否認)の枝番として規定され、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」と同一の課税要件規定が措置されているにもかかわらず、法人税法132条の2の規定による租税回避否認の射程は、法人税法132条により否認される「経済行為の不合理・不自然である場合」のほか、「一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものを含む」という新しい解釈を示した。
しかしながら、その判示は、すでに論じたことから明らかなように、法人税法132条1項の「不当減少」の意義・範囲(つまり、「講学上の租税回避」)とは異なるものであり、その判示する趣旨目的論による否認は、税法の個別規定の解釈領域の問題として解決すべき問題である。それを租税回避行為の否認規定により否認することは、租税回避行為否認の法理のさらなる混迷をもたらすことになるというべきである。
すなわち、平成13年度改正税法当時の主税局(担当者と思われる執筆者)の解説では、同族会社の行為計算の否認規定の「不当減少」とは異なる意義・概念として規定されたのが法人税法132条の2の「不当減少」であるという趣旨の解説が皆無であることに照らしても、制度創設に当たっては、両否認規定の「不当減少」の意味内容は同義として観念して立法されていたことは容易に推測できよう。
仮に、趣旨目的論による否認を念頭においたのであれば、法人税法132条の枝番ではなく、組織再編成税制の固有の個別規定(法法62)の一つとして法定すべきであり、そして、その規定の中で、当該否認の射程範囲が予測可能な課税要件規定を法定すべきことはいうまでもないことである。
すでに論じたことから明らかなように、租税回避の否認は、現実の経済的成果又は経済事象に相応した課税関係を形成することにある。ところが、ヤフー事件はみなし共同事業要件の充足の有無という課税要件規定の解釈適用の問題であり、租税回避行為の否認論とは異質の問題といえよう。
本判決の背景には、ヤフーの代表取締役の被合併法人の副社長就任が正式な機関で承認、選任された以上、特定役員就任の法的事実を虚偽として否認することが困難であることから(脚注15)、判決は、当該就任期間が短期間で無報酬であること等の当該役員の業務実態に焦点を当て、その現実の問題点を指摘して、それを根拠に組織再編成や個別規定の趣旨目的に違背するとして、この場合には法人税法132条の2の租税回避行為として否認できるという、これまでに議論されたこともない奇抜な論理を採用したものである。
私法上、被合併法人の副社長就任という真の事実につき、税法上においてのみ、副社長就任の事実を否定することは、前述したように、租税回避の否認の法理を逸脱したものであり許されないことが理解されるべきである(脚注16)。
本件において、仮に、当該役員の被合併法人又は合併法人の職務執行が短期間であるという事実をもって、特定役員引継要件の充足性を否定すべきというのであれば、個別の規定により、具体的期間を法定して対処すべきことは立法の基本である。そのような立法的対応によることなく、制度の趣旨目的に違背するという制度の解釈論の領域の問題を租税回避行為否認論の問題にすり替えた本判決は疑問といわざるを得ない。換言すれば、ヤフー事件の更正処分及び判決は、前記IBM事件と同様に、税法上の制度創設に際しての立法の不備を、「伝家の宝刀」の租税回避行為の否認規定(法法132の2)を適用して課税したものという批判を甘受しなければならない。
2 おわりに 以上、論じたことから明らかなように、これまでの租税回避行為の否認事例からみる「租税回避」の意義の理解は区々であり、最近の判決では、古い時代には見られなかった、「真実発生している事実」を発生していないとフィクションし、また、「発生していない事実」を発生しているとフィクションする誤った否認事例が発生している。特に、他の一般規定による否認が可能であるにもかかわらず(過大管理料の否認)、租税回避行為の否認規定により否認しているものがみられるのは、反省すべき点である。
IBM事件及びヤフー事件は、立法的手当により解決すべき問題であり、かかる法的手当てによることなく、租税回避行為の包括的否認規定によって、法の不備を是正することは許されないことを指摘しておきたい。
脚注
1 紙幅の関係もあって、本稿での引用は可能な限り省略することとする。なお、本稿に関連した租税回避行為の否認の筆者の著作として、『法人税法解釈の検証と実践的展開Ⅱ』税務経理協会(2014年)第1章・第2章及び最近の拙稿として「学説・判例理論の租税回避否認論の検証と問題点」租税研究2015年1月号~同3月号参照。
2 この「伝統的な租税回避の概念は狭すぎる」と指摘しているものとして、今村隆「租税回避とは何か」(税務大学論叢40周年記念論文集(2008年6月)57頁)がある。
3 参照・「税法上の実質主義・租税回避防止等如何なる理由からでも、私法上全く有効に形成された法律効果自体はこれを絶対に否定できない」(渡辺伸平「税法上の所得を巡る諸問題」『司法研究報告書』第19輯1号(1967年)28頁)。
4 その結果、代表取締役の加算後の役員給与に係る源泉徴収所得税の納税告知処分、そして、加算した後の代表取締役の役員給与の形式・実質基準からの過大役員給与否認の是非を検討することになる。また、子息が役員給与として取得した金員は、扶養義務者の父親(代表取締役)からの贈与によるものとして非課税(源泉所得税の還付)とされることになる。この場合、法人からの資金支出・子息の役員報酬相当額の金員の取得という経済的意義(成果)を前提とした引き直しであることに留意。
5 課税実務において、否認した過大管理料部分を同族会社(管理会社)の所得から減額する対応的調整が行われているかどうかは不明である。
6 この場合の過大管理料の認定は,同族会社の行為計算の否認規定による平均値課税ではなく、最も類似する事例の管理料を採用するか、類似事例の最高額の管理料を採用すべきである。他方で、所得税法157条1項による否認の場合には、対応的調整により同族会社で減額されるのであろうが、そうであれば、対応的調整の機能しない非同族会社や個人に対する同額の過大管理料の支払いとの不整合・不公平が発生することになる。このことをみても、すべての場合に、同一の課税の根拠(事実認定の実質主義)を採用して課税の公平を図ることの合理性が理解できよう。
7 法基通7-3-1(固定資産の取得価額)では、資産の高価買取の高額部分の金額は、取得価額に含まれない(一般には寄附金)と規定しているが、これは、講学上の租税回避行為の否認ではなく、「事実認定の実質主義」により広く適用される私法上の否認である。
8 これに対して、相続税法64条1項により、銀行債務の引受けを否認できるという論者もいるが、被相続人の債務引受の真否は私法上の事実認定の問題であり、この真の事実(債務引受)を同規定により否認し、高価部分の銀行債務の引受けは存在しないという真実と異なる事実をフィクションすることは、租税回避行為の否認の領域の問題ではなく許されない。
9 ちなみに、この場合の未払金のうち、高価部分の2,000万円の支払債務の実質は、株主から同族会社に対する贈与契約による債務であり、したがって、書面による贈与は契約時に贈与債務が確定し、当該同族会社には受贈益が発生することになるから、当該株主(被相続人)の相続税の課税価格の計算上債務控除が認められることになる。大阪地裁平成18年10月25日判決は相続税法64条1項の否認規定により、未払金債務の債務控除を否認した課税処分を適法として支持しているが、判決は、租税回避行為の否認の本質を理解せず誤っている。真実存在する当該贈与債務を相続人が履行すれば、承継した相続財産が減少する以上、その債務控除は許容すべきことになる。この問題は、私法上の事実認定の問題であり、税法上においてのみフィクションする同族会社の行為計算の否認の問題ではないということである。
10 仄聞するところによると、10億円未満の無利息貸付金の利息認定が行われている事例もあるようである。
11 昭和40年前の法人税法では、二段階説・有償取引同視説により収益と贈与(寄附金)認定を行っていたが、それは営利法人の特質と合わせて、無償の役務提供等による寄附金課税の潜脱を否認するものであることに留意。
12 日本子会社従業員等の精勤による子会社の業績向上は親会社の業績に反映されるから、それがその精勤に対する対価的関係と認定して、親会社と子会社従業員等は雇用契約類似の関係があるとし、親会社からの当該従業員等のストックオプションの権利行使益を給与所得とした最高裁判決の論旨に照らせば、正に、株主の同族会社に対する無利息貸付が正常な取引であるということが理解できよう。
13 この事例の判決は一審東京地裁平成26.5.9判決、控訴審平成27.3.25判決で納税者が勝訴し、現在上告申立て及び上告受理申立中である。
14 平成13年度改正では、法人株主に株式譲渡損が発生しない限度においてのみ、みなし配当として取り扱うこととする規定が廃止され、当該譲渡損の計上とみなし配当の益金不算入制度が併用されることとされたが、その後、平成22年度税制改正において、自己株式の取得を予定して株式を取得した場合のみなし配当は益金不算入の適用を排除する制度が創設された。このような改正の狭間の事業年度であるにもかからず、行為計算の否認ができるという朝長英樹氏の論説の紹介とそれに対する詳細で的確な批判的指摘については、太田洋・伊藤剛志共編著『企業取引と税務否認の実務』大蔵財務協会(2015年)164頁~182頁に詳しい。
15 適法に取締役に選任された役員が、現実には役員の業務執行に携わっていないとしても、法人税上は役員として取り扱われること、また、単なる「名刺専務」である場合を除き、正式な機関で選任された専務取締役等が平取締役の仕事にのみ従事しているとしても、専務であることを否定することは許されないし、したがって、当該専務等は、使用人兼務役員になれない専務等の役付役員として取り扱われている課税実務に留意。
16 株主(被相続人)が同族会社に対する貸付金の全部又は一部を契約により免除することにより、相続財産を減らす行為が、相続税法64条1項(同族会社の行為計算の否認)の不当減少として債務免除の事実を否認して消滅し存在しない貸付金を相続財産として課税する誤謬と同様である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -