解説記事2016年02月22日 【ニュース特集】 図表で読み解く国外転出時課税制度の改正(2016年2月22日号・№631)
ニュース特集
ストックオプションは適用対象外に
図表で読み解く国外転出時課税制度の改正
平成27年7月から施行されている国外転出時課税制度だが、平成28年度税制改正では、さらなる見直しが実施される。本誌ですでにお伝えしている未分割課税後の遺産分割への対応以外でも、ストックオプションの適用除外や、納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直しなど、これまで指摘されていた問題点の修正などが行われる。本特集では、図表を用いながら国外転出時課税制度の改正事項について解説する。
国外転出時課税制度の問題点などを修正
国外転出時課税制度が平成27年7月1日から施行されている。同制度は①対象者が国外転出をする時、②対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ有価証券等の一部又は全部を贈与する時、③対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時において、一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有している場合において、その対象資産の含み益に対して所得税が課税されるものである。
平成28年度税制改正では、現行の国外転出時課税制度で指摘されている問題点の修正や取扱いの明確化などが行われる。その最たるものは、すでに本誌でもお伝えしている未分割課税後の遺産分割に対応するものだ(本誌623号11頁、627号24頁参照)。
国外転出時課税に係る準確定申告の期限(相続開始を知った日から4月以内)までに有価証券等が未分割である場合には、非居住者(相続人)の法定相続分で準確定申告を行うことになる。しかし、その後の遺産分割協議の成立により非居住者が有価証券等を取得しない場合、準確定申告をした所得税に関し更正の請求が認められるか否かが法令等により明らかにされていなかった。この点、平成28年度税制改正では、非居住者(相続人)が法定相続分で準確定申告を行った後に遺産分割が行われたことで、非居住者に移転した有価証券等が当初の申告と異なることとなった場合には、国外転出時課税制度の適用を受けた居住者の相続人はその遺産分割が行われた日から4月以内に、税額が減少する場合は更正の請求をすることが可能になる(改正所得税法151条の5等)。平成28年1月1日以後に遺産分割の確定等が生じた場合から適用される。
その他にも、(1)納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直し、(2)国外転出時に確定申告をしていない場合等の取得価額の洗替えの適用除外、(3)ストックオプションに係る国外転出時課税制度の適用除外、(4)国外転出時課税により譲渡損失が生じた場合の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用、(5)国外転出の後に同一銘柄の有価証券等を取得している場合の取扱いの明確化、(6)NISA口座内の上場株式等が国外転出時課税の対象となる場合の時価評価日の見直しについて整備が行われることになる。
以下、概要について見てみることにする。
納期限を国外転出の日以後5年4月に
1点目は、納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直しである。現行、国外転出の日から納税猶予の期限の満了日まで引き続き保有している有価証券等の価額が、その納税猶予の期限の満了日において国外転出の日よりも下落している場合には、その下落した価額により国外転出時の課税の再計算をすることができる特例が設けられている。特例の適用を受けるには、納税猶予の期限の満了日から4月を経過する日までに更正の請求をすることとされている。
しかし、納税猶予の期限の満了に伴う納期限は国外転出の日から5年(又は10年)を経過する日となっているため、一度、納税猶予の適用を受けていた税額を納付する必要が生じてしまうという問題点があった。
このため、平成28年度税制改正では、この手続上の負担をなくすため、納税猶予の期限の満了に伴う納期限について、国外転出の日以後5年4月(又は10年4月)を経過する日に見直している(改正所得税法137条の2、137条の3、図表1参照)。この改正は、平成28年1月1日以後に納税猶予に係る期限の満了日が到来する場合について適用される。
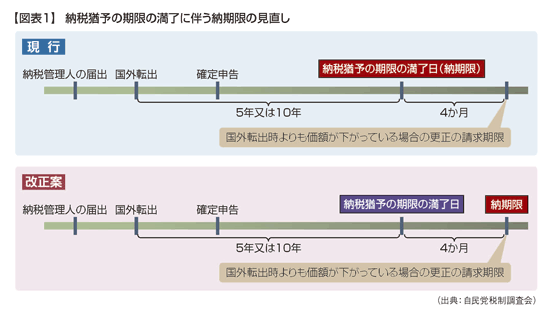
国外転出時課税が適用ない場合は取得価額の洗替えせず
2点目は、国外転出時に確定申告をしていない場合等の取得価額の洗替えの適用除外である。
現行、時価1億円以上の有価証券等を所有する者が国外転出する場合には、その際に時価によりその有価証券等を譲渡して再取得したものとみなされ、その有価証券等の取得価額はその国外転出時の時価に洗い替えられることになる。これは、確定申告をするかしないかは関係なく適用される。5年以内に帰国した場合には、更正の請求により課税を取り消すことが可能となっており、この場合の有価証券等の取得価額は国外転出前の価額に戻ることになる(図表2、事例1参照)。
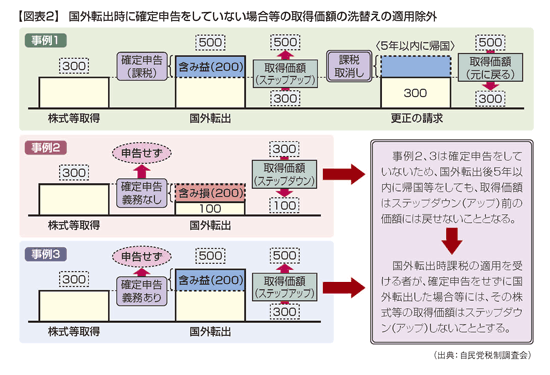
しかし、問題となるのは確定申告をせずに国外転出した場合だ。例えば、譲渡損失が生じていたため確定申告を行わず国外転出した場合には、5年以内に帰国等をしても修正申告ができず、取得価額を国外転出前の価額に戻すことができない(図表2、事例2参照)。
一方、申告義務があるにもかかわらず、無申告で国外転出した者については、課税されないまま取得価額がステップアップすることになってしまう(図表2、事例3参照)。
このような弊害を解消するため、平成28年度税制改正では、国外転出の日の属する年の所得税の計算において、国外転出時課税が適用されていない場合には、国外転出の時において所有する有価証券等の取得価額を時価に洗い替えないこととしている(改正所得税法60条の2等)。平成28年1月1日以後に帰国等をした場合について適用される。
ストックオプションは国外転出後も日本で課税
3点目はストックオプションに係る国外転出時課税制度の適用除外だ。現行、ストックオプションについては、国外転出時課税制度の対象となっている。しかし、税制非適格ストックオプションの場合は、非居住者が国外において税制非適格ストックオプションの権利行使により得た経済的利益のうち国内勤務期間に対応する分については、国内源泉所得として課税することとされている。また、税制適格ストックオプションは、権利行使時に給与課税は行われず、株式譲渡時に課税されることになるが、その譲渡所得は国内源泉所得として課税されることになる。
このため、スットクオプションの行使による所得は、税制非適格及び税制適格に関係なく、国内源泉所得として国外転出後も日本において課税することができるため、国外転出時課税制度の対象から除外することとされている(改正所得税法60条の2等)。平成28年分以後の所得税について適用される。
譲渡損失の繰越控除が可能に
4点目は、国外転出時課税により譲渡損失が生じた場合の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用についてだ。現行、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除については、金融商品取引業者等への売委託により行う譲渡や、金融商品取引業者等に対する譲渡など一定の譲渡により生じた譲渡損失のみが対象とされているが、国外転出時課税制度の適用により生じた上場株式等の譲渡損失については対象とされていない。
このため、平成28年度税制改正では、国外転出時課税制度の適用により生じた上場株式等の譲渡損失についても損益通算及び繰越控除の対象に追加する(改正措置法37条の12の2等)。これにより、上場株式等の譲渡による損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が可能になる。平成28年分以後の所得税について適用される。
国外転出後に同一銘柄を取得した場合の譲渡の判定を明らかに
5点目は、国外転出の後に同一銘柄の有価証券等を取得している場合の取扱いの明確化だ。現行では、納税猶予の適用を受けている非居住者が、国外転出の後に有価証券等を譲渡した場合については、国外転出の後に取得した有価証券等から先に譲渡したものとされ、納税猶予の適用を継続することができる(図表3、事例1参照)。しかし、国外転出後、贈与等により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予の適用を受けている場合については、どちらの有価証券等を譲渡したものであるか規定が定かではなかった。
このため、平成28年度税制改正では、判定方法として、まずは①納税猶予の適用を受けている有価証券等と②それ以外の有価証券等に区分。②の有価証券等から先に譲渡したものとされる。この点、贈与等により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予を受けているものは①に含まれていることを明確化する。①の納税猶予の適用を受けている有価証券等に関しては、先に取得したものから先に譲渡したものとされる(図表3、事例2参照)。平成28年1月1日以後の譲渡等について適用される。
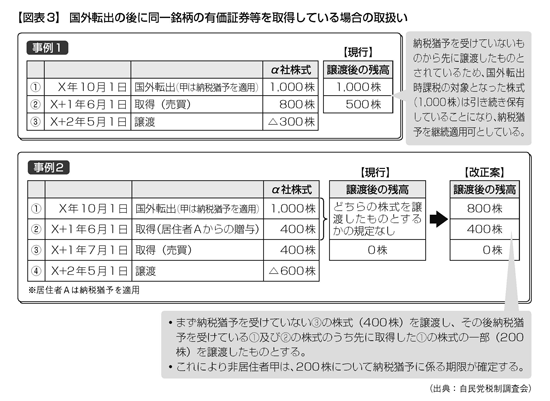
NISAも国外転出日の3月前の日で統一
6点目は、NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式等が国外転出時課税の対象となる場合の時価評価日の見直しだ。現行、NISA口座を開設している者が国外転出をする場合には、当該口座は国外転出の日に廃止され、口座内の上場株式等はその国外転出の日に国外転出の日の時価で譲渡したものとみなされる。一方、国外転出をする者が、納税管理人の届出をしないで国外転出の時までに準確定申告をする場合には、所有する対象資産はその国外転出の日に、国外転出の日の3月前の日の時価で譲渡したものとみなされる。
このため、平成28年度税制改正では、NISAと国外転出時課税制度の時価評価日を統一し、NISA口座内の上場株式等が準確定申告によって国外転出時課税の対象となる場合には、その口座内の上場株式等は、国外転出の日に、国外転出の日の3月前の日の時価で譲渡したものとみなして非課税の適用対象とする。ジュニアNISAについても同様である。
ストックオプションは適用対象外に
図表で読み解く国外転出時課税制度の改正
平成27年7月から施行されている国外転出時課税制度だが、平成28年度税制改正では、さらなる見直しが実施される。本誌ですでにお伝えしている未分割課税後の遺産分割への対応以外でも、ストックオプションの適用除外や、納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直しなど、これまで指摘されていた問題点の修正などが行われる。本特集では、図表を用いながら国外転出時課税制度の改正事項について解説する。
国外転出時課税制度の問題点などを修正
国外転出時課税制度が平成27年7月1日から施行されている。同制度は①対象者が国外転出をする時、②対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ有価証券等の一部又は全部を贈与する時、③対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時において、一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有している場合において、その対象資産の含み益に対して所得税が課税されるものである。
平成28年度税制改正では、現行の国外転出時課税制度で指摘されている問題点の修正や取扱いの明確化などが行われる。その最たるものは、すでに本誌でもお伝えしている未分割課税後の遺産分割に対応するものだ(本誌623号11頁、627号24頁参照)。
国外転出時課税に係る準確定申告の期限(相続開始を知った日から4月以内)までに有価証券等が未分割である場合には、非居住者(相続人)の法定相続分で準確定申告を行うことになる。しかし、その後の遺産分割協議の成立により非居住者が有価証券等を取得しない場合、準確定申告をした所得税に関し更正の請求が認められるか否かが法令等により明らかにされていなかった。この点、平成28年度税制改正では、非居住者(相続人)が法定相続分で準確定申告を行った後に遺産分割が行われたことで、非居住者に移転した有価証券等が当初の申告と異なることとなった場合には、国外転出時課税制度の適用を受けた居住者の相続人はその遺産分割が行われた日から4月以内に、税額が減少する場合は更正の請求をすることが可能になる(改正所得税法151条の5等)。平成28年1月1日以後に遺産分割の確定等が生じた場合から適用される。
その他にも、(1)納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直し、(2)国外転出時に確定申告をしていない場合等の取得価額の洗替えの適用除外、(3)ストックオプションに係る国外転出時課税制度の適用除外、(4)国外転出時課税により譲渡損失が生じた場合の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用、(5)国外転出の後に同一銘柄の有価証券等を取得している場合の取扱いの明確化、(6)NISA口座内の上場株式等が国外転出時課税の対象となる場合の時価評価日の見直しについて整備が行われることになる。
以下、概要について見てみることにする。
納期限を国外転出の日以後5年4月に
1点目は、納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直しである。現行、国外転出の日から納税猶予の期限の満了日まで引き続き保有している有価証券等の価額が、その納税猶予の期限の満了日において国外転出の日よりも下落している場合には、その下落した価額により国外転出時の課税の再計算をすることができる特例が設けられている。特例の適用を受けるには、納税猶予の期限の満了日から4月を経過する日までに更正の請求をすることとされている。
しかし、納税猶予の期限の満了に伴う納期限は国外転出の日から5年(又は10年)を経過する日となっているため、一度、納税猶予の適用を受けていた税額を納付する必要が生じてしまうという問題点があった。
このため、平成28年度税制改正では、この手続上の負担をなくすため、納税猶予の期限の満了に伴う納期限について、国外転出の日以後5年4月(又は10年4月)を経過する日に見直している(改正所得税法137条の2、137条の3、図表1参照)。この改正は、平成28年1月1日以後に納税猶予に係る期限の満了日が到来する場合について適用される。
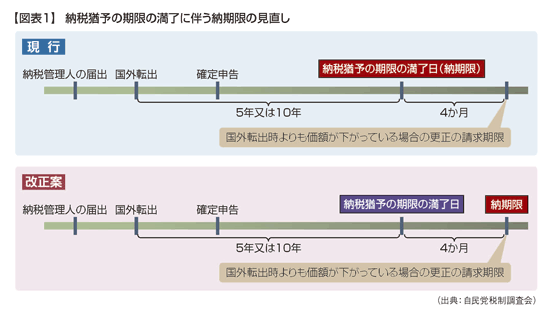
国外転出時課税が適用ない場合は取得価額の洗替えせず
2点目は、国外転出時に確定申告をしていない場合等の取得価額の洗替えの適用除外である。
現行、時価1億円以上の有価証券等を所有する者が国外転出する場合には、その際に時価によりその有価証券等を譲渡して再取得したものとみなされ、その有価証券等の取得価額はその国外転出時の時価に洗い替えられることになる。これは、確定申告をするかしないかは関係なく適用される。5年以内に帰国した場合には、更正の請求により課税を取り消すことが可能となっており、この場合の有価証券等の取得価額は国外転出前の価額に戻ることになる(図表2、事例1参照)。
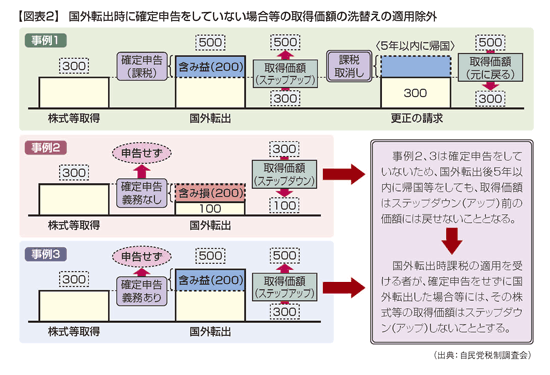
しかし、問題となるのは確定申告をせずに国外転出した場合だ。例えば、譲渡損失が生じていたため確定申告を行わず国外転出した場合には、5年以内に帰国等をしても修正申告ができず、取得価額を国外転出前の価額に戻すことができない(図表2、事例2参照)。
一方、申告義務があるにもかかわらず、無申告で国外転出した者については、課税されないまま取得価額がステップアップすることになってしまう(図表2、事例3参照)。
このような弊害を解消するため、平成28年度税制改正では、国外転出の日の属する年の所得税の計算において、国外転出時課税が適用されていない場合には、国外転出の時において所有する有価証券等の取得価額を時価に洗い替えないこととしている(改正所得税法60条の2等)。平成28年1月1日以後に帰国等をした場合について適用される。
ストックオプションは国外転出後も日本で課税
3点目はストックオプションに係る国外転出時課税制度の適用除外だ。現行、ストックオプションについては、国外転出時課税制度の対象となっている。しかし、税制非適格ストックオプションの場合は、非居住者が国外において税制非適格ストックオプションの権利行使により得た経済的利益のうち国内勤務期間に対応する分については、国内源泉所得として課税することとされている。また、税制適格ストックオプションは、権利行使時に給与課税は行われず、株式譲渡時に課税されることになるが、その譲渡所得は国内源泉所得として課税されることになる。
このため、スットクオプションの行使による所得は、税制非適格及び税制適格に関係なく、国内源泉所得として国外転出後も日本において課税することができるため、国外転出時課税制度の対象から除外することとされている(改正所得税法60条の2等)。平成28年分以後の所得税について適用される。
譲渡損失の繰越控除が可能に
4点目は、国外転出時課税により譲渡損失が生じた場合の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用についてだ。現行、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除については、金融商品取引業者等への売委託により行う譲渡や、金融商品取引業者等に対する譲渡など一定の譲渡により生じた譲渡損失のみが対象とされているが、国外転出時課税制度の適用により生じた上場株式等の譲渡損失については対象とされていない。
このため、平成28年度税制改正では、国外転出時課税制度の適用により生じた上場株式等の譲渡損失についても損益通算及び繰越控除の対象に追加する(改正措置法37条の12の2等)。これにより、上場株式等の譲渡による損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が可能になる。平成28年分以後の所得税について適用される。
国外転出後に同一銘柄を取得した場合の譲渡の判定を明らかに
5点目は、国外転出の後に同一銘柄の有価証券等を取得している場合の取扱いの明確化だ。現行では、納税猶予の適用を受けている非居住者が、国外転出の後に有価証券等を譲渡した場合については、国外転出の後に取得した有価証券等から先に譲渡したものとされ、納税猶予の適用を継続することができる(図表3、事例1参照)。しかし、国外転出後、贈与等により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予の適用を受けている場合については、どちらの有価証券等を譲渡したものであるか規定が定かではなかった。
このため、平成28年度税制改正では、判定方法として、まずは①納税猶予の適用を受けている有価証券等と②それ以外の有価証券等に区分。②の有価証券等から先に譲渡したものとされる。この点、贈与等により取得した有価証券等でその贈与者等が納税猶予を受けているものは①に含まれていることを明確化する。①の納税猶予の適用を受けている有価証券等に関しては、先に取得したものから先に譲渡したものとされる(図表3、事例2参照)。平成28年1月1日以後の譲渡等について適用される。
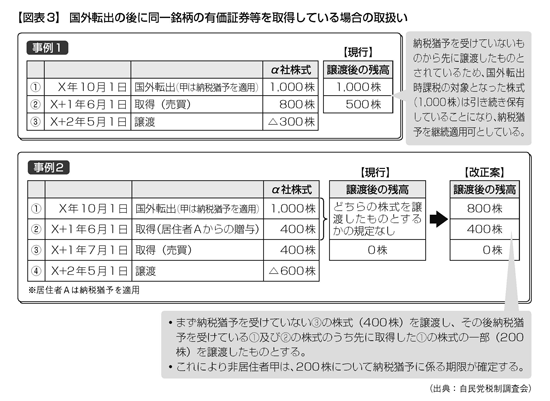
NISAも国外転出日の3月前の日で統一
6点目は、NISA(少額投資非課税制度)口座内の上場株式等が国外転出時課税の対象となる場合の時価評価日の見直しだ。現行、NISA口座を開設している者が国外転出をする場合には、当該口座は国外転出の日に廃止され、口座内の上場株式等はその国外転出の日に国外転出の日の時価で譲渡したものとみなされる。一方、国外転出をする者が、納税管理人の届出をしないで国外転出の時までに準確定申告をする場合には、所有する対象資産はその国外転出の日に、国外転出の日の3月前の日の時価で譲渡したものとみなされる。
このため、平成28年度税制改正では、NISAと国外転出時課税制度の時価評価日を統一し、NISA口座内の上場株式等が準確定申告によって国外転出時課税の対象となる場合には、その口座内の上場株式等は、国外転出の日に、国外転出の日の3月前の日の時価で譲渡したものとみなして非課税の適用対象とする。ジュニアNISAについても同様である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























