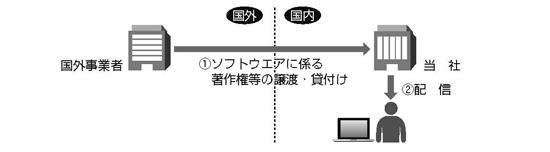解説記事2016年02月29日 【税務マエストロ】 資産の譲渡等の範囲(2)(2016年2月29日号・№632)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
資産の譲渡等の範囲(2)
#157 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#158 外国法人課税とAOAの適用開始②
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 今月は、「資産の譲渡等の範囲」のうち、「資産の貸付け」と「役務の提供」について学習し、関連する国税庁質疑応答事例を紹介する。また、平成27年度改正において、「著作物の利用の許諾に該当する取引」が役務の提供に分類されたことの理由、親族間の取引に対する考え方についても確認する。
1 資産の貸付け
(1)資産の貸付けの意義 「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれる(消法2②)。「資産に係る権利の設定」とは、土地に対する地上権や地役権の設定、特許権等の工業所有権に対する実施権や使用権の設定、著作物に対する出版権の設定などをいう(消基通5-4-1)。これらの権利を設定する行為は、「譲渡」「貸付け」「役務の提供」のいずれかに該当するのか、あるいは該当しないのかが判然としない。そこで、これらの権利の設定は「資産の貸付け」に含まれることを明記したということである。
〇国税庁質疑応答事例 土地に設定された抵当権の譲渡(資産の譲渡の範囲30)
(2)従業員などに対する福利厚生施設の貸付け
社宅や保養所などの福利厚生施設を従業員に有料で貸付ける行為は消費税の課税の対象となる。消費税は、社外の者との取引についてだけを課税の対象とするのではない。従業員などの会社内部の者との取引であっても、対価を得ている限りは課税の対象に組み込むものである(消基通5-4-4)。
(3)不動産の賃貸借(消基通5-4-3・9-1-23・5-2-7) 建物や土地の賃貸借契約にあたり収受する保証金や権利金などのうち、賃借人に返還しない金額については、家賃や地代の先取りと考え、課税の対象とするのであるが、契約期間終了時に返還する部分の金額は賃借人からの預り金であり、課税の対象とはならない(図参照)。
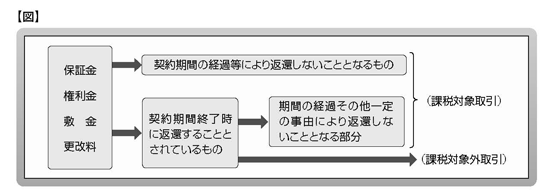
なお、建物を賃借人が破損した場合や、契約により毎年5%ずつ保証金を償却するような場合については、その返還しないこととなった時点で、その返還不要となる金額を課税の対象に組み込むことになる。
(注)住宅の貸付けは、課税対象取引に区分したうえで非課税取引となる。
また、建物などの賃貸借契約を解除し、入居者が家主から立退料を収受するようなことがあるが、この立退料の実体は、権利の消滅や営業上の損失に対する補償として支払われるものであり、原則として課税の対象とはならない。
〔参考〕違約金・保証金償却・建築協力金
2 役務の提供
(1)役務の提供の意義 「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる(消基通5-5-1)。
消費税法基本通達5-5-1(役務の提供の意義)は、「意義」ではなく、例示の列挙である。
(2)平成27年度改正 平成27年度改正では、国際電子商取引に対する課税の見直しを図るために、内外判定、納税義務者、仕入税額控除など、広範囲にわたり法律の改正が行われた。国内取引の課税対象要件である内外判定は、「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」ごとにその基準が定められている。したがって、その取引が「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」のいずれに該当するかということで、内外判定も変わってくることになるのである。
著作権(出版権又は著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)の貸付けは、貸付者の住所地により内外判定をすることとされている(消令6①七)。これに対し、電子書籍や音楽の配信のような「著作物の利用の許諾に該当する取引」については、上記のような内外判定によらず、「電気通信利用役務の提供」として「リバースチャージ方式」又は「国外事業者申告納税方式」を適用することとなった(消法4③三)。
〔参考〕国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A
(平成27年9月改訂・国税庁消費税室)
3 親族間の取引 個人事業者が生計を一にする親族間で行った資産の譲渡等であっても、それが事業として対価を得ているものであるときは、これらの行為は課税の対象となる(消基通5-1-10)。また、その対価の額が著しく低額であったとしても、役員に対する低額譲渡ではないので時価による認定課税はされない。その実際の譲渡対価を基に税額計算をすることになるのである。
ところで、所得税法では、事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に給料、家賃、借入金の利子などを支払ったとしても、その支払った金額を必要経費に算入することは認められない。反面、事業主から家賃などの支払を受ける親族が要した経費については、事業主の必要経費に算入することとしている(所法56)。
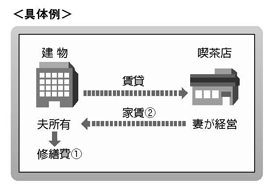 所得税では、妻は事業所得(喫茶店)の計算上、夫に支払った家賃②を必要経費に算入することはできないが、夫が負担した修繕費①を必要経費に算入することができる。
所得税では、妻は事業所得(喫茶店)の計算上、夫に支払った家賃②を必要経費に算入することはできないが、夫が負担した修繕費①を必要経費に算入することができる。
消費税では、妻が課税事業者の場合、夫が負担した修繕費①は課税仕入れとはならないが、夫に支払った家賃②が課税仕入れとなり、仕入控除税額の計算に取り込まれることになる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
資産の譲渡等の範囲(2)
#157 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#158 外国法人課税とAOAの適用開始②
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 今月は、「資産の譲渡等の範囲」のうち、「資産の貸付け」と「役務の提供」について学習し、関連する国税庁質疑応答事例を紹介する。また、平成27年度改正において、「著作物の利用の許諾に該当する取引」が役務の提供に分類されたことの理由、親族間の取引に対する考え方についても確認する。
1 資産の貸付け
(1)資産の貸付けの意義 「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれる(消法2②)。「資産に係る権利の設定」とは、土地に対する地上権や地役権の設定、特許権等の工業所有権に対する実施権や使用権の設定、著作物に対する出版権の設定などをいう(消基通5-4-1)。これらの権利を設定する行為は、「譲渡」「貸付け」「役務の提供」のいずれかに該当するのか、あるいは該当しないのかが判然としない。そこで、これらの権利の設定は「資産の貸付け」に含まれることを明記したということである。
〇国税庁質疑応答事例 土地に設定された抵当権の譲渡(資産の譲渡の範囲30)
| 【照会要旨】
融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。 また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税の対象となります。 また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税の対象となります。 (理由) 抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。 |
(3)不動産の賃貸借(消基通5-4-3・9-1-23・5-2-7) 建物や土地の賃貸借契約にあたり収受する保証金や権利金などのうち、賃借人に返還しない金額については、家賃や地代の先取りと考え、課税の対象とするのであるが、契約期間終了時に返還する部分の金額は賃借人からの預り金であり、課税の対象とはならない(図参照)。
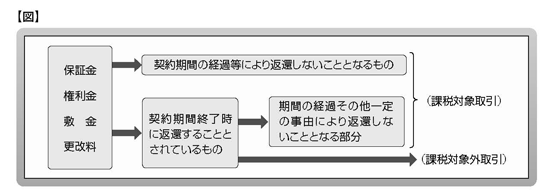
なお、建物を賃借人が破損した場合や、契約により毎年5%ずつ保証金を償却するような場合については、その返還しないこととなった時点で、その返還不要となる金額を課税の対象に組み込むことになる。
(注)住宅の貸付けは、課税対象取引に区分したうえで非課税取引となる。
また、建物などの賃貸借契約を解除し、入居者が家主から立退料を収受するようなことがあるが、この立退料の実体は、権利の消滅や営業上の損失に対する補償として支払われるものであり、原則として課税の対象とはならない。
〔参考〕違約金・保証金償却・建築協力金
| 建物の賃貸借契約について、入居者からの解約の申入れにより収受する違約金は、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものであり、損害賠償金として課税の対象とはならない。これは、違約金相当額を保証金と相殺する場合であろうと、また、賃借人から別途受領する場合であろうと、その取扱いが変わるものではない。 例えば、「中途解約の場合には保証金の20%相当額を返還しない」と契約書で定めている場合には、保証金の20%相当額は課税対象外収入となる。一方、「5年ごとに保証金の20%相当額を償却する」と契約書で定めている場合には、契約により定めた5年目ではなく、初年度で保証金の20%相当額が課税の対象となる。結果、店舗の賃貸であれば、その保証金の償却額は課税されることになる。 保証金の償却額は家賃収入とは異なり、現預金が移動して通帳などに記録が残るものではない。したがって、契約書の内容をしっかりと確認し、決算の際に忘れずに帳簿上で振替処理をする必要がある。 また、賃貸人が賃借人から建築協力金を収受し、月々の家賃と相殺することによりこれを返済することがある。この場合には、実際に収受する金銭ではなく、相殺前の金額を家賃として計上する必要があるので注意が必要だ。 <具体例> 家賃100を収受する際に、建築協力金60を相殺した後の金額40が通帳に振り込まれた場合の仕訳は次のようになる。  なお、中途解約があったことにより保証金(建築協力金)を家主が没収する場合には、その没収する保証金の残金は対価性がないことから課税対象外収入となる。 |
2 役務の提供
(1)役務の提供の意義 「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれる(消基通5-5-1)。
消費税法基本通達5-5-1(役務の提供の意義)は、「意義」ではなく、例示の列挙である。
(2)平成27年度改正 平成27年度改正では、国際電子商取引に対する課税の見直しを図るために、内外判定、納税義務者、仕入税額控除など、広範囲にわたり法律の改正が行われた。国内取引の課税対象要件である内外判定は、「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」ごとにその基準が定められている。したがって、その取引が「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」のいずれに該当するかということで、内外判定も変わってくることになるのである。
著作権(出版権又は著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)の貸付けは、貸付者の住所地により内外判定をすることとされている(消令6①七)。これに対し、電子書籍や音楽の配信のような「著作物の利用の許諾に該当する取引」については、上記のような内外判定によらず、「電気通信利用役務の提供」として「リバースチャージ方式」又は「国外事業者申告納税方式」を適用することとなった(消法4③三)。
| 区 分 | 内外判定の基準 |
| 著作権、出版権、著作隣接権、ノウハウなどの無形資産の譲渡や貸付け | 譲渡又は貸付者の住所、本店、主たる事務所の所在地 |
| 著作物の利用の許諾に該当する取引(著作物のダウンロード販売など) | 受益者の住所等 |
〔参考〕国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A
(平成27年9月改訂・国税庁消費税室)
(「電気通信利用役務の提供」の範囲②)
①の取引は、著作権・著作隣接権という資産の譲渡又は貸付けに該当し、電気通信回線を介して行われる役務の提供には該当しませんので、平成27年10月以後(改正法施行後)も、著作権・著作隣接権の譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととなり、改正前後においても国外取引として消費税の課税対象外となります(令6①七)。 ②の取引は、インターネットを通じたソフトウエアの販売であり、電気通信利用役務の提供に該当することから、平成27年10月以後は、役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地で内外判定を行うこととなりますが、国内事業者が国内のエンドユーザーに販売するものですので、これまでと課税関係に変更はなく、国内取引として消費税の課税対象となります(法4③三)。 |
3 親族間の取引 個人事業者が生計を一にする親族間で行った資産の譲渡等であっても、それが事業として対価を得ているものであるときは、これらの行為は課税の対象となる(消基通5-1-10)。また、その対価の額が著しく低額であったとしても、役員に対する低額譲渡ではないので時価による認定課税はされない。その実際の譲渡対価を基に税額計算をすることになるのである。
ところで、所得税法では、事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に給料、家賃、借入金の利子などを支払ったとしても、その支払った金額を必要経費に算入することは認められない。反面、事業主から家賃などの支払を受ける親族が要した経費については、事業主の必要経費に算入することとしている(所法56)。
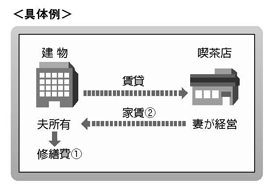 所得税では、妻は事業所得(喫茶店)の計算上、夫に支払った家賃②を必要経費に算入することはできないが、夫が負担した修繕費①を必要経費に算入することができる。
所得税では、妻は事業所得(喫茶店)の計算上、夫に支払った家賃②を必要経費に算入することはできないが、夫が負担した修繕費①を必要経費に算入することができる。消費税では、妻が課税事業者の場合、夫が負担した修繕費①は課税仕入れとはならないが、夫に支払った家賃②が課税仕入れとなり、仕入控除税額の計算に取り込まれることになる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -