解説記事2016年07月11日 【ニュース特集】 熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む(2016年7月11日号・№650)
ニュース特集
「災害損失特別勘定」計上で損金算入が可
熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む
4月14日の発生以来、いまだに工場の操業が停止しているなど、熊本地震の被害はまだ収まっていない。このような中、国税庁は6月21日、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下、費用通達)を公表した(今号36頁参照)。費用通達では、東日本大震災の際と同じく、「災害損失特別勘定」の損金算入が認められている。本特集では、費用通達の概要をお伝えする。なお、国税庁では、「平成28年熊本地震関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」も公表している。
東日本大震災時の通達と同様の内容
今回の熊本地震に関する費用通達は、平成23年の東日本大震災の際に発遣された「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)と同様のものとなっている。主な内容としては、①災害損失特別勘定への繰入額(修繕費用等の見積額)の損金算入、②損壊した賃借資産等に係る補修費、③被災者用仮設住宅の設置費用が挙げられる。
原則として申告調整できないが…… 費用通達の1番目のポイントは、東日本大震災の際と同じく、「災害損失特別勘定」の損金算入が認められた点だろう。
費用通達では、法人が災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額を災害損失特別勘定として経理した場合には、その災害損失特別勘定として経理した金額を当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できる旨の取扱いが定められている(費用通達2)。
また、災害損失特別勘定は、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれる修繕費用等の見積額であるため、減価償却費の計上などと同様、法人の認識を明確にするという意味で、被災事業年度等における損金経理が要件とされている。したがって、申告調整の方法により災害損失特別勘定への繰入額を損金算入することができないとされている。
ただし、4月から6月までの決算法人で、今回の費用通達の公表時に、すでに決算手続が終了しており、災害損失特別勘定の損金経理をできなかった等やむを得ない事情がある場合には、特例的に申告調整での損金算入も認めるとしている。
災害損失特別勘定に関する明細書が必要 勘定科目については、特別損失又は災害損失引当金繰入損等として処理している場合であっても、内容が災害損失特別勘定であり、損金算入及び益金算入に当たって、災害損失特別勘定に関する所要の明細書が確定申告書等に添付されていれば、これが認められるとしている。
また、災害損失特別勘定への繰入額が少額であり、企業会計上、特別損失として処理することが適当でないときは、企業会計上相当と認められる勘定科目で処理したとしてもOKだ。この場合、災害損失特別勘定に関する明細書の添付を要件に税務上も認められることとされている。
被災事業年度等の災害損失特別勘定に繰入れ 災害損失特別勘定の繰入れについては、災害のあった日の属する事業年度等に行うことになる(図1参照)。また、被災した事業年度等につき、仮決算による中間申告書等を提出する場合も災害損失特別勘定の繰入れを行うことができる(費用通達2(注)3)。
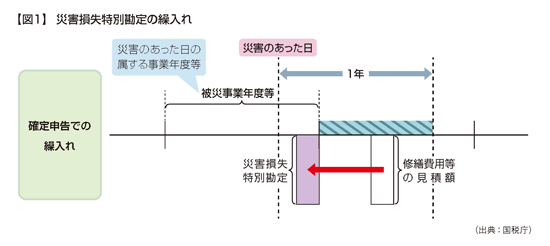
工場建物一式で計算も可 災害損失特別勘定の繰入限度額については、①被災資産(評価損を計上したものを除く)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合にその差額に相当する金額、②被災資産の修繕費用等(災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる費用)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれる金額に限る)のいずれか多い金額となる。①及び②の金額については、原則として個々の資産ごとに計算することになるが、例えば、「○○工場建物一式」「○○製造設備一式」とすることも可能としている。
なお、災害損失特別勘定の繰入対象とするものに係る保険金、損害賠償金、補助金等により補填される金額がある場合には、その金額を控除することになる。
残額がある場合は益金算入 また、災害損失特別勘定については、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、その残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することになる(費用通達4、図2参照)。
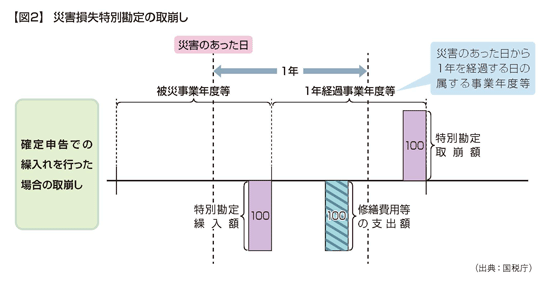
賃借人が行った補修費の損金算入が可能 2番目のポイントは、賃借人が賃借資産について補修のために要した費用について損金算入を認めていることだ(費用通達9)。
民法606条では、賃貸資産の修繕については、賃貸人の負担により行うべきとされており、賃借人が賃借資産の補修を行った場合には、その補修費用を賃貸人に請求することになっている。しかし、今回の取扱いは、災害による被害が甚大なこと等を鑑みた措置となっている。
なお、賃借人が修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その支払いを受けた日の属する事業年度等の益金の額に算入することになる(費用通達9(注)2)。
また、法人が修繕等の補修義務のない販売をした資産又は賃貸をしている資産について無償で補修や点検をした場合についても、法人が支出時に修繕費として損金経理した場合には、損金算入できることとしている。
仮設住宅設置費用の損金算入が可能 3番目のポイントは、法人が被災した役員や従業員の住居として仮設住宅を設置した場合の取扱いである。
この仮設住宅の組立て、設置のための費用については、その仮設住宅を居住の用に供した事業年度等において費用として経理したときは、これが認められる(費用通達10)。この点、法人が被災した従業員等のための仮設住宅の一部について、自己の従業員等以外の被災者の居住の用に供した場合についても、同様の取扱いが行われる。
反復利用する場合は7年で償却 また、法人が取得した仮設住宅用資材については、利用実態に即した償却が認められる(費用通達10)。被災した従業員等の住居として一時的に使用する場合には、仮設住宅に使用すると見込まれる期間(1年未満の端数は切捨て)を耐用年数として償却できる。一方、仮設住宅用資材を反復して使用する場合(仮設住宅として使用した後に他の用途に転用、再利用する)には、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」の7年で償却することになる。
「災害損失特別勘定」計上で損金算入が可
熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱い通達を読む
4月14日の発生以来、いまだに工場の操業が停止しているなど、熊本地震の被害はまだ収まっていない。このような中、国税庁は6月21日、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下、費用通達)を公表した(今号36頁参照)。費用通達では、東日本大震災の際と同じく、「災害損失特別勘定」の損金算入が認められている。本特集では、費用通達の概要をお伝えする。なお、国税庁では、「平成28年熊本地震関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」も公表している。
東日本大震災時の通達と同様の内容
今回の熊本地震に関する費用通達は、平成23年の東日本大震災の際に発遣された「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)と同様のものとなっている。主な内容としては、①災害損失特別勘定への繰入額(修繕費用等の見積額)の損金算入、②損壊した賃借資産等に係る補修費、③被災者用仮設住宅の設置費用が挙げられる。
原則として申告調整できないが…… 費用通達の1番目のポイントは、東日本大震災の際と同じく、「災害損失特別勘定」の損金算入が認められた点だろう。
費用通達では、法人が災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額を災害損失特別勘定として経理した場合には、その災害損失特別勘定として経理した金額を当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できる旨の取扱いが定められている(費用通達2)。
また、災害損失特別勘定は、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれる修繕費用等の見積額であるため、減価償却費の計上などと同様、法人の認識を明確にするという意味で、被災事業年度等における損金経理が要件とされている。したがって、申告調整の方法により災害損失特別勘定への繰入額を損金算入することができないとされている。
ただし、4月から6月までの決算法人で、今回の費用通達の公表時に、すでに決算手続が終了しており、災害損失特別勘定の損金経理をできなかった等やむを得ない事情がある場合には、特例的に申告調整での損金算入も認めるとしている。
災害損失特別勘定に関する明細書が必要 勘定科目については、特別損失又は災害損失引当金繰入損等として処理している場合であっても、内容が災害損失特別勘定であり、損金算入及び益金算入に当たって、災害損失特別勘定に関する所要の明細書が確定申告書等に添付されていれば、これが認められるとしている。
また、災害損失特別勘定への繰入額が少額であり、企業会計上、特別損失として処理することが適当でないときは、企業会計上相当と認められる勘定科目で処理したとしてもOKだ。この場合、災害損失特別勘定に関する明細書の添付を要件に税務上も認められることとされている。
被災事業年度等の災害損失特別勘定に繰入れ 災害損失特別勘定の繰入れについては、災害のあった日の属する事業年度等に行うことになる(図1参照)。また、被災した事業年度等につき、仮決算による中間申告書等を提出する場合も災害損失特別勘定の繰入れを行うことができる(費用通達2(注)3)。
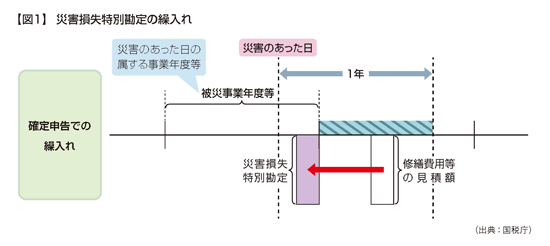
工場建物一式で計算も可 災害損失特別勘定の繰入限度額については、①被災資産(評価損を計上したものを除く)の被災事業年度等終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合にその差額に相当する金額、②被災資産の修繕費用等(災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる費用)の見積額(被災事業年度等終了の日の翌日以後に支出すると見込まれる金額に限る)のいずれか多い金額となる。①及び②の金額については、原則として個々の資産ごとに計算することになるが、例えば、「○○工場建物一式」「○○製造設備一式」とすることも可能としている。
なお、災害損失特別勘定の繰入対象とするものに係る保険金、損害賠償金、補助金等により補填される金額がある場合には、その金額を控除することになる。
残額がある場合は益金算入 また、災害損失特別勘定については、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、その残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することになる(費用通達4、図2参照)。
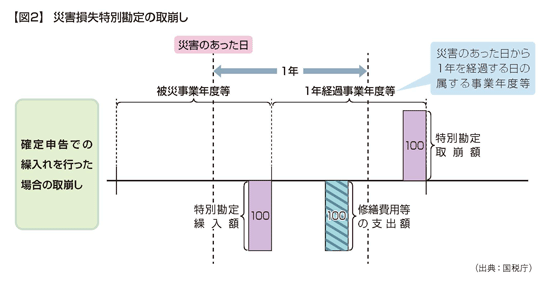
賃借人が行った補修費の損金算入が可能 2番目のポイントは、賃借人が賃借資産について補修のために要した費用について損金算入を認めていることだ(費用通達9)。
民法606条では、賃貸資産の修繕については、賃貸人の負担により行うべきとされており、賃借人が賃借資産の補修を行った場合には、その補修費用を賃貸人に請求することになっている。しかし、今回の取扱いは、災害による被害が甚大なこと等を鑑みた措置となっている。
なお、賃借人が修繕費として経理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その支払いを受けた日の属する事業年度等の益金の額に算入することになる(費用通達9(注)2)。
また、法人が修繕等の補修義務のない販売をした資産又は賃貸をしている資産について無償で補修や点検をした場合についても、法人が支出時に修繕費として損金経理した場合には、損金算入できることとしている。
仮設住宅設置費用の損金算入が可能 3番目のポイントは、法人が被災した役員や従業員の住居として仮設住宅を設置した場合の取扱いである。
この仮設住宅の組立て、設置のための費用については、その仮設住宅を居住の用に供した事業年度等において費用として経理したときは、これが認められる(費用通達10)。この点、法人が被災した従業員等のための仮設住宅の一部について、自己の従業員等以外の被災者の居住の用に供した場合についても、同様の取扱いが行われる。
反復利用する場合は7年で償却 また、法人が取得した仮設住宅用資材については、利用実態に即した償却が認められる(費用通達10)。被災した従業員等の住居として一時的に使用する場合には、仮設住宅に使用すると見込まれる期間(1年未満の端数は切捨て)を耐用年数として償却できる。一方、仮設住宅用資材を反復して使用する場合(仮設住宅として使用した後に他の用途に転用、再利用する)には、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる「建物」の「簡易建物」の「仮設のもの」の7年で償却することになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















