解説記事2016年12月26日 【税務マエストロ】 租税公課と消費税の関係(2016年12月26日号・№672)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
租税公課と消費税の関係
#179 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#180
平成29年度税制改正~国際課税関連について
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 個別消費税には、酒税のように消費税が事実上二重課税(Tax on Tax)となるもののほか、軽油引取税のように預り金としての性格を有するため、消費税が課されないものがある。また、旅費や保険料、○○税という名目で収受する金銭であっても、事実上資産の譲渡対価として取り扱われるものもあるので注意が必要だ。今月は、これらの租税公課と消費税との関係について確認する。
1 印紙税
(1)別途請求する印紙税 領収証に貼付する印紙の負担者(納税義務者)は、課税文書である領収証の作成者である。(印法3①)。したがって、製品代とは別に印紙代を請求されたとしても、その印紙代相当額は製品の販売価格の一部となるので、印紙代も含めた決済金額に対して消費税が課税されることになる。よって、「印紙代」などの名目で別途金銭を受領するような行為は誤解の基となるので慎むべきである。仮に「印紙税」という名目で決済した場合でも、受領する印紙代は課税売上高となり、また、支払サイドでは勘定科目に関わらず、課税仕入高として処理することができる。
(2)チケットショップにおける印紙の売買 郵便切手類や印紙を指定された場所以外で売買すると消費税が課税される(消基通6-4-1)。したがって、チケットショップに不要印紙を売却した場合には、その印紙の売却収入は課税売上高となる。また、チケットショップから購入した印紙については、たとえ租税公課勘定で処理しても、その購入費は課税仕入高となる。
(3)印紙の融通 営業マンや外交員が使用するための郵便切手や印紙を買い置きし、必要に応じて社外の外交員などに額面金額で売却することがある。このような取引は、金券ショップなどで行う郵便切手や印紙の譲渡とは異なり、実態は立替あるいは融通取引であると考えられる。
したがって、その売却代金は課税売上高に計上せずに、通信費勘定や租税公課勘定を減額処理しても問題ないものと思われる。
2 別途請求する登録免許税 抵当権を設定する際に課される登録免許税は、依頼者(抵当権の設定登記を受ける者)が納付することとされている(登免法3)。したがって、司法書士から請求された登録免許税は立替金であり、司法書士の報酬額とはならない(消基通10-1-4(注))。
また、謄本代も実費相当額は立替金であり、同様に報酬額には含まれないことになる。依頼者は、自らが納付することとされている登録免許税は当然に課税仕入高とはならず、また、謄本代は行政手数料(非課税)となるのでこれも仕入税額控除の対象とすることはできない。
3 酒税 酒税、たばこ税など、特定の課税物件だけを対象に課税するものを「個別消費税」という。これらの個別消費税は、原則として課税資産の譲渡対価に含めるものとされている。
例えば、酒税の場合、納税義務者は製造者とされており、製造者がお酒を製造場から出荷した分だけ酒税が課税されることになっている(製造場移出課税制度)。よって、酒造メーカーは、酒税の負担分をコストとして考慮したうえで、お酒の売値を決定する必要がある(図表1参照)。
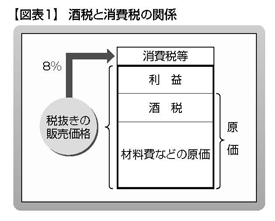
この場合の酒税は、あくまでもコスト(原価)として認識することになるので、酒造メーカーは、お酒の販売価格から酒税相当分を控除して消費税計算をすることはできない。結果、酒税に対してさらに消費税が併課され、事実上の二重課税(Tax on Tax)の状態が生ずることになるのである。
4 ゴルフ場利用税・入湯税
(1)ゴルフ場利用税・入湯税と酒税の違い 酒税やたばこ税などの個別消費税は、課税売上(仕入)高に含まれる。これに対し、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税については、利用者等が納税義務者となっていることから、課税売上(仕入)高には含まれない(消基通10-1-11)。
例えば、ゴルフ場利用税の場合には、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用者(納税義務者)からゴルフ場利用税を預り、これを都道府県に代理納付することとされている。したがって、ゴルフ場の経営者は預ったゴルフ場利用税を売上高に計上する必要はなく、利用者(プレーヤー)は支払ったゴルフ場利用税を仕入税額控除の対象とすることはできない。
入湯税については、温泉旅館などの経営者が宿泊客などから入湯税を預り、これを市区町村に代理納付するものであるから、旅館などの経営者は預った入湯税を売上高に計上する必要はなく、利用者は支払った入湯税を仕入税額控除の対象とすることはできないことになる。
(注)ゴルフ場利用税については、1人1日800円から1,200円、入湯税については、1人1日150円の税率で課税することとなっている。
(2)領収証にゴルフ場利用税の記載がない場合 実務上、ゴルフ場利用税やゴルフ保険料は、領収証ではなく、明細書に記載されているケースが多いようであるが、領収証にゴルフ場利用税やゴルフ保険料の記載がないからといって、領収証に記載されている全額を課税仕入高として処理することは認められない。ゴルフ場利用税に限らず、軽油引取税や入湯税については、とりわけ仕入税額控除についてのミスが多いようである。領収証だけではなく、利用明細書などもちゃんと確認するように心がけることが重要だ。
ところで、消費税法基本通達10-1-11(個別消費税の取扱い)のただし書では、ゴルフ場利用税が明確に区分されていない場合は、そのゴルフ場利用税は対価の額に含むものと定めている。この通達のただし書は、預り金であるゴルフ場利用税などを売上高と区分経理していない場合には、これらの税金も含めたところで課税売上高を計算させるという意図であると思われるのであるが、特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者は、通常であれば翌月の15日までにプレーヤーから徴収したゴルフ場利用税を都道府県に納入することが義務付けられているので、区分経理がされていないなどということは、実務上あり得ないはずである。
こういった理由からも、仕入税額控除におけるミスを防止するために、特別徴収義務者であるゴルフ場や旅館などの経営者が発行する領収証には、ゴルフ場利用税や入湯税の明記を義務付けるべきである。
消費税法基本通達5-5-3(会費、組合費等)の(注)3では、課税の対象とならない通常会費等を収受する同業者団体や組合等は、その旨をその構成員に通知することとしている。この通知により、構成員は支払った会費等が課税仕入れに該当しないことを確認できるという効果がある。ゴルフ場利用税や入湯税などについても、特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者や旅館などに領収証への明記を義務付けることにより、仕入税額控除におけるミスは相当に防げるのではないだろうか?
5 軽油引取税
(1)軽油引取税の納税義務者 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引き取り等に対して課税される。したがって、特約店から軽油を仕入れている小売店は、軽油引取税の納税義務者となる。特別徴収義務者である特約店は、納税義務者である小売店から軽油の販売代金と共に軽油引取税を徴収し、都道府県に代理納付をするというシステムになっているのである。
つまり、特約店が小売店から受領する軽油引取税は単なる預り金であり、軽油の譲渡対価ではない。また、小売店が仕入税額控除の対象とできるのは当然に軽油代だけであり、軽油引取税は課税仕入高に該当しないことになる。
軽油の売上代金から軽油引取税をマイナスすることができるのは、軽油引取税の特別徴収義務者である特約店だけである。つまり、ガソリンスタンドなどの小売店が特約店から軽油を仕入れ、これを販売する場合には、たとえ軽油代と軽油引取税を区分していたとしても、その合計金額に対し、消費税が課税されることになるので注意が必要だ(図表2参照)。
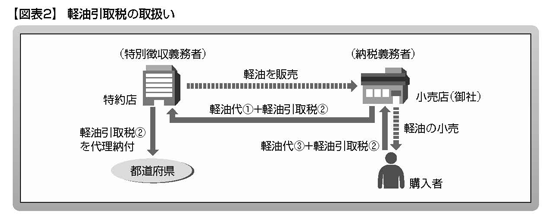
図表2において、特約店の課税売上高は①となる。小売店は、特約店に支払った軽油引取税②は課税仕入高とはならず、①だけが課税仕入高となる。さらに、この軽油引取税②を軽油の販売代金③と区分して領収したとしても、軽油引取税②は形式上区分した販売価格の一部分と認識するので、「③+②」の金額が課税売上高になる。小売店が支払った軽油引取税②は、あくまでも小売店の原価(コスト)として認識しなければいけないということに注意する必要がある。
(2)委託販売契約の検討 軽油引取税に対して消費税が課税されることを防ぐために、業界内では、委託販売形態による取引を指導しているようである。全国石油商業組合連合会で発行しているパンフレット(軽油の販売と消費税)によると、軽油の販売について、小売店と特約店との間で委託販売契約を結ぶことにより、手数料(軽油の販売による粗利益)だけを課税売上高に計上することが認められている。図表2のケ-スが委託販売の場合であれば、小売店の課税売上高は、軽油の売上高と軽油の仕入高の差額(③-①)だけ計上すればよいことになる。会計処理については、委託販売であれば、本来は「委託販売勘定」で処理すべきなのであるが、従来から業界では、売上、仕入勘定で処理してきたという経緯があるので、委託販売契約によることになっても従来どおりの勘定科目で処理をしてよいこととされている。なお、この場合には、帳簿に委託販売である旨を明記する必要があるので注意が必要だ(詳細については「軽油の販売と消費税~全国石油商業組合連合会発行」を参照されたい)。
(3)委託販売による売上(仕入)金額の計算 図表2において、特約店と小売店の間で委託販売契約が結ばれている場合には、委託者である特約店は、③の金額を課税売上高に計上し、「③-①」の金額を委託販売手数料として課税仕入高に計上することになる。
委託販売その他業務代行等に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは図表3のとおりである(消基通10-1-12)。したがって、委託者である特約店は、原則として受託者である小売店が収受する③の金額を課税売上高に計上しなければならないのであるが、図表3の「例外」にあるように、委託販売手数料を控除した残額を委託者の課税売上高とすることも認められていることから、特約店は自らの売上高である①の金額だけを課税売上高に計上することもできることになる。
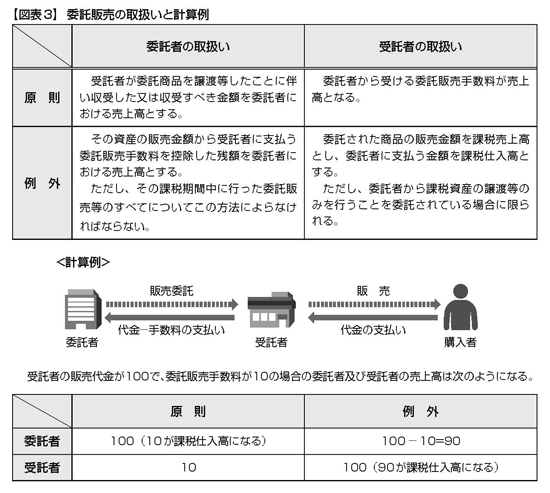
結果、特約店は、委託販売契約の有無によって会計処理が変わることはない。なお、「例外」による場合には、委託販売等のすべてについて統一適用しなければならない。特定の特約店とだけしか委託販売契約を結んでいないような場合には、原則どおり「③+②」の金額が小売店の課税売上高となるので注意が必要だ。
(4)軽油の購入者の取扱い 仕入先が特約店の場合、あるいは特約店と委託販売契約を結んでいる小売店の場合には、軽油代と区分された軽油引取税は当然に課税仕入高とはならない。一方で、小売店が特約店と委託販売契約を結んでいない場合には、たとえ軽油代と軽油引取税が区分されていたとしても、その全額を課税仕入高とすることができることになる。しかし、現実問題として、仕入先が特約店かどうか、あるいは特約店と委託販売契約を結んでいるかどうかということは、軽油を購入する側で判断することは難しいように思われる。したがって、軽油代と軽油引取税が区分されている場合には、実務上は、軽油引取税は課税仕入高から除外せざるを得ないものと思われる。
なお、ガソリンスタンドのなかには、図表4のような領収証を発行する店もあるようだ。このような領収証を発行している場合には、販売者は軽油引取税も含めた金額を課税売上高として処理していることが明らかであるから、軽油を購入する側においても、その全額を課税仕入高として処理することができる。
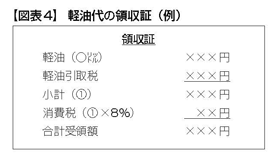
6 自動車税と自賠責保険料の清算 自動車税は、その年4月1日(賦課期日)における自動車の所有者に対し、翌年3月31日までの税金が課税される。そこで、中古自動車を売買する場合には、所有権が移転した後の未経過期間分を売り手と買い手で清算することが商慣行となっているようである。この自動車税や自賠責保険料の清算は、法令で義務付けられたものではない。こういった理由から、自動車税や自賠責保険料の清算金は売買した中古車の譲渡対価として取り扱うこととされている。結果、収受した清算金は課税売上高、支払った清算金は課税仕入高として処理することになる(消基通10-1-6)。
○参考(国税庁質疑応答事例~資産の譲渡の範囲 42中古車販売における未経過自動車税等の取扱い)
7 自動車取得税 自動車(新車)を購入したときに、車輌代と共に支払う自動車取得税と自賠責保険料は支払済経費の清算金ではない。また、自動車の販売業者が納税義務を負う性質のものでもない。自動車取得税は自動車の購入者が納税義務者となり、また、自賠責保険料は自動車の購入者に加入が義務付けられているものである。したがって、いずれの経費も課税仕入高とはならない(消基通10-1-4(注))。
法人税法上、自動車取得税は自動車の取得価額に算入して減価償却するのが原則であるが、自動車の取得時に租税公課として損金処理することも認められている(法基通7-3-3の2(1)イ)。これに対し、消費税では、自動車取得税は租税公課として処理した場合はもちろんのこと、取得価額に算入した場合であっても課税仕入高とはならないので注意が必要だ。
8 固定資産税等
(1)未経過固定資産税等の清算金 固定資産税と都市計画税は、その年1月1日(賦課期日)における土地や建物の所有者に対し、1年分の税金が課税される。そこで、年の中途に不動産を売買する場合には、所有権が移転した後の未経過期間分を売り手と買い手で清算することが商慣行となっているようである。この未経過固定資産税等の清算は、中古自動車を売買する際に清算する自動車税と同様に法令で義務付けられたものではない。
したがって、未経過固定資産税等の清算金は売買した不動産の譲渡対価として取り扱うこととされている。結果、清算金のうち、建物部分は課税売上高、土地部分は非課税売上高となる(消基通10-1-6)。
(2)未登記の場合の固定資産税 不動産を売買したものの、所有権移転登記が翌年にずれ込んでしまった場合には、その翌年においても、固定資産税等は旧所有者に対して課されることになる。
この場合において、その翌年において課される固定資産税等を譲受人に請求することとした場合のその金銭は未経過期間分の清算金ではない。本来は土地の所有者である譲受人に課されるべきものが、登記の遅れが原因で譲渡人に課されたものである。よって、譲渡人が納付することとなる固定資産税等は単なる立替金であり、売買した土地の譲渡対価に加算する必要はない(消基通10-1-6(注))。
○参考(国税庁質疑応答事例~資産の譲渡の範囲 34不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税)
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
今週のマエストロ&テーマ
租税公課と消費税の関係
#179 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#180
平成29年度税制改正~国際課税関連について
PwC税理士法人
品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
マエストロの解説 個別消費税には、酒税のように消費税が事実上二重課税(Tax on Tax)となるもののほか、軽油引取税のように預り金としての性格を有するため、消費税が課されないものがある。また、旅費や保険料、○○税という名目で収受する金銭であっても、事実上資産の譲渡対価として取り扱われるものもあるので注意が必要だ。今月は、これらの租税公課と消費税との関係について確認する。
1 印紙税
(1)別途請求する印紙税 領収証に貼付する印紙の負担者(納税義務者)は、課税文書である領収証の作成者である。(印法3①)。したがって、製品代とは別に印紙代を請求されたとしても、その印紙代相当額は製品の販売価格の一部となるので、印紙代も含めた決済金額に対して消費税が課税されることになる。よって、「印紙代」などの名目で別途金銭を受領するような行為は誤解の基となるので慎むべきである。仮に「印紙税」という名目で決済した場合でも、受領する印紙代は課税売上高となり、また、支払サイドでは勘定科目に関わらず、課税仕入高として処理することができる。
(2)チケットショップにおける印紙の売買 郵便切手類や印紙を指定された場所以外で売買すると消費税が課税される(消基通6-4-1)。したがって、チケットショップに不要印紙を売却した場合には、その印紙の売却収入は課税売上高となる。また、チケットショップから購入した印紙については、たとえ租税公課勘定で処理しても、その購入費は課税仕入高となる。
(3)印紙の融通 営業マンや外交員が使用するための郵便切手や印紙を買い置きし、必要に応じて社外の外交員などに額面金額で売却することがある。このような取引は、金券ショップなどで行う郵便切手や印紙の譲渡とは異なり、実態は立替あるいは融通取引であると考えられる。
したがって、その売却代金は課税売上高に計上せずに、通信費勘定や租税公課勘定を減額処理しても問題ないものと思われる。
2 別途請求する登録免許税 抵当権を設定する際に課される登録免許税は、依頼者(抵当権の設定登記を受ける者)が納付することとされている(登免法3)。したがって、司法書士から請求された登録免許税は立替金であり、司法書士の報酬額とはならない(消基通10-1-4(注))。
また、謄本代も実費相当額は立替金であり、同様に報酬額には含まれないことになる。依頼者は、自らが納付することとされている登録免許税は当然に課税仕入高とはならず、また、謄本代は行政手数料(非課税)となるのでこれも仕入税額控除の対象とすることはできない。
3 酒税 酒税、たばこ税など、特定の課税物件だけを対象に課税するものを「個別消費税」という。これらの個別消費税は、原則として課税資産の譲渡対価に含めるものとされている。
例えば、酒税の場合、納税義務者は製造者とされており、製造者がお酒を製造場から出荷した分だけ酒税が課税されることになっている(製造場移出課税制度)。よって、酒造メーカーは、酒税の負担分をコストとして考慮したうえで、お酒の売値を決定する必要がある(図表1参照)。
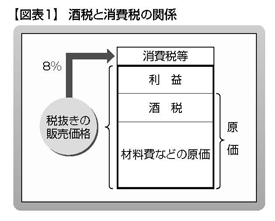
この場合の酒税は、あくまでもコスト(原価)として認識することになるので、酒造メーカーは、お酒の販売価格から酒税相当分を控除して消費税計算をすることはできない。結果、酒税に対してさらに消費税が併課され、事実上の二重課税(Tax on Tax)の状態が生ずることになるのである。
4 ゴルフ場利用税・入湯税
(1)ゴルフ場利用税・入湯税と酒税の違い 酒税やたばこ税などの個別消費税は、課税売上(仕入)高に含まれる。これに対し、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税については、利用者等が納税義務者となっていることから、課税売上(仕入)高には含まれない(消基通10-1-11)。
例えば、ゴルフ場利用税の場合には、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用者(納税義務者)からゴルフ場利用税を預り、これを都道府県に代理納付することとされている。したがって、ゴルフ場の経営者は預ったゴルフ場利用税を売上高に計上する必要はなく、利用者(プレーヤー)は支払ったゴルフ場利用税を仕入税額控除の対象とすることはできない。
入湯税については、温泉旅館などの経営者が宿泊客などから入湯税を預り、これを市区町村に代理納付するものであるから、旅館などの経営者は預った入湯税を売上高に計上する必要はなく、利用者は支払った入湯税を仕入税額控除の対象とすることはできないことになる。
(注)ゴルフ場利用税については、1人1日800円から1,200円、入湯税については、1人1日150円の税率で課税することとなっている。
(2)領収証にゴルフ場利用税の記載がない場合 実務上、ゴルフ場利用税やゴルフ保険料は、領収証ではなく、明細書に記載されているケースが多いようであるが、領収証にゴルフ場利用税やゴルフ保険料の記載がないからといって、領収証に記載されている全額を課税仕入高として処理することは認められない。ゴルフ場利用税に限らず、軽油引取税や入湯税については、とりわけ仕入税額控除についてのミスが多いようである。領収証だけではなく、利用明細書などもちゃんと確認するように心がけることが重要だ。
ところで、消費税法基本通達10-1-11(個別消費税の取扱い)のただし書では、ゴルフ場利用税が明確に区分されていない場合は、そのゴルフ場利用税は対価の額に含むものと定めている。この通達のただし書は、預り金であるゴルフ場利用税などを売上高と区分経理していない場合には、これらの税金も含めたところで課税売上高を計算させるという意図であると思われるのであるが、特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者は、通常であれば翌月の15日までにプレーヤーから徴収したゴルフ場利用税を都道府県に納入することが義務付けられているので、区分経理がされていないなどということは、実務上あり得ないはずである。
こういった理由からも、仕入税額控除におけるミスを防止するために、特別徴収義務者であるゴルフ場や旅館などの経営者が発行する領収証には、ゴルフ場利用税や入湯税の明記を義務付けるべきである。
消費税法基本通達5-5-3(会費、組合費等)の(注)3では、課税の対象とならない通常会費等を収受する同業者団体や組合等は、その旨をその構成員に通知することとしている。この通知により、構成員は支払った会費等が課税仕入れに該当しないことを確認できるという効果がある。ゴルフ場利用税や入湯税などについても、特別徴収義務者であるゴルフ場の経営者や旅館などに領収証への明記を義務付けることにより、仕入税額控除におけるミスは相当に防げるのではないだろうか?
5 軽油引取税
(1)軽油引取税の納税義務者 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引き取り等に対して課税される。したがって、特約店から軽油を仕入れている小売店は、軽油引取税の納税義務者となる。特別徴収義務者である特約店は、納税義務者である小売店から軽油の販売代金と共に軽油引取税を徴収し、都道府県に代理納付をするというシステムになっているのである。
つまり、特約店が小売店から受領する軽油引取税は単なる預り金であり、軽油の譲渡対価ではない。また、小売店が仕入税額控除の対象とできるのは当然に軽油代だけであり、軽油引取税は課税仕入高に該当しないことになる。
軽油の売上代金から軽油引取税をマイナスすることができるのは、軽油引取税の特別徴収義務者である特約店だけである。つまり、ガソリンスタンドなどの小売店が特約店から軽油を仕入れ、これを販売する場合には、たとえ軽油代と軽油引取税を区分していたとしても、その合計金額に対し、消費税が課税されることになるので注意が必要だ(図表2参照)。
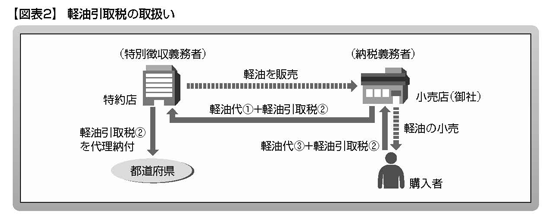
図表2において、特約店の課税売上高は①となる。小売店は、特約店に支払った軽油引取税②は課税仕入高とはならず、①だけが課税仕入高となる。さらに、この軽油引取税②を軽油の販売代金③と区分して領収したとしても、軽油引取税②は形式上区分した販売価格の一部分と認識するので、「③+②」の金額が課税売上高になる。小売店が支払った軽油引取税②は、あくまでも小売店の原価(コスト)として認識しなければいけないということに注意する必要がある。
(2)委託販売契約の検討 軽油引取税に対して消費税が課税されることを防ぐために、業界内では、委託販売形態による取引を指導しているようである。全国石油商業組合連合会で発行しているパンフレット(軽油の販売と消費税)によると、軽油の販売について、小売店と特約店との間で委託販売契約を結ぶことにより、手数料(軽油の販売による粗利益)だけを課税売上高に計上することが認められている。図表2のケ-スが委託販売の場合であれば、小売店の課税売上高は、軽油の売上高と軽油の仕入高の差額(③-①)だけ計上すればよいことになる。会計処理については、委託販売であれば、本来は「委託販売勘定」で処理すべきなのであるが、従来から業界では、売上、仕入勘定で処理してきたという経緯があるので、委託販売契約によることになっても従来どおりの勘定科目で処理をしてよいこととされている。なお、この場合には、帳簿に委託販売である旨を明記する必要があるので注意が必要だ(詳細については「軽油の販売と消費税~全国石油商業組合連合会発行」を参照されたい)。
(3)委託販売による売上(仕入)金額の計算 図表2において、特約店と小売店の間で委託販売契約が結ばれている場合には、委託者である特約店は、③の金額を課税売上高に計上し、「③-①」の金額を委託販売手数料として課税仕入高に計上することになる。
委託販売その他業務代行等に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは図表3のとおりである(消基通10-1-12)。したがって、委託者である特約店は、原則として受託者である小売店が収受する③の金額を課税売上高に計上しなければならないのであるが、図表3の「例外」にあるように、委託販売手数料を控除した残額を委託者の課税売上高とすることも認められていることから、特約店は自らの売上高である①の金額だけを課税売上高に計上することもできることになる。
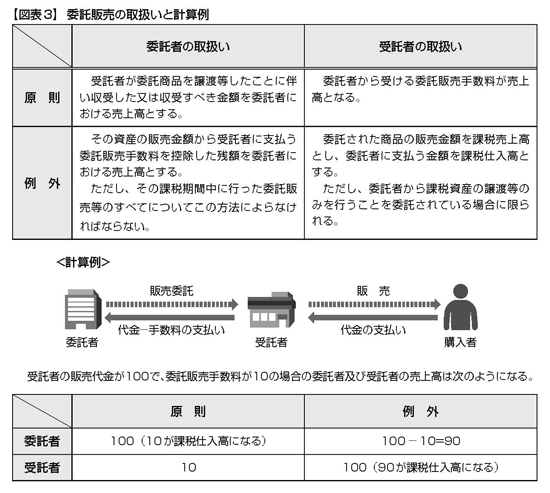
結果、特約店は、委託販売契約の有無によって会計処理が変わることはない。なお、「例外」による場合には、委託販売等のすべてについて統一適用しなければならない。特定の特約店とだけしか委託販売契約を結んでいないような場合には、原則どおり「③+②」の金額が小売店の課税売上高となるので注意が必要だ。
(4)軽油の購入者の取扱い 仕入先が特約店の場合、あるいは特約店と委託販売契約を結んでいる小売店の場合には、軽油代と区分された軽油引取税は当然に課税仕入高とはならない。一方で、小売店が特約店と委託販売契約を結んでいない場合には、たとえ軽油代と軽油引取税が区分されていたとしても、その全額を課税仕入高とすることができることになる。しかし、現実問題として、仕入先が特約店かどうか、あるいは特約店と委託販売契約を結んでいるかどうかということは、軽油を購入する側で判断することは難しいように思われる。したがって、軽油代と軽油引取税が区分されている場合には、実務上は、軽油引取税は課税仕入高から除外せざるを得ないものと思われる。
なお、ガソリンスタンドのなかには、図表4のような領収証を発行する店もあるようだ。このような領収証を発行している場合には、販売者は軽油引取税も含めた金額を課税売上高として処理していることが明らかであるから、軽油を購入する側においても、その全額を課税仕入高として処理することができる。
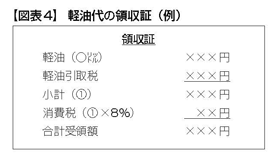
6 自動車税と自賠責保険料の清算 自動車税は、その年4月1日(賦課期日)における自動車の所有者に対し、翌年3月31日までの税金が課税される。そこで、中古自動車を売買する場合には、所有権が移転した後の未経過期間分を売り手と買い手で清算することが商慣行となっているようである。この自動車税や自賠責保険料の清算は、法令で義務付けられたものではない。こういった理由から、自動車税や自賠責保険料の清算金は売買した中古車の譲渡対価として取り扱うこととされている。結果、収受した清算金は課税売上高、支払った清算金は課税仕入高として処理することになる(消基通10-1-6)。
○参考(国税庁質疑応答事例~資産の譲渡の範囲 42中古車販売における未経過自動車税等の取扱い)
| 【照会要旨】
中古車を販売する際に、車両本体価格と未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額を区分して表示した場合、未経過分の自動車税相当額及びリサイクル預託金相当額は、資産の譲渡等の対価の額に含まれないこととなるのでしょうか。 【回答要旨】 自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。 したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。 一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令91四)。 |
7 自動車取得税 自動車(新車)を購入したときに、車輌代と共に支払う自動車取得税と自賠責保険料は支払済経費の清算金ではない。また、自動車の販売業者が納税義務を負う性質のものでもない。自動車取得税は自動車の購入者が納税義務者となり、また、自賠責保険料は自動車の購入者に加入が義務付けられているものである。したがって、いずれの経費も課税仕入高とはならない(消基通10-1-4(注))。
法人税法上、自動車取得税は自動車の取得価額に算入して減価償却するのが原則であるが、自動車の取得時に租税公課として損金処理することも認められている(法基通7-3-3の2(1)イ)。これに対し、消費税では、自動車取得税は租税公課として処理した場合はもちろんのこと、取得価額に算入した場合であっても課税仕入高とはならないので注意が必要だ。
8 固定資産税等
(1)未経過固定資産税等の清算金 固定資産税と都市計画税は、その年1月1日(賦課期日)における土地や建物の所有者に対し、1年分の税金が課税される。そこで、年の中途に不動産を売買する場合には、所有権が移転した後の未経過期間分を売り手と買い手で清算することが商慣行となっているようである。この未経過固定資産税等の清算は、中古自動車を売買する際に清算する自動車税と同様に法令で義務付けられたものではない。
したがって、未経過固定資産税等の清算金は売買した不動産の譲渡対価として取り扱うこととされている。結果、清算金のうち、建物部分は課税売上高、土地部分は非課税売上高となる(消基通10-1-6)。
(2)未登記の場合の固定資産税 不動産を売買したものの、所有権移転登記が翌年にずれ込んでしまった場合には、その翌年においても、固定資産税等は旧所有者に対して課されることになる。
この場合において、その翌年において課される固定資産税等を譲受人に請求することとした場合のその金銭は未経過期間分の清算金ではない。本来は土地の所有者である譲受人に課されるべきものが、登記の遅れが原因で譲渡人に課されたものである。よって、譲渡人が納付することとなる固定資産税等は単なる立替金であり、売買した土地の譲渡対価に加算する必要はない(消基通10-1-6(注))。
○参考(国税庁質疑応答事例~資産の譲渡の範囲 34不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税)
| 【照会要旨】
不動産の売買により引渡しを行いましたが、その引渡し時に登記簿上名義書替えを行わなかったため、登録名義人である譲渡者が当該不動産の固定資産税を納付することとなりました。この場合に、譲受人から譲渡人に対して当該固定資産税に相当する金額を支払った場合の課税関係はどうなるのでしょうか。 登記が遅れる場合としては次のようなことが考えられます。 (1)当事者間の手違いで遅れた場合 (2)土地の譲渡代金の相当部分を支払った段階で引渡しがあったものとして帳簿上計上するが、移転登記の日は代金の全部を支払ったときとしている場合(基通9-1-2《棚卸資産の引渡しの日の判定》) 【回答要旨】 不動産の引渡しが行われた後、所有権移転登記が行われないことを原因として所有権移転後の固定資産税が前所有者に課税された場合に、当事者で当該固定資産税相当額であることを明記して金銭を授受した場合には、当該固定資産税相当額は資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱います。 ただし、当事者間で名義借料等役務の提供の対価として授受した場合は、資産の譲渡等の対価として課税となります。 (注)不動産を年の中途で売買した場合に授受する未経過固定資産税相当額は、資産の譲渡の対価を構成するものであり、課税の対象となりますから留意してください。 |
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























