解説記事2017年02月20日 【SCOPE】 子会社に対する高額外注費に行為計算否認規定を適用(2017年2月20日号・№679)
受注単価を上回る外注単価に経済的合理性なし
子会社に対する高額外注費に行為計算否認規定を適用
請求人が計上した子会社に対する外注費をめぐり、行為計算否認規定により外注費の損金算入を否定した課税処分の適法性が問題となった裁決で国税不服審判所は平成28年6月6日、行為計算否認規定(法法132①)を用いた課税処分を適法とする裁決を下した(広裁(法)平27第17号)。審判所は、請求人がA社から受注した単価(3,750円)を上回る単価(5,250円又は7,000円)で子会社に外注した点について、請求人が子会社外注単価を増額することに合理的な理由が認められないなどと指摘。増額による請求人の法人税負担の減少は「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合に該当すると判断した。
子会社の繰越欠損金を利用した法人税負担の圧縮を顧問税理士が助言
インターネットサーバーの運営・提供及びコンサルティングなどを事業とする請求人(同族会社である)とソフトウェアの企画・開発などを事業とする請求人の子会社が関与していた取引は次のようなものだ(図参照)。
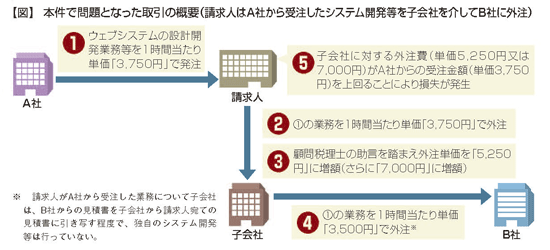
請求人は、システムエンジニア1人につき1時間当たり単価3,750円に作業時間を乗じて計算した請負金額でA社からウェブシステムの設計開発業務等(以下「本件業務」)を受注。請求人は、この業務を子会社を経由してB社に外注した。このとき請求人から子会社への外注単価は3,750円(請求人がA社から受注した単価と同額)で、子会社からB社に対する外注単価は3,500円であった。
しかし、請求人は、子会社外注単価を増額することにより子会社の繰越欠損金を利用して請求人の税負担を圧縮できるという顧問税理士の助言を受け、子会社外注単価を5,250円、7,000円と順次増額した(なお子会社は本件業務について独自のシステム開発等を行っていない)。これにより請求人には、請求人におけるA社からの受注金額(単価3,750円)と子会社に対する外注金額(単価5,250円又は7,000円)との差額に相当する損失(外注費が売上高を上回ることにより生じる損失)が発生。その損失は、平成24年分は約243万円、平成25年分は約462万円、平成26年分は約498万円に及んでいた。
これに対し原処分庁は、請求人が計上した子会社に対する外注費が不当に高額であると判断し、行為計算否認規定(法法132①)により外注費の損金算入を否認した。これを不服とした請求人は、国税不服審判所に対して課税処分の取り消しを求めた。
国税不服審判所はまず、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法法132①)か否かは専ら経済的、実質的見地においてその行為又は計算が純粋経済人の行為として不合理・不自然なものと認められるか否かという客観的・合理的基準に従って判断すべきと解釈。その行為又は計算が純粋経済人として不自然・不合理なもの、すなわち、経済的合理性を欠く場合には独立当事者間の通常の取引と異なっている場合を含むものと解するのが相当であるとした。
そして本件について審判所は、子会社外注単価は一般的な取引の相場とかけ離れて高額であるなどと不自然かつ不合理であり、請求人の外注先としての実質的な役割が小さいことなどから請求人が子会社外注単価をA社からの受注単価を超えて増額する合理的な理由は認められないと指摘。また、子会社外注単価の増額は子会社のもつ繰越欠損金を利用して請求人の税負担を圧縮する意図の下に行われたもので、独立当事者間の通常の取引であるとは想定し難く、経済的合理性に欠けると指摘した。
これらの点などを踏まえ審判所は、増額により生じた損失が損金算入されたことによる法人税負担の減少は、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法法132①)と評価することができるとしたうえで、行為計算否認規定により外注費の増額分の損金算入を否定した課税処分は適法であると判断した。
子会社に対する高額外注費に行為計算否認規定を適用
請求人が計上した子会社に対する外注費をめぐり、行為計算否認規定により外注費の損金算入を否定した課税処分の適法性が問題となった裁決で国税不服審判所は平成28年6月6日、行為計算否認規定(法法132①)を用いた課税処分を適法とする裁決を下した(広裁(法)平27第17号)。審判所は、請求人がA社から受注した単価(3,750円)を上回る単価(5,250円又は7,000円)で子会社に外注した点について、請求人が子会社外注単価を増額することに合理的な理由が認められないなどと指摘。増額による請求人の法人税負担の減少は「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合に該当すると判断した。
子会社の繰越欠損金を利用した法人税負担の圧縮を顧問税理士が助言
インターネットサーバーの運営・提供及びコンサルティングなどを事業とする請求人(同族会社である)とソフトウェアの企画・開発などを事業とする請求人の子会社が関与していた取引は次のようなものだ(図参照)。
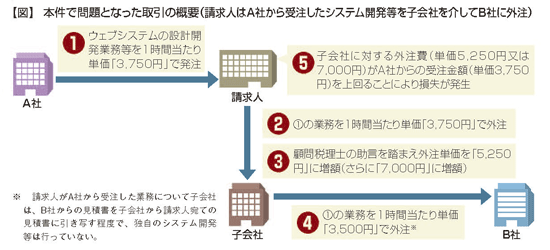
請求人は、システムエンジニア1人につき1時間当たり単価3,750円に作業時間を乗じて計算した請負金額でA社からウェブシステムの設計開発業務等(以下「本件業務」)を受注。請求人は、この業務を子会社を経由してB社に外注した。このとき請求人から子会社への外注単価は3,750円(請求人がA社から受注した単価と同額)で、子会社からB社に対する外注単価は3,500円であった。
しかし、請求人は、子会社外注単価を増額することにより子会社の繰越欠損金を利用して請求人の税負担を圧縮できるという顧問税理士の助言を受け、子会社外注単価を5,250円、7,000円と順次増額した(なお子会社は本件業務について独自のシステム開発等を行っていない)。これにより請求人には、請求人におけるA社からの受注金額(単価3,750円)と子会社に対する外注金額(単価5,250円又は7,000円)との差額に相当する損失(外注費が売上高を上回ることにより生じる損失)が発生。その損失は、平成24年分は約243万円、平成25年分は約462万円、平成26年分は約498万円に及んでいた。
これに対し原処分庁は、請求人が計上した子会社に対する外注費が不当に高額であると判断し、行為計算否認規定(法法132①)により外注費の損金算入を否認した。これを不服とした請求人は、国税不服審判所に対して課税処分の取り消しを求めた。
国税不服審判所はまず、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法法132①)か否かは専ら経済的、実質的見地においてその行為又は計算が純粋経済人の行為として不合理・不自然なものと認められるか否かという客観的・合理的基準に従って判断すべきと解釈。その行為又は計算が純粋経済人として不自然・不合理なもの、すなわち、経済的合理性を欠く場合には独立当事者間の通常の取引と異なっている場合を含むものと解するのが相当であるとした。
そして本件について審判所は、子会社外注単価は一般的な取引の相場とかけ離れて高額であるなどと不自然かつ不合理であり、請求人の外注先としての実質的な役割が小さいことなどから請求人が子会社外注単価をA社からの受注単価を超えて増額する合理的な理由は認められないと指摘。また、子会社外注単価の増額は子会社のもつ繰越欠損金を利用して請求人の税負担を圧縮する意図の下に行われたもので、独立当事者間の通常の取引であるとは想定し難く、経済的合理性に欠けると指摘した。
これらの点などを踏まえ審判所は、増額により生じた損失が損金算入されたことによる法人税負担の減少は、「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法法132①)と評価することができるとしたうえで、行為計算否認規定により外注費の増額分の損金算入を否定した課税処分は適法であると判断した。
| 審判所、子会社外注単価は取引相場に比べて非常に高額で不自然 |
| 本件で請求人は、子会社は繰越欠損金を抱えている関係会社であることから子会社への外注単価が業界における一般的な取引価格を逸脱するものでない限り、グループ全体で利益・節税を考えて取引を行うことは経済人として自然であると指摘。法人税の負担を不当に減少させているか否かの判断はグループ全体での利益等を考慮すべきである旨を主張していた。これに対し審判所は、子会社への外注単価(5,250円又は7,000円)は周辺地区におけるシステム関連業務の一般的な時間単価の相場(3,125円から3,750円程度)に比べて非常に高額で相場とかけ離れているため「業界における一般的な取引価格」とはいえないと指摘。また、グループ全体での利益等を考慮すべきとの請求人の主張に法令上の根拠がないなどと指摘したうえで、請求人の主張をすべて斥けている。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























