解説記事2017年07月31日 【最新判決研究】 財産評価基本通達に定める「私道」の該非と評価額(2017年7月31日号・№701)
最新判決研究
財産評価基本通達に定める「私道」の該非と評価額
最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決(平成28年(行ヒ)第169号)
東京高裁平成28年1月13日判決(平成27年(行コ)第286号)
東京地裁平成27年7月16日判決(平成25年(行ウ)第373号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)Xら5名(原告、控訴人、上告人、以下「Xら」という。)は、平成20年3月19日、被相続人甲の死亡により、同人の財産を共同相続した(以下「本件相続」という。)。その相続財産の中には、次の財産が含まれていた。
① 神奈川県S市所在の2件合計1394㎡の宅地(以下「本件S地」という。)
② 神奈川県D市所在の4件計3860㎡の宅地(以下「本件D地」という。)
③ 本件S地上の共同住宅3棟(以下「本件S共同住宅」という。)
④ 本件D地上の共同住宅8棟(以下「本件D共同住宅」という。)
Xらは、平成20年5月25日、本件相続に係る遺産分割協議をし、Xらの1人X1が、本件S地、本件D地、本件S共同住宅及び本件D共同住宅(各住宅については以下「本件各共同宅地」という。)を取得した。
本件S地には、舗装された幅員2mの歩道状空地(以下「本件S歩道」という。)が存在し、同歩道は、甲が平成14年11月にS市長から都市計画法所定の開発行為の許可を受けて本件S共同住宅を建築した際に、市の指導によって、市道に接する形で整備された。
本件D地には、舗装された幅員2mの歩道状空地(以下「本件D歩道」という。)が存在し、同歩道は、甲が平成14年11月及び同15年6月にD市長から都市計画法所定の開発行為を受けて本件D共同住宅を建築した際に市の指導によって、市道に接する形で整備された。
本件S歩道及び本件D歩道(以下「本件各歩道」という。)とこれらに接する各市道との間には、若干の段差があるものの、特に出入りを遮るものはなく、外観上、車道脇の歩道として本件各共同住宅の居住者等以外の第三者も利用することが可能な状態になっている。なお、本件各歩道は、いずれも遅くとも平成25年4月以降、近隣の小学校の通学路として指定され、児童らが通学に利用している。
(2)Xらは、平成21年1月、所轄税務署長に対し、本件各歩道につき、不特定多数の者の通行の用に供されている私道供用宅地であるとしてその価額を評価せずに、本件相続に係る相続税申告書を提出した。その後、Xらは、本件S歩道につき、その価額を自用地の価額の100分の30に相当する価額とする旨の修正申告書を提出した。これに対し、所轄税務署長は、平成23年7月8日付けで、本件各私道につき、いずれも私道供用宅地に該当せず、本件各共同住宅の敷地(貸家建付地)として評価すべきであるとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をした。Xらは、本件各処分を不服として、国(被告、被控訴人、被上告人)に対し、その取消しを求めて、本訴を提起した。
なお、本件S歩道の状況は、図のとおりである(本件D歩道は、8棟にまたがって歩道が付設されている。)。本件D歩道についても、貸家が8棟繋がっている状態以外は同様である。
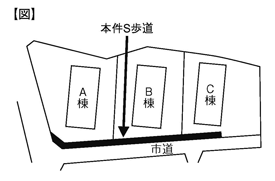
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件各歩道が財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)24に定める「私道の用に供されている宅地」(私道供用宅地)に該当するか否かとその評価額である。
2 Xらの主張 (1)私道供用宅地に該当するか否かは、①通り抜け道路であれば現に不特定多数の者の通行の用に供されているか否か、②行き止まり道路であれば現に専ら特定の者の通行の用に供されているか否かによって判断すべきであり、通り抜け道路に当たるか否かについては、①道路としての用法に応じて利用されることにより、第三者が通行することを容認しなければならないか否か、②道路内建築の制限により、通行を妨害する行為が禁止されるか否か、③私道の廃止又は変更が制限されるか否か、④私道の減価を100パーセントとみるか否かを基準として判断すべきであるところ、本件各歩道については、近隣の小学校の児童の通学のための通行の用等に供されており、私道供用宅地に該当するというべきである。
(2)本件各歩道は、都市計画法29条の開発許可を受けるための条件として、同法32条の協議において私道として整備することを義務付けられ、開発許可の内容に従って整備されたものである。許可権者であるS市及びD市は、当時、開発指導要綱を作成して、これに従うことを求めており、本件各歩道を設けない限り開発許可を受けることができなかった。
(3)公共の用に供する道路として利用されている土地は、地方税法348条2項5号及び同法702条の規定により、固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が非課税とされるところ、本件各歩道は、いずれも公共の用に供する道路であると認定されたことから非課税とされている。
3 国の主張 (1)私道供用宅地に当たるか否かは、その私道が私有物として使用・収益する権能が制約されることにより、私道の宅地としての価額が著しく低下しているか否かによって判断するのが相当であるところ、①本件各歩道は本件各土地と併せて建築基準法上の接道義務(同法43条1項)を満たしており、本件各歩道の歩道としての状況は、同法上の接道義務の判断に何ら影響しないこと、②本件各歩道は、建築基準法上の道路内の建築制限(同法44条1項)及び③建築基準法上の私道の変更又は廃止の制限(同法45条1項)のほか、④道路法4条の道路上の私権の行使の制限も受けない土地であること、さらに、⑤都市計画法による開発行為に該当しない戸建住宅を建築する際には、本件各歩道を戸建住宅の敷地の一部として使用することも可能であり、加えて、⑥本件各共同住宅を建築した際には、建築基準法上の建ぺい率及び容積率(以下、併せて「建ぺい率等」という。)の算定の基となり、宅地の一部として扱われていることが認められるから、本件各歩道の制約の程度はごく限られていたものであるということができ、本件各歩道の価額が著しく低下しているものとは認められない。
(2)本件各土地の開発行為に係るS市及びD市による指導に関するXらの主張については、それらの指導の事実上の拘束力とはいかなるものか明らかではないし、本件各歩道は、建築基準法や道路法上の制限を受けておらず、また、開発許可後に他の用途に転用することについても、法令等による規制を受けていないのであるから、仮に、開発行為の当時、許可権者の指導にXらの主張するような事実上の拘束力があったとしても、かかる事情は、その後に生じた本件相続における相続財産に何ら影響を及ぼすものではない。
(3)Xらは、証拠として提出した各調査報告書によれば、本件各歩道はいずれも私道供用宅地として評価すべきであり、その減価は100パーセントである旨主張するが、上記各調査報告書は、本件各土地の開発当時施行されていなかった条例によって歩道の設置が義務付けられていたとする点において誤っていることなどから、各調査報告書に基づいて本件各歩道を私道供用宅地と評価すべきとはいえない。
また、本件S共同住宅及び本件S土地は、本件相続の開始後である平成21年12月28日に、X1から同人が代表取締役を務めるP社に譲渡されているところ、本件S歩道は、本件S共同住宅の敷地と一体として、同一の単価で評価されて、売却しているのであって、この点からも、本件S歩道を私道供用宅地と評価すべきであるとはいえない。
(4)Xらは、本件各歩道は、近隣住民のみならず、通学路としても利用されるなどしており、私道としての負担を強いられている旨主張するが、通学路について法令上定義されているのは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令4条2号以外にはないところ、本件各歩道はいずれも道路法上の道路とされていないことから、同施行令に定める通学路には当たらない。
(5)固定資産税等の非課税規定は、政策的目的から公共性が高い一定の財産を非課税とするものと解されるところ、評価通達24が適用される私道供用宅地に該当するか否かは、相続等により取得した財産価値に着目し、私道の宅地としての価額が著しく低下しているか否かにより判断するのが相当であるから、固定資産税等が非課税とされているからといって、評価通達24に定める私道供用宅地に該当するとはいえない。
三、一審判決要旨
請求棄却。
(1)本件の認定事実を前提として、本件各歩道が評価通達24の適用される私道供用宅地に該当するか否かを検討する。
そこで検討すると、私人が所有する道という広い意味で私道を捉えた場合、その中には、例えば、複数の建物敷地のいわゆる接道義務を満たすために当該各敷地所有者が共有する道であって建築基準法上の道路とされているものもあるであろうし、他方において、宅地の所有者が事実上その宅地の一部を通路として一般の通行の用に供しているものもあり得るところである。このうち、前者は、これに隣接する各敷地の所有者が、それぞれの接道義務を果たすために不可欠のものであるから、個別の敷地所有者の意思により、これを私道以外の用途に用いることには困難を伴うといえるし、また、道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって、その利用には制約があるものである。これに対し、後者は宅地の所有者が宅地の使用方法の選択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず、特段の事情のない限り、通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に委ねられているのであって、その利用に制約があるわけではない。
このような違いを宅地の価額の評価という観点からみた場合、前者については、上記のような制約がある以上、評価通達24が定めるように、所定の方法により計算された価額の30%で評価することとし、それが不特定多数の者の通行の用に供されているためにより大きい制約を受ける状況にあるといえるときにはその価額を評価しないとすることには、合理性があるものということができる。しかしながら、後者については、そもそもかかる制約がなく、特段の事情がない限り、私道を廃止して通常の宅地として利用することも所有者の意思によって可能である以上、これを通常の宅地と同様に評価するのがむしろ合理的というべきである。
(2)そこで、本件各歩道状空地が評価通達24の適用される私道共用宅地に該当するか否かを検討する。まず、本件各土地は、いずれも公道に接しているのであり、本件各歩道は、接道義務を果たすために設けられたものではない。したがって、本件各歩道の利用について、私道としての建築基準法上の利用制限が課されることになるわけではない。
本件各歩道が設けられたのは、S市やD市から、要綱等に基づき歩道部分を設けるように指導されたことによるものであるが、かかる指導がされることとなったのは、甲が、本件各土地上に、それぞれ共同住宅を建築するべく、都市計画法に基づく開発行為を行うこととしたためである。すなわち、本件各土地の利用方法として様々な選択肢があり得る中で、甲は、上記開発行為をすることを選択したのであって、その結果、上記指導を受けて、本件各歩道を設けることとなったものであるところ、かかる指導によって本件各歩道を設けることを事実上やむなくされたことをもって仮に制約と評価する余地があるとしても、かかる制約は、それを受け入れつつ開発行為を行うのが本件各土地の利用形態として適切であると考えた上での選択の結果生じたものということができる。しかも、本件各土地は、甲が所有し、Xらが相続したものであり、その利用形態は同人らが決定し得るものであって、同人らが、その意思により、本件各土地の利用形態を変更すれば、上記のような制約を受けることもなくなるのであるから、通常の宅地と同様に利用することができる潜在的可能性とそれに相当する価値を有しているといえる。また、制約の態様についてみると、本件各土地においては、歩道としての供用が求められているにすぎないし、しかも、本件各歩道も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているのであって、つまるところ、同部分は、所定の容積率の建物を建築し得るための建物敷地としての役割をも果たしており、それに相当する価値を現に有していると考えられるところである。
以上のような事情に照らすと、評価通達24が想定している私道に課された制約の程度と、本件各歩道に課されている上記の制約の程度は、大きく異なるものといわざるを得ないのであり、本件各歩道をもって、評価通達24の適用される私道供用宅地に該当するということはできない。
(3)Xらは、本件各歩道は、近隣の小学校の通学路として指定されており、私道としての負担を強いられているなどと主張する。しかし、証拠によれば、上記通学路としての指定は、本件S歩道についてはS市立P小学校により、本件D歩道についてはD市立O小学校ないしD市教育委員会によってされるものであるが、いずれについても、通学路の指定に当該歩道状空地ないし私道の廃止又は変更を規制する権限はなく、仮に通学路として使用することができなくなった場合には、隣接する道路や迂回できる道路などを新たに通学路として指定することになるというものであることが認められ、評価通達24が想定するほどの制約が課せられているとはいえない。
さらに、公共の用に供する道路について固定資産税を非課税とする旨を定める地方税法348条2項の規定は、同項各号において非課税とされている他の固定資産と同様に、主として、固定資産の性格及び用途に鑑み、固定資産税を非課税とすべきものを定めたものであると解されるところであり、同項によって固定資産税が非課税とされたとしても、必ずしもその財産的価値がないことを意味しないというべきであって、相続税についても同様に取り扱うべきであるとはいえない。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却(請求棄却)
(1)当裁判所も、Xらの請求は、いずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の理由を引用する。
(2)Xらは、将来の本件各歩道の利用形態の変更をも考慮することは誤りである旨主張する。しかしながら、上記潜在的可能性は、利用形態の変更が制限されていない本件各歩道の現況(現時点における客観的可能性)にほかならず、Xらの主観的事情によって左右されるものではないから、Xらの主張は採用できない。
(3)Xらは、本件各歩道を除いても建物を建てることができることを理由として、本件各歩道が上記価値を有することを否定する主張をするが、現に上記のとおりの算定がされている以上、本件各歩道が建物敷地としての役割を果たしており、それに相応する価値を現に有していることは明らかであるから、Xらの主張は採用できない。
五、上告審判決要旨
原判決破棄。
原審差戻し。
(1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているところ、ここにいう時価とは、課税時期である被相続人の死亡時における当該財産の客観的交換価値をいうものと解される。そして、私道の用に供されている宅地については、それが第三者の通行の用に供され、所有者が自己の意思によって自由に使用、収益又は処分をすることに制約が存在することにより、その客観的交換価値が低下する場合に、そのような制約のない宅地と比較して、相続税に係る財産の評価において減額されるべきものということができる。
そうすると、相続税に係る財産の評価において、私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を、建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく、そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。
(2)これを本件についてみると、本件各歩道は、車道に沿って幅員2mの歩道としてインターロッキング舗装が施されたもので、いずれも相応の面積がある上に、本件各共同住宅の居住者以外の第三者による自由な通行の用に供されていることがうかがわれる。また、本件各歩道は、いずれも本件各共同住宅を建築する際、都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、市の指導要綱等を踏まえた行政指導によって私道の用に供されるに至ったものであり、本件各共同住宅が存在する限りにおいて、Xらが道路以外の用途へ転用することが容易であるとは認め難い。そして、これらの事情に照らせば、本件各共同住宅の建築のための開発行為が甲による選択の結果であるとしても、このことから直ちに本件各歩道について減額して評価をする必要がないということはできない。
(3)以上によれば、本件各歩道の相続税に係る財産の評価につき、建築基準法等の法令による制約がある土地でないことや、所有者が市の指導を受け入れつつ開発行為を行うことが適切であると考えて選択した結果として設置された私道であることのみを理由として、前記(1)において説示した点について具体的に検討することなく、減額をする必要がないとした原審の判断には、相続税法22条の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
(4)したがって、原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。
六、解説
はじめに
本件は、貸家3棟又は8棟の敷地(貸家建付地)と市道との間に挟まれた幅員2mの歩道状空地(舗装済み、本件各歩道)が、貸家建付地として評価すべきか、又は評価通達24に定める歩道として評価すべきかが争われた事案である。相続税法上、相続等によって取得した財産の価額は「時価」によることとされているので、本件各歩道のような歩道状態の宅地の「時価」が幾許であるかが争われた場合には、当該「時価」の多寡を評価すれば足りるはずである。しかしながら、課税の実務においては、相続等によって取得した財産の価額が一次的には評価通達に定める評価額(評価方法)によって算定されるため、当該財産の価額(時価)が争われるときには、まず、評価通達に定める評価方法の適用の可否が問題となる。
本件においても、本件各歩道の相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものであるので、当該「時価」が後述するような客観的交換価値を表わすというのであれば、国が主張するような本件各歩道についての処分可能価額を重視すべきであるとも考えられるのであるが、最高裁判所は、本件各歩道が評価通達24に定める「歩道」との類似性を強調しているようである。ともあれ、本件においては、単に、本件各歩道が評価通達24に定める「歩道」の該非のみならず、評価通達が本条の「時価」の解釈に影響を及ぼしている点にも着目すべきであると考えられる。
1 相続税法上の「時価」と評価通達 (1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。この「時価」の意義については、評価通達では、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」(同通達1(2))をいうと定めている。この意義については、一般に、客観的交換価値又は客観的交換価額を意味するものとして、学説、判例において広く支持されている(注1)。また、所得税法及び法人税法においても、資産の無償又は低額取引において当該資産の「価額」が問題となるところ(所法36②、59①、法法22②、37⑦等)、当該「価額」の解釈(評価)においても共通している(注2)。
また、評価通達は、上記の「財産の現況」等に関し、「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」と定めている。このように、評価通達は、基本的には、各財産の取得の時において、かつ、当該財産がおかれた個別の状況に応じて、当該財産の客観的交換価値を把握すべきものとしている。
(2)しかしながら、相続、贈与等によって財産を取得することにより発生する全ての課税原因において、当該財産の客観的交換価値を個々に算定(把握)するということは、技術的に極めて困難であり、かつ、当該価値判断を個々の担当者の主観に委ねることとなるので、それぞれの財産の評価額が不均一となり、ひいては納税者間に課税の不公平をもたらすことになる。
そのため、課税の実務では、国税庁長官が発出する評価通達の定めによって、各財産の価額(時価)が評価され、当該評価額が相続税及び贈与税の課税の基準となっている。すなわち、前述の評価通達1(2)は、「時価とは、……自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定めている。要するに、評価通達は、「時価」が客観的交換価値を意味することを標榜しながらも、各財産の「時価」を同通達の定めによって統一的に評価することとしている(注3)。このように、相続等によって取得した財産の価額(時価)は、実務的には評価通達が定める評価方法によって画一的に評価されるのであるが、それらの評価方法の是非を論じる前に、評価通達という「通達」の法的性格等を明らかにしておく必要がある(注4)。
(3)まず、課税実務の規範となっている税務通達が存在する法的根拠は、国家行政組織法14条2項にある。同項は、「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。かくして、評価通達も、国税庁部内の行政命令であるので、国税庁職員に対しては、当該命令を遵守する義務がかせられている(国家公務員法98、82)が、法的には納税者がその通達の取扱いに拘束される謂れはないことになる。
しかしながら、評価通達のような税務通達は、実質的には、納税者を拘束すること(法解釈の規範)になる。すなわち、評価通達の国税庁職員に対する通達遵守義務は、納税者の法解釈を間接的に強制する(評価通達に従わない納税申告については、更正処分等を甘受せざるを得なくなる。)。また、評価通達は、路線価のような土地の価額(時価)については、公示価格水準の8掛としているので、通常の取引価額よりも路線価等を利用して申告をした方が有利であるし(有利性、安全性、謙抑性)、便利でもある(便宜性)。更に、近年、税理士に対する損害賠償請求事件が多発しているが、それらの判決では、税理士が税務通達の取扱いを無視して申告代理等を行い、納税者に損害を与えたときには、その税理士は専門家責任を果たしたことにはならない旨判示されている。
(4)更に、評価通達は、前述のように、各財産の評価額(評価方法)を画一的に定めているところ、宅地については、後述するように、路線価方式又は倍率方式によって一律に評価額が算定できるように定められている。しかし、このように画一的に評価される評価額は、標準的な宅地を想定し、評価日もその年の1月1日に特定されているので、一種の標準価額(基準価額)という性質を有することになる。そのため、実際に相続等によって取得した宅地の価額(時価)を路線価等によって評価した場合に、当該評価額が当該宅地の価額(時価)に対し相当に乖離することもあり得る。
このような評価通達の定めによる評価額と当該財産の客観的交換価値の間に著しい乖離が生じた場合に、評価通達は、その取扱いの中で包括的な補完措置を設けている。すなわち、評価通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。
この規定は、前述したように、通達における標準価額による評価(評価基準制度)の弊害を防止するものであるが、側面では、納税者側の予測可能性と法的安定性を害するということにもなるので、同族会社等の行為計算の否認規定(所法157、法法132、相法64等)等と同視されることがある(注5)。
2 評価通達における宅地・私道の評価 (1)評価通達における宅地のような土地の価額の評価は、前述した標準価額による評価という評価基準制度の典型である。すなわち、評価通達は、土地の評価上の区分について、宅地など10種類に区分し(評基通7)、土地の価額は、それぞれの土地の種類に応じて、評価単位ごとに評価することとしている(評基通7-2)。そして、宅地については、「一画地の宅地(利用の単位となっている一区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。」(評基通7-2(1))ことになる。ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「一画地の宅地」とする(評基通7-2(1)(注))。これは、遺産分割等において「一画地」を無道路地等にして、評価額を恣意的に著しく引き下げること等に対処したことにほかならない(注6)。
次に、宅地の評価は、①市街地的形態を形成する地域にある宅地については、路線価方式により、②①以外の宅地については、倍率方式による(評基通11)。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基として、評価通達15項以下に定める奥行価格補正等の画地調整を行うことにより計算した金額によって評価する方式である(評基通13)。また、倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額による(評基通21)。
(2)上記の路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。)ごとに設定する(評基通14)。また、不特定多数の者の通行の用に供されていない道路に面している宅地については、当該道路について、納税義務者の申出等に基づき路線価(特定路線価)を設定することができる(評基通14-3)。
この路線に付される価格すなわち路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法の規定により公示された標準地の価額)、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定した価額)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価額である(評基通14)。
① その路線のほぼ中央部にあること。
② その一連の宅地に共通している地勢にあること。
③ その路線だけに接していること。
④ その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有する矩形又は正方形のものであること。
以上のように、路線価は、売買実例価額等の多くの判定要素を総合して算定されるのであるが、その中で、公示価格が最も重要な判定要素となっている。すなわち、平成4年以降の路線価は、公示価格水準の80%相当額とされ(注7)、その評価日も、平成3年分までの前年7月1日から、公示価格の評価日に合わせるために、当年の1月1日とされた。
このような路線価による宅地の評価は、一定の路線において標準的な間口距離等を有する標準的な宅地についての価額設定であるから、当該標準的な宅地に該当しない宅地であれば、当該路線価によって算定された価額に加減算するための調整率が適用される。加算されるものには、側方路線、二方路線、三方又は四方路線の影響加算がある(評基通16~18)。減算されるものには、奥行価格補正(評基通15)、不整形地補正(同20)、無道路地補正(同20-2)、間口挟小補正(同20-3)等がある。そのほか、大規模工場用地(評基通22-2、22-3)、広大地(同24-4)等には、特別の評価方法が採用されている。
(3)次に、本件の私道のように、当該宅地を所有権によって支配しているものの、その支配権等が何らかの形で制限されているものについては、その支配制限に対応した評価減が行われる。まず、評価通達24は、「私道の用に供されている宅地の価額は、11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」と定めている。
このように、私道の価額は、その私道の形態に応じて、30%評価が行われるものと、零%評価が行われるものに区分される。この点について、「私道には、公共の用に供するもの、つまり、不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通り抜け道路と、そうでないもの、つまり、袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供するいわゆる行き止まり道路がある。」(注8)ことに対応したもので、前者が零評価となり、後者が30%評価に区分されている。
そして、この30%評価について、国税庁の担当者は、次のように説明している(注9)。
「これに対し、後者は、現在その使用収益にある程度の制約はあるが、私有物として、所有者の意思に基づく処分の可能性は残されている。特に、そのような私道に沿接する土地が同一人の所有に帰属することになると、現在の私道は、容易にその敷地内に包含されて、私道ではなくなってしまうことになる。このようなことから、もっぱら特定の者の通行の用に供される私道の価額は、路線価方式又は倍率方式のいずれかによって評価した価額の30%相当額によって評価することにしている。」
なお、袋小路の私道の形態を有していても、それが1人が所有している宅地と路線に接しているものについては、私道として評価されることはない(注10)。
次に、零評価される私道には、次のようなものが挙げられている(注11)。
① 公道と公道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け私道
② 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
③ 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道
(4)そのほか、私道と同じように、その宅地の使用等が制限されているため、相応の評価減が行われる場合に、次のようなものがある。例えば、建築基準法42条2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地(セットバックを必要とする宅地)の価額は、通常の評価額から7割を控除することとしている(評基通24-6)。このように、セットバックを必要とする宅地の価額が、私道と同様に3割評価する理由については、次のように説明されている(注12)。
「セットバックを必要とする宅地は、現在の利用には特に支障がない場合であっても、その宅地の価額は、セットバックを要しない宅地の価額に比較して減少することになり、セットバックを必要とする部分については、私道と比較すると、現にセットバックをしていない限り宅地として利用されているわけであるから、少なくとも私道の価値率(評価基本通達では30%)を下回ることはないと考えられる。」
また、貸宅地については、その価額は、他人の借地権の目的となっている(自己が使用収益できない)が故に、自用地の価額から当該借地権の価額を控除して評価される(評基通25)。この場合、借地権が存在しない場合にも、最低20%は評価減されることになっている(同上)。
3 本件各私道の評価 (1)本件は、神奈川県のS市及びD市に所在する貸家建付地沿いに付設された私道状態の各宅地(本件各歩道)の価額が幾許であるかが争われたのであるが、具体的には、本件各歩道が評価通達24に定める歩道として、70%の評価減が認められるか否かが争われた事案である。このような評価上の区分が争われるのは、「私道」と一口に言っても、その使用形態、処分形態等がそれぞれ異なるからにほかならないが、評価通達においても、それぞれの使用形態等に応じて、自用地の価額に比し、30%評価するものと零評価するものに区分している。本件各私道についても、前記通達にいう「私道」そのものに該当するか否かが争われた。
この点につき、Xらは、本件各私道が、いずれも、本件各共同住宅の建設に当たり、都市計画法上の開発許可を受けるための条件として、各市との協議において私道として整備することが義務付けられたものであり、現に、近隣の学童の通学の用等に供されているところであり、そのため、固定資産税、都市計画税等も非課税とされている旨等を主張した。
これに対し、国は、評価減の対象となる「私道」に当たるか否かは、その私道が私有物として使用・収益する権能が制約されることにより、宅地としての価額が著しく低下しているか否かによって判断すべきところ、本件各私道については、建築基準法上建築制限等の制約は全くなく、現に、本件相続開始後、X1が本件S地を関係会社を譲渡するに当たって本件S歩道部分も他の宅地と同一単価で譲渡されているところであり、固定資産税等が非課税とされているのは政策的目的から行われているものであって本件S歩道の宅地としての価額に影響を及ぼすものではない旨等を主張した。
結局は、両者の主張は、本件各歩道の価額の評価につき、Xらは、本件各歩道が現に他人によって使用収益されているという使用状況を強調しているのに対し、国は、本件各歩道の宅地としての価額につき、それが処分された時の価額によって評価すべきことを強調していることに差異がある。この場合、国の主張については、前記2の(4)で述べたセットバックを必要とする宅地の評価と逆のパターンとなることが注目される。
(2)このような両者の主張の差異に対し、本件各判決は、次のように判示している。まず、一審判決は、前述のように、評価通達24にいう「私道」がいかなるものかが明らかにされていないところ、いわゆる私道には、複数の建物敷地のいわゆる接道義務を満たすために当該各敷地所有者が共有する道であって建築基準法上の道路とされるものと、宅地の所有者が事実上その宅地の一部を通路として一般の通行の用に供しているもの、とに区分でき、「後者については、そもそもかかる制約がなく、特段の事情がない限り、私道を廃止して通常の宅地として利用することも所有者の意思によって可能である以上、これを通常の宅地と同様に評価するのがむしろ合理的というべきである。」と判示し、本件各歩道は上記歩道に該当すると判断した。
また、控訴審判決も、一審判決の理由を引用しつつ、「時価とは「財産の現況に応じ」て判断すべきであるから将来の利用形態の変更を考慮して判断するのは違法である」旨のXらの主張に対し、当該潜在的可能性は利用形態の変更が制限されていない本件各歩道の現況(現時点における客観的可能性)にほかならない旨判示し、上記Xらの主張を排斥している。
これらの下級審の各判決に対し、上告審判決は、前述のように、「宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある」と判示し、本件各歩道が、本件各共同住宅を建築する際、行政指導によって私道の用に供されている現況が当該歩道の価額の減額にどのように影響すべきかを考慮する必要があるとして、原審に差し戻した。
(3)以上のように、本件においては、前記(1)で述べたような形状を有する本件各歩道の価額の評価につき、当該歩道が都市計画法上の規定に基づき市の指導によって歩道の用に供されている現況を重視すべきか、あるいは、建築基準法の規定において何ら使用(処分)制限が課せられていない現況を重視すべきか、が問題となった。
この点につき、一審判決及び控訴審判決は、後者を重視して本件各歩道の価額を他の貸家建付地並に評価できるとした本件各処分を適法とし、上告審判決は、前者を重視して原判決を破棄し、原審へ差し戻した。そのため、本件は、再び東京高等裁判所で審理されることになるが、恐らく、同裁判所において、本件各歩道の価額の評価において何らかの減額判断(評価通達24の適用等)が行われるものと見込まれた。その後、差戻し審において、国側が、本件各処分を全部取り消す旨を表示したようで、本事件としては解決することとなった(注13)。
4 本件各判決の意義と問題点 以上のように、本件は、貸家3棟又は8棟の敷地(貸家建付地)と市道との間に挟まれた幅員2mの本件各歩道の価額を、当該貸家建付地の一部として評価すべきか、あるいは、評価通達24に定める歩道として70%の評価減が行われるべきか、が争われた事案である。
一審判決及び控訴審判決は、本件各歩道が建築基準法上の使用・処分に制限がないことに着目して貸家建付地の一部として評価した本件各処分を適法とし、上告審判決は、都市計画法上の行政指導に基づき現に私道として使用されている現況を重視すべきとして、原判決を破棄・差し戻した。
実務においては、何が私道に該当するか、私道に該当する場合に評価通達24に定める評価減(30%評価が零評価か)の適用がまま問題となることがあるが、それが訴訟まで争われることは稀である。よって、本件各判決は、歩道に関する訴訟事例として意義がある。また、「私道」と称されるものには、種々の形態、法律関係を有するものがあるが、それぞれの形態等に応じて、当該歩道の価額をどのように評価すべきかは、評価論的にも問題のあるところであるので、一層の検討を要する課題でもある。
(注1)金子宏「租税法 第22版」(弘文堂 平成29年)662頁、東京地裁昭和53年4月17日判決(税資101号115頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等参照。
(注2)名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、東京高裁昭和59年11月14日判決(同140号232頁)等参照。
(注3)品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)120頁等参照。
(注4)前出(注3)48頁以下、品川芳宣編著「資産・事業承継対策の現状と課題」(大蔵財務協会 平成28年)534頁以下参照。
(注5)評価通達6項をめぐる種々の問題については、前出(注3)122頁、前出(注4)「資産・事業承継対策の現状と課題」540頁等参照。
(注6)谷口裕之「財産評価基本通達逐条解説 平成25年版」(大蔵財務協会 平成25年)38頁参照。
(注7)従前は、公示価格水準の概ね70%とされていたが、現実には、それよりも相当低額で評価されていた。そして、平成4年以降80%相当額としたのは、平成4年度税制改正大綱による公的土地評価の均衡・適正化の一還として行われた。そのため、80%評価の根拠は、評価通達には明記されていない。
(注8)前出(注6)126頁。
(注9)前出(注6)127頁。
(注10)前出(注6)128頁。
(注11)前出(注6)127頁。
(注12)前出(注6)161頁。
(注13)週刊税務通信 平成29年6月19日号4頁等参照。
財産評価基本通達に定める「私道」の該非と評価額
最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決(平成28年(行ヒ)第169号)
東京高裁平成28年1月13日判決(平成27年(行コ)第286号)
東京地裁平成27年7月16日判決(平成25年(行ウ)第373号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)Xら5名(原告、控訴人、上告人、以下「Xら」という。)は、平成20年3月19日、被相続人甲の死亡により、同人の財産を共同相続した(以下「本件相続」という。)。その相続財産の中には、次の財産が含まれていた。
① 神奈川県S市所在の2件合計1394㎡の宅地(以下「本件S地」という。)
② 神奈川県D市所在の4件計3860㎡の宅地(以下「本件D地」という。)
③ 本件S地上の共同住宅3棟(以下「本件S共同住宅」という。)
④ 本件D地上の共同住宅8棟(以下「本件D共同住宅」という。)
Xらは、平成20年5月25日、本件相続に係る遺産分割協議をし、Xらの1人X1が、本件S地、本件D地、本件S共同住宅及び本件D共同住宅(各住宅については以下「本件各共同宅地」という。)を取得した。
本件S地には、舗装された幅員2mの歩道状空地(以下「本件S歩道」という。)が存在し、同歩道は、甲が平成14年11月にS市長から都市計画法所定の開発行為の許可を受けて本件S共同住宅を建築した際に、市の指導によって、市道に接する形で整備された。
本件D地には、舗装された幅員2mの歩道状空地(以下「本件D歩道」という。)が存在し、同歩道は、甲が平成14年11月及び同15年6月にD市長から都市計画法所定の開発行為を受けて本件D共同住宅を建築した際に市の指導によって、市道に接する形で整備された。
本件S歩道及び本件D歩道(以下「本件各歩道」という。)とこれらに接する各市道との間には、若干の段差があるものの、特に出入りを遮るものはなく、外観上、車道脇の歩道として本件各共同住宅の居住者等以外の第三者も利用することが可能な状態になっている。なお、本件各歩道は、いずれも遅くとも平成25年4月以降、近隣の小学校の通学路として指定され、児童らが通学に利用している。
(2)Xらは、平成21年1月、所轄税務署長に対し、本件各歩道につき、不特定多数の者の通行の用に供されている私道供用宅地であるとしてその価額を評価せずに、本件相続に係る相続税申告書を提出した。その後、Xらは、本件S歩道につき、その価額を自用地の価額の100分の30に相当する価額とする旨の修正申告書を提出した。これに対し、所轄税務署長は、平成23年7月8日付けで、本件各私道につき、いずれも私道供用宅地に該当せず、本件各共同住宅の敷地(貸家建付地)として評価すべきであるとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をした。Xらは、本件各処分を不服として、国(被告、被控訴人、被上告人)に対し、その取消しを求めて、本訴を提起した。
なお、本件S歩道の状況は、図のとおりである(本件D歩道は、8棟にまたがって歩道が付設されている。)。本件D歩道についても、貸家が8棟繋がっている状態以外は同様である。
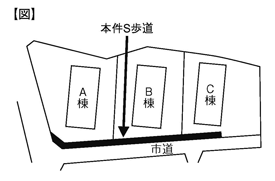
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件各歩道が財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)24に定める「私道の用に供されている宅地」(私道供用宅地)に該当するか否かとその評価額である。
2 Xらの主張 (1)私道供用宅地に該当するか否かは、①通り抜け道路であれば現に不特定多数の者の通行の用に供されているか否か、②行き止まり道路であれば現に専ら特定の者の通行の用に供されているか否かによって判断すべきであり、通り抜け道路に当たるか否かについては、①道路としての用法に応じて利用されることにより、第三者が通行することを容認しなければならないか否か、②道路内建築の制限により、通行を妨害する行為が禁止されるか否か、③私道の廃止又は変更が制限されるか否か、④私道の減価を100パーセントとみるか否かを基準として判断すべきであるところ、本件各歩道については、近隣の小学校の児童の通学のための通行の用等に供されており、私道供用宅地に該当するというべきである。
(2)本件各歩道は、都市計画法29条の開発許可を受けるための条件として、同法32条の協議において私道として整備することを義務付けられ、開発許可の内容に従って整備されたものである。許可権者であるS市及びD市は、当時、開発指導要綱を作成して、これに従うことを求めており、本件各歩道を設けない限り開発許可を受けることができなかった。
(3)公共の用に供する道路として利用されている土地は、地方税法348条2項5号及び同法702条の規定により、固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が非課税とされるところ、本件各歩道は、いずれも公共の用に供する道路であると認定されたことから非課税とされている。
3 国の主張 (1)私道供用宅地に当たるか否かは、その私道が私有物として使用・収益する権能が制約されることにより、私道の宅地としての価額が著しく低下しているか否かによって判断するのが相当であるところ、①本件各歩道は本件各土地と併せて建築基準法上の接道義務(同法43条1項)を満たしており、本件各歩道の歩道としての状況は、同法上の接道義務の判断に何ら影響しないこと、②本件各歩道は、建築基準法上の道路内の建築制限(同法44条1項)及び③建築基準法上の私道の変更又は廃止の制限(同法45条1項)のほか、④道路法4条の道路上の私権の行使の制限も受けない土地であること、さらに、⑤都市計画法による開発行為に該当しない戸建住宅を建築する際には、本件各歩道を戸建住宅の敷地の一部として使用することも可能であり、加えて、⑥本件各共同住宅を建築した際には、建築基準法上の建ぺい率及び容積率(以下、併せて「建ぺい率等」という。)の算定の基となり、宅地の一部として扱われていることが認められるから、本件各歩道の制約の程度はごく限られていたものであるということができ、本件各歩道の価額が著しく低下しているものとは認められない。
(2)本件各土地の開発行為に係るS市及びD市による指導に関するXらの主張については、それらの指導の事実上の拘束力とはいかなるものか明らかではないし、本件各歩道は、建築基準法や道路法上の制限を受けておらず、また、開発許可後に他の用途に転用することについても、法令等による規制を受けていないのであるから、仮に、開発行為の当時、許可権者の指導にXらの主張するような事実上の拘束力があったとしても、かかる事情は、その後に生じた本件相続における相続財産に何ら影響を及ぼすものではない。
(3)Xらは、証拠として提出した各調査報告書によれば、本件各歩道はいずれも私道供用宅地として評価すべきであり、その減価は100パーセントである旨主張するが、上記各調査報告書は、本件各土地の開発当時施行されていなかった条例によって歩道の設置が義務付けられていたとする点において誤っていることなどから、各調査報告書に基づいて本件各歩道を私道供用宅地と評価すべきとはいえない。
また、本件S共同住宅及び本件S土地は、本件相続の開始後である平成21年12月28日に、X1から同人が代表取締役を務めるP社に譲渡されているところ、本件S歩道は、本件S共同住宅の敷地と一体として、同一の単価で評価されて、売却しているのであって、この点からも、本件S歩道を私道供用宅地と評価すべきであるとはいえない。
(4)Xらは、本件各歩道は、近隣住民のみならず、通学路としても利用されるなどしており、私道としての負担を強いられている旨主張するが、通学路について法令上定義されているのは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令4条2号以外にはないところ、本件各歩道はいずれも道路法上の道路とされていないことから、同施行令に定める通学路には当たらない。
(5)固定資産税等の非課税規定は、政策的目的から公共性が高い一定の財産を非課税とするものと解されるところ、評価通達24が適用される私道供用宅地に該当するか否かは、相続等により取得した財産価値に着目し、私道の宅地としての価額が著しく低下しているか否かにより判断するのが相当であるから、固定資産税等が非課税とされているからといって、評価通達24に定める私道供用宅地に該当するとはいえない。
三、一審判決要旨
請求棄却。
(1)本件の認定事実を前提として、本件各歩道が評価通達24の適用される私道供用宅地に該当するか否かを検討する。
そこで検討すると、私人が所有する道という広い意味で私道を捉えた場合、その中には、例えば、複数の建物敷地のいわゆる接道義務を満たすために当該各敷地所有者が共有する道であって建築基準法上の道路とされているものもあるであろうし、他方において、宅地の所有者が事実上その宅地の一部を通路として一般の通行の用に供しているものもあり得るところである。このうち、前者は、これに隣接する各敷地の所有者が、それぞれの接道義務を果たすために不可欠のものであるから、個別の敷地所有者の意思により、これを私道以外の用途に用いることには困難を伴うといえるし、また、道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって、その利用には制約があるものである。これに対し、後者は宅地の所有者が宅地の使用方法の選択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず、特段の事情のない限り、通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に委ねられているのであって、その利用に制約があるわけではない。
このような違いを宅地の価額の評価という観点からみた場合、前者については、上記のような制約がある以上、評価通達24が定めるように、所定の方法により計算された価額の30%で評価することとし、それが不特定多数の者の通行の用に供されているためにより大きい制約を受ける状況にあるといえるときにはその価額を評価しないとすることには、合理性があるものということができる。しかしながら、後者については、そもそもかかる制約がなく、特段の事情がない限り、私道を廃止して通常の宅地として利用することも所有者の意思によって可能である以上、これを通常の宅地と同様に評価するのがむしろ合理的というべきである。
(2)そこで、本件各歩道状空地が評価通達24の適用される私道共用宅地に該当するか否かを検討する。まず、本件各土地は、いずれも公道に接しているのであり、本件各歩道は、接道義務を果たすために設けられたものではない。したがって、本件各歩道の利用について、私道としての建築基準法上の利用制限が課されることになるわけではない。
本件各歩道が設けられたのは、S市やD市から、要綱等に基づき歩道部分を設けるように指導されたことによるものであるが、かかる指導がされることとなったのは、甲が、本件各土地上に、それぞれ共同住宅を建築するべく、都市計画法に基づく開発行為を行うこととしたためである。すなわち、本件各土地の利用方法として様々な選択肢があり得る中で、甲は、上記開発行為をすることを選択したのであって、その結果、上記指導を受けて、本件各歩道を設けることとなったものであるところ、かかる指導によって本件各歩道を設けることを事実上やむなくされたことをもって仮に制約と評価する余地があるとしても、かかる制約は、それを受け入れつつ開発行為を行うのが本件各土地の利用形態として適切であると考えた上での選択の結果生じたものということができる。しかも、本件各土地は、甲が所有し、Xらが相続したものであり、その利用形態は同人らが決定し得るものであって、同人らが、その意思により、本件各土地の利用形態を変更すれば、上記のような制約を受けることもなくなるのであるから、通常の宅地と同様に利用することができる潜在的可能性とそれに相当する価値を有しているといえる。また、制約の態様についてみると、本件各土地においては、歩道としての供用が求められているにすぎないし、しかも、本件各歩道も含めて建物敷地の一部として建ぺい率等が算定されているのであって、つまるところ、同部分は、所定の容積率の建物を建築し得るための建物敷地としての役割をも果たしており、それに相当する価値を現に有していると考えられるところである。
以上のような事情に照らすと、評価通達24が想定している私道に課された制約の程度と、本件各歩道に課されている上記の制約の程度は、大きく異なるものといわざるを得ないのであり、本件各歩道をもって、評価通達24の適用される私道供用宅地に該当するということはできない。
(3)Xらは、本件各歩道は、近隣の小学校の通学路として指定されており、私道としての負担を強いられているなどと主張する。しかし、証拠によれば、上記通学路としての指定は、本件S歩道についてはS市立P小学校により、本件D歩道についてはD市立O小学校ないしD市教育委員会によってされるものであるが、いずれについても、通学路の指定に当該歩道状空地ないし私道の廃止又は変更を規制する権限はなく、仮に通学路として使用することができなくなった場合には、隣接する道路や迂回できる道路などを新たに通学路として指定することになるというものであることが認められ、評価通達24が想定するほどの制約が課せられているとはいえない。
さらに、公共の用に供する道路について固定資産税を非課税とする旨を定める地方税法348条2項の規定は、同項各号において非課税とされている他の固定資産と同様に、主として、固定資産の性格及び用途に鑑み、固定資産税を非課税とすべきものを定めたものであると解されるところであり、同項によって固定資産税が非課税とされたとしても、必ずしもその財産的価値がないことを意味しないというべきであって、相続税についても同様に取り扱うべきであるとはいえない。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却(請求棄却)
(1)当裁判所も、Xらの請求は、いずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の理由を引用する。
(2)Xらは、将来の本件各歩道の利用形態の変更をも考慮することは誤りである旨主張する。しかしながら、上記潜在的可能性は、利用形態の変更が制限されていない本件各歩道の現況(現時点における客観的可能性)にほかならず、Xらの主観的事情によって左右されるものではないから、Xらの主張は採用できない。
(3)Xらは、本件各歩道を除いても建物を建てることができることを理由として、本件各歩道が上記価値を有することを否定する主張をするが、現に上記のとおりの算定がされている以上、本件各歩道が建物敷地としての役割を果たしており、それに相応する価値を現に有していることは明らかであるから、Xらの主張は採用できない。
五、上告審判決要旨
原判決破棄。
原審差戻し。
(1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているところ、ここにいう時価とは、課税時期である被相続人の死亡時における当該財産の客観的交換価値をいうものと解される。そして、私道の用に供されている宅地については、それが第三者の通行の用に供され、所有者が自己の意思によって自由に使用、収益又は処分をすることに制約が存在することにより、その客観的交換価値が低下する場合に、そのような制約のない宅地と比較して、相続税に係る財産の評価において減額されるべきものということができる。
そうすると、相続税に係る財産の評価において、私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を、建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく、そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。
(2)これを本件についてみると、本件各歩道は、車道に沿って幅員2mの歩道としてインターロッキング舗装が施されたもので、いずれも相応の面積がある上に、本件各共同住宅の居住者以外の第三者による自由な通行の用に供されていることがうかがわれる。また、本件各歩道は、いずれも本件各共同住宅を建築する際、都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、市の指導要綱等を踏まえた行政指導によって私道の用に供されるに至ったものであり、本件各共同住宅が存在する限りにおいて、Xらが道路以外の用途へ転用することが容易であるとは認め難い。そして、これらの事情に照らせば、本件各共同住宅の建築のための開発行為が甲による選択の結果であるとしても、このことから直ちに本件各歩道について減額して評価をする必要がないということはできない。
(3)以上によれば、本件各歩道の相続税に係る財産の評価につき、建築基準法等の法令による制約がある土地でないことや、所有者が市の指導を受け入れつつ開発行為を行うことが適切であると考えて選択した結果として設置された私道であることのみを理由として、前記(1)において説示した点について具体的に検討することなく、減額をする必要がないとした原審の判断には、相続税法22条の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
(4)したがって、原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。
六、解説
はじめに
本件は、貸家3棟又は8棟の敷地(貸家建付地)と市道との間に挟まれた幅員2mの歩道状空地(舗装済み、本件各歩道)が、貸家建付地として評価すべきか、又は評価通達24に定める歩道として評価すべきかが争われた事案である。相続税法上、相続等によって取得した財産の価額は「時価」によることとされているので、本件各歩道のような歩道状態の宅地の「時価」が幾許であるかが争われた場合には、当該「時価」の多寡を評価すれば足りるはずである。しかしながら、課税の実務においては、相続等によって取得した財産の価額が一次的には評価通達に定める評価額(評価方法)によって算定されるため、当該財産の価額(時価)が争われるときには、まず、評価通達に定める評価方法の適用の可否が問題となる。
本件においても、本件各歩道の相続税法上の「時価」が幾許であるかが争われたものであるので、当該「時価」が後述するような客観的交換価値を表わすというのであれば、国が主張するような本件各歩道についての処分可能価額を重視すべきであるとも考えられるのであるが、最高裁判所は、本件各歩道が評価通達24に定める「歩道」との類似性を強調しているようである。ともあれ、本件においては、単に、本件各歩道が評価通達24に定める「歩道」の該非のみならず、評価通達が本条の「時価」の解釈に影響を及ぼしている点にも着目すべきであると考えられる。
1 相続税法上の「時価」と評価通達 (1)相続税法22条は、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。この「時価」の意義については、評価通達では、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」(同通達1(2))をいうと定めている。この意義については、一般に、客観的交換価値又は客観的交換価額を意味するものとして、学説、判例において広く支持されている(注1)。また、所得税法及び法人税法においても、資産の無償又は低額取引において当該資産の「価額」が問題となるところ(所法36②、59①、法法22②、37⑦等)、当該「価額」の解釈(評価)においても共通している(注2)。
また、評価通達は、上記の「財産の現況」等に関し、「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」と定めている。このように、評価通達は、基本的には、各財産の取得の時において、かつ、当該財産がおかれた個別の状況に応じて、当該財産の客観的交換価値を把握すべきものとしている。
(2)しかしながら、相続、贈与等によって財産を取得することにより発生する全ての課税原因において、当該財産の客観的交換価値を個々に算定(把握)するということは、技術的に極めて困難であり、かつ、当該価値判断を個々の担当者の主観に委ねることとなるので、それぞれの財産の評価額が不均一となり、ひいては納税者間に課税の不公平をもたらすことになる。
そのため、課税の実務では、国税庁長官が発出する評価通達の定めによって、各財産の価額(時価)が評価され、当該評価額が相続税及び贈与税の課税の基準となっている。すなわち、前述の評価通達1(2)は、「時価とは、……自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」と定めている。要するに、評価通達は、「時価」が客観的交換価値を意味することを標榜しながらも、各財産の「時価」を同通達の定めによって統一的に評価することとしている(注3)。このように、相続等によって取得した財産の価額(時価)は、実務的には評価通達が定める評価方法によって画一的に評価されるのであるが、それらの評価方法の是非を論じる前に、評価通達という「通達」の法的性格等を明らかにしておく必要がある(注4)。
(3)まず、課税実務の規範となっている税務通達が存在する法的根拠は、国家行政組織法14条2項にある。同項は、「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めている。かくして、評価通達も、国税庁部内の行政命令であるので、国税庁職員に対しては、当該命令を遵守する義務がかせられている(国家公務員法98、82)が、法的には納税者がその通達の取扱いに拘束される謂れはないことになる。
しかしながら、評価通達のような税務通達は、実質的には、納税者を拘束すること(法解釈の規範)になる。すなわち、評価通達の国税庁職員に対する通達遵守義務は、納税者の法解釈を間接的に強制する(評価通達に従わない納税申告については、更正処分等を甘受せざるを得なくなる。)。また、評価通達は、路線価のような土地の価額(時価)については、公示価格水準の8掛としているので、通常の取引価額よりも路線価等を利用して申告をした方が有利であるし(有利性、安全性、謙抑性)、便利でもある(便宜性)。更に、近年、税理士に対する損害賠償請求事件が多発しているが、それらの判決では、税理士が税務通達の取扱いを無視して申告代理等を行い、納税者に損害を与えたときには、その税理士は専門家責任を果たしたことにはならない旨判示されている。
(4)更に、評価通達は、前述のように、各財産の評価額(評価方法)を画一的に定めているところ、宅地については、後述するように、路線価方式又は倍率方式によって一律に評価額が算定できるように定められている。しかし、このように画一的に評価される評価額は、標準的な宅地を想定し、評価日もその年の1月1日に特定されているので、一種の標準価額(基準価額)という性質を有することになる。そのため、実際に相続等によって取得した宅地の価額(時価)を路線価等によって評価した場合に、当該評価額が当該宅地の価額(時価)に対し相当に乖離することもあり得る。
このような評価通達の定めによる評価額と当該財産の客観的交換価値の間に著しい乖離が生じた場合に、評価通達は、その取扱いの中で包括的な補完措置を設けている。すなわち、評価通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。
この規定は、前述したように、通達における標準価額による評価(評価基準制度)の弊害を防止するものであるが、側面では、納税者側の予測可能性と法的安定性を害するということにもなるので、同族会社等の行為計算の否認規定(所法157、法法132、相法64等)等と同視されることがある(注5)。
2 評価通達における宅地・私道の評価 (1)評価通達における宅地のような土地の価額の評価は、前述した標準価額による評価という評価基準制度の典型である。すなわち、評価通達は、土地の評価上の区分について、宅地など10種類に区分し(評基通7)、土地の価額は、それぞれの土地の種類に応じて、評価単位ごとに評価することとしている(評基通7-2)。そして、宅地については、「一画地の宅地(利用の単位となっている一区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。」(評基通7-2(1))ことになる。ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「一画地の宅地」とする(評基通7-2(1)(注))。これは、遺産分割等において「一画地」を無道路地等にして、評価額を恣意的に著しく引き下げること等に対処したことにほかならない(注6)。
次に、宅地の評価は、①市街地的形態を形成する地域にある宅地については、路線価方式により、②①以外の宅地については、倍率方式による(評基通11)。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基として、評価通達15項以下に定める奥行価格補正等の画地調整を行うことにより計算した金額によって評価する方式である(評基通13)。また、倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額による(評基通21)。
(2)上記の路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。)ごとに設定する(評基通14)。また、不特定多数の者の通行の用に供されていない道路に面している宅地については、当該道路について、納税義務者の申出等に基づき路線価(特定路線価)を設定することができる(評基通14-3)。
この路線に付される価格すなわち路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格(地価公示法の規定により公示された標準地の価額)、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定した価額)、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1㎡当たりの価額である(評基通14)。
① その路線のほぼ中央部にあること。
② その一連の宅地に共通している地勢にあること。
③ その路線だけに接していること。
④ その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有する矩形又は正方形のものであること。
以上のように、路線価は、売買実例価額等の多くの判定要素を総合して算定されるのであるが、その中で、公示価格が最も重要な判定要素となっている。すなわち、平成4年以降の路線価は、公示価格水準の80%相当額とされ(注7)、その評価日も、平成3年分までの前年7月1日から、公示価格の評価日に合わせるために、当年の1月1日とされた。
このような路線価による宅地の評価は、一定の路線において標準的な間口距離等を有する標準的な宅地についての価額設定であるから、当該標準的な宅地に該当しない宅地であれば、当該路線価によって算定された価額に加減算するための調整率が適用される。加算されるものには、側方路線、二方路線、三方又は四方路線の影響加算がある(評基通16~18)。減算されるものには、奥行価格補正(評基通15)、不整形地補正(同20)、無道路地補正(同20-2)、間口挟小補正(同20-3)等がある。そのほか、大規模工場用地(評基通22-2、22-3)、広大地(同24-4)等には、特別の評価方法が採用されている。
(3)次に、本件の私道のように、当該宅地を所有権によって支配しているものの、その支配権等が何らかの形で制限されているものについては、その支配制限に対応した評価減が行われる。まず、評価通達24は、「私道の用に供されている宅地の価額は、11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。」と定めている。
このように、私道の価額は、その私道の形態に応じて、30%評価が行われるものと、零%評価が行われるものに区分される。この点について、「私道には、公共の用に供するもの、つまり、不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通り抜け道路と、そうでないもの、つまり、袋小路のようにもっぱら特定の者の通行の用に供するいわゆる行き止まり道路がある。」(注8)ことに対応したもので、前者が零評価となり、後者が30%評価に区分されている。
そして、この30%評価について、国税庁の担当者は、次のように説明している(注9)。
「これに対し、後者は、現在その使用収益にある程度の制約はあるが、私有物として、所有者の意思に基づく処分の可能性は残されている。特に、そのような私道に沿接する土地が同一人の所有に帰属することになると、現在の私道は、容易にその敷地内に包含されて、私道ではなくなってしまうことになる。このようなことから、もっぱら特定の者の通行の用に供される私道の価額は、路線価方式又は倍率方式のいずれかによって評価した価額の30%相当額によって評価することにしている。」
なお、袋小路の私道の形態を有していても、それが1人が所有している宅地と路線に接しているものについては、私道として評価されることはない(注10)。
次に、零評価される私道には、次のようなものが挙げられている(注11)。
① 公道と公道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け私道
② 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
③ 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道
(4)そのほか、私道と同じように、その宅地の使用等が制限されているため、相応の評価減が行われる場合に、次のようなものがある。例えば、建築基準法42条2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地(セットバックを必要とする宅地)の価額は、通常の評価額から7割を控除することとしている(評基通24-6)。このように、セットバックを必要とする宅地の価額が、私道と同様に3割評価する理由については、次のように説明されている(注12)。
「セットバックを必要とする宅地は、現在の利用には特に支障がない場合であっても、その宅地の価額は、セットバックを要しない宅地の価額に比較して減少することになり、セットバックを必要とする部分については、私道と比較すると、現にセットバックをしていない限り宅地として利用されているわけであるから、少なくとも私道の価値率(評価基本通達では30%)を下回ることはないと考えられる。」
また、貸宅地については、その価額は、他人の借地権の目的となっている(自己が使用収益できない)が故に、自用地の価額から当該借地権の価額を控除して評価される(評基通25)。この場合、借地権が存在しない場合にも、最低20%は評価減されることになっている(同上)。
3 本件各私道の評価 (1)本件は、神奈川県のS市及びD市に所在する貸家建付地沿いに付設された私道状態の各宅地(本件各歩道)の価額が幾許であるかが争われたのであるが、具体的には、本件各歩道が評価通達24に定める歩道として、70%の評価減が認められるか否かが争われた事案である。このような評価上の区分が争われるのは、「私道」と一口に言っても、その使用形態、処分形態等がそれぞれ異なるからにほかならないが、評価通達においても、それぞれの使用形態等に応じて、自用地の価額に比し、30%評価するものと零評価するものに区分している。本件各私道についても、前記通達にいう「私道」そのものに該当するか否かが争われた。
この点につき、Xらは、本件各私道が、いずれも、本件各共同住宅の建設に当たり、都市計画法上の開発許可を受けるための条件として、各市との協議において私道として整備することが義務付けられたものであり、現に、近隣の学童の通学の用等に供されているところであり、そのため、固定資産税、都市計画税等も非課税とされている旨等を主張した。
これに対し、国は、評価減の対象となる「私道」に当たるか否かは、その私道が私有物として使用・収益する権能が制約されることにより、宅地としての価額が著しく低下しているか否かによって判断すべきところ、本件各私道については、建築基準法上建築制限等の制約は全くなく、現に、本件相続開始後、X1が本件S地を関係会社を譲渡するに当たって本件S歩道部分も他の宅地と同一単価で譲渡されているところであり、固定資産税等が非課税とされているのは政策的目的から行われているものであって本件S歩道の宅地としての価額に影響を及ぼすものではない旨等を主張した。
結局は、両者の主張は、本件各歩道の価額の評価につき、Xらは、本件各歩道が現に他人によって使用収益されているという使用状況を強調しているのに対し、国は、本件各歩道の宅地としての価額につき、それが処分された時の価額によって評価すべきことを強調していることに差異がある。この場合、国の主張については、前記2の(4)で述べたセットバックを必要とする宅地の評価と逆のパターンとなることが注目される。
(2)このような両者の主張の差異に対し、本件各判決は、次のように判示している。まず、一審判決は、前述のように、評価通達24にいう「私道」がいかなるものかが明らかにされていないところ、いわゆる私道には、複数の建物敷地のいわゆる接道義務を満たすために当該各敷地所有者が共有する道であって建築基準法上の道路とされるものと、宅地の所有者が事実上その宅地の一部を通路として一般の通行の用に供しているもの、とに区分でき、「後者については、そもそもかかる制約がなく、特段の事情がない限り、私道を廃止して通常の宅地として利用することも所有者の意思によって可能である以上、これを通常の宅地と同様に評価するのがむしろ合理的というべきである。」と判示し、本件各歩道は上記歩道に該当すると判断した。
また、控訴審判決も、一審判決の理由を引用しつつ、「時価とは「財産の現況に応じ」て判断すべきであるから将来の利用形態の変更を考慮して判断するのは違法である」旨のXらの主張に対し、当該潜在的可能性は利用形態の変更が制限されていない本件各歩道の現況(現時点における客観的可能性)にほかならない旨判示し、上記Xらの主張を排斥している。
これらの下級審の各判決に対し、上告審判決は、前述のように、「宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある」と判示し、本件各歩道が、本件各共同住宅を建築する際、行政指導によって私道の用に供されている現況が当該歩道の価額の減額にどのように影響すべきかを考慮する必要があるとして、原審に差し戻した。
(3)以上のように、本件においては、前記(1)で述べたような形状を有する本件各歩道の価額の評価につき、当該歩道が都市計画法上の規定に基づき市の指導によって歩道の用に供されている現況を重視すべきか、あるいは、建築基準法の規定において何ら使用(処分)制限が課せられていない現況を重視すべきか、が問題となった。
この点につき、一審判決及び控訴審判決は、後者を重視して本件各歩道の価額を他の貸家建付地並に評価できるとした本件各処分を適法とし、上告審判決は、前者を重視して原判決を破棄し、原審へ差し戻した。そのため、本件は、再び東京高等裁判所で審理されることになるが、恐らく、同裁判所において、本件各歩道の価額の評価において何らかの減額判断(評価通達24の適用等)が行われるものと見込まれた。その後、差戻し審において、国側が、本件各処分を全部取り消す旨を表示したようで、本事件としては解決することとなった(注13)。
4 本件各判決の意義と問題点 以上のように、本件は、貸家3棟又は8棟の敷地(貸家建付地)と市道との間に挟まれた幅員2mの本件各歩道の価額を、当該貸家建付地の一部として評価すべきか、あるいは、評価通達24に定める歩道として70%の評価減が行われるべきか、が争われた事案である。
一審判決及び控訴審判決は、本件各歩道が建築基準法上の使用・処分に制限がないことに着目して貸家建付地の一部として評価した本件各処分を適法とし、上告審判決は、都市計画法上の行政指導に基づき現に私道として使用されている現況を重視すべきとして、原判決を破棄・差し戻した。
実務においては、何が私道に該当するか、私道に該当する場合に評価通達24に定める評価減(30%評価が零評価か)の適用がまま問題となることがあるが、それが訴訟まで争われることは稀である。よって、本件各判決は、歩道に関する訴訟事例として意義がある。また、「私道」と称されるものには、種々の形態、法律関係を有するものがあるが、それぞれの形態等に応じて、当該歩道の価額をどのように評価すべきかは、評価論的にも問題のあるところであるので、一層の検討を要する課題でもある。
(注1)金子宏「租税法 第22版」(弘文堂 平成29年)662頁、東京地裁昭和53年4月17日判決(税資101号115頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等参照。
(注2)名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、東京高裁昭和59年11月14日判決(同140号232頁)等参照。
(注3)品川芳宣「租税法律主義と税務通達」(ぎょうせい 平成16年)120頁等参照。
(注4)前出(注3)48頁以下、品川芳宣編著「資産・事業承継対策の現状と課題」(大蔵財務協会 平成28年)534頁以下参照。
(注5)評価通達6項をめぐる種々の問題については、前出(注3)122頁、前出(注4)「資産・事業承継対策の現状と課題」540頁等参照。
(注6)谷口裕之「財産評価基本通達逐条解説 平成25年版」(大蔵財務協会 平成25年)38頁参照。
(注7)従前は、公示価格水準の概ね70%とされていたが、現実には、それよりも相当低額で評価されていた。そして、平成4年以降80%相当額としたのは、平成4年度税制改正大綱による公的土地評価の均衡・適正化の一還として行われた。そのため、80%評価の根拠は、評価通達には明記されていない。
(注8)前出(注6)126頁。
(注9)前出(注6)127頁。
(注10)前出(注6)128頁。
(注11)前出(注6)127頁。
(注12)前出(注6)161頁。
(注13)週刊税務通信 平成29年6月19日号4頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























