解説記事2017年11月06日 【税理士のための相続法講座】 遺言(7)-遺言の効力(1)(2017年11月6日号・№714)
税理士のための相続法講座
第33回
遺言(7)-遺言の効力(1)
弁護士 間瀬まゆ子
1 遺言の無効 遺言書が存在したとしても、その遺言が無効だとして紛争が生じるケースは珍しくありません。その際に、無効原因としてあげられるのが以下のようなものです。
このうち、最も争いになるのは①です。これについては次回解説します。
④の遺言の方式、⑤の遺言の撤回と撤回擬制については、前回までに触れたとおりです。
以下では、②、③、⑥及び⑦の無効原因について解説します。
なお、条件付の遺言でも、相続開始時またはその後に遺言が無効と解される場合があります。すなわち、停止条件付遺言の条件の不成就が確定した場合には、条件に係る内容につき無効の遺言となり(民法131条2項)、また、解除条件付遺言の条件が遺言者死亡の時既に成就していれば、無効の遺言となり(同条1項)、死亡後に条件が成就すれば、その時から遺言は効力を失うこととされています(同法127条2項)。
2 偽造 遺言書が偽造されたか否かが争われた事例として、布製かばんメーカーのオーナー一族の紛争が有名になりましたが、この事案でも話題になった筆跡鑑定というのは極めて曖昧なものです。訴訟で筆跡が本人のものかが争われた場合、裁判所も、筆跡鑑定の結果のみで判断することはなく、遺言者の自書能力、遺言書の体裁や内容、保管状況等を総合考慮して偽造か否かの判断を下します。つまり、裁判官の「さじ加減」で180度判断が変わる可能性を元々内包しており、結論を予測するのが困難な類の事件なのです。
そうであるからこそ、そもそも紛争事態を回避するため、公正証書にしておくべきことは以前にも述べたとおりです。
3 民法総則規定による無効 民法総則規定により無効となるのは、公序良俗違反(90条)や錯誤(95条)の場合です。その他、民法総則規定のうち、詐欺強迫取消し(96条)も遺言の場合に適用されます。
不倫相手に対する遺贈が公序良俗に違反するか否かについては、これを肯定した事例(東京地判昭和63年11月14日判時1318号78ページ)がある一方、妻との婚姻の実態がある程度失われていたことや、法定相続人である妻子も3分の1を取得することとされていた等の事情を考慮し、公序良俗に違反しないとされた事例(最一小判昭和61年11月20日民集40巻7号1167ページ)もあります。結局は、個別事案ごとの事情によって判断されることになるでしょう。
4 遺言者の死亡以前の相続人・受遺者の死亡 遺言者の死亡以前の受遺者の死亡に関しては、民法に明文規定があります。民法994条1項は、遺言者が死亡する以前に受遺者が死亡したときは、遺贈が効力を生じない旨を規定しています。
これに対し、遺言で遺産分割の方法の指定がなされた後、遺言者の相続が開始する前に相続人が死亡してしまった場合に、当該遺言の効力が代襲相続人にまで及ぶかについては、明文の定めがありません。
この点、遺言で全ての財産を相続させると指定されていた長男Bが、遺言者である母Aより先に亡くなった場合に、その遺言の効力が長男の子C(孫)に及ぶかが争われた事例について、最高裁の判決が出ています。
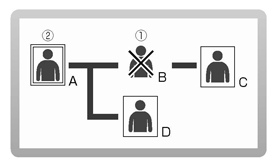
最高裁第三小法廷平成23年2月22日判決(民集65巻2号699ページ)は、遺言書の記載や遺言作成当時の事情等から、Aが「Bが先に死亡した場合には遺産をCに相続させる」との意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、Bに全ての財産を相続させるとの遺言は効力を生じないとしました。
この判例により、民法994条1項の趣旨は「相続させる」遺言にも妥当し、遺言者の死亡以前に相続人が死亡した場合には、代襲相続人がいたとしても原則として代襲相続はしないと解されることになりました。ただ、遺言者が代襲相続人等に相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情があれば、例外的に効力を生じることとされます。
この点、東京地裁平成25年12月12日判決(判例集未登載)の事案では、Eが妻Fと長男G以外の子Hらの相続分を指定する遺言を作成していたものの、FがEより先に死亡してしまい、Fの指定相続分の帰属が争点になりました。裁判所は、EがGを廃除する遺言を残していたこと等を考慮し、Fが先に死亡した場合には、Fの指定相続分はHらに均等の割合で指定する旨の意思をEが有していたとみるべき特段の事情があると認め、遺言を有効としました。
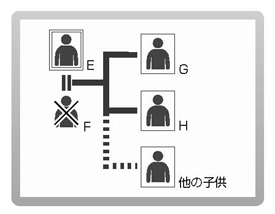
特別の事情ありと認められるかは事案ごとの個別判断となり、相続開始後に相続人らを不安定な状態に置くことになりますから、そのような疑義が生じない遺言にしておくことが望まれます。具体的には、「ただし、妻Fが遺言者Eの相続開始前に死亡したときは、子H及びIに均等の割合で前記財産を相続させる。」などと入れておくことになるでしょう(ただ、配偶者であればともかく、相続人が子である場合には、遺言者に「あなたのお子さんが先に死ぬかもしれない」などとはなかなか言いにくいものですが。)。
5 相続人・受遺者の欠格事由 民法891条に定める欠格事由に該当する者は、相続人となることができません。この規定は、受遺者についても準用されています(民法965条)。
欠格事由のうち、故意に被相続人を死亡するに至らせる等して刑に処せられた者(民法891条1号)等は、滅多に問題とされることがないでしょうが、実務で争いが生じることがあるのが、遺言書の偽造又は隠匿(同条5号)です。
具体的には、相続開始後時間が経過してから相続人の一人が遺言を出してきた場合に、他の相続人が「遺言書の隠匿」があったとして相続欠格を主張する場合があります。ただ、欠格事由ありと認められるためには、破棄又は隠匿についての故意に加えて、これにより自己が相続又は遺贈について有利になろうとする動機・目的が必要と解されており(最三小判平成9年1月28日民集51巻1号184ページ)、ハードルは高くなっています(「隠匿」を認めたものとしては、上記最高裁判決以前の東京高判昭和45年3月17日家月22巻10号81ページのほか、千葉地裁八日市場支部判決平成11年2月17日判タ1030号251ページがあります。)。
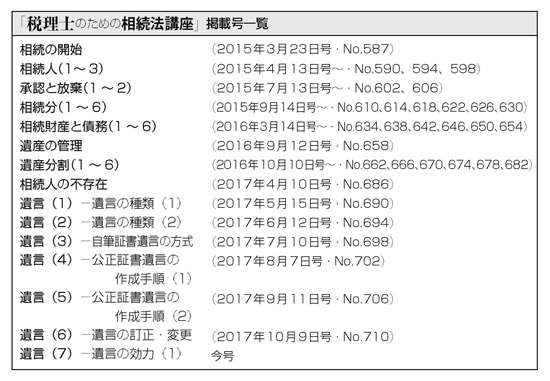
第33回
遺言(7)-遺言の効力(1)
弁護士 間瀬まゆ子
1 遺言の無効 遺言書が存在したとしても、その遺言が無効だとして紛争が生じるケースは珍しくありません。その際に、無効原因としてあげられるのが以下のようなものです。
| ① 遺言能力 ② 偽造 ③ 民法総則規定による無効 ④ 方式違背 ⑤ 遺言の撤回・撤回擬制 ⑥ 遺言者の死亡以前の相続人・受遺者の死亡 ⑦ 相続人・受遺者の欠格事由 |
④の遺言の方式、⑤の遺言の撤回と撤回擬制については、前回までに触れたとおりです。
以下では、②、③、⑥及び⑦の無効原因について解説します。
なお、条件付の遺言でも、相続開始時またはその後に遺言が無効と解される場合があります。すなわち、停止条件付遺言の条件の不成就が確定した場合には、条件に係る内容につき無効の遺言となり(民法131条2項)、また、解除条件付遺言の条件が遺言者死亡の時既に成就していれば、無効の遺言となり(同条1項)、死亡後に条件が成就すれば、その時から遺言は効力を失うこととされています(同法127条2項)。
2 偽造 遺言書が偽造されたか否かが争われた事例として、布製かばんメーカーのオーナー一族の紛争が有名になりましたが、この事案でも話題になった筆跡鑑定というのは極めて曖昧なものです。訴訟で筆跡が本人のものかが争われた場合、裁判所も、筆跡鑑定の結果のみで判断することはなく、遺言者の自書能力、遺言書の体裁や内容、保管状況等を総合考慮して偽造か否かの判断を下します。つまり、裁判官の「さじ加減」で180度判断が変わる可能性を元々内包しており、結論を予測するのが困難な類の事件なのです。
そうであるからこそ、そもそも紛争事態を回避するため、公正証書にしておくべきことは以前にも述べたとおりです。
3 民法総則規定による無効 民法総則規定により無効となるのは、公序良俗違反(90条)や錯誤(95条)の場合です。その他、民法総則規定のうち、詐欺強迫取消し(96条)も遺言の場合に適用されます。
不倫相手に対する遺贈が公序良俗に違反するか否かについては、これを肯定した事例(東京地判昭和63年11月14日判時1318号78ページ)がある一方、妻との婚姻の実態がある程度失われていたことや、法定相続人である妻子も3分の1を取得することとされていた等の事情を考慮し、公序良俗に違反しないとされた事例(最一小判昭和61年11月20日民集40巻7号1167ページ)もあります。結局は、個別事案ごとの事情によって判断されることになるでしょう。
4 遺言者の死亡以前の相続人・受遺者の死亡 遺言者の死亡以前の受遺者の死亡に関しては、民法に明文規定があります。民法994条1項は、遺言者が死亡する以前に受遺者が死亡したときは、遺贈が効力を生じない旨を規定しています。
これに対し、遺言で遺産分割の方法の指定がなされた後、遺言者の相続が開始する前に相続人が死亡してしまった場合に、当該遺言の効力が代襲相続人にまで及ぶかについては、明文の定めがありません。
この点、遺言で全ての財産を相続させると指定されていた長男Bが、遺言者である母Aより先に亡くなった場合に、その遺言の効力が長男の子C(孫)に及ぶかが争われた事例について、最高裁の判決が出ています。
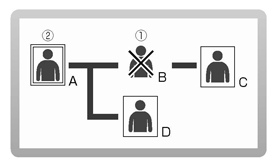
最高裁第三小法廷平成23年2月22日判決(民集65巻2号699ページ)は、遺言書の記載や遺言作成当時の事情等から、Aが「Bが先に死亡した場合には遺産をCに相続させる」との意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、Bに全ての財産を相続させるとの遺言は効力を生じないとしました。
この判例により、民法994条1項の趣旨は「相続させる」遺言にも妥当し、遺言者の死亡以前に相続人が死亡した場合には、代襲相続人がいたとしても原則として代襲相続はしないと解されることになりました。ただ、遺言者が代襲相続人等に相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情があれば、例外的に効力を生じることとされます。
この点、東京地裁平成25年12月12日判決(判例集未登載)の事案では、Eが妻Fと長男G以外の子Hらの相続分を指定する遺言を作成していたものの、FがEより先に死亡してしまい、Fの指定相続分の帰属が争点になりました。裁判所は、EがGを廃除する遺言を残していたこと等を考慮し、Fが先に死亡した場合には、Fの指定相続分はHらに均等の割合で指定する旨の意思をEが有していたとみるべき特段の事情があると認め、遺言を有効としました。
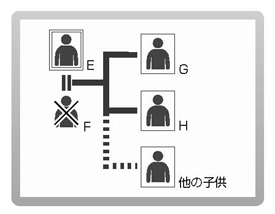
特別の事情ありと認められるかは事案ごとの個別判断となり、相続開始後に相続人らを不安定な状態に置くことになりますから、そのような疑義が生じない遺言にしておくことが望まれます。具体的には、「ただし、妻Fが遺言者Eの相続開始前に死亡したときは、子H及びIに均等の割合で前記財産を相続させる。」などと入れておくことになるでしょう(ただ、配偶者であればともかく、相続人が子である場合には、遺言者に「あなたのお子さんが先に死ぬかもしれない」などとはなかなか言いにくいものですが。)。
5 相続人・受遺者の欠格事由 民法891条に定める欠格事由に該当する者は、相続人となることができません。この規定は、受遺者についても準用されています(民法965条)。
欠格事由のうち、故意に被相続人を死亡するに至らせる等して刑に処せられた者(民法891条1号)等は、滅多に問題とされることがないでしょうが、実務で争いが生じることがあるのが、遺言書の偽造又は隠匿(同条5号)です。
具体的には、相続開始後時間が経過してから相続人の一人が遺言を出してきた場合に、他の相続人が「遺言書の隠匿」があったとして相続欠格を主張する場合があります。ただ、欠格事由ありと認められるためには、破棄又は隠匿についての故意に加えて、これにより自己が相続又は遺贈について有利になろうとする動機・目的が必要と解されており(最三小判平成9年1月28日民集51巻1号184ページ)、ハードルは高くなっています(「隠匿」を認めたものとしては、上記最高裁判決以前の東京高判昭和45年3月17日家月22巻10号81ページのほか、千葉地裁八日市場支部判決平成11年2月17日判タ1030号251ページがあります。)。
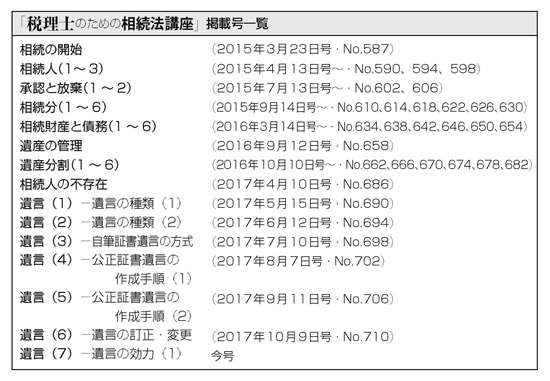
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























