解説記事2017年12月18日 【判例評釈】 デンソーを勝たせた最高裁のロジック―タックス・ヘイブン対策税制における事業基準(2017年12月18日号・№719)
判例評釈
デンソーを勝たせた最高裁のロジック―タックス・ヘイブン対策税制における事業基準
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 仲谷栄一郎
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 梶原康平
Ⅰ はじめに
タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準のうち事業基準の該当性が争われた第1次デンソー事件において、今般、納税者勝訴の最高裁判決(脚注1)が下された。
本件は、第一審(脚注2)で更正処分等の取消請求が認められ納税者が勝訴した後、第二審(脚注3)では逆転して敗訴し、また、後続事業年度に係る第2次デンソー事件では第一審(脚注4)、第二審(脚注5)とも納税者が勝訴しており、下級審の判断が分かれていたことから、最高裁による判断が注目されていた。
本件の最高裁判決は、海外の一定の地域に所在する子会社を束ねる地域統括業務と、タックス・ヘイブン対策税制の事業基準のいう「株式……の保有」(租税特別措置法66条の6第3項柱書。以下「株式保有業」という。)との関係を示すとともに、外国関係会社が複数の事業を営む場合における事業基準のいう「主たる事業」(同柱書)の判定方法を示したものとして重要である。本稿では、最高裁判決の判示を紹介した上でその実務への影響を検討する。
Ⅱ 事実関係
1 本件の原告である株式会社デンソー(以下「X社」という。)は、自動車関連部品の製造販売等を目的とする株式会社(内国法人)であり、35の国と地域で事業を展開し、全世界に200以上のグループ会社を有していた。
X社は、東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」という。)域内での集中生産・相互補完体制の円滑化を図るため、平成7年、豪亜地域における各拠点間の事業活動の調整及びサポートを行う目的で、シンガポールに地域統括センターとしてB社を設立し、同10年、ASEAN域内のX社のグループ会社に対する統率力を高めるために、B社を含むASEAN・台湾地域のグループ会社の保有株式を現物出資してシンガポールにA社を設立した。このA社が、本件でタックス・ヘイブン対策税制の適用の有無が問題となった特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項)である。
A社は、平成19年3月31日及び同20年3月31日において、X社の100%子会社であり、同18年4月1日から同19年3月31日まで及び同年4月1日から同20年3月31日までの各事業年度(以下、それぞれ「2007事業年度」、「2008事業年度」といい、併せて「対象事業年度」という。)において、ASEAN諸国等に存する子会社13社及び関連会社3社の株式を保有していた。
A社のシンガポールにおける所得に対する租税の負担割合は、2007事業年度では22.89%、2008事業年度では12.78%であった。
2(1)A社は、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図るため、設立以来、順次業務を拡大し、対象事業年度当時、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善に係る地域統括に関する業務(以下「本件地域統括業務」という(脚注6)。)のほか、持株(株主総会、配当処理等)に関する業務、プログラム設計業務及びB社のための各種業務の代行業務を行っていた。
A社は、対象事業年度当時、ASEAN諸国、インド及びオーストラリア連邦に所在するX社のグループ会社13社(以下「域内グループ会社」という。)に対し本件地域統括業務を行い、個々の業務につき、域内グループ会社から第三者向け売上高等に一定の料率を乗じた金額又は実費相当額等を徴収していた。
(2)A社は、対象事業年度当時、シンガポールに開設された現地事務所において、現地に在住する日本人の代表取締役と現地勤務の従業員三十数人で業務を遂行していたところ、従業員のうち20人以上は本件地域統括業務に、その余はプログラム設計業務及びB社のための各種業務の代行業務に従事しており、持株に関する業務のみに従事している者はいなかった。
A社は、上記現地事務所を賃借し、事務用什器備品、車両、コンピューター等の有形固定資産を保有していたが、これらの施設等は全て持株に関する業務以外の業務に使用され、その大半は本件地域統括業務に供されていた。
(3)A社の収入金額のうち本件地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上額は、2007事業年度において約4.9億シンガポールドル、2008事業年度において約6.1億シンガポールドルに上り、いずれも収入金額の約85%を占めていた。他方、その所得金額(税引前当期利益)においては、保有株式の受取配当の占める割合が高かった(2007事業年度は約92.3%、2008事業年度は約86.5%)が、本件地域統括業務によって集中生産・相互補完体制の構築、維持及び発展が図られた結果、域内グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、対象事業年度においても、これがA社の域内グループ会社からの配当収入の中に相当程度反映されていた。
(4)A社は、対象事業年度当時、シンガポールにおいて株主総会及び取締役会を開催し、役員は同国において職務執行をしていた。また、A社は、上記現地事務所において会計帳簿を作成し、保管していた。
3 所轄税務署長は、X社に対し、A社の主たる事業は株式保有業であり、X社の平成20年3月期及び平成21年3月期の所得金額の計算上A社の課税対象留保金額に相当する金額は益金の額に算入されるとして、これらの事業年度の法人税の更正処分等をした。
これに対して、X社は、所轄国税局長への異議申立て及び国税不服審判所長への審査請求を経て、上記処分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
4 第一審(原々審)は、A社の主たる事業は株式保有業ではなく地域統括業務であったため事業基準を満たすとし、その他の適用除外基準である実体基準、管理支配基準及び所在地国基準もいずれも満たすため、X社の平成20年3月期及び平成21年3月期においてタックス・ヘイブン対策税制の適用が除外されると判示した。ところが、第二審(原審)は、A社は株式保有業を主たる事業とするものであり事業基準を満たさないとし、X社のこれらの事業年度においてタックス・ヘイブン対策税制が適用されると判示した。
Ⅲ 争点及び背景
1 争 点 一定の軽課税国(脚注7)に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(特定外国子会社等)について、その発行済株式の一定割合以上を有する等の要件を満たす内国法人は、原則としてタックス・ヘイブン対策税制の適用を受け、当該特定外国子会社等の所得を益金の額に算入して課税を受けることになる(租税特別措置法66条の6第1項)。もっとも、適用除外基準(事業基準、実体基準、管理支配基準及び所在地国基準又は非関連者基準)をすべて満たす場合、同税制の適用は除外される(租税特別措置法66条の6第3項)。そして、事業基準は、株式保有業等の一定の事業を主たる事業とするものでないことを、その要件としている。
最高裁における本件の争点は、A社が株式保有業を主たる事業とするものに該当し、事業基準を満たさないこととなるかどうかであった。当該争点に関して、A社による本件地域統括業務は株式保有業の一部に過ぎないのかという点、及びA社が営んでいる複数の事業のうちいずれが主たる事業に該当するのかという点が争われた。
2 背 景 本件の対象事業年度後、平成22年度税制改正により事業持株会社の特例が設けられた。これは、株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等であっても、他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する一定の業務(統括業務)を行っており、かつ当該他の法人の株式の保有を行う等の一定の要件を満たす場合には、事業基準を満たすものとする特例である(租税特別措置法66条の6第3項括弧書、同法施行令39条の17)。地域統括業務を行っていたA社は、平成22年度税制改正後であれば、事業持株会社の特例の適用によってタックス・ヘイブン対策税制の適用除外が認められる可能性もあったといえる。
他方で、上記改正後の租税特別措置法の文言(同括弧書)は、本件の第一審も指摘するとおり、一見、地域統括業務を行う特定外国子会社等が、株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等に包含されているようにも見えなくもないものであった。
そこで、上記のとおり、地域統括業務は株式保有業に包含され、主たる事業とはなり得ないのではないか、という点が争われることとなった。
Ⅳ 最高裁の判断及びその検討
1 地域統括業務は株式保有業に包含されない
(1)最高裁の判断 最高裁は、「株式を保有する者は、利益配当請求権等の自益権や株主総会の議決権等の共益権を行使することができるほか、保有に係る株式の運用として売買差益等を得ることが可能であり、それゆえ、他の会社に係る議決権の過半数の株式を保有する特定外国子会社等は、上記の株主権の行使を通じて、当該会社の経営を支配し、これを管理することができる。」「しかし、他の会社の株式を保有する特定外国子会社等が、当該会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務を行う場合、このような業務は、通常、当該会社の業務の合理化、効率化等を通じてその収益性の向上を図ることを直接の目的として、その内容も上記のとおり幅広い範囲に及び、これによって当該会社を含む一定の範囲に属する会社を統括していくものであるから、その結果として当該会社の配当額の増加や資産価値の上昇に資することがあるとしても、株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とは異なる独自の目的、内容、機能等を有するものというべきであって、上記の業務が株式の保有に係る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。」と判示し、一般論として地域統括業務が株式保有業に包含されるという解釈を否定した。
そのうえで、対象事業年度におけるA社による本件地域統括業務については、「地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものということができるのであって、個々の業務につき対価を得て行われていたことも併せ考慮すると、上記の地域統括業務が株主権の行使や株式の運用に関連する業務等であるということはできない。」として、株式保有業には該当しないと認定した。
さらに、最高裁は、適用除外基準において株式保有業が主たる事業でないことが必要とされる趣旨について、「株式の保有に係る事業はその性質上我が国においても十分に行い得るものであり、タックス・ヘイブンに所在して行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見いだし難いことにある。」と述べて、A社による本件地域統括業務は「地域経済圏の存在を踏まえて域内グループ会社の業務の合理化、効率化を目的とするものであって、当該地域において事業活動をする積極的な経済合理性を有することが否定できないから、これが株式の保有に係る事業に含まれると解することは上記規定の趣旨とも整合しない。」と述べ、原審の判断は制度趣旨に合致しないとした。
(2)検 討
ア 株式保有業と地域統括業務の関係 本件の原審が、「一定地域内にある被支配会社を統括するための諸業務」(地域統括業務)は株式保有業の一部をなすと判示していたのに対し、最高裁は、株式保有業と地域統括業務を以下のとおり別のものと位置づけたと考えられる。
最高裁の判示からすると、株式保有業は、対象会社の株式の過半数を保有しその株主権の行使を通じて対象会社を支配、管理することを含むものではあるが、このような通常の親会社としての子会社に対する支配を超えて地域統括業務を行うものは含まない、ということになる。株式保有業と地域統括業務の関係は、図表1のように理解できるだろう。最高裁は、株式保有業とは別物として地域統括業務が存在することを認め、また、図表1で株式の保有(左側の円)と地域統括業務(右側の円)が重なっている部分(被統括会社の株式を保有しつつ地域統括業務を行っている場合。本件のA社。)については、株式保有業ではなく地域統括業務の方に含まれるとしたものと考えられる。
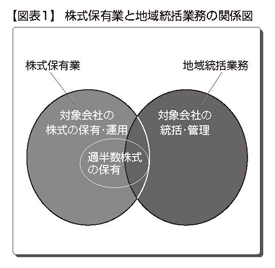
イ 株式保有業と地域統括業務の境界 「会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務」は株式保有業に含まれないとされたが、具体的事案においては、外国関係会社が行っている業務がこのような地域統括業務に当たるか、それとも株式保有業の枠を出ない株主権の行使にとどまるか、明確に判断がつかない場合もあるであろう。本件地域統括業務についても、最高裁は、以下の点に係る原審の詳細な事実認定を踏まえた上で初めて、本件地域統括業務が株式保有業に含まれないという判断を下したといえる。
また、最高裁は、我が国においても十分行うことができ、現地(海外)に所在して行う経済的合理性を見いだせないため、タックス・ヘイブン対策税制の適用を除外するという、事業基準の趣旨に立ち返って、現地で事業活動を行う経済的合理性を否定できない本件地域統括業務についての上記判断を補強している。
したがって、外国関係会社が行う業務が地域統括業務であり、株式保有業に含まれないとされるためには、当該業務が我が国ではなく現地で行う必要性の認められるだけの内容・目的を備えているか、被統括会社から対価を受領しているか、といったことが問われることになるであろう。
2 平成22年度税制改正を根拠に地域統括業務が株式保有業に包含されるということはできない
(1)最高裁の判断 本件の対象事業年度後の平成22年度税制改正で導入された事業持株会社の特例との関係については、最高裁は、「これによって事業基準を満たすこととなる統括会社は、もともと株式等の保有を主たる事業とするものであって(同項(筆者注:租税特別措置法66条の6第3項)柱書き)、それ以外の統括会社はその対象となるものではないから」、平成22年度税制改正の「経過を根拠に上記の統括業務が株式の保有に係る事業に包含される関係にあるものということはできず、A社の行っていた地域統括業務が株式の保有に係る事業に含まれるということはできない。」と判示した。
(2)検 討
ア 事業持株会社との関係 前述のとおり、事業持株会社の特例により、株式保有業を主たる事業とするもののうち統括業務を行う一定のもの(事業持株会社)は、事業基準を満たすこととされた。原審は、当該改正が、地域統括業務が株式保有業に包含されるという原審の理解と整合する旨を述べていた。
これに対し、最高裁は、株式保有業を主たる事業とするものの中に事業持株会社の特例を利用できる統括会社が存在するからといって、統括会社はおよそすべて株式保有業を主たる事業とするというわけではなく、地域統括業務等を主たる事業とする統括会社も存在し、そのような会社は事業持株会社特例を用いるまでもなく事業基準を満たすことを認めた。
これらの関係は、図表2(脚注8)及び図表3のとおり整理できるであろう。地域統括業務を営む外国関係会社は、事業持株会社の特例を使うほかに、主たる事業を株式保有業以外(地域統括業務等)とすることによっても、事業基準を満たしてタックス・ヘイブン税制の適用除外を受けられることが、本件の最高裁判決により明らかとなったといえる。
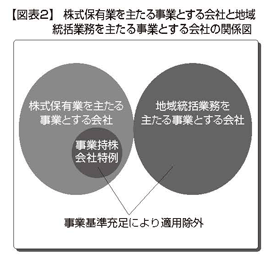
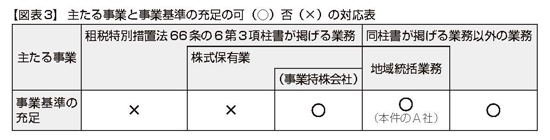 イ 地域統括業務を主たる事業とする類型の意義
平成22年度税制改正後の現在においては、地域統括業務を行っている外国関係会社は、事業持株会社の特例の要件を満たすようにプランニングされている例が多いと思われる。また、本件で最高裁が提示した総合考慮による主たる事業の認定は、事業持株会社の特例と比べ、事業基準を充足できるか否かについての予測可能性に欠ける。そのため、これらの会社を適用除外とするためには、今後も事業持株会社の特例が主に利用されるであろう。
イ 地域統括業務を主たる事業とする類型の意義
平成22年度税制改正後の現在においては、地域統括業務を行っている外国関係会社は、事業持株会社の特例の要件を満たすようにプランニングされている例が多いと思われる。また、本件で最高裁が提示した総合考慮による主たる事業の認定は、事業持株会社の特例と比べ、事業基準を充足できるか否かについての予測可能性に欠ける。そのため、これらの会社を適用除外とするためには、今後も事業持株会社の特例が主に利用されるであろう。
もっとも、従来事業持株会社の特例の要件を満たせずにタックス・ヘイブン対策税制の対象となっていたもの(例えば、現地の外資規制の存在等の事情により、内国法人がその発行済株式の全部を保有することができない外国関係会社(租税特別措置法施行令39条の17第4項柱書)等が考えられる。)については、地域統括業務を主たる事業とすることによって事業基準を充足する余地が生まれたといえるだろう。
3 主たる事業は諸要素を総合的に勘案して判定する
(1)最高裁の判断 本件地域統括業務が株式保有業に含まれないとすると、次に、これらを含むA社の複数の業務のうちいずれが主たる事業に該当するかが問題となる。この点について、最高裁は、「特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当であ」るとし、また、複数の事業のうちいずれが主たる事業に該当するかについては、「当該特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当である。」と判示した。
本件については、「A社は、豪亜地域における地域統括会社として、域内グループ会社の業務の合理化、効率化を図ることを目的として、個々の業務につき対価を得つつ、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム、物流改善という多岐にわたる地域統括業務を有機的に関連するものとして域内グループ会社に提供していたものである。」として、A社が行っていた業務の目的及び内容並びに当該業務について対価を得ていたことを指摘した。そして、各考慮要素について以下の事実を認定した上で、これらを「総合的に勘案すれば、A社の行っていた地域統括業務は、相当の規模と実体を有するものであり、受取配当の所得金額に占める割合が高いことを踏まえても、事業活動として大きな比重を占めていた」として、対象事業年度においては本件地域統括業務がA社の主たる事業であったと認定し、事業基準の充足を認めた。
(2)検 討
主たる事業を、当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定し、また複数の事業のうちそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する最高裁の判示は、従来下級審裁判例(脚注9)が示してきた基準に沿ったものである(脚注10)。したがって、本件の最高裁判決は、主たる事業の判定方法について、従来の実務を追認したものといえるだろう。
上記基準は複数の考慮要素を挙げていることから、各考慮要素で最も重要とされる事業が分かれてしまう場合、どのようにして主たる事業が判定されるかが問題となる。また、主たる事業は「当該事業年度における」事業活動から判定するとされているため、例えば従来地域統括業務が主たる事業とされていた会社が、ある事業年度に株式を譲渡する等して一時的に株式保有業に係る多額の収入金額及び所得金額を得た場合に、その事業年度においては株式保有業が主たる事業に該当して事業基準を充足しなくなってしまうのか、という問題もある。
本件も、収入金額、使用人の数及び固定施設の状況の観点からは本件地域統括業務が最も重要といえるが、他方で、所得金額の観点からは受取配当が全体の8、9割を占めるため株式保有業が最も重要ともいえ、考慮要素間で重要性が分かれていると考えられる事案であった。この点について、最高裁は、本件においては「地域統括業務によって域内グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利益」が配当収入に相当程度反映されていたと述べて、所得金額の観点についても本件地域統括業務が間接的に重要な影響を与えていたことに言及している。
この最高裁の理由付けは、地域統括業務と株式保有業の間であれば収入金額においても流用でき、また域内グループ会社(被統括会社)に生じる利益は配当金額だけでなくその企業価値・株式の価額にも影響しうるため、株式譲渡によって一時的に株式保有業に係る多額の収入金額及び所得金額を得た場合にも流用できる可能性がある。
他方、地域統括業務と株式保有業のように一方の業務が他方の業務における収入金額や所得金額の増加に貢献する関係がない場合で、上記考慮要素間で重要性が分かれたときに、主たる事業がどのように判断されるのかは明らかではない。今後の判例の展開が待たれる。
Ⅴ 平成29年度税制改正
タックス・ヘイブン対策税制は、平成29年度税制改正によりその構成を大きく変えることになった。これは、租税回避リスクを外国子会社の租税負担割合により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改めるものであると説明されており(脚注11)、従来租税負担割合によりいったん制度の対象とされた後の適用除外基準として機能していた事業基準、実体基準、管理支配基準及び所在地国基準又は非関連者基準(これらの基準をすべて満たす場合に、タックス・ヘイブン対策税制の適用が除外される。)は、改正後は、そもそもタックス・ヘイブン対策税制の対象となるかという制度発動要件(経済活動基準。上記基準のいずれかに該当しない場合に、タックス・ヘイブン対策税制が適用される。)にその位置づけを変えることとなった。このほか、平成29年度税制改正では、ペーパーカンパニー等の特定外国関係会社に対する合算課税や、受動的所得に対する部分合算課税の拡大等、重要な改正がなされている。これらの改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以降に開始する事業年度から適用される(平成29年度税制改正・改正法附則70条)。
ただ、上記のとおり適用除外基準は制度発動要件(経済活動基準)に位置づけを変えるものの、各基準の中身は改正後も大きくは変わらない。特に、事業基準を定める改正後租税特別措置法66条の6第2項3号イのうち株式保有業に関連する文言は、現行法の同条3項柱書の該当する箇所と同様の文言となっている。したがって、平成29年度税制改正適用後においても、地域統括業務と株式保有業との関係や主たる事業の判定方法を示した本件の最高裁判決は、先例として意義を有するであろう。
脚注
1 最三小判平成29年10月24日裁判所ウェブサイト
2 名古屋地判平成26年9月4日税務訴訟資料264号順号12524
3 名古屋高判平成28年2月10日訟務月報62巻11号1943頁
4 名古屋地判平成29年1月26日ウエストロー・ジャパン文献番号2017WLJPCA01266005
5 名古屋高判平成29年10月18日ウエストロー・ジャパン文献番号2017WLJPCA10186001
6 最高裁は、判決文中で当該業務を単に「地域統括業務」と定義している。本稿においては、当該業務が、一般的な意味で地域を統括する業務を意味するのではなく、A社が具体的に行っていた業務を意味していることを踏まえて、「本件地域統括業務」と呼ぶことにする。
7 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域、及び税負担割合が20%未満となる国又は地域(租税特別措置法施行令39条の14第1項参照)。なお、平成22年度税制改正前の本件当時は、租税負担割合に係る要件は25%以下とされていた。
8 前掲の図表1が事業・業務(株式保有業と地域統括業務)の関係を示したものであるのに対し、図表2は会社(株式保有業を主たる事業とする会社と地域統括業務を主たる事業とする会社)の関係を示したものである。例えば、図表2の株式保有業を主たる事業とする会社(左側の円)の中には、地域統括業務を(従たる事業として)行っているものも含まれる。
9 東京地判平成28年5月13日判例秘書判例番号L07131248、東京地判平成20年10月3日訟務月報55巻7号2532頁、東京地判平成20年8月28日訟務月報55巻7号2532頁(東京高判平成21年2月26日税務訴訟資料259号順号11149で是認)、静岡地判平成7年11月9日訟務月報42巻12号3042頁(東京高判平成8年6月19日税務訴訟資料216号619頁、最二小判平成9年9月12日税務訴訟資料228号565頁で是認)等
10 租税特別措置法施行令39条の14第2項4号における「主たる事業」の判定に係る、租税特別措置(法人税関係)基本通達66の6-8とも、基本的に同内容となっている。
11 財務省『平成29年度 税制改正の解説』658頁
デンソーを勝たせた最高裁のロジック―タックス・ヘイブン対策税制における事業基準
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 仲谷栄一郎
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 梶原康平
Ⅰ はじめに
タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準のうち事業基準の該当性が争われた第1次デンソー事件において、今般、納税者勝訴の最高裁判決(脚注1)が下された。
本件は、第一審(脚注2)で更正処分等の取消請求が認められ納税者が勝訴した後、第二審(脚注3)では逆転して敗訴し、また、後続事業年度に係る第2次デンソー事件では第一審(脚注4)、第二審(脚注5)とも納税者が勝訴しており、下級審の判断が分かれていたことから、最高裁による判断が注目されていた。
本件の最高裁判決は、海外の一定の地域に所在する子会社を束ねる地域統括業務と、タックス・ヘイブン対策税制の事業基準のいう「株式……の保有」(租税特別措置法66条の6第3項柱書。以下「株式保有業」という。)との関係を示すとともに、外国関係会社が複数の事業を営む場合における事業基準のいう「主たる事業」(同柱書)の判定方法を示したものとして重要である。本稿では、最高裁判決の判示を紹介した上でその実務への影響を検討する。
Ⅱ 事実関係
1 本件の原告である株式会社デンソー(以下「X社」という。)は、自動車関連部品の製造販売等を目的とする株式会社(内国法人)であり、35の国と地域で事業を展開し、全世界に200以上のグループ会社を有していた。
X社は、東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」という。)域内での集中生産・相互補完体制の円滑化を図るため、平成7年、豪亜地域における各拠点間の事業活動の調整及びサポートを行う目的で、シンガポールに地域統括センターとしてB社を設立し、同10年、ASEAN域内のX社のグループ会社に対する統率力を高めるために、B社を含むASEAN・台湾地域のグループ会社の保有株式を現物出資してシンガポールにA社を設立した。このA社が、本件でタックス・ヘイブン対策税制の適用の有無が問題となった特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項)である。
A社は、平成19年3月31日及び同20年3月31日において、X社の100%子会社であり、同18年4月1日から同19年3月31日まで及び同年4月1日から同20年3月31日までの各事業年度(以下、それぞれ「2007事業年度」、「2008事業年度」といい、併せて「対象事業年度」という。)において、ASEAN諸国等に存する子会社13社及び関連会社3社の株式を保有していた。
A社のシンガポールにおける所得に対する租税の負担割合は、2007事業年度では22.89%、2008事業年度では12.78%であった。
2(1)A社は、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図るため、設立以来、順次業務を拡大し、対象事業年度当時、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善に係る地域統括に関する業務(以下「本件地域統括業務」という(脚注6)。)のほか、持株(株主総会、配当処理等)に関する業務、プログラム設計業務及びB社のための各種業務の代行業務を行っていた。
A社は、対象事業年度当時、ASEAN諸国、インド及びオーストラリア連邦に所在するX社のグループ会社13社(以下「域内グループ会社」という。)に対し本件地域統括業務を行い、個々の業務につき、域内グループ会社から第三者向け売上高等に一定の料率を乗じた金額又は実費相当額等を徴収していた。
(2)A社は、対象事業年度当時、シンガポールに開設された現地事務所において、現地に在住する日本人の代表取締役と現地勤務の従業員三十数人で業務を遂行していたところ、従業員のうち20人以上は本件地域統括業務に、その余はプログラム設計業務及びB社のための各種業務の代行業務に従事しており、持株に関する業務のみに従事している者はいなかった。
A社は、上記現地事務所を賃借し、事務用什器備品、車両、コンピューター等の有形固定資産を保有していたが、これらの施設等は全て持株に関する業務以外の業務に使用され、その大半は本件地域統括業務に供されていた。
(3)A社の収入金額のうち本件地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上額は、2007事業年度において約4.9億シンガポールドル、2008事業年度において約6.1億シンガポールドルに上り、いずれも収入金額の約85%を占めていた。他方、その所得金額(税引前当期利益)においては、保有株式の受取配当の占める割合が高かった(2007事業年度は約92.3%、2008事業年度は約86.5%)が、本件地域統括業務によって集中生産・相互補完体制の構築、維持及び発展が図られた結果、域内グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、対象事業年度においても、これがA社の域内グループ会社からの配当収入の中に相当程度反映されていた。
(4)A社は、対象事業年度当時、シンガポールにおいて株主総会及び取締役会を開催し、役員は同国において職務執行をしていた。また、A社は、上記現地事務所において会計帳簿を作成し、保管していた。
3 所轄税務署長は、X社に対し、A社の主たる事業は株式保有業であり、X社の平成20年3月期及び平成21年3月期の所得金額の計算上A社の課税対象留保金額に相当する金額は益金の額に算入されるとして、これらの事業年度の法人税の更正処分等をした。
これに対して、X社は、所轄国税局長への異議申立て及び国税不服審判所長への審査請求を経て、上記処分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
4 第一審(原々審)は、A社の主たる事業は株式保有業ではなく地域統括業務であったため事業基準を満たすとし、その他の適用除外基準である実体基準、管理支配基準及び所在地国基準もいずれも満たすため、X社の平成20年3月期及び平成21年3月期においてタックス・ヘイブン対策税制の適用が除外されると判示した。ところが、第二審(原審)は、A社は株式保有業を主たる事業とするものであり事業基準を満たさないとし、X社のこれらの事業年度においてタックス・ヘイブン対策税制が適用されると判示した。
Ⅲ 争点及び背景
1 争 点 一定の軽課税国(脚注7)に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(特定外国子会社等)について、その発行済株式の一定割合以上を有する等の要件を満たす内国法人は、原則としてタックス・ヘイブン対策税制の適用を受け、当該特定外国子会社等の所得を益金の額に算入して課税を受けることになる(租税特別措置法66条の6第1項)。もっとも、適用除外基準(事業基準、実体基準、管理支配基準及び所在地国基準又は非関連者基準)をすべて満たす場合、同税制の適用は除外される(租税特別措置法66条の6第3項)。そして、事業基準は、株式保有業等の一定の事業を主たる事業とするものでないことを、その要件としている。
最高裁における本件の争点は、A社が株式保有業を主たる事業とするものに該当し、事業基準を満たさないこととなるかどうかであった。当該争点に関して、A社による本件地域統括業務は株式保有業の一部に過ぎないのかという点、及びA社が営んでいる複数の事業のうちいずれが主たる事業に該当するのかという点が争われた。
2 背 景 本件の対象事業年度後、平成22年度税制改正により事業持株会社の特例が設けられた。これは、株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等であっても、他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する一定の業務(統括業務)を行っており、かつ当該他の法人の株式の保有を行う等の一定の要件を満たす場合には、事業基準を満たすものとする特例である(租税特別措置法66条の6第3項括弧書、同法施行令39条の17)。地域統括業務を行っていたA社は、平成22年度税制改正後であれば、事業持株会社の特例の適用によってタックス・ヘイブン対策税制の適用除外が認められる可能性もあったといえる。
他方で、上記改正後の租税特別措置法の文言(同括弧書)は、本件の第一審も指摘するとおり、一見、地域統括業務を行う特定外国子会社等が、株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等に包含されているようにも見えなくもないものであった。
そこで、上記のとおり、地域統括業務は株式保有業に包含され、主たる事業とはなり得ないのではないか、という点が争われることとなった。
Ⅳ 最高裁の判断及びその検討
1 地域統括業務は株式保有業に包含されない
(1)最高裁の判断 最高裁は、「株式を保有する者は、利益配当請求権等の自益権や株主総会の議決権等の共益権を行使することができるほか、保有に係る株式の運用として売買差益等を得ることが可能であり、それゆえ、他の会社に係る議決権の過半数の株式を保有する特定外国子会社等は、上記の株主権の行使を通じて、当該会社の経営を支配し、これを管理することができる。」「しかし、他の会社の株式を保有する特定外国子会社等が、当該会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務を行う場合、このような業務は、通常、当該会社の業務の合理化、効率化等を通じてその収益性の向上を図ることを直接の目的として、その内容も上記のとおり幅広い範囲に及び、これによって当該会社を含む一定の範囲に属する会社を統括していくものであるから、その結果として当該会社の配当額の増加や資産価値の上昇に資することがあるとしても、株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とは異なる独自の目的、内容、機能等を有するものというべきであって、上記の業務が株式の保有に係る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。」と判示し、一般論として地域統括業務が株式保有業に包含されるという解釈を否定した。
そのうえで、対象事業年度におけるA社による本件地域統括業務については、「地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものということができるのであって、個々の業務につき対価を得て行われていたことも併せ考慮すると、上記の地域統括業務が株主権の行使や株式の運用に関連する業務等であるということはできない。」として、株式保有業には該当しないと認定した。
さらに、最高裁は、適用除外基準において株式保有業が主たる事業でないことが必要とされる趣旨について、「株式の保有に係る事業はその性質上我が国においても十分に行い得るものであり、タックス・ヘイブンに所在して行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見いだし難いことにある。」と述べて、A社による本件地域統括業務は「地域経済圏の存在を踏まえて域内グループ会社の業務の合理化、効率化を目的とするものであって、当該地域において事業活動をする積極的な経済合理性を有することが否定できないから、これが株式の保有に係る事業に含まれると解することは上記規定の趣旨とも整合しない。」と述べ、原審の判断は制度趣旨に合致しないとした。
(2)検 討
ア 株式保有業と地域統括業務の関係 本件の原審が、「一定地域内にある被支配会社を統括するための諸業務」(地域統括業務)は株式保有業の一部をなすと判示していたのに対し、最高裁は、株式保有業と地域統括業務を以下のとおり別のものと位置づけたと考えられる。
| 株式保有業:対象会社の自益権及び共益権を行使し、株式の運用として売買差益等を得る事業(議決権の過半数保有による経営の支配・管理を含む) 地域統括業務:対象会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理・調整等に係る業務を行い、業務の合理化・効率化等を通じてその収益性の向上を図る業務 |
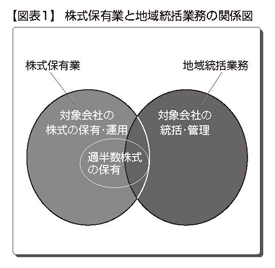
イ 株式保有業と地域統括業務の境界 「会社を統括し管理するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務」は株式保有業に含まれないとされたが、具体的事案においては、外国関係会社が行っている業務がこのような地域統括業務に当たるか、それとも株式保有業の枠を出ない株主権の行使にとどまるか、明確に判断がつかない場合もあるであろう。本件地域統括業務についても、最高裁は、以下の点に係る原審の詳細な事実認定を踏まえた上で初めて、本件地域統括業務が株式保有業に含まれないという判断を下したといえる。
| ・本件地域統括業務が多岐にわたる業務から成ること ・地域統括会社として各拠点の事業運営効率化・コスト低減を目的としていたこと ・個々の業務について対価を得ていたこと |
したがって、外国関係会社が行う業務が地域統括業務であり、株式保有業に含まれないとされるためには、当該業務が我が国ではなく現地で行う必要性の認められるだけの内容・目的を備えているか、被統括会社から対価を受領しているか、といったことが問われることになるであろう。
2 平成22年度税制改正を根拠に地域統括業務が株式保有業に包含されるということはできない
(1)最高裁の判断 本件の対象事業年度後の平成22年度税制改正で導入された事業持株会社の特例との関係については、最高裁は、「これによって事業基準を満たすこととなる統括会社は、もともと株式等の保有を主たる事業とするものであって(同項(筆者注:租税特別措置法66条の6第3項)柱書き)、それ以外の統括会社はその対象となるものではないから」、平成22年度税制改正の「経過を根拠に上記の統括業務が株式の保有に係る事業に包含される関係にあるものということはできず、A社の行っていた地域統括業務が株式の保有に係る事業に含まれるということはできない。」と判示した。
(2)検 討
ア 事業持株会社との関係 前述のとおり、事業持株会社の特例により、株式保有業を主たる事業とするもののうち統括業務を行う一定のもの(事業持株会社)は、事業基準を満たすこととされた。原審は、当該改正が、地域統括業務が株式保有業に包含されるという原審の理解と整合する旨を述べていた。
これに対し、最高裁は、株式保有業を主たる事業とするものの中に事業持株会社の特例を利用できる統括会社が存在するからといって、統括会社はおよそすべて株式保有業を主たる事業とするというわけではなく、地域統括業務等を主たる事業とする統括会社も存在し、そのような会社は事業持株会社特例を用いるまでもなく事業基準を満たすことを認めた。
これらの関係は、図表2(脚注8)及び図表3のとおり整理できるであろう。地域統括業務を営む外国関係会社は、事業持株会社の特例を使うほかに、主たる事業を株式保有業以外(地域統括業務等)とすることによっても、事業基準を満たしてタックス・ヘイブン税制の適用除外を受けられることが、本件の最高裁判決により明らかとなったといえる。
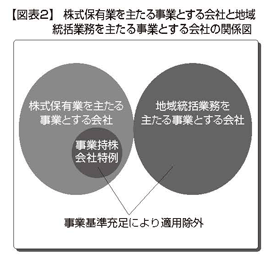
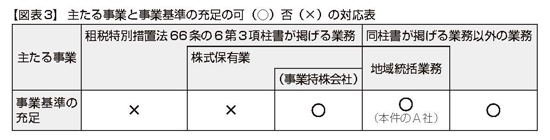 イ 地域統括業務を主たる事業とする類型の意義
平成22年度税制改正後の現在においては、地域統括業務を行っている外国関係会社は、事業持株会社の特例の要件を満たすようにプランニングされている例が多いと思われる。また、本件で最高裁が提示した総合考慮による主たる事業の認定は、事業持株会社の特例と比べ、事業基準を充足できるか否かについての予測可能性に欠ける。そのため、これらの会社を適用除外とするためには、今後も事業持株会社の特例が主に利用されるであろう。
イ 地域統括業務を主たる事業とする類型の意義
平成22年度税制改正後の現在においては、地域統括業務を行っている外国関係会社は、事業持株会社の特例の要件を満たすようにプランニングされている例が多いと思われる。また、本件で最高裁が提示した総合考慮による主たる事業の認定は、事業持株会社の特例と比べ、事業基準を充足できるか否かについての予測可能性に欠ける。そのため、これらの会社を適用除外とするためには、今後も事業持株会社の特例が主に利用されるであろう。もっとも、従来事業持株会社の特例の要件を満たせずにタックス・ヘイブン対策税制の対象となっていたもの(例えば、現地の外資規制の存在等の事情により、内国法人がその発行済株式の全部を保有することができない外国関係会社(租税特別措置法施行令39条の17第4項柱書)等が考えられる。)については、地域統括業務を主たる事業とすることによって事業基準を充足する余地が生まれたといえるだろう。
3 主たる事業は諸要素を総合的に勘案して判定する
(1)最高裁の判断 本件地域統括業務が株式保有業に含まれないとすると、次に、これらを含むA社の複数の業務のうちいずれが主たる事業に該当するかが問題となる。この点について、最高裁は、「特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当であ」るとし、また、複数の事業のうちいずれが主たる事業に該当するかについては、「当該特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当である。」と判示した。
本件については、「A社は、豪亜地域における地域統括会社として、域内グループ会社の業務の合理化、効率化を図ることを目的として、個々の業務につき対価を得つつ、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム、物流改善という多岐にわたる地域統括業務を有機的に関連するものとして域内グループ会社に提供していたものである。」として、A社が行っていた業務の目的及び内容並びに当該業務について対価を得ていたことを指摘した。そして、各考慮要素について以下の事実を認定した上で、これらを「総合的に勘案すれば、A社の行っていた地域統括業務は、相当の規模と実体を有するものであり、受取配当の所得金額に占める割合が高いことを踏まえても、事業活動として大きな比重を占めていた」として、対象事業年度においては本件地域統括業務がA社の主たる事業であったと認定し、事業基準の充足を認めた。
| 収入金額:本件地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上高は収入金額の約85%に上っていたこと 所得金額:保有株式の受取配当の占める割合が8、9割であったものの、その配当収入の中には本件地域統括業務によって域内グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利益が相当程度反映されていたこと 使用人の数:本件現地事務所で勤務する従業員の多く(三十数人中20人以上)が本件地域統括業務に従事していたこと 固定施設の状況:A社の保有する有形固定資産の大半が本件地域統括業務に供されていたこと |
上記基準は複数の考慮要素を挙げていることから、各考慮要素で最も重要とされる事業が分かれてしまう場合、どのようにして主たる事業が判定されるかが問題となる。また、主たる事業は「当該事業年度における」事業活動から判定するとされているため、例えば従来地域統括業務が主たる事業とされていた会社が、ある事業年度に株式を譲渡する等して一時的に株式保有業に係る多額の収入金額及び所得金額を得た場合に、その事業年度においては株式保有業が主たる事業に該当して事業基準を充足しなくなってしまうのか、という問題もある。
本件も、収入金額、使用人の数及び固定施設の状況の観点からは本件地域統括業務が最も重要といえるが、他方で、所得金額の観点からは受取配当が全体の8、9割を占めるため株式保有業が最も重要ともいえ、考慮要素間で重要性が分かれていると考えられる事案であった。この点について、最高裁は、本件においては「地域統括業務によって域内グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利益」が配当収入に相当程度反映されていたと述べて、所得金額の観点についても本件地域統括業務が間接的に重要な影響を与えていたことに言及している。
この最高裁の理由付けは、地域統括業務と株式保有業の間であれば収入金額においても流用でき、また域内グループ会社(被統括会社)に生じる利益は配当金額だけでなくその企業価値・株式の価額にも影響しうるため、株式譲渡によって一時的に株式保有業に係る多額の収入金額及び所得金額を得た場合にも流用できる可能性がある。
他方、地域統括業務と株式保有業のように一方の業務が他方の業務における収入金額や所得金額の増加に貢献する関係がない場合で、上記考慮要素間で重要性が分かれたときに、主たる事業がどのように判断されるのかは明らかではない。今後の判例の展開が待たれる。
Ⅴ 平成29年度税制改正
タックス・ヘイブン対策税制は、平成29年度税制改正によりその構成を大きく変えることになった。これは、租税回避リスクを外国子会社の租税負担割合により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改めるものであると説明されており(脚注11)、従来租税負担割合によりいったん制度の対象とされた後の適用除外基準として機能していた事業基準、実体基準、管理支配基準及び所在地国基準又は非関連者基準(これらの基準をすべて満たす場合に、タックス・ヘイブン対策税制の適用が除外される。)は、改正後は、そもそもタックス・ヘイブン対策税制の対象となるかという制度発動要件(経済活動基準。上記基準のいずれかに該当しない場合に、タックス・ヘイブン対策税制が適用される。)にその位置づけを変えることとなった。このほか、平成29年度税制改正では、ペーパーカンパニー等の特定外国関係会社に対する合算課税や、受動的所得に対する部分合算課税の拡大等、重要な改正がなされている。これらの改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以降に開始する事業年度から適用される(平成29年度税制改正・改正法附則70条)。
ただ、上記のとおり適用除外基準は制度発動要件(経済活動基準)に位置づけを変えるものの、各基準の中身は改正後も大きくは変わらない。特に、事業基準を定める改正後租税特別措置法66条の6第2項3号イのうち株式保有業に関連する文言は、現行法の同条3項柱書の該当する箇所と同様の文言となっている。したがって、平成29年度税制改正適用後においても、地域統括業務と株式保有業との関係や主たる事業の判定方法を示した本件の最高裁判決は、先例として意義を有するであろう。
| 仲谷栄一郎 なかたに えいいちろう 東京大学法学部卒業。弁護士。アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。『租税条約と国内税法の交錯』(第36回日本公認会計士協会学術賞受賞、共著、商事法務)、『外国企業との取引と税務』(共著、商事法務)ほか、著書・論文多数。 梶原康平 かじわら こうへい 東京大学経済学部、同法科大学院卒業。弁護士。アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。論文として、『平成28年度税制改正大綱への対応 役員給与に関する改正』(共著、ザ・ローヤーズ2016年3月号)など。 |
脚注
1 最三小判平成29年10月24日裁判所ウェブサイト
2 名古屋地判平成26年9月4日税務訴訟資料264号順号12524
3 名古屋高判平成28年2月10日訟務月報62巻11号1943頁
4 名古屋地判平成29年1月26日ウエストロー・ジャパン文献番号2017WLJPCA01266005
5 名古屋高判平成29年10月18日ウエストロー・ジャパン文献番号2017WLJPCA10186001
6 最高裁は、判決文中で当該業務を単に「地域統括業務」と定義している。本稿においては、当該業務が、一般的な意味で地域を統括する業務を意味するのではなく、A社が具体的に行っていた業務を意味していることを踏まえて、「本件地域統括業務」と呼ぶことにする。
7 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域、及び税負担割合が20%未満となる国又は地域(租税特別措置法施行令39条の14第1項参照)。なお、平成22年度税制改正前の本件当時は、租税負担割合に係る要件は25%以下とされていた。
8 前掲の図表1が事業・業務(株式保有業と地域統括業務)の関係を示したものであるのに対し、図表2は会社(株式保有業を主たる事業とする会社と地域統括業務を主たる事業とする会社)の関係を示したものである。例えば、図表2の株式保有業を主たる事業とする会社(左側の円)の中には、地域統括業務を(従たる事業として)行っているものも含まれる。
9 東京地判平成28年5月13日判例秘書判例番号L07131248、東京地判平成20年10月3日訟務月報55巻7号2532頁、東京地判平成20年8月28日訟務月報55巻7号2532頁(東京高判平成21年2月26日税務訴訟資料259号順号11149で是認)、静岡地判平成7年11月9日訟務月報42巻12号3042頁(東京高判平成8年6月19日税務訴訟資料216号619頁、最二小判平成9年9月12日税務訴訟資料228号565頁で是認)等
10 租税特別措置法施行令39条の14第2項4号における「主たる事業」の判定に係る、租税特別措置(法人税関係)基本通達66の6-8とも、基本的に同内容となっている。
11 財務省『平成29年度 税制改正の解説』658頁
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















