解説記事2018年02月19日 【特別解説】 のれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト(2018年2月19日号・№727)
特別解説
のれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
はじめに
のれんと耐用年数を確定できない無形資産は、いずれも償却をしてはならないとされていることから、耐用年数にわたって毎期定額償却を行う耐用年数を確定できる無形資産と比較すると、減損テストが果たす役割が大きい。そのため、毎年及び当該無形資産又はのれんに減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストを行わなければならない(IAS第38号「無形資産」第107項、108項)とされている。
資産の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合に、かつ、その場合にのみ、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額(資産の処分コスト控除後の公正価値及び使用価値のいずれか高い金額)まで減額しなければならない。当該減額が減損損失であるとされており、減損損失を計上した場合には、当期中に減損損失の認識をした個別の資産(のれんを含む)又は資金生成単位に関して、企業は次の事項を開示しなければならない(IAS第36号「資産の減損」第130項)。
(a)減損損失の認識又は戻入れに至った事象及び状況
(b)認識又は戻入れをした減損損失の金額
(c)個別資産について
(i)当該資産の性質
(ii)もし企業が、IFRS第8号「事業セグメント」に従ってセグメント情報を報告している場合には、資産が所属する報告セグメント
(d)資金生成単位について
(i)当該資金生成単位の記述(例えば、生産ライン、工場、事業、地域、又はIFRS第8号に定義されている報告セグメントのうち、どれに該当するか)
(ii)資産の種類ごとに、認識又は戻入れをした減損損失の金額、また企業がIFRS第8号に従ってセグメント情報を報告する場合、報告セグメント別に、認識又は戻入れをした減損損失の金額
(iii)当該資金生成単位を識別するための資産の集約が、以前の資金生成単位の回収可能価額の見積り(もしあれば)から変更されている場合には、企業は資産の現在と以前の集約方法の記述、及び資金生成単位の識別方法の変更理由
(e)当該資産(資金生成単位)の回収可能価額及び当該資産(資金生成単位)の回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値又は使用価値のどちらであるか
(f)回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値である場合には、企業は以下の情報を開示しなければならない。
(i)当該資産(資金生成単位)の公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキー(IFRS第13号参照)のレベル(「処分コスト」が観察可能かどうかは考慮に入れない)
(ii)公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値測定について、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いた評価技法の記述。評価技法の変更があった場合には、企業は当該変更及びそれを行った理由を開示しなければならない。
(iii)公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値測定について、経営者が処分コスト控除後の公正価値の算定の基礎とした主要な各仮定。主要な仮定とは、資産(資金生成単位)の回収可能価額が非常に敏感に反応する仮定をいう。企業は、処分コスト控除後の公正価値を現在価値技法を用いて測定している場合には、最新の測定及び過去の測定に使用した割引率も開示しなければならない。
(g)回収可能価額が使用価値である場合には、使用価値の現在及び過去の見積り(もしあれば)に用いた割引率
本稿では、IFRSを適用して連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を公表した日本企業(IFRS任意適用日本企業)が行ったのれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テストに関する開示のうち、記載が充実しているものや特徴的なものを紹介することとしたい。
日本板硝子による開示(2017年3月期)
日本板硝子は、減損損失の計上について、特に使用価値の算定方法を中心に、感応度分析に至るまで非常に充実した開示を行っている。のれんの減損テストに使用される主要な仮定として、将来営業キャッシュ・フローの予測期間や成長率、割引率等については大半の企業が何らかの開示を行っているが、日本板硝子はそれらに加え、ガラス製品の販売価格、市場数量の成長率並びに投入コストといった企業固有の仮定についても詳細な開示を行っている点に特徴がある。
また、日本板硝子はのれんに加え、ピルキントン・ブランドを「耐用年数を確定できない無形資産」と判定しており、減損テストのためにこれを各資金生成単位に配分するとともに、のれんの減損テストの一部として減損テストを実施している。
「IAS第36号「資産の減損」に従い、当連結会計年度末(2017年3月末)において、のれんに対する減損テストを行いました。当連結会計年度(2017年3月期)及び前連結会計年度(2016年3月期)の減損テストでは、資金生成単位毎の帳簿価額(当該資金生成単位に配分されたのれんと無形資産の額を含む)と当該資金生成単位の使用価値との比較を行いました。使用価値は、各資金生成単位の将来営業キャッシュ・フローを以下の表に記載の割引率で割り引いた現在価値として算定しております。将来営業キャッシュ・フローの見積額は、当社グループの業績見通しを基礎としており、業績見通しの対象年数は、最長で、通常当社グループが見通しの対象年数とする4年間としております(この期間以降は、一定の成長率での増加が永続すると仮定)。
各資金生成単位の将来営業キャッシュ・フローの見積りにおいて、欧州と北米については2.0%の年間成長率(前連結会計年度(2016年3月期)は2.0%)が、またその他の地域については建築用ガラス事業及び自動車用ガラス事業においてそれぞれ2.0%、3.5%の年間成長率(前連結会計年度はそれぞれ2.0%、3.5%)が、それぞれ永続するものと仮定しております。割引率については、当社グループの加重平均資本コストに適切なリスク・プレミアムを織り込んだうえで、各資金生成単位ごとに税引前ベースの割引率として算定しております(中略)。
のれんの減損テストに使用される主要な仮定は以下の通りです(編注:表1参照)。
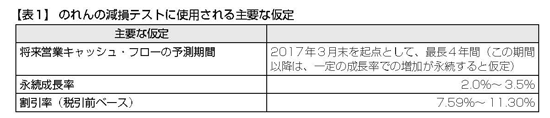
その他の主要な仮定としては、ガラス製品の販売価格、市場数量の成長率並びに投入コストが挙げられます。ガラス製品の販売価格は、対象期間における需要と供給の動向に関する現在までの趨勢及び予想に基づき予測しております。市場数量の成長率は、各国・地域におけるGDP成長率や各市場におけるガラス産業に固有の要素(例えば規制環境の変化など)を参照して見積っております。また、投入コストについては、最近のサプライヤーとの交渉内容や業界における一般的な見通し情報を考慮した上で見積っております。
減損テストにおいて主要な感応度を示す仮定は、割引率です。もし割引率が上記の表に記載された率よりも上昇するならば、各資金生成単位における減損計上までの余裕度は低下します。
自動車用ガラス事業のその他の地域は、減損計上までの余裕度の絶対額が最も小さい資金生成単位です。自動車用ガラス事業のその他の地域に配分された残存金額について、0.53%の割引率の上昇があった場合、減損損失までの余裕度はゼロになるものと想定しております。
当社グループは、自動車用ガラス事業のその他の地域以外の資金生成単位については、減損計上までの余裕度を十分に有していると考えております。
貸借対照表上に計上されるピルキントン・ブランドは、減損テストのため、以下の通り各資金生成単位に配分しております(編注:表2参照)。ピルキントン・ブランドの減損テストは、のれんの減損テストの一部として実施されます。」

ノーリツ鋼機による開示(2017年3月期)
ノーリツ鋼機は、使用価値のみならず、処分コスト控除後の公正価値に関しても充実した開示を行っている。
「(4)のれん及び耐用年数が確定できない無形資産を含む資金生成単位の減損テスト
各資金生成単位に配分されたのれん及び耐用年数が確定できない無形資産は以下のとおりであります(編注:表3参照)。
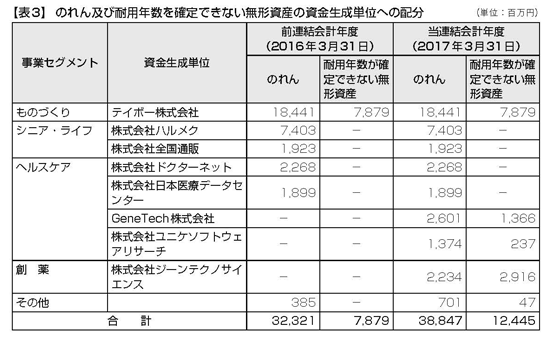
当社グループは、のれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位について、少なくとも年1回の減損テストを行っており、さらに減損の兆候がある場合にはその都度、減損テストを行っております。のれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位の回収可能価額の算定方法は、以下のとおりです。
使用価値:テイボー株式会社、株式会社ハルメク、全国通販株式会社、株式会社ドクターネット、株式会社日本医療データセンター、GeneTech株式会社、株式会社ユニケソフトウェアリサーチ及びその他
処分コスト控除後の公正価値:株式会社ジーンテクノサイエンス
使用価値は、経営者によって承認された5年のキャッシュ・フローの見積額を基礎として算定し、当該期間を超過した期間のキャッシュ・フローは一定の成長率(1%)により見込んでおります。割引率は、資金生成単位が行う事業の類似企業の資本コストを用いて算定しております。なお成長率は資金生成単位が属する国における加重平均成長率であり、外部情報とも整合的であります。
処分コスト控除後の公正価値は、活発な市場における相場価格に基づいて算定しております。
重要なのれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位の使用価値の算定に用いた税引前の割引率は次のとおりであります(編注:表4参照)。
株式会社ジーンテクノサイエンスの2017年3月31日の株価は1,395円であり、1株当たり連結簿価を上回っておりました。
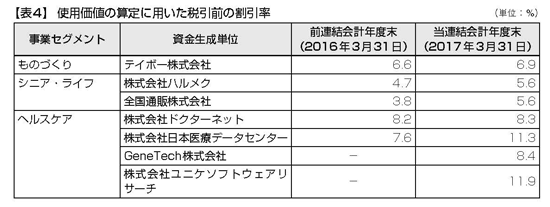
減損テストの結果、いずれの資金生成単位においても減損損失を認識しておりません。
資金生成単位の使用価値を算定して実施した減損テストにおいて主要な感応度を示す仮定は割引率です。もし割引率が上記の表に記載された率よりも上昇するならば、各資金生成単位における減損計上までの余裕度は低下します。割引率の変動に対する減損計上までの余裕度が低く、かつその影響額が大きい資金生成単位はテイボー株式会社であります。割引率以外の条件が一定と仮定した場合において、減損計上までの余裕度がゼロとなる割引率までの差と、更に割引率が1ポイント上昇した場合に発生する減損損失の見込額は以下のとおりであります(編注:表5参照)。
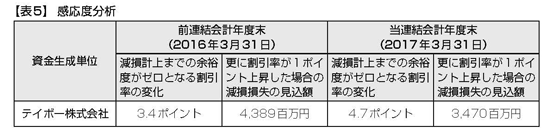
一方、資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値の測定は、株価のみに依拠せず、株価以外のインプットである支配プレミアムを考慮して測定しております。株式会社ジーンテクノサイエンスの株価及び時価総額の大幅な長期間にわたる下落及び減少は、公正価値の見積りに影響し、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の将来の大幅な減損につながる可能性があります。」
ソフトバンクによる開示(2017年3月期)
米国のスプリント社や英国のアーム社の買収により、非償却の無形資産残高が9兆円弱(のれん:4.1兆円、耐用年数を確定できない無形資産:4.8兆円)に達するソフトバンクは、回収可能価額の測定方法等について次のような開示を行っている。
「各資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額の測定方法は、以下の通りです。
使用価値:ソフトバンク、マーケティングソリューション、ショッピング、決済金融、一休、ブライトスター、ブライトスターの米国・カナダ地域、中南米地域、アジア・オセアニア地域、欧州・アフリカ地域、ソフトバンクコマース&サービス(株)
処分コスト控除後の公正価値:スプリント、ヤフー、アーム
使用価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後5年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位または資金生成単位グループの税引前の割引率7.21%~16.17%により現在価値に割引いて測定しています。なお、キャッシュ・フローの見積りにおいて、5年超のキャッシュ・フローは、0%~2.34%の成長率で逓増すると仮定しています。
処分コスト控除後の公正価値は、スプリントおよびヤフーについては、活発な市場における相場価格に基づいて測定しています。アームについては、市場参加者の想定する仮定に基づき、市場参加者が将来受け取ると期待するキャッシュ・フローを、今後10年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額に反映させ、税引後の割引率9%により現在価値に割引いて測定しています。10年超のキャッシュ・フローについて、11年目は19%、12年目は10%の成長率と仮定し、13年目以降は、2%の成長率で逓増すると仮定しています。なお、公正価値測定において、観察可能でないインプットを使用しているため、レベル3に分類しています。」
大塚ホールディングスによる開示(2016年12月期)
耐用年数を確定できない無形資産の減損テストは、のれんの減損テストの一部として実施される場合が多く、開示ものれんの減損テストと一つにまとめられるケースがほとんどであるが、大塚ホールディングスは、次のように、ブランドの減損テストについて独自の開示を行っている。
「(3)耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
当連結会計年度の商標権に含まれる耐用年数を確定できない無形資産は、主としてニュートリションエサンテSASグループ(ニュートラシューティカルズ関連事業)が保有するブランドであり、その帳簿価額は22,056百万円であります。
それぞれのブランドは、ロイヤリティ免除法と超過収益法を適用して、毎期又は減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施しております。使用価値は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した今後5年分の事業計画と、税引前加重平均資本コストに、必要に応じて特定のカントリーリスク及び為替リスクを加味したものに等しい割引率(6.5~14.0%)を使用して算定しております。成長率は、資金生成単位の属する産業もしくは国における長期の平均成長率を勘案して0~3.5%と決定しており、市場の長期の平均成長率を超過しておりません。いずれの場合も、使用価値は帳簿価額を十分に上回っており、減損テストに使用した主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変化したとしても、使用価値が帳簿価額を下回る可能性は低いと判断しております。」
おわりに
長期にわたる低金利政策や景気の拡大、堅調な株価の後押し等を受けて、我が国の企業による海外企業等のM&Aが引き続き高水準となっている。海外に幅広く事業を展開していることが多く、のれんの毎期定額償却が求められないIFRS任意適用日本企業においては、そのような傾向がより顕著に見られるといえるかもしれない。冒頭にも記したが、毎期の定額償却を求められないのれんや耐用年数を確定できない無形資産の残高が積み上がっていくような局面においては、特に、これらの資産の収益性を適時かつ適切に評価していくことが欠かせない。
有形固定資産やのれんを含む無形資産の減損テストは、煩雑かつ難解で、手間もコストもかかりすぎると言われて久しい。そして、減損損失の金額の算定過程や仮定、前提条件等を記述した注記も、膨大かつ分かりにくいものになりがちといえる。本稿で取り上げた開示例も量は多いが、詳細に読み解くと、各社が展開する事業領域ごとの今後の収益性やリスク等を経営者がどのように見ているかがよく理解できる内容になっている。
我が国の「固定資産の減損にかかる会計基準」や適用指針も一通りの開示を要求してはいるものの、使用価値の算定方法や感応度分析等に関する開示等はIFRSと比較するとまだ弱いと考えられる。のれんや耐用年数を確定できない無形資産の重要性がますます増してきている昨今において、減損損失の計上過程等について詳細かつ分かりやすい開示が行われることが望まれる。
のれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
はじめに
のれんと耐用年数を確定できない無形資産は、いずれも償却をしてはならないとされていることから、耐用年数にわたって毎期定額償却を行う耐用年数を確定できる無形資産と比較すると、減損テストが果たす役割が大きい。そのため、毎年及び当該無形資産又はのれんに減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストを行わなければならない(IAS第38号「無形資産」第107項、108項)とされている。
資産の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合に、かつ、その場合にのみ、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額(資産の処分コスト控除後の公正価値及び使用価値のいずれか高い金額)まで減額しなければならない。当該減額が減損損失であるとされており、減損損失を計上した場合には、当期中に減損損失の認識をした個別の資産(のれんを含む)又は資金生成単位に関して、企業は次の事項を開示しなければならない(IAS第36号「資産の減損」第130項)。
(a)減損損失の認識又は戻入れに至った事象及び状況
(b)認識又は戻入れをした減損損失の金額
(c)個別資産について
(i)当該資産の性質
(ii)もし企業が、IFRS第8号「事業セグメント」に従ってセグメント情報を報告している場合には、資産が所属する報告セグメント
(d)資金生成単位について
(i)当該資金生成単位の記述(例えば、生産ライン、工場、事業、地域、又はIFRS第8号に定義されている報告セグメントのうち、どれに該当するか)
(ii)資産の種類ごとに、認識又は戻入れをした減損損失の金額、また企業がIFRS第8号に従ってセグメント情報を報告する場合、報告セグメント別に、認識又は戻入れをした減損損失の金額
(iii)当該資金生成単位を識別するための資産の集約が、以前の資金生成単位の回収可能価額の見積り(もしあれば)から変更されている場合には、企業は資産の現在と以前の集約方法の記述、及び資金生成単位の識別方法の変更理由
(e)当該資産(資金生成単位)の回収可能価額及び当該資産(資金生成単位)の回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値又は使用価値のどちらであるか
(f)回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値である場合には、企業は以下の情報を開示しなければならない。
(i)当該資産(資金生成単位)の公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒエラルキー(IFRS第13号参照)のレベル(「処分コスト」が観察可能かどうかは考慮に入れない)
(ii)公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値測定について、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いた評価技法の記述。評価技法の変更があった場合には、企業は当該変更及びそれを行った理由を開示しなければならない。
(iii)公正価値ヒエラルキーのレベル2及びレベル3に区分される公正価値測定について、経営者が処分コスト控除後の公正価値の算定の基礎とした主要な各仮定。主要な仮定とは、資産(資金生成単位)の回収可能価額が非常に敏感に反応する仮定をいう。企業は、処分コスト控除後の公正価値を現在価値技法を用いて測定している場合には、最新の測定及び過去の測定に使用した割引率も開示しなければならない。
(g)回収可能価額が使用価値である場合には、使用価値の現在及び過去の見積り(もしあれば)に用いた割引率
本稿では、IFRSを適用して連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を公表した日本企業(IFRS任意適用日本企業)が行ったのれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テストに関する開示のうち、記載が充実しているものや特徴的なものを紹介することとしたい。
日本板硝子による開示(2017年3月期)
日本板硝子は、減損損失の計上について、特に使用価値の算定方法を中心に、感応度分析に至るまで非常に充実した開示を行っている。のれんの減損テストに使用される主要な仮定として、将来営業キャッシュ・フローの予測期間や成長率、割引率等については大半の企業が何らかの開示を行っているが、日本板硝子はそれらに加え、ガラス製品の販売価格、市場数量の成長率並びに投入コストといった企業固有の仮定についても詳細な開示を行っている点に特徴がある。
また、日本板硝子はのれんに加え、ピルキントン・ブランドを「耐用年数を確定できない無形資産」と判定しており、減損テストのためにこれを各資金生成単位に配分するとともに、のれんの減損テストの一部として減損テストを実施している。
「IAS第36号「資産の減損」に従い、当連結会計年度末(2017年3月末)において、のれんに対する減損テストを行いました。当連結会計年度(2017年3月期)及び前連結会計年度(2016年3月期)の減損テストでは、資金生成単位毎の帳簿価額(当該資金生成単位に配分されたのれんと無形資産の額を含む)と当該資金生成単位の使用価値との比較を行いました。使用価値は、各資金生成単位の将来営業キャッシュ・フローを以下の表に記載の割引率で割り引いた現在価値として算定しております。将来営業キャッシュ・フローの見積額は、当社グループの業績見通しを基礎としており、業績見通しの対象年数は、最長で、通常当社グループが見通しの対象年数とする4年間としております(この期間以降は、一定の成長率での増加が永続すると仮定)。
各資金生成単位の将来営業キャッシュ・フローの見積りにおいて、欧州と北米については2.0%の年間成長率(前連結会計年度(2016年3月期)は2.0%)が、またその他の地域については建築用ガラス事業及び自動車用ガラス事業においてそれぞれ2.0%、3.5%の年間成長率(前連結会計年度はそれぞれ2.0%、3.5%)が、それぞれ永続するものと仮定しております。割引率については、当社グループの加重平均資本コストに適切なリスク・プレミアムを織り込んだうえで、各資金生成単位ごとに税引前ベースの割引率として算定しております(中略)。
のれんの減損テストに使用される主要な仮定は以下の通りです(編注:表1参照)。
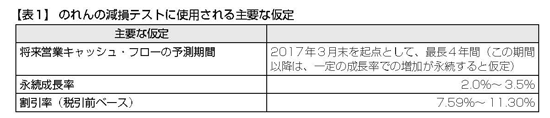
その他の主要な仮定としては、ガラス製品の販売価格、市場数量の成長率並びに投入コストが挙げられます。ガラス製品の販売価格は、対象期間における需要と供給の動向に関する現在までの趨勢及び予想に基づき予測しております。市場数量の成長率は、各国・地域におけるGDP成長率や各市場におけるガラス産業に固有の要素(例えば規制環境の変化など)を参照して見積っております。また、投入コストについては、最近のサプライヤーとの交渉内容や業界における一般的な見通し情報を考慮した上で見積っております。
減損テストにおいて主要な感応度を示す仮定は、割引率です。もし割引率が上記の表に記載された率よりも上昇するならば、各資金生成単位における減損計上までの余裕度は低下します。
自動車用ガラス事業のその他の地域は、減損計上までの余裕度の絶対額が最も小さい資金生成単位です。自動車用ガラス事業のその他の地域に配分された残存金額について、0.53%の割引率の上昇があった場合、減損損失までの余裕度はゼロになるものと想定しております。
当社グループは、自動車用ガラス事業のその他の地域以外の資金生成単位については、減損計上までの余裕度を十分に有していると考えております。
貸借対照表上に計上されるピルキントン・ブランドは、減損テストのため、以下の通り各資金生成単位に配分しております(編注:表2参照)。ピルキントン・ブランドの減損テストは、のれんの減損テストの一部として実施されます。」

ノーリツ鋼機による開示(2017年3月期)
ノーリツ鋼機は、使用価値のみならず、処分コスト控除後の公正価値に関しても充実した開示を行っている。
「(4)のれん及び耐用年数が確定できない無形資産を含む資金生成単位の減損テスト
各資金生成単位に配分されたのれん及び耐用年数が確定できない無形資産は以下のとおりであります(編注:表3参照)。
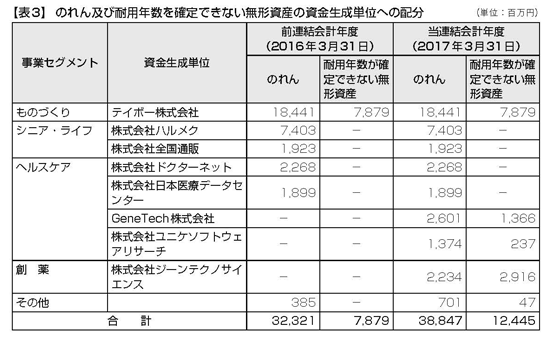
当社グループは、のれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位について、少なくとも年1回の減損テストを行っており、さらに減損の兆候がある場合にはその都度、減損テストを行っております。のれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位の回収可能価額の算定方法は、以下のとおりです。
使用価値:テイボー株式会社、株式会社ハルメク、全国通販株式会社、株式会社ドクターネット、株式会社日本医療データセンター、GeneTech株式会社、株式会社ユニケソフトウェアリサーチ及びその他
処分コスト控除後の公正価値:株式会社ジーンテクノサイエンス
使用価値は、経営者によって承認された5年のキャッシュ・フローの見積額を基礎として算定し、当該期間を超過した期間のキャッシュ・フローは一定の成長率(1%)により見込んでおります。割引率は、資金生成単位が行う事業の類似企業の資本コストを用いて算定しております。なお成長率は資金生成単位が属する国における加重平均成長率であり、外部情報とも整合的であります。
処分コスト控除後の公正価値は、活発な市場における相場価格に基づいて算定しております。
重要なのれん又は耐用年数が確定できない無形資産が配分された資金生成単位の使用価値の算定に用いた税引前の割引率は次のとおりであります(編注:表4参照)。
株式会社ジーンテクノサイエンスの2017年3月31日の株価は1,395円であり、1株当たり連結簿価を上回っておりました。
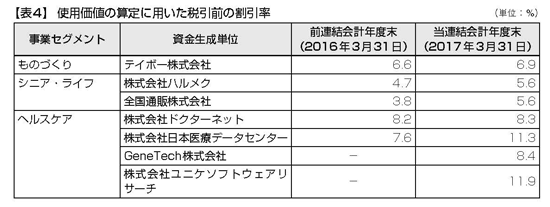
減損テストの結果、いずれの資金生成単位においても減損損失を認識しておりません。
資金生成単位の使用価値を算定して実施した減損テストにおいて主要な感応度を示す仮定は割引率です。もし割引率が上記の表に記載された率よりも上昇するならば、各資金生成単位における減損計上までの余裕度は低下します。割引率の変動に対する減損計上までの余裕度が低く、かつその影響額が大きい資金生成単位はテイボー株式会社であります。割引率以外の条件が一定と仮定した場合において、減損計上までの余裕度がゼロとなる割引率までの差と、更に割引率が1ポイント上昇した場合に発生する減損損失の見込額は以下のとおりであります(編注:表5参照)。
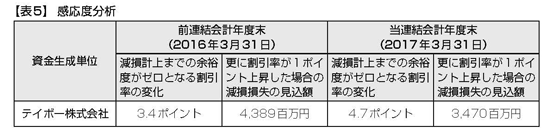
一方、資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値の測定は、株価のみに依拠せず、株価以外のインプットである支配プレミアムを考慮して測定しております。株式会社ジーンテクノサイエンスの株価及び時価総額の大幅な長期間にわたる下落及び減少は、公正価値の見積りに影響し、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の将来の大幅な減損につながる可能性があります。」
ソフトバンクによる開示(2017年3月期)
米国のスプリント社や英国のアーム社の買収により、非償却の無形資産残高が9兆円弱(のれん:4.1兆円、耐用年数を確定できない無形資産:4.8兆円)に達するソフトバンクは、回収可能価額の測定方法等について次のような開示を行っている。
「各資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額の測定方法は、以下の通りです。
使用価値:ソフトバンク、マーケティングソリューション、ショッピング、決済金融、一休、ブライトスター、ブライトスターの米国・カナダ地域、中南米地域、アジア・オセアニア地域、欧州・アフリカ地域、ソフトバンクコマース&サービス(株)
処分コスト控除後の公正価値:スプリント、ヤフー、アーム
使用価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、マネジメントが承認した今後5年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を、当該資金生成単位または資金生成単位グループの税引前の割引率7.21%~16.17%により現在価値に割引いて測定しています。なお、キャッシュ・フローの見積りにおいて、5年超のキャッシュ・フローは、0%~2.34%の成長率で逓増すると仮定しています。
処分コスト控除後の公正価値は、スプリントおよびヤフーについては、活発な市場における相場価格に基づいて測定しています。アームについては、市場参加者の想定する仮定に基づき、市場参加者が将来受け取ると期待するキャッシュ・フローを、今後10年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額に反映させ、税引後の割引率9%により現在価値に割引いて測定しています。10年超のキャッシュ・フローについて、11年目は19%、12年目は10%の成長率と仮定し、13年目以降は、2%の成長率で逓増すると仮定しています。なお、公正価値測定において、観察可能でないインプットを使用しているため、レベル3に分類しています。」
大塚ホールディングスによる開示(2016年12月期)
耐用年数を確定できない無形資産の減損テストは、のれんの減損テストの一部として実施される場合が多く、開示ものれんの減損テストと一つにまとめられるケースがほとんどであるが、大塚ホールディングスは、次のように、ブランドの減損テストについて独自の開示を行っている。
「(3)耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
当連結会計年度の商標権に含まれる耐用年数を確定できない無形資産は、主としてニュートリションエサンテSASグループ(ニュートラシューティカルズ関連事業)が保有するブランドであり、その帳簿価額は22,056百万円であります。
それぞれのブランドは、ロイヤリティ免除法と超過収益法を適用して、毎期又は減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施しております。使用価値は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した今後5年分の事業計画と、税引前加重平均資本コストに、必要に応じて特定のカントリーリスク及び為替リスクを加味したものに等しい割引率(6.5~14.0%)を使用して算定しております。成長率は、資金生成単位の属する産業もしくは国における長期の平均成長率を勘案して0~3.5%と決定しており、市場の長期の平均成長率を超過しておりません。いずれの場合も、使用価値は帳簿価額を十分に上回っており、減損テストに使用した主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変化したとしても、使用価値が帳簿価額を下回る可能性は低いと判断しております。」
おわりに
長期にわたる低金利政策や景気の拡大、堅調な株価の後押し等を受けて、我が国の企業による海外企業等のM&Aが引き続き高水準となっている。海外に幅広く事業を展開していることが多く、のれんの毎期定額償却が求められないIFRS任意適用日本企業においては、そのような傾向がより顕著に見られるといえるかもしれない。冒頭にも記したが、毎期の定額償却を求められないのれんや耐用年数を確定できない無形資産の残高が積み上がっていくような局面においては、特に、これらの資産の収益性を適時かつ適切に評価していくことが欠かせない。
有形固定資産やのれんを含む無形資産の減損テストは、煩雑かつ難解で、手間もコストもかかりすぎると言われて久しい。そして、減損損失の金額の算定過程や仮定、前提条件等を記述した注記も、膨大かつ分かりにくいものになりがちといえる。本稿で取り上げた開示例も量は多いが、詳細に読み解くと、各社が展開する事業領域ごとの今後の収益性やリスク等を経営者がどのように見ているかがよく理解できる内容になっている。
我が国の「固定資産の減損にかかる会計基準」や適用指針も一通りの開示を要求してはいるものの、使用価値の算定方法や感応度分析等に関する開示等はIFRSと比較するとまだ弱いと考えられる。のれんや耐用年数を確定できない無形資産の重要性がますます増してきている昨今において、減損損失の計上過程等について詳細かつ分かりやすい開示が行われることが望まれる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























