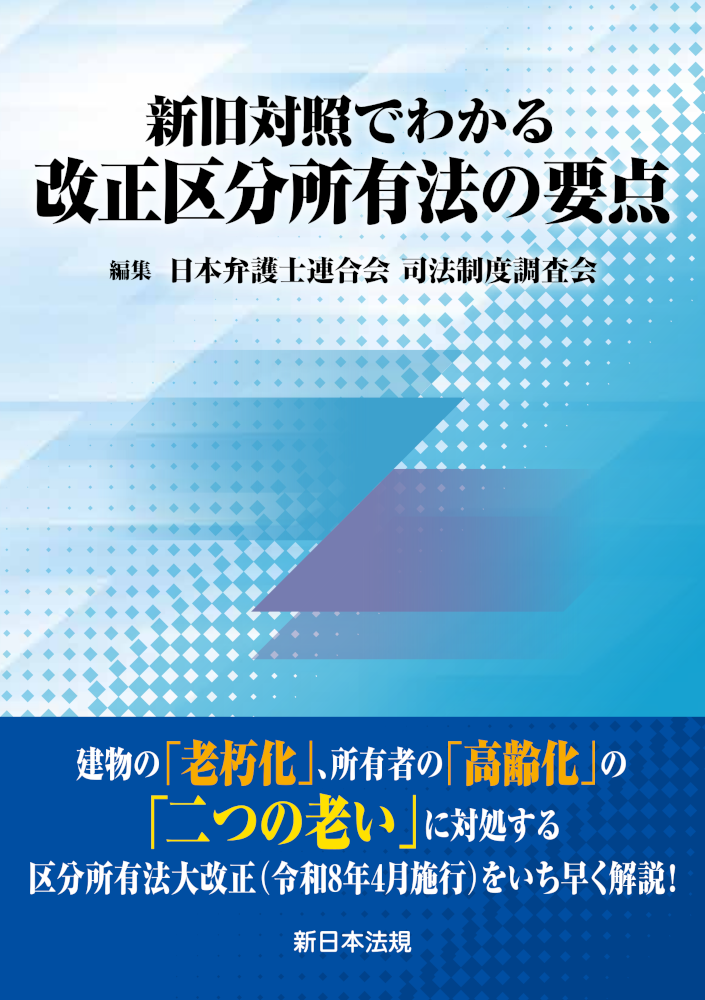解説記事2018年03月19日 【最新判決研究】 役員退職給与適正額の算定に平均功績倍率1.5倍を適用(2018年3月19日号・№731)
最新判決研究
役員退職給与適正額の算定に平均功績倍率1.5倍を適用
一、事実
(1)X(原告)は、資本金4950万円、売上金額13億5493万円余であり、ミシン部品等の製造、販売等を業とする株式会社であるが、平成20年8月21日から同21年8月20日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)分法人税につき、平成20年10月4日に死亡退任した代表取締役甲に対して、平成21年7月1日、臨時株主総会において決議した退職慰労金4億2000万円(以下「本件退職給与」という。)を支給し、所得金額の計算上損金の額に算入して所得金額6391万円余とする確定申告をした。
これに対し、所轄税務署長は、本件退職給与につき、法人税法上容認される適正額が2億1124万円であるから、当該金額を超える2億875万円余を所得金額に加算すべきとする更正等(以下「本件更正等」という。)をした。Xは、これを不服とし、前審手続を経て、平成27年12月21日、国(被告)に対し、本件更正等の取り消しを求めて本訴を提起した。
(2)甲は、昭和42年にXに入社した後、昭和56年にXの取締役に就任し、平成15年10月にXの代表取締役に就任し、同20年10月に死亡退職した。その死亡当時、Xの役員退職慰労金規定には、退職慰労金は株主総会の決議に基づき支給すること、退任時に報酬月額がある場合の退職慰労金の額は「退任時報酬月額×役員在任期間×退職時役位係数」の範囲内とすること、代表取締役の退任時役位係数は5.0倍とすること、在任期間は1年を単位とし、1年に満たない端数は1年とすること、在任中特別に功労があったと認められるときは上記規定による退職慰労金のほかに、その30%を超えない範囲において功労加算を行うことが定められていた。
なお、Xの株主総会の議事録によると、本件退職給与を算定する計算式は、次のようになっている。
240万円(最終報酬月額)×27年(勤続年数)×5倍(役員倍数)×1.3(功労加算金)=4億2120万円
二、争点と当事者の主張
1 争 点
(1)本件退職給与のうち、「不相当等に高額な部分の金額」
(2)国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無
(3)本件更正等における権利の濫用、信義則違反の有無
以上の争点のうち、(2)及び(3)については、当事者の主張と判決を紹介することにとどめる。
2 国の主張 (1)役員退職給与の相当額の算定方法としては、「平均功績倍率法」が、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の趣旨に最も合致する合理的な算定方法というべきである。
そして、国は、本件における同業類似法人として、①Xの所在地と経済事情が類似する地域である新潟県内に所在し、②Xと同種の事業である「金属製品製造業」を基幹の事業とし、③事業規模の類似性を判断する要素である売上金額に係るいわゆる倍半基準である事業年度(平成18年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了するもの)があり、④当該事業年度においてXと同じく死亡退職した代表取締役に対して退職給与の支給があり、⑤当該事業年度について不服申立て又は訴訟が係属中でないという抽出基準の全てを満たす法人を機械的に抽出した。この抽出基準及び抽出方法は合理的なものであるが、その同業類似法人は次のとおりの5法人(以下「本件類似法人」という。)であり、平均功績倍率は3.26である。
 (2)本件更正等において権利の濫用又は信義則違反はなく、過少申告について「正当な理由」もない。
(2)本件更正等において権利の濫用又は信義則違反はなく、過少申告について「正当な理由」もない。
3 Xの主張 (1)そもそも、役員退職給与は、法人と退職役員との間で交わされた委任契約に基づく職務執行の対価であり、その金額は職務執行の対価としての合理性がある限り相当であり、職務対価としての合理性があるか否かについては私的自治の原則が妥当し当該法人のみが判断することができるのであって、租税法により役員退職給与の費用性を否定することはできないというべきである。そして、本件のように、あらかじめ就業規則等により定められた規定により支給された退職給与については、役員退職給与の支払に乗じて利益処分を行うものでないことは明らかであるから、役員退職給与の額の相当性が推定されるというべきである。就業規則等の規定に基づく役員退職給与の支給であるか否かは、法人税法施行令70条2号には規定されていないものの、上記の解釈と異なり、このような場合に役員退職給与の損金算入が否定されるというのであれば、法人税法34条2項は、「不相当に高額な部分の金額」を政令に白紙委任するものとして、租税法律主義(憲法84条)に反するといわざるを得ない。
(2)Xは、平成9年に当時の専務が死亡したため、Xの役員退職慰労金規定に従って算出した退職慰労金を支給し、法人税の確定申告をしたが、更正処分等はされなかったところ、本件退職給与も同様にXの役員退職慰労金規定に従って算出したのであるという、Xの責めに帰することができない客観的事情があるから、過少申告につき「正当な理由」があるというべきである。
(3)本件更正等は、本件退職給与の支給に係る事情が既に本件事業年度末の平成21年8月には判明していたにもかかわらず平成26年7月に至ってされたものであり、時効が完成した後にされたものであるか、権利の濫用に当たり又は信義則に違反するから違法である。
三、判決要旨
請求一部認容。
1 本件退職給与のうち「不相当に高額な部分の金額」について(争点1)
(1)法人税法34条2項の趣旨は、法人の役員に対する退職給与等が法人の利益処分たる性質を有する場合があることから、法人所得の金額の計算上、一般に相当と認められる金額に限り必要経費として損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、実態に即した適正な課税を行うことにあると解される。
そして、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を役員退職給与について算定するに当たり考慮すべき事項を類型化して具体的に定めたものということができる。
この点、Xは、あらかじめ就業規則等に定められた規定により算定された役員退職給与は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を含まない旨を主張する。しかしながら、上述のとおりの同項の趣旨からすると、就業規則等の規定により役員退職給与が算定されたとしても、当該規定の内容自体やその適用の過程で考慮された事情が一般に相当と認められるとは限らず、一般に相当と認められる金額を超える部分の金額については法人所得の金額の計算上損金算入を認めないこととし、実態に即した適正な課税を行うことが相当であるから、Xの上記主張は採用できない。
また、Xは、法人税法34条2項が政令に白紙委任するものとして租税法律主義(憲法84条)に違反する旨、法人税法施行令70条2号が法人税法34条2項の委任の範囲を超えるのみならず、課税要件の基準として不明確であり、納税者の予測可能性を欠き、適用違憲の可能性がある旨を主張する。しかしながら、法人税法34条2項の趣旨・目的が、上述のとおり、法人の役員に対する退職給与等の額のうち、一般に相当と認められる金額に限り、法人所得の金額の計算上必要経費として損金算入を認めることによって、実態に即した適正な課税を行うことにあることは、同項の規定内容自体から容易にうかがい知ることができることであり、また、法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」の考慮要素を役員退職給与について具体的に定めたものであって、その規定内容は、当該役員の在任期間、退職の事情、同業類似法人における退職給与の支給の状況等を考慮要素とするものであり、同項の上記の趣旨・目的に沿うものであるということができるから、同項の規定が政令に白紙委任したものであるとか、法人税法施行令70条2号がその委任の範囲を逸脱したものであるということはできない。
(2)国は、本件役員退職給与のうち相当であると認められる金額の算定方法として、平均功績倍率法を用いている。しかるところ、平均功績倍率法で用いる算定要素のうち、まず、最終月額報酬額は、通常、当該退職役員の在任期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに、当該退職役員の在任期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものということができる。また、勤続年数は、法人税法施行令70条2項が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当する。さらに、功績倍率は、これらの要素以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であり、同業類似法人における功績倍率の平均値(平均功績倍率)を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものということができる。このような各算定要素を用いて役員退職給与の相当額を算定しようとする平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われ、かつ、その平均功績倍率を当該法人に適用することが相当と認められる限り、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の趣旨に合致する合理的な方法というべきである。
この点、Xは、最高功績倍率法等の納税者により有利な算定方法を採用すべきである旨を主張する。しかしながら、功績倍率の平均値(平均功績倍率)を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られることは前記のとおりである一方、功績倍率の最高値は最高値に係る法人の特殊性等に影響されるものであって、指標としての客観性が劣るといわざるを得ない。また、後記のとおり本件において合理的と認められる抽出基準により同業類似法人を抽出した結果、5法人という相当数の法人が抽出されている上、これらの法人の功績倍率には極端なばらつきがなく、その偏差も平均功績倍率の30%程度の範囲内に収まっているのであって、本件において役員退職給与の相当額を算定するための指標として平均功績倍率を採用することが相当でないとか、最高功績倍率法がより適切であるとみるべき事情は見当たらない。したがって、Xの上記主張も採用できない。
(3)そこで次に、国がXの同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準が合理的であると認められるか否かについて検討する。
証拠によれば、国がXの同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準は、次のとおりであり、国は、平成28年3月22日付けの関東信越国税局長名により新潟県内の税務署長宛ての指示文書により、次の抽出基準に該当する法人の調査を求め、これに加え、S税務署長が本件更正等に先立ち平成26年1月から6月までの間にXの法人税調査を実施した際に調査担当者等が電子データの処理等により抽出した同業類似法人の中から、国が次の抽出基準に該当するものを調査したところ、次の抽出基準に該当するXの同業類似法人は前掲のとおりの5法人となったことが認められる。
① 新潟県内に納税地を有する法人であること
② 日本標準産業分類における、大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品製造業」を基幹の事業としていること
③ 平成18年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了する事業年度において、売上金額が6億7746万円余(Xの本件事業年度の売上金額の半額)以上27億0987万円余(Xの本件事業年度の売上金額の倍額)以下である事業年度があること
④ 死亡を理由とする代表取締役の退職があり、かつ、上記③に該当する事業年度において、当該退職した代表取締役に対して退職給与の支払いがあること
⑤ 上記③に該当する事業年度について、国税通則法又は行政事件訴訟法所定の不服申立て又は訴訟が係属中でないこと
上記抽出基準のうち、①の合理性について、国がXの本店所在地である三条市と経済事情が類似すると認められる新潟県内に納税地を有する法人を対象としてXの同業類似法人の調査をしたことは合理的ということができる。
また、抽出基準②の合理性について、Xは、業種を金属製品製造業に限定したことが不合理である旨を主張するが、Xは、ミシン部品の製造及び販売、家庭金物、建材金物の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、本件事業年度分の法人税の確定申告書には事業種目を「足場金具製造」と記載し、Xの本件事業年度の直前の3事業年度の商品別売上金額の中でも金属製品の売上金額が占める割合が大きく、リース業及びメンテナンス業の売上金額は計14%に満たないことからすれば、Xの同業類似法人の抽出に当たり、日本標準産業分類における、大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品製造業」を基幹の事業としていることを基準としたことは合理的ということができる。
さらに、抽出基準③の合理性について、Xは、売上金額を基準としたことや倍半基準を用いたことが不合理である旨を主張するが、法人税法施行令70条2号が、役員退職給与の相当額の算定に当たり考慮すべき要素として、その法人と同種の事業を営む法人でその「事業規模が類似するもの」の役員に対する退職給与の支給の状況を挙げていることからすれば、Xと事業規模が類似する法人を抽出するに当たり、事業の規模を示す指標である各法人の売上金額を抽出基準の一つとすることは合理的であり、また、具体的な基準として売上金額がXの売上金額の半額から倍額までの金額の範囲内にあることを抽出基準としたこともXと事業規模が類似する法人を抽出する基準として合理的であるということができる。そして、調査対象年度を平成18年2月1日から平成25年10月31日までの7年9か月の間に終了する事業年度としたことも、同期間に本件事業年度が含まれることや、本件事業年度をはさんでその前後4年程度の期間に限定していること、一定数の同業類似法人を抽出するには一定の期間を調査対象年度とする必要があると考えられることからすれば、合理的ということができる。
そして、抽出基準④及び⑤も、Xの場合と同じ役職名の役員の同じ退任理由による退職給与の損金算入額が争いなく確定している法人を抽出する基準であり、支給事例としての適格性を担保するための基準として合理性があるということができる。
(4)そこで次に、本件平均功績倍率をXに適用し、これに甲の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じて得た額をもって、甲に対する退職給与として相当な金額と認めることが相当といえるか否かについて検討する。
前記前提事実及び証拠によれば、甲の最終月額報酬額は240万円、役員(取締役、代表取締役)としての勤続年数は27年であり、本件役員退職給与に係る功績倍率は6.49であること、甲は、昭和56年に取締役に就任した後、Xの経理及び労務管理を任され、債務の弁済計画等を立て、不動産等を売却することなく、平成9年頃に8億円以上あった借金を平成20年頃までに完済することに貢献したこと、平成15年には三男の乙が代表取締役社長に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任したこと、Xの売上金額は昭和56年頃には約6億8000万円であったのが、平成15年頃には15億円前後にまで増加したことが認められる。
同業類似法人間における平均功績倍率は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、役員退職給与として相当であると認められる金額を算定するための合理的な指標となるものであるが、あくまでも同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象して平準化した平均的な値であるにすぎず、本来役員退職給与が当該退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方であって、実態に即した適正な課税を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反することにもなりかねず、相当であるとはいえない。しかも、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になるとすると、例えば本件においても、前掲のA及びEの支給事例は不相当に高額な金額の退職給与の支給をしていたということになりかねず、当該支給事例が、役員退職給与の損金算入額が争いなく確定し、支給事例としての一定の適格性が担保されている同業類似法人であるという本件平均功績倍率の算出の前提と矛盾することになるから、この点でも不合理というべきである。さらに、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条各号の規定は、課税庁が課税処分を行う際の準則でもあるのみならず、法人税の納税者が法人税の申告をする際に従うべき準則でもあるところ、前述したとおり、法人税の納税者は、同令70条2号所定の考慮要素である「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況」を考慮するに当たり、公刊物等を参酌することで上記の支給の状況を相当程度まで認識することが可能であるとは解されるものの、国が行う通達回答方式のような厳密な調査は期待し得べくもないから、このような納税者側の一般的な認識可能性の程度にも十分に配慮する必要があり、役員退職給与として相当であると認められる金額は、事後的な課税庁側の調査による平均功績倍率を適用した金額からの相当程度の乖離を許容するものとして観念されるべきものと解される。このように考えると、少なくとも、課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は、当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしてその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、同号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではないと解するのが相当であるというべきである。
これを本件についてみると、上記の事実関係によれば、本件役員退職給与に係る功績倍率は6.49であり、本件平均功績倍率3.26にその半数を加えた4.89を超えるものであるところ、甲がXの取締役及び代表取締役として、借金の完済や売上金額の増加、経営者の世代交代の橋渡し等に相当の功績を有していたことがうかがわれることからすると、甲の功績倍率を上記の4.89として算定される役員退職給与の額について上記特段の事情があるとは認められないから、本件役員退職給与の額4億2000万円のうち、上記の功績倍率4.89に甲の最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年を乗じて計算される金額に相当する3億1687万円余までの部分は、甲に対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではないというべきである。
2 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無について(争点2) 本件において、Xが本件役員退職給与の全額を損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできない。
3 本件更正等における権利の濫用、信義則違反等の有無について(争点3) 国税通則法上の本件更正等の期間制限は、平成26年10月20日であるから、平成26年7月4日付けでされた本件更正等は、上記の期間制限に違反するものではなく、他に本件更正等が権利の濫用又は信義則違反により違法と評価すべき事情はうかがわれないから、この点に関するXの主張も理由がない。
四、解説
はじめに
役員退職給与(退職慰労金)の損金性が問題とされるのは、主として、分掌変更等に伴って支給される場合に「退職」の事実が問題とされる場合(注1)と当該退職給与の額が不相当に高額である場合である。本件は、後者の事例に該当するが、その場合には、本件においてもそうであるが、その「相当の額」(適正額)(以下「相当額」という。)をどのように算定するかである。
このような場合には、役員給与の損金不算入を定めている法人税法34条等の規定の合理性(違憲性)が問題となる。この合理性(違憲性)の問題については、後述するように、従前の最高裁判決(判例)の考え方に照らし、納税者側の主張が裁判所に届くのは極めて困難であると考えられる。
また、相当額については、当該役員退職給与支給の個別事情(実態)によって判断されるべきであろうが、それが故に、各判決の事案の内容と判決の考え方を整理、検討して置くことが重要である。本件においては、相当額の判定に多用されている類似法人における平均功績倍率法の適用が否定され、当該平均功績倍率の1.5倍によって相当額を算定すべき旨判示されたことが極めて注目される。恐らく、このような事例は、最初の事例のようであるので、今後の実務への影響も注目される(もっとも、本判決については、国は控訴しているので、控訴審の判断を注目する必要がある。)。
1 役員退職給与損金不算入規定の合理性(違憲性) (1)平成18年改正前の旧法人税法では、役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺい仮装して経理したものは、損金不算入とされ(旧法34①②)、役員賞与は、原則として、損金不算入とされ(旧法35①)、役員退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な金額は、損金不算入とされていた(旧法36)(注2)。
ところが、平成17年に制定された会社法の下では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価が一括して「報酬等」として括られ、その報酬等が定款の定め又は株主総会の決議によって律せられることとなった(会社法361)。これは、役員賞与が利益処分でないこと、そして、退職慰労金も職務執行の対価である限り、報酬等に含まれることを意味している。そのため、企業会計基準委員会も、平成17年11月29日付で、「役員賞与に関する会計基準」を発し、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」(同基準3)ことを明確にした(注3)。
かくして、平成18年に法人税法が改正され、同法34条は、そのタイトルを「過大役員報酬の損金不算入」から「役員給与の損金不算入」に改められ、同条が定める定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与以外の給与(退職給与等の一部の給与を除く。)を損金不算入とし(法法34①)、かつ、役員給与の額のうち不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽・仮装して支給する給与の額を損金不算入とした(法法34②③)。更に、同法35条は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与については、当該給与に係る所得税法28条3項に定める給与所得控除額相当額について損金不算入とした(旧法法35)。
(2)かくして、法人税法34条以下の役員給与課税の規定については、当初からその合理性が問われてきたところであり(注4)、同法35条については、平成22年に廃止されたところである。そのため、本訴においても、Xは、法人税法34条2項等の規定に基づく本件各更正等の違憲性を主張するに至っている。
しかしながら、租税法規の違憲問題については、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注5)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。」と判示して以降、それが判例法として機能し、各裁判所は違憲判断について極めて慎重になっている(注6)。そのため、本判決も、前述のように法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の各規定の合理性を容認し、Xの違憲主張を退けている。
2 役員退職給与の相当額の算定方法 (1)前記1の(1)で述べたように、法人税法34条1項は、退職給与等の一部の給与を除き、所定の給与に該当しないものを損金の額に算入しないとしている。そして、同条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(〈略〉)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。この不相当に高額とされる給与には、通常、各事業年度ごとに支払われる報酬と当該役員が退任する際に支払われる役員退職慰労金が含まれるので、双方について「不相当に高額な部分の金額」を算定する必要がある(前者については、法人税法施行令70条1号に算定方法が定められている。)。
次に、法人税法施行令70条2号は、役員退職給与の相当額につき、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当と認められる金額」と定めている。
このような役員給与に対する法規制は、本件におけるX会社の平成19年2月期に適用される平成18年改正前の旧法人税法の下でも同様であった。
(2)かくして、役員退職給与の相当額の算定については、①当該役員の役員従事年数、②退職の事情、③類似法人における退職給与の支給状況等が基準となる。この場合、通常の給与の場合と異なって、当該法人の収益状況や使用人に対する支給状況が明示されていないことに留意を要する。また、役員退職給与が当該役員の長年の功績に報いる趣旨があるので、上記の明示事項以外の「等」には、当該功績の証しとも言える当該法人の純資産価額(内部留保金額)が重視されるべきであろう。
また、上記の比準要素のうち、役員退職給与についても、類似法人の支給額との比準が最も多く利用される。しかも、具体的な比準方法として、本件でも採用されている功績倍率法、1年当たり平均額等が採用される。そのため、それらの合理性が問題となる。
一般的には、類似法人の選定については、同じ国税局管内等において、類似する業種に属する法人のうち、主として、売上規模等において倍半基準が採用される場合が多い。この場合に問題となるのは、そもそも類似法人の選定が不透明であるということである。国(処分行政庁)は、課税処分又は争訟過程において、然るべき類似法人を選定することができるが、納税者側からすると、そのような類似法人が存在するか否かも確認できないわけであるし、国が選定した以外に当該納税者に一層類似する法人がいるか否かも確認できないわけである。そのため、本件においても、Xが主張するように、類似法人との比準を中核とする法令に基づく課税処分それ自体の違憲性も問題とされるところである。また、売上規模のみを基にした倍半基準による類似法人の選定については、役員退職給与が売上に応じて支給されるものではないので、常に合理性があるとは言い難いであろう(注7)。
(3)次に、退職給与の相当額の具体的な判定方法は、主として、功績倍率法と1年当たり平均額法が採用されている(注8)。前者の功績倍率法は、本件においても採用されているが、退職役員の最終報酬月額に役員従事年数及び類似法人の功績倍率を乗じる方法である。この場合、最も問題となるのが、功績倍率の平均値を採用すべきか、最高値を採用すべきかであり、あるいは、それらの数値に何らかの修正を加えるかである。
従前の裁判例では、最も多く採用されてきたのが、平均功績倍率法であると言える。その中でも、その方法を厳格に適用した裁判例として、東京高裁昭和49年1月31日判決(税資74号293頁)及び最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決(税資80号259頁)が挙げられる。この事案では、会社創立以来の代表取締役が退任するに際し、功績倍率3.0を適用して退職慰労金が支給されたことに対し、所轄税務署長が、類似法人3社の平均功績倍率2.1を適用して相当額を算定し、それを上回る部分の損金算入を否認する課税処分を行い、当該処分の適否が争われた。
一審の東京地裁昭和46年6月29日判決(行裁例集22巻6号885頁)は、被告が採用した類似法人3社と原告との類似性を認めることに主張・立証はなく、原告が採用した役員功績倍率3.0は同業種・同規模の法人の役員に対する退職給与の支給状況に照らして、不相当に失するものとは認め難い旨判示し、当該課税処分を違法なものとした。これに対し、控訴審の前掲東京高裁判決は、平均功績倍率をもって役員退職給与の額の相当性を判断することは過大役員退職給与金の損金不算入を定めた法令の趣旨に合致する合理的なものである旨判示し、当該課税処分の適法性を容認した、前掲の最高裁判決も、原判決の判断を支持している。
そのほか、平均功績倍率を採用した裁判例として、静岡地裁昭和63年9月30日判決(税資165号962頁)及び東京高裁平成元年1月23日判決(同169号5頁)、福島地裁平成8年3月18日判決(同215号891頁)、札幌地裁平成11年12月10日判決(同245号703頁)、東京地裁平成25年3月22日判決(平成23年(行ウ)第421号)及び東京高裁平成25年7月18日判決(平成25年(行コ)第169号)等がある。特に、前掲東京地裁平成25年3月22日判決等では、平均功績倍率1.18という非常に低い数値が採用されていることが注目される。
(4)このように、課税の実務及び裁判例においては、平均功績倍率法が多用されているのであるが、この方法には、幾つかの問題点を有している。そもそも、退職給与を含む役員給与は、当該役員の会社に対する役務提供の対価として支払われるものであるから、本来、当該役務提供の内容は極めて個別性の強いものであり、当該対価の相当額を同業者の平均値によって推し測ることができるものではない。また、平均値を重視することは、当該平均値を上回る数値によって算定されている退職給与額は全て課税上否認の対象になり、そうなると当該平均値は限りなく低下することになる。それに加え、功績倍率の基礎となる最終報酬月額は、一般的には、当該役員の会社に対する功績度を表わす適切なものであると解されているが、例えば、役員在任中、会社の業績を盛り立てるために滅私奉公の精神で自己の報酬まで削って会社の業績向上に貢献した役員に対し「退職慰労金」によってその貢献に報いようとしても、課税上否認されるという極めて納得し難い結果を招来することにもなる。
そのため、課税の実務及び裁判例においては、功績倍率法を採用する場合にも、類似法人における最高功績倍率を適用して、当該退職給与額の相当額を算定する例が幾つか見られる(注9)。
また、功績倍率法は、前述のように、当該役員の最終報酬月額を基礎とすることによる弊害が生じるのであるが、それを是正するために、1年当たり平均額法が採用される場合がある。すなわち、同法は、類似法人における役員退職給与額を当該役員の役員在任年数で除し、その金額を基にして、算定すべき役員の在任年数を乗じて、相当額を算定する方法である。この場合にも、1年当たり平均額について、類似法人の平均値を採用する場合と最高値を採用する場合とがあるが、通常、前者が採用されることになる。例えば、1年当たり平均額法を最初に適用したと目される札幌地裁昭和58年5月27日判決(行裁例集34巻5号930頁)の事案では、課税処分の段階において、当該退職給与相当額につき、平均功績倍率法を適用した場合に3102万円余となり、1年当たり平均額法(平均値)を適用した場合に6342万円余となるところ、後者の金額の1割増の7000万円と算定された場合に、上記判決は、当該課税処分を適法である旨判示している(注10)。
3 本件退職給与の相当額 (1)本件においては、本件退職給与が、Xの役員退職慰労金規定に基づき、甲の最終報酬月額(240万円)と役員従事年数(27年)を基にし、役員倍数(5.0)及び功労加算金(1.3)をそれぞれ乗じて(功績倍率換算6.5)、4億2120万円(支給額4億2000万円)と算定したものである。これに対し、所轄税務署長は、類似法人5社を選定してそれぞれの功績倍率を算定し、その平均功績倍率3.26を適用して、甲の退職給与の相当額を2億1124万円と算定し、本件退職給与のうち当該相当額を上回る部分の損金算入を否認する本件更正等を行ったものである。本訴における国の主張も、本件更正等の適法性を強調するものである。
これに対し、Xは、前述のように、本件更正等の根拠となる法人税法34条2項及び同法施行令70条2号の不合理性(違憲性)を主張するとともに、本件類似法人とXとの間に類似性は乏しく、かつ、功績倍率法を適用するにしても、最高功績倍率を適用すべきである旨主張した。
(2)かくして、本判決は、前述のように、本件における類似法人の選定の合理性及び平均功績倍率法を適用することの一般的合理性を容認したものの、当該功績倍率法適用の限界等について、次のように判示した。
「同業類似法人間における平均功績倍率は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、役員退職給与として相当であると認められる金額を算定するための合理的な指標となるものであるが、あくまでも同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象して平準化した平均的な値であるにすぎず、本来役員退職給与が当該退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりに硬直的な考え方であって、実態に即した適正な課税を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反することにもなりかねず、相当であるとはいえない。しかも、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になるとすると、例えば本件においても、別表2の順号1及び5(編注=前記二の2の(1)のA及びE)の支給事例は不相当に高額な金額の退職給与の支給をしていたことになりかねず、当該支給事例が、役員退職給与の損金算入額が争いなく確定し、支給事例としての一定の適格性が担保されている同業類似法人であるという本件平均功績倍率の算出の前提と矛盾することになるから、この点でも不合理というべきである。」
次いで、本判決は、本件退職給与の相当額を平均功績倍率の1.5倍とすべき根拠について、次のように判示した。
「このように考えると、少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は、当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、同号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではないと解するのが相当であるというべきである。」
(3)以上のように、本判決は、従前の裁判例において最も多く支持されてきた平均功績倍率法を機械的に適用することに疑問を呈したことがまず注目される。そのことは、筆者も従前から指摘したところであり、評価できるところである。次いで、本判決は、「平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率」により役員退職給与の額を算定する限りは「相当額」を超えないと解するのが相当である旨判示し、本件退職給与の相当額についても、本件類似法人の平均功績倍率の1.5倍の功績倍率を適用して算定すべきと判示した。
このような1.5倍基準説については、前述のように、平均功績倍率法に問題点がある以上それを解決するための一つの方法であるとも評価できるところであるが、その理論的根拠が明確にされているわけではない。また、従前の裁判例においては、当該事案において平均功績倍率法の適用が適切でないと思料される場合には、最高功績倍率が適用されていたところであるが、そのような場合と1.5倍基準説との関係も判然としない。例えば、本件については、類似法人の最高功績倍率が4.31であるところ、本件判決が1.5倍の4.89といずれがどのような理由で適切であるかについても定かでない。
なお、本判決は、国が類似法人の選定について売上金額の倍半基準によっていることについてそれを前提として(是として)、前述のよう結論を導いているのであるが、役員退職給与の相当額の算定に関し、売上基準のみを採用することには問題が多いことを指摘しておきたい。
4 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、金属製品製造業を営む中堅会社の代表取締役が死亡退任した場合に支給された本件退職給与の法人税法上の相当額が幾許であるかが争われたものである。本件のような役員退職給与の相当額については、多くの争訟事件で争われてきたところであるが、従前の裁判例等においては、平均功績倍率法を適用して相当額を算定するのが最も多かったと言える。ところが、本判決は、前述のように、平均功績倍率法を機械的に適用することは問題があるとして、本件に即して、平均功績倍率を1.5倍した数値によって相当額を算定するのが相当であるし、本件退職給与については、当該相当額を上回る部分のみが不相当に高額になるとして、本件更正等の一部を取り消した。
このような判決は、従前、多くの裁判例が平均功績倍率法の合理性を容認していただけに、役員退職給与相当額の算定方法に一石を投じたものとして評価できる。もっとも、前述したように、本判決には、平均功績倍率を1.5倍したことについて明確な根拠を示したものとも言い難く、また、類似法人の選定についても、売上金額の倍半基準によって国が選定した5件の類似法人をそのまま認めたにすぎず、問題を残していると言える。
なお、国は、本判決を不服として控訴しているので、控訴審でどのような判断が下されるかが注目される。
(注1)この問題に関する最近の事例として、東京地裁平成29年1月12日判決(平成27年(行ウ)第204号)及び東京高裁平成29年7月12日判決(平成29年(行コ)第39号)(以上については、本誌2017年11月20日号18頁参照)等を参照。
(注2)旧法時代の役員報酬課税の問題点等については、品川芳宣「役員報酬課税の問題点と方向性」JICPAジャーナル2006年2月号39頁等参照。
(注3)これらの経緯については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)」本誌2008年4月14日号27頁参照。
(注4)平成18年改正の役員給与課税規定の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(後)」本誌2008年4月21日号24頁等参照。
(注5)同判決は、給与所得者が事業所得者等に対し不平等に扱われているということで、所得税法28条の憲法14条違反の有無が争われた事案につき、合憲判断を示したものである(詳細については、品川芳宣ほか「戦後重要租税判例の再検証-税務事例創刊400号記念-」(財経詳報社 2003年)2頁、12頁等参照)。
(注6)最近の租税法規に係る違憲訴訟の動向については、前出(注4)32頁等参照。
(注7)売上基準とともにそれ以外の基準を採用した裁判例として、東京地裁平成28年4月22日判決(平成25年(行ウ)第5号)が、経常利益についての倍半基準を、札幌地裁平成11年12月10日判決が、純資産価額基準をそれぞれ採用している。
(注8)それ以外の判定方法としては、大阪地裁昭和44年3月27日判決(税資56号316頁)が、類似法人17社の公表利益金額と役員退職給与額の相関係数等を考慮して適正額と判定しており、大阪高裁昭和54年2月28日判決(税資104号531頁)が、国家公務員の退職給与支給額に比準して適正額を算定している。
(注9)最高功績倍率法によって役員退職給与の相当額を算定した裁判例として、東京地裁平成28年4月22日判決(平成25年(行ウ)第5号)、東京高裁昭和56年11月18日判決(行裁例集32巻11号1998頁)、岐阜地裁平成2年12月26日判決(税資181号1104頁)、仙台高裁平成10年4月7日判決(同231号470頁)等参照。なお、静岡地裁昭和63年9月30日判決(同165号962頁)及び東京高裁平成元年1月23日判決(同169号5頁)の事案では、類似法人における最高値3.41(平均値2.2)であるにもかかわらず、課税処分の段階において功績倍率4.1を適用して相当額を算定している。
(注10)その他1年当たり平均額法を適用した事例として、昭和61年9月1日裁決(裁決事例集32号231頁)、岡山地裁平成元年8月9日判決(税資173号432頁)等を参照。なお、前掲岡山地裁判決は、最高値を適用しても当該課税処分は適法となる旨判示している。
役員退職給与適正額の算定に平均功績倍率1.5倍を適用
東京地裁平成29年10月13日判決(平成27年(行ウ)第730号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣一、事実
(1)X(原告)は、資本金4950万円、売上金額13億5493万円余であり、ミシン部品等の製造、販売等を業とする株式会社であるが、平成20年8月21日から同21年8月20日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)分法人税につき、平成20年10月4日に死亡退任した代表取締役甲に対して、平成21年7月1日、臨時株主総会において決議した退職慰労金4億2000万円(以下「本件退職給与」という。)を支給し、所得金額の計算上損金の額に算入して所得金額6391万円余とする確定申告をした。
これに対し、所轄税務署長は、本件退職給与につき、法人税法上容認される適正額が2億1124万円であるから、当該金額を超える2億875万円余を所得金額に加算すべきとする更正等(以下「本件更正等」という。)をした。Xは、これを不服とし、前審手続を経て、平成27年12月21日、国(被告)に対し、本件更正等の取り消しを求めて本訴を提起した。
(2)甲は、昭和42年にXに入社した後、昭和56年にXの取締役に就任し、平成15年10月にXの代表取締役に就任し、同20年10月に死亡退職した。その死亡当時、Xの役員退職慰労金規定には、退職慰労金は株主総会の決議に基づき支給すること、退任時に報酬月額がある場合の退職慰労金の額は「退任時報酬月額×役員在任期間×退職時役位係数」の範囲内とすること、代表取締役の退任時役位係数は5.0倍とすること、在任期間は1年を単位とし、1年に満たない端数は1年とすること、在任中特別に功労があったと認められるときは上記規定による退職慰労金のほかに、その30%を超えない範囲において功労加算を行うことが定められていた。
なお、Xの株主総会の議事録によると、本件退職給与を算定する計算式は、次のようになっている。
240万円(最終報酬月額)×27年(勤続年数)×5倍(役員倍数)×1.3(功労加算金)=4億2120万円
二、争点と当事者の主張
1 争 点
(1)本件退職給与のうち、「不相当等に高額な部分の金額」
(2)国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無
(3)本件更正等における権利の濫用、信義則違反の有無
以上の争点のうち、(2)及び(3)については、当事者の主張と判決を紹介することにとどめる。
2 国の主張 (1)役員退職給与の相当額の算定方法としては、「平均功績倍率法」が、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の趣旨に最も合致する合理的な算定方法というべきである。
そして、国は、本件における同業類似法人として、①Xの所在地と経済事情が類似する地域である新潟県内に所在し、②Xと同種の事業である「金属製品製造業」を基幹の事業とし、③事業規模の類似性を判断する要素である売上金額に係るいわゆる倍半基準である事業年度(平成18年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了するもの)があり、④当該事業年度においてXと同じく死亡退職した代表取締役に対して退職給与の支給があり、⑤当該事業年度について不服申立て又は訴訟が係属中でないという抽出基準の全てを満たす法人を機械的に抽出した。この抽出基準及び抽出方法は合理的なものであるが、その同業類似法人は次のとおりの5法人(以下「本件類似法人」という。)であり、平均功績倍率は3.26である。
 (2)本件更正等において権利の濫用又は信義則違反はなく、過少申告について「正当な理由」もない。
(2)本件更正等において権利の濫用又は信義則違反はなく、過少申告について「正当な理由」もない。3 Xの主張 (1)そもそも、役員退職給与は、法人と退職役員との間で交わされた委任契約に基づく職務執行の対価であり、その金額は職務執行の対価としての合理性がある限り相当であり、職務対価としての合理性があるか否かについては私的自治の原則が妥当し当該法人のみが判断することができるのであって、租税法により役員退職給与の費用性を否定することはできないというべきである。そして、本件のように、あらかじめ就業規則等により定められた規定により支給された退職給与については、役員退職給与の支払に乗じて利益処分を行うものでないことは明らかであるから、役員退職給与の額の相当性が推定されるというべきである。就業規則等の規定に基づく役員退職給与の支給であるか否かは、法人税法施行令70条2号には規定されていないものの、上記の解釈と異なり、このような場合に役員退職給与の損金算入が否定されるというのであれば、法人税法34条2項は、「不相当に高額な部分の金額」を政令に白紙委任するものとして、租税法律主義(憲法84条)に反するといわざるを得ない。
(2)Xは、平成9年に当時の専務が死亡したため、Xの役員退職慰労金規定に従って算出した退職慰労金を支給し、法人税の確定申告をしたが、更正処分等はされなかったところ、本件退職給与も同様にXの役員退職慰労金規定に従って算出したのであるという、Xの責めに帰することができない客観的事情があるから、過少申告につき「正当な理由」があるというべきである。
(3)本件更正等は、本件退職給与の支給に係る事情が既に本件事業年度末の平成21年8月には判明していたにもかかわらず平成26年7月に至ってされたものであり、時効が完成した後にされたものであるか、権利の濫用に当たり又は信義則に違反するから違法である。
三、判決要旨
請求一部認容。
1 本件退職給与のうち「不相当に高額な部分の金額」について(争点1)
(1)法人税法34条2項の趣旨は、法人の役員に対する退職給与等が法人の利益処分たる性質を有する場合があることから、法人所得の金額の計算上、一般に相当と認められる金額に限り必要経費として損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、実態に即した適正な課税を行うことにあると解される。
そして、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を役員退職給与について算定するに当たり考慮すべき事項を類型化して具体的に定めたものということができる。
この点、Xは、あらかじめ就業規則等に定められた規定により算定された役員退職給与は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を含まない旨を主張する。しかしながら、上述のとおりの同項の趣旨からすると、就業規則等の規定により役員退職給与が算定されたとしても、当該規定の内容自体やその適用の過程で考慮された事情が一般に相当と認められるとは限らず、一般に相当と認められる金額を超える部分の金額については法人所得の金額の計算上損金算入を認めないこととし、実態に即した適正な課税を行うことが相当であるから、Xの上記主張は採用できない。
また、Xは、法人税法34条2項が政令に白紙委任するものとして租税法律主義(憲法84条)に違反する旨、法人税法施行令70条2号が法人税法34条2項の委任の範囲を超えるのみならず、課税要件の基準として不明確であり、納税者の予測可能性を欠き、適用違憲の可能性がある旨を主張する。しかしながら、法人税法34条2項の趣旨・目的が、上述のとおり、法人の役員に対する退職給与等の額のうち、一般に相当と認められる金額に限り、法人所得の金額の計算上必要経費として損金算入を認めることによって、実態に即した適正な課税を行うことにあることは、同項の規定内容自体から容易にうかがい知ることができることであり、また、法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」の考慮要素を役員退職給与について具体的に定めたものであって、その規定内容は、当該役員の在任期間、退職の事情、同業類似法人における退職給与の支給の状況等を考慮要素とするものであり、同項の上記の趣旨・目的に沿うものであるということができるから、同項の規定が政令に白紙委任したものであるとか、法人税法施行令70条2号がその委任の範囲を逸脱したものであるということはできない。
(2)国は、本件役員退職給与のうち相当であると認められる金額の算定方法として、平均功績倍率法を用いている。しかるところ、平均功績倍率法で用いる算定要素のうち、まず、最終月額報酬額は、通常、当該退職役員の在任期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに、当該退職役員の在任期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものということができる。また、勤続年数は、法人税法施行令70条2項が規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当する。さらに、功績倍率は、これらの要素以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であり、同業類似法人における功績倍率の平均値(平均功績倍率)を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものということができる。このような各算定要素を用いて役員退職給与の相当額を算定しようとする平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われ、かつ、その平均功績倍率を当該法人に適用することが相当と認められる限り、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の趣旨に合致する合理的な方法というべきである。
この点、Xは、最高功績倍率法等の納税者により有利な算定方法を採用すべきである旨を主張する。しかしながら、功績倍率の平均値(平均功績倍率)を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られることは前記のとおりである一方、功績倍率の最高値は最高値に係る法人の特殊性等に影響されるものであって、指標としての客観性が劣るといわざるを得ない。また、後記のとおり本件において合理的と認められる抽出基準により同業類似法人を抽出した結果、5法人という相当数の法人が抽出されている上、これらの法人の功績倍率には極端なばらつきがなく、その偏差も平均功績倍率の30%程度の範囲内に収まっているのであって、本件において役員退職給与の相当額を算定するための指標として平均功績倍率を採用することが相当でないとか、最高功績倍率法がより適切であるとみるべき事情は見当たらない。したがって、Xの上記主張も採用できない。
(3)そこで次に、国がXの同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準が合理的であると認められるか否かについて検討する。
証拠によれば、国がXの同業類似法人を抽出するために用いた抽出基準は、次のとおりであり、国は、平成28年3月22日付けの関東信越国税局長名により新潟県内の税務署長宛ての指示文書により、次の抽出基準に該当する法人の調査を求め、これに加え、S税務署長が本件更正等に先立ち平成26年1月から6月までの間にXの法人税調査を実施した際に調査担当者等が電子データの処理等により抽出した同業類似法人の中から、国が次の抽出基準に該当するものを調査したところ、次の抽出基準に該当するXの同業類似法人は前掲のとおりの5法人となったことが認められる。
① 新潟県内に納税地を有する法人であること
② 日本標準産業分類における、大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品製造業」を基幹の事業としていること
③ 平成18年2月1日から平成25年10月31日までの間に終了する事業年度において、売上金額が6億7746万円余(Xの本件事業年度の売上金額の半額)以上27億0987万円余(Xの本件事業年度の売上金額の倍額)以下である事業年度があること
④ 死亡を理由とする代表取締役の退職があり、かつ、上記③に該当する事業年度において、当該退職した代表取締役に対して退職給与の支払いがあること
⑤ 上記③に該当する事業年度について、国税通則法又は行政事件訴訟法所定の不服申立て又は訴訟が係属中でないこと
上記抽出基準のうち、①の合理性について、国がXの本店所在地である三条市と経済事情が類似すると認められる新潟県内に納税地を有する法人を対象としてXの同業類似法人の調査をしたことは合理的ということができる。
また、抽出基準②の合理性について、Xは、業種を金属製品製造業に限定したことが不合理である旨を主張するが、Xは、ミシン部品の製造及び販売、家庭金物、建材金物の製造及び販売等を目的とする株式会社であり、本件事業年度分の法人税の確定申告書には事業種目を「足場金具製造」と記載し、Xの本件事業年度の直前の3事業年度の商品別売上金額の中でも金属製品の売上金額が占める割合が大きく、リース業及びメンテナンス業の売上金額は計14%に満たないことからすれば、Xの同業類似法人の抽出に当たり、日本標準産業分類における、大分類「E-製造業」の中分類「24-金属製品製造業」を基幹の事業としていることを基準としたことは合理的ということができる。
さらに、抽出基準③の合理性について、Xは、売上金額を基準としたことや倍半基準を用いたことが不合理である旨を主張するが、法人税法施行令70条2号が、役員退職給与の相当額の算定に当たり考慮すべき要素として、その法人と同種の事業を営む法人でその「事業規模が類似するもの」の役員に対する退職給与の支給の状況を挙げていることからすれば、Xと事業規模が類似する法人を抽出するに当たり、事業の規模を示す指標である各法人の売上金額を抽出基準の一つとすることは合理的であり、また、具体的な基準として売上金額がXの売上金額の半額から倍額までの金額の範囲内にあることを抽出基準としたこともXと事業規模が類似する法人を抽出する基準として合理的であるということができる。そして、調査対象年度を平成18年2月1日から平成25年10月31日までの7年9か月の間に終了する事業年度としたことも、同期間に本件事業年度が含まれることや、本件事業年度をはさんでその前後4年程度の期間に限定していること、一定数の同業類似法人を抽出するには一定の期間を調査対象年度とする必要があると考えられることからすれば、合理的ということができる。
そして、抽出基準④及び⑤も、Xの場合と同じ役職名の役員の同じ退任理由による退職給与の損金算入額が争いなく確定している法人を抽出する基準であり、支給事例としての適格性を担保するための基準として合理性があるということができる。
(4)そこで次に、本件平均功績倍率をXに適用し、これに甲の最終月額報酬額及び勤続年数を乗じて得た額をもって、甲に対する退職給与として相当な金額と認めることが相当といえるか否かについて検討する。
前記前提事実及び証拠によれば、甲の最終月額報酬額は240万円、役員(取締役、代表取締役)としての勤続年数は27年であり、本件役員退職給与に係る功績倍率は6.49であること、甲は、昭和56年に取締役に就任した後、Xの経理及び労務管理を任され、債務の弁済計画等を立て、不動産等を売却することなく、平成9年頃に8億円以上あった借金を平成20年頃までに完済することに貢献したこと、平成15年には三男の乙が代表取締役社長に就任するまでの橋渡しとして代表取締役に就任したこと、Xの売上金額は昭和56年頃には約6億8000万円であったのが、平成15年頃には15億円前後にまで増加したことが認められる。
同業類似法人間における平均功績倍率は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、役員退職給与として相当であると認められる金額を算定するための合理的な指標となるものであるが、あくまでも同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象して平準化した平均的な値であるにすぎず、本来役員退職給与が当該退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方であって、実態に即した適正な課税を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反することにもなりかねず、相当であるとはいえない。しかも、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になるとすると、例えば本件においても、前掲のA及びEの支給事例は不相当に高額な金額の退職給与の支給をしていたということになりかねず、当該支給事例が、役員退職給与の損金算入額が争いなく確定し、支給事例としての一定の適格性が担保されている同業類似法人であるという本件平均功績倍率の算出の前提と矛盾することになるから、この点でも不合理というべきである。さらに、法人税法34条2項及び法人税法施行令70条各号の規定は、課税庁が課税処分を行う際の準則でもあるのみならず、法人税の納税者が法人税の申告をする際に従うべき準則でもあるところ、前述したとおり、法人税の納税者は、同令70条2号所定の考慮要素である「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況」を考慮するに当たり、公刊物等を参酌することで上記の支給の状況を相当程度まで認識することが可能であるとは解されるものの、国が行う通達回答方式のような厳密な調査は期待し得べくもないから、このような納税者側の一般的な認識可能性の程度にも十分に配慮する必要があり、役員退職給与として相当であると認められる金額は、事後的な課税庁側の調査による平均功績倍率を適用した金額からの相当程度の乖離を許容するものとして観念されるべきものと解される。このように考えると、少なくとも、課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は、当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしてその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、同号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではないと解するのが相当であるというべきである。
これを本件についてみると、上記の事実関係によれば、本件役員退職給与に係る功績倍率は6.49であり、本件平均功績倍率3.26にその半数を加えた4.89を超えるものであるところ、甲がXの取締役及び代表取締役として、借金の完済や売上金額の増加、経営者の世代交代の橋渡し等に相当の功績を有していたことがうかがわれることからすると、甲の功績倍率を上記の4.89として算定される役員退職給与の額について上記特段の事情があるとは認められないから、本件役員退職給与の額4億2000万円のうち、上記の功績倍率4.89に甲の最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年を乗じて計算される金額に相当する3億1687万円余までの部分は、甲に対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではないというべきである。
2 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」の有無について(争点2) 本件において、Xが本件役員退職給与の全額を損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできない。
3 本件更正等における権利の濫用、信義則違反等の有無について(争点3) 国税通則法上の本件更正等の期間制限は、平成26年10月20日であるから、平成26年7月4日付けでされた本件更正等は、上記の期間制限に違反するものではなく、他に本件更正等が権利の濫用又は信義則違反により違法と評価すべき事情はうかがわれないから、この点に関するXの主張も理由がない。
四、解説
はじめに
役員退職給与(退職慰労金)の損金性が問題とされるのは、主として、分掌変更等に伴って支給される場合に「退職」の事実が問題とされる場合(注1)と当該退職給与の額が不相当に高額である場合である。本件は、後者の事例に該当するが、その場合には、本件においてもそうであるが、その「相当の額」(適正額)(以下「相当額」という。)をどのように算定するかである。
このような場合には、役員給与の損金不算入を定めている法人税法34条等の規定の合理性(違憲性)が問題となる。この合理性(違憲性)の問題については、後述するように、従前の最高裁判決(判例)の考え方に照らし、納税者側の主張が裁判所に届くのは極めて困難であると考えられる。
また、相当額については、当該役員退職給与支給の個別事情(実態)によって判断されるべきであろうが、それが故に、各判決の事案の内容と判決の考え方を整理、検討して置くことが重要である。本件においては、相当額の判定に多用されている類似法人における平均功績倍率法の適用が否定され、当該平均功績倍率の1.5倍によって相当額を算定すべき旨判示されたことが極めて注目される。恐らく、このような事例は、最初の事例のようであるので、今後の実務への影響も注目される(もっとも、本判決については、国は控訴しているので、控訴審の判断を注目する必要がある。)。
1 役員退職給与損金不算入規定の合理性(違憲性) (1)平成18年改正前の旧法人税法では、役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺい仮装して経理したものは、損金不算入とされ(旧法34①②)、役員賞与は、原則として、損金不算入とされ(旧法35①)、役員退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な金額は、損金不算入とされていた(旧法36)(注2)。
ところが、平成17年に制定された会社法の下では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価が一括して「報酬等」として括られ、その報酬等が定款の定め又は株主総会の決議によって律せられることとなった(会社法361)。これは、役員賞与が利益処分でないこと、そして、退職慰労金も職務執行の対価である限り、報酬等に含まれることを意味している。そのため、企業会計基準委員会も、平成17年11月29日付で、「役員賞与に関する会計基準」を発し、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」(同基準3)ことを明確にした(注3)。
かくして、平成18年に法人税法が改正され、同法34条は、そのタイトルを「過大役員報酬の損金不算入」から「役員給与の損金不算入」に改められ、同条が定める定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与以外の給与(退職給与等の一部の給与を除く。)を損金不算入とし(法法34①)、かつ、役員給与の額のうち不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽・仮装して支給する給与の額を損金不算入とした(法法34②③)。更に、同法35条は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与については、当該給与に係る所得税法28条3項に定める給与所得控除額相当額について損金不算入とした(旧法法35)。
(2)かくして、法人税法34条以下の役員給与課税の規定については、当初からその合理性が問われてきたところであり(注4)、同法35条については、平成22年に廃止されたところである。そのため、本訴においても、Xは、法人税法34条2項等の規定に基づく本件各更正等の違憲性を主張するに至っている。
しかしながら、租税法規の違憲問題については、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注5)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。」と判示して以降、それが判例法として機能し、各裁判所は違憲判断について極めて慎重になっている(注6)。そのため、本判決も、前述のように法人税法34条2項及び法人税法施行令70条2号の各規定の合理性を容認し、Xの違憲主張を退けている。
2 役員退職給与の相当額の算定方法 (1)前記1の(1)で述べたように、法人税法34条1項は、退職給与等の一部の給与を除き、所定の給与に該当しないものを損金の額に算入しないとしている。そして、同条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(〈略〉)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。この不相当に高額とされる給与には、通常、各事業年度ごとに支払われる報酬と当該役員が退任する際に支払われる役員退職慰労金が含まれるので、双方について「不相当に高額な部分の金額」を算定する必要がある(前者については、法人税法施行令70条1号に算定方法が定められている。)。
次に、法人税法施行令70条2号は、役員退職給与の相当額につき、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当と認められる金額」と定めている。
このような役員給与に対する法規制は、本件におけるX会社の平成19年2月期に適用される平成18年改正前の旧法人税法の下でも同様であった。
(2)かくして、役員退職給与の相当額の算定については、①当該役員の役員従事年数、②退職の事情、③類似法人における退職給与の支給状況等が基準となる。この場合、通常の給与の場合と異なって、当該法人の収益状況や使用人に対する支給状況が明示されていないことに留意を要する。また、役員退職給与が当該役員の長年の功績に報いる趣旨があるので、上記の明示事項以外の「等」には、当該功績の証しとも言える当該法人の純資産価額(内部留保金額)が重視されるべきであろう。
また、上記の比準要素のうち、役員退職給与についても、類似法人の支給額との比準が最も多く利用される。しかも、具体的な比準方法として、本件でも採用されている功績倍率法、1年当たり平均額等が採用される。そのため、それらの合理性が問題となる。
一般的には、類似法人の選定については、同じ国税局管内等において、類似する業種に属する法人のうち、主として、売上規模等において倍半基準が採用される場合が多い。この場合に問題となるのは、そもそも類似法人の選定が不透明であるということである。国(処分行政庁)は、課税処分又は争訟過程において、然るべき類似法人を選定することができるが、納税者側からすると、そのような類似法人が存在するか否かも確認できないわけであるし、国が選定した以外に当該納税者に一層類似する法人がいるか否かも確認できないわけである。そのため、本件においても、Xが主張するように、類似法人との比準を中核とする法令に基づく課税処分それ自体の違憲性も問題とされるところである。また、売上規模のみを基にした倍半基準による類似法人の選定については、役員退職給与が売上に応じて支給されるものではないので、常に合理性があるとは言い難いであろう(注7)。
(3)次に、退職給与の相当額の具体的な判定方法は、主として、功績倍率法と1年当たり平均額法が採用されている(注8)。前者の功績倍率法は、本件においても採用されているが、退職役員の最終報酬月額に役員従事年数及び類似法人の功績倍率を乗じる方法である。この場合、最も問題となるのが、功績倍率の平均値を採用すべきか、最高値を採用すべきかであり、あるいは、それらの数値に何らかの修正を加えるかである。
従前の裁判例では、最も多く採用されてきたのが、平均功績倍率法であると言える。その中でも、その方法を厳格に適用した裁判例として、東京高裁昭和49年1月31日判決(税資74号293頁)及び最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決(税資80号259頁)が挙げられる。この事案では、会社創立以来の代表取締役が退任するに際し、功績倍率3.0を適用して退職慰労金が支給されたことに対し、所轄税務署長が、類似法人3社の平均功績倍率2.1を適用して相当額を算定し、それを上回る部分の損金算入を否認する課税処分を行い、当該処分の適否が争われた。
一審の東京地裁昭和46年6月29日判決(行裁例集22巻6号885頁)は、被告が採用した類似法人3社と原告との類似性を認めることに主張・立証はなく、原告が採用した役員功績倍率3.0は同業種・同規模の法人の役員に対する退職給与の支給状況に照らして、不相当に失するものとは認め難い旨判示し、当該課税処分を違法なものとした。これに対し、控訴審の前掲東京高裁判決は、平均功績倍率をもって役員退職給与の額の相当性を判断することは過大役員退職給与金の損金不算入を定めた法令の趣旨に合致する合理的なものである旨判示し、当該課税処分の適法性を容認した、前掲の最高裁判決も、原判決の判断を支持している。
そのほか、平均功績倍率を採用した裁判例として、静岡地裁昭和63年9月30日判決(税資165号962頁)及び東京高裁平成元年1月23日判決(同169号5頁)、福島地裁平成8年3月18日判決(同215号891頁)、札幌地裁平成11年12月10日判決(同245号703頁)、東京地裁平成25年3月22日判決(平成23年(行ウ)第421号)及び東京高裁平成25年7月18日判決(平成25年(行コ)第169号)等がある。特に、前掲東京地裁平成25年3月22日判決等では、平均功績倍率1.18という非常に低い数値が採用されていることが注目される。
(4)このように、課税の実務及び裁判例においては、平均功績倍率法が多用されているのであるが、この方法には、幾つかの問題点を有している。そもそも、退職給与を含む役員給与は、当該役員の会社に対する役務提供の対価として支払われるものであるから、本来、当該役務提供の内容は極めて個別性の強いものであり、当該対価の相当額を同業者の平均値によって推し測ることができるものではない。また、平均値を重視することは、当該平均値を上回る数値によって算定されている退職給与額は全て課税上否認の対象になり、そうなると当該平均値は限りなく低下することになる。それに加え、功績倍率の基礎となる最終報酬月額は、一般的には、当該役員の会社に対する功績度を表わす適切なものであると解されているが、例えば、役員在任中、会社の業績を盛り立てるために滅私奉公の精神で自己の報酬まで削って会社の業績向上に貢献した役員に対し「退職慰労金」によってその貢献に報いようとしても、課税上否認されるという極めて納得し難い結果を招来することにもなる。
そのため、課税の実務及び裁判例においては、功績倍率法を採用する場合にも、類似法人における最高功績倍率を適用して、当該退職給与額の相当額を算定する例が幾つか見られる(注9)。
また、功績倍率法は、前述のように、当該役員の最終報酬月額を基礎とすることによる弊害が生じるのであるが、それを是正するために、1年当たり平均額法が採用される場合がある。すなわち、同法は、類似法人における役員退職給与額を当該役員の役員在任年数で除し、その金額を基にして、算定すべき役員の在任年数を乗じて、相当額を算定する方法である。この場合にも、1年当たり平均額について、類似法人の平均値を採用する場合と最高値を採用する場合とがあるが、通常、前者が採用されることになる。例えば、1年当たり平均額法を最初に適用したと目される札幌地裁昭和58年5月27日判決(行裁例集34巻5号930頁)の事案では、課税処分の段階において、当該退職給与相当額につき、平均功績倍率法を適用した場合に3102万円余となり、1年当たり平均額法(平均値)を適用した場合に6342万円余となるところ、後者の金額の1割増の7000万円と算定された場合に、上記判決は、当該課税処分を適法である旨判示している(注10)。
3 本件退職給与の相当額 (1)本件においては、本件退職給与が、Xの役員退職慰労金規定に基づき、甲の最終報酬月額(240万円)と役員従事年数(27年)を基にし、役員倍数(5.0)及び功労加算金(1.3)をそれぞれ乗じて(功績倍率換算6.5)、4億2120万円(支給額4億2000万円)と算定したものである。これに対し、所轄税務署長は、類似法人5社を選定してそれぞれの功績倍率を算定し、その平均功績倍率3.26を適用して、甲の退職給与の相当額を2億1124万円と算定し、本件退職給与のうち当該相当額を上回る部分の損金算入を否認する本件更正等を行ったものである。本訴における国の主張も、本件更正等の適法性を強調するものである。
これに対し、Xは、前述のように、本件更正等の根拠となる法人税法34条2項及び同法施行令70条2号の不合理性(違憲性)を主張するとともに、本件類似法人とXとの間に類似性は乏しく、かつ、功績倍率法を適用するにしても、最高功績倍率を適用すべきである旨主張した。
(2)かくして、本判決は、前述のように、本件における類似法人の選定の合理性及び平均功績倍率法を適用することの一般的合理性を容認したものの、当該功績倍率法適用の限界等について、次のように判示した。
「同業類似法人間における平均功績倍率は、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、役員退職給与として相当であると認められる金額を算定するための合理的な指標となるものであるが、あくまでも同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象して平準化した平均的な値であるにすぎず、本来役員退職給与が当該退職役員の具体的な功績等に応じて支給されるべきものであることに鑑みると、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりに硬直的な考え方であって、実態に即した適正な課税を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反することにもなりかねず、相当であるとはいえない。しかも、平均功績倍率を少しでも超える功績倍率により算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になるとすると、例えば本件においても、別表2の順号1及び5(編注=前記二の2の(1)のA及びE)の支給事例は不相当に高額な金額の退職給与の支給をしていたことになりかねず、当該支給事例が、役員退職給与の損金算入額が争いなく確定し、支給事例としての一定の適格性が担保されている同業類似法人であるという本件平均功績倍率の算出の前提と矛盾することになるから、この点でも不合理というべきである。」
次いで、本判決は、本件退職給与の相当額を平均功績倍率の1.5倍とすべき根拠について、次のように判示した。
「このように考えると、少なくとも課税庁側の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は、当該法人における当該役員の具体的な功績等に照らしその額が明らかに過大であると解すべき特段の事情がある場合でない限り、同号にいう「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超えるものではないと解するのが相当であるというべきである。」
(3)以上のように、本判決は、従前の裁判例において最も多く支持されてきた平均功績倍率法を機械的に適用することに疑問を呈したことがまず注目される。そのことは、筆者も従前から指摘したところであり、評価できるところである。次いで、本判決は、「平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率」により役員退職給与の額を算定する限りは「相当額」を超えないと解するのが相当である旨判示し、本件退職給与の相当額についても、本件類似法人の平均功績倍率の1.5倍の功績倍率を適用して算定すべきと判示した。
このような1.5倍基準説については、前述のように、平均功績倍率法に問題点がある以上それを解決するための一つの方法であるとも評価できるところであるが、その理論的根拠が明確にされているわけではない。また、従前の裁判例においては、当該事案において平均功績倍率法の適用が適切でないと思料される場合には、最高功績倍率が適用されていたところであるが、そのような場合と1.5倍基準説との関係も判然としない。例えば、本件については、類似法人の最高功績倍率が4.31であるところ、本件判決が1.5倍の4.89といずれがどのような理由で適切であるかについても定かでない。
なお、本判決は、国が類似法人の選定について売上金額の倍半基準によっていることについてそれを前提として(是として)、前述のよう結論を導いているのであるが、役員退職給与の相当額の算定に関し、売上基準のみを採用することには問題が多いことを指摘しておきたい。
4 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、金属製品製造業を営む中堅会社の代表取締役が死亡退任した場合に支給された本件退職給与の法人税法上の相当額が幾許であるかが争われたものである。本件のような役員退職給与の相当額については、多くの争訟事件で争われてきたところであるが、従前の裁判例等においては、平均功績倍率法を適用して相当額を算定するのが最も多かったと言える。ところが、本判決は、前述のように、平均功績倍率法を機械的に適用することは問題があるとして、本件に即して、平均功績倍率を1.5倍した数値によって相当額を算定するのが相当であるし、本件退職給与については、当該相当額を上回る部分のみが不相当に高額になるとして、本件更正等の一部を取り消した。
このような判決は、従前、多くの裁判例が平均功績倍率法の合理性を容認していただけに、役員退職給与相当額の算定方法に一石を投じたものとして評価できる。もっとも、前述したように、本判決には、平均功績倍率を1.5倍したことについて明確な根拠を示したものとも言い難く、また、類似法人の選定についても、売上金額の倍半基準によって国が選定した5件の類似法人をそのまま認めたにすぎず、問題を残していると言える。
なお、国は、本判決を不服として控訴しているので、控訴審でどのような判断が下されるかが注目される。
(注1)この問題に関する最近の事例として、東京地裁平成29年1月12日判決(平成27年(行ウ)第204号)及び東京高裁平成29年7月12日判決(平成29年(行コ)第39号)(以上については、本誌2017年11月20日号18頁参照)等を参照。
(注2)旧法時代の役員報酬課税の問題点等については、品川芳宣「役員報酬課税の問題点と方向性」JICPAジャーナル2006年2月号39頁等参照。
(注3)これらの経緯については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)」本誌2008年4月14日号27頁参照。
(注4)平成18年改正の役員給与課税規定の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(後)」本誌2008年4月21日号24頁等参照。
(注5)同判決は、給与所得者が事業所得者等に対し不平等に扱われているということで、所得税法28条の憲法14条違反の有無が争われた事案につき、合憲判断を示したものである(詳細については、品川芳宣ほか「戦後重要租税判例の再検証-税務事例創刊400号記念-」(財経詳報社 2003年)2頁、12頁等参照)。
(注6)最近の租税法規に係る違憲訴訟の動向については、前出(注4)32頁等参照。
(注7)売上基準とともにそれ以外の基準を採用した裁判例として、東京地裁平成28年4月22日判決(平成25年(行ウ)第5号)が、経常利益についての倍半基準を、札幌地裁平成11年12月10日判決が、純資産価額基準をそれぞれ採用している。
(注8)それ以外の判定方法としては、大阪地裁昭和44年3月27日判決(税資56号316頁)が、類似法人17社の公表利益金額と役員退職給与額の相関係数等を考慮して適正額と判定しており、大阪高裁昭和54年2月28日判決(税資104号531頁)が、国家公務員の退職給与支給額に比準して適正額を算定している。
(注9)最高功績倍率法によって役員退職給与の相当額を算定した裁判例として、東京地裁平成28年4月22日判決(平成25年(行ウ)第5号)、東京高裁昭和56年11月18日判決(行裁例集32巻11号1998頁)、岐阜地裁平成2年12月26日判決(税資181号1104頁)、仙台高裁平成10年4月7日判決(同231号470頁)等参照。なお、静岡地裁昭和63年9月30日判決(同165号962頁)及び東京高裁平成元年1月23日判決(同169号5頁)の事案では、類似法人における最高値3.41(平均値2.2)であるにもかかわらず、課税処分の段階において功績倍率4.1を適用して相当額を算定している。
(注10)その他1年当たり平均額法を適用した事例として、昭和61年9月1日裁決(裁決事例集32号231頁)、岡山地裁平成元年8月9日判決(税資173号432頁)等を参照。なお、前掲岡山地裁判決は、最高値を適用しても当該課税処分は適法となる旨判示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.