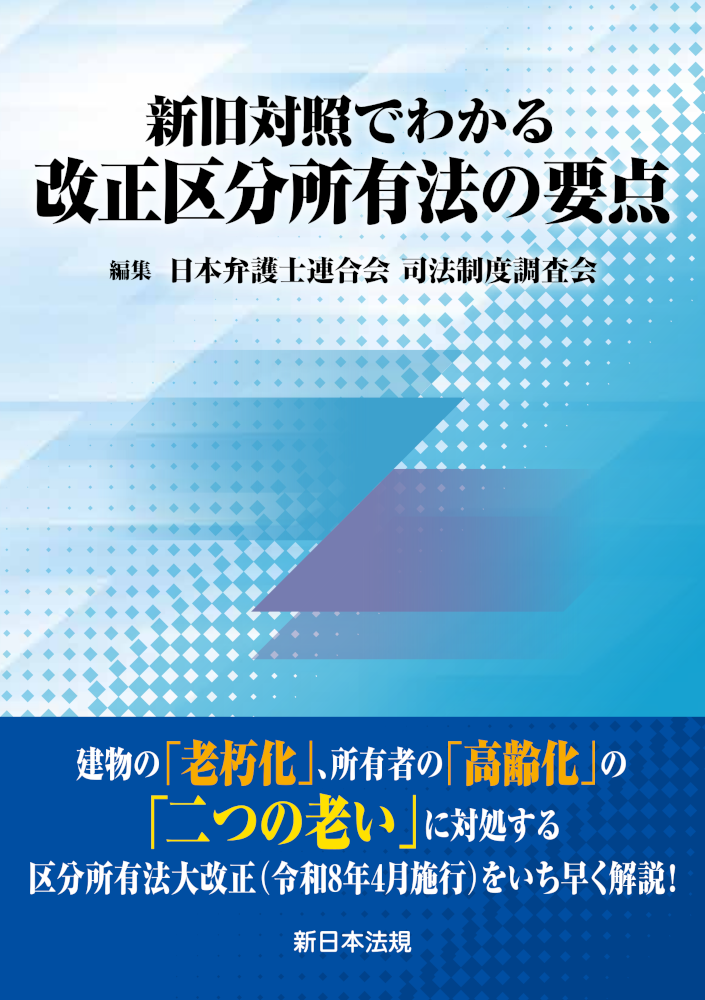解説記事2018年05月14日 【税理士のための相続法講座】 遺言(12)―遺言の内容(4)(2018年5月14日号・№738)
税理士のための相続法講座
第38回
遺言(12)―遺言の内容(4)
弁護士 間瀬まゆ子
3 包括遺贈と特定遺贈
(1)意義 包括遺贈とは、遺贈の目的の範囲を、遺贈者が自己の財産全体に対する割合をもって表示した遺贈をいいます。一方、特定遺贈とは、遺贈の目的を特定した遺贈をいいます。
「全財産の2分の1を遺贈する」というような遺贈は包括遺贈であり、「自宅の土地建物を遺贈する」というような遺贈は特定遺贈です。このように説明するとその区分は明らかであるように思われますが、特定遺贈と包括遺贈のどちらにあたるかが問題になる例があります。これについては後述します。
(2)包括受遺者の権利義務 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます(民法990条)。そのため、プラスの財産のみならず、マイナスの債務も承継することになります。
相続放棄する場合に、相続開始を知ったときから3ケ月以内に行わなければならないことも、相続人の場合と同様です。遺贈の承認・放棄について定めた民法986条は、特定遺贈に係る規定であり、包括遺贈の場合には適用されません。
また、被相続人が遺産全部を包括遺贈した場合には、遺産の全部が直ちに受遺者に帰属することになりますので、遺産分割の対象となることはありませんが、第三者に割合的包括遺贈がなされた場合、当該第三者は、相続人らとともに、遺産分割を行うことになります。
割合的包括遺贈を受けた第三者が例えば相続人Aの配偶者Bであり、被相続人Cの介護を行っていたというようなときに、一定の寄与行為が認められる場合があるでしょうが、包括受遺者を寄与分の主体として認めないのが多数説です。
ですから、配偶者Bは、遺言で認められた指定相続分以外の権利を主張することができないわけです。ただ、現在国会で審議中の民法改正案では「特別寄与料」の制度が新しく盛り込まれており、この法律が施行されれば、別途「特別寄与料」(※)の請求が認められる可能性があります。
※ 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することを認める制度(改正法案1050条)。
なお、現行法の下でも、配偶者Bが相続人Aの履行補助者にあたるとの考え方に基づき、配偶者Bによる寄与が、被相続人Cの相続に際して、相続人Aの寄与分として認められる場合はあります(と言っても、そもそも現在の裁判所の実務では、寄与分が認められる場合が限定的ですので、Bらが期待するような相続分の増加を裁判所に認めてもらえない場合がほとんどです。)。
その他、包括受遺者と相続人には、以下のような違いがあります。
・包括受遺者は法人でもよい。
・包括受遺者には代襲制度はない(民法994条1項参照)。
・包括受遺者には遺留分はない。
・他の相続人や包括受遺者が放棄をしたときに、放棄された分は別の相続人の相続分に加えられるが、包括受遺者の受遺分は増加しない。
この事例では、不動産(自宅の土地建物)を法人に遺贈しているため、みなし譲渡所得の申告・納税の問題が生じます。
本件のような相続人不存在の場合、相続財産は相続財産法人となり、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されれば、当該相続財産管理人が所得税の申告納税義務を負うことになります。
ただし、相続人がいなくても、包括受遺者が存在する場合には、「相続人のあることが明らかでないとき」にあたらないので相続財産管理人の選任が必要ないとされ(最二小判平成9年9月12日民集51巻8号3887頁)、相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者が所得税の申告納税義務を負うことになります(所得税法2条2項、125条1項)。
そこで、F法人に対する「その他の全ての財産」の遺贈が特定遺贈か包括遺贈かが問題になります。
この点については、税務訴訟で争われた先例があり、特定の財産を除く全ての財産の遺贈が、特定遺贈ではなく包括遺贈であり、受遺者は所得税の申告納税義務を負うとの判断が示されています(東地判平成10年6月26日訟月45巻3号742頁)。
したがって、上記事例の場合でも、F法人が準確定の所得税の申告を行うべきことになるでしょう(ただ、特定遺贈か包括遺贈かは、遺言の解釈の問題であり、個別の事案によっては異なる判断となる可能性があります。)。
包括遺贈を受ける法人の立場からすると、所得税の確定申告の要否の判断を4か月という限られた時間内に行わなければならないこととなり、大きな負担となり得ます(対象財産の内容や負担する税金の額によっては放棄を検討することもあり得ますが、この場合の熟慮期間も原則として3ケ月という短期間です。)。
やはり、相続が開始してから突然知らせるのではなく、遺言を作成する段階で相談しておくのが親切でしょう。

第38回
遺言(12)―遺言の内容(4)
弁護士 間瀬まゆ子
3 包括遺贈と特定遺贈
(1)意義 包括遺贈とは、遺贈の目的の範囲を、遺贈者が自己の財産全体に対する割合をもって表示した遺贈をいいます。一方、特定遺贈とは、遺贈の目的を特定した遺贈をいいます。
「全財産の2分の1を遺贈する」というような遺贈は包括遺贈であり、「自宅の土地建物を遺贈する」というような遺贈は特定遺贈です。このように説明するとその区分は明らかであるように思われますが、特定遺贈と包括遺贈のどちらにあたるかが問題になる例があります。これについては後述します。
(2)包括受遺者の権利義務 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます(民法990条)。そのため、プラスの財産のみならず、マイナスの債務も承継することになります。
相続放棄する場合に、相続開始を知ったときから3ケ月以内に行わなければならないことも、相続人の場合と同様です。遺贈の承認・放棄について定めた民法986条は、特定遺贈に係る規定であり、包括遺贈の場合には適用されません。
また、被相続人が遺産全部を包括遺贈した場合には、遺産の全部が直ちに受遺者に帰属することになりますので、遺産分割の対象となることはありませんが、第三者に割合的包括遺贈がなされた場合、当該第三者は、相続人らとともに、遺産分割を行うことになります。
割合的包括遺贈を受けた第三者が例えば相続人Aの配偶者Bであり、被相続人Cの介護を行っていたというようなときに、一定の寄与行為が認められる場合があるでしょうが、包括受遺者を寄与分の主体として認めないのが多数説です。
ですから、配偶者Bは、遺言で認められた指定相続分以外の権利を主張することができないわけです。ただ、現在国会で審議中の民法改正案では「特別寄与料」の制度が新しく盛り込まれており、この法律が施行されれば、別途「特別寄与料」(※)の請求が認められる可能性があります。
※ 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することを認める制度(改正法案1050条)。
なお、現行法の下でも、配偶者Bが相続人Aの履行補助者にあたるとの考え方に基づき、配偶者Bによる寄与が、被相続人Cの相続に際して、相続人Aの寄与分として認められる場合はあります(と言っても、そもそも現在の裁判所の実務では、寄与分が認められる場合が限定的ですので、Bらが期待するような相続分の増加を裁判所に認めてもらえない場合がほとんどです。)。
その他、包括受遺者と相続人には、以下のような違いがあります。
・包括受遺者は法人でもよい。
・包括受遺者には代襲制度はない(民法994条1項参照)。
・包括受遺者には遺留分はない。
・他の相続人や包括受遺者が放棄をしたときに、放棄された分は別の相続人の相続分に加えられるが、包括受遺者の受遺分は増加しない。
| Dが亡くなったが、Dには相続人がいなかった。Dは生前に遺言を作成しており、その遺言には、金融資産の一部を親戚のEらに、自宅の土地建物とその他の全ての財産をF法人に寄付する旨が書かれていた。 |
本件のような相続人不存在の場合、相続財産は相続財産法人となり、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されれば、当該相続財産管理人が所得税の申告納税義務を負うことになります。
ただし、相続人がいなくても、包括受遺者が存在する場合には、「相続人のあることが明らかでないとき」にあたらないので相続財産管理人の選任が必要ないとされ(最二小判平成9年9月12日民集51巻8号3887頁)、相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者が所得税の申告納税義務を負うことになります(所得税法2条2項、125条1項)。
そこで、F法人に対する「その他の全ての財産」の遺贈が特定遺贈か包括遺贈かが問題になります。
この点については、税務訴訟で争われた先例があり、特定の財産を除く全ての財産の遺贈が、特定遺贈ではなく包括遺贈であり、受遺者は所得税の申告納税義務を負うとの判断が示されています(東地判平成10年6月26日訟月45巻3号742頁)。
したがって、上記事例の場合でも、F法人が準確定の所得税の申告を行うべきことになるでしょう(ただ、特定遺贈か包括遺贈かは、遺言の解釈の問題であり、個別の事案によっては異なる判断となる可能性があります。)。
包括遺贈を受ける法人の立場からすると、所得税の確定申告の要否の判断を4か月という限られた時間内に行わなければならないこととなり、大きな負担となり得ます(対象財産の内容や負担する税金の額によっては放棄を検討することもあり得ますが、この場合の熟慮期間も原則として3ケ月という短期間です。)。
やはり、相続が開始してから突然知らせるのではなく、遺言を作成する段階で相談しておくのが親切でしょう。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.