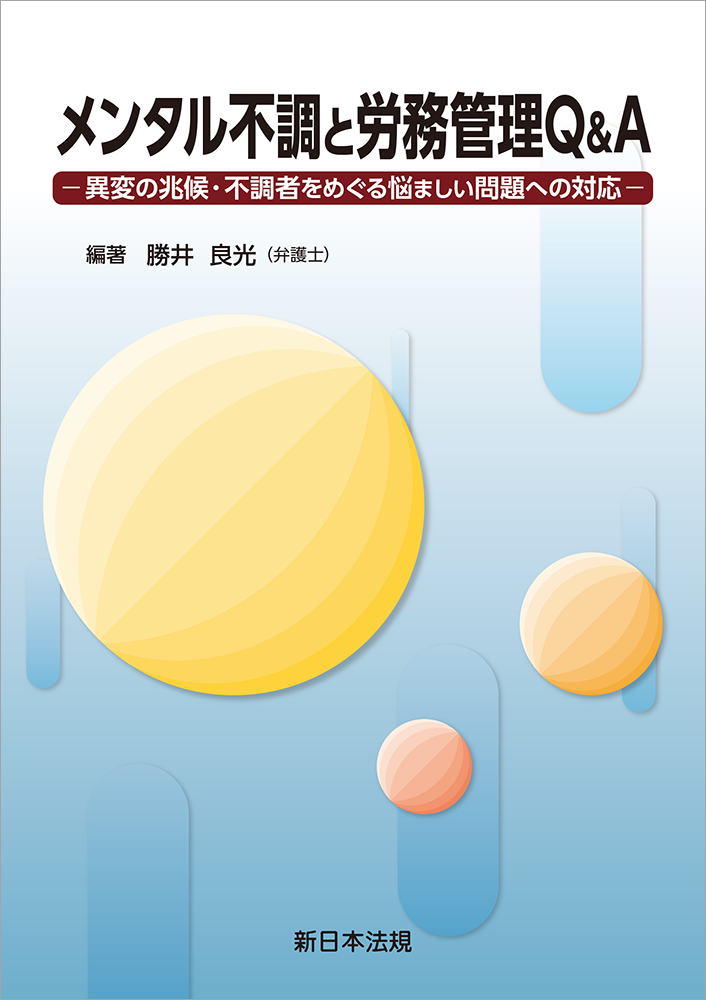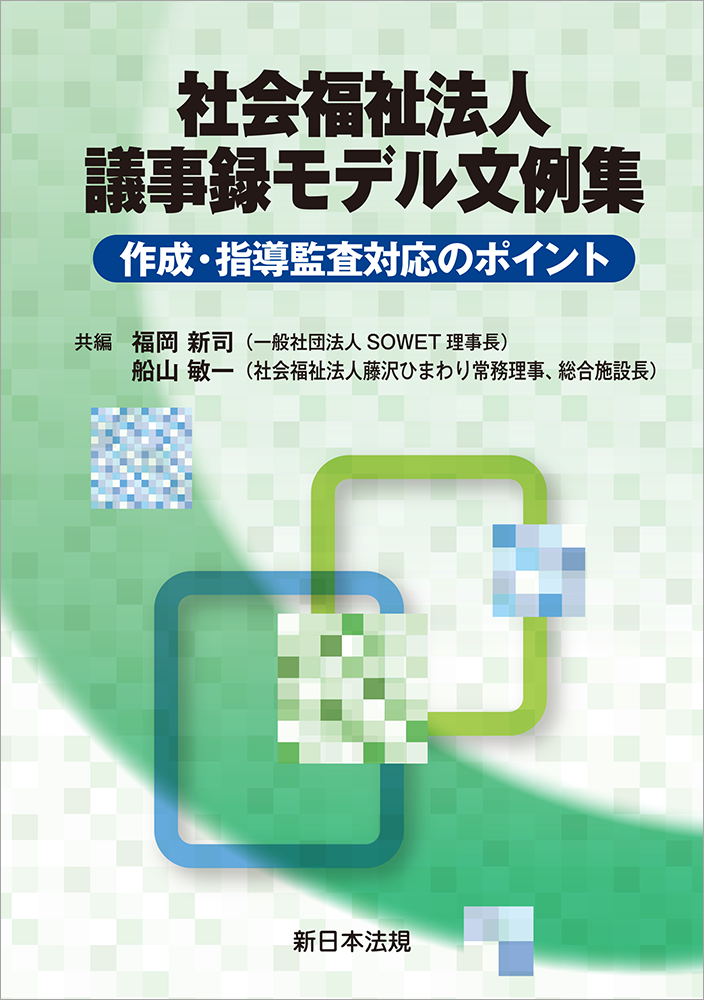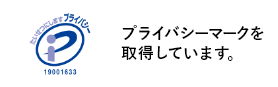解説記事2018年05月21日 【最新判決研究】 特許業務法人の社員に対する歩合給の損金性・法人税法34条の合憲性・更正の理由附記の違法性(2018年5月21日号・№739)
最新判決研究
特許業務法人の社員に対する歩合給の損金性・法人税法34条の合憲性・更正の理由附記の違法性
東京高裁平成29年8月28日判決(平成29年(行コ)第37号)
東京地裁平成29年1月18日判決(平成26年(行ウ)第533号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)特許業務法人であるX(原告・控訴人)は、平成20年3月期ないし平成24年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の各期分法人税につき、代表社員であるA以外の社員であるL、M及びN(以下3名を「本件社員ら」という。)に対し、固定給のほか、各人の業績に対応した実績給及び賞与(以下「本件各歩合給」という。)を支給し、所得金額の計算上損金の額に算入して確定申告をした。
これに対し、所轄税務署長は、本件社員らがいずれも法人税法(以下「法」という。)上の役員に該当し、かつ、使用人としての職務を有する役員(以下「使用人兼務役員」という。)に該当しないから、本件各歩合給は本件各事業年度分法人税の所得金額の計算上損金の額に算入できないとする更正処分(以下「本件各更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定」といい、本件各更正と併せて「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、前審手続を経て、国(被告・被控訴人)に対し、本件更正等の取り消しを求めて本訴を提起した。
(2)Xは、Aが昭和51年3月1日から個人事業主として弁理士業を営んでいたH国際特許事務所の業務を承継し、平成15年3月5日に弁理士法に基づき設立された特許業務法人であり、国内及び外国への特許・実用新案等の出願代理、審判・訴訟代理、鑑定書の作成等の業務をしている。そして、Aは、上記法人設立時に代表者に選任され、本件社員らは、H国際特許事務所の時代から弁理士として業務に従事し、上記法人設立時のXの社員になったものである。本件社員らは、平成15年4月1日付で、Xとの間で、Xから受ける給与に関し契約(以下「本件各契約」という。)を締結しているところ、本件社員らに対する報酬は、月給制で、固定給及び歩合給の両建てとなっており、歩合給の金額は本件社員らの担当した件についてXが顧客に請求する額に一定比率を乗じた額とされた。また、本件社員らには、Xの就業規則に規定された賞与及び退職金の規定は適用されないとされた。
(3)特許業務法人は、弁理士の業務を組織的に行うことを目的として、弁理士法の定めるところにより、弁理士が共同して設立する法人である(同法2⑥)。特許業務法人の社員は、弁理士でなければならないとされ(同法39①)、全ての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う(同法46)。そして、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされる(同法47の4①)。また、各自、特許業務法人を代表することとされる(同法47の2①)一方、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げないとされており(同②)、その上で、特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされている(同③)。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件更正等の適法性(本件各歩合給の損金への算入の可否)であるところ、具体的には、①本件社員らの役員該当性、②本件社員らの使用人兼務役員該当性及び③法34条1項の合憲性である。なお、Xは、控訴審において、本件更正の理由附記の不備の違法性を主張している。
2 国の主張 (1)本件社員らはいずれも特許業務法人であるXの社員であるところ、特許業務法人の社員は、全ての社員がその業務を執行する権利を有し、義務を負うとされる上、特許業務法人の社員の業務を執行する権利は、法令上、定款によっても制限することができず、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるから、本件社員らはXという特許業務法人の経営に従事する権限を有する地位にあるものとして、役員に該当するというべきである。
(2)特許業務法人の社員は、前記のとおり、定款によっても制限できない特許業務法人の業務を執行する権利を有し、義務を負うのみならず、弁理士法上、その代表者を選任する権限を有すること、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされること等から、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものとはおよそいえず、使用人兼務役員には該当しない。
(3)法34条1項の規定は、役員の給与の支給の恣意性を排除することにより課税の公平を害することがないようにするためであると解され、その立法目的は正当なものというべきであり、また、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められないから、同項が憲法に違反するとはいえない。
3 Xの主張 (1)法2条15号、令7条1号は、役員につき、法人の経営に従事する権限を有する者とするのではなく、法人の経営に従事している者とする旨を定めていることからすれば、役員該当性については、経営の権限の有無ではなく、実際に経営に従事しているかで判断すべきである。Xにおいては、代表社員であるAのみが、代表権、すなわち、対外的な業務を執行する権利を有し、Xの経営に従事している一方、本件社員らは、弁理士法46条の規定により業務を執行する権利を有するとしても、対外的な業務を執行する権利を有しておらず、実際上、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に従事していない。
(2)本件社員らについては、法34条5項に照らし、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者に該当するか又はその実質があれば、使用人兼務役員と認められるというべきである。そして、仮に法人の使用人としての職制上の地位を有すると認められないとしても、法人税基本通達9-2-6にあるように、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるから、使用人兼務役員に該当するというべきである。
(3)役員の給与は、企業会計上は費用として処理されるものであるが、平成18年法律第10号による改正(以下「平成18年改正」という。)後の法34条1項は、原則として、定期同額給与等、一定の要件に該当するもの以外、役員の給与を損金の額に算入することを制限するに至ったものであるところ、かかる制限は、過度なものであって、憲法22条、29条が規定する法人の営業の自由を侵害し、また、憲法14条1項が規定する平等原則に反して違憲・無効である。
(4)そもそも、使用人兼務役員は、役員としての地位(委任関係)と使用人としての地位(雇用関係)を併有するものと解されるところ、原判決のように法人との関係で委任関係にあることをもって使用人兼務役員とされない役員と解釈するのであれば、法上、使用人兼務役員の存在を認める余地がなくなる。また、特許業務法人の社員が経営に関与する程度は様々であるから、当該法人の定款の規定及び勤務の実態を検討することなく、特許業務法人の社員が、弁理士法上、業務を執行する権利を有することから直ちに使用人兼務役員とされない役員に当たるということはできない(控訴審)。
(5)本件各更正では、「更正の理由」として、「弁理士法第46条においては、「特許業務法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う」こととされており、この社員の業務を執行する権限は、定款によっても制限することはできないこととされています。また、同条の業務執行とは法人の営業に関する事務を執行することとされており、契約締結等の法人の営業に関する法律行為や帳簿の記入等の事実行為も含まれることとされていることからすれば、特許業務法人の社員は、令7条1号の「職制上使用人としての地位のみを有する者」とはなり得ず、かつ、特許業務法人の社員全てが、営業に関する法律行為を含む業務執行を行う者であり、同号の「法人の経営に従事している者」と認められることから、法人税法上の役員に該当します。」との記載がある。
しかし、本件各更正の「更正の理由」には一見して明白な誤りがあるから、この点だけからも、本件各更正は取り消されるべきである(控訴審)。
三、一審判決要旨
請求棄却。
1 本件社員らの役員該当性 (1)法2条15号及び法34条5項の規定からすれば、法は、常時使用人としての職務に従事する者であっても、「法人の経営に従事している」者として役員に該当し得るものであることを定めているということができ、また、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る地位・職責を有する者を列挙し、これらの者については、当該個々の法人において具体的にどのような内容の職務に従事しているかを問うことなく、一律に役員に該当するものとしているのであるから、同号の規定にいう「法人の経営に従事している」者とは、法人内における地位・職責からみて法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る者を指し、このような者に該当する者であれば当該個々の法人における具体的な職務の内容を問わないものと解するのが相当であり、令7条1号にいう「法人の経営に従事している」者についても、これと同義と解するのが相当である。
(2)そこで、本件について検討するに、本件社員らはいずれも特許業務法人であるXの社員であるところ、弁理士法の規定によれば、特許業務法人の社員は、全ての社員がその業務を執行する権利を有し、義務を負うとされる上、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解され、また、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされる。したがって、上記の権限や責任を伴う特許業務法人の社員は、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得るものであり、役員に該当すると解されるから、その地位にある本件社員らは、Xにおける具体的な職務の内容にかかわらず、Xの役員に該当するというべきである。
2 本件社員らの使用人兼務役員該当性 (1)法は、34条5項において、役員のうち「部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」を使用人兼務役員と定めるが、役員のうち「社長、理事長その他政令で定めるもの」については、使用人兼務役員から除いている。このように法が「社長、理事長」を使用人兼務役員から除いているのは、これらの役員が、法人との間で雇用契約等に基づく事業主と使用人との関係に立つものではなく、その従事する具体的な職務の中に使用人が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るからであると解される。そして、使用人としての職制上の地位を有さず、又は、使用人としての立場でその職務に従事しているものではないと一般的・類型的に評価し得る役員は、上記のように定義される使用人兼務役員には含まれないから、このような役員は、使用人兼務役員に該当しないと解するのが相当であり、法34条5項による政令への委任も、そのように一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員を定めることを委ねたものということができる。
(2)そこで、本件について検討するに、特許業務法人の社員は、法34条5項の社長及び理事長や、その他、同項の委任を受けた令71条1項各号で定める役員には該当しない。
もっとも、前述のとおり、特許業務法人の社員は、特許業務法人の経営に係る業務を含む業務の執行をする権利を有し、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるところ、業務を執行する役員と特許業務法人との関係には民法の委任に関する規定が準用され(弁理士法55①、会社法593④)、両者は一般には雇用契約等に基づく使用人と事業主との関係に立つものではないというべきであるから、弁理士である役員が従事する具体的な職務の中に使用人である弁理士が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るものである。したがって、特許業務法人の社員は、使用人兼務役員に該当しないものというべきであり、このような解釈は、令71条1項3号に、特許業務法人の役員と同様に民法の委任の規定が準用される(会社法593④)「合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員」が掲げられていることと整合的であるということができる。
(3)以上に対して、Xは、本件社員らは、法人税基本通達9-2-6にあるように、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるから、使用人兼務役員に該当する上、その各給与は、本件各歩合給も含め、全額が使用人としての職務に対して支給されたものである旨を主張する。しかしながら、法人税基本通達9-2-6は、前述のとおり一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員には適用されないものと解されるから、Xの主張は採用することができない。
3 法人税法34条1項の合憲性 (1)租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、専門技術的な判断を必要とすることも明らかであって、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきであるから、その租税法の立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された課税要件等の定めが同目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項、22条、29条等の規定に違反するものということはできないものというべきである(最高裁昭和60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁参照)。
(2)そこで、法34条1項について検討するに、同項の趣旨は、法人と役員との関係に鑑み、役員の給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば、その支給額をほしいままに決定し、法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがあり、課税の公平を害することとなるためであり、他方、同項各号に該当するものや使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与等については、上記のような役員の給与の支給の恣意性が排除されており、その額を損金の額に算入することとしても、課税の公平を害することはないと判断されたためであると解されるところ、その立法目的は正当なものというべきであり、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められないから、同項の規定は憲法14条1項、22条、29条等の規定に違反するものではないというべきである。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。 (1)当裁判所も、Xの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正・付加するほかは、原判決のとおりであるから、これを引用する。
(2)法2条15号前段は、その列挙する取締役等につき、その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、一律に「法人の経営に従事している者」に該当すると規定するものであることは明らかであり、それは、法2条15号前段に列挙されている職位の者が、その有する法令上の権限等に照らし、その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができることによるものであるから、同号後段及び令7条1号の「法人の経営に従事している者(もの)」に該当するか否かも、その有する法令上の権限等に照らし、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができるか否かにより判断すべきであって、これと異なるXの主張は採用できない。
また、そもそも、法上の役員の範囲はその定義規定である法2条15号によって画されることは明らかであるから、法34条1項の趣旨を根拠に役員の範囲を画することはできない。また、当該個々の法人における具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る地位・職責を有する者を法34条1項の対象とすることは、予測可能性や納税者間の公平の観点からみて合理的であると解することができる。
(3)Xは、使用人兼務役員は、役員としての地位(委任関係)と使用人としての地位(雇用関係)を併有するものと解されるところ、原判決のように法人との関係で委任関係にあることをもって使用人兼務役員とされない役員と解釈するのであれば、法上、使用人兼務役員の存在を認める余地がなくなると主張する。
しかし、引用に係る原判決に説示のとおり、原判決は、使用人兼務役員に該当するか否かについて、当該役員が法人との間で委任関係にあるか否かで一律に判断するとしたものではなく、法34条5項の「常時使用人としての職務に従事するもの」に該当するか否かの判断につき、当該役員が従事する具体的な職務の中に使用人が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、使用人としての立場でその職務に従事しているものではないと認められる場合があるとしたものであるから、Xの非難は当たらない。
(4)Xは、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあるから、それだけで同処分は取り消されるべきであると主張する。しかし、法130条2項によれば、内国法人が提出した法人税の青色申告書につき、税務署長が更正処分を行う場合には更正通知書に更正の理由を付記することを要するが、証拠によれば、本件各更正には更正の理由が付記されていると認められ、また、更正処分取消訴訟においては、原則として理由の追加及び差替えが認められると解されていること(最高裁昭和56年7月14日判決・民集35巻5号901頁参照)に照らせば、仮に本件各更正の「更正の理由」の記載中に一部誤りがあったとしても、それ自体が本件各更正の取消事由となるとは解されない。
また、上記の点はひとまず措くとしても、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあるとも認められない。
五、解説
はじめに 本件は、特許業務法人であるXが、その社員3名(代表社員を除く。本件社員ら)に対し、固定給のほか、各人の業績に対応した実績給与及び賞与(本件各歩合給)を支給した場合に、本件各歩合給の損金性が争われたものである。平成18年改正後の法人税法34条は、そのタイトルを「役員給与の損金不算入」と題し、原則として、会社法等において適法に支給された役員報酬等の損金性を否定し、同条1項に定めた3項目の給与についてのみ、損金算入を認めている。
そのため、本件各歩合給のような役員報酬等については、損金性についての実質とは関係なく、形式的に損金不算入とされるので、法人税法34条の規定それ自体の合理性・違憲性が問題となる。本件においても、そのことがもろに争われている。また、本件各歩合給のような給与であっても、法人税法上の使用人兼務役員に支給される場合には、損金算入の道が開かれるため、本件においても、本件社員らの使用人兼務役員の該非が問題になっている。以下、これらの論点について解説する。
なお、本件は、特許業務法人の社員に対する給与の損金性が問題になっているのであるが、当該社員と税理士法人の社員と共通するところが多いので、税理士法人の実務についても両者を比較しながら注視しておく必要がある。
1 役員給与損金不算入規定の合理性(違憲性) (1)平成18年改正前の旧法人税法では、役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺい仮装して経理したものは、損金不算入とされ(旧法34①②)、役員賞与は損金不算入とされ(旧法35①)、役員退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な金額は、損金不算入とされていた(旧法36)(注1)。ところが、平成17年に制定された会社法の下では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価が一括して「報酬等」として括られ、その報酬等が定款の定め又は株主総会の決議によって律せられることとなった(会社法361)。これは、役員賞与が利益処分でないこと、そして、退職慰労金も職務執行の対価である限り、報酬等に含まれることを意味している。そのため、企業会計基準委員会も、平成17年11月29日付で、「役員賞与に関する会計基準」を発し、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」(同基準3)ことを明確にした(注2)。かくして、平成18年に、これらの企業会計上の役員報酬の会計処理に対処するため、法人税法が改正され、同法34条は、そのタイトルを「過大役員報酬の損金不算入」から「役員給与の損金不算入」に改められ、同条が定める定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与以外の給与を損金不算入とし(法法34①)、かつ、役員給与の額のうち不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽・仮装して支給する給与の額を損金不算入とした(法法34②③)。更に、同法35条は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与については、当該給与に係る所得税法28条3項に定める給与所得控除額相当額について損金不算入とした(旧法法35)。このような法人税法の税務処理は、会社法及び企業会計上が役員報酬の費用処理を弾力的(拡大的)にしたのに逆行し、役員給与の損金性を殊更に狭くしたものと言える。
(2)かくして、法人税法34条以下の役員給与課税の規定については、当初からその合理性が問われてきたところであり(注3)、同法35条については、立法政策上その合理性に問題があるということで、平成22年に廃止されたところである。そのため、本訴においても、X会社は、法人税法34条1項等の規定に基づく本件各更正等は憲法14条、22条、29条等に違反する旨主張するに至っている。
しかしながら、租税法規の違憲問題については、本件各判決も引用する最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注4)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。」と判示して以降、それが判例法として機能し、各裁判所は違憲判断について極めて慎重になっている(注5)。そのため、一審判決も、法人税法34条1項の規定につき、「法人と役員との関係に鑑み、役員の給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば、その支給額をほしいままに決定し、法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがあり、課税の公平を害することとなるためであり」と判示し、次いで、「その立法目的は正当なものというべきであり、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められない」と判示し、Ⅹの違憲主張を斥け、控訴審判決もそれを支持している。
もっとも、このような合憲判断については、例えば、役員給与を恣意的に過大に支給すれば、法人税率よりも一層厳しい所得税の累進税率の適用を受けるわけであるから、説得的な判示とも認め難いわけである。また、平成18年改正で設けられた法人税法35条の規定については、前述したように、その合理性に問題があったからこそ廃止されたわけであるし、そのほか、法人税法34条等には種々の問題点を有しているところであるので、当該立法政策の合理性の有無と解釈の方向性については引き続き検討すべきである(注6)。
2 役員給与の損金不算入 (1)前述したように、法人税法34条は、そのタイトルを「役員給与の損金不算入」と題し、同条1項では、「内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。(以下略))のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。
そして、損金算入の対象となる給与について、次の3項目を定めている(法法34①一~三)。
① 定期同額給与 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(その他これに準ずるものとして政令で定める給与)
② 所定の給与で①及び③に該当しないもの(事前確定届出給与) その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
③ 業績連動給与 内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(所定の役員に限る。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、所定の要件を満たすもの
また、上記の業績連動給与とは、「利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第54条の2第1項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。」(法法34⑤)と定められている。
(2)かくして、法人税法においては、役員に対して支給する給与については、それが「退職給与」に該当するか、あるいは、「使用人としての職務を有する役員」すなわち使用人兼務役員に対して支給するものに該当する以外は、前記(1)にいう①から③に該当する給与を除き損金の額に算入されないことになる。そのため、本来、役員の役務提供の対価として支給されるものであり、企業会計上も賞与であっても費用として認識され、かつ、会社法上もお手盛り支給を規制するために株主総会の承認等を経ている「役員給与」について、原則的に損金性を否定することは、前記1で述べたように、その合理性が否定されることにもなり、当該規定の違憲性が惹起されることになる(注7)。
ともあれ、本件各歩合給のような不規則的に支給される役員給与であっても、前述のように、それが使用人兼務役員に対して支給するものであれば、当該給与の損金性に道を開くことになるので、法人税法上の「役員」及び「使用人兼務役員」の意義・範囲を確認しておく必要がある。
なお、法人税34条において損金不算入の対象となる「給与」には、「債務の免除による利益その他の経済的な理由を含むものとする。」(法法34④)(注8)と定められている。
3 「役員」・「使用人兼務役員」の意義と範囲 (1)法人税法上の「役員」とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」(法法2・一五)と定められている。そして、令7条は、役員の範囲について、次のように定めている。
「一、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二、同族会社の使用人のうち、第71条第1項第5号イからハまで(〈略〉)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの」
また、上記の「役員」の解釈については、法人税基本通達が、「「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。」(法基通9-2-1)と定め、「……役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する。」(同9-2-2)と定めている。
(2)次に、本件で問題となっている「使用人兼務役員」の意義・範囲については、次のように定められている。まず、法34条6項は、「第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。」と定めている。
そして、令71条1項は、使用人兼務役員とされない役員について、次の5項目に該当する役員を挙げている。
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
④ 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ 同族会社の役員のうち所定の株主グループに属する者
また、上記の法令に定める「使用人兼務役員」の範囲についての解釈につき、法人税基本通達の取扱いの主要なものは、次のとおりである。まず、法人税基本通達9-2-4は、「令第71条第1項第2号(〈略〉)に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。」と定めている。これは、営業活動の便宜上、通称専務・常務あるいは名刺上の専務・常務についてはその実態に応じて使用人兼務役員に該当することがあり得ることを意味している(注9)。
また、法人税基本通達9-2-5は、「法第34条第6項(〈略〉)に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位ではなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員に該当しない。」と定めている。
なお、小規模な法人においては機構上職制が明確でないこともあって、法人税基本通達9-2-6は、「事業内容が単純で使用人が少数等である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第35条第5項括弧書(〈略〉)に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。」と定めている。
そのほか、同族会社の役員のうち所定の株主グループに属する者は使用人兼務役員に該当しないと定められているところ、当該株主グループに属するか否かの判定等について所要の定めが設けられている(法基通9-2-7、9-2-8参照)。
4 本件各歩合給の損金性等 (1)本件においては、法34条の規定が違憲である旨のXの主張が容認されれば、本件更正等が無効(違法)となるが、それが適わなかったことは前記1で述べたとおりである。また、Xが控訴審において主張した本件各更正に係る理由附記の違法性については、控訴審判決は、前述のように、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあっても、当該更正の取消訴訟において理由の追加及び差替えが認められるから、違法事由にはならない旨判示し、かつ、本件各更正の理由には誤りが認められない旨判示している。
この控訴審判決については、更正の理由附記の不備(違法性)は、最高裁昭和47年3月31日第二小法廷判決(民集26巻2号319頁)等によって、更正の理由附記の不備は後の処分により是正されたとしても遡って違法性が治癒されるものではないと解されていることに照らすと妥当性を欠くものではないと考えられる(すなわち、控訴審判決が引用する理由の差替え問題とは事案を異にするものと考えられる。)。もっとも、控訴審判決は、本件各更正の理由附記に誤りがない旨認定しているのであるから、当該理由附記に不備はなかったことになる。
ともあれ、本件においては、本件各歩合給の損金性については、本件各歩合給が法34条1項1号から3号に規定する給与に該当しないことについては当事者間に争いがないわけであるから、後述するように、本件社員らが法人税法上の「役員」に該当するか、あるいは「使用人兼務役員」に該当するかが、究極の争点になる。
(2)まず、本件社員らが役員に該当しない理由について、Xは、「本件社員らは、弁理士法46条の規定により業務を執行する権利を有するとしても、対外的な業務を執行する権利を有しておらず、実際上、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に従事していない」旨主張した。
これに対し、一審判決は、弁理士法における特殊業務法人の社員の権限等に関する規定を参照し、「上記の権限や責任を伴う特許業務法人の社員は、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得るものであり、役員に該当する」と判示している。また、控訴審判決も、法2条15号の定義規定に照らし、特許業務法人の社員について、「その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができる」旨判示し、本件社員らの「役員」該当性を容認している。
確かに、前述したような法2条15号、令7条1号及び令71条1項3号の各規定と法人税基本通達9-2-1及び9-2-2の各規定に照らし、かつ、弁理士法人の特許業務法人の社員の権限、責任等に関する規定に照らすと、Xが主張するように、当該社員の勤務の実態に照らして、役員該当性を否定することは困難であると考えられる。
(3)次に、本件社員らの使用人兼務役員該当性については、役員該当性よりも検討する余地があるように考えられる。そこで、Xは、本件社員らが使用人兼務役員に該当することについて、「本件社員らについては、顧客ごとに編成されたグループのグループ代表として、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に全く従事してはいない」、「特許業務法人の社員が経営に関与する程度は様々であるから、当該法人の定款の規定及び勤務の実態を検討することなく、特許業務法人の社員が、弁理士法上、業務を執行する権利を有することから直ちに使用人兼務役員とされない役員に当たるということはできない」等を主張した。
これに対し、一審判決は、特許業務法人の社員が令71条1項各号に定める役員に該当しないことを認めながらも、「特許業務法人の社員は、特許業務法人の経営に係る業務を含む業務の執行をする権利を有し、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるところ、業務を執行する役員と特許業務法人との関係には民法の委任に関する規定が準用され(〈略〉)、両者は一般には雇用契約等に基づく使用人と事業主との関係に立つものではないというべきであるから、弁理士である役員が従事する具体的な職務の中に使用人である弁理士が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るものである。」と判示し、特許業務法人の社員の使用人兼務役員該当性を否定している。そして、控訴審判決も、前述のように、原判決の考え方を支持している。
また、本件のような場合には、法人税基本通達9-2-6の適用が特に問題とされるところ、本件各判決は、同通達の適用につき、前述のように、「一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員には適用されない」と一蹴している。このような判断については、判示における理論的整合性はともかくとして、税理士法人の場合には、税理士事務所の法人化を行うため、オーナー所長を代表とし、税理士有資格者を数合わせのために社員に登用しているが、当該社員の勤務状態は従前の勤務税理士と同様な場合が多く見られるところであるので、単に「一般的・類型的」で判断することに疑問が生じる。換言すると、本件各判決の考え方で足りるというのであれば、法人税基本通達9-2-6の存在が無意味になるように考えられる。
5 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、特許業務法人の社員に対して支給した本件各歩合給の損金性が争われたものであるが、主要な争点として、法34条1項の規定の合憲性、本件社員らの「役員」及び「使用人兼務役員」の該当性が問題となったものである。法34条1項の規定の合憲性については、筆者もかねてから疑問を提起したところであるが、それが法廷で争われることになると、本件各判決も引用する最高裁昭和60年3月27日大法廷判決が盾となって、本件各判決の判示するところとなる。しかしながら、このような事件が度重なることになると、平成18年改正で創設された法35条が、その合理性に問題があるということでその4年後に廃止されたように、法34条1項についても再検討の道が開かれることになるかも知れない。
また、本件社員らの法人税法上の「役員」該当性については、弁理士法等の規定に照らして否定し難いことであろうが、「使用人兼務役員」該当性については、前述したように問題点が残されているものと考えられる。特に、この点については、税理士法人の社員については、一層問題があるように考えられるので、当該解釈論については更に検討する必要があるものと考えられる。
(注1)旧法時代の役員報酬課税の問題点等については、品川芳宣「役員報酬課税の問題点と方向性」JICPAジャーナル2006年2月号39頁等参照。
(注2)これらの経緯については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)」本誌2008年4月14日号27頁参照。
(注3)平成18年改正の役員給与課税規定の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(後)」本誌2008年4月21日号24頁等参照。
(注4)同判決は、給与所得者が事業所得者等に対し不平等に扱われているということで、所得税法28条の憲法14条違反の有無が争われた事案につき、合憲判断を示したものである(詳細については、品川芳宣ほか「戦後重要租税判例の再検証-税務事例創刊400号記念-」(財経詳報社 2003年)2頁、12頁等参照)。
(注5)最近の租税法規に係る違憲訴訟の動向については、前出(注3)32頁等参照。
(注6)これらの問題の解決の方向性については、前出(注4)31頁等参照。
(注7)法人税法上の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の「益金の額から損金の額を控除した金額」(法法22①)であると定められているところ、法人税法では伝統的に純資産増加税が採用されており、当該損金の額について、「純資産減少の原因となるべき一切の事実をいう」(旧法人税基本通達52)と解されてきたことに鑑みても、「役員給与」それ自体の損金性を原則的に否定することに合理性があるものとは考えられない。
(注8)経済的利益の意義・範囲については、法人税基本通達9-2-9、同9-2-10に例示されている。
(注9)小原一博編著「法人税基本通達逐条解説 8訂版」(税務研究会 平成28年)733頁、大阪地裁昭和35年1月26日判決(行裁例集11巻1号107頁)、広島高裁昭和45年6月17日判決(税資59号1001頁)等参照。
特許業務法人の社員に対する歩合給の損金性・法人税法34条の合憲性・更正の理由附記の違法性
東京高裁平成29年8月28日判決(平成29年(行コ)第37号)
東京地裁平成29年1月18日判決(平成26年(行ウ)第533号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)特許業務法人であるX(原告・控訴人)は、平成20年3月期ないし平成24年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の各期分法人税につき、代表社員であるA以外の社員であるL、M及びN(以下3名を「本件社員ら」という。)に対し、固定給のほか、各人の業績に対応した実績給及び賞与(以下「本件各歩合給」という。)を支給し、所得金額の計算上損金の額に算入して確定申告をした。
これに対し、所轄税務署長は、本件社員らがいずれも法人税法(以下「法」という。)上の役員に該当し、かつ、使用人としての職務を有する役員(以下「使用人兼務役員」という。)に該当しないから、本件各歩合給は本件各事業年度分法人税の所得金額の計算上損金の額に算入できないとする更正処分(以下「本件各更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定」といい、本件各更正と併せて「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、前審手続を経て、国(被告・被控訴人)に対し、本件更正等の取り消しを求めて本訴を提起した。
(2)Xは、Aが昭和51年3月1日から個人事業主として弁理士業を営んでいたH国際特許事務所の業務を承継し、平成15年3月5日に弁理士法に基づき設立された特許業務法人であり、国内及び外国への特許・実用新案等の出願代理、審判・訴訟代理、鑑定書の作成等の業務をしている。そして、Aは、上記法人設立時に代表者に選任され、本件社員らは、H国際特許事務所の時代から弁理士として業務に従事し、上記法人設立時のXの社員になったものである。本件社員らは、平成15年4月1日付で、Xとの間で、Xから受ける給与に関し契約(以下「本件各契約」という。)を締結しているところ、本件社員らに対する報酬は、月給制で、固定給及び歩合給の両建てとなっており、歩合給の金額は本件社員らの担当した件についてXが顧客に請求する額に一定比率を乗じた額とされた。また、本件社員らには、Xの就業規則に規定された賞与及び退職金の規定は適用されないとされた。
(3)特許業務法人は、弁理士の業務を組織的に行うことを目的として、弁理士法の定めるところにより、弁理士が共同して設立する法人である(同法2⑥)。特許業務法人の社員は、弁理士でなければならないとされ(同法39①)、全ての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う(同法46)。そして、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされる(同法47の4①)。また、各自、特許業務法人を代表することとされる(同法47の2①)一方、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げないとされており(同②)、その上で、特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するとされている(同③)。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件更正等の適法性(本件各歩合給の損金への算入の可否)であるところ、具体的には、①本件社員らの役員該当性、②本件社員らの使用人兼務役員該当性及び③法34条1項の合憲性である。なお、Xは、控訴審において、本件更正の理由附記の不備の違法性を主張している。
2 国の主張 (1)本件社員らはいずれも特許業務法人であるXの社員であるところ、特許業務法人の社員は、全ての社員がその業務を執行する権利を有し、義務を負うとされる上、特許業務法人の社員の業務を執行する権利は、法令上、定款によっても制限することができず、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるから、本件社員らはXという特許業務法人の経営に従事する権限を有する地位にあるものとして、役員に該当するというべきである。
(2)特許業務法人の社員は、前記のとおり、定款によっても制限できない特許業務法人の業務を執行する権利を有し、義務を負うのみならず、弁理士法上、その代表者を選任する権限を有すること、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされること等から、使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものとはおよそいえず、使用人兼務役員には該当しない。
(3)法34条1項の規定は、役員の給与の支給の恣意性を排除することにより課税の公平を害することがないようにするためであると解され、その立法目的は正当なものというべきであり、また、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められないから、同項が憲法に違反するとはいえない。
3 Xの主張 (1)法2条15号、令7条1号は、役員につき、法人の経営に従事する権限を有する者とするのではなく、法人の経営に従事している者とする旨を定めていることからすれば、役員該当性については、経営の権限の有無ではなく、実際に経営に従事しているかで判断すべきである。Xにおいては、代表社員であるAのみが、代表権、すなわち、対外的な業務を執行する権利を有し、Xの経営に従事している一方、本件社員らは、弁理士法46条の規定により業務を執行する権利を有するとしても、対外的な業務を執行する権利を有しておらず、実際上、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に従事していない。
(2)本件社員らについては、法34条5項に照らし、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者に該当するか又はその実質があれば、使用人兼務役員と認められるというべきである。そして、仮に法人の使用人としての職制上の地位を有すると認められないとしても、法人税基本通達9-2-6にあるように、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるから、使用人兼務役員に該当するというべきである。
(3)役員の給与は、企業会計上は費用として処理されるものであるが、平成18年法律第10号による改正(以下「平成18年改正」という。)後の法34条1項は、原則として、定期同額給与等、一定の要件に該当するもの以外、役員の給与を損金の額に算入することを制限するに至ったものであるところ、かかる制限は、過度なものであって、憲法22条、29条が規定する法人の営業の自由を侵害し、また、憲法14条1項が規定する平等原則に反して違憲・無効である。
(4)そもそも、使用人兼務役員は、役員としての地位(委任関係)と使用人としての地位(雇用関係)を併有するものと解されるところ、原判決のように法人との関係で委任関係にあることをもって使用人兼務役員とされない役員と解釈するのであれば、法上、使用人兼務役員の存在を認める余地がなくなる。また、特許業務法人の社員が経営に関与する程度は様々であるから、当該法人の定款の規定及び勤務の実態を検討することなく、特許業務法人の社員が、弁理士法上、業務を執行する権利を有することから直ちに使用人兼務役員とされない役員に当たるということはできない(控訴審)。
(5)本件各更正では、「更正の理由」として、「弁理士法第46条においては、「特許業務法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う」こととされており、この社員の業務を執行する権限は、定款によっても制限することはできないこととされています。また、同条の業務執行とは法人の営業に関する事務を執行することとされており、契約締結等の法人の営業に関する法律行為や帳簿の記入等の事実行為も含まれることとされていることからすれば、特許業務法人の社員は、令7条1号の「職制上使用人としての地位のみを有する者」とはなり得ず、かつ、特許業務法人の社員全てが、営業に関する法律行為を含む業務執行を行う者であり、同号の「法人の経営に従事している者」と認められることから、法人税法上の役員に該当します。」との記載がある。
しかし、本件各更正の「更正の理由」には一見して明白な誤りがあるから、この点だけからも、本件各更正は取り消されるべきである(控訴審)。
三、一審判決要旨
請求棄却。
1 本件社員らの役員該当性 (1)法2条15号及び法34条5項の規定からすれば、法は、常時使用人としての職務に従事する者であっても、「法人の経営に従事している」者として役員に該当し得るものであることを定めているということができ、また、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る地位・職責を有する者を列挙し、これらの者については、当該個々の法人において具体的にどのような内容の職務に従事しているかを問うことなく、一律に役員に該当するものとしているのであるから、同号の規定にいう「法人の経営に従事している」者とは、法人内における地位・職責からみて法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る者を指し、このような者に該当する者であれば当該個々の法人における具体的な職務の内容を問わないものと解するのが相当であり、令7条1号にいう「法人の経営に従事している」者についても、これと同義と解するのが相当である。
(2)そこで、本件について検討するに、本件社員らはいずれも特許業務法人であるXの社員であるところ、弁理士法の規定によれば、特許業務法人の社員は、全ての社員がその業務を執行する権利を有し、義務を負うとされる上、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解され、また、特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずるとされる。したがって、上記の権限や責任を伴う特許業務法人の社員は、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得るものであり、役員に該当すると解されるから、その地位にある本件社員らは、Xにおける具体的な職務の内容にかかわらず、Xの役員に該当するというべきである。
2 本件社員らの使用人兼務役員該当性 (1)法は、34条5項において、役員のうち「部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」を使用人兼務役員と定めるが、役員のうち「社長、理事長その他政令で定めるもの」については、使用人兼務役員から除いている。このように法が「社長、理事長」を使用人兼務役員から除いているのは、これらの役員が、法人との間で雇用契約等に基づく事業主と使用人との関係に立つものではなく、その従事する具体的な職務の中に使用人が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るからであると解される。そして、使用人としての職制上の地位を有さず、又は、使用人としての立場でその職務に従事しているものではないと一般的・類型的に評価し得る役員は、上記のように定義される使用人兼務役員には含まれないから、このような役員は、使用人兼務役員に該当しないと解するのが相当であり、法34条5項による政令への委任も、そのように一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員を定めることを委ねたものということができる。
(2)そこで、本件について検討するに、特許業務法人の社員は、法34条5項の社長及び理事長や、その他、同項の委任を受けた令71条1項各号で定める役員には該当しない。
もっとも、前述のとおり、特許業務法人の社員は、特許業務法人の経営に係る業務を含む業務の執行をする権利を有し、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるところ、業務を執行する役員と特許業務法人との関係には民法の委任に関する規定が準用され(弁理士法55①、会社法593④)、両者は一般には雇用契約等に基づく使用人と事業主との関係に立つものではないというべきであるから、弁理士である役員が従事する具体的な職務の中に使用人である弁理士が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るものである。したがって、特許業務法人の社員は、使用人兼務役員に該当しないものというべきであり、このような解釈は、令71条1項3号に、特許業務法人の役員と同様に民法の委任の規定が準用される(会社法593④)「合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員」が掲げられていることと整合的であるということができる。
(3)以上に対して、Xは、本件社員らは、法人税基本通達9-2-6にあるように、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるから、使用人兼務役員に該当する上、その各給与は、本件各歩合給も含め、全額が使用人としての職務に対して支給されたものである旨を主張する。しかしながら、法人税基本通達9-2-6は、前述のとおり一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員には適用されないものと解されるから、Xの主張は採用することができない。
3 法人税法34条1項の合憲性 (1)租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、専門技術的な判断を必要とすることも明らかであって、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきであるから、その租税法の立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された課税要件等の定めが同目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項、22条、29条等の規定に違反するものということはできないものというべきである(最高裁昭和60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁参照)。
(2)そこで、法34条1項について検討するに、同項の趣旨は、法人と役員との関係に鑑み、役員の給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば、その支給額をほしいままに決定し、法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがあり、課税の公平を害することとなるためであり、他方、同項各号に該当するものや使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与等については、上記のような役員の給与の支給の恣意性が排除されており、その額を損金の額に算入することとしても、課税の公平を害することはないと判断されたためであると解されるところ、その立法目的は正当なものというべきであり、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められないから、同項の規定は憲法14条1項、22条、29条等の規定に違反するものではないというべきである。
四、控訴審判決要旨
控訴棄却。 (1)当裁判所も、Xの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正・付加するほかは、原判決のとおりであるから、これを引用する。
(2)法2条15号前段は、その列挙する取締役等につき、その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、一律に「法人の経営に従事している者」に該当すると規定するものであることは明らかであり、それは、法2条15号前段に列挙されている職位の者が、その有する法令上の権限等に照らし、その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができることによるものであるから、同号後段及び令7条1号の「法人の経営に従事している者(もの)」に該当するか否かも、その有する法令上の権限等に照らし、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができるか否かにより判断すべきであって、これと異なるXの主張は採用できない。
また、そもそも、法上の役員の範囲はその定義規定である法2条15号によって画されることは明らかであるから、法34条1項の趣旨を根拠に役員の範囲を画することはできない。また、当該個々の法人における具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得る地位・職責を有する者を法34条1項の対象とすることは、予測可能性や納税者間の公平の観点からみて合理的であると解することができる。
(3)Xは、使用人兼務役員は、役員としての地位(委任関係)と使用人としての地位(雇用関係)を併有するものと解されるところ、原判決のように法人との関係で委任関係にあることをもって使用人兼務役員とされない役員と解釈するのであれば、法上、使用人兼務役員の存在を認める余地がなくなると主張する。
しかし、引用に係る原判決に説示のとおり、原判決は、使用人兼務役員に該当するか否かについて、当該役員が法人との間で委任関係にあるか否かで一律に判断するとしたものではなく、法34条5項の「常時使用人としての職務に従事するもの」に該当するか否かの判断につき、当該役員が従事する具体的な職務の中に使用人が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、使用人としての立場でその職務に従事しているものではないと認められる場合があるとしたものであるから、Xの非難は当たらない。
(4)Xは、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあるから、それだけで同処分は取り消されるべきであると主張する。しかし、法130条2項によれば、内国法人が提出した法人税の青色申告書につき、税務署長が更正処分を行う場合には更正通知書に更正の理由を付記することを要するが、証拠によれば、本件各更正には更正の理由が付記されていると認められ、また、更正処分取消訴訟においては、原則として理由の追加及び差替えが認められると解されていること(最高裁昭和56年7月14日判決・民集35巻5号901頁参照)に照らせば、仮に本件各更正の「更正の理由」の記載中に一部誤りがあったとしても、それ自体が本件各更正の取消事由となるとは解されない。
また、上記の点はひとまず措くとしても、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあるとも認められない。
五、解説
はじめに 本件は、特許業務法人であるXが、その社員3名(代表社員を除く。本件社員ら)に対し、固定給のほか、各人の業績に対応した実績給与及び賞与(本件各歩合給)を支給した場合に、本件各歩合給の損金性が争われたものである。平成18年改正後の法人税法34条は、そのタイトルを「役員給与の損金不算入」と題し、原則として、会社法等において適法に支給された役員報酬等の損金性を否定し、同条1項に定めた3項目の給与についてのみ、損金算入を認めている。
そのため、本件各歩合給のような役員報酬等については、損金性についての実質とは関係なく、形式的に損金不算入とされるので、法人税法34条の規定それ自体の合理性・違憲性が問題となる。本件においても、そのことがもろに争われている。また、本件各歩合給のような給与であっても、法人税法上の使用人兼務役員に支給される場合には、損金算入の道が開かれるため、本件においても、本件社員らの使用人兼務役員の該非が問題になっている。以下、これらの論点について解説する。
なお、本件は、特許業務法人の社員に対する給与の損金性が問題になっているのであるが、当該社員と税理士法人の社員と共通するところが多いので、税理士法人の実務についても両者を比較しながら注視しておく必要がある。
1 役員給与損金不算入規定の合理性(違憲性) (1)平成18年改正前の旧法人税法では、役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺい仮装して経理したものは、損金不算入とされ(旧法34①②)、役員賞与は損金不算入とされ(旧法35①)、役員退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な金額は、損金不算入とされていた(旧法36)(注1)。ところが、平成17年に制定された会社法の下では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価が一括して「報酬等」として括られ、その報酬等が定款の定め又は株主総会の決議によって律せられることとなった(会社法361)。これは、役員賞与が利益処分でないこと、そして、退職慰労金も職務執行の対価である限り、報酬等に含まれることを意味している。そのため、企業会計基準委員会も、平成17年11月29日付で、「役員賞与に関する会計基準」を発し、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」(同基準3)ことを明確にした(注2)。かくして、平成18年に、これらの企業会計上の役員報酬の会計処理に対処するため、法人税法が改正され、同法34条は、そのタイトルを「過大役員報酬の損金不算入」から「役員給与の損金不算入」に改められ、同条が定める定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与以外の給与を損金不算入とし(法法34①)、かつ、役員給与の額のうち不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽・仮装して支給する給与の額を損金不算入とした(法法34②③)。更に、同法35条は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与については、当該給与に係る所得税法28条3項に定める給与所得控除額相当額について損金不算入とした(旧法法35)。このような法人税法の税務処理は、会社法及び企業会計上が役員報酬の費用処理を弾力的(拡大的)にしたのに逆行し、役員給与の損金性を殊更に狭くしたものと言える。
(2)かくして、法人税法34条以下の役員給与課税の規定については、当初からその合理性が問われてきたところであり(注3)、同法35条については、立法政策上その合理性に問題があるということで、平成22年に廃止されたところである。そのため、本訴においても、X会社は、法人税法34条1項等の規定に基づく本件各更正等は憲法14条、22条、29条等に違反する旨主張するに至っている。
しかしながら、租税法規の違憲問題については、本件各判決も引用する最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注4)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。」と判示して以降、それが判例法として機能し、各裁判所は違憲判断について極めて慎重になっている(注5)。そのため、一審判決も、法人税法34条1項の規定につき、「法人と役員との関係に鑑み、役員の給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば、その支給額をほしいままに決定し、法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがあり、課税の公平を害することとなるためであり」と判示し、次いで、「その立法目的は正当なものというべきであり、その課税要件等の定めが当該立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとも認められない」と判示し、Ⅹの違憲主張を斥け、控訴審判決もそれを支持している。
もっとも、このような合憲判断については、例えば、役員給与を恣意的に過大に支給すれば、法人税率よりも一層厳しい所得税の累進税率の適用を受けるわけであるから、説得的な判示とも認め難いわけである。また、平成18年改正で設けられた法人税法35条の規定については、前述したように、その合理性に問題があったからこそ廃止されたわけであるし、そのほか、法人税法34条等には種々の問題点を有しているところであるので、当該立法政策の合理性の有無と解釈の方向性については引き続き検討すべきである(注6)。
2 役員給与の損金不算入 (1)前述したように、法人税法34条は、そのタイトルを「役員給与の損金不算入」と題し、同条1項では、「内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。(以下略))のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。
そして、損金算入の対象となる給与について、次の3項目を定めている(法法34①一~三)。
① 定期同額給与 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(その他これに準ずるものとして政令で定める給与)
② 所定の給与で①及び③に該当しないもの(事前確定届出給与) その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
③ 業績連動給与 内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(所定の役員に限る。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、所定の要件を満たすもの
また、上記の業績連動給与とは、「利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第54条の2第1項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。」(法法34⑤)と定められている。
(2)かくして、法人税法においては、役員に対して支給する給与については、それが「退職給与」に該当するか、あるいは、「使用人としての職務を有する役員」すなわち使用人兼務役員に対して支給するものに該当する以外は、前記(1)にいう①から③に該当する給与を除き損金の額に算入されないことになる。そのため、本来、役員の役務提供の対価として支給されるものであり、企業会計上も賞与であっても費用として認識され、かつ、会社法上もお手盛り支給を規制するために株主総会の承認等を経ている「役員給与」について、原則的に損金性を否定することは、前記1で述べたように、その合理性が否定されることにもなり、当該規定の違憲性が惹起されることになる(注7)。
ともあれ、本件各歩合給のような不規則的に支給される役員給与であっても、前述のように、それが使用人兼務役員に対して支給するものであれば、当該給与の損金性に道を開くことになるので、法人税法上の「役員」及び「使用人兼務役員」の意義・範囲を確認しておく必要がある。
なお、法人税34条において損金不算入の対象となる「給与」には、「債務の免除による利益その他の経済的な理由を含むものとする。」(法法34④)(注8)と定められている。
3 「役員」・「使用人兼務役員」の意義と範囲 (1)法人税法上の「役員」とは、「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」(法法2・一五)と定められている。そして、令7条は、役員の範囲について、次のように定めている。
「一、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二、同族会社の使用人のうち、第71条第1項第5号イからハまで(〈略〉)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの」
また、上記の「役員」の解釈については、法人税基本通達が、「「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。」(法基通9-2-1)と定め、「……役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する。」(同9-2-2)と定めている。
(2)次に、本件で問題となっている「使用人兼務役員」の意義・範囲については、次のように定められている。まず、法34条6項は、「第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。」と定めている。
そして、令71条1項は、使用人兼務役員とされない役員について、次の5項目に該当する役員を挙げている。
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
④ 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ 同族会社の役員のうち所定の株主グループに属する者
また、上記の法令に定める「使用人兼務役員」の範囲についての解釈につき、法人税基本通達の取扱いの主要なものは、次のとおりである。まず、法人税基本通達9-2-4は、「令第71条第1項第2号(〈略〉)に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。」と定めている。これは、営業活動の便宜上、通称専務・常務あるいは名刺上の専務・常務についてはその実態に応じて使用人兼務役員に該当することがあり得ることを意味している(注9)。
また、法人税基本通達9-2-5は、「法第34条第6項(〈略〉)に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位ではなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員に該当しない。」と定めている。
なお、小規模な法人においては機構上職制が明確でないこともあって、法人税基本通達9-2-6は、「事業内容が単純で使用人が少数等である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第35条第5項括弧書(〈略〉)に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。」と定めている。
そのほか、同族会社の役員のうち所定の株主グループに属する者は使用人兼務役員に該当しないと定められているところ、当該株主グループに属するか否かの判定等について所要の定めが設けられている(法基通9-2-7、9-2-8参照)。
4 本件各歩合給の損金性等 (1)本件においては、法34条の規定が違憲である旨のXの主張が容認されれば、本件更正等が無効(違法)となるが、それが適わなかったことは前記1で述べたとおりである。また、Xが控訴審において主張した本件各更正に係る理由附記の違法性については、控訴審判決は、前述のように、本件各更正の「更正の理由」の記載中に誤りがあっても、当該更正の取消訴訟において理由の追加及び差替えが認められるから、違法事由にはならない旨判示し、かつ、本件各更正の理由には誤りが認められない旨判示している。
この控訴審判決については、更正の理由附記の不備(違法性)は、最高裁昭和47年3月31日第二小法廷判決(民集26巻2号319頁)等によって、更正の理由附記の不備は後の処分により是正されたとしても遡って違法性が治癒されるものではないと解されていることに照らすと妥当性を欠くものではないと考えられる(すなわち、控訴審判決が引用する理由の差替え問題とは事案を異にするものと考えられる。)。もっとも、控訴審判決は、本件各更正の理由附記に誤りがない旨認定しているのであるから、当該理由附記に不備はなかったことになる。
ともあれ、本件においては、本件各歩合給の損金性については、本件各歩合給が法34条1項1号から3号に規定する給与に該当しないことについては当事者間に争いがないわけであるから、後述するように、本件社員らが法人税法上の「役員」に該当するか、あるいは「使用人兼務役員」に該当するかが、究極の争点になる。
(2)まず、本件社員らが役員に該当しない理由について、Xは、「本件社員らは、弁理士法46条の規定により業務を執行する権利を有するとしても、対外的な業務を執行する権利を有しておらず、実際上、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に従事していない」旨主張した。
これに対し、一審判決は、弁理士法における特殊業務法人の社員の権限等に関する規定を参照し、「上記の権限や責任を伴う特許業務法人の社員は、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価し得るものであり、役員に該当する」と判示している。また、控訴審判決も、法2条15号の定義規定に照らし、特許業務法人の社員について、「その従事する具体的な職務の内容にかかわらず、法人の経営に従事していると一般的・類型的に評価することができる」旨判示し、本件社員らの「役員」該当性を容認している。
確かに、前述したような法2条15号、令7条1号及び令71条1項3号の各規定と法人税基本通達9-2-1及び9-2-2の各規定に照らし、かつ、弁理士法人の特許業務法人の社員の権限、責任等に関する規定に照らすと、Xが主張するように、当該社員の勤務の実態に照らして、役員該当性を否定することは困難であると考えられる。
(3)次に、本件社員らの使用人兼務役員該当性については、役員該当性よりも検討する余地があるように考えられる。そこで、Xは、本件社員らが使用人兼務役員に該当することについて、「本件社員らについては、顧客ごとに編成されたグループのグループ代表として、他の社員ではない従業員である弁理士と同様、弁理士としての日常の職務を行っているのみであって、Xの経営に全く従事してはいない」、「特許業務法人の社員が経営に関与する程度は様々であるから、当該法人の定款の規定及び勤務の実態を検討することなく、特許業務法人の社員が、弁理士法上、業務を執行する権利を有することから直ちに使用人兼務役員とされない役員に当たるということはできない」等を主張した。
これに対し、一審判決は、特許業務法人の社員が令71条1項各号に定める役員に該当しないことを認めながらも、「特許業務法人の社員は、特許業務法人の経営に係る業務を含む業務の執行をする権利を有し、定款又は総社員の同意によって代表社員が定められた場合であっても、代表権以外の業務を執行する権利を有するものと解されるところ、業務を執行する役員と特許業務法人との関係には民法の委任に関する規定が準用され(〈略〉)、両者は一般には雇用契約等に基づく使用人と事業主との関係に立つものではないというべきであるから、弁理士である役員が従事する具体的な職務の中に使用人である弁理士が行う職務と同種の職務が含まれている場合であっても、それは使用人としての立場で従事するものではないと一般的・類型的に評価し得るものである。」と判示し、特許業務法人の社員の使用人兼務役員該当性を否定している。そして、控訴審判決も、前述のように、原判決の考え方を支持している。
また、本件のような場合には、法人税基本通達9-2-6の適用が特に問題とされるところ、本件各判決は、同通達の適用につき、前述のように、「一般的・類型的に使用人兼務役員から除かれる役員には適用されない」と一蹴している。このような判断については、判示における理論的整合性はともかくとして、税理士法人の場合には、税理士事務所の法人化を行うため、オーナー所長を代表とし、税理士有資格者を数合わせのために社員に登用しているが、当該社員の勤務状態は従前の勤務税理士と同様な場合が多く見られるところであるので、単に「一般的・類型的」で判断することに疑問が生じる。換言すると、本件各判決の考え方で足りるというのであれば、法人税基本通達9-2-6の存在が無意味になるように考えられる。
5 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、特許業務法人の社員に対して支給した本件各歩合給の損金性が争われたものであるが、主要な争点として、法34条1項の規定の合憲性、本件社員らの「役員」及び「使用人兼務役員」の該当性が問題となったものである。法34条1項の規定の合憲性については、筆者もかねてから疑問を提起したところであるが、それが法廷で争われることになると、本件各判決も引用する最高裁昭和60年3月27日大法廷判決が盾となって、本件各判決の判示するところとなる。しかしながら、このような事件が度重なることになると、平成18年改正で創設された法35条が、その合理性に問題があるということでその4年後に廃止されたように、法34条1項についても再検討の道が開かれることになるかも知れない。
また、本件社員らの法人税法上の「役員」該当性については、弁理士法等の規定に照らして否定し難いことであろうが、「使用人兼務役員」該当性については、前述したように問題点が残されているものと考えられる。特に、この点については、税理士法人の社員については、一層問題があるように考えられるので、当該解釈論については更に検討する必要があるものと考えられる。
(注1)旧法時代の役員報酬課税の問題点等については、品川芳宣「役員報酬課税の問題点と方向性」JICPAジャーナル2006年2月号39頁等参照。
(注2)これらの経緯については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)」本誌2008年4月14日号27頁参照。
(注3)平成18年改正の役員給与課税規定の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(後)」本誌2008年4月21日号24頁等参照。
(注4)同判決は、給与所得者が事業所得者等に対し不平等に扱われているということで、所得税法28条の憲法14条違反の有無が争われた事案につき、合憲判断を示したものである(詳細については、品川芳宣ほか「戦後重要租税判例の再検証-税務事例創刊400号記念-」(財経詳報社 2003年)2頁、12頁等参照)。
(注5)最近の租税法規に係る違憲訴訟の動向については、前出(注3)32頁等参照。
(注6)これらの問題の解決の方向性については、前出(注4)31頁等参照。
(注7)法人税法上の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の「益金の額から損金の額を控除した金額」(法法22①)であると定められているところ、法人税法では伝統的に純資産増加税が採用されており、当該損金の額について、「純資産減少の原因となるべき一切の事実をいう」(旧法人税基本通達52)と解されてきたことに鑑みても、「役員給与」それ自体の損金性を原則的に否定することに合理性があるものとは考えられない。
(注8)経済的利益の意義・範囲については、法人税基本通達9-2-9、同9-2-10に例示されている。
(注9)小原一博編著「法人税基本通達逐条解説 8訂版」(税務研究会 平成28年)733頁、大阪地裁昭和35年1月26日判決(行裁例集11巻1号107頁)、広島高裁昭和45年6月17日判決(税資59号1001頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -