解説記事2018年10月01日 【特別解説】 日本企業がIFRS移行時に行った表示科目の組替~差異調整表の調査分析①~(2018年10月1日号・№757)
特別解説
日本企業がIFRS移行時に行った表示科目の組替~差異調整表の調査分析①~
はじめに
2010年3月期より、一定の要件を満たしたわが国の企業に対して、IFRS(国際財務報告基準)の任意適用が認められるようになってから満8年が経過した。最初の3年間ほどはIFRSを任意適用する企業の数が伸び悩んだものの、その後は毎年20社前後のペースで着実に増加してきている。また、すかいらーくをはじめ、IFRSを任意適用して新規に上場する企業も増えており、IFRSを任意適用する日本企業の総数が200社を超えるのも、そう遠い先ではないように思われる。
これまでわが国の会計処理や表示の基準を適用していた日本企業がIFRSに移行する場合、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」第23項に基づいて、企業は、従前の会計原則からIFRSへの移行が、報告された財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローにどのように影響したのかを説明しなければならない。これは、従前の会計原則に従って報告されていた資本から、IFRSに準拠した資本への調整表(以下、「調整表」という。)と呼ばれ、ここでは、利用者が財政状態計算書及び包括利益計算書に対する重要な修正を理解できるようにするのに十分な詳細を示さなければならないとされている(IFRS第1号第25項)。
この「重要な修正」には、のれんの償却/非償却に代表される、IFRSとわが国の会計基準との間の差であるいわゆる「GAAP差異の修正(認識と測定に係る修正)」と、特別損益項目の区分表示の可否などの「財務諸表の表示科目の差異の修正」の2種類があり、いずれも調整表で説明が加えられている。
本稿では、「IFRSを任意適用して有価証券報告書を作成・提出した企業」(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)各社が、IFRSを初めて適用した期に作成した調整表を題材として、どのような項目が「財務諸表の表示科目の差異の修正」として説明されているかを調査分析した。その結果を、実際の開示例を紹介しつつ、2回に分けて紹介することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査の対象とした企業は、日本基準からIFRSへ任意で移行し、2018年3月期の有価証券報告書までに調整表を作成して開示した企業の149社である。なお、日立製作所やパナソニック、本田技研工業など、米国会計基準からIFRSに移行した企業は、今回の調査の対象とはしていない。また、調整表への説明の中で、本稿では「財務諸表上の表示科目の差異」のみを調査対象としており、「認識と測定の差異項目」は調査対象から除いている。したがって、今回調査対象とした修正項目はいずれも、最終損益には影響しないものである。また、今回は基本財務諸表の表示科目の組替項目のうち、財政状態計算書(連結貸借対照表)と包括利益計算書(連結損益計算書)に関するもののみを調査対象とし、キャッシュ・フロー計算書や株主持分変動計算書の表示科目の組替についての調査は省略した。
IAS第1号「財務諸表の表示」が規定する財務諸表の表示科目
わが国の連結財務諸表規則や財務諸表等規則が貸借対照表、損益計算書等の表示科目を詳細に定めているのに対し、原則主義に立脚するIFRSは、表示科目は最低限のものしか規定していない(特に、純損益の部に表示すべき科目として列挙されているものが少ない)といわれる。
IAS第1号が、財政状態計算書に掲記しなければならないとしている項目は、次のとおりである(第54項)。
IFRSは原則主義であるため、定められている表示科目は最低限であると述べたが、財政状態計算書(貸借対照表)に関する限り、表示科目はそれなりに細かく定められている。そして、金融資産や金融負債、投資不動産や持分法で会計処理されている投資などの区分掲記が要求されている点に特徴がある。また、IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産や、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的保有に分類される資産と、売却目的保有に分類される処分グループに含まれる資産との合計額、並びに売却目的保有に分類される処分グループに含まれる負債等、わが国では該当する会計基準がない項目も、区分して表示すべき科目とされている。
次に、純損益の部又は純損益計算書に含めなければならないとされている科目は、次のとおりである(第82項)。
これらのうち、IFRS第9号(金融商品)の適用に伴って新たに加えられた項目を除くと、純損益の部で表示が要求されるのは、収益、財務費用、持分法適用による損益、税金費用と非継続事業に係る損益のみとなる。わが国でもよく知られているように、営業利益や経常利益、営業外損益や特別損益項目の表示を求める規定はない。また、財政状態計算書と同様に、持分法で会計処理されている関連会社及び共同支配企業の純損益に対する持分や、非継続事業の合計に関する単一の金額の区分表示が求められている点が特徴であるといえよう。
IFRS任意適用日本企業が初度適用時に開示した表示組替の内容
IFRS任意適用日本企業が、IFRSの初度適用時に調整表で開示した連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示科目の主な組替を示すと、表1のとおりである。なお、各社の調整表において、最も多く記載されていた表示科目組替の内容は、「日本基準では流動・非流動の区分に分けて表示されていた繰延税金資産・負債を、IFRSでは一律に非流動項目に組み替えた」というものであったが、企業会計基準第28号「税効果会計に係る会計基準の一部改正について(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)」により、繰延税金資産・負債はIFRSと同様に、わが国においても一律に非流動項目として表示されるようになったことから、今回の調査では、両者の差異はなくなったものとみなして集計しなかった。
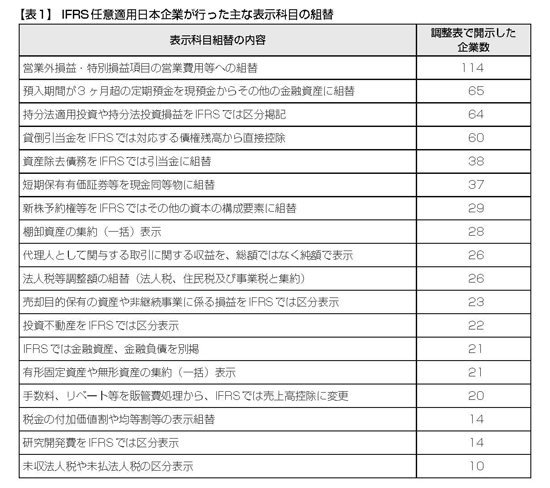
最終損益への影響はないとはいえ、これまでわが国企業の損益計算書においておなじみであった営業利益や営業外損益、特別損益の区分がIFRSではなくなるため、損益計算書の見かけは、これまでとは相当違ったものにならざるをえない。営業利益や経常利益が表示されないIFRSにおいて、何をもって企業の「本業で稼ぐ力」と見るべきかについては世界中で議論が行われており、まだ結論が出ていないが、財務諸表の利用者としては、日本基準でこれまで特別損益区分に表示されていた各項目(発生が臨時・多額な項目)が、IFRSに基づく損益計算書ではどこに含められているのか、注記に目を凝らして十分に分析する必要があるだろう。
IFRS任意適用企業がIFRSの初度適用時に行った表示科目の組替の状況を、IFRS上の表示科目をキーにして、貸借対照表、損益計算書の別に一覧にして示すと、表2及び表3のとおりである。
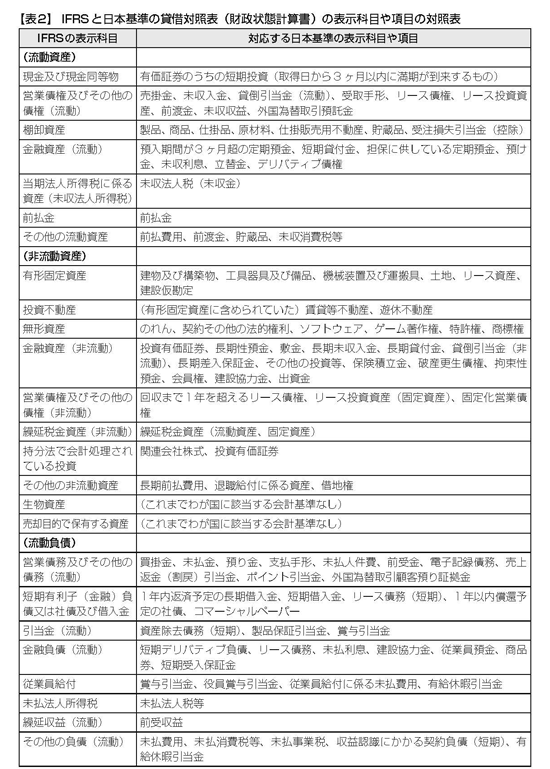
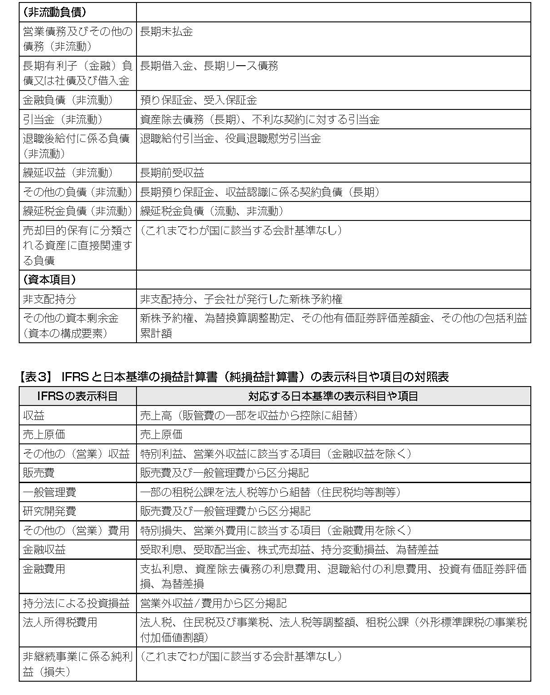
使用する勘定科目や区分の方法、それぞれの勘定科目残高の金額的な重要性等は各社各様であることから、必ずしも表2のとおりの勘定科目が使用されていない事例も存在し、したがってこの分類は絶対的なものではない。よく見られる代表例の一つ、目安としてご理解いただければ幸いである。
なお、本調査分析のパート2では、本稿の表1の「IFRS任意適用日本企業が行った主な表示科目の組替」で列挙した18項目について、実際の開示例を紹介しながら簡単にコメントしていくこととしたい。
日本企業がIFRS移行時に行った表示科目の組替~差異調整表の調査分析①~
はじめに
2010年3月期より、一定の要件を満たしたわが国の企業に対して、IFRS(国際財務報告基準)の任意適用が認められるようになってから満8年が経過した。最初の3年間ほどはIFRSを任意適用する企業の数が伸び悩んだものの、その後は毎年20社前後のペースで着実に増加してきている。また、すかいらーくをはじめ、IFRSを任意適用して新規に上場する企業も増えており、IFRSを任意適用する日本企業の総数が200社を超えるのも、そう遠い先ではないように思われる。
これまでわが国の会計処理や表示の基準を適用していた日本企業がIFRSに移行する場合、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」第23項に基づいて、企業は、従前の会計原則からIFRSへの移行が、報告された財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローにどのように影響したのかを説明しなければならない。これは、従前の会計原則に従って報告されていた資本から、IFRSに準拠した資本への調整表(以下、「調整表」という。)と呼ばれ、ここでは、利用者が財政状態計算書及び包括利益計算書に対する重要な修正を理解できるようにするのに十分な詳細を示さなければならないとされている(IFRS第1号第25項)。
この「重要な修正」には、のれんの償却/非償却に代表される、IFRSとわが国の会計基準との間の差であるいわゆる「GAAP差異の修正(認識と測定に係る修正)」と、特別損益項目の区分表示の可否などの「財務諸表の表示科目の差異の修正」の2種類があり、いずれも調整表で説明が加えられている。
本稿では、「IFRSを任意適用して有価証券報告書を作成・提出した企業」(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)各社が、IFRSを初めて適用した期に作成した調整表を題材として、どのような項目が「財務諸表の表示科目の差異の修正」として説明されているかを調査分析した。その結果を、実際の開示例を紹介しつつ、2回に分けて紹介することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査の対象とした企業は、日本基準からIFRSへ任意で移行し、2018年3月期の有価証券報告書までに調整表を作成して開示した企業の149社である。なお、日立製作所やパナソニック、本田技研工業など、米国会計基準からIFRSに移行した企業は、今回の調査の対象とはしていない。また、調整表への説明の中で、本稿では「財務諸表上の表示科目の差異」のみを調査対象としており、「認識と測定の差異項目」は調査対象から除いている。したがって、今回調査対象とした修正項目はいずれも、最終損益には影響しないものである。また、今回は基本財務諸表の表示科目の組替項目のうち、財政状態計算書(連結貸借対照表)と包括利益計算書(連結損益計算書)に関するもののみを調査対象とし、キャッシュ・フロー計算書や株主持分変動計算書の表示科目の組替についての調査は省略した。
IAS第1号「財務諸表の表示」が規定する財務諸表の表示科目
わが国の連結財務諸表規則や財務諸表等規則が貸借対照表、損益計算書等の表示科目を詳細に定めているのに対し、原則主義に立脚するIFRSは、表示科目は最低限のものしか規定していない(特に、純損益の部に表示すべき科目として列挙されているものが少ない)といわれる。
IAS第1号が、財政状態計算書に掲記しなければならないとしている項目は、次のとおりである(第54項)。
| (a)有形固定資産 (b)投資不動産 (c)無形資産 (d)金融資産(次の(e)、(h)及び(i)に示す金額を除く) (e)持分法で会計処理されている投資 (f)IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産 (g)棚卸資産 (h)売掛金及びその他の債権 (i)現金及び現金同等物 (j)IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的保有に分類される資産と、売却目的保有に分類される処分グループに含まれる資産との合計額 (k)買掛金及びその他の未払金 (l)引当金 (m)金融負債(上の(k)及び(l)に示す金額を除く) (n)IAS第12号「法人所得税」に基づく当期税金に係る負債及び資産 (o)IAS第12号に基づく繰延税金負債及び繰延税金資産 (p)IFRS第5号に従って売却目的保有に分類される処分グループに含まれる負債 (q)資本に表示される非支配持分 (r)親会社の所有者に帰属する発行済資本金及び剰余金 |
次に、純損益の部又は純損益計算書に含めなければならないとされている科目は、次のとおりである(第82項)。
| (a)収益(実効金利法を用いて計算した金利収益を区分して表示) (aa)償却原価で測定する金融資産の認識の中止により生じた利得及び損失 (b)財務費用 (ba)IFRS第9号のセクション5.5に従って算定した減損損失(減損損失の戻入れ又は減損利得を含む) (c)持分法で会計処理されている関連会社及び共同支配企業の純損益に対する持分 (ca)金融資産を償却原価の測定区分から純損益を通じて公正価値で測定するように分類変更した場合に、当該金融資産の従前の償却原価と分類変更日(IFRS第9号で定義)時点の公正価値との間の差額から生じた利得又は損失 (cb)金融資産をその他の包括利益を通じた公正価値の測定区分から純損益を通じた公正価値で測定するように分類変更した場合に、過去にその他の包括利益に認識した利得又は損失の累計額のうち純損益に振り替えるもの (d)税金費用 (ea)非継続事業の合計に関する単一の金額(IFRS第5号参照) |
IFRS任意適用日本企業が初度適用時に開示した表示組替の内容
IFRS任意適用日本企業が、IFRSの初度適用時に調整表で開示した連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示科目の主な組替を示すと、表1のとおりである。なお、各社の調整表において、最も多く記載されていた表示科目組替の内容は、「日本基準では流動・非流動の区分に分けて表示されていた繰延税金資産・負債を、IFRSでは一律に非流動項目に組み替えた」というものであったが、企業会計基準第28号「税効果会計に係る会計基準の一部改正について(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)」により、繰延税金資産・負債はIFRSと同様に、わが国においても一律に非流動項目として表示されるようになったことから、今回の調査では、両者の差異はなくなったものとみなして集計しなかった。
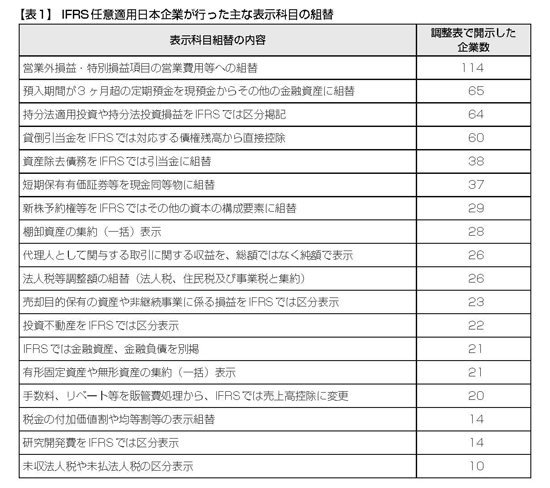
最終損益への影響はないとはいえ、これまでわが国企業の損益計算書においておなじみであった営業利益や営業外損益、特別損益の区分がIFRSではなくなるため、損益計算書の見かけは、これまでとは相当違ったものにならざるをえない。営業利益や経常利益が表示されないIFRSにおいて、何をもって企業の「本業で稼ぐ力」と見るべきかについては世界中で議論が行われており、まだ結論が出ていないが、財務諸表の利用者としては、日本基準でこれまで特別損益区分に表示されていた各項目(発生が臨時・多額な項目)が、IFRSに基づく損益計算書ではどこに含められているのか、注記に目を凝らして十分に分析する必要があるだろう。
IFRS任意適用企業がIFRSの初度適用時に行った表示科目の組替の状況を、IFRS上の表示科目をキーにして、貸借対照表、損益計算書の別に一覧にして示すと、表2及び表3のとおりである。
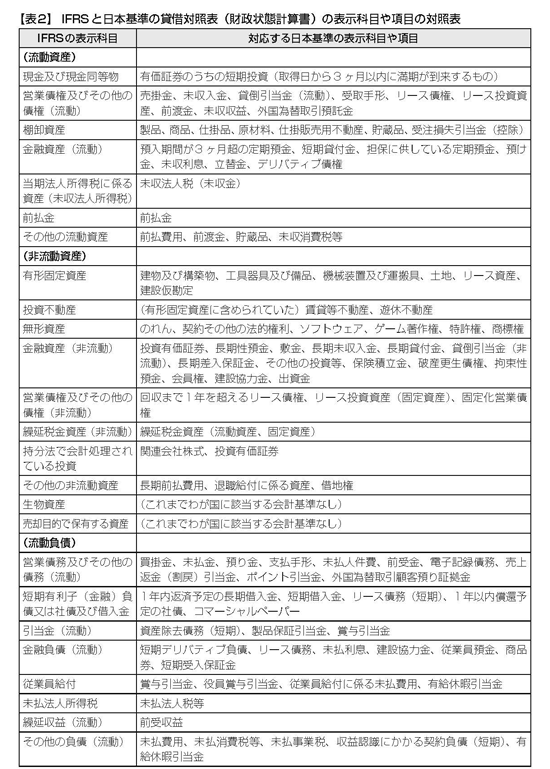
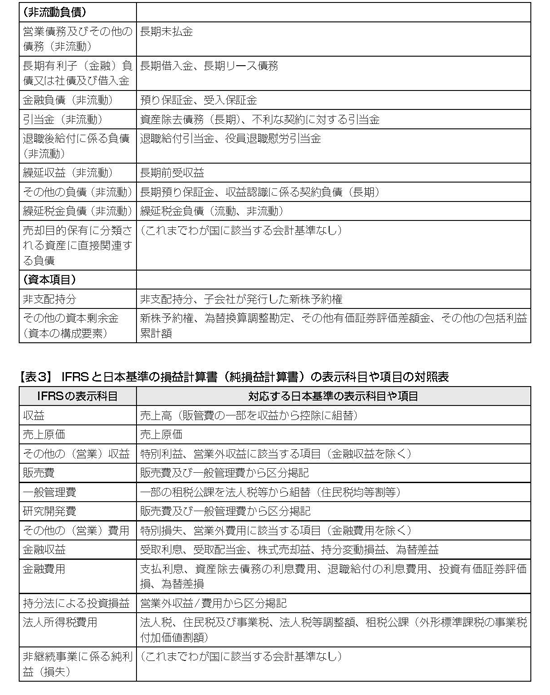
使用する勘定科目や区分の方法、それぞれの勘定科目残高の金額的な重要性等は各社各様であることから、必ずしも表2のとおりの勘定科目が使用されていない事例も存在し、したがってこの分類は絶対的なものではない。よく見られる代表例の一つ、目安としてご理解いただければ幸いである。
なお、本調査分析のパート2では、本稿の表1の「IFRS任意適用日本企業が行った主な表示科目の組替」で列挙した18項目について、実際の開示例を紹介しながら簡単にコメントしていくこととしたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















