解説記事2018年11月12日 【ニュース特集】 相続税・財産評価の審理事例をチェック(1)(2018年11月12日号・№763)
ニュース特集
小規模宅地特例、地積規模の大きな宅地の評価etc.
相続税・財産評価の審理事例をチェック(1)
今号の特集は、課税当局が相続税・財産評価の審理上の留意点として掲げているQ&Aを掲載する。相続税では、生産緑地に係る納税猶予の特例、小規模宅地等の特例について、財産評価では、地積規模の大きな宅地の評価に関する取扱いが示されている。
相続税編
01 特定生産緑地の指定を受けない都市営農農地(生産緑地)に係る納税猶予の特例の適用について
Q 平成30年度税制改正によって、生産緑地法及び都市計画法の改正に伴う都市営農農地等の範囲等が見直され、平成30年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する特例適用農地等に係る相続税又は贈与税に適用されることとなった。
ところで、E区の生産緑地Aを平成25年4月に父から相続により取得し、相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人甲は、同区に存する生産緑地Bを平成30年5月に母から相続により取得し、その後、引き続き耕作を行っている。
また、甲は、生産緑地A及びBについて、いずれも平成34年に申出基準日(生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての告示の日から起算して30年を経過する日をいう。以下同じ。)を迎えるものの、生産緑地法の改正に伴う特定生産緑地としての指定を受ける予定はない。
なお、甲は、これらの生産緑地の買取りの申し出をせずに引き続き耕作を継続する予定である。
この場合、次の(1)及び(2)はどのようになるか。
(1)生産緑地Bは、母の相続税申告において、納税猶予の特例(措法70の6)の適用対象となる都市営農農地等に該当するか。
(2)納税猶予の特例の適用を受けている生産緑地について、特定生産緑地の指定を受けないことは、納税猶予の確定事由となるか。
A
(1)生産緑地Bは納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に該当する。
(2)生産緑地A及びBについて、特定生産緑地の指定を受けないことは、納税猶予の確定事由とならない。
(理由) 1 生産緑地法における特定生産緑地制度の創設
平成4年(1992年)の生産緑地法の一部改正の施行により保全すべき農地として位置づけを与えられた生産緑地の指定を受けた農地について、買取りの申出ができない期間(指定から30年間)が経過することから、2022年頃に生産緑地の指定解除が集中することも予想され、その場合、農地の保全が図られなくなるほか、土地の供給が過剰となる可能性が指摘されている(いわゆる「2022年問題」)。
こうした問題に対応するため、平成29年に生産緑地法の改正が行われ、平成30年4月1日から生産緑地地区に関する都市計画について告示の日から30年を経過する生産緑地については、事前に特定生産緑地として市町村長の指定を受けることにより、引き続き買取りの規制が課される制度が創設された。
なお、特定生産緑地とは、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものとして、市町村長が指定したものをいう。
この指定は、申出基準日までに行うものとされ、その指定の期限は、その申出基準日から起算して10年を経過する日とされている(生産緑地法10の2)。また、申出基準日から起算して10年を経過する日が近く到来することとなる特定生産緑地についてその日以後においても指定を継続する必要があると認めるときは、その指定の期限を延長することができることとされている(生産緑地法10の3)。この10年を経過する日又は延長後の期限が経過する日を「指定期限日」という。
2 生産緑地法の改正に伴う相続税及び贈与税の納税猶予の特例の見直し
(1)都市営農農地等の範囲の見直し(入口要件)
都市営農農地等の範囲に、特定生産緑地内にある農地が追加されるとともに、次の生産緑地が除外された(措法70の4②四)。
イ 特定生産緑地のうち買取りの申出がされたもの
ロ 申出基準日までに特定生産緑地の指定がされなかったもの
ハ 指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
ニ 特定生産緑地の指定が解除されたもの
(2)買取りの申出等があった場合の納税猶予期限の確定の見直し(確定事由)
納税猶予期間中に特例適用農地等について買取りの申出等があった場合には、その買取りの申出があった日の翌日から2月を経過する日をもって納税猶予期限が確定するが、この買取りの申出等の範囲に上記(1)イの買取りの申出及びニの指定の解除が追加された(措法70の4⑤、70の6⑧一)。
なお、申出基準日までに特定生産緑地の指定がされなかった生産緑地及び指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、都市営農農地等に該当しないことから、これらの生産緑地について新たに相続税又は贈与税の納税猶予制度の特例を受けることはできないが、これらの指定又は延長を受けなかったことは納税猶予の確定事由とはされていないことから、これらの生産緑地につき納税猶予の特例の適用を受けている猶予適用者については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予が継続される(次の相続・贈与の際には適用対象外)。
3 当てはめ
(1)について 生産緑地Bは、相続時点において、生産緑地地区の指定の告示を受けてから30年を経過していない(申出基準日が到来していない)ことから、上記2(1)ロには該当しないため、納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に該当する。
(2)について
上記2(2)のとおり、特定生産緑地の指定を受けないことは納税猶予の確定事由とならないことから、甲が生産緑地A及びBにつき納税猶予の特例の適用を受けている場合において、引き続き耕作を続けていくのであれば、納税猶予の期限は確定しない。
02 小規模宅地等の特例の適用における一棟の建物の範囲(区分所有建物でない場合・区分所有建物である場合)
Q 被相続人甲(以下「甲」という。)が所有する宅地の上に、甲及び同人と生計を別にする長男丙が所有する一棟の建物(二世帯住宅)があり、当該建物は、甲とその配偶者乙及び長男丙の居住の用に供されていた。
そして、甲に相続が発生したところ、当該宅地について、配偶者乙及び長男丙がそれぞれ2分の1を取得し、申告期限まで引き続き所有し居住の用に供していた。
当該建物に係る甲及び長男丙の所有形態が次の各事例の場合において、それぞれ当該宅地のうち租税特別措置法69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項(以下「小規模宅地等の特例」という。)に規定する特定居住用宅地等に該当するのはどの部分になるか。
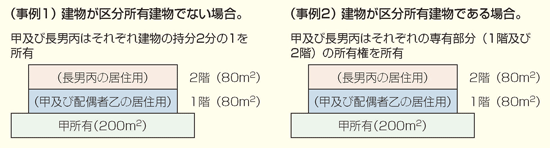
A
(事例1)配偶者乙及び長男丙の取得した宅地の全てが特定居住用宅地等に該当する。
(事例2)配偶者乙が取得した100㎡のうち、50㎡が特定居住用宅地等に該当する。
(理由) 小規模宅地等の特例の適用上、「被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族をいう。以下同じ。)の居住の用に供されていた宅地等」とは、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で被相続人又は被相続人の親族が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等をいう。
この「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」については、当該宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物が区分所有建物でない場合は、その敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族(生計を一にしているか否かは問わない)の居住の用に供されていた部分も「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」に含まれるが、区分所有建物である場合は、被相続人等の居住の用に供されていた部分に限られることとなる(措令40の2④、措通69の4-7、69の4-7の3)。
そして、この「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」のうち、小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等には、被相続人の配偶者又は相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた被相続人の親族(申告時期まで引き続き当該宅地を有し、かつ、当該建物に居住している者)が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応じる部分がその対象として含まれている。そして、この場合の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物の範囲には、当該一棟の建物が区分所有建物でない場合は、当該被相続人の親族(生計を一にしているか否かは問わない)が居住の用に供していた部分も含む一方、区分所有建物である場合は、被相続人の居住の用に供されていた部分に限られることとなる(措法69の4③二イ、措令40の2⑩)。
1 事例1について
本事例の家屋は区分所有建物ではないため、その敷地については、甲と生計が別である長男丙の居住部分も含めて甲の居住の用に供されていた宅地等となる。
また、同様の理由によって、長男丙は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者となり、相続開始時から申告時期まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していることから、特定居住用宅地等(措法69の4③二イ)の要件を満たす親族に該当する。
したがって、配偶者乙が取得した100㎡及び長男丙が取得した100㎡は、その全てが特定居住用宅地等に該当する。
2 事例2について
本事例の家屋は、区分所有建物であるため、長男丙が所有し居住の用に供していた部分(2階)を除いた1階部分のみが甲の居住の用に供されていた部分となる。
また、同様の理由によって、長男丙は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者とならないことから、特定居住用宅地等の要件を満たす親族(措法69の4③二イ)に該当しない(なお、長男丙は同号ロ又はハに規定する親族にも該当しない)。
したがって、甲の居住の用に供されていた宅地等(1階部分に係る100㎡)のうち、配偶者乙が取得した持分2分の1部分(50㎡)のみが特定居住用宅地等に該当する。
03 老人ホーム等に入居していた場合の小規模宅地等の特例の適用について
Q 甲は、自己が所有する家屋A及びその敷地である土地Aを居住の用に供していた(甲以外に同居していた者はいない。)が、平成28年4月から高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条1項に規定するサービス付き高齢者有料老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)へ入居した。その後の状況は次のとおりである。
平成29年1月 甲は、介護保険法19条2項に規定する要支援の認定を受けた。
平成30年1月 甲の長男乙(甲と生計は別である)が、家屋Aへ入居を始めた。
平成30年8月 甲の相続開始。家屋A及び土地Aは長男乙が相続した。
この場合、長男乙は、甲に係る相続税の申告において、相続により取得した土地Aにつき租税特別措置法69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)の適用を受けることができるか。
A
長男乙は、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない。
(理由)
1 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていない宅地等の小規模宅地等の特例の適用について
平成25年度税制改正において、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、次の①及び②の要件を満たす場合には、その被相続人の居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、その被相続人の居住の用に供されていた宅地等に当たるものとされた(措令40の2②、措規23の2②)。
① 被相続人の居住の用に供されていなかった事由が次のイ又はロであること
イ 介護保険法19条1項に規定する要介護認定若しくは同条2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人(介護保険法施行規則140条の62の4第2号に該当していた者を含む。)が、次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。
(イ)認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
(ロ)養護老人ホーム
(ハ)特別養護老人ホーム
(ニ)軽費老人ホーム
(ホ)有料老人ホーム
(へ)介護老人保健施設
(ト)介護医療院※
※ 介護医療院は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る相続について適用される。
(チ)サービス付き高齢者向け住宅((ホ)に規定する有料老人ホームを除く。)
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法5条11項に規定する障害者支援施設(同条10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条15項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと
なお、被相続人が、上記の要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、当該被相続人が、当該被相続人の相続の開始の直前において当該認定を受けていたかにより判定することとされていることから、老人ホーム等への入居又は入所をする前にこれらの認定を受けている必要はない(措通69の4-7の2)。
② 上記①の事由により被相続人の居住の用に供されなくなった宅地等を次の用途に供していないこと(措令40の2③)。 イ 租税特別措置法69条の4第1項に規定する事業の用
ロ 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人と上記①の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、被相続人が居住の用に供していた建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用 2 当てはめ
甲は、本件老人ホームへ入居するまで土地Aを居住の用に供し、相続開始直前まで本件老人ホームに居住していた。また、本件老人ホームは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に該当しており、甲は、要支援認定を本件老人ホームの入居時点では受けていないものの、相続開始の直前において受けていたのであるから、上記1①の要件は満たすこととなる。
しかしながら、土地Aは、甲の居住の用に供されなくなった後、平成30年1月から生計が別である長男乙の居住の用に供されていることから、上記1②の要件を満たさない。
したがって、土地Aは、甲の居住の用に供されていた宅地等には該当せず、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
財産評価編
01 地積規模の大きな宅地の評価~不整形地~
Q 下図のような不整形地の評価額はいくらになるか。
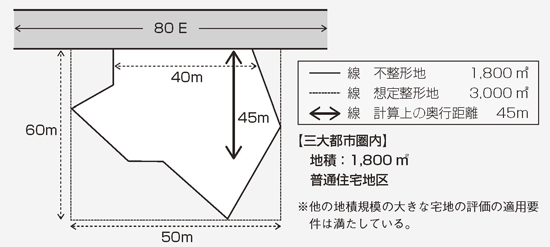
A
評価額は、89,424,000円となる。
1 奥行価格補正後の価額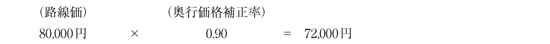
2 不整形地補正率 (1)不整形地補正率表の補正率 0.92
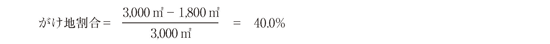
(2)間口狭小補正率 1.00
(3)奥行長大補正率 1.00
(4)不整形地補正率
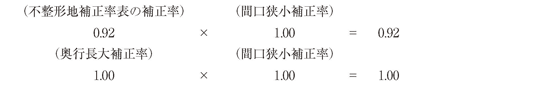
したがって、不整形地補正率は0.92となる。
3 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)
4 1㎡当たりの価額
5 不整形地の評価額
02 地積規模の大きな宅地の評価~市街地農地~
Q 下図のような市街地農地の評価額はいくらになるか。
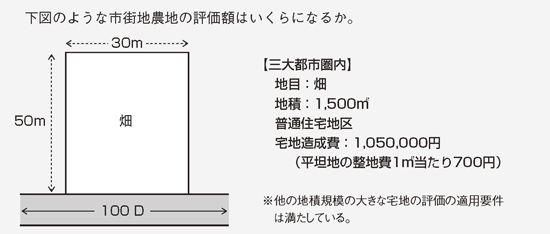
A
評価額は、100,410,000円となる。
1 奥行価格補正後の価額
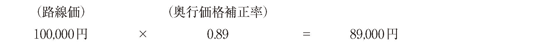
2 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)

3 宅地であるとした場合の価額

4 市街地農地の評価額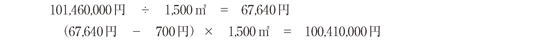
03 地積規模の大きな宅地の評価~いわゆる「羊羹切り」が可能な宅地などの場合~
Q 下図のように、いわゆる「羊羹切り」が可能な宅地の場合であっても、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのか。

A
適用要件に該当すれば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
(理由) 改正前の財産評価基本通達24-4(以下「旧広大地通達」という。)の定めについては、都市計画法4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益施設用地の負担が必要と認められない対象地は、適用対象でなかったため、本事例のようないわゆる「羊羹切り」が可能な宅地については、旧広大地通達の適用は認められなかった。
しかし、改正後の財産評価基本通達20-2《地積規模の大きな宅地の評価》には、上記の開発行為に係る要件がないため、いわゆる羊羹切りが可能な宅地であっても、同通達に定める要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
なお、旧広大地通達の適用が認められなかった路地状開発が最有効利用である宅地やマンション適地又は現に有効利用がなされている宅地であっても、財産評価基本通達20-2に定める適用要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
小規模宅地特例、地積規模の大きな宅地の評価etc.
相続税・財産評価の審理事例をチェック(1)
今号の特集は、課税当局が相続税・財産評価の審理上の留意点として掲げているQ&Aを掲載する。相続税では、生産緑地に係る納税猶予の特例、小規模宅地等の特例について、財産評価では、地積規模の大きな宅地の評価に関する取扱いが示されている。
相続税編
01 特定生産緑地の指定を受けない都市営農農地(生産緑地)に係る納税猶予の特例の適用について
Q 平成30年度税制改正によって、生産緑地法及び都市計画法の改正に伴う都市営農農地等の範囲等が見直され、平成30年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する特例適用農地等に係る相続税又は贈与税に適用されることとなった。
ところで、E区の生産緑地Aを平成25年4月に父から相続により取得し、相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人甲は、同区に存する生産緑地Bを平成30年5月に母から相続により取得し、その後、引き続き耕作を行っている。
また、甲は、生産緑地A及びBについて、いずれも平成34年に申出基準日(生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての告示の日から起算して30年を経過する日をいう。以下同じ。)を迎えるものの、生産緑地法の改正に伴う特定生産緑地としての指定を受ける予定はない。
なお、甲は、これらの生産緑地の買取りの申し出をせずに引き続き耕作を継続する予定である。
この場合、次の(1)及び(2)はどのようになるか。
(1)生産緑地Bは、母の相続税申告において、納税猶予の特例(措法70の6)の適用対象となる都市営農農地等に該当するか。
(2)納税猶予の特例の適用を受けている生産緑地について、特定生産緑地の指定を受けないことは、納税猶予の確定事由となるか。
A
(1)生産緑地Bは納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に該当する。
(2)生産緑地A及びBについて、特定生産緑地の指定を受けないことは、納税猶予の確定事由とならない。
(理由) 1 生産緑地法における特定生産緑地制度の創設
平成4年(1992年)の生産緑地法の一部改正の施行により保全すべき農地として位置づけを与えられた生産緑地の指定を受けた農地について、買取りの申出ができない期間(指定から30年間)が経過することから、2022年頃に生産緑地の指定解除が集中することも予想され、その場合、農地の保全が図られなくなるほか、土地の供給が過剰となる可能性が指摘されている(いわゆる「2022年問題」)。
こうした問題に対応するため、平成29年に生産緑地法の改正が行われ、平成30年4月1日から生産緑地地区に関する都市計画について告示の日から30年を経過する生産緑地については、事前に特定生産緑地として市町村長の指定を受けることにより、引き続き買取りの規制が課される制度が創設された。
なお、特定生産緑地とは、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものとして、市町村長が指定したものをいう。
この指定は、申出基準日までに行うものとされ、その指定の期限は、その申出基準日から起算して10年を経過する日とされている(生産緑地法10の2)。また、申出基準日から起算して10年を経過する日が近く到来することとなる特定生産緑地についてその日以後においても指定を継続する必要があると認めるときは、その指定の期限を延長することができることとされている(生産緑地法10の3)。この10年を経過する日又は延長後の期限が経過する日を「指定期限日」という。
2 生産緑地法の改正に伴う相続税及び贈与税の納税猶予の特例の見直し
(1)都市営農農地等の範囲の見直し(入口要件)
都市営農農地等の範囲に、特定生産緑地内にある農地が追加されるとともに、次の生産緑地が除外された(措法70の4②四)。
イ 特定生産緑地のうち買取りの申出がされたもの
ロ 申出基準日までに特定生産緑地の指定がされなかったもの
ハ 指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかったもの
ニ 特定生産緑地の指定が解除されたもの
(2)買取りの申出等があった場合の納税猶予期限の確定の見直し(確定事由)
納税猶予期間中に特例適用農地等について買取りの申出等があった場合には、その買取りの申出があった日の翌日から2月を経過する日をもって納税猶予期限が確定するが、この買取りの申出等の範囲に上記(1)イの買取りの申出及びニの指定の解除が追加された(措法70の4⑤、70の6⑧一)。
なお、申出基準日までに特定生産緑地の指定がされなかった生産緑地及び指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、都市営農農地等に該当しないことから、これらの生産緑地について新たに相続税又は贈与税の納税猶予制度の特例を受けることはできないが、これらの指定又は延長を受けなかったことは納税猶予の確定事由とはされていないことから、これらの生産緑地につき納税猶予の特例の適用を受けている猶予適用者については、現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予が継続される(次の相続・贈与の際には適用対象外)。
3 当てはめ
(1)について 生産緑地Bは、相続時点において、生産緑地地区の指定の告示を受けてから30年を経過していない(申出基準日が到来していない)ことから、上記2(1)ロには該当しないため、納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に該当する。
(2)について
上記2(2)のとおり、特定生産緑地の指定を受けないことは納税猶予の確定事由とならないことから、甲が生産緑地A及びBにつき納税猶予の特例の適用を受けている場合において、引き続き耕作を続けていくのであれば、納税猶予の期限は確定しない。
02 小規模宅地等の特例の適用における一棟の建物の範囲(区分所有建物でない場合・区分所有建物である場合)
Q 被相続人甲(以下「甲」という。)が所有する宅地の上に、甲及び同人と生計を別にする長男丙が所有する一棟の建物(二世帯住宅)があり、当該建物は、甲とその配偶者乙及び長男丙の居住の用に供されていた。
そして、甲に相続が発生したところ、当該宅地について、配偶者乙及び長男丙がそれぞれ2分の1を取得し、申告期限まで引き続き所有し居住の用に供していた。
当該建物に係る甲及び長男丙の所有形態が次の各事例の場合において、それぞれ当該宅地のうち租税特別措置法69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項(以下「小規模宅地等の特例」という。)に規定する特定居住用宅地等に該当するのはどの部分になるか。
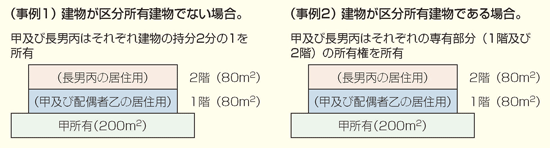
A
(事例1)配偶者乙及び長男丙の取得した宅地の全てが特定居住用宅地等に該当する。
(事例2)配偶者乙が取得した100㎡のうち、50㎡が特定居住用宅地等に該当する。
(理由) 小規模宅地等の特例の適用上、「被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族をいう。以下同じ。)の居住の用に供されていた宅地等」とは、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で被相続人又は被相続人の親族が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等をいう。
この「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」については、当該宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物が区分所有建物でない場合は、その敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族(生計を一にしているか否かは問わない)の居住の用に供されていた部分も「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」に含まれるが、区分所有建物である場合は、被相続人等の居住の用に供されていた部分に限られることとなる(措令40の2④、措通69の4-7、69の4-7の3)。
そして、この「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」のうち、小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等には、被相続人の配偶者又は相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた被相続人の親族(申告時期まで引き続き当該宅地を有し、かつ、当該建物に居住している者)が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応じる部分がその対象として含まれている。そして、この場合の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物の範囲には、当該一棟の建物が区分所有建物でない場合は、当該被相続人の親族(生計を一にしているか否かは問わない)が居住の用に供していた部分も含む一方、区分所有建物である場合は、被相続人の居住の用に供されていた部分に限られることとなる(措法69の4③二イ、措令40の2⑩)。
1 事例1について
本事例の家屋は区分所有建物ではないため、その敷地については、甲と生計が別である長男丙の居住部分も含めて甲の居住の用に供されていた宅地等となる。
また、同様の理由によって、長男丙は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者となり、相続開始時から申告時期まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していることから、特定居住用宅地等(措法69の4③二イ)の要件を満たす親族に該当する。
したがって、配偶者乙が取得した100㎡及び長男丙が取得した100㎡は、その全てが特定居住用宅地等に該当する。
2 事例2について
本事例の家屋は、区分所有建物であるため、長男丙が所有し居住の用に供していた部分(2階)を除いた1階部分のみが甲の居住の用に供されていた部分となる。
また、同様の理由によって、長男丙は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者とならないことから、特定居住用宅地等の要件を満たす親族(措法69の4③二イ)に該当しない(なお、長男丙は同号ロ又はハに規定する親族にも該当しない)。
したがって、甲の居住の用に供されていた宅地等(1階部分に係る100㎡)のうち、配偶者乙が取得した持分2分の1部分(50㎡)のみが特定居住用宅地等に該当する。
03 老人ホーム等に入居していた場合の小規模宅地等の特例の適用について
Q 甲は、自己が所有する家屋A及びその敷地である土地Aを居住の用に供していた(甲以外に同居していた者はいない。)が、平成28年4月から高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条1項に規定するサービス付き高齢者有料老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)へ入居した。その後の状況は次のとおりである。
平成29年1月 甲は、介護保険法19条2項に規定する要支援の認定を受けた。
平成30年1月 甲の長男乙(甲と生計は別である)が、家屋Aへ入居を始めた。
平成30年8月 甲の相続開始。家屋A及び土地Aは長男乙が相続した。
この場合、長男乙は、甲に係る相続税の申告において、相続により取得した土地Aにつき租税特別措置法69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)の適用を受けることができるか。
A
長男乙は、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない。
(理由)
1 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていない宅地等の小規模宅地等の特例の適用について
平成25年度税制改正において、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、次の①及び②の要件を満たす場合には、その被相続人の居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、その被相続人の居住の用に供されていた宅地等に当たるものとされた(措令40の2②、措規23の2②)。
① 被相続人の居住の用に供されていなかった事由が次のイ又はロであること
イ 介護保険法19条1項に規定する要介護認定若しくは同条2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人(介護保険法施行規則140条の62の4第2号に該当していた者を含む。)が、次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。
(イ)認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
(ロ)養護老人ホーム
(ハ)特別養護老人ホーム
(ニ)軽費老人ホーム
(ホ)有料老人ホーム
(へ)介護老人保健施設
(ト)介護医療院※
※ 介護医療院は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る相続について適用される。
(チ)サービス付き高齢者向け住宅((ホ)に規定する有料老人ホームを除く。)
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法5条11項に規定する障害者支援施設(同条10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条15項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと
なお、被相続人が、上記の要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、当該被相続人が、当該被相続人の相続の開始の直前において当該認定を受けていたかにより判定することとされていることから、老人ホーム等への入居又は入所をする前にこれらの認定を受けている必要はない(措通69の4-7の2)。
② 上記①の事由により被相続人の居住の用に供されなくなった宅地等を次の用途に供していないこと(措令40の2③)。 イ 租税特別措置法69条の4第1項に規定する事業の用
ロ 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人と上記①の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、被相続人が居住の用に供していた建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用 2 当てはめ
甲は、本件老人ホームへ入居するまで土地Aを居住の用に供し、相続開始直前まで本件老人ホームに居住していた。また、本件老人ホームは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に該当しており、甲は、要支援認定を本件老人ホームの入居時点では受けていないものの、相続開始の直前において受けていたのであるから、上記1①の要件は満たすこととなる。
しかしながら、土地Aは、甲の居住の用に供されなくなった後、平成30年1月から生計が別である長男乙の居住の用に供されていることから、上記1②の要件を満たさない。
したがって、土地Aは、甲の居住の用に供されていた宅地等には該当せず、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
財産評価編
01 地積規模の大きな宅地の評価~不整形地~
Q 下図のような不整形地の評価額はいくらになるか。
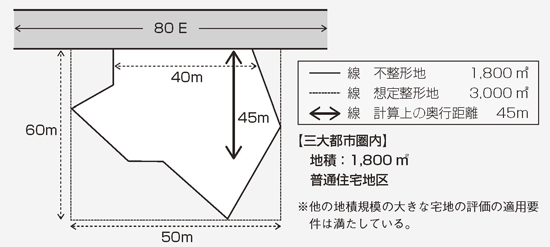
A
評価額は、89,424,000円となる。
1 奥行価格補正後の価額
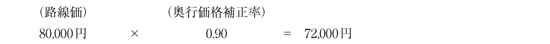
2 不整形地補正率 (1)不整形地補正率表の補正率 0.92
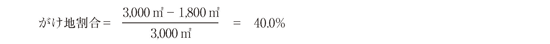
(2)間口狭小補正率 1.00
(3)奥行長大補正率 1.00
(4)不整形地補正率
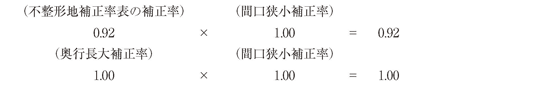
したがって、不整形地補正率は0.92となる。
3 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)

4 1㎡当たりの価額

5 不整形地の評価額

02 地積規模の大きな宅地の評価~市街地農地~
Q 下図のような市街地農地の評価額はいくらになるか。
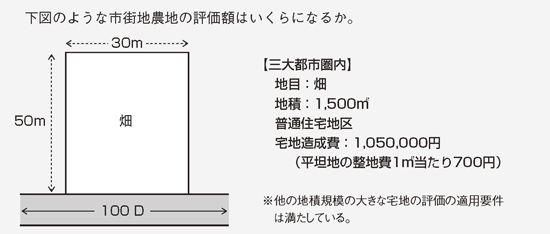
A
評価額は、100,410,000円となる。
1 奥行価格補正後の価額
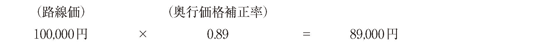
2 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)

3 宅地であるとした場合の価額

4 市街地農地の評価額
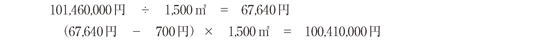
03 地積規模の大きな宅地の評価~いわゆる「羊羹切り」が可能な宅地などの場合~
Q 下図のように、いわゆる「羊羹切り」が可能な宅地の場合であっても、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのか。

A
適用要件に該当すれば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
(理由) 改正前の財産評価基本通達24-4(以下「旧広大地通達」という。)の定めについては、都市計画法4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益施設用地の負担が必要と認められない対象地は、適用対象でなかったため、本事例のようないわゆる「羊羹切り」が可能な宅地については、旧広大地通達の適用は認められなかった。
しかし、改正後の財産評価基本通達20-2《地積規模の大きな宅地の評価》には、上記の開発行為に係る要件がないため、いわゆる羊羹切りが可能な宅地であっても、同通達に定める要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
なお、旧広大地通達の適用が認められなかった路地状開発が最有効利用である宅地やマンション適地又は現に有効利用がなされている宅地であっても、財産評価基本通達20-2に定める適用要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















