解説記事2018年12月03日 【特別解説】 のれんの計上の状況等の分析~わが国のIFRS任意適用日本企業と日本基準適用企業の場合~(2018年12月3日号・№765)
特別解説
のれんの計上の状況等の分析
~わが国のIFRS任意適用日本企業と日本基準適用企業の場合~
はじめに
国際財務報告基準(IFRS)を作成する国際会計基準審議会(IASB)は、ここのところ数年は金融商品、収益認識、リース、保険契約といった大型の基準書や概念フレームワークの開発作業等に追われ、息つく暇もない状況であったが、ここにきて基準書の作成や業務への適用支援活動が一区切りしたことから、今後は投資家とのコミュニケーション(IFRSの「使い勝手」の向上)や開示のフレームワークづくり、あるいはリサーチ・プロジェクトといった、より長期のプロジェクトに軸足を移そうとしている。
それらの長期的なプロジェクトの一つとして、のれんの取扱いの見直しの検討がある。我が国でもよく知られているように、IFRSと米国基準ではのれんは定額償却を行わず、減損テストのみであるのに対して、我が国の会計基準では、20年以内の期間にわたって定額償却が行われる(減損の兆候がある場合には、減損テストも実施する。)。
2018年9月に来日したIASBのハンス・フーガーホースト議長がインタビューに応じ、のれんの償却の導入について、将来ディスカッション・ペーパーを公表したうえで、幅広い利害関係者から意見を集約していく旨を表明した(2018年9月14日付 日本経済新聞)。
こうした動きを踏まえ、本稿では、国内の企業ののれんの計上額や連結純資産に対するのれん計上額の比率、昨年度ののれんの減損処理額等を調査し、傾向等の分析を試みた。具体的には、IFRSに基づく連結財務諸表を作成・公表した日本企業(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)と、日本基準を適用する主要な日本企業の動向を分析することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査対象としたのは、2018年3月期まで(2017年度)にIFRSを適用して有価証券報告書を作成・提出した日本企業(IFRS任意適用日本企業)の158社であり、いずれも最も直近の本決算での数値を用いている。また、米国会計基準からIFRSに移行した企業や、IFRSを適用して新規に上場した企業も調査対象の158社に含まれている。また、本稿の後段では、2018年6月末日時点の、東京証券取引所での株式時価総額上位200社の企業のうち、IFRS任意適用日本企業と米国会計基準適用企業を除いた計110社を対象として、調査分析を行っている。
のれんの計上額等
(1)多額ののれんを計上しているIFRS任意適用日本企業 調査対象のIFRS任意適用日本企業158社が計上したのれんの残高は、すべて合計すると18兆6,798億400万円であった。1社あたりで単純に平均すると、1,182億円になる。この中で、まず、のれんの計上額が大きい上位10社は、表1のとおりであった。
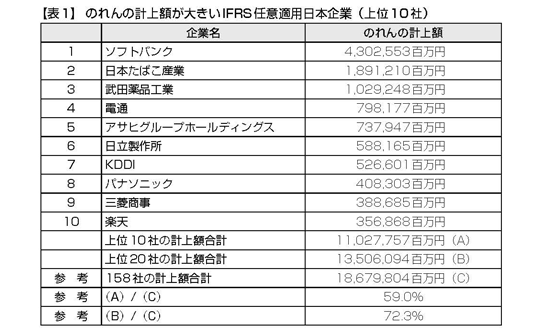
ソフトバンク1社だけで、IFRS任意適用日本企業全体(158社)の23%を占めており、日立製作所までの上位6社で過半数、上位10社で6割弱、上位20社になると7割強を占めている。日本企業全体の中で見ると、IFRS任意適用日本企業は海外展開やM&Aに積極的な企業が多いが、その中でも多額ののれんを計上している企業は、まだほんの一握りであることがわかる。
なお、今回調査の対象とした158社には含まれていないが、2019年3月期第一四半期からIFRSを任意適用しているNTTグループの各社は、2018年3月末日現在、表2の金額ののれんを計上している。

(2)のれんの計上額の分布 次に、IFRS任意適用日本企業ののれん計上額の分布を示すと、表3のとおりである。
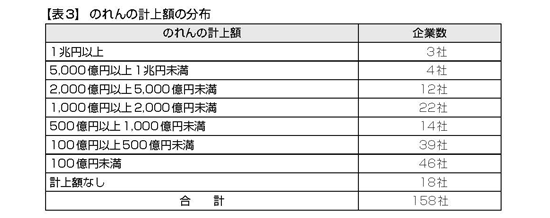
1社あたりののれん計上額の単純平均値は1,182億円と記載したが、ソフトバンク1社を除くと、1社あたりの平均額は大きく下がって910億円となる。表3の分布を見ても、158社のうちの3分の2近い103社ののれんの計上額が500億円未満であった。
なお、のれんをまったく計上していなかったIFRS任意適用日本企業18社の内訳は、次のとおりである。
のれんを計上していないIFRS任意適用日本企業
本田技研工業とそのグループ企業、及び一部の製薬会社が目立つ。
(3)連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高いIFRS任意適用日本企業 連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高いIFRS任意適用日本企業を列挙すると、表4のとおりであった。
表4には、表1で記載した「のれん計上額の上位10社」の企業が1社も含まれておらず、まったく顔ぶれが異なっている。そして、表4の10社のうち、アウトソーシングとコロワイドを除く8社が、いずれもIFRSを適用して新規上場を果たした会社という共通点がある。

連結純資産に対するのれんの計上額の割合(比率)の分布を示すと、表5のとおりである。
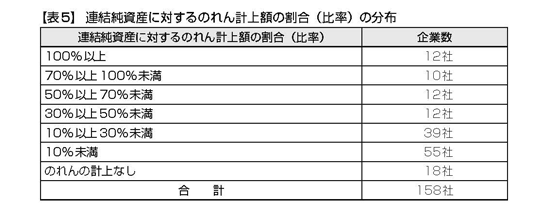
158社のうち、連結純資産に対するのれん計上額の割合が100%を超えたのは12社(表4の10社のほか、テクノプロ・ホールディングスとリンクアンドモチベーション)であった。IFRS任意適用日本企業のうちの70%強が、連結純資産に対するのれん計上額の割合が30%を下回っている。なお、全158社の連結純資産に対するのれん計上額の割合(単純平均)は、17.5%であった。
(4)のれんの減損処理額 IFRS任意適用日本企業が2017年度に計上したのれんの減損損失の金額は、合計で2,738億6百万円であり、のれん残高全体に対する費用化率は1.46%であった。これを耐用年数に換算すると68年強に相当する。
2017年度にのれんの減損損失を計上したIFRS任意適用日本企業は計42社であり、主要な企業は、表6のとおりである。
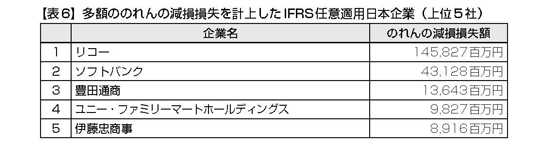
リコー1社で、42社が計上したのれんの減損損失の合計額の過半を超えている。
リコーは、減損損失計上の対象となったのれんは、主に北米のオフィスプリンティング事業に係るものであることを開示している。
IFRS任意適用日本企業以外の日本企業の状況
IFRS任意適用日本企業の状況と比較するために、IFRS任意適用日本企業以外の、日本の会計基準を適用している主要な日本企業ののれんの計上額等の状況について、同様の調査を実施した。調査の対象とした企業は、3月決算の各社の有価証券報告書が出揃う2018年6月末日現在の、株式時価総額の上位200社である。200社のうち、IFRS任意適用日本企業やIFRSの任意適用を既に表明している企業、米国会計基準の適用企業、及び外国企業が合計で90社あったため、これらを除外して、調査の対象とした日本企業は、合計で110社となった。
(1)多額ののれんを計上している、日本の会計基準を適用する日本企業
調査対象の、日本の会計基準を適用する日本企業110社が計上したのれんの残高は、合計すると5兆2,372億7,200万円であった。1社あたりで単純に平均すると476億円強となり、IFRS任意適用日本企業(1,182億円)の約4割の水準であった。まず、のれんの計上額が大きい上位10社は、表7のとおりである。
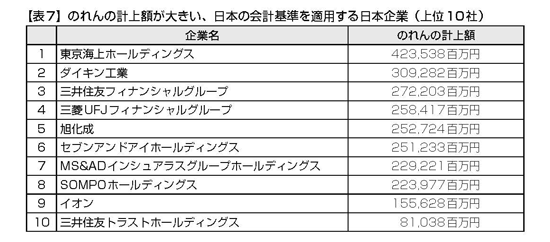
IFRS任意適用日本企業の表1と比較して一目で分かるのは、のれん計上額(絶対額)の少なさである。IFRS任意適用日本企業では、のれん残高が5,000億円超の企業が7社、1,000億円超の企業だと41社あったが、日本の会計基準を適用する日本企業の場合には、のれんの残高が5,000億円を超える企業は皆無、1,000億円を超える企業もわずか9社に過ぎなかった。いわゆる我が国のエクセレント・カンパニーといわれる企業の中で、多額ののれん残高を有する企業のほとんどは、日本の会計基準ではなく、IFRSまたは米国会計基準を適用していることが分かる。表7の顔ぶれを見ると、メガバンクや保険会社といった、金融機関が目に付く。
(2)のれんの計上額の分布 次に、日本の会計基準を適用する日本企業ののれん計上額の分布を示すと、表8のとおりである。
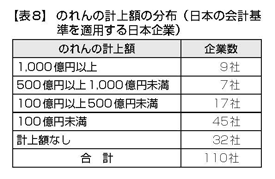
のれんの計上額が100億円未満の企業が全体の7割に達し、のれんをまったく計上していない企業も3割弱を占めていることが分かる。
(3)連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高い、日本の会計基準を適用する日本企業 連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高い、日本の会計基準を適用する日本企業は、表9のとおりである。
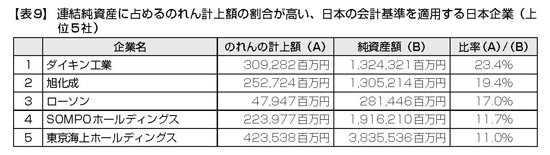
表1の「のれんの計上額が大きいIFRS任意適用日本企業(上位10社)」もすべて、時価総額上位200社に入っているが、表9と同様に、のれんの計上額と連結純資産額、並びにのれんの計上額が連結純資産に占める比率を併記すると表10のとおりとなる。比率が50%から70%の間となっている企業が多いことが分かる。同じ日本企業とはいえ、同比率が10%台~多くても20%台前半となっている、表9の日本の会計基準を適用する大手日本企業とは大きな差がある。

なお、連結純資産に占めるのれん計上額の割合の、今回調査対象とした110社全体の単純平均は、わずか3.4%に過ぎなかった。連結純資産に対するのれん計上額の比率については、IFRS任意適用日本企業の場合には、IFRSを適用して新規上場した会社という「特殊要因」があるものの、これらを除外して考えても、日本基準を適用する主要な日本企業ののれん計上額の水準の低さ(及び連結純資産の厚さ)が読み取れる結果と言えるであろう。
(4)のれんの減損処理額 調査対象とした日本基準を適用する日本企業110社が、2017年度に計上したのれんの減損損失の金額は、合計で1,231億73百万円であった。のれんの残高に対する減損損失の計上額を比率にすると、2.35%であり、IFRS任意適用日本企業の1.46%を大きく上回る水準であった。
多額ののれんの減損損失を計上した、日本基準を適用する日本企業を示すと、表11のとおりである。
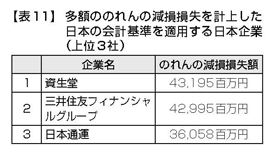
また、日本の会計基準を適用する日本企業の場合には、のれんの減損テストや減損損失計上のほかに、のれんの毎期定額償却(最長の償却年数:20年)を行っているため、のれん残高の費用化率は、少なくとも7.35%以上(平均償却年数に直すと13.6年未満)はあるということになる。
終わりに
世界中で活発化するM&Aにより、のれんの残高が膨張を続けていると言われて久しい。日経新聞の2018年9月13日付の記事によると、2017年度時点で欧州の主要600社では240兆円(1社当たり4,000億円)ののれんが計上されており、大型M&Aが活発な米国では、主要500社でのれんが340兆円(1社当たり6.800億円)にのぼると記載されている。これは、IFRS任意適用日本企業の平均的なのれんの計上額(1,182億円)の4倍~5倍、日本基準を適用する日本企業の場合(476億円)には10倍~15倍にも達する金額である。言うまでもなく、のれんの計上額が小さければそれでよい、といった単純な話ではなく、のれんを毎期定額償却するためには、耐用年数の決定方法など様々な課題はあるものの、一般的に言って、日本の会計基準によってのれんの毎期定額償却を義務付けられている日本企業のバランスシートのほうが、IFRSや米国会計基準を適用している欧米の主要企業に比べて「身軽」であり、投資家にとっても、いざというときに巨額の減損リスクが生じる可能性がより少ないことは間違いないであろう。
IASBのフーガーホースト議長は、インタビューの中で、のれんの減損テストには大きな課題があることや、企業の収益見通しが楽観的過ぎるため、減損のタイミングが遅くなりがちであること、のれんが非償却の現状では、投資家が財務諸表に対して実態以上に好印象を持ってしまい、減損が多発すれば一般投資家が大きな損失を被りかねないこと等を認めている。IFRS第9号「金融商品」において、これまでの金融資産の減損のアプローチであった「発生損失モデル」の問題点(金額が小さすぎ、かつタイミングが遅すぎる)が指摘され、損失見込み額を早めに計上する予想損失モデルに置き換えられた、といった最近の流れを考えても、非金融資産であるのれんの減損についても、今後同じような方向での見直しが行われる可能性は否定できないであろう。
IFRS第3号によってIFRS上ののれんの会計処理が非償却と定められた後も、我が国は、基本的にのれんの毎期定額償却を支持する立場をとり、のれんの会計処理の見直しの必要性を訴えてきた。我が国の企業会計基準委員会(ASBJ)も、2015年から2017年にかけて3本のリサーチ・ペーパー(注)を公表し、問題提起を続けてきた。
環境の変化も追い風となって、ここにきてようやく我が国の地道な意見発信の成果が表れ、主張が受け入れられる余地が出てきたのかもしれない。のれんは金額的な影響が極めて大きい論点であるため、議論が最終的に決着するまでには、まだまだ紆余曲折が予想されるが、IFRSの基準書開発や実務への適用に我が国が貢献できる大きなチャンスであるととらえ、前向きかつ有用な情報発信を続けていくことが必要と考える。
(注)ASBJが公表したリサーチ・ペーパーは次の3本である。
リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」(2015年5月19日)
リサーチ・ペーパー第2号「のれん及び減損に関する定量的調査」(2016年10月3日)
リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」(2017年6月12日)
(参考)
日本経済新聞電子版記事
・「M&A『のれん』」費用計上の義務化検討 国際会計基準見直し、2021年にも結論(2018年9月13日)
・「のれん償却 国際会計基準でも検討 甘い評価、投資家に損失 国際会計基準審議会議長 フーガーホースト氏」(2018年9月14日)
のれんの計上の状況等の分析
~わが国のIFRS任意適用日本企業と日本基準適用企業の場合~
はじめに
国際財務報告基準(IFRS)を作成する国際会計基準審議会(IASB)は、ここのところ数年は金融商品、収益認識、リース、保険契約といった大型の基準書や概念フレームワークの開発作業等に追われ、息つく暇もない状況であったが、ここにきて基準書の作成や業務への適用支援活動が一区切りしたことから、今後は投資家とのコミュニケーション(IFRSの「使い勝手」の向上)や開示のフレームワークづくり、あるいはリサーチ・プロジェクトといった、より長期のプロジェクトに軸足を移そうとしている。
それらの長期的なプロジェクトの一つとして、のれんの取扱いの見直しの検討がある。我が国でもよく知られているように、IFRSと米国基準ではのれんは定額償却を行わず、減損テストのみであるのに対して、我が国の会計基準では、20年以内の期間にわたって定額償却が行われる(減損の兆候がある場合には、減損テストも実施する。)。
2018年9月に来日したIASBのハンス・フーガーホースト議長がインタビューに応じ、のれんの償却の導入について、将来ディスカッション・ペーパーを公表したうえで、幅広い利害関係者から意見を集約していく旨を表明した(2018年9月14日付 日本経済新聞)。
こうした動きを踏まえ、本稿では、国内の企業ののれんの計上額や連結純資産に対するのれん計上額の比率、昨年度ののれんの減損処理額等を調査し、傾向等の分析を試みた。具体的には、IFRSに基づく連結財務諸表を作成・公表した日本企業(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)と、日本基準を適用する主要な日本企業の動向を分析することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査対象としたのは、2018年3月期まで(2017年度)にIFRSを適用して有価証券報告書を作成・提出した日本企業(IFRS任意適用日本企業)の158社であり、いずれも最も直近の本決算での数値を用いている。また、米国会計基準からIFRSに移行した企業や、IFRSを適用して新規に上場した企業も調査対象の158社に含まれている。また、本稿の後段では、2018年6月末日時点の、東京証券取引所での株式時価総額上位200社の企業のうち、IFRS任意適用日本企業と米国会計基準適用企業を除いた計110社を対象として、調査分析を行っている。
のれんの計上額等
(1)多額ののれんを計上しているIFRS任意適用日本企業 調査対象のIFRS任意適用日本企業158社が計上したのれんの残高は、すべて合計すると18兆6,798億400万円であった。1社あたりで単純に平均すると、1,182億円になる。この中で、まず、のれんの計上額が大きい上位10社は、表1のとおりであった。
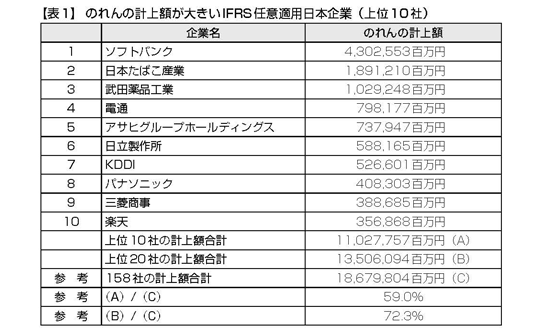
ソフトバンク1社だけで、IFRS任意適用日本企業全体(158社)の23%を占めており、日立製作所までの上位6社で過半数、上位10社で6割弱、上位20社になると7割強を占めている。日本企業全体の中で見ると、IFRS任意適用日本企業は海外展開やM&Aに積極的な企業が多いが、その中でも多額ののれんを計上している企業は、まだほんの一握りであることがわかる。
なお、今回調査の対象とした158社には含まれていないが、2019年3月期第一四半期からIFRSを任意適用しているNTTグループの各社は、2018年3月末日現在、表2の金額ののれんを計上している。

(2)のれんの計上額の分布 次に、IFRS任意適用日本企業ののれん計上額の分布を示すと、表3のとおりである。
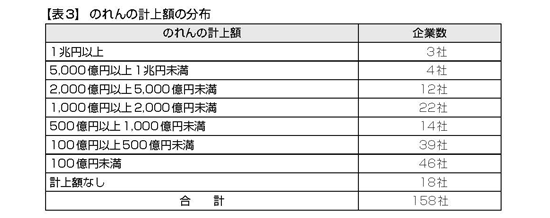
1社あたりののれん計上額の単純平均値は1,182億円と記載したが、ソフトバンク1社を除くと、1社あたりの平均額は大きく下がって910億円となる。表3の分布を見ても、158社のうちの3分の2近い103社ののれんの計上額が500億円未満であった。
なお、のれんをまったく計上していなかったIFRS任意適用日本企業18社の内訳は、次のとおりである。
のれんを計上していないIFRS任意適用日本企業
| 小野薬品工業、窪田製薬ホールディングス、クレハ、ケーヒン、サイバーダイン、山洋電気、ソレイジア・ファーマ、中外製薬、ティアック、テイ・エステック、トーセイ、日信工業、日本精機、日本精工、パルコ、本田技研工業、ユタカ技研、夢展望 |
(3)連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高いIFRS任意適用日本企業 連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高いIFRS任意適用日本企業を列挙すると、表4のとおりであった。
表4には、表1で記載した「のれん計上額の上位10社」の企業が1社も含まれておらず、まったく顔ぶれが異なっている。そして、表4の10社のうち、アウトソーシングとコロワイドを除く8社が、いずれもIFRSを適用して新規上場を果たした会社という共通点がある。

連結純資産に対するのれんの計上額の割合(比率)の分布を示すと、表5のとおりである。
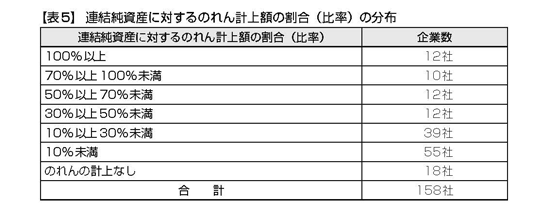
158社のうち、連結純資産に対するのれん計上額の割合が100%を超えたのは12社(表4の10社のほか、テクノプロ・ホールディングスとリンクアンドモチベーション)であった。IFRS任意適用日本企業のうちの70%強が、連結純資産に対するのれん計上額の割合が30%を下回っている。なお、全158社の連結純資産に対するのれん計上額の割合(単純平均)は、17.5%であった。
(4)のれんの減損処理額 IFRS任意適用日本企業が2017年度に計上したのれんの減損損失の金額は、合計で2,738億6百万円であり、のれん残高全体に対する費用化率は1.46%であった。これを耐用年数に換算すると68年強に相当する。
2017年度にのれんの減損損失を計上したIFRS任意適用日本企業は計42社であり、主要な企業は、表6のとおりである。
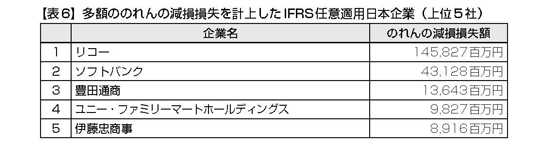
リコー1社で、42社が計上したのれんの減損損失の合計額の過半を超えている。
リコーは、減損損失計上の対象となったのれんは、主に北米のオフィスプリンティング事業に係るものであることを開示している。
IFRS任意適用日本企業以外の日本企業の状況
IFRS任意適用日本企業の状況と比較するために、IFRS任意適用日本企業以外の、日本の会計基準を適用している主要な日本企業ののれんの計上額等の状況について、同様の調査を実施した。調査の対象とした企業は、3月決算の各社の有価証券報告書が出揃う2018年6月末日現在の、株式時価総額の上位200社である。200社のうち、IFRS任意適用日本企業やIFRSの任意適用を既に表明している企業、米国会計基準の適用企業、及び外国企業が合計で90社あったため、これらを除外して、調査の対象とした日本企業は、合計で110社となった。
(1)多額ののれんを計上している、日本の会計基準を適用する日本企業
調査対象の、日本の会計基準を適用する日本企業110社が計上したのれんの残高は、合計すると5兆2,372億7,200万円であった。1社あたりで単純に平均すると476億円強となり、IFRS任意適用日本企業(1,182億円)の約4割の水準であった。まず、のれんの計上額が大きい上位10社は、表7のとおりである。
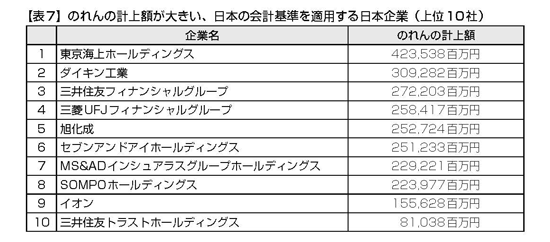
IFRS任意適用日本企業の表1と比較して一目で分かるのは、のれん計上額(絶対額)の少なさである。IFRS任意適用日本企業では、のれん残高が5,000億円超の企業が7社、1,000億円超の企業だと41社あったが、日本の会計基準を適用する日本企業の場合には、のれんの残高が5,000億円を超える企業は皆無、1,000億円を超える企業もわずか9社に過ぎなかった。いわゆる我が国のエクセレント・カンパニーといわれる企業の中で、多額ののれん残高を有する企業のほとんどは、日本の会計基準ではなく、IFRSまたは米国会計基準を適用していることが分かる。表7の顔ぶれを見ると、メガバンクや保険会社といった、金融機関が目に付く。
(2)のれんの計上額の分布 次に、日本の会計基準を適用する日本企業ののれん計上額の分布を示すと、表8のとおりである。
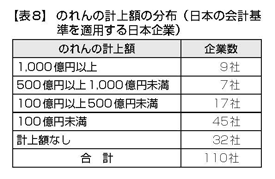
のれんの計上額が100億円未満の企業が全体の7割に達し、のれんをまったく計上していない企業も3割弱を占めていることが分かる。
(3)連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高い、日本の会計基準を適用する日本企業 連結純資産に占めるのれん計上額の割合が高い、日本の会計基準を適用する日本企業は、表9のとおりである。
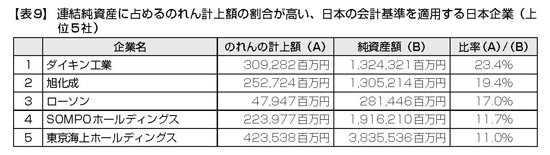
表1の「のれんの計上額が大きいIFRS任意適用日本企業(上位10社)」もすべて、時価総額上位200社に入っているが、表9と同様に、のれんの計上額と連結純資産額、並びにのれんの計上額が連結純資産に占める比率を併記すると表10のとおりとなる。比率が50%から70%の間となっている企業が多いことが分かる。同じ日本企業とはいえ、同比率が10%台~多くても20%台前半となっている、表9の日本の会計基準を適用する大手日本企業とは大きな差がある。

なお、連結純資産に占めるのれん計上額の割合の、今回調査対象とした110社全体の単純平均は、わずか3.4%に過ぎなかった。連結純資産に対するのれん計上額の比率については、IFRS任意適用日本企業の場合には、IFRSを適用して新規上場した会社という「特殊要因」があるものの、これらを除外して考えても、日本基準を適用する主要な日本企業ののれん計上額の水準の低さ(及び連結純資産の厚さ)が読み取れる結果と言えるであろう。
(4)のれんの減損処理額 調査対象とした日本基準を適用する日本企業110社が、2017年度に計上したのれんの減損損失の金額は、合計で1,231億73百万円であった。のれんの残高に対する減損損失の計上額を比率にすると、2.35%であり、IFRS任意適用日本企業の1.46%を大きく上回る水準であった。
多額ののれんの減損損失を計上した、日本基準を適用する日本企業を示すと、表11のとおりである。
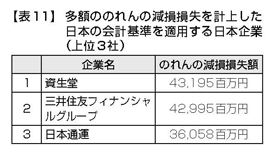
また、日本の会計基準を適用する日本企業の場合には、のれんの減損テストや減損損失計上のほかに、のれんの毎期定額償却(最長の償却年数:20年)を行っているため、のれん残高の費用化率は、少なくとも7.35%以上(平均償却年数に直すと13.6年未満)はあるということになる。
終わりに
世界中で活発化するM&Aにより、のれんの残高が膨張を続けていると言われて久しい。日経新聞の2018年9月13日付の記事によると、2017年度時点で欧州の主要600社では240兆円(1社当たり4,000億円)ののれんが計上されており、大型M&Aが活発な米国では、主要500社でのれんが340兆円(1社当たり6.800億円)にのぼると記載されている。これは、IFRS任意適用日本企業の平均的なのれんの計上額(1,182億円)の4倍~5倍、日本基準を適用する日本企業の場合(476億円)には10倍~15倍にも達する金額である。言うまでもなく、のれんの計上額が小さければそれでよい、といった単純な話ではなく、のれんを毎期定額償却するためには、耐用年数の決定方法など様々な課題はあるものの、一般的に言って、日本の会計基準によってのれんの毎期定額償却を義務付けられている日本企業のバランスシートのほうが、IFRSや米国会計基準を適用している欧米の主要企業に比べて「身軽」であり、投資家にとっても、いざというときに巨額の減損リスクが生じる可能性がより少ないことは間違いないであろう。
IASBのフーガーホースト議長は、インタビューの中で、のれんの減損テストには大きな課題があることや、企業の収益見通しが楽観的過ぎるため、減損のタイミングが遅くなりがちであること、のれんが非償却の現状では、投資家が財務諸表に対して実態以上に好印象を持ってしまい、減損が多発すれば一般投資家が大きな損失を被りかねないこと等を認めている。IFRS第9号「金融商品」において、これまでの金融資産の減損のアプローチであった「発生損失モデル」の問題点(金額が小さすぎ、かつタイミングが遅すぎる)が指摘され、損失見込み額を早めに計上する予想損失モデルに置き換えられた、といった最近の流れを考えても、非金融資産であるのれんの減損についても、今後同じような方向での見直しが行われる可能性は否定できないであろう。
IFRS第3号によってIFRS上ののれんの会計処理が非償却と定められた後も、我が国は、基本的にのれんの毎期定額償却を支持する立場をとり、のれんの会計処理の見直しの必要性を訴えてきた。我が国の企業会計基準委員会(ASBJ)も、2015年から2017年にかけて3本のリサーチ・ペーパー(注)を公表し、問題提起を続けてきた。
環境の変化も追い風となって、ここにきてようやく我が国の地道な意見発信の成果が表れ、主張が受け入れられる余地が出てきたのかもしれない。のれんは金額的な影響が極めて大きい論点であるため、議論が最終的に決着するまでには、まだまだ紆余曲折が予想されるが、IFRSの基準書開発や実務への適用に我が国が貢献できる大きなチャンスであるととらえ、前向きかつ有用な情報発信を続けていくことが必要と考える。
(注)ASBJが公表したリサーチ・ペーパーは次の3本である。
リサーチ・ペーパー第1号「のれんの償却に関するリサーチ」(2015年5月19日)
リサーチ・ペーパー第2号「のれん及び減損に関する定量的調査」(2016年10月3日)
リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」(2017年6月12日)
(参考)
日本経済新聞電子版記事
・「M&A『のれん』」費用計上の義務化検討 国際会計基準見直し、2021年にも結論(2018年9月13日)
・「のれん償却 国際会計基準でも検討 甘い評価、投資家に損失 国際会計基準審議会議長 フーガーホースト氏」(2018年9月14日)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















