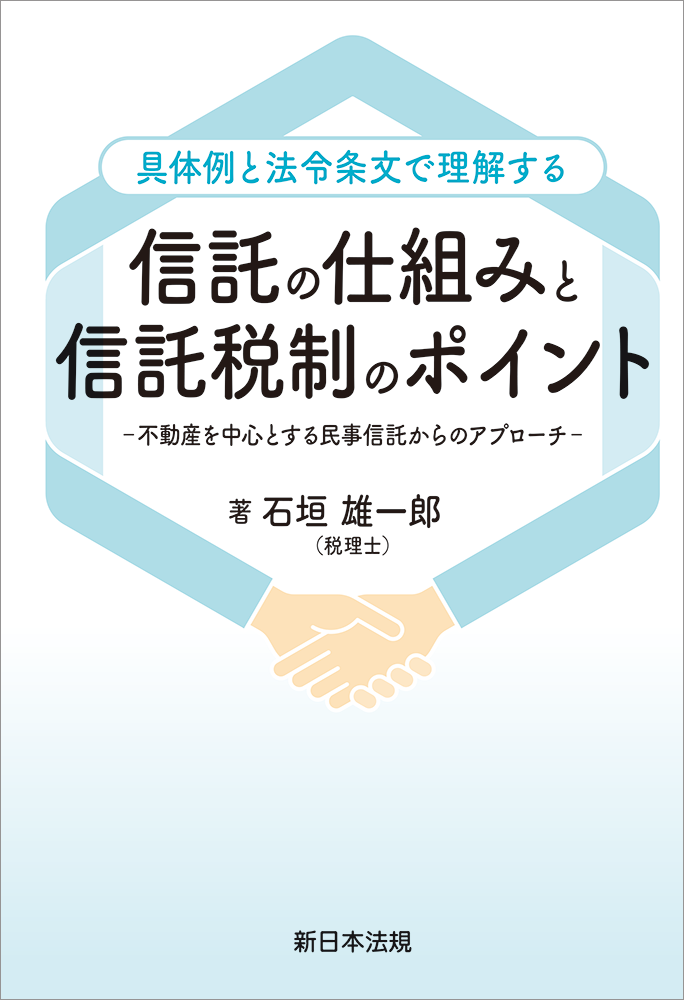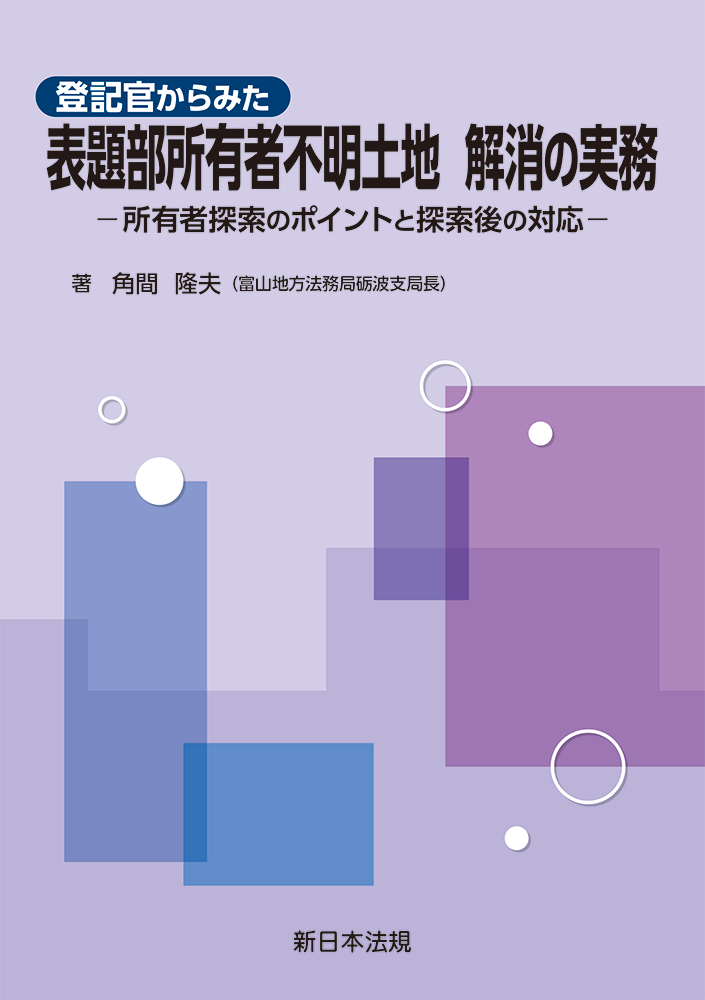解説記事2019年03月11日 【特別解説】 米国会計基準を適用している日本企業(のれんと耐用年数を確定できない無形資産の計上と減損テスト)(2019年3月11日号・№778)
特別解説
米国会計基準を適用している日本企業(のれんと耐用年数を確定できない無形資産の計上と減損テスト)
はじめに
国際財務報告基準(IFRS)を任意適用(適用予定を含む)する日本企業は、任意適用の開始から約9年で200社に達したが、一方でIFRSと並ぶ国際的な会計基準である米国会計基準を適用する日本企業の数は一貫して減り続け、現在のところ13社となっている。この現状を反映するかのように、我が国の会計基準を設定する場である企業会計審議会や企業会計基準委員会(ASBJ)、あるいは国際的な会計に関する書籍や雑誌の解説記事等においても、IFRSの任意適用に関する状況やIFRSの新しい基準書等に関する話題がほとんどを占めており、米国会計基準や米国会計基準を適用する企業に関する記述や説明は少なくなる一方である。本稿では、米国会計基準を適用する日本企業が減っている背景を簡単に述べた後で、現在もなお米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している日本企業による、のれんや無形資産等の計上の状況や開示等を紹介してみたい。
今回の調査対象とした企業
本稿では、2017年度(2017年12月期及び2018年3月期)において、米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を提出した次の日本企業(13社)を調査対象とした。(50音順)
なお、これまでは米国会計基準を適用し、2018年12月期、又は2019年3月期からIFRSを任意適用予定の企業(エヌ・ティ・ティ・ドコモ、京セラ、クボタ、日本電信電話(NTT)、日本ハム、マキタの6社。)は、今回の調査対象からは除外している。また、東芝は米国会計基準からIFRSへの移行をすでに表明しているが、具体的な移行時期が未定のため、米国会計基準を適用する企業として今回の調査対象に含めている。
IFRSと米国会計基準
国際財務報告基準(IFRS)の任意適用が我が国の企業に対して認められてからまだ10年経過していない一方で、ニューヨークに株式やADR(米国預託証券)を上場する企業や大手商社等を中心に、日本企業による米国会計基準適用の歴史は古く、最盛期には40社近くの日本企業が米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成していた。適用する会社数が13社にまで減少した現在でもなお、米国会計基準を適用する日本企業は、トヨタ自動車、ソニー、野村ホールディングス等の我が国やそれぞれの業界を代表する超優良グローバルカンパニーが多い。世界の会計をリードし、最も厳格な会計基準と長らく言われてきた米国会計基準の適用は、我が国の一流国際企業にとって、ある種の「ステータスシンボル」となってきたものと考えられる。
米国会計基準を取り巻く我が国の状況が大きく変わったのは、2009年6月30日に、企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」(以下、日本版ロードマップという)が公表されてからである。これにより、我が国においては2010年3月期から一定の上場会社の連結財務諸表についてIFRSを任意適用できるようになり、2015年又は2016年からすべての上場会社の連結財務諸表についてIFRSを強制適用する方向性が示された。一方、2009年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(内閣府令第73号)により、米国会計基準による連結財務諸表の作成は、2016年3月31日までとすることとされたのである。この決定は、その後の我が国での政権交代やIFRSへの対応姿勢の変化、金融危機等の経済環境の激変等もあって覆され、最終的に米国会計基準の使用期限は撤廃されたが、日本版ロードマップの公表や、最終的には撤廃されたとはいえ、米国会計基準の使用期限の設定が、次章で述べるような、これまで米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成してきた日本企業による、IFRSへの乗り換えの動きを促したことは間違いなく、現在に至るまで、その流れは続いているといえる。
米国会計基準からIFRSへの切り替え
EY新日本有限責任監査法人のホームページ(【一覧】米国会計基準を採用して有価証券報告書を作成している会社。平成24年10月11日付)によると、今から約7年前の平成23年12月期及び平成24年3月期には、32社の日本企業が米国会計基準を適用していた(下記の表1を参照)。
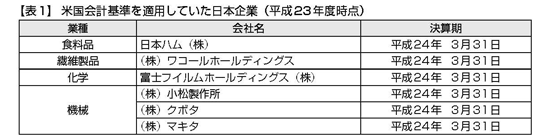

これらの32社のうち、今現在も米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している13社を除いた19社のその後の顛末を見ると、平成25年7月30日付で上場廃止となったジュピターテレコムを除く18社は、すべてIFRSに移行している(表2を参照)。
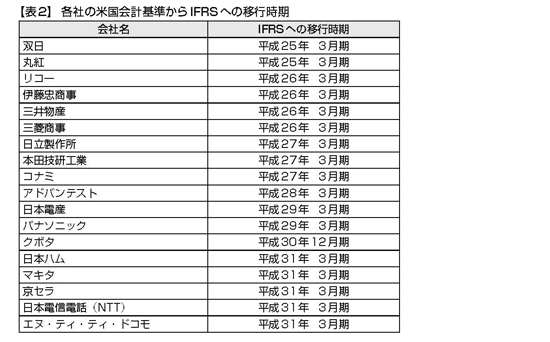
平成30年12月期と平成31年3月期とで、合計6社が米国会計基準からIFRSへの切り替えを予定している。
今なお米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している13社の分析
今回調査対象とした13社(表3)のうちで、将来の米国会計基準からIFRSへの切り替えを表明した会社は、今のところ存在しない。
【表3】米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している日本企業(再掲)
以後は、表3の各社について若干の調査分析を試みてみたい。
なお、平成30年末時点での日経平均株式時価総額上位ランキングを見ると、13社のうちの9社がトップ100社、11社がトップ200社以内にランクインしている。米国会計基準を適用する日本企業数は全盛期の半数以下となっているものの、依然として日本を代表するような超一流企業が顔をそろえていることが分かる。
ここでは、各社ののれん及び耐用年数を確定できない無形資産の計上額と、連結純資産に対する比率を分析した後で、のれんや耐用年数を確定できない無形資産に関する減損テストの開示を紹介してみたい。
① のれんの計上額と連結純資産に対する比率 米国会計基準を適用する日本企業各社ののれんの計上額と連結純資産に対する比率は、表4のとおりである。

のれんの計上額が1兆円を超える企業は1社もなく、残高が5,000億円を超える企業も13社のうちわずか3社に過ぎない。米国基準を適用する主要な米国企業(S&P株式指数構成銘柄)は、1社平均でおおよそ2兆円ののれんを計上しており、のれんの残高が連結純資産を上回る会社も珍しくなかったことを考えると、米国会計基準を適用する日本企業が計上しているのれんの金額、及び連結純資産に対する比率はともに、極めて低い水準にあることが分かる。
② 耐用年数を確定できない無形資産の計上額 米国会計基準では、のれんと同様に非償却とされる耐用年数を確定できない無形資産の計上額とその主要なものの内容は、表5のとおりである。
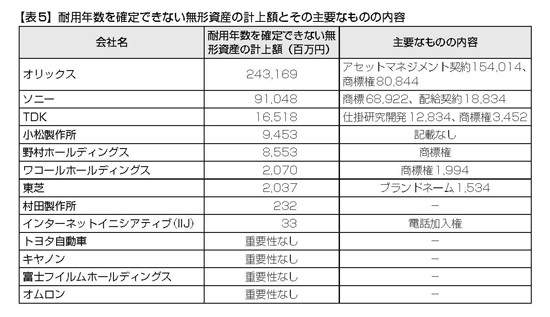
IFRS任意適用日本企業では、ソフトバンク、サントリー食品インターナショナルやLIXILグループなど、1,000億円を超える耐用年数を確定できない無形資産を計上している事例が複数あるが、米国会計基準を適用する日本企業の場合、オリックスのアセットマネジメント契約と商標権、及びソニーの商標権が目立つ程度であり、前記ののれんと同様に、計上額の水準は決して高いとは言えない。米国会計基準は、IAS第38号「無形資産」第57項が定める一定の要件を満たす開発費の無形資産計上を認めていないため(我が国の会計基準と同様に、研究開発費はすべて費用処理の取扱い)、のれんにせよ、耐用年数を確定できない無形資産にせよ、米国会計基準に基づく連結貸借対照表に計上される無形資産は、外部から取得したものに限定される。米国会計基準を適用する日本企業は、成熟した超優良企業が多いということもあり、M&Aや事業、ブランド等の外部からの取得にはあまり熱心ではない(自社グループ内で事足りる)という傾向がみられるのかもしれない。
③ のれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト 最後に、オリックスが開示した、のれん(営業権)及びその他の無形資産に関する重要な会計方針において注記した、減損テストの方法についての開示が個別具体的で興味深いため、紹介することとしたい。
(v)営業権及びその他の無形資産
(営業権)
(耐用年数を確定できない無形資産)
終わりに
20世紀、いや、我が国におけるIFRSの任意適用が開始される2010年まで、我が国において「国際的な会計基準」と言えば、それはすなわち米国会計基準を指していたと思われる。米国会計基準には世界の最先端の考え方が反映されており、最も厳格で、我が国を含む各国の会計基準を設定する際の「お手本」でもあり続けてきた。そして、我が国を代表するような超優良企業が米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成、公表するという時代が長く続いたのである。
それがこの10年から15年の間で、世界の共通言語としての会計基準として、IFRSがにわかに脚光を浴びるようになり、IFRSを任意適用する企業数の増加と反比例するかたちで、米国会計基準を適用する日本企業の数も減少の一途をたどってきた。しかし、それでもなお、米国会計基準は世界の会計の中で確固たる地位を築いており、IASB(国際会計基準審議会)とFASB(財務会計基準審議会)との間の共同プロジェクト等を通じて企業結合、収益認識、金融商品、リース等のIFRSの基準書にも、その影響が色濃く反映されている。また、数は少ないとはいえ、本稿で調査分析した米国会計基準を適用する日本企業は、いずれも、我が国を代表するエクセレント・カンパニーばかりである。昨今、我が国においては米国会計基準やそれを適用する企業が話題に上ることは少なくなってきているが、まだまだそれらからは目を離すことはできないと考えられる。
~参考~
EY新日本有限責任監査法人ホームページ「米国会計基準を採用して有価証券報告書を作成している会社(平成24年10月11日付)」
米国会計基準を適用している日本企業(のれんと耐用年数を確定できない無形資産の計上と減損テスト)
はじめに
国際財務報告基準(IFRS)を任意適用(適用予定を含む)する日本企業は、任意適用の開始から約9年で200社に達したが、一方でIFRSと並ぶ国際的な会計基準である米国会計基準を適用する日本企業の数は一貫して減り続け、現在のところ13社となっている。この現状を反映するかのように、我が国の会計基準を設定する場である企業会計審議会や企業会計基準委員会(ASBJ)、あるいは国際的な会計に関する書籍や雑誌の解説記事等においても、IFRSの任意適用に関する状況やIFRSの新しい基準書等に関する話題がほとんどを占めており、米国会計基準や米国会計基準を適用する企業に関する記述や説明は少なくなる一方である。本稿では、米国会計基準を適用する日本企業が減っている背景を簡単に述べた後で、現在もなお米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している日本企業による、のれんや無形資産等の計上の状況や開示等を紹介してみたい。
今回の調査対象とした企業
本稿では、2017年度(2017年12月期及び2018年3月期)において、米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成し、有価証券報告書を提出した次の日本企業(13社)を調査対象とした。(50音順)
| インターネットイニシアティブ(IIJ)、オムロン、オリックス、キヤノン、小松製作所、ソニー、TDK、東芝、トヨタ自動車、野村ホールディングス、富士フイルムホールディングス、村田製作所、ワコールホールディングス |
IFRSと米国会計基準
国際財務報告基準(IFRS)の任意適用が我が国の企業に対して認められてからまだ10年経過していない一方で、ニューヨークに株式やADR(米国預託証券)を上場する企業や大手商社等を中心に、日本企業による米国会計基準適用の歴史は古く、最盛期には40社近くの日本企業が米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成していた。適用する会社数が13社にまで減少した現在でもなお、米国会計基準を適用する日本企業は、トヨタ自動車、ソニー、野村ホールディングス等の我が国やそれぞれの業界を代表する超優良グローバルカンパニーが多い。世界の会計をリードし、最も厳格な会計基準と長らく言われてきた米国会計基準の適用は、我が国の一流国際企業にとって、ある種の「ステータスシンボル」となってきたものと考えられる。
米国会計基準を取り巻く我が国の状況が大きく変わったのは、2009年6月30日に、企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」(以下、日本版ロードマップという)が公表されてからである。これにより、我が国においては2010年3月期から一定の上場会社の連結財務諸表についてIFRSを任意適用できるようになり、2015年又は2016年からすべての上場会社の連結財務諸表についてIFRSを強制適用する方向性が示された。一方、2009年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(内閣府令第73号)により、米国会計基準による連結財務諸表の作成は、2016年3月31日までとすることとされたのである。この決定は、その後の我が国での政権交代やIFRSへの対応姿勢の変化、金融危機等の経済環境の激変等もあって覆され、最終的に米国会計基準の使用期限は撤廃されたが、日本版ロードマップの公表や、最終的には撤廃されたとはいえ、米国会計基準の使用期限の設定が、次章で述べるような、これまで米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成してきた日本企業による、IFRSへの乗り換えの動きを促したことは間違いなく、現在に至るまで、その流れは続いているといえる。
米国会計基準からIFRSへの切り替え
EY新日本有限責任監査法人のホームページ(【一覧】米国会計基準を採用して有価証券報告書を作成している会社。平成24年10月11日付)によると、今から約7年前の平成23年12月期及び平成24年3月期には、32社の日本企業が米国会計基準を適用していた(下記の表1を参照)。
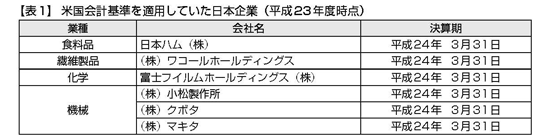

これらの32社のうち、今現在も米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している13社を除いた19社のその後の顛末を見ると、平成25年7月30日付で上場廃止となったジュピターテレコムを除く18社は、すべてIFRSに移行している(表2を参照)。
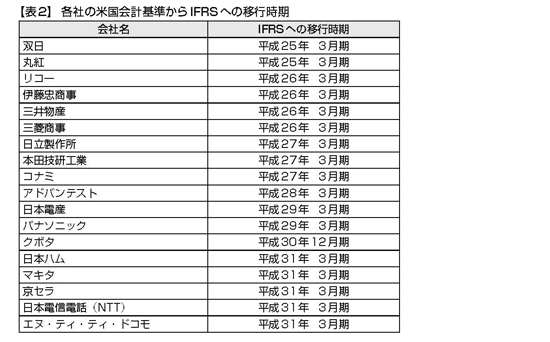
平成30年12月期と平成31年3月期とで、合計6社が米国会計基準からIFRSへの切り替えを予定している。
今なお米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している13社の分析
今回調査対象とした13社(表3)のうちで、将来の米国会計基準からIFRSへの切り替えを表明した会社は、今のところ存在しない。
【表3】米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している日本企業(再掲)
| インターネットイニシアティブ(IIJ)、オムロン、オリックス、キヤノン、小松製作所、ソニー、TDK、東芝、トヨタ自動車、野村ホールディングス、富士フイルムホールディングス、村田製作所、ワコールホールディングス |
以後は、表3の各社について若干の調査分析を試みてみたい。
なお、平成30年末時点での日経平均株式時価総額上位ランキングを見ると、13社のうちの9社がトップ100社、11社がトップ200社以内にランクインしている。米国会計基準を適用する日本企業数は全盛期の半数以下となっているものの、依然として日本を代表するような超一流企業が顔をそろえていることが分かる。
ここでは、各社ののれん及び耐用年数を確定できない無形資産の計上額と、連結純資産に対する比率を分析した後で、のれんや耐用年数を確定できない無形資産に関する減損テストの開示を紹介してみたい。
① のれんの計上額と連結純資産に対する比率 米国会計基準を適用する日本企業各社ののれんの計上額と連結純資産に対する比率は、表4のとおりである。

のれんの計上額が1兆円を超える企業は1社もなく、残高が5,000億円を超える企業も13社のうちわずか3社に過ぎない。米国基準を適用する主要な米国企業(S&P株式指数構成銘柄)は、1社平均でおおよそ2兆円ののれんを計上しており、のれんの残高が連結純資産を上回る会社も珍しくなかったことを考えると、米国会計基準を適用する日本企業が計上しているのれんの金額、及び連結純資産に対する比率はともに、極めて低い水準にあることが分かる。
② 耐用年数を確定できない無形資産の計上額 米国会計基準では、のれんと同様に非償却とされる耐用年数を確定できない無形資産の計上額とその主要なものの内容は、表5のとおりである。
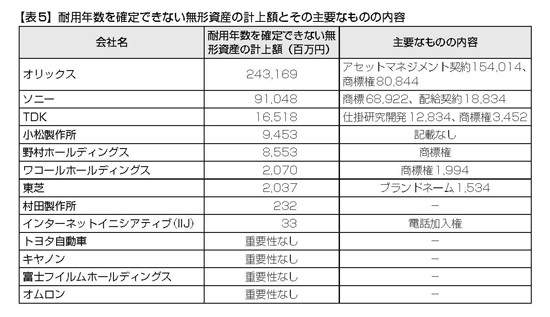
IFRS任意適用日本企業では、ソフトバンク、サントリー食品インターナショナルやLIXILグループなど、1,000億円を超える耐用年数を確定できない無形資産を計上している事例が複数あるが、米国会計基準を適用する日本企業の場合、オリックスのアセットマネジメント契約と商標権、及びソニーの商標権が目立つ程度であり、前記ののれんと同様に、計上額の水準は決して高いとは言えない。米国会計基準は、IAS第38号「無形資産」第57項が定める一定の要件を満たす開発費の無形資産計上を認めていないため(我が国の会計基準と同様に、研究開発費はすべて費用処理の取扱い)、のれんにせよ、耐用年数を確定できない無形資産にせよ、米国会計基準に基づく連結貸借対照表に計上される無形資産は、外部から取得したものに限定される。米国会計基準を適用する日本企業は、成熟した超優良企業が多いということもあり、M&Aや事業、ブランド等の外部からの取得にはあまり熱心ではない(自社グループ内で事足りる)という傾向がみられるのかもしれない。
③ のれんと耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト 最後に、オリックスが開示した、のれん(営業権)及びその他の無形資産に関する重要な会計方針において注記した、減損テストの方法についての開示が個別具体的で興味深いため、紹介することとしたい。
(v)営業権及びその他の無形資産
(営業権)
| 当社及び子会社は、営業権及び耐用年数を確定できない無形資産は償却を行わず、少なくとも年1回の減損テストを行っています。また、減損の可能性を示す事象又は状況の変化が起きた場合、発生した時点において減損テストを行っています。 営業権の減損は、2つのステップによる営業権の減損テストを実施する前に、報告単位の公正価値が営業権を含むその帳簿価額を下回っている可能性が50%超であるか否かについての定性的評価を行うことが認められています。当社及び子会社は、一部の営業権については定性的評価を行っていますが、その他の営業権については定性的評価を行わずに、直接2つのステップによる減損テストの第一ステップを行っています。定性的評価を行っている一部の営業権について、事象や状況を総合的に評価した結果、報告単位の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が50%超ではないと判断した場合には、その報告単位については2つのステップによる減損テストを行っていません。一方、報告単位の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が50%超であると判断された営業権及び定性的評価を行わない営業権については、2つのステップによる減損テストを行っています。2つのステップによる減損テストの第1ステップでは、特定された報告単位の公正価値と帳簿価額とを比較し、潜在的な減損の把握を行っています。公正価値が帳簿価額を下回っている場合は、減損金額を測定するため第2ステップの判定を行っています。第2ステップでは、営業権の暗示された公正価値と帳簿価額を比較し、営業権の暗示された公正価値が帳簿価額を下回っている場合は、公正価値まで減額し、評価損を期間損益として認識しています。当社及び子会社は、それぞれの事業部門またはそれより一つ下のレベルの単位で、営業権の減損テストを行っています。 |
(耐用年数を確定できない無形資産)
| 耐用年数を確定できない無形資産の減損は、定量的な減損テストを実施する前に、耐用年数を確定できない無形資産が減損している可能性が50%超であるか否かについての定性的評価を行うことが認められています。当社及び子会社は、一部の耐用年数を確定できない無形資産については定性的評価を行っていますが、その他の耐用年数を確定できない無形資産については定性的評価を行わずに、直接定量的な減損テストを行っています。定性的評価を行っている一部の耐用年数を確定できない無形資産について、事象や状況を総合的に評価した結果、減損している可能性が50%超ではないと判断した場合には、定量的な減損テストを行っていません。一方、減損している可能性が50%超であると判断された耐用年数を確定できない無形資産及び定性的評価を行っていない耐用年数を確定できない無形資産については、当該無形資産の公正価値を算定して、定量的な減損テストを行っています。耐用年数を確定できない無形資産の公正価値と帳簿価額とを比較し、公正価値が帳簿価額を下回っている場合は、公正価値まで減額し、評価損を期間損益として認識しています。 |
終わりに
20世紀、いや、我が国におけるIFRSの任意適用が開始される2010年まで、我が国において「国際的な会計基準」と言えば、それはすなわち米国会計基準を指していたと思われる。米国会計基準には世界の最先端の考え方が反映されており、最も厳格で、我が国を含む各国の会計基準を設定する際の「お手本」でもあり続けてきた。そして、我が国を代表するような超優良企業が米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成、公表するという時代が長く続いたのである。
それがこの10年から15年の間で、世界の共通言語としての会計基準として、IFRSがにわかに脚光を浴びるようになり、IFRSを任意適用する企業数の増加と反比例するかたちで、米国会計基準を適用する日本企業の数も減少の一途をたどってきた。しかし、それでもなお、米国会計基準は世界の会計の中で確固たる地位を築いており、IASB(国際会計基準審議会)とFASB(財務会計基準審議会)との間の共同プロジェクト等を通じて企業結合、収益認識、金融商品、リース等のIFRSの基準書にも、その影響が色濃く反映されている。また、数は少ないとはいえ、本稿で調査分析した米国会計基準を適用する日本企業は、いずれも、我が国を代表するエクセレント・カンパニーばかりである。昨今、我が国においては米国会計基準やそれを適用する企業が話題に上ることは少なくなってきているが、まだまだそれらからは目を離すことはできないと考えられる。
~参考~
EY新日本有限責任監査法人ホームページ「米国会計基準を採用して有価証券報告書を作成している会社(平成24年10月11日付)」
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -