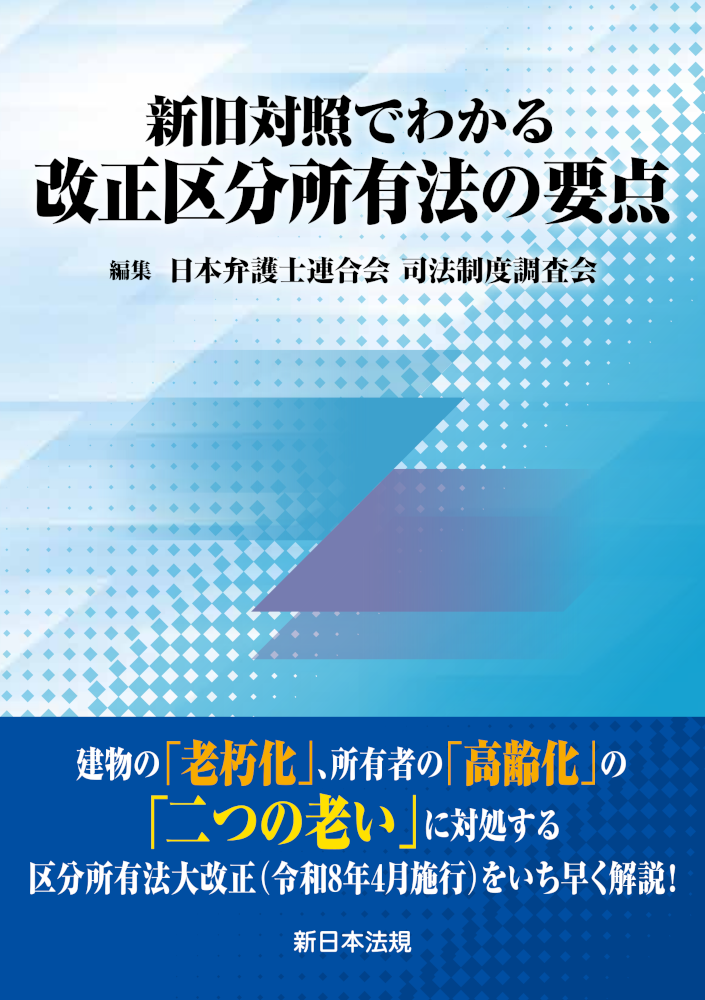解説記事2019年03月18日 【最新判決研究】 相続税における名義有価証券等の帰属(2019年3月18日号・№779)
最新判決研究
相続税における名義有価証券等の帰属
一、事実
(1)X(原告)は、父甲が平成22年11月11日死亡したことにより、母乙(甲の妻)及び弟丙(以下X、乙及び丙を「本件共同相続人」という。)とともに甲を相続した(以下「本件相続」という。)。Xは、平成23年9月12日、乙及び丙とともに、本件相続に係る相続税について、課税価格を3382万円余とする申告を行い(以下「本件当初申告」という。)、次いで平成26年2月7日、課税価格を6413万円余とする修正申告(以下「本件修正申告」という。)をした。
これに対し、処分行政庁は、平成26年7月8日、課税価格を1億1596万円余とする更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の額を182万円余とする賦課決定(以下本件更正と併せて「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、異議申立て及び審査請求を経て(異議決定において課税価格は9246万円余に減額されている。)、平成28年6月2日、国(被告)に対し、課税価格8284万円余を上回る部分の本件更正等の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)本訴において、問題となったのは、乙名義のN証券会社の本店口座及びY支店口座で管理されている有価証券等総額1億4907万円余(以下「本件乙名義有価証券等」という。)(そのほか、N証券会社に存する甲名義及びX名義の各口座と併せて「本件各証券口座」という。)の帰属である。この帰属につき、Xは、当初申告において、その40%相当額(5949万円余)が本件相続財産に含まれるとし、本件修正申告においてはそれが45%相当額(6946万円余)であるとした。これに対し、処分行政庁は、本件乙名義有価証券等の全額が本件相続財産に含まれるとして本件更正等を行い、国も、本訴においてその旨主張している。他方、Xは、本訴において、その50%相当額7453万円余(以下「本件係争部分」という。)がXに帰属し、本件相続財産に含まれない旨主張している。
(3)甲は、昭和21年頃から税務職員として勤務した後、昭和55年以降税理士業を営んでいた。Xは、昭和60年に税理士登録をした後、税理士として甲の事務所に勤務していた。乙は、昭和35年に結婚し、甲が税理士事務所を開設してから6年程度、事務員として税理士業務を補助していた。また、甲は、処分行政庁に対し、X及び乙をそれぞれ事業専従者とする青色事業専従者給与に関する届出書を提出していた。なお、本件相続開始時における乙名義の資産は、本件乙名義有価証券等を除き、預貯金等が約1521万円、生命保険金等が約4670万円、合計6191万円余であり、X名義の資産は、預貯金が約300万円、有価証券約5652万円及び生命保険金等が約7425万円の合計約1億3378万円であった。
他方、乙は、本件乙名義有価証券等の全部が本件相続財産に含まれるものとして相続税の額を計算した平成25年12月3日付け及び同26年7月8日付け各修正申告書を提出した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分が、「相続により取得した財産」、すなわち本件相続財産に含まれるか否かであり、とりわけ、本件係争部分が、甲のXに対する給与を原資として形成されたものか否かにある。
2 国の主張 (1)被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであるか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものと解されている。
(2)本件各証券口座の管理及び運用については、甲が自ら行っていたほか、乙が甲の指示の下、あるいは同人と相談した上で行っており、Xは関与していなかったから、その実質的な主体は、乙が行っていた時期も含めて、一貫して甲であったと認められる。また、本件相続開始日前5年を超える期間の金員の動きに関する各事情を考慮すれば、乙各証券口座における有価証券の過半は、甲の資金を原資として構成されているものと認められる。
(3)前記で述べた管理及び運用の点、並びに原資の点に加え、①乙各証券口座の名義人は乙であるものの、乙と甲は夫婦であり、家族の中でも夫婦間においては、配偶者の名義で自己の財産を保有、管理することはまれではないこと、②甲、乙、X及び丙の各名義の口座は、必ずしも原資の出捐者の負担部分に応じた区分管理がされていたとはいえないこと、③乙が、平成25年12月3日及び平成26年7月8日、処分行政庁に対して、乙各証券口座における有価証券が甲に帰属するものであることを前提とした相続税の修正申告書を提出していることを総合勘案すれば、本件乙名義有価証券等はXに帰属するもの、すなわち、本件相続財産に含まれると優に推認することができる。
(4)乙は本件相続開始時において6191万円余の資産(本件乙名義有価証券等を除く。)を有しているところ、上記の各事情に鑑みれば、この資産の金額は、推定される乙が甲の事業に従事した期間である30年(実際は6年)の間に事業専従者として得ていた収入に照らし相応なものであるといえ、乙が、本件相続開始日当時において、上記金額を超えて1億4907万円余もの本件乙名義有価証券等を有することができたとは認められない。
3 Xの主張 (1)本件各証券口座における資産の購入原資には、甲からXに支払われるはずの給与が含まれている。甲は、昭和21年頃から税務署で勤務した後、昭和55年に退官して税理士登録し、その後は他界するまで税理士として稼働していた。他方、Xは、昭和60年に税理士登録し、甲の事務所で勤務していた。甲は、上記事務所において他の事務職員を雇用したことはなく、20年以上、Xと二人三脚で上記事務所の切り盛りをしていた。Xは、税務申告上、甲から賃金(青色事業専従者給与)が支払われる形となっていたが、実際には一切手にしておらず、甲の証券取引等の原資となることも含めて、その全額の運用を甲に委ねていた。その額は、平均して毎月50万円程度であり、これをXが甲の下で稼働していた26年4か月に換算すると、合計1億5800万円となる。
(2)上記のとおり、Xは、甲に対し、本件Xに支払われるべき青色事業専従者給与の運用を委ね、その寄与により本件乙名義有価証券等が形成されたのであって、これを法的に評価すると、Xと甲との間には、互いに出資して株式等により利益を得ることを目的とする組合契約(以下「本件組合契約」という。)が成立しており、本件乙名義有価証券等は本件組合契約に基づき形成された財産であると評価できる。そして、組合業務により造成された財産は、その一部の所有名義が組合員のうち1人の名義となっていても、実質的に各組合員が組合業務を目的として一種の組合契約を締結し、その事業執行の結果得られた財産とみられるから、組合員の一部が死亡し、他に組合員がいる場合には、組合の解散に準じその出資割合に応じて残余財産を精算し、その精算の結果、他の組合員の取得する持分(他の組合員の固有持分)に相当する部分は、相続財産から除外し、死亡した組合員の取得分のみを相続財産として取り扱うべきであるし、仮に、本件において、組合の解散又は解散に準じる事実が認められないとしても、組合員が脱退により払戻しを受けられる組合財産は、脱退時における当該組合員の組合財産に対する持分割合に従って決せられるのであり、これを超えて組合財産の払戻しを受けることはできないのであるから(民法681条1項)、他の組合員の固有持分に相当する部分は相続財産から除外し、死亡した組合員の持分に相当する部分のみを相続財産として取り扱うべきものと解するのが相当である。したがって、本件乙名義有価証券等については、少なくともその価額の50%に相当する部分(本件係争部分)についてはXに帰属する。
(3)国が主張する資産のうち、X名義の預貯金300万円余は、甲からXに対して支払われるはずの賃金とは関係がなく、Xが税理士として独自に稼働して形成した資産である。また、X名義の生命保険等は、甲が、その可処分所得の中から、子であり共同経営者でもあるXの掛金を負担したものであり、甲からXに支払われるはずであった給与を原資としたものではない。それにもかかわらず、国は、本件乙名義有価証券等が本件相続財産に含まれるか否かを検討するに際し、本件相続開始時のXの保有財産にこれらの資産が含まれていることを看過しており、失当である。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)本件においては、本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分が本件相続財産に含まれるか否かが争われている。相続税の課税物件である財産の法律上の帰属については、当該財産の名義によるのみでなく、その実質に即した認定判断をすべきものであり、とりわけ、親族間においては、例えば夫が妻や子の名義を借りて自らの資産を原資として有価証券取引に係る口座を開設し、当該口座で取引を行うこともまれではないといえることに照らすと、上記の認定判断に当たっては、当該財産の名義のほか、当該財産の取得(その購入の原資となった資産の取得を含む。以下同じ)が誰の出捐によるものか、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等の各事情を総合考慮して認定判断することが相当である。
そして、本件においては、本件係争部分につき本件相続財産に含まれるか否かが争われているのであるから、本件乙名義有価証券等の取得は甲の出捐によるものか、それとも、Xの出捐によるものかが特に問題となる。また、これらの出捐に関する問題を検討する前提として、甲及びその家族の資産がどのように管理されてきたのかについても検討する必要がある。
(2)そこで、まず、甲及びその家族の資産の管理状況等につき検討すると、前記認定事実によれば、甲は、税務署を退官した後に税理士事務所を開業し、これによる事業収入を得る一方、妻である乙及び子であるXに対しては青色事業専従者給与として給与を支払ったとして、当該給与相当額を自らの収入から控除して所得税の申告をしていた。もっとも、税理士であるXが昭和60年頃から甲とともに税理士の業務を行っていたのに対し、乙が甲の事務所において事務員の業務を行っていたのは、昭和55年頃から6年間程度にすぎず、それ以降においては給与の対象となるような労務提供の実態はなかった上、乙の収入は、上記の青色事業専従者給与を除けば、年金等に限られていた。また、甲の子である丙については、会社員として稼働し、結婚後独立して生活していたため、経済的にも甲から独立していた。
このように、経済的に独立していた丙の関係を除けば、甲の一家の収入は、主として、同人の事務所で営まれていた税理士業の収入により成って
いたものであり、甲はその収入により得られた資産の管理及び運用を、Xへの青色事業専従者給与として支払われた分も含めて、自ら又はその意を受けた乙を通じて行っていたものと認められる。
そして、甲は、上記のような一家の資産の管理及び運用のために、独立していた丙の名義をも利用して、甲、乙、丙及びXの各名義で預金口座(本件各預金口座)を開設するとともに、これらの名義で有価証券取引の口座(本件各証券口座のほか、丙の名義の口座を含む。)を開設して、これらの預金口座相互間及び預金口座と証券口座との間で頻繁かつ複雑な資金のやり取りをしながら、証券取引等を通じた資産の形成を行ってきたものである。本件乙名義有価証券等の取引が行われた乙各証券口座もまた、このような中で開設されたものであり、甲による一家の資産の管理及び運用のために乙の名義を利用したものであった。
(3)以上を前提として、本件乙名義有価証券等の取得に係る出捐につき、甲がその全額を出捐したか否かについて検討する。
ア 前記認定事実によれば、乙各証券口座には、合計9984万円余の資金流入があり、これが本件乙名義有価証券等の購入の原資となったと認められるところ、上記9984万円余の資金流入は、主として、①乙名義預金口座から入金された8571万円余及び②甲名義預金口座から入金された564万円によるものと認められる。そして、上記①の乙名義預金口座への入金として、③甲名義預金口座からの5679万円余、④丙名義預金口座からの1897万円余、⑤乙名義の年金及び保険金の収入3183万円余並びに⑥乙名義の有価証券に係る受取配当金707万円余の各入金があったことが認められる。
イ 上記のとおり、本件乙名義有価証券等の購入の原資のうち、甲名義預金口座から乙名義の口座へ入金されたものは5679万円余及び564万円の合計6243万円余であるところ、甲名義預金口座の預貯金については甲の資産であると推認される。また、丙名義預金口座から入金された1897万円余についても、丙自身が同口座は甲が丙名義で有価証券取引を行うためのものであると認識していたことに照らせば、その実質は、甲の資産であったものと推認することができる。
さらに、乙名義の年金及び保険金の収入3183万円余及び乙名義の有価証券に係る受取配当金707万円余についても、このうち年金収入を除く部分が乙の固有の資産であったといえるかには疑問があり、少なくともその相当部分は甲の資産により形成されたものと推認することができる。すなわち、乙に係る青色事業専従者給与の額の推移や、乙の所得税の確定申告における平成15年分から平成22年分までの収入金額の1年当たりの平均額が406万円であったこと、これらの給与以外には乙には年金等の収入しかなかったこと、乙名義預金口座からはN証券本店X口座等へ2000万円以上の資金が流出しているほか、約927万円が保険料の支払に充てられていることなどに照らせば、これらの収入による資産形成にも限界があるといわざるを得ず、乙がXとの訴訟において乙の母親から3700万円を相続した旨を供述していることを踏まえても、本件相続開始時における乙名義の資産(約6191万円)のほかに本件乙名義有価証券等の購入の原資となった資産を形成し得たといえるかには疑問がある。このことに加え、そもそも乙が甲の事務所において事務員の業務を行っていたのは、昭和55年頃から6年間程度にすぎず、それ以降においては給与の対象となるような労務提供の実態はなかったことに照らすと、確定申告どおりの給与が乙に支払われていたのかにも疑問を抱かざるを得ない。なお、乙自身、本件相続に係る相続税について提出した修正申告書において、本件乙名義有価証券等の全部が本件相続財産に含まれるものとして相続税の額を計算して申告をしており、少なくとも上記申告の時点では本件乙名義有価証券等の全部又は一部が自己に帰属する財産であるとの主張をしていないことからも、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった資産が甲に帰属するものであったことが裏付けられる。
ウ 以上によれば、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった9984万円余については、その大半を占める8140万円余が甲の出捐によるものと推認できること、そのほか、乙名義預金口座へ入金された保険金・配当金等収入3891万円余についても、その相当部分が甲の資産により形成されたものと推認できることに照らせば、上記9984万円の全部につき甲に帰属するものであったと推認することができる。
エ これに対し、Xは、甲の平成17年分から平成22年分までの所得の金額は約3307万円であるところ、甲は、この所得の中から、所得税や家族の生活費等、自宅及び事務所のローン等を支払っている上に、本件相続開始時に約3000万円の預貯金等を有していたのであるから、このほかに、本件乙名義有価証券等の全部につきその購入の原資となるような資産を有していたということは困難であり、甲以外の者からの資金流入がなければ合理的な説明が困難である旨を主張する。
しかしながら、甲は、昭和21年頃から昭和55年まで税務職員として勤務し、その後平成22年までの長年にわたり税理士業を営んでいたものであり、その間の収入により相当の貯蓄があったと考えられるほか、Xの陳述によればXが税理士登録をした昭和60年よりも前から株式等の取引をしていたことがうかがわれ、その取引により得られた利益も相当にあったものと考えられる。また、甲は、平成12年から平成13年にかけては甲、乙及びXの各名義でN証券Y支店に口座を開設し、平成18年にはN証券本店にも上記各名義の口座を開設し、上記3名のほか丙の名義を含む預金口座相互間における頻繁かつ複雑な資金移動を繰り返しながら株式の取引を含む資金運用を活発に行っていたのであるから、これらの証券口座(本件各証券口座)を開設した時点においては、長年にわたる管理及び運用の成果として相当多額の資産を形成していたと推認される。また、実際に、例えば甲名義のM銀行K支店の普通預金口座には、甲に係る株式の売却代金(平成18年11月28日の199万円余、平成19年7月9日の123万円余)や保険金収入(平成17年4月28日の13万円余、平成19年11月26日の624万円余)など、株式取引や保険加入等による資金の管理及び運用の結果として生じた利益が振り込まれていたことが認められる。
これらの事実に照らすと、甲は、Xが主張する種々の支出や本件相続開始時における預貯金等の額を踏まえても、なお本件乙名義有価証券等の全部について購入の原資を拠出することのできる十分な資力を有していたものと認められるから、Xの上記主張は採用できない。
(4)次に、本件乙名義有価証券等の取得につき、Xが本件係争部分に係る出捐をした可能性の有無について検討する。
ア 前記(3)のとおり、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった乙各証券口座への資金流入について、X名義預金口座からの入金は含まれていない(むしろ、X名義の口座から乙名義の口座への入金が合計929万円余であるのに対して、乙名義の口座からX名義の口座への入金は合計2885万円余であり、後者の方が上回っている。)。
イ Xは、甲から受けた給与につきその全額の運用を甲に委ねており、甲はこれを原資として本件各証券口座で管理されている株式等を購入したものであると主張する。
しかしながら、そもそも、Xが甲から受けた給与の額として主張する金額(平均月50万円程度、26年4か月による勤務の合計で1億5800万円)については、給与額が月50万円に増額されたのは平成15年7月以降であり、それ以前においては月15万円から順次増額され、平成2年1月から平成15年6月までは月40万円にとどまっていたことに照らせば、Xがその主張の金額の給与を受けていたとは認め難い。
また、Xは、本件相続開始時において合計約1億3378万円の資産を有していたものであり、これらの総計はXが受けていた給与の額を大きく上回るものといえる(Xが主張する給与の額と比べても、若干上回る。)。
(5)以上のとおり、甲は、自らの事務所で営んでいた税理士業の収入につき、甲、乙、丙及びXの各名義を利用して資産の管理及び運用を行ってきたものであり、乙各証券口座もその中で開設されたものであるところ、本件乙名義有価証券等の購入の原資として、乙各証券口座又は乙名義預貯金口座に、甲名義預金口座及び甲の資産と推認される丙名義預金口座からその大半を占める資金が流入しているほか、乙名義の保険金や配当金の収入についても、その相当部分が甲の資産により形成されたものと推認できることから、上記購入の原資となった9984万円余についてはその全部が甲に帰属するものであったと推認することができるものである。他方、X名義預金口座からは、本件乙名義有価証券等の購入の原資となるような資金流入は認められず、また、Xが甲から受けた給与及びその運用により得られた収益については、既にX名義の資産として形成されているものと認められ、このほかに、本件乙名義有価証券等の購入の原資となるような資産をXが有していたとは認め難い。これらに照らせば、本件乙名義有価証券等は、その全部が甲に帰属する(本件相続財産に含まれる)ものと認めるのが相当である。
四、解説
はじめに
相続税の申告、課税実務においては、相続開始時において、被相続人名義外の財産が当該被相続人の財産として認定できるのか、あるいは名義人となっている当該相続人に帰属していたのかがよく問題になることがある。この場合、当該財産の帰属等については、被相続人が存在していない以上、相続人が一番良く知悉していることであろうから、申告納税の建前上、当該相続人の判断で当該相続税の申告をすれば足りるはずである。また、当該申告後、課税上問題があれば、税務職員は、質問検査権の行使(税務調査)によって、それらの事実関係を調査し、当該事実に基づいて課税処分をすれば足りることになる。
問題は、税務代理人となる税理士の方である。税理士は、多くの相続税申告について代理人を務めているが、代理人となった時点では、当該相続に係る各財産の帰属関係について知る由もない。しかし、税理士は、「納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」(税理士法1)ことを使命としているため、被相続人に関わる各財産の帰属をできるだけ明確にした上で、当該相続税の代理申告に当たらなければならないことになる。そうは言っても、税理士は、税務職員のような質問検査権の行使が認められているわけではなく、かつ、納税者からの依頼を受けて申告代理をする立場であるが故に、納税者のプライバシーに関わる事実関係を厳しく追求するわけにも行かないので(注1)、その調査にも自ずから限界がある。そのため、税理士自身も、当該事実関係に疑問を感じながらも申告代理を行わざるを得ない場合も考えられる。
本件においては、その税理士(X)が、自己が相続人となって、父親である被相続人甲の妻乙(Xの母)の名義となっていた本件乙名義有価証券等が甲に帰属するもの(本件の相続財産)か否かが争われたものである。しかも、Xは、甲が経営していた税理士事務所の勤務税理士であったというのであるから、X自身が家族内の財産の帰属関係を最も知悉していたものとも考えられるので、それを訴訟まで持ち込んで争うからには、その主張を裏付ける余程の事情があったものかも知れないし、あるいは税の専門家としての判断を誤ったものかも知れない。
そこで、本稿においては、相続税における被相続人名義以外で家族等の名義となっている預貯金、株式、その他の有価証券等の帰属問題について、従前の一般論を検討した上で、本件乙名義有価証券等の帰属について検討することとする。
1 名義預貯金、名義株式等の帰属 (1)前述したように、相続税における相続財産については、相続開始時において、被相続人の名義ではなく、当該家族名義である財産が当該被相続人に帰属するものとして相続財産に該当するか否かがよく問題となる。その中でも、預貯金、株式、その他の有価証券等に係るものが特に問題となり、税務調査時又課税処分の段階において、「名義預金」等としてその帰属が争われることが多い(注2)。そのような事例の形態としては、次のようなものが挙げられる(注3)。
① 相続開始前後の預貯金の引出し等 相続開始直前においては、被相続人になる者の財産管理能力が低下(無力化)することもあって、相続人となる者が被相続人になる者の預貯金を引き出して利用することはままあることである。また、相続開始後においても、相続人が1人であるように遺産分割の協議の必要がなければ、当該相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して自己名義の預貯金等にすることも可能である。このような場合に、当該引出し金の行方と当該預貯金等について相続財産に該当するか否か等が問題となる。
② 名義預金 相続税において被相続人の財産であったか否かが最も問題となるのが、いわゆる名義預金である。名義預金とは、当該預金の名義と真の所有者(帰属)が異なることを意味している。この名義預金については、2種類に区分できる。一つは、被相続人が、生前、自己の現預金を家族名義で分散しておくもので、当該名義変更等について当事者間で贈与の認識もない場合が多い。また、預金通帳及び印鑑の管理も当該被相続人が独自に行っている場合が多い。このようなことは、かつて、少額貯金の非課税制度が採用されていた頃は、よく行われていたことでもある。
二つは、被相続人が、子や孫に対する贈与の意思を持って、子や孫名義の預金をすることである。この場合、当該家族間で贈与(契約)が成立しているか否かが問題となる。その贈与の根拠として、贈与契約書の有無、贈与税の申告の有無(注4)、通帳及び印鑑の管理状態が問題となるが、贈与契約それ自体は口頭でも可能であるし、非課税範囲の贈与であれば申告も必要ではないので、それらを決定的な根拠にすることも難しいと言える。
③ 名義株式 多くの同族会社では、経営と資本が一体となっており、経営者による株式の発行、割当ても自由であり、それに必要な資金も当該経営者によって支弁されることがある。よって、経営者の家族が無償でかつ認識のないまま株主になる機会も多く、名義預金と同じような問題が生じる。また、本件のように、家族名義で株式取引が行われることがあり、相続時に当該家族名義の株式等が存することになる。
④ 夫婦間の贈与と名義預金等 専業主婦が夫の給与で生活費をやりくりし、余剰金を妻名義の預金にしている場合に、当該預金の所有者が問題となる。この場合、夫から「生活費のやりくりは甲斐性だから余剰金は贈与する」旨の約束(贈与)があった場合に、その法的効力も問題となる。
また、本件のように、夫の事業に妻が従事して専従者給与を受けている場合に、当該給与によって預金や有価証券が取得できたか否かも問題となる。
⑤ 親族間の金銭貸借 親子間等の金銭貸借については、当初は契約書等が締結され、金銭等の移転があった後、契約どおりに返済されたか否か、それが仮装であったものか否か、相続時の残高が確認されているか否か等問題となり易いことが多い。
(2)以上のように、相続開始時においては、多くの相続税事例において、被相続人名義以外の預貯金、有価証券、不動産等の真の所有者が誰であるのか(財産の帰属)が問題となる。この場合、当該財産の真の所有者(帰属)をどのようにして判断するかについて、名古屋地裁平成10年2月6日判決(税資230号384頁)は、実質課税の原則の見地から(注5)、次のように判示している。
「相続税は、相続財産を相続又は遺贈により取得した財産としており、何を相続税の課税財産とみるかは、原則として、民法等の一般私法の定めるところに基づいて、私法上の法律関係を前提として判断されるものである。しかしながら、相続税が財産の無償取得により生じる担税力の増加を課税の根拠としていることからすると、相続財産が何であるかを判断する際には、単に形式的な法律的観点ないし私法上の法律関係の如何にとらわれることなく、相続課税上の妥当性、相当性という観点、言い換えれば経済的実質という観点からもなされるべきである。」
また、最近の裁判例においては、近年、学説等において実質課税の原則が制限的に通用すべきであると解されるようになっていることもあって、種々の事実関係を総合考慮して判断すべきこととしているが、例えば、札幌地裁平成26年7月30日判決(平成25年(行ウ)第14号)は、次のように判示している。本判決も、このような考え方に基づいている(注6)。
「ある財産が相続人以外の者の名義になっていたとしても、当該財産が相続開始時において被相続人に属していたものと認められるものであれば、当該財産は、相続税の課税対象となる相続財産となる。そして、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったといえるか否かは、当該財産又はその取得原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産を管理及び運用する者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である。」
2 参考となる判決・裁決事例 前記1で述べたように、相続税の課税においては、名義預金、名義株式等の帰属(被相続人のものか、当該名義人のものか)が問題になるが、その主要の形態は、前記1の①から⑤のとおりである。そこで、それらの形態別に、参考となる事例を紹介することとする。
① 相続開始前後の預貯金の引出し等-東京地裁平成30年1月19日判決(平成28(行ウ)第240号)(注7)。 本事案では、相続人(共同相続人なし)が、相続開始前に被相続人(相続人の母)の名義の預貯金合計5180万円を引き出し、そのうち300万円を被相続人の医療費、生活費等に費消したものの、残額のうち、1070万円を自己名義の預金とし、3810万円を手許に残しておいた。これについて、上記の相続人名義の預金と手許現金が相続財産に含まれるとし、かつ、当該申告につき重加算税を課するとする課税処分が行われ、当該課税処分の違法性が争われた。原告は、当該相続の4年前にあった父の相続に係る遺産が未分割であったため、上記母名義の預貯金には父のものであったものも含まれていて母と共有であった等を主張したが、当該判決は、上記主張を認めず、原告の一連の行為が国税通則法68条に定める「隠ぺい・仮装」に当たる旨判示した。
② 名義預金(孫への積立預金)-平成3年1月18日裁決(裁決事例集41号271頁) 本事案では、被相続人の孫名義の定期貯金200万円が相続財産に含まれるか否かが問題となった。相続人である審査請求人は、当該定期貯金は自分が長女(被相続人の孫)のために毎月1~2万円積み立て、一定額になったものを定期貯金としたものである旨主張した。これに対し、本裁決は、①当該定期貯金の届出住所、届出印鑑及び申込書の筆跡が被相続人名義の他の定期貯金のものと同一であること、②当該定期貯金の利息と被相続人名義の定期貯金の利息とを合わせて別段預金としているが、それらに利用されている印鑑が同一であること、③被相続人には、当該定期貯金を設定した頃土地代金の入金があったこと等からすると、当該定期貯金は、被相続人が非課税貯蓄に着目して孫の名義を使用したものと推認できるとして、当該定期貯金を相続財産に含めた課税処分を適法とした。
③ 名義株式(相続人名義の株式)-東京地裁平成18年9月22日判決(税資256号順号10512) 本事案では、相続人ら(妻、子ら5名)の名義となっていた19銘柄約2億円の株式が相続財産に含まれるか否かが争われた。相続人らは、当該株式は被相続人から生前贈与により取得したものである旨主張した。これに対し、本判決は、当該株式は、被相続人が原資を負担して取得していて、被相続人の住所地が株主の登録住所となっており、被相続人が取得後もこれを一括管理していたものであり、株式の配当についても被相続人が自ら取得していたものと認められるから、被相続人に帰属するものと認められる旨判示した。しかし、本判決は、当該株式の1銘柄6750株のうち3500株については、その登録住所・登録印について、昭和52年1月1日時点では被相続人の住所が登録されていたものの、平成元年4月18日には、子の自宅を登録住所とするものと認められ、登録印もその他の登録印と異なっているなどから、相続財産から除外すべきものとした。
④ 名義預金(夫婦間の生前贈与)-平成19年4月11日裁決(TAINS-F0-3-312) 本事案では、被相続人の妻名義となっている預貯金等合計約6300万円が相続財産となるか否か(課税処分では、被相続人の財産になる旨認定)が問題となった。審査請求の審理において、当該妻は、①専業主婦であるが、結婚後、夫から、月54万円、盆暮に50万円から100万円を生活費等として受け取り、「渡したお金の残りはお前にやる、好きにしてよい」と云われたこと、②①の残金は妻名義の預金等として積み立て、その通帳等と印鑑は自分の衣装だんすの中に保管していたこと等を主張していた。しかし、裁決は、当該預貯金については、妻名義となっているものの、その原資は被相続人が拠出したものであって、被相続人か妻への生活費の余剰金の贈与を認めるに足りる証拠も見当たらないことから、被相続人に帰属すると認めるのが相当である旨判断した(同旨東京地裁平成20年10月17日判決(平成19年(行ウ)第19号)、東京高裁平成21年4月16日判決(平成20年(行コ)第386号)等参照)。
⑤ 親族間の金銭貸借(貸付金の存否)-宮崎地裁平成23年9月9日判決(平成22年(行ウ)第3号)、福岡高裁平成24年2月15日判決(平成23年(行コ)第9号) 本事案では、被相続人が、生前、相続人である長男に約3779万円の金員を交付し、その長男が計15枚の借用書を差し入れている場合に、当該金員が贈与済であるのか、貸付金として相続財産に含まれるかが争われた。その長男は、当該金員の交付には利息、返済期限が一切なく、返済できないことも当事者間で認識していたから、「贈与」済である旨主張した(贈与税の除斥期間は徒過している)。これに対し、上記各判決は、①当該借用書記載の金員はすべて被相続人が管理しており、長男の求めに応じて交付されたこと、②次男からの遺言無効確認訴訟の和解において、当該金員を持ち戻し財産から除外して被相続人の遺産の範囲を確認していること、③税務調査の際、長男が当該金員は被相続人から借りたものであり、その一部は返済していると述べていること、等を認定し、当該金員は貸付金として相続財産に含まれる旨判示した(関連事例として、静岡地裁平成17年3月30日判決(税資255号順号9982)、平成25年3月4日裁決(裁決事例集90号222頁)等参照)。
3 本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分の帰属 (1)本件においては、本件相続の際に存在していた本件乙名義有価証券等の総額1億4907万円余のうち何割が相続財産に含まれるかが争われたものである。Xは、当初申告において、その4割が相続財産に含まれるとして申告し、次いで、本件修正申告では45%が含まれるとし、本訴においては、50%が相続財産に含まれると主張し、かつ、残りの50相当額は自己の財産である旨主張するに至った。このような財産の帰属問題については、まず、当該財産の原資が問題になるところである。
この点については、被相続人及び本件共同相続人である甲、乙、X及び丙の各名義の財産の大部分が、甲が営んでいた税理士事務所の収益、同事務所に事業専従者として勤務していたX及び乙の給与、甲の有価証券投資からの収益等からなるものと推測される。また、係争の対象となった本件乙名義有価証券等のほか、乙名義の預貯金等の財産が合計6191万円、X名義の有価証券等の財産が合計1億3378万円あったが、それらは名義どおりの財産として係争の対象となっていない。更に、乙は、その後、本件乙名義有価証券等の全額が相続財産に含まれるとする修正申告を行っており、本件共同相続人間の足並みの乱れがある。
そのような中で、Xは、本訴において、Xが甲の事務所において勤務していた26年4月の間に毎月50万円支払われるべき給与相当額の運用を甲に委ねて本件乙名義有価証券等が形成されたものであるから、甲と乙との間には互いに出資して株式等により利益を得ることを目的とする組合契約(本件組合契約)が成立していたのであるから、本件乙名義有価証券等の2分の1はXの財産である旨主張した。
(2)本判決は、本件の事実関係を詳細に認定した上で、甲一家の収入は、主として、甲の税理士業の収入によって成っていたものであり、その収入を原資として、甲、乙、丙及びXの各名義の預金口座等によって資金運用が行われてその収益を合わせて資産形成が行われたことを認定し、本件乙名義有価証券等の原資についても、主として、甲名義の預貯金口座等から流入しているものと認められ、かつ、乙が甲税理士事務所に勤務した期間(6年)とその給与(年平均406万円)を考慮し、乙自身が本件乙名義有価証券等を相続財産に含めて修正申告していること等に照らし、本件乙名義有価証券等の全額が甲に帰属していたものと認められると判示した。
また、本判決は、Xは、本件乙名義有価証券等の原資も自ら出捐しており、それは甲との共有財産である旨主張するが、Xが甲から受けた給与の額として主張する金額(月50万円)については、50万円に増額されたのは平成15年7月以降であり、それ以前は15万円から順次増額され、平成2年以降40万円に止まっていたこと、X自身本件相続開始時に合計1億3378万円の資産を有しており、その金額さえ自己が受けていた給与の額を上回っていたこと等を考慮すると、Xの上記主張は採用できない旨判示した。
(3)冒頭に述べたように、名義預金、名義株式等をめぐる実務上の問題は、納税者がその真実を知る立場にあり、税務職員は質問検査権を行使して真実を追求することができるのに対し、納税者の税務代理を務める税理士は、真実を調べようとすると納税者に嫌われることにもなり、納税者の申し立てどおりにして、税務調査等において真実が発覚すると専門家責任を問われることにもなる。
本件においては、そのような難しい立場にある税理士が当事者(納税者)の立場で、本件の名義有価証券等(本件乙名義有価証券等)の帰属を争ったものであるので、どのような主張・立証が展開されるかについて興味があったところである。
しかしながら、本件において共同相続人であるXと乙がとった手法・行動には、納得し難い所が多い。そもそも、本件乙名義有価証券等の帰属について、当初申告、本件修正申告、そして、本訴の主張において一貫していないし、更に、修正申告段階において乙自身が本件乙名義有価証券等を自己の財産でなく相続財産であると認めている。本来、名義預金等の帰属を最も知る立場にある相続人間において別々の認識を示して、被告及び裁判官を説得することは不可能であるとも考えられる。いずれにしても、本訴に至るまでの経緯においては、税の専門家である税理士がとった処理には理解の苦しむところがある。
4 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、納税者の税務代理人として、名義預金等の帰属に係る実務処理に悩んでいる税理士が、自己が納税者の立場になって、本件乙名義有価証券等の帰属を法廷で争ったものである。その点では、日頃実務において悩んでいる立場としては興味のあるところであり、本判決を知ることに意義がある。しかしながら、前述したように、本訴に至るまでのX側がとった行動、本訴における主張・立証には問題が多いと言える。そのため、本判決の結論は、出されるべくして出されたとも言える。
(注1)税理上の実務においては、それらの事実関係を正確に把握しようと努めると、納税者の感情を害することにもなりかねず、顧客を失うことにもなる。
(注2)相続税の実地調査(調査割合約20%)を受けたうち、約8割が非違事項(申告漏れ)が指摘されているが、最も多い申告漏れが現預金等であり、多くは、名義預金、名義株式等に係るものである(風岡範哉「相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断」(清文社 平成27年)7頁等参照)。
(注3)その他多くの事例については、前出(注2)の書等を参照。それらのうち、主要な事例について、後述する。
(注4)このような贈与の事実を明確にしておくために、受贈者1人に年111万円贈与し、1万円が非課税枠を超えていることで、贈与税額1000円の申告書を提出している事例も見受けられる。
(注5)このように、実質課税の原則の見地から相続財産の帰属を判断すべきとした裁判例として、東京高裁昭和48年3月12日判決(税資69号634頁)、大阪高裁昭和41年12月26日判決(同45号673頁)、名古屋高裁昭和41年9月30日判決(判例時報468号27頁)、大阪高裁昭和39年12月21日判決(行裁例集15巻12号2331頁)等参照。
(注6)このように、相続財産の帰属について総合判断すべきとした裁判例については、本判決のほか、東京地裁平成30年1月19日判決(平成28年(行ウ)第240号、本誌2018年11月12日号18頁参照)、神戸地裁平成11年11月29日判決(税資245号497頁)等参照。
(注7)詳細については、本誌2018年11月12日号18頁等参照。
相続税における名義有価証券等の帰属
東京地裁平成30年4月24日判決(平成28年(行ウ)第238号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣一、事実
(1)X(原告)は、父甲が平成22年11月11日死亡したことにより、母乙(甲の妻)及び弟丙(以下X、乙及び丙を「本件共同相続人」という。)とともに甲を相続した(以下「本件相続」という。)。Xは、平成23年9月12日、乙及び丙とともに、本件相続に係る相続税について、課税価格を3382万円余とする申告を行い(以下「本件当初申告」という。)、次いで平成26年2月7日、課税価格を6413万円余とする修正申告(以下「本件修正申告」という。)をした。
これに対し、処分行政庁は、平成26年7月8日、課税価格を1億1596万円余とする更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の額を182万円余とする賦課決定(以下本件更正と併せて「本件更正等」という。)をした。Xは、本件更正等を不服として、異議申立て及び審査請求を経て(異議決定において課税価格は9246万円余に減額されている。)、平成28年6月2日、国(被告)に対し、課税価格8284万円余を上回る部分の本件更正等の取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)本訴において、問題となったのは、乙名義のN証券会社の本店口座及びY支店口座で管理されている有価証券等総額1億4907万円余(以下「本件乙名義有価証券等」という。)(そのほか、N証券会社に存する甲名義及びX名義の各口座と併せて「本件各証券口座」という。)の帰属である。この帰属につき、Xは、当初申告において、その40%相当額(5949万円余)が本件相続財産に含まれるとし、本件修正申告においてはそれが45%相当額(6946万円余)であるとした。これに対し、処分行政庁は、本件乙名義有価証券等の全額が本件相続財産に含まれるとして本件更正等を行い、国も、本訴においてその旨主張している。他方、Xは、本訴において、その50%相当額7453万円余(以下「本件係争部分」という。)がXに帰属し、本件相続財産に含まれない旨主張している。
(3)甲は、昭和21年頃から税務職員として勤務した後、昭和55年以降税理士業を営んでいた。Xは、昭和60年に税理士登録をした後、税理士として甲の事務所に勤務していた。乙は、昭和35年に結婚し、甲が税理士事務所を開設してから6年程度、事務員として税理士業務を補助していた。また、甲は、処分行政庁に対し、X及び乙をそれぞれ事業専従者とする青色事業専従者給与に関する届出書を提出していた。なお、本件相続開始時における乙名義の資産は、本件乙名義有価証券等を除き、預貯金等が約1521万円、生命保険金等が約4670万円、合計6191万円余であり、X名義の資産は、預貯金が約300万円、有価証券約5652万円及び生命保険金等が約7425万円の合計約1億3378万円であった。
他方、乙は、本件乙名義有価証券等の全部が本件相続財産に含まれるものとして相続税の額を計算した平成25年12月3日付け及び同26年7月8日付け各修正申告書を提出した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分が、「相続により取得した財産」、すなわち本件相続財産に含まれるか否かであり、とりわけ、本件係争部分が、甲のXに対する給与を原資として形成されたものか否かにある。
2 国の主張 (1)被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであるか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものと解されている。
(2)本件各証券口座の管理及び運用については、甲が自ら行っていたほか、乙が甲の指示の下、あるいは同人と相談した上で行っており、Xは関与していなかったから、その実質的な主体は、乙が行っていた時期も含めて、一貫して甲であったと認められる。また、本件相続開始日前5年を超える期間の金員の動きに関する各事情を考慮すれば、乙各証券口座における有価証券の過半は、甲の資金を原資として構成されているものと認められる。
(3)前記で述べた管理及び運用の点、並びに原資の点に加え、①乙各証券口座の名義人は乙であるものの、乙と甲は夫婦であり、家族の中でも夫婦間においては、配偶者の名義で自己の財産を保有、管理することはまれではないこと、②甲、乙、X及び丙の各名義の口座は、必ずしも原資の出捐者の負担部分に応じた区分管理がされていたとはいえないこと、③乙が、平成25年12月3日及び平成26年7月8日、処分行政庁に対して、乙各証券口座における有価証券が甲に帰属するものであることを前提とした相続税の修正申告書を提出していることを総合勘案すれば、本件乙名義有価証券等はXに帰属するもの、すなわち、本件相続財産に含まれると優に推認することができる。
(4)乙は本件相続開始時において6191万円余の資産(本件乙名義有価証券等を除く。)を有しているところ、上記の各事情に鑑みれば、この資産の金額は、推定される乙が甲の事業に従事した期間である30年(実際は6年)の間に事業専従者として得ていた収入に照らし相応なものであるといえ、乙が、本件相続開始日当時において、上記金額を超えて1億4907万円余もの本件乙名義有価証券等を有することができたとは認められない。
3 Xの主張 (1)本件各証券口座における資産の購入原資には、甲からXに支払われるはずの給与が含まれている。甲は、昭和21年頃から税務署で勤務した後、昭和55年に退官して税理士登録し、その後は他界するまで税理士として稼働していた。他方、Xは、昭和60年に税理士登録し、甲の事務所で勤務していた。甲は、上記事務所において他の事務職員を雇用したことはなく、20年以上、Xと二人三脚で上記事務所の切り盛りをしていた。Xは、税務申告上、甲から賃金(青色事業専従者給与)が支払われる形となっていたが、実際には一切手にしておらず、甲の証券取引等の原資となることも含めて、その全額の運用を甲に委ねていた。その額は、平均して毎月50万円程度であり、これをXが甲の下で稼働していた26年4か月に換算すると、合計1億5800万円となる。
(2)上記のとおり、Xは、甲に対し、本件Xに支払われるべき青色事業専従者給与の運用を委ね、その寄与により本件乙名義有価証券等が形成されたのであって、これを法的に評価すると、Xと甲との間には、互いに出資して株式等により利益を得ることを目的とする組合契約(以下「本件組合契約」という。)が成立しており、本件乙名義有価証券等は本件組合契約に基づき形成された財産であると評価できる。そして、組合業務により造成された財産は、その一部の所有名義が組合員のうち1人の名義となっていても、実質的に各組合員が組合業務を目的として一種の組合契約を締結し、その事業執行の結果得られた財産とみられるから、組合員の一部が死亡し、他に組合員がいる場合には、組合の解散に準じその出資割合に応じて残余財産を精算し、その精算の結果、他の組合員の取得する持分(他の組合員の固有持分)に相当する部分は、相続財産から除外し、死亡した組合員の取得分のみを相続財産として取り扱うべきであるし、仮に、本件において、組合の解散又は解散に準じる事実が認められないとしても、組合員が脱退により払戻しを受けられる組合財産は、脱退時における当該組合員の組合財産に対する持分割合に従って決せられるのであり、これを超えて組合財産の払戻しを受けることはできないのであるから(民法681条1項)、他の組合員の固有持分に相当する部分は相続財産から除外し、死亡した組合員の持分に相当する部分のみを相続財産として取り扱うべきものと解するのが相当である。したがって、本件乙名義有価証券等については、少なくともその価額の50%に相当する部分(本件係争部分)についてはXに帰属する。
(3)国が主張する資産のうち、X名義の預貯金300万円余は、甲からXに対して支払われるはずの賃金とは関係がなく、Xが税理士として独自に稼働して形成した資産である。また、X名義の生命保険等は、甲が、その可処分所得の中から、子であり共同経営者でもあるXの掛金を負担したものであり、甲からXに支払われるはずであった給与を原資としたものではない。それにもかかわらず、国は、本件乙名義有価証券等が本件相続財産に含まれるか否かを検討するに際し、本件相続開始時のXの保有財産にこれらの資産が含まれていることを看過しており、失当である。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)本件においては、本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分が本件相続財産に含まれるか否かが争われている。相続税の課税物件である財産の法律上の帰属については、当該財産の名義によるのみでなく、その実質に即した認定判断をすべきものであり、とりわけ、親族間においては、例えば夫が妻や子の名義を借りて自らの資産を原資として有価証券取引に係る口座を開設し、当該口座で取引を行うこともまれではないといえることに照らすと、上記の認定判断に当たっては、当該財産の名義のほか、当該財産の取得(その購入の原資となった資産の取得を含む。以下同じ)が誰の出捐によるものか、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等の各事情を総合考慮して認定判断することが相当である。
そして、本件においては、本件係争部分につき本件相続財産に含まれるか否かが争われているのであるから、本件乙名義有価証券等の取得は甲の出捐によるものか、それとも、Xの出捐によるものかが特に問題となる。また、これらの出捐に関する問題を検討する前提として、甲及びその家族の資産がどのように管理されてきたのかについても検討する必要がある。
(2)そこで、まず、甲及びその家族の資産の管理状況等につき検討すると、前記認定事実によれば、甲は、税務署を退官した後に税理士事務所を開業し、これによる事業収入を得る一方、妻である乙及び子であるXに対しては青色事業専従者給与として給与を支払ったとして、当該給与相当額を自らの収入から控除して所得税の申告をしていた。もっとも、税理士であるXが昭和60年頃から甲とともに税理士の業務を行っていたのに対し、乙が甲の事務所において事務員の業務を行っていたのは、昭和55年頃から6年間程度にすぎず、それ以降においては給与の対象となるような労務提供の実態はなかった上、乙の収入は、上記の青色事業専従者給与を除けば、年金等に限られていた。また、甲の子である丙については、会社員として稼働し、結婚後独立して生活していたため、経済的にも甲から独立していた。
このように、経済的に独立していた丙の関係を除けば、甲の一家の収入は、主として、同人の事務所で営まれていた税理士業の収入により成って
いたものであり、甲はその収入により得られた資産の管理及び運用を、Xへの青色事業専従者給与として支払われた分も含めて、自ら又はその意を受けた乙を通じて行っていたものと認められる。
そして、甲は、上記のような一家の資産の管理及び運用のために、独立していた丙の名義をも利用して、甲、乙、丙及びXの各名義で預金口座(本件各預金口座)を開設するとともに、これらの名義で有価証券取引の口座(本件各証券口座のほか、丙の名義の口座を含む。)を開設して、これらの預金口座相互間及び預金口座と証券口座との間で頻繁かつ複雑な資金のやり取りをしながら、証券取引等を通じた資産の形成を行ってきたものである。本件乙名義有価証券等の取引が行われた乙各証券口座もまた、このような中で開設されたものであり、甲による一家の資産の管理及び運用のために乙の名義を利用したものであった。
(3)以上を前提として、本件乙名義有価証券等の取得に係る出捐につき、甲がその全額を出捐したか否かについて検討する。
ア 前記認定事実によれば、乙各証券口座には、合計9984万円余の資金流入があり、これが本件乙名義有価証券等の購入の原資となったと認められるところ、上記9984万円余の資金流入は、主として、①乙名義預金口座から入金された8571万円余及び②甲名義預金口座から入金された564万円によるものと認められる。そして、上記①の乙名義預金口座への入金として、③甲名義預金口座からの5679万円余、④丙名義預金口座からの1897万円余、⑤乙名義の年金及び保険金の収入3183万円余並びに⑥乙名義の有価証券に係る受取配当金707万円余の各入金があったことが認められる。
イ 上記のとおり、本件乙名義有価証券等の購入の原資のうち、甲名義預金口座から乙名義の口座へ入金されたものは5679万円余及び564万円の合計6243万円余であるところ、甲名義預金口座の預貯金については甲の資産であると推認される。また、丙名義預金口座から入金された1897万円余についても、丙自身が同口座は甲が丙名義で有価証券取引を行うためのものであると認識していたことに照らせば、その実質は、甲の資産であったものと推認することができる。
さらに、乙名義の年金及び保険金の収入3183万円余及び乙名義の有価証券に係る受取配当金707万円余についても、このうち年金収入を除く部分が乙の固有の資産であったといえるかには疑問があり、少なくともその相当部分は甲の資産により形成されたものと推認することができる。すなわち、乙に係る青色事業専従者給与の額の推移や、乙の所得税の確定申告における平成15年分から平成22年分までの収入金額の1年当たりの平均額が406万円であったこと、これらの給与以外には乙には年金等の収入しかなかったこと、乙名義預金口座からはN証券本店X口座等へ2000万円以上の資金が流出しているほか、約927万円が保険料の支払に充てられていることなどに照らせば、これらの収入による資産形成にも限界があるといわざるを得ず、乙がXとの訴訟において乙の母親から3700万円を相続した旨を供述していることを踏まえても、本件相続開始時における乙名義の資産(約6191万円)のほかに本件乙名義有価証券等の購入の原資となった資産を形成し得たといえるかには疑問がある。このことに加え、そもそも乙が甲の事務所において事務員の業務を行っていたのは、昭和55年頃から6年間程度にすぎず、それ以降においては給与の対象となるような労務提供の実態はなかったことに照らすと、確定申告どおりの給与が乙に支払われていたのかにも疑問を抱かざるを得ない。なお、乙自身、本件相続に係る相続税について提出した修正申告書において、本件乙名義有価証券等の全部が本件相続財産に含まれるものとして相続税の額を計算して申告をしており、少なくとも上記申告の時点では本件乙名義有価証券等の全部又は一部が自己に帰属する財産であるとの主張をしていないことからも、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった資産が甲に帰属するものであったことが裏付けられる。
ウ 以上によれば、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった9984万円余については、その大半を占める8140万円余が甲の出捐によるものと推認できること、そのほか、乙名義預金口座へ入金された保険金・配当金等収入3891万円余についても、その相当部分が甲の資産により形成されたものと推認できることに照らせば、上記9984万円の全部につき甲に帰属するものであったと推認することができる。
エ これに対し、Xは、甲の平成17年分から平成22年分までの所得の金額は約3307万円であるところ、甲は、この所得の中から、所得税や家族の生活費等、自宅及び事務所のローン等を支払っている上に、本件相続開始時に約3000万円の預貯金等を有していたのであるから、このほかに、本件乙名義有価証券等の全部につきその購入の原資となるような資産を有していたということは困難であり、甲以外の者からの資金流入がなければ合理的な説明が困難である旨を主張する。
しかしながら、甲は、昭和21年頃から昭和55年まで税務職員として勤務し、その後平成22年までの長年にわたり税理士業を営んでいたものであり、その間の収入により相当の貯蓄があったと考えられるほか、Xの陳述によればXが税理士登録をした昭和60年よりも前から株式等の取引をしていたことがうかがわれ、その取引により得られた利益も相当にあったものと考えられる。また、甲は、平成12年から平成13年にかけては甲、乙及びXの各名義でN証券Y支店に口座を開設し、平成18年にはN証券本店にも上記各名義の口座を開設し、上記3名のほか丙の名義を含む預金口座相互間における頻繁かつ複雑な資金移動を繰り返しながら株式の取引を含む資金運用を活発に行っていたのであるから、これらの証券口座(本件各証券口座)を開設した時点においては、長年にわたる管理及び運用の成果として相当多額の資産を形成していたと推認される。また、実際に、例えば甲名義のM銀行K支店の普通預金口座には、甲に係る株式の売却代金(平成18年11月28日の199万円余、平成19年7月9日の123万円余)や保険金収入(平成17年4月28日の13万円余、平成19年11月26日の624万円余)など、株式取引や保険加入等による資金の管理及び運用の結果として生じた利益が振り込まれていたことが認められる。
これらの事実に照らすと、甲は、Xが主張する種々の支出や本件相続開始時における預貯金等の額を踏まえても、なお本件乙名義有価証券等の全部について購入の原資を拠出することのできる十分な資力を有していたものと認められるから、Xの上記主張は採用できない。
(4)次に、本件乙名義有価証券等の取得につき、Xが本件係争部分に係る出捐をした可能性の有無について検討する。
ア 前記(3)のとおり、本件乙名義有価証券等の購入の原資となった乙各証券口座への資金流入について、X名義預金口座からの入金は含まれていない(むしろ、X名義の口座から乙名義の口座への入金が合計929万円余であるのに対して、乙名義の口座からX名義の口座への入金は合計2885万円余であり、後者の方が上回っている。)。
イ Xは、甲から受けた給与につきその全額の運用を甲に委ねており、甲はこれを原資として本件各証券口座で管理されている株式等を購入したものであると主張する。
しかしながら、そもそも、Xが甲から受けた給与の額として主張する金額(平均月50万円程度、26年4か月による勤務の合計で1億5800万円)については、給与額が月50万円に増額されたのは平成15年7月以降であり、それ以前においては月15万円から順次増額され、平成2年1月から平成15年6月までは月40万円にとどまっていたことに照らせば、Xがその主張の金額の給与を受けていたとは認め難い。
また、Xは、本件相続開始時において合計約1億3378万円の資産を有していたものであり、これらの総計はXが受けていた給与の額を大きく上回るものといえる(Xが主張する給与の額と比べても、若干上回る。)。
(5)以上のとおり、甲は、自らの事務所で営んでいた税理士業の収入につき、甲、乙、丙及びXの各名義を利用して資産の管理及び運用を行ってきたものであり、乙各証券口座もその中で開設されたものであるところ、本件乙名義有価証券等の購入の原資として、乙各証券口座又は乙名義預貯金口座に、甲名義預金口座及び甲の資産と推認される丙名義預金口座からその大半を占める資金が流入しているほか、乙名義の保険金や配当金の収入についても、その相当部分が甲の資産により形成されたものと推認できることから、上記購入の原資となった9984万円余についてはその全部が甲に帰属するものであったと推認することができるものである。他方、X名義預金口座からは、本件乙名義有価証券等の購入の原資となるような資金流入は認められず、また、Xが甲から受けた給与及びその運用により得られた収益については、既にX名義の資産として形成されているものと認められ、このほかに、本件乙名義有価証券等の購入の原資となるような資産をXが有していたとは認め難い。これらに照らせば、本件乙名義有価証券等は、その全部が甲に帰属する(本件相続財産に含まれる)ものと認めるのが相当である。
四、解説
はじめに
相続税の申告、課税実務においては、相続開始時において、被相続人名義外の財産が当該被相続人の財産として認定できるのか、あるいは名義人となっている当該相続人に帰属していたのかがよく問題になることがある。この場合、当該財産の帰属等については、被相続人が存在していない以上、相続人が一番良く知悉していることであろうから、申告納税の建前上、当該相続人の判断で当該相続税の申告をすれば足りるはずである。また、当該申告後、課税上問題があれば、税務職員は、質問検査権の行使(税務調査)によって、それらの事実関係を調査し、当該事実に基づいて課税処分をすれば足りることになる。
問題は、税務代理人となる税理士の方である。税理士は、多くの相続税申告について代理人を務めているが、代理人となった時点では、当該相続に係る各財産の帰属関係について知る由もない。しかし、税理士は、「納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図る」(税理士法1)ことを使命としているため、被相続人に関わる各財産の帰属をできるだけ明確にした上で、当該相続税の代理申告に当たらなければならないことになる。そうは言っても、税理士は、税務職員のような質問検査権の行使が認められているわけではなく、かつ、納税者からの依頼を受けて申告代理をする立場であるが故に、納税者のプライバシーに関わる事実関係を厳しく追求するわけにも行かないので(注1)、その調査にも自ずから限界がある。そのため、税理士自身も、当該事実関係に疑問を感じながらも申告代理を行わざるを得ない場合も考えられる。
本件においては、その税理士(X)が、自己が相続人となって、父親である被相続人甲の妻乙(Xの母)の名義となっていた本件乙名義有価証券等が甲に帰属するもの(本件の相続財産)か否かが争われたものである。しかも、Xは、甲が経営していた税理士事務所の勤務税理士であったというのであるから、X自身が家族内の財産の帰属関係を最も知悉していたものとも考えられるので、それを訴訟まで持ち込んで争うからには、その主張を裏付ける余程の事情があったものかも知れないし、あるいは税の専門家としての判断を誤ったものかも知れない。
そこで、本稿においては、相続税における被相続人名義以外で家族等の名義となっている預貯金、株式、その他の有価証券等の帰属問題について、従前の一般論を検討した上で、本件乙名義有価証券等の帰属について検討することとする。
1 名義預貯金、名義株式等の帰属 (1)前述したように、相続税における相続財産については、相続開始時において、被相続人の名義ではなく、当該家族名義である財産が当該被相続人に帰属するものとして相続財産に該当するか否かがよく問題となる。その中でも、預貯金、株式、その他の有価証券等に係るものが特に問題となり、税務調査時又課税処分の段階において、「名義預金」等としてその帰属が争われることが多い(注2)。そのような事例の形態としては、次のようなものが挙げられる(注3)。
① 相続開始前後の預貯金の引出し等 相続開始直前においては、被相続人になる者の財産管理能力が低下(無力化)することもあって、相続人となる者が被相続人になる者の預貯金を引き出して利用することはままあることである。また、相続開始後においても、相続人が1人であるように遺産分割の協議の必要がなければ、当該相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して自己名義の預貯金等にすることも可能である。このような場合に、当該引出し金の行方と当該預貯金等について相続財産に該当するか否か等が問題となる。
② 名義預金 相続税において被相続人の財産であったか否かが最も問題となるのが、いわゆる名義預金である。名義預金とは、当該預金の名義と真の所有者(帰属)が異なることを意味している。この名義預金については、2種類に区分できる。一つは、被相続人が、生前、自己の現預金を家族名義で分散しておくもので、当該名義変更等について当事者間で贈与の認識もない場合が多い。また、預金通帳及び印鑑の管理も当該被相続人が独自に行っている場合が多い。このようなことは、かつて、少額貯金の非課税制度が採用されていた頃は、よく行われていたことでもある。
二つは、被相続人が、子や孫に対する贈与の意思を持って、子や孫名義の預金をすることである。この場合、当該家族間で贈与(契約)が成立しているか否かが問題となる。その贈与の根拠として、贈与契約書の有無、贈与税の申告の有無(注4)、通帳及び印鑑の管理状態が問題となるが、贈与契約それ自体は口頭でも可能であるし、非課税範囲の贈与であれば申告も必要ではないので、それらを決定的な根拠にすることも難しいと言える。
③ 名義株式 多くの同族会社では、経営と資本が一体となっており、経営者による株式の発行、割当ても自由であり、それに必要な資金も当該経営者によって支弁されることがある。よって、経営者の家族が無償でかつ認識のないまま株主になる機会も多く、名義預金と同じような問題が生じる。また、本件のように、家族名義で株式取引が行われることがあり、相続時に当該家族名義の株式等が存することになる。
④ 夫婦間の贈与と名義預金等 専業主婦が夫の給与で生活費をやりくりし、余剰金を妻名義の預金にしている場合に、当該預金の所有者が問題となる。この場合、夫から「生活費のやりくりは甲斐性だから余剰金は贈与する」旨の約束(贈与)があった場合に、その法的効力も問題となる。
また、本件のように、夫の事業に妻が従事して専従者給与を受けている場合に、当該給与によって預金や有価証券が取得できたか否かも問題となる。
⑤ 親族間の金銭貸借 親子間等の金銭貸借については、当初は契約書等が締結され、金銭等の移転があった後、契約どおりに返済されたか否か、それが仮装であったものか否か、相続時の残高が確認されているか否か等問題となり易いことが多い。
(2)以上のように、相続開始時においては、多くの相続税事例において、被相続人名義以外の預貯金、有価証券、不動産等の真の所有者が誰であるのか(財産の帰属)が問題となる。この場合、当該財産の真の所有者(帰属)をどのようにして判断するかについて、名古屋地裁平成10年2月6日判決(税資230号384頁)は、実質課税の原則の見地から(注5)、次のように判示している。
「相続税は、相続財産を相続又は遺贈により取得した財産としており、何を相続税の課税財産とみるかは、原則として、民法等の一般私法の定めるところに基づいて、私法上の法律関係を前提として判断されるものである。しかしながら、相続税が財産の無償取得により生じる担税力の増加を課税の根拠としていることからすると、相続財産が何であるかを判断する際には、単に形式的な法律的観点ないし私法上の法律関係の如何にとらわれることなく、相続課税上の妥当性、相当性という観点、言い換えれば経済的実質という観点からもなされるべきである。」
また、最近の裁判例においては、近年、学説等において実質課税の原則が制限的に通用すべきであると解されるようになっていることもあって、種々の事実関係を総合考慮して判断すべきこととしているが、例えば、札幌地裁平成26年7月30日判決(平成25年(行ウ)第14号)は、次のように判示している。本判決も、このような考え方に基づいている(注6)。
「ある財産が相続人以外の者の名義になっていたとしても、当該財産が相続開始時において被相続人に属していたものと認められるものであれば、当該財産は、相続税の課税対象となる相続財産となる。そして、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったといえるか否かは、当該財産又はその取得原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産を管理及び運用する者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である。」
2 参考となる判決・裁決事例 前記1で述べたように、相続税の課税においては、名義預金、名義株式等の帰属(被相続人のものか、当該名義人のものか)が問題になるが、その主要の形態は、前記1の①から⑤のとおりである。そこで、それらの形態別に、参考となる事例を紹介することとする。
① 相続開始前後の預貯金の引出し等-東京地裁平成30年1月19日判決(平成28(行ウ)第240号)(注7)。 本事案では、相続人(共同相続人なし)が、相続開始前に被相続人(相続人の母)の名義の預貯金合計5180万円を引き出し、そのうち300万円を被相続人の医療費、生活費等に費消したものの、残額のうち、1070万円を自己名義の預金とし、3810万円を手許に残しておいた。これについて、上記の相続人名義の預金と手許現金が相続財産に含まれるとし、かつ、当該申告につき重加算税を課するとする課税処分が行われ、当該課税処分の違法性が争われた。原告は、当該相続の4年前にあった父の相続に係る遺産が未分割であったため、上記母名義の預貯金には父のものであったものも含まれていて母と共有であった等を主張したが、当該判決は、上記主張を認めず、原告の一連の行為が国税通則法68条に定める「隠ぺい・仮装」に当たる旨判示した。
② 名義預金(孫への積立預金)-平成3年1月18日裁決(裁決事例集41号271頁) 本事案では、被相続人の孫名義の定期貯金200万円が相続財産に含まれるか否かが問題となった。相続人である審査請求人は、当該定期貯金は自分が長女(被相続人の孫)のために毎月1~2万円積み立て、一定額になったものを定期貯金としたものである旨主張した。これに対し、本裁決は、①当該定期貯金の届出住所、届出印鑑及び申込書の筆跡が被相続人名義の他の定期貯金のものと同一であること、②当該定期貯金の利息と被相続人名義の定期貯金の利息とを合わせて別段預金としているが、それらに利用されている印鑑が同一であること、③被相続人には、当該定期貯金を設定した頃土地代金の入金があったこと等からすると、当該定期貯金は、被相続人が非課税貯蓄に着目して孫の名義を使用したものと推認できるとして、当該定期貯金を相続財産に含めた課税処分を適法とした。
③ 名義株式(相続人名義の株式)-東京地裁平成18年9月22日判決(税資256号順号10512) 本事案では、相続人ら(妻、子ら5名)の名義となっていた19銘柄約2億円の株式が相続財産に含まれるか否かが争われた。相続人らは、当該株式は被相続人から生前贈与により取得したものである旨主張した。これに対し、本判決は、当該株式は、被相続人が原資を負担して取得していて、被相続人の住所地が株主の登録住所となっており、被相続人が取得後もこれを一括管理していたものであり、株式の配当についても被相続人が自ら取得していたものと認められるから、被相続人に帰属するものと認められる旨判示した。しかし、本判決は、当該株式の1銘柄6750株のうち3500株については、その登録住所・登録印について、昭和52年1月1日時点では被相続人の住所が登録されていたものの、平成元年4月18日には、子の自宅を登録住所とするものと認められ、登録印もその他の登録印と異なっているなどから、相続財産から除外すべきものとした。
④ 名義預金(夫婦間の生前贈与)-平成19年4月11日裁決(TAINS-F0-3-312) 本事案では、被相続人の妻名義となっている預貯金等合計約6300万円が相続財産となるか否か(課税処分では、被相続人の財産になる旨認定)が問題となった。審査請求の審理において、当該妻は、①専業主婦であるが、結婚後、夫から、月54万円、盆暮に50万円から100万円を生活費等として受け取り、「渡したお金の残りはお前にやる、好きにしてよい」と云われたこと、②①の残金は妻名義の預金等として積み立て、その通帳等と印鑑は自分の衣装だんすの中に保管していたこと等を主張していた。しかし、裁決は、当該預貯金については、妻名義となっているものの、その原資は被相続人が拠出したものであって、被相続人か妻への生活費の余剰金の贈与を認めるに足りる証拠も見当たらないことから、被相続人に帰属すると認めるのが相当である旨判断した(同旨東京地裁平成20年10月17日判決(平成19年(行ウ)第19号)、東京高裁平成21年4月16日判決(平成20年(行コ)第386号)等参照)。
⑤ 親族間の金銭貸借(貸付金の存否)-宮崎地裁平成23年9月9日判決(平成22年(行ウ)第3号)、福岡高裁平成24年2月15日判決(平成23年(行コ)第9号) 本事案では、被相続人が、生前、相続人である長男に約3779万円の金員を交付し、その長男が計15枚の借用書を差し入れている場合に、当該金員が贈与済であるのか、貸付金として相続財産に含まれるかが争われた。その長男は、当該金員の交付には利息、返済期限が一切なく、返済できないことも当事者間で認識していたから、「贈与」済である旨主張した(贈与税の除斥期間は徒過している)。これに対し、上記各判決は、①当該借用書記載の金員はすべて被相続人が管理しており、長男の求めに応じて交付されたこと、②次男からの遺言無効確認訴訟の和解において、当該金員を持ち戻し財産から除外して被相続人の遺産の範囲を確認していること、③税務調査の際、長男が当該金員は被相続人から借りたものであり、その一部は返済していると述べていること、等を認定し、当該金員は貸付金として相続財産に含まれる旨判示した(関連事例として、静岡地裁平成17年3月30日判決(税資255号順号9982)、平成25年3月4日裁決(裁決事例集90号222頁)等参照)。
3 本件乙名義有価証券等のうち本件係争部分の帰属 (1)本件においては、本件相続の際に存在していた本件乙名義有価証券等の総額1億4907万円余のうち何割が相続財産に含まれるかが争われたものである。Xは、当初申告において、その4割が相続財産に含まれるとして申告し、次いで、本件修正申告では45%が含まれるとし、本訴においては、50%が相続財産に含まれると主張し、かつ、残りの50相当額は自己の財産である旨主張するに至った。このような財産の帰属問題については、まず、当該財産の原資が問題になるところである。
この点については、被相続人及び本件共同相続人である甲、乙、X及び丙の各名義の財産の大部分が、甲が営んでいた税理士事務所の収益、同事務所に事業専従者として勤務していたX及び乙の給与、甲の有価証券投資からの収益等からなるものと推測される。また、係争の対象となった本件乙名義有価証券等のほか、乙名義の預貯金等の財産が合計6191万円、X名義の有価証券等の財産が合計1億3378万円あったが、それらは名義どおりの財産として係争の対象となっていない。更に、乙は、その後、本件乙名義有価証券等の全額が相続財産に含まれるとする修正申告を行っており、本件共同相続人間の足並みの乱れがある。
そのような中で、Xは、本訴において、Xが甲の事務所において勤務していた26年4月の間に毎月50万円支払われるべき給与相当額の運用を甲に委ねて本件乙名義有価証券等が形成されたものであるから、甲と乙との間には互いに出資して株式等により利益を得ることを目的とする組合契約(本件組合契約)が成立していたのであるから、本件乙名義有価証券等の2分の1はXの財産である旨主張した。
(2)本判決は、本件の事実関係を詳細に認定した上で、甲一家の収入は、主として、甲の税理士業の収入によって成っていたものであり、その収入を原資として、甲、乙、丙及びXの各名義の預金口座等によって資金運用が行われてその収益を合わせて資産形成が行われたことを認定し、本件乙名義有価証券等の原資についても、主として、甲名義の預貯金口座等から流入しているものと認められ、かつ、乙が甲税理士事務所に勤務した期間(6年)とその給与(年平均406万円)を考慮し、乙自身が本件乙名義有価証券等を相続財産に含めて修正申告していること等に照らし、本件乙名義有価証券等の全額が甲に帰属していたものと認められると判示した。
また、本判決は、Xは、本件乙名義有価証券等の原資も自ら出捐しており、それは甲との共有財産である旨主張するが、Xが甲から受けた給与の額として主張する金額(月50万円)については、50万円に増額されたのは平成15年7月以降であり、それ以前は15万円から順次増額され、平成2年以降40万円に止まっていたこと、X自身本件相続開始時に合計1億3378万円の資産を有しており、その金額さえ自己が受けていた給与の額を上回っていたこと等を考慮すると、Xの上記主張は採用できない旨判示した。
(3)冒頭に述べたように、名義預金、名義株式等をめぐる実務上の問題は、納税者がその真実を知る立場にあり、税務職員は質問検査権を行使して真実を追求することができるのに対し、納税者の税務代理を務める税理士は、真実を調べようとすると納税者に嫌われることにもなり、納税者の申し立てどおりにして、税務調査等において真実が発覚すると専門家責任を問われることにもなる。
本件においては、そのような難しい立場にある税理士が当事者(納税者)の立場で、本件の名義有価証券等(本件乙名義有価証券等)の帰属を争ったものであるので、どのような主張・立証が展開されるかについて興味があったところである。
しかしながら、本件において共同相続人であるXと乙がとった手法・行動には、納得し難い所が多い。そもそも、本件乙名義有価証券等の帰属について、当初申告、本件修正申告、そして、本訴の主張において一貫していないし、更に、修正申告段階において乙自身が本件乙名義有価証券等を自己の財産でなく相続財産であると認めている。本来、名義預金等の帰属を最も知る立場にある相続人間において別々の認識を示して、被告及び裁判官を説得することは不可能であるとも考えられる。いずれにしても、本訴に至るまでの経緯においては、税の専門家である税理士がとった処理には理解の苦しむところがある。
4 本判決の意義と問題点 以上のように、本件は、納税者の税務代理人として、名義預金等の帰属に係る実務処理に悩んでいる税理士が、自己が納税者の立場になって、本件乙名義有価証券等の帰属を法廷で争ったものである。その点では、日頃実務において悩んでいる立場としては興味のあるところであり、本判決を知ることに意義がある。しかしながら、前述したように、本訴に至るまでのX側がとった行動、本訴における主張・立証には問題が多いと言える。そのため、本判決の結論は、出されるべくして出されたとも言える。
(注1)税理上の実務においては、それらの事実関係を正確に把握しようと努めると、納税者の感情を害することにもなりかねず、顧客を失うことにもなる。
(注2)相続税の実地調査(調査割合約20%)を受けたうち、約8割が非違事項(申告漏れ)が指摘されているが、最も多い申告漏れが現預金等であり、多くは、名義預金、名義株式等に係るものである(風岡範哉「相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断」(清文社 平成27年)7頁等参照)。
(注3)その他多くの事例については、前出(注2)の書等を参照。それらのうち、主要な事例について、後述する。
(注4)このような贈与の事実を明確にしておくために、受贈者1人に年111万円贈与し、1万円が非課税枠を超えていることで、贈与税額1000円の申告書を提出している事例も見受けられる。
(注5)このように、実質課税の原則の見地から相続財産の帰属を判断すべきとした裁判例として、東京高裁昭和48年3月12日判決(税資69号634頁)、大阪高裁昭和41年12月26日判決(同45号673頁)、名古屋高裁昭和41年9月30日判決(判例時報468号27頁)、大阪高裁昭和39年12月21日判決(行裁例集15巻12号2331頁)等参照。
(注6)このように、相続財産の帰属について総合判断すべきとした裁判例については、本判決のほか、東京地裁平成30年1月19日判決(平成28年(行ウ)第240号、本誌2018年11月12日号18頁参照)、神戸地裁平成11年11月29日判決(税資245号497頁)等参照。
(注7)詳細については、本誌2018年11月12日号18頁等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.