解説記事2019年04月08日 【特別解説】 主要な米国企業における会計監査人の在任期間に関する記述(2019年4月8日号・№782)
特別解説
主要な米国企業における会計監査人の在任期間に関する記述
はじめに
これまで長らく「専門家の領域で、外部から見るとブラックボックス」と言われていた監査の領域にも、ここ数年で、世界中で透明化への大波が押し寄せている。欧州のEU諸国では、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載に加えて監査法人の強制ローテーション(一定期間経過後の入札手続実施の義務付け等)がすでに制度化されており、我が国とともに、監査法人の強制ローテーション制度の導入を見送った米国においても、米国公開企業会計監視委員会(PCAOB)が、2017年6月に監査基準(AS)3101「無限定適正意見の監査報告書」及び関連する他の監査基準の適合修正を承認し、公表した。その中では、EU諸国でのKAMと類似した「監査上の重要な事項(Critical Audit Matters(CAM))」や監査人の独立性に関する記述、監査意見を監査報告書の最初の区分に記載すること、及び監査人の在任期間に関する記述などが盛り込まれている。これらのうち、本稿では、主要な米国企業に対して発行される監査報告書に記載されている、会計監査人(監査法人)の在任期間に関する記述を取り上げて、主要な米国企業に監査業務を提供している監査法人の在任期間について、調査分析を行うこととしたい。
監査法人の強制ローテーション制度に対する米国の対応
監査法人のローテーション制度に関する調査報告(金融庁 2017年7月20日)によると、米国においては、現在、監査法人の強制ローテーション制度の導入は議題として取り上げられていないが、監査法人の独立性確保は重要な課題の1つとされている。
また、PCAOBが現在取り組んでいる会計監査に関する基準設定等の議題としては、会計上の見積り、公正価値評価など、会計監査において特に職業的専門家としての懐疑心の発揮が重要となる領域に関するものが増加しており、そのためにも独立性は重要な課題であるとされている。最近基準化されたものには、会計監査の透明化を促進するもの(業務執行社員の氏名の開示、重要な他の監査人(重要な子会社を担当している親会社監査人以外の監査人等)の情報の開示等)などがあり、情報開示は監査人の独立性を評価する上で有用であるとされている。
また、監査法人を監視する責任を有する監査委員会が、適切に会計監査の品質を評価し、監査法人を選任できるようにするため、AQI(Audit Quality Indicators:監査品質の指標)の導入について現在検討が行われている。AQIを実施しその内容を会計監査のステークホルダーに開示することは、監査法人の独立性の確保や会計監査の品質向上を図ることにつながると考えられている。なお、PCAOBは2017年6月に、監査報告書の一項目として監査法人の長期間の関与(Audit firm tenure)について記載することを含む監査基準の改訂を公表した(詳細については次節を参照)。
なお、米国では、「監査法人そのもの」の強制ローテーション制度は導入されていないものの、エンロン事件後の2002年に成立した企業改革法(Sarbanes-Oxley Act Section 203,208)等により、筆頭業務執行社員及び審査担当社員には最長継続任期5年、最短インターバル5年、その他の業務執行社員は、最長継続任期7年、最短インターバル2年の「パートナーローテーション制度」が義務付けられている(上場会社については、我が国も同様の取扱いとなっている)。
PCAOBによる監査基準上の規定
AS3101の第10項bでは、2017年12月15日以降終了する事業年度の監査から、監査事務所が会社の監査人になった年度を記載することが要求されており、これに関連してPCAOBは、次のような背景等に関する解説を行っている。
・監査人の在任期間に関する記載は現在要求されていないが、近年、会社が株主総会招集通知書において任意で開示することが増える傾向にある。ただし、PCAOBの監督対象である監査業務の全体を考えると、任意開示が行われている数は多くなく、また、情報が記載される場所はさまざまとなっている。
・再公開草案に対して、在任期間に関する記載は、監査人の在任期間と監査の品質、及び監査人の独立性の間に何らかの関連性があるとの誤った認識を生む可能性があるとのコメントがあった。しかし、PCAOBは当該懸念に同意しない。投資家は、監査人の在任期間に関する情報を強く要望している。当該情報は、投資家に提供される、監査事務所の名称以外の監査人に関するデータの一つである。
・監査報告書における在任期間に関する記述の位置は具体的に規定されていない。最終版の基準に含まれる監査報告書の記載例では、監査報告書の最後に記載されているが、監査人は、監査報告書内のそれ以外の場所に記載することも認められる。
この解説からは、監査人の在任期間の開示が制度化されるまでの過程では、様々な議論や反対のコメント等、紆余曲折があったことが伺われるが、結局、投資家側の強い要望を受け入れるかたちで制度化がなされたものと考えられる。
なお、AS3101「無限定適正意見の監査報告書」の付録Bに含まれる監査報告書の記載例では、監査報告書の末尾(会計事務所名の署名の後)に、「私たちは××××年以降、会社の監査人となっている。」という記載がなされており、今回調査した100社の監査報告書においても、おおむね同様の方法により記載が行われていた。
今回の調査の対象とした企業
今回は、米国ニューヨークの証券取引所に株式を上場し、S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)株価指数100(S&P500中、時価総額の特に大きい、超大型株100銘柄で構成)に選定されている各社(100社)について、直近期のForm10-K(SECに提出される年次報告書)に掲載されている監査報告書を調査対象とした。決算期が異なる企業も一部にあるが、2018年12月期決算にかかるForm10-Kに織り込まれた監査報告書が、今回の調査対象のほとんどを占めている。今回調査対象とした会社には、後述の表3で取り上げた各社のほか、ゼネラル・モーターズ(GM)やフォード、マクドナルド、バンク・オブ・アメリカ、ウォルト・ディズニーといった老舗企業や、GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル。なお、本調査ではグーグルの持株会社であるアルファベット社が対象となっている)に代表される、新興IT企業も含まれている。
調査の結果
まず、今回調査の対象とした各社(100社)の会計監査人の分布を示すと、表1のとおりであった。
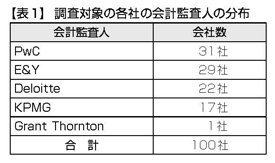
PwCとE&Yで全体の6割を占めており、1社(アラガン)を除くすべて企業の監査を、いわゆる4大監査事務所で分け合う形となっていた。米国においても欧州や我が国と同様に、4大監査事務所が、超大企業の監査をほぼ独占するかたちになっているといえる。
次に、それぞれの会計監査人の在任期間の長さ別の分布を示すと、表2のとおりであった。

我が国の公認会計士(会計監査)制度が先日ようやく70周年を迎えたことを考え合わせると、会計監査人の継続在任期間が80年を超える米国の大企業が100社中15社もあるということは、実に驚くべきことである。米国における会計監査や、投資家保護の歴史の長さをあらためて痛感させられた。会計監査人の在任期間が40年を超える企業で、全体の4割超(41%)を占めていた。なお、在任期間が11年~20年の33社のうち、約半数の16社が、2002年に会計監査人が新たに就任していた(現任監査事務所の在任年数:16年)が、この年は、エンロン社の粉飾決算発覚・倒産を主因として、アーサーアンダーセン会計事務所が倒産した年に該当する。
次に、会計監査人の在任期間が80年を超える企業と会計監査人を一覧で示すと、表3のとおりであった。
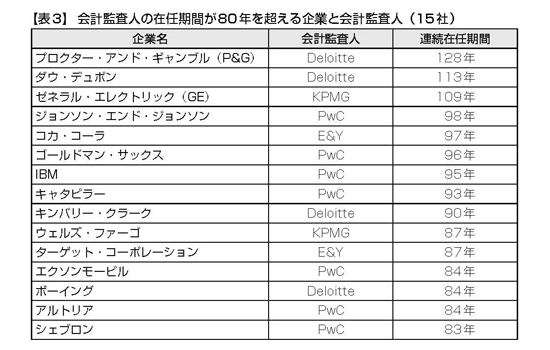
我が国でも非常に知名度が高い、まさに米国を代表するビッグネームがずらりと顔をそろえている。プロクター・アンド・ギャンブル社は1890年にデロイトを会計監査人に選任していた。これらのそうそうたる大会社が80年以上もの期間、ずっと同一の会計監査人の監査を受け続けてきたことを考え合わせると、EU諸国において導入された監査法人の強制ローテーション(入札手続実施の義務付け)制度が米国においては強い反対にあい、結局導入が見送られた背景が伺える。
まとめ
本稿の冒頭に記載したように、欧州のEU諸国は監査法人の強制ローテーション(入札)制度をすでに導入したが、米国と我が国は、同制度の導入を現状は留保している。我が国においては、大企業の会計監査人の在任期間が総じて長く、(監査報告書に署名する監査責任者は定期的に交替しているとはいえ)それによって緊張感の欠如や馴れ合いが生じて不正な会計処理の温床となっているという批判がなされて久しい。しかしながら、本稿でも調査分析したように、米国の大企業の場合には、米国における会計監査制度の歴史の長さもあって、我が国の大企業よりもはるかに長い期間にわたって、同一の監査法人が監査を担当しているケースが多く、会社創業以来、会計監査人が一度も交替したことがないという場合がほとんどで、途中で交替があるケースはむしろ珍しいと考えられる。特に大規模な大手企業について監査法人の固定化が著しいと言われる我が国に負けず劣らず、米国においても、監査法人交替に関する流動性は非常に乏しいことが分かる。
会社のビジネスに関する深度ある理解やノウハウの継続的な保持、手続の重複の回避等、同一の監査法人が長期間にわたって企業を監査するメリットは大きい。また、いわゆる四大監査法人の代わりとなるような監査事務所が不在といった問題もある。したがって、同一の監査法人が企業の監査を長期にわたって担当することイコール悪で、監査法人間の競争や自助努力等が働かないために、定期的に監査法人を交替させないと投資家のためにならない、といった短絡的な結論を出すべきではないであろう。
しかしながら、その一方で、米国では、監査法人の強制ローテーション制度を導入するとした場合に留意すべき事項への対応策についての議論も行われ、例えば以下のような意見が聞かれたとされている。
-ローテーション期間を十分に長く設定する(10年またはそれ以上)
-ローテーションの対象となる業種を限定する
-監査リスクが高い場合にのみローテーションを実施する
-検査結果に問題があった場合にのみローテーションを実施する
-特殊事情がある場合、ローテーションの時期を延期する
-非監査業務を行っている場合、調整するための期間を十分に確保する
-ローテーションが一斉に行われないような配慮を行う
-初年度監査や監査人の引継ぎに関する基準を策定する
-交代初年度においては、前任監査人との共同監査を行う
-PCAOBが初年度監査の検査を行う
これらの意見や提案には、まだ詰めるべき点も多く、課題も多いが、わが国にとって決して「対岸の火事」や「他人事」ではないはずである。将来、我が国において不幸にして大規模な不正会計等が起こったような場合などには、「フレッシュ・ルック」の重要性が改めて強調され、このような見解・アイディアを織り込んだ監査法人の強制ローテーション制度の導入が、我が国で検討される可能性も十分にありうると考えられる。
先に引用した「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(金融庁 2017年7月20日)」は、「第一次報告」と位置付けられており、以下のような文章で結ばれている。
「今後は、欧州における監査法人の強制ローテーション制度導入の効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家、関係団体、有識者など会計監査関係者からのヒアリング等の調査を行い、監査法人の強制ローテーション制度の導入に関する論点についての分析・検討を進めていくことが考えられる。」
終わりに
急速に経済のグローバル化が進む中、わが国だけが世界の動向に背を向け、無縁でいるわけにはいかない。我が国においても、欧州のEU諸国や米国と足並みを揃えるかたちで2018年7月5日に監査基準が改訂され、監査報告書に新たに「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載が求められるようになったほか、監査報告書の記載順序の見直し等も行われた。さらに、2019年2月27日付で、日本公認会計士協会から、実務への適用上のガイドラインである監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が公表され、あとは2021年3月期(2020年3月期から早期適用することも可能)からの適用を待つばかりとなっている。
さらに、2018年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャー・ワーキング・グループ」報告における「財務情報及び記述情報の充実」「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み」に向けた適切な制度整備を行うべきとの提言を踏まえて、有価証券報告書等の記載事項の改正を行うため、2019年1月31日に内閣府令第3号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が改正された。その中で、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み」の一つとして、監査法人による継続監査期間の開示が、2020年3月31日以後終了する事業年度にかかる有価証券報告書等から要求されている(2019年3月31日以後終了する事業年度から早期適用が可能)。
これらの一連の制度化によって、我が国の監査や監査法人をめぐる開示もEU諸国や米国並みに大幅に拡充され、投資家への情報提供も進むと思われる。特に大手企業について、担当する監査法人の固定化が著しいと言われる我が国であるが、実際のところはどうなのか、また、本稿で取り上げた米国の大企業と比較するとどうなのか、筆者としても興味を引かれるところである。
参考文献
・甲斐幸子 米国公開企業会計監視委員会 監査報告に関する新しい監査基準~監査の透明性の向上に向けて 会計・監査ジャーナル 2017年9月号
・高平圭 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正のポイント
・監査法人のローテーション制度に関する調査報告 金融庁 2017年7月20日
主要な米国企業における会計監査人の在任期間に関する記述
はじめに
これまで長らく「専門家の領域で、外部から見るとブラックボックス」と言われていた監査の領域にも、ここ数年で、世界中で透明化への大波が押し寄せている。欧州のEU諸国では、「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載に加えて監査法人の強制ローテーション(一定期間経過後の入札手続実施の義務付け等)がすでに制度化されており、我が国とともに、監査法人の強制ローテーション制度の導入を見送った米国においても、米国公開企業会計監視委員会(PCAOB)が、2017年6月に監査基準(AS)3101「無限定適正意見の監査報告書」及び関連する他の監査基準の適合修正を承認し、公表した。その中では、EU諸国でのKAMと類似した「監査上の重要な事項(Critical Audit Matters(CAM))」や監査人の独立性に関する記述、監査意見を監査報告書の最初の区分に記載すること、及び監査人の在任期間に関する記述などが盛り込まれている。これらのうち、本稿では、主要な米国企業に対して発行される監査報告書に記載されている、会計監査人(監査法人)の在任期間に関する記述を取り上げて、主要な米国企業に監査業務を提供している監査法人の在任期間について、調査分析を行うこととしたい。
監査法人の強制ローテーション制度に対する米国の対応
監査法人のローテーション制度に関する調査報告(金融庁 2017年7月20日)によると、米国においては、現在、監査法人の強制ローテーション制度の導入は議題として取り上げられていないが、監査法人の独立性確保は重要な課題の1つとされている。
また、PCAOBが現在取り組んでいる会計監査に関する基準設定等の議題としては、会計上の見積り、公正価値評価など、会計監査において特に職業的専門家としての懐疑心の発揮が重要となる領域に関するものが増加しており、そのためにも独立性は重要な課題であるとされている。最近基準化されたものには、会計監査の透明化を促進するもの(業務執行社員の氏名の開示、重要な他の監査人(重要な子会社を担当している親会社監査人以外の監査人等)の情報の開示等)などがあり、情報開示は監査人の独立性を評価する上で有用であるとされている。
また、監査法人を監視する責任を有する監査委員会が、適切に会計監査の品質を評価し、監査法人を選任できるようにするため、AQI(Audit Quality Indicators:監査品質の指標)の導入について現在検討が行われている。AQIを実施しその内容を会計監査のステークホルダーに開示することは、監査法人の独立性の確保や会計監査の品質向上を図ることにつながると考えられている。なお、PCAOBは2017年6月に、監査報告書の一項目として監査法人の長期間の関与(Audit firm tenure)について記載することを含む監査基準の改訂を公表した(詳細については次節を参照)。
なお、米国では、「監査法人そのもの」の強制ローテーション制度は導入されていないものの、エンロン事件後の2002年に成立した企業改革法(Sarbanes-Oxley Act Section 203,208)等により、筆頭業務執行社員及び審査担当社員には最長継続任期5年、最短インターバル5年、その他の業務執行社員は、最長継続任期7年、最短インターバル2年の「パートナーローテーション制度」が義務付けられている(上場会社については、我が国も同様の取扱いとなっている)。
PCAOBによる監査基準上の規定
AS3101の第10項bでは、2017年12月15日以降終了する事業年度の監査から、監査事務所が会社の監査人になった年度を記載することが要求されており、これに関連してPCAOBは、次のような背景等に関する解説を行っている。
・監査人の在任期間に関する記載は現在要求されていないが、近年、会社が株主総会招集通知書において任意で開示することが増える傾向にある。ただし、PCAOBの監督対象である監査業務の全体を考えると、任意開示が行われている数は多くなく、また、情報が記載される場所はさまざまとなっている。
・再公開草案に対して、在任期間に関する記載は、監査人の在任期間と監査の品質、及び監査人の独立性の間に何らかの関連性があるとの誤った認識を生む可能性があるとのコメントがあった。しかし、PCAOBは当該懸念に同意しない。投資家は、監査人の在任期間に関する情報を強く要望している。当該情報は、投資家に提供される、監査事務所の名称以外の監査人に関するデータの一つである。
・監査報告書における在任期間に関する記述の位置は具体的に規定されていない。最終版の基準に含まれる監査報告書の記載例では、監査報告書の最後に記載されているが、監査人は、監査報告書内のそれ以外の場所に記載することも認められる。
この解説からは、監査人の在任期間の開示が制度化されるまでの過程では、様々な議論や反対のコメント等、紆余曲折があったことが伺われるが、結局、投資家側の強い要望を受け入れるかたちで制度化がなされたものと考えられる。
なお、AS3101「無限定適正意見の監査報告書」の付録Bに含まれる監査報告書の記載例では、監査報告書の末尾(会計事務所名の署名の後)に、「私たちは××××年以降、会社の監査人となっている。」という記載がなされており、今回調査した100社の監査報告書においても、おおむね同様の方法により記載が行われていた。
今回の調査の対象とした企業
今回は、米国ニューヨークの証券取引所に株式を上場し、S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)株価指数100(S&P500中、時価総額の特に大きい、超大型株100銘柄で構成)に選定されている各社(100社)について、直近期のForm10-K(SECに提出される年次報告書)に掲載されている監査報告書を調査対象とした。決算期が異なる企業も一部にあるが、2018年12月期決算にかかるForm10-Kに織り込まれた監査報告書が、今回の調査対象のほとんどを占めている。今回調査対象とした会社には、後述の表3で取り上げた各社のほか、ゼネラル・モーターズ(GM)やフォード、マクドナルド、バンク・オブ・アメリカ、ウォルト・ディズニーといった老舗企業や、GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル。なお、本調査ではグーグルの持株会社であるアルファベット社が対象となっている)に代表される、新興IT企業も含まれている。
調査の結果
まず、今回調査の対象とした各社(100社)の会計監査人の分布を示すと、表1のとおりであった。
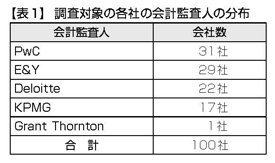
PwCとE&Yで全体の6割を占めており、1社(アラガン)を除くすべて企業の監査を、いわゆる4大監査事務所で分け合う形となっていた。米国においても欧州や我が国と同様に、4大監査事務所が、超大企業の監査をほぼ独占するかたちになっているといえる。
次に、それぞれの会計監査人の在任期間の長さ別の分布を示すと、表2のとおりであった。

我が国の公認会計士(会計監査)制度が先日ようやく70周年を迎えたことを考え合わせると、会計監査人の継続在任期間が80年を超える米国の大企業が100社中15社もあるということは、実に驚くべきことである。米国における会計監査や、投資家保護の歴史の長さをあらためて痛感させられた。会計監査人の在任期間が40年を超える企業で、全体の4割超(41%)を占めていた。なお、在任期間が11年~20年の33社のうち、約半数の16社が、2002年に会計監査人が新たに就任していた(現任監査事務所の在任年数:16年)が、この年は、エンロン社の粉飾決算発覚・倒産を主因として、アーサーアンダーセン会計事務所が倒産した年に該当する。
次に、会計監査人の在任期間が80年を超える企業と会計監査人を一覧で示すと、表3のとおりであった。
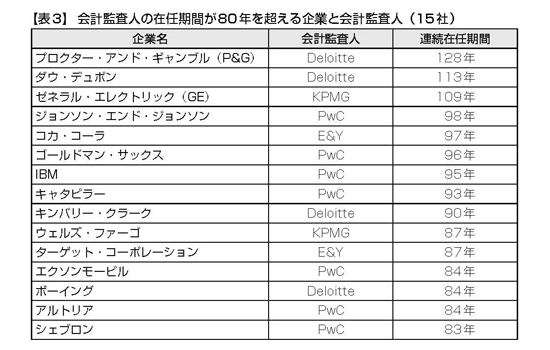
我が国でも非常に知名度が高い、まさに米国を代表するビッグネームがずらりと顔をそろえている。プロクター・アンド・ギャンブル社は1890年にデロイトを会計監査人に選任していた。これらのそうそうたる大会社が80年以上もの期間、ずっと同一の会計監査人の監査を受け続けてきたことを考え合わせると、EU諸国において導入された監査法人の強制ローテーション(入札手続実施の義務付け)制度が米国においては強い反対にあい、結局導入が見送られた背景が伺える。
まとめ
本稿の冒頭に記載したように、欧州のEU諸国は監査法人の強制ローテーション(入札)制度をすでに導入したが、米国と我が国は、同制度の導入を現状は留保している。我が国においては、大企業の会計監査人の在任期間が総じて長く、(監査報告書に署名する監査責任者は定期的に交替しているとはいえ)それによって緊張感の欠如や馴れ合いが生じて不正な会計処理の温床となっているという批判がなされて久しい。しかしながら、本稿でも調査分析したように、米国の大企業の場合には、米国における会計監査制度の歴史の長さもあって、我が国の大企業よりもはるかに長い期間にわたって、同一の監査法人が監査を担当しているケースが多く、会社創業以来、会計監査人が一度も交替したことがないという場合がほとんどで、途中で交替があるケースはむしろ珍しいと考えられる。特に大規模な大手企業について監査法人の固定化が著しいと言われる我が国に負けず劣らず、米国においても、監査法人交替に関する流動性は非常に乏しいことが分かる。
会社のビジネスに関する深度ある理解やノウハウの継続的な保持、手続の重複の回避等、同一の監査法人が長期間にわたって企業を監査するメリットは大きい。また、いわゆる四大監査法人の代わりとなるような監査事務所が不在といった問題もある。したがって、同一の監査法人が企業の監査を長期にわたって担当することイコール悪で、監査法人間の競争や自助努力等が働かないために、定期的に監査法人を交替させないと投資家のためにならない、といった短絡的な結論を出すべきではないであろう。
しかしながら、その一方で、米国では、監査法人の強制ローテーション制度を導入するとした場合に留意すべき事項への対応策についての議論も行われ、例えば以下のような意見が聞かれたとされている。
-ローテーション期間を十分に長く設定する(10年またはそれ以上)
-ローテーションの対象となる業種を限定する
-監査リスクが高い場合にのみローテーションを実施する
-検査結果に問題があった場合にのみローテーションを実施する
-特殊事情がある場合、ローテーションの時期を延期する
-非監査業務を行っている場合、調整するための期間を十分に確保する
-ローテーションが一斉に行われないような配慮を行う
-初年度監査や監査人の引継ぎに関する基準を策定する
-交代初年度においては、前任監査人との共同監査を行う
-PCAOBが初年度監査の検査を行う
これらの意見や提案には、まだ詰めるべき点も多く、課題も多いが、わが国にとって決して「対岸の火事」や「他人事」ではないはずである。将来、我が国において不幸にして大規模な不正会計等が起こったような場合などには、「フレッシュ・ルック」の重要性が改めて強調され、このような見解・アイディアを織り込んだ監査法人の強制ローテーション制度の導入が、我が国で検討される可能性も十分にありうると考えられる。
先に引用した「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(金融庁 2017年7月20日)」は、「第一次報告」と位置付けられており、以下のような文章で結ばれている。
「今後は、欧州における監査法人の強制ローテーション制度導入の効果等を注視するとともに、我が国において、監査法人、企業、機関投資家、関係団体、有識者など会計監査関係者からのヒアリング等の調査を行い、監査法人の強制ローテーション制度の導入に関する論点についての分析・検討を進めていくことが考えられる。」
終わりに
急速に経済のグローバル化が進む中、わが国だけが世界の動向に背を向け、無縁でいるわけにはいかない。我が国においても、欧州のEU諸国や米国と足並みを揃えるかたちで2018年7月5日に監査基準が改訂され、監査報告書に新たに「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載が求められるようになったほか、監査報告書の記載順序の見直し等も行われた。さらに、2019年2月27日付で、日本公認会計士協会から、実務への適用上のガイドラインである監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が公表され、あとは2021年3月期(2020年3月期から早期適用することも可能)からの適用を待つばかりとなっている。
さらに、2018年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャー・ワーキング・グループ」報告における「財務情報及び記述情報の充実」「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み」に向けた適切な制度整備を行うべきとの提言を踏まえて、有価証券報告書等の記載事項の改正を行うため、2019年1月31日に内閣府令第3号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が改正された。その中で、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取り組み」の一つとして、監査法人による継続監査期間の開示が、2020年3月31日以後終了する事業年度にかかる有価証券報告書等から要求されている(2019年3月31日以後終了する事業年度から早期適用が可能)。
これらの一連の制度化によって、我が国の監査や監査法人をめぐる開示もEU諸国や米国並みに大幅に拡充され、投資家への情報提供も進むと思われる。特に大手企業について、担当する監査法人の固定化が著しいと言われる我が国であるが、実際のところはどうなのか、また、本稿で取り上げた米国の大企業と比較するとどうなのか、筆者としても興味を引かれるところである。
参考文献
・甲斐幸子 米国公開企業会計監視委員会 監査報告に関する新しい監査基準~監査の透明性の向上に向けて 会計・監査ジャーナル 2017年9月号
・高平圭 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正のポイント
・監査法人のローテーション制度に関する調査報告 金融庁 2017年7月20日
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























