解説記事2019年05月13日 【ニュース特集】 取締役の報酬や解任をめぐる会社法の訴訟トラブル(2019年5月13日号・№786)
ニュース特集
定められた報酬を同意なく減額した会社側が敗訴した事例も
取締役の報酬や解任をめぐる会社法の訴訟トラブル
報酬の減額や解任といった取締役と会社との間の会社法をめぐるトラブルが訴訟にまで発展するケースも見受けられるなか、本特集では、報酬の減額や解任をめぐり元取締役が会社を訴えた最近の裁判事例を2つ紹介する。1つめの事例は、入院による長期欠勤により定められた取締役報酬を減額された元取締役が会社に対して減額分(未支給額)の支給を請求したもの。地裁は、減額支給には取締役本人の同意がなかったとして、被告会社に対して減額分の支払いを命じた。2つめの事例は、任期途中で解任された元取締役が会社に対して残存任期中の取締役報酬相当額の損害賠償などを請求したもの。地裁は、取締役としての職務遂行能力や適性に著しく欠けるところがあったとして解任には正当な理由があったと判断している。
取締役が入院で長期欠勤、定められた報酬の減額の可否が問題に
最初に紹介する裁判事例は、非上場企業である被告会社の取締役であった原告が被告会社に対して、定められた取締役報酬を入院による長期欠勤により減額されたことを不服として減額分の支給を請求していたものである。
事実関係をみていくと、被告会社は平成26年6月の定時株主総会で原告を取締役に選任する旨の決議をし、原告は取締役に就任した(任期は平成28年6月までの2年間)。被告会社における取締役報酬は、定時株主総会の決議により取締役会に一任することとされていた。そこで被告会社の取締役会は、原告の取締役報酬を月額約65万円とすることを決議していた。ところが、原告は平成27年5月下旬に入院し、その後は平成28年6月に任期満了により取締役を退任するまで欠勤が継続する状態となった。被告会社の代表取締役は、原告の欠勤が続いたことから、取締役会に諮ったうえで平成27年9月分から11月分の月額報酬を約20万円、平成27年12月分から平成28年6月分の月額報酬を約10万円に減額した(なお、被告会社には当時、取締役の長期欠勤の際の報酬の取扱いに関する特段の定めはなかった)。
定められた報酬の減額には本人の同意が必要 東京地裁はまず、最高裁平成4年12月18日判決を引用するかたちで、定められた報酬額は取締役と会社との間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、仮に取締役の職務内容に著しい変更があり、株主総会等でこれを変更する旨の決議をしても、その取締役がその変更に同意しない限り、その取締役は報酬請求権を失わないことになるという解釈を示した。
そして本件について地裁は、被告会社は原告の月額報酬を減額する旨を原告の自宅にFAXしたことが認められるものの、単に入院中である原告から月額報酬を減額する旨に対する明示的な異議申し出がないということのみでは、原告が平成27年9月以降の減額について黙示的にこれに同意していたものと解することはできないとした。そのうえで地裁は、平成27年9月分以降の減額分の合計約523万円について、被告会社に対して原告への支払を命じた(東京地裁平成30年9月7日判決・確定済み)。
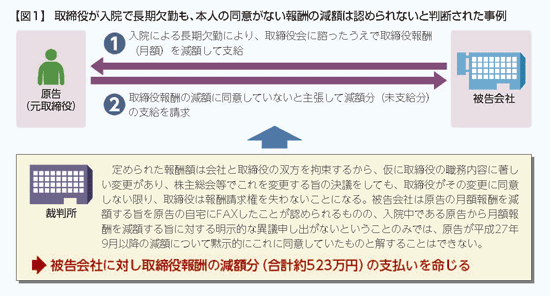
取役の中途解任に「正当な理由」があったか否かが問題に
株主総会の決議による役員の解任に「正当な理由」がない場合には、解任された役員は会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(会社法339条)。
次に紹介する裁判事例は、上場企業(東証第一部上場)である被告会社の臨時株主総会において取締役を解任された原告が被告会社に対して、解任には「正当な理由」がないと主張して、損害賠償(残存任期中の取締役報酬相当額)などを請求していたものである。
事実関係をみていくと、上場企業の専務取締役を退任した原告は、平成28年6月の定時株主総会により被告会社の新たな取締役として選任されたものの、同年10月の臨時株主総会により取締役を解任されることになった。解任理由として臨時株主総会の招集通知書には、①被告会社に告知することなく他社の代表取締役に就任していた事実の発覚、②秘密保持誓約の締結拒否などが取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するほか、原告の合弁事業計画は被告会社の目指す戦略と乖離する一方で、原告が高額な報酬を強硬に要求するなど信頼関係を構築できない状態に至った旨が記載されていた。
取締役としての職務遂行能力を問題視 東京地裁は、被告会社は原告を取締役に選任することにより売上の飛躍的増加を期待するとともにこれに応じた報酬の支払いを企図した一方で、原告が目標の売上を繰り返し一方的に下方修正したにもかかわらず報酬金額の支払いにだけは固執したことによる信頼関係の崩壊があるというべきであると指摘。原告には信頼関係の崩壊に繋がる不誠実な職務遂行を行った者として取締役としての職務遂行能力や適性に問題があったというべきであるとした。また、地裁は、原告が代表取締役に就任した会社の事業が被告会社との関係で競合に当たらないことなどに関して被告会社に十分な説明を行っていないことなどにより、原告及び被告会社間の信頼関係はさらに悪化したものというべきであるとした。
これらの事情を踏まえ地裁は、原告は信頼関係の崩壊・悪化に繋がる不誠実な職務遂行を行った者として取締役としての職務遂行能力や適性に著しく欠けるところがあったというべきであると指摘。原告に対する取締役解任には「正当な理由」があると判断したうえで、原告の請求を棄却する判決を下した(東京地裁平成30年11月29日判決・控訴あり)。
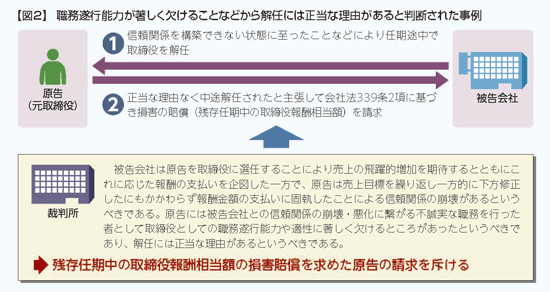
定められた報酬を同意なく減額した会社側が敗訴した事例も
取締役の報酬や解任をめぐる会社法の訴訟トラブル
報酬の減額や解任といった取締役と会社との間の会社法をめぐるトラブルが訴訟にまで発展するケースも見受けられるなか、本特集では、報酬の減額や解任をめぐり元取締役が会社を訴えた最近の裁判事例を2つ紹介する。1つめの事例は、入院による長期欠勤により定められた取締役報酬を減額された元取締役が会社に対して減額分(未支給額)の支給を請求したもの。地裁は、減額支給には取締役本人の同意がなかったとして、被告会社に対して減額分の支払いを命じた。2つめの事例は、任期途中で解任された元取締役が会社に対して残存任期中の取締役報酬相当額の損害賠償などを請求したもの。地裁は、取締役としての職務遂行能力や適性に著しく欠けるところがあったとして解任には正当な理由があったと判断している。
取締役が入院で長期欠勤、定められた報酬の減額の可否が問題に
最初に紹介する裁判事例は、非上場企業である被告会社の取締役であった原告が被告会社に対して、定められた取締役報酬を入院による長期欠勤により減額されたことを不服として減額分の支給を請求していたものである。
事実関係をみていくと、被告会社は平成26年6月の定時株主総会で原告を取締役に選任する旨の決議をし、原告は取締役に就任した(任期は平成28年6月までの2年間)。被告会社における取締役報酬は、定時株主総会の決議により取締役会に一任することとされていた。そこで被告会社の取締役会は、原告の取締役報酬を月額約65万円とすることを決議していた。ところが、原告は平成27年5月下旬に入院し、その後は平成28年6月に任期満了により取締役を退任するまで欠勤が継続する状態となった。被告会社の代表取締役は、原告の欠勤が続いたことから、取締役会に諮ったうえで平成27年9月分から11月分の月額報酬を約20万円、平成27年12月分から平成28年6月分の月額報酬を約10万円に減額した(なお、被告会社には当時、取締役の長期欠勤の際の報酬の取扱いに関する特段の定めはなかった)。
定められた報酬の減額には本人の同意が必要 東京地裁はまず、最高裁平成4年12月18日判決を引用するかたちで、定められた報酬額は取締役と会社との間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、仮に取締役の職務内容に著しい変更があり、株主総会等でこれを変更する旨の決議をしても、その取締役がその変更に同意しない限り、その取締役は報酬請求権を失わないことになるという解釈を示した。
そして本件について地裁は、被告会社は原告の月額報酬を減額する旨を原告の自宅にFAXしたことが認められるものの、単に入院中である原告から月額報酬を減額する旨に対する明示的な異議申し出がないということのみでは、原告が平成27年9月以降の減額について黙示的にこれに同意していたものと解することはできないとした。そのうえで地裁は、平成27年9月分以降の減額分の合計約523万円について、被告会社に対して原告への支払を命じた(東京地裁平成30年9月7日判決・確定済み)。
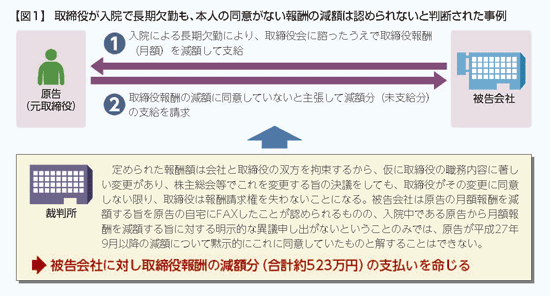
取役の中途解任に「正当な理由」があったか否かが問題に
株主総会の決議による役員の解任に「正当な理由」がない場合には、解任された役員は会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(会社法339条)。
次に紹介する裁判事例は、上場企業(東証第一部上場)である被告会社の臨時株主総会において取締役を解任された原告が被告会社に対して、解任には「正当な理由」がないと主張して、損害賠償(残存任期中の取締役報酬相当額)などを請求していたものである。
事実関係をみていくと、上場企業の専務取締役を退任した原告は、平成28年6月の定時株主総会により被告会社の新たな取締役として選任されたものの、同年10月の臨時株主総会により取締役を解任されることになった。解任理由として臨時株主総会の招集通知書には、①被告会社に告知することなく他社の代表取締役に就任していた事実の発覚、②秘密保持誓約の締結拒否などが取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するほか、原告の合弁事業計画は被告会社の目指す戦略と乖離する一方で、原告が高額な報酬を強硬に要求するなど信頼関係を構築できない状態に至った旨が記載されていた。
取締役としての職務遂行能力を問題視 東京地裁は、被告会社は原告を取締役に選任することにより売上の飛躍的増加を期待するとともにこれに応じた報酬の支払いを企図した一方で、原告が目標の売上を繰り返し一方的に下方修正したにもかかわらず報酬金額の支払いにだけは固執したことによる信頼関係の崩壊があるというべきであると指摘。原告には信頼関係の崩壊に繋がる不誠実な職務遂行を行った者として取締役としての職務遂行能力や適性に問題があったというべきであるとした。また、地裁は、原告が代表取締役に就任した会社の事業が被告会社との関係で競合に当たらないことなどに関して被告会社に十分な説明を行っていないことなどにより、原告及び被告会社間の信頼関係はさらに悪化したものというべきであるとした。
これらの事情を踏まえ地裁は、原告は信頼関係の崩壊・悪化に繋がる不誠実な職務遂行を行った者として取締役としての職務遂行能力や適性に著しく欠けるところがあったというべきであると指摘。原告に対する取締役解任には「正当な理由」があると判断したうえで、原告の請求を棄却する判決を下した(東京地裁平成30年11月29日判決・控訴あり)。
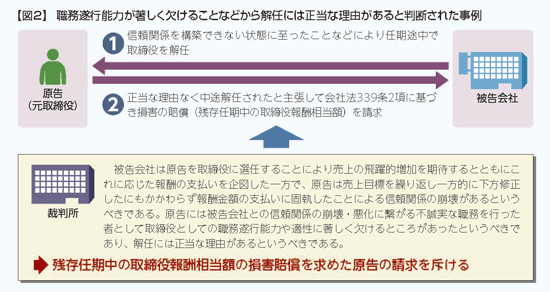
| Column | 取締役解任の理由の記載、記載事項は名誉毀損に当たらず |
| 2番目に紹介した裁判事例のなかで原告は、適時開示情報システム等及び臨時株主総会の招集通知に解任の理由として記載された事項は原告の社会的信用を著しく低下させる名誉棄損に当たると主張して、被告会社に損害賠償を求めていた。これに対し地裁は、記載された事項の重要な部分は真実であると認定したうえで、原告に対する人身攻撃に当たるということはできないことなどから、名誉毀損には当たらない旨の判断を示した。 | |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























