解説記事2019年08月12日 【ニュース特集】 所得税法上の住所の認定をめぐり東京地裁が注目判決!(2019年8月12日号・№799)
ニュース特集
居住者であると判断した課税当局が全面敗訴
所得税法上の住所の認定をめぐり東京地裁が注目判決!
経済活動の国際化により居住者と非居住者の区分に関する税務紛争が数多く見受けられるなか、その区分の前提となる住所(生活の本拠)の認定をめぐり東京地裁が注目すべき判決を下した。本件で問題となったのは、国内法人数社及び関連海外法人数社の代表者を務める納税者(日本人)が所得税法上の「居住者」に該当するか否かという点である。東京地裁は、「居住者」には該当しないと判断して、居住者を前提とした税務署による通知処分などの全部を取り消す判決を下した(令和元年5月30日判決)。本判決は、国側の控訴により未確定である。判決が確定すれば本件の裁判所による住所の認定が他の事案に影響を与える可能性もあるだけに、控訴審の行方に注目が集まりそうだ。
納税者は複数国に滞在、海外の滞在業務期間は年間66%~70%
納税者(日本国籍を持つ男性)は、国内法人数社のほか、米国・シンガポール・中国などに所在する関連海外法人の代表者を務めており、海外法人における業務のために各国に滞在していた。各国における滞在日数は、表1のとおりである。
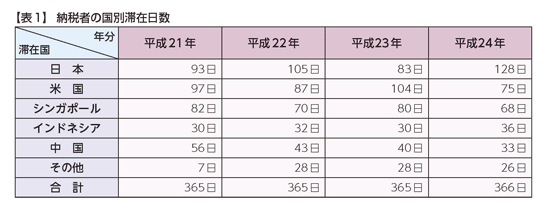
納税者は、日本・米国・シンガポールの3国に居宅を有しており、その3国に滞在している間はその居宅で生活していた。納税者は、自らが所得税法2条1項5号に規定する「非居住者」に該当すると考えて日本で所得税の申告を行っていなかった(なお、納税者はシンガポールの居住者としてシンガポールで納税申告をしていた)。だが、税務署から「居住者」に該当するとの指摘を受けたことから、税務署の指摘を受け入れるかたちで所得税の期限後申告を行った。その後納税者は、「非居住者」に該当するとして更正の請求をしたものの、税務署から更正をすべき理由がない旨の通知処分などを受けた。これを不服とした納税者は、自らを所得税法上の「非居住者」に該当すると主張して、国税不服審判所に対して通知処分などの取り消しを求める審査請求を行った。
日本の方が生活本拠の実体があると判断 審判所はまず、武富士事件の最高裁判決(平成23年2月18日第二小法廷判決)を引用したうえで、住所(生活の本拠)の認定は①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業及び業務の内容・従事状況、④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出状況等の客観的諸事情を総合的に勘案して行うのが相当であるとした。
そして本件について審判所は、①日本に定期的に帰国し滞在していたこと、②日本滞在時には日本の居宅で種々の消費活動や通院等をしていたこと、③国内・海外法人の代表者として経営判断等の重要性の高い業務を行っていたこと、④日本の居宅を居住地とする妻らと生計を一にしていたこと、⑤国外に比べて日本に主な資産を所有していること、⑥日本の公的機関等に対し住所が日本にあるとする届出をしていることなどの客観的諸事情を総合的に勘案すると、納税者の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは日本の居宅の所在地であると認められることから、納税者は「居住者」に該当すると判断して審査請求を棄却していた(平成28年3月1日裁決・詳しくは本誌669号40頁、672号26頁参照)。裁決を不服とした納税者は、改めて自らは非居住者に該当すると主張して、通知処分などの取り消しを求める税務訴訟を提起した。
職業活動の本拠をシンガポールと認めるなどして「非居住者」と判断
東京地裁はまず、住所(生活の本拠)について、平成28年3月1日裁決と同様に武富士事件の最高裁判決を引用したうえで、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かは、①滞在日数及び住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情を総合的に考慮して判断するのが相当であるとした。
そして本件について地裁は、②職業については納税者の職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められると判断した。また、①滞在日数及び住居、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情については、納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえないと判断した(東京地裁の詳しい判断内容は表2参照)。
以上の点を踏まえ地裁は、納税者の住所(生活の本拠)が日本にあったと認めることはできないから、納税者は所得税法2条1項3号の「居住者」に該当するとは認められないと判断したうえで、納税者が「居住者」に該当することを前提としてされた税務署による通知処分などは違法であるとしてその全部を取り消した。
居住者であると判断した課税当局が全面敗訴
所得税法上の住所の認定をめぐり東京地裁が注目判決!
経済活動の国際化により居住者と非居住者の区分に関する税務紛争が数多く見受けられるなか、その区分の前提となる住所(生活の本拠)の認定をめぐり東京地裁が注目すべき判決を下した。本件で問題となったのは、国内法人数社及び関連海外法人数社の代表者を務める納税者(日本人)が所得税法上の「居住者」に該当するか否かという点である。東京地裁は、「居住者」には該当しないと判断して、居住者を前提とした税務署による通知処分などの全部を取り消す判決を下した(令和元年5月30日判決)。本判決は、国側の控訴により未確定である。判決が確定すれば本件の裁判所による住所の認定が他の事案に影響を与える可能性もあるだけに、控訴審の行方に注目が集まりそうだ。
納税者は複数国に滞在、海外の滞在業務期間は年間66%~70%
納税者(日本国籍を持つ男性)は、国内法人数社のほか、米国・シンガポール・中国などに所在する関連海外法人の代表者を務めており、海外法人における業務のために各国に滞在していた。各国における滞在日数は、表1のとおりである。
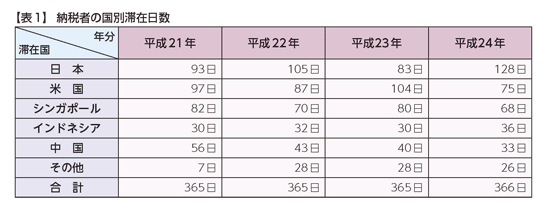
納税者は、日本・米国・シンガポールの3国に居宅を有しており、その3国に滞在している間はその居宅で生活していた。納税者は、自らが所得税法2条1項5号に規定する「非居住者」に該当すると考えて日本で所得税の申告を行っていなかった(なお、納税者はシンガポールの居住者としてシンガポールで納税申告をしていた)。だが、税務署から「居住者」に該当するとの指摘を受けたことから、税務署の指摘を受け入れるかたちで所得税の期限後申告を行った。その後納税者は、「非居住者」に該当するとして更正の請求をしたものの、税務署から更正をすべき理由がない旨の通知処分などを受けた。これを不服とした納税者は、自らを所得税法上の「非居住者」に該当すると主張して、国税不服審判所に対して通知処分などの取り消しを求める審査請求を行った。
日本の方が生活本拠の実体があると判断 審判所はまず、武富士事件の最高裁判決(平成23年2月18日第二小法廷判決)を引用したうえで、住所(生活の本拠)の認定は①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業及び業務の内容・従事状況、④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出状況等の客観的諸事情を総合的に勘案して行うのが相当であるとした。
そして本件について審判所は、①日本に定期的に帰国し滞在していたこと、②日本滞在時には日本の居宅で種々の消費活動や通院等をしていたこと、③国内・海外法人の代表者として経営判断等の重要性の高い業務を行っていたこと、④日本の居宅を居住地とする妻らと生計を一にしていたこと、⑤国外に比べて日本に主な資産を所有していること、⑥日本の公的機関等に対し住所が日本にあるとする届出をしていることなどの客観的諸事情を総合的に勘案すると、納税者の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは日本の居宅の所在地であると認められることから、納税者は「居住者」に該当すると判断して審査請求を棄却していた(平成28年3月1日裁決・詳しくは本誌669号40頁、672号26頁参照)。裁決を不服とした納税者は、改めて自らは非居住者に該当すると主張して、通知処分などの取り消しを求める税務訴訟を提起した。
職業活動の本拠をシンガポールと認めるなどして「非居住者」と判断
東京地裁はまず、住所(生活の本拠)について、平成28年3月1日裁決と同様に武富士事件の最高裁判決を引用したうえで、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かは、①滞在日数及び住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情を総合的に考慮して判断するのが相当であるとした。
そして本件について地裁は、②職業については納税者の職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められると判断した。また、①滞在日数及び住居、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情については、納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえないと判断した(東京地裁の詳しい判断内容は表2参照)。
| 【表2】住所の認定のポイントに対する東京地裁の判断内容 |
| 認定の ポイント | 東京地裁の判断内容 |
| ①滞在日数及び住居 | ・日本における滞在日数と納税者が自らの住所があったと主張するシンガポールにおける滞在日数を比較すると、両国における滞在日数に大きな差があるとはいえない。 ・納税者が各国への渡航の利便性が高いシンガポールを起点として中国やその他の国(ヨーロッパ・中東など)に渡航していることからすると、シンガポールが居住3か国以外の各国へ渡航する際の主な拠点となっていたことは否定し難い。この点を考慮すると日本とシンガポールの滞在には量的な点から有意な差があるとはいえない。 →納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない |
| ②職業 | ・納税者の日本国内における業務は、代表者としての月1回の経営会議や株主総会及び取締役会(年2~3回程度)に出席することなどであり、その業務従事日数は納税者が日本に滞在した日数のおよそ半分に相当する年間13%~17%の日数にすぎない。 ・一方で、納税者が諸外国に滞在して業務を行っているのは年間66~75%で、年間約40%の日数はシンガポール又は同国を起点として近隣国に滞在していた。 →納税者の職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められる |
| ③生計を一にする配偶者その他の親族の居所 | ・生計を一にする妻や二女が妻らの生活の便宜や子の教育上の配慮から日本の居宅に滞在しても、年間の大部分を海外の各地で過ごすことになる納税者の職業活動に適応した生活の在り方として、妻らの生活の本拠は海外に移さず、日本のままとするという生活の方法を選択したものということができる。 →納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない |
| ④資産の所在 | ・納税者が所有する資産の多くは日本に所在しているものの、シンガポールにおいても1,700万円以上の預貯金がある(当面生活するために十分な資産を有していたといえる)。日本の預貯金等の資産をシンガポールに移転していないことは、家族を残して海外赴任をする者の行動として不自然なものとはいえない。 →納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない |
| ⑤その他の事情 | ・納税者が日本住所地で住民登録をしていても、海外赴任者が手続上の便宜のために日本国内に住民登録を残しておくことはその者の行動として不自然であるとは言い難い。 ・納税者が日本の健康保険組合に継続加入し、毎月通院していたとしても、世界各地を頻繁に行き来して一時帰国数も少なくない者であれば、医療水準等を踏まえて一時帰国時に日本の病院に通院等することが不自然であるとは言い難い。 →納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない |
| ↓ |
| 納税者の住所(生活の本拠)が日本にあったと認めることはできないから、 納税者は所得税法上の「居住者」に該当しないと判断 |
以上の点を踏まえ地裁は、納税者の住所(生活の本拠)が日本にあったと認めることはできないから、納税者は所得税法2条1項3号の「居住者」に該当するとは認められないと判断したうえで、納税者が「居住者」に該当することを前提としてされた税務署による通知処分などは違法であるとしてその全部を取り消した。
| Column | 納税者が代表取締役を務める国内法人に対する納税告知処分等も取り消す |
| 納税者が代表取締役を務める国内法人2社は、納税者に支払う役員報酬について、非居住者に対する源泉徴収として源泉所得税を徴収・納付していた。これに対し税務署は、納税者が「居住者」に該当するとの前提で納税告知処分等を行った。本件税務訴訟では、国内法人2社も原告となっており、東京地裁が納税者は「居住者」に該当しないと判断したことから、国内法人2社に対する納税告知処分等の全部も取り消されている。 | |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























