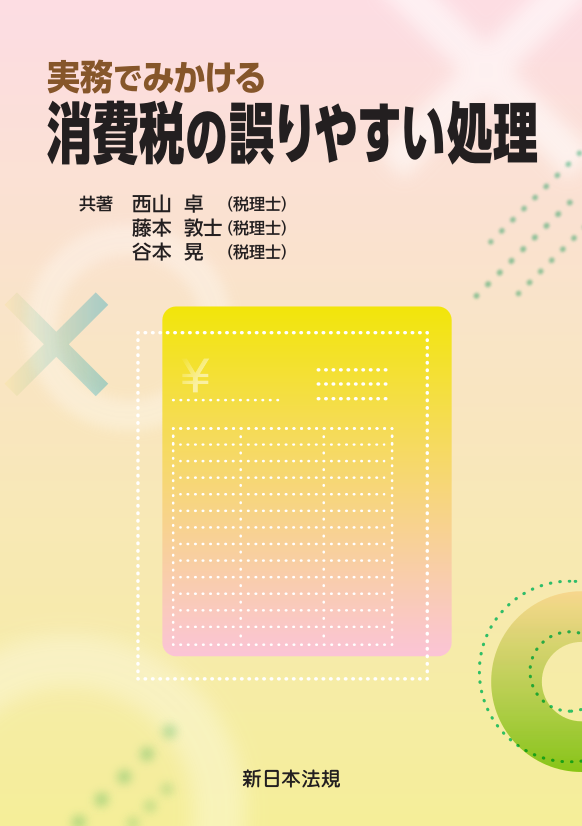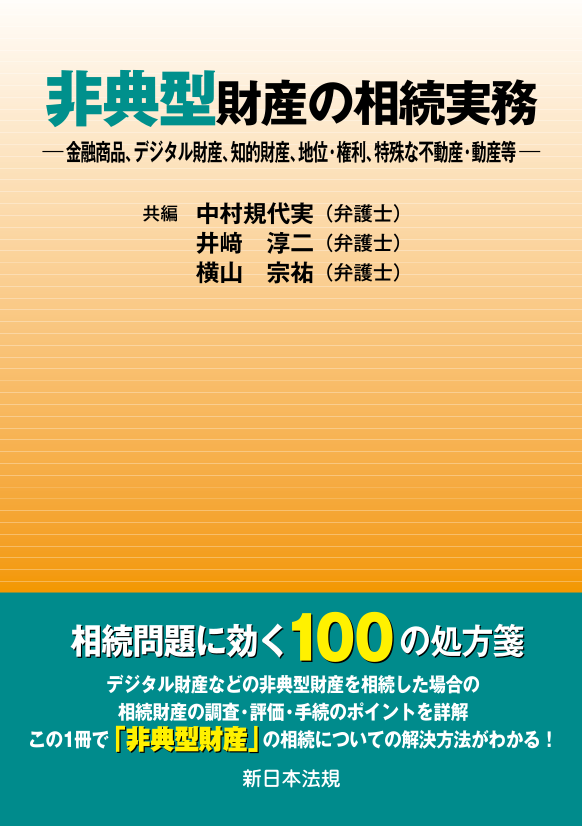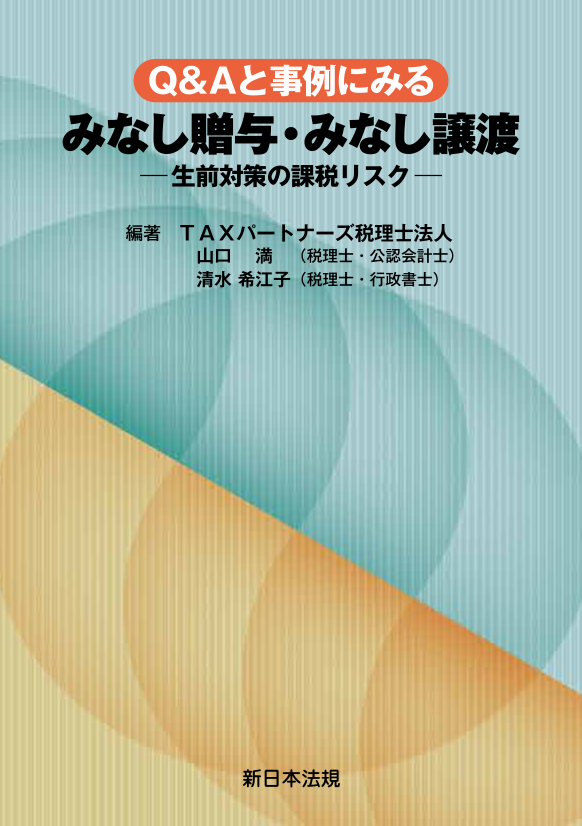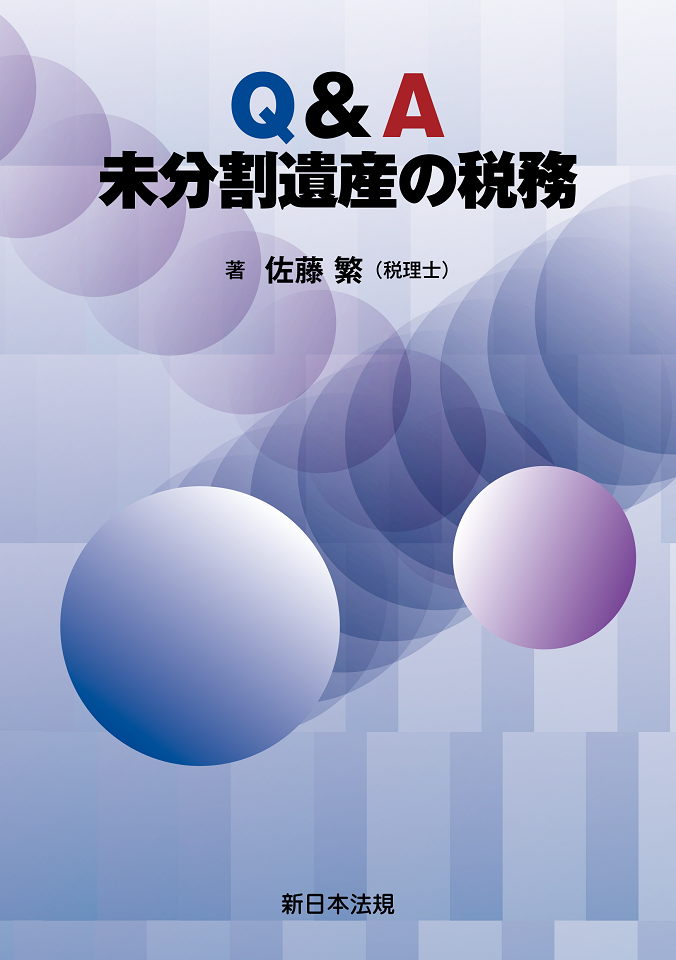税務ニュース2012年08月27日 42%控除の可否、法基通改正が分岐点に(2012年8月27日号・№464) 最高裁、平成12年の法基通改正後の事案で法人税額等相当額控除を認めず
42%控除の可否、法基通改正が分岐点に
最高裁、平成12年の法基通改正後の事案で法人税額等相当額控除を認めず
非上場株式を純資産価額方式で評価する場合、財産評価基本通達185では評価会社の時価純資産価額と簿価純資産価額の差額から法人税額等相当額(42%)が控除できる旨が規定されている。一方で、法人税課税においては、平成12年の法人税基本通達の改正により、評価通達の準用に際して法人税額等相当額の控除が認められない旨が明確にされた(法基通9-1-14(3))。
今回の事案では、納税者が関連法人である外国法人の発行株式を額面で引き受けたことに対し、有価証券の有利発行による受贈益を認定した課税処分の適否が争われるなかで、株式評価の際に法人税額等相当額が控除できるか否かが問題となっていた。
納税者は、最高裁平成17年11月8日判決・同平成18年1月24日判決を踏まえ、評価通達が法人税額等相当額を控除するものとしているのは、財産の直接所有支配と間接所有支配との均衡を図るためであり、その趣旨は対象会社が現実に解散することを前提としている場合でなくても当てはまると指摘。法人税額等相当額の控除は、相続・贈与税の場面に限定されず、法人税課税の分野においても適用されるべきであると主張していた。
第一審および控訴審判決は、法人税額等相当額が控除できるか否かについて、相続税の分野の取扱いと会社が継続的に事業活動を行うことを前提とする法人税課税の取扱いとが異なることは、合理的な措置として是認できると指摘。平成12年の法基達9-1-14(3)の改正により、法人税課税の場面では、法人税額等相当額を控除しないこととされたのであり、本事案に係る平成17年当時においては、法人税額等相当額を控除しない取扱いが課税実務上定着していたため、合理性が認められると判断していた。また、法人税額等相当額を控除しないことを定める法基通9-1-14(3)は、最高裁平成17年判決および同平成18年判決にも抵触する点はないというべきであると指摘している。
前述の2つの最高裁判決は、通達改正前の事案について、法人税額等相当額の控除を認める判断を示したもの。今回の上告不受理決定により、通達改正後の本事案については、控除しない旨を判示した控訴審判決が確定することとなった。
最高裁、平成12年の法基通改正後の事案で法人税額等相当額控除を認めず
|
今回の事案では、納税者が関連法人である外国法人の発行株式を額面で引き受けたことに対し、有価証券の有利発行による受贈益を認定した課税処分の適否が争われるなかで、株式評価の際に法人税額等相当額が控除できるか否かが問題となっていた。
納税者は、最高裁平成17年11月8日判決・同平成18年1月24日判決を踏まえ、評価通達が法人税額等相当額を控除するものとしているのは、財産の直接所有支配と間接所有支配との均衡を図るためであり、その趣旨は対象会社が現実に解散することを前提としている場合でなくても当てはまると指摘。法人税額等相当額の控除は、相続・贈与税の場面に限定されず、法人税課税の分野においても適用されるべきであると主張していた。
第一審および控訴審判決は、法人税額等相当額が控除できるか否かについて、相続税の分野の取扱いと会社が継続的に事業活動を行うことを前提とする法人税課税の取扱いとが異なることは、合理的な措置として是認できると指摘。平成12年の法基達9-1-14(3)の改正により、法人税課税の場面では、法人税額等相当額を控除しないこととされたのであり、本事案に係る平成17年当時においては、法人税額等相当額を控除しない取扱いが課税実務上定着していたため、合理性が認められると判断していた。また、法人税額等相当額を控除しないことを定める法基通9-1-14(3)は、最高裁平成17年判決および同平成18年判決にも抵触する点はないというべきであると指摘している。
前述の2つの最高裁判決は、通達改正前の事案について、法人税額等相当額の控除を認める判断を示したもの。今回の上告不受理決定により、通達改正後の本事案については、控除しない旨を判示した控訴審判決が確定することとなった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.