解説記事2019年09月02日 税制改正解説 法人版事業承継税制と遺留分侵害額の請求(2019年9月2日号・№801)
税制改正解説
法人版事業承継税制と遺留分侵害額の請求
税理士 竹内陽一
公認会計士・税理士 有田賢臣
事業承継税制の適用対象となる中小企業では、先代経営者の財産に占める自社株式の割合が高く、自社株式を後継者に集中して承継させると他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも少なくない。
後継者が他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたものの、支払うべき金銭を有していない場合には、①後継者が銀行や自社から資金を借り入れる、②自社株式を譲渡して資金を得る、③金銭の支払に代えて自社株式を他の相続人に移転する(現物分与する)といった方法が考えられる。
自社株式の譲渡(②)や現物分与(③)を行うと納税猶予の期限が確定してしまうので、借入れ(①)が有力な選択肢になると思われる。その一方で、いつかは返済しなければならないという意味で、借入れは問題の先送りにすぎない。自社株式の譲渡や現物分与による場合と比較検討した上でいずれの方法で対応するかを選択すべきである。
Ⅰ 遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ
民法(相続法)が改正され、原則として令和元年7月1日以後に開始する相続について適用されている。遺留分については、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へと改正された。
1 改正前の遺留分減殺請求権
改正前の遺留分減殺請求権は、その行使により、遺留分を侵害する限度で贈与又は遺贈が無効となり、目的物が不可分である場合には受贈者・受遺者(以下、「受贈者等」)と遺留分権利者で共有することになる。例外として、受贈者等に価額弁償の抗弁が認められ、実務では多くが価額弁償=金銭の交付であった。
自社株式の贈与であれば、後継者が100株の生前贈与を受けていたとして、25株が遺留分減殺請求の対象となる場合、25株分の贈与が無効となり、その25株は他の相続人(遺留分権利者)に帰属することになる。一方、後継者が価額弁償の抗弁をした場合には、後継者の保有株式は100株のままとなり、代わりに25株相当の金銭を他の相続人(遺留分権利者)に支払うことになる。遺留分を算定するための基礎財産が自社株式100株のみであるとして、この100株の贈与時の相続税評価額が1億円、相続時(贈与者死亡時)の時価が2億円であるならば、25株相当の金銭は、5,000万円(=2億円×25株÷100株)となる。つまり、相続時の時価で遺留分の金額を算定するということである。
平成22年に公表された事業承継税制に係る質疑応答事例の問41では、「贈与者の相続の開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合の贈与税の納税猶予の特例関係」について解説されている(22頁参照)。その解説では、遺留分減殺請求に伴い、後継者が適用対象株式を現物返還したとしても、①後継者が受けていた贈与税の納税猶予の適用について取り消されることはなく、②当初の贈与税の申告に係る課税価格及び贈与税額が過大となったときは、相続税法32条1項3号(更正の請求の特則)の規定に基づき更正の請求ができるとされている。事業承継税制においては、遺留分減殺請求に伴う現物返還を、後継者による株式の譲渡(期限確定事由)とは捉えないということである。
なお、問41には「(注2)特例受贈非上場株式等の返還によらず、現金等価額による弁償があった場合も上記と同様である。」との記述があることから、価額弁償による場合でも期限確定事由に該当しないと理解されていた方もいると思われる。しかし、この「同様である」とは、過大となった課税価格及び贈与税額について更正の請求ができるという意味であり、後継者が支払う資金を捻出するために行う自社株式の譲渡は、通常どおり期限確定事由になるようである。
贈与税の納税猶予の適用を受けている後継者が行う贈与税・相続税の更正の請求は、表1のようになるものと考える(民法相続法改正前)。
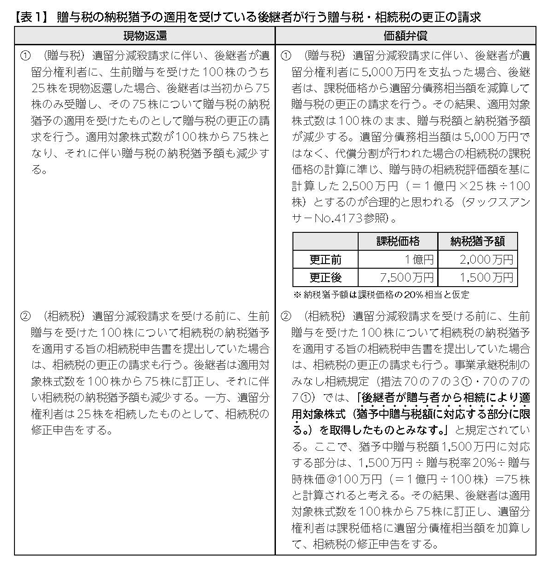
2 改正後の遺留分侵害額請求権
今年(令和元年)の7月1日以後に開始する相続からは、遺留分侵害額請求となる。遺留分権利者の権利は金銭債権化された。遺留分侵害額請求権が行使されても、贈与・遺贈は無効とならず事実の変更はない。遺留分権利者は、遺留分侵害額相当の金銭支払いのみを請求できるとされた。ただし、受贈者等と遺留分権利者とで合意すれば、金銭支払いに代えて現物分与をすることも可能である。
遺留分侵害額請求は2段階になると考える。遺留分に関する権利の行使(形成権の行使)を死亡後1年以内に行う。立法担当者の解説では、必ずしも金額を明示して行う必要はないとされている。これが第1段階である。第2段階では、遺留分権利者が受贈者等に対して具体的な金額を示してその履行を請求する。
この第2段階で遺留分権利者と受贈者等が金額についてのみ合意した場合、受贈者等は即日払いが原則となる。弁済期限の定めのない債務はその履行の請求の意思表示が受贈者等に到達した日の翌日から履行遅滞となり遅延損害金が発生するからである。受贈者等は資金を捻出するために資産の譲渡が必要であれば、そのための期間として、弁済期限も含めて遺留分権利者と合意する必要がある。弁済期限について合意できない場合は、受贈者等は遺留分権利者を相手方とする期限の許与を家庭裁判所に求めることになる。
金額(遺留分侵害額)について合意できない場合は、遺留分権利者が家庭裁判所に調停を申立てることになる。調停不成立の場合には地方裁判所等へ遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなり、受贈者等は期限の許与も含め、金銭債務額について反論を行うことになると考える。
自社株式や事業用財産の生前贈与が遡及して無効とならないので、事業承継を円滑に行うことができることになった。遺留分侵害額請求を受けたとしても、事業承継税制の適用対象株式数には影響が及ばない。ただし、遺留分権利者に支払う資金を捻出するために、受贈者等が資産を譲渡した場合には、譲渡所得税が課される。事業承継税制においても、後継者が適用対象株式を譲渡すれば、期限確定事由に該当することになる。
金銭支払いに代えて現物分与を行う場合も、代物弁済を行ったとして譲渡所得税が課される。受贈者等は当該資産を時価で譲渡したことになり、遺留分権利者は当該資産を時価で取得したことになる(所基通33-1の6・38-7の2)(表2参照)。事業承継税制においても、後継者が適用対象株式を現物分与した場合には期限確定事由に該当することになる。
【表2】所基通33-1の6・38-7の2
所得税基本通達33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した資産の取得費については、38-7の2参照
所得税基本通達38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したこととなる。
なお、遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金額が確定した場合、受贈者等は贈与税又は相続税の更正の請求を行うことができる(相法32①三)。相続税の更正の請求について代償分割の場合に準じて行うという点は、遺留分減殺請求を受けた場合(民法改正前)の実務から変更はない。
Ⅱ 事業承継税制の適用を受ける後継者が民法相続法改正後の遺留分侵害額請求を受けた場合の対応
自社株式の取得が贈与・遺贈のいずれによるのか、及び、遺留分侵害額請求を受けたタイミングにより後継者の対応は異なる。
以下では、遺留分を算定するための基礎財産が自社株式100株のみであり、25株が遺留分侵害額請求の対象になるというシンプルなケースを前提に、金銭支払いによる場合と現物分与による場合を比較する。なお、金銭支払いによる場合は、25株を発行会社に譲渡することにより資金を捻出したことにする。
1 相続税の申告期限前に遺留分について検討した場合
① 贈与により取得した自社株式100株が遺留分を侵害しているケース
贈与者(先代経営者)の死亡により、納税猶予を受けていた贈与税は免除されるが、自社株式100株を相続により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。
金銭支払いによる場合は、自社株式25株を発行会社に譲渡して資金を捻出し、遺留分権利者に支払う。残りの75株について相続税の納税猶予の適用を受けることができる。後継者は25株の譲渡について所得税が課されるが、みなし配当特例(措法9の7)と取得費加算特例(措法39)が適用できる。ちなみに、いずれの特例においても、みなし相続により取得した財産の譲渡も適用対象に含まれている。
(文書回答 平成24年4月17日東京国税局 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)、措通39-12)
現物分与による場合は、自社株式25株を遺留分権利者に移転する。残りの75株について相続税の納税猶予の適用を受けることができる。後継者は25株の現物分与について所得税が課されるが、取得費加算特例(措法39)が適用できる。遺留分権利者が現物分与により取得した自社株式は相続により取得したものではないことから、みなし配当特例(措法9の7)と取得費加算特例(措法39)を適用する余地はない。
| 侵害額請求+金銭支払 | ・(後継者)100株をみなし相続 ・(後継者)75株は納税猶予の適用を受ける/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
| 侵害額請求+現物分与 | ・(後継者)100株をみなし相続 ・(後継者)75株は納税猶予の適用を受ける/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)取得費加算特例の適用が可能 ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用余地なし |
② 遺贈により取得した自社株式100株が遺留分を侵害しているケース
(A)遺留分侵害額請求がなされる前に後継者と遺留分権利者との間で協議を行う対応が考えられる。遺贈を放棄した上で遺産分割協議を行い、後継者が75株、遺留分権利者が25株を相続するというような対応である。この場合、後継者に譲渡所得課税はなく、75株について相続税の納税猶予の適用を受けることができる。遺留分権利者は、25株を相続により取得しているので、当該25株を譲渡する場合には、みなし配当特例(措法9の7)と取得費加算特例(措法39)が適用できる。
| 遺贈の放棄+遺産分割期限内協議 | ・(後継者)75株を相続/(遺留分権利者)25株を相続 ・(後継者)75株は納税猶予の適用を受ける ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
(B)協議が整わず遺留分侵害額請求がなされた場合の対応は、上記①を参照のこと(みなし相続による取得か、相続による取得かの違い)。遺贈株式について相続税の申告期限前に1株でも譲渡した場合は、相続税の納税猶予において特例経営承継相続人の要件を満たさないので注意が必要である。
| 侵害額請求+金銭支払 (申告期限後に実行すること) |
・(後継者)100株を相続 ・(後継者)75株は納税猶予の適用を受ける/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
| 侵害額請求+現物分与 (申告期限後に実行すること) |
・(後継者)100株を相続 ・(後継者)75株は納税猶予の適用を受ける/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)取得費加算特例の適用が可能 ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用余地なし |
2 相続税の申告期限後に遺留分侵害額請求を受けた場合
① 贈与により取得した自社株式100株が遺留分を侵害しているケース
贈与者(先代経営者)の死亡により、納税猶予を受けていた贈与税は免除されるが、自社株式100株を相続により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。みなし相続した100株について相続税の納税猶予を適用した後に遺留分侵害額請求を受けた場合の対応は2通り考えられる。
(C)事業承継税制に係る質疑応答事例の問41に倣い、贈与税の更正の請求から始めて、その後に相続税の更正の請求を行う方法である。具体的な更正の請求の内容は、金銭支払い・現物分与のいずれにおいても、(改正前の)遺留分減殺請求に伴い、価額弁償した場合と同じになると思われる。
(C)の方法では相続税の納税猶予の適用対象株式数は75株となり、(D)の方法では適用対象株式数100株のうち25株が期限確定する。(C)の方法では、自社株式の譲渡や現物分与が行われても、相続税の納税猶予の適用を受けていない株式から優先的に譲渡したものとみなされるため(措令40の8の2等)、期限確定を免れる。相続税の納税猶予の適用開始から期限確定までの期間が短いことが想定されるので、利子税は僅かであり、(C)の方法と(D)の方法に大差はない。ただし、全部期限確定のリスクを考えると(C)の方法(贈与税の更正の請求から始める方法)のほうが無難であると言える。
| 侵害額請求+金銭支払 | ・(後継者)100株をみなし相続するが贈与税の更正の請求により、みなし相続は75株 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式が75株に修正/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
| 侵害額請求+現物分与 | ・(後継者)100株をみなし相続するが贈与税の更正の請求により、みなし相続は75株 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式が75株に修正/25株は譲渡所得課税 ・(後継者)取得費加算特例の適用が可能 ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用余地なし |
(D)相続税の更正の請求のみ行う方法である。(改正後の)遺留分侵害額請求では贈与が遡って無効になるわけではないし、贈与者の死亡により贈与税が免除されているのであれば、相続税の更正の請求のみで対応可能ではないかと思われる。この場合、適用対象株式数は100株のまま変わらず、後継者は更正の請求(課税価格から遺留分債務相当額を減算)を行い、遺留分権利者は修正申告(課税価格に遺留分債権相当額を加算)を行うことが想定される。金銭支払いの資金を捻出するための自社株式の譲渡や、自社株式の現物分与が行われれば、相続税の納税猶予額が期限確定する。経営承継期間内に自社株式の譲渡や現物分与が行われてしまった場合には、納税猶予額の全部が期限確定してしまうので注意が必要である。
| 侵害額請求+金銭支払 | ・(後継者)100株をみなし相続 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式は100株/25株は譲渡所得課税及び納税猶予の期限確定(全部期限確定への配慮が必要) ・(後継者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
| 侵害額請求+現物分与 | ・(後継者)100株をみなし相続 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式は100株/25株は譲渡所得課税及び納税猶予の期限確定(全部期限確定への配慮が必要) ・(後継者)取得費加算特例の適用が可能 ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用余地なし |
② 遺贈により取得した自社株式100株が遺留分を侵害しているケース
相続税の更正請求を行うことになる(上記2①(D)の方法を参照)。ただし、遺贈について遺留分侵害額請求が行われた場合には、経営承継期間内に自社株式の譲渡や現物分与を行うことがほとんどと思われるので、全部期限確定のリスクが高いと言える。したがって、遺贈の場合は上記1②(A)を参考に申告期限内に対応したい。
| 侵害額請求+金銭支払 | ・(後継者)100株を相続 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式は100株を受けた/25株は譲渡所得課税及び納税猶予の期限確定(全部期限確定の可能性大) ・(後継者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用が可能 |
| 侵害額請求+現物分与 | ・(後継者)100株を相続 ・(後継者)納税猶予の適用対象株式は100株を受けた/25株は譲渡所得課税及び納税猶予の期限確定(全部期限確定の可能性大) ・(後継者)取得費加算特例の適用が可能 ・(遺留分権利者)みなし配当特例と取得費加算特例の適用余地なし |
(参考)
問41 特例受贈非上場株式等の修正(2):贈与者の相続の開始に伴い遺留分減殺請求がなされた場合の贈与税の納税猶予の特例関係
(問)子Aは、父から認定贈与承継会社に係る非上場株式等の贈与を受け、適法に贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、贈与者である父が死亡したため、特例の適用を受けていた猶予中贈与税額に相当する贈与税について免除届出書等必要な書類を提出し、免除された。
ところで、贈与者である父の死亡に係る遺産の相続に関し、子Aに対し遺留分権利者である子Bから遺留分の減殺請求がなされ、子Aは亡くなった父から贈与を受けた特例受贈非上場株式等の一部を子Bに返還した。
この場合に、子Aが子Bに対し特例受贈非上場株式等の一部を返還することにより、子Aが適用を受けていた贈与税の納税猶予の特例について、措置法第70条の7第1項に規定する特例の対象となる贈与に係る要件を満たさないこととして遡及して取り消されることになるのか。
また、子Aが特例受贈非上場株式等を子Bに返還したことにより、当初の贈与税の申告における課税価格及び贈与税額が過大となったときは、子Aは、相続税法第32条第3号の規定に基づき更正の請求をすることができるのか。
(答)
子Aが適法に受けていた贈与税の納税猶予の特例の適用について、特例適用時に遡及して取り消されることはない。
なお、子Aは、特例受贈非上場株式等を子Bに返還したことにより、当初の贈与税の申告に係る課税価格及び贈与税額が過大となったときは、相続税法第32条第3号の規定に基づき更正の請求をすることができる。
(注1)子Aが贈与者である父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告において措置法第70条の7の4(贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例)の規定の適用を受けている場合には、遺留分の減殺請求があったことにより、子Aは遺留分権利者である子Bに対し返還した特例相続非上場株式等を有しないこととなるため、当該返還した株式等に係る特例相続非上場株式等は、贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の対象とならない。したがって、子Aは、特例相続非上場株式等を返還したことにより、父の死亡による相続又は遺贈に係る相続税の申告における課税価格及び相続税額が過大となったときは、相続税法第32条第3号の規定に基づき、当該相続税の申告について更正の請求をすることができる。
(注2)特例受贈非上場株式等の返還によらず、現金等価額による弁償があった場合も上記と同様である。
(解説)
1 特定遺贈及び遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求により遺留分権利者が取り戻した財産がどこに帰属するのかについて、判例は、取り戻した財産は、遺産分割の対象となる「遺産」には帰属しないとし、遺留分権利者の固有財産として直接帰属するとしている。(参考) 昭和51年8月30日最高裁第二小法廷判決(昭和50年(オ)第920号)では、「遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得をした権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するものと解するのが相当」としている。
また、平成8年1月26日最高裁第二小法廷判決(平成3年(オ)第1772号)では、「遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。特定遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはなく、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め(1031条)、遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね(1031条、1043条参照)、減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する(1036条、1037条、1039条、1040条、1041条参照)など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。」としている。
2 問は、子Aが亡父から受けた生前贈与に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使したものであるが、判例に沿って整理した場合、遺留分の減殺請求があったことにより遺留分権利者である子Bに対し返還した特例受贈非上場株式等は、その返還時にいったん遡及的に贈与者である父の所有に帰属するものではないと考えることが適当であることから、子Aが適用を受けていた贈与税の納税猶予の特例について、遡及して措置法第70条の7第1項に規定する特例の対象となる贈与の要件を満たしていたかどうかを判定する必要はないものと考えられる。したがって、子Aが適法に受けていた贈与税の納税猶予の特例の適用については、特例適用時に遡及して取り消されることはない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















