解説記事2021年03月08日 ニュース特集 国税当局が注意喚起 共通ポイントの課税上の取扱い(2021年3月8日号・№873)
ニュース特集
ポイント運営会社と加盟店の合意内容により異なる取扱い
国税当局が注意喚起 共通ポイントの課税上の取扱い
ポイント経済圏の拡大にともなって、ポイント制度に係る課税上の取扱いについて多くの疑問が提起されてきた。しばらく統一的な取扱いが確立されているとは言えない状態にあったが、令和2年1月14日に公表されたタックスアンサー等を中心に、徐々に国税庁から見解が公表されてきている。しかし、ポイント運営会社と加盟店の間の取引を巡る課税関係などまだ明確にされていない点も多く、過去には納税者と国税当局の間で争いになった事例も存在する。
ポイント制度の課税上の取扱いを判断するに当たっては、ポイント制度の私法上の法律関係を把握することが不可欠となる。ポイントの法的性質は当事者間の合意によって決まるため、最近は国税当局も、規約等で当事者間の合意内容を明確にするよう、セミナー等で納税者や実務家に注意を呼びかけている。
ポイント制度には、大きく分けて、発行から利用までその事業者が独自に運営する自社発行型と、他社が運営する共通ポイント制度に加入する共通型とがある。本特集では、それぞれのポイント制度を巡る課税上の論点と過去に国税当局と争いになった事例などを紹介する。
1.自社発行型ポイント制度を巡る論点
所得税の取扱い
まず、自社ポイントの所得税の取扱いについては、国税庁から示されている見解として「タックスアンサー(所得税)No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(令和2年1月14日)」がある。
そこでは、ポイントの取得又は使用は課税対象となる経済的利益には該当せず、原則として確定申告をする必要がないことが明らかにされている。ただし、ポイントの付与を景品とする抽選に当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、使用したポイント相当額を一時所得の計算上、総収入金額に算入することや、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合などには、医療費控除額の計算上考慮(ポイントによる値引き分は控除対象外)が必要であることが示されている。
消費税の取扱い
消費税の取扱いについては、一般的に、顧客の買物の金額に応じたポイントの付与は、ポイント相当額に応じて買物ができる権利又は値引きを受ける権利などの権利の行使が未だ行われていないとして、消費税の課税関係は生じないとされている。
顧客によるポイントの行使については、国税庁から「タックスアンサー(消費税)No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(令和2年1月14日)」が示されており、商品購入時にポイントを使用した場合の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、①ポイント使用が「対価の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)となり、②ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には、商品対価の合計額(全額)となるとされている。なお、①と②のどちらに該当するかは、レシートの表記から判断してよいとされている。
経理処理についても、国税庁から「企業発行ポイントの使用に係る経理処理(令和2年1月14日)」が公表されており、①ポイント使用後の支払金額を経費算入する処理(値引処理)と、②ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともに、ポイント使用額を雑収入に計上する処理(両建て処理)の両方の処理が示されている(図表1参照)。
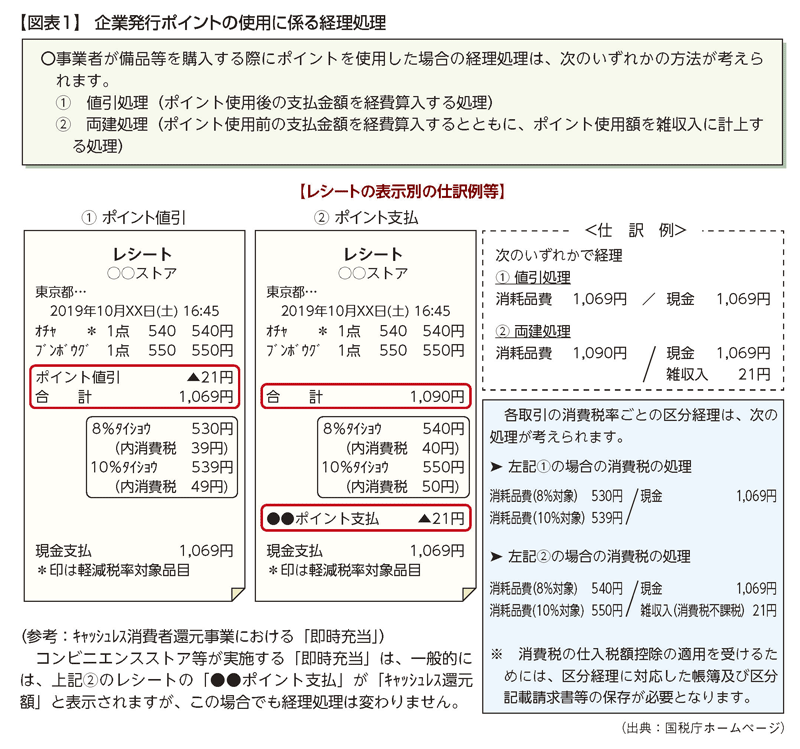
法人税の取扱い
法人税の取扱いに関しては、平成30年に「収益認識に関する会計基準」の取扱いに対応して、法人税基本通達2−1−1の7「ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位」が新設され、一定の要件に該当する場合には、継続適用を条件として、「当該自己発行ポイント等について当初の資産の販売等とは別の取引に係る収入の一部又は全部の前受けとすることができる」とされた。これにより法人税と消費税でポイントに対応する部分の収益の認識のタイミングが異なることとなった。国税庁からは、「収益認識基準による場合の取扱いの例」(平成30年5月)が公表されており、法人税における所得金額の計算上益金の額に算入する金額と消費税における課税資産の譲渡等の対価の額がそれぞれ異なる事例の一つとして「ケース1 自社ポイントの付与」が挙げられている(図表2参照)。
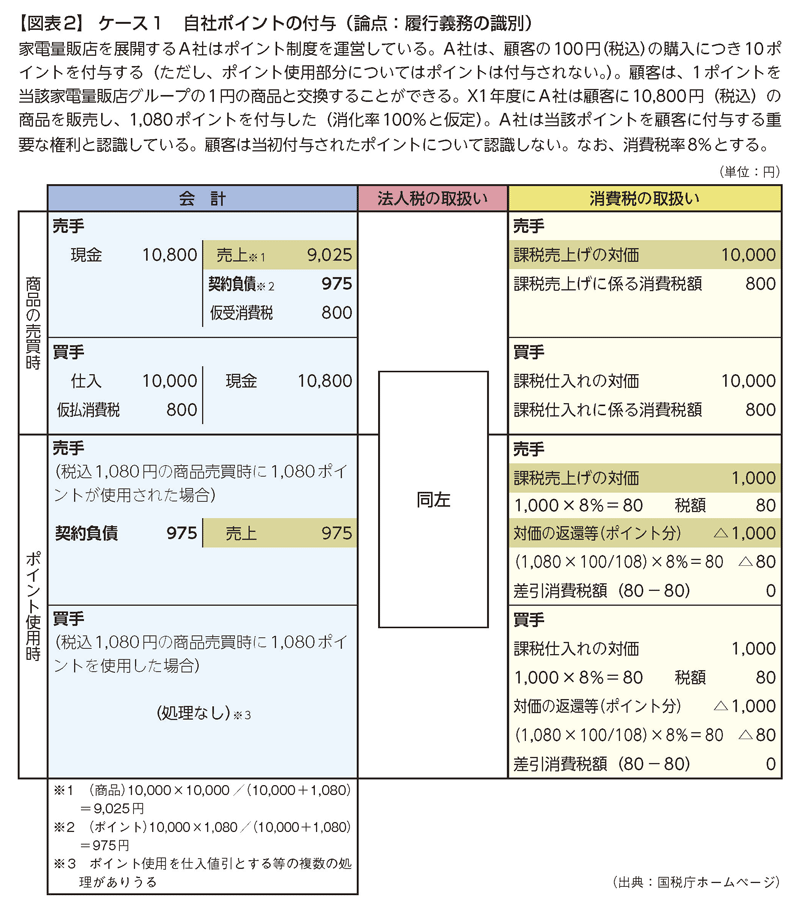
自社ポイントを巡り争われた事例
自社ポイントの課税関係を巡り争われたケースとして、以下のように複数の事例があるが、いずれもポイント制度の課税関係を判断するためには、ポイント制度の私法上の法律関係を把握することが必要であることを表している。
| 東京地裁令和元年10月24日判決(平成29年(行ウ)第403号) |
| アニメのキャラクター商品の販売等を行う会社が、顧客に付与したポイントについて、各事業年度末におけるポイント未使用分に相当する金額が損金算入できるかどうかが争われた事件。処分行政庁が、ポイント未使用分に相当する金額は債務が確定していないとして損金算入を否認したことから訴訟に至ったもの。東京地裁は、原告のポイントシステムについて、ポイントが失効して使用されなくなる可能性があることに加えて、次回購入時における代金充当の選択又は景品交換の選択がされない限り、その債務に基づいて給付をすべき具体的内容が明らかにならないため、これに伴う費用が発生したとはいえず、その費用の金額を合理的に算定することができるともいえないと指摘。法人税基本通達2−2−12に定める債務確定要件を充足していると認めることができず、本件各事業年度の終了の日までに債務が確定していないと判断した。 |
| 東京地裁平成26年2月18日判決(平成25年(行ウ)第23号) |
| 会員制リゾートクラブの会員から入会時に受けた金員の収受が、消費税法上の「資産の譲渡等」(課税取引)に該当するか否かを巡り争われた事件。 東京地裁は、「課税は私法上の法律関係に即して行われるべき」との観点から、入会契約時における双方の共通認識や契約に至る経緯等の検討を行い、本件金員は、資産の譲渡等の対価である「入会金(消基通5−5−5)」ではなく、入会時に付与される宿泊ポイント(会員が提携ホテル利用時に宿泊料金等の精算として使用できるもの)の対価であり、物品切手等の発行の対価(不課税)にあたるとして、本件金員の収受を課税売上とした課税処分を取り消した。 |
| メルカリに対する更正処分 平成30年5月(本誌742号参照) |
| メルカリは、商品購入者が支払った商品購入の対価のうち「無料で付与されたポイント」により支払われた分を、購入者にマーケットに参加してもらうためにメルカリが負担している費用として課税仕入れとして処理していたが、課税当局は、当該費用には対価性がなく、消費税法上の課税仕入れにはならない(不課税)として更正処分を行った。 |
2.共通ポイント制度を巡る論点
加盟店及び顧客の処理
共通ポイントの法人税・消費税の取扱いについては、一般的な処理例として、「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例(令和2年1月14日)」が国税庁から公表されている(図表3及び4参照)。
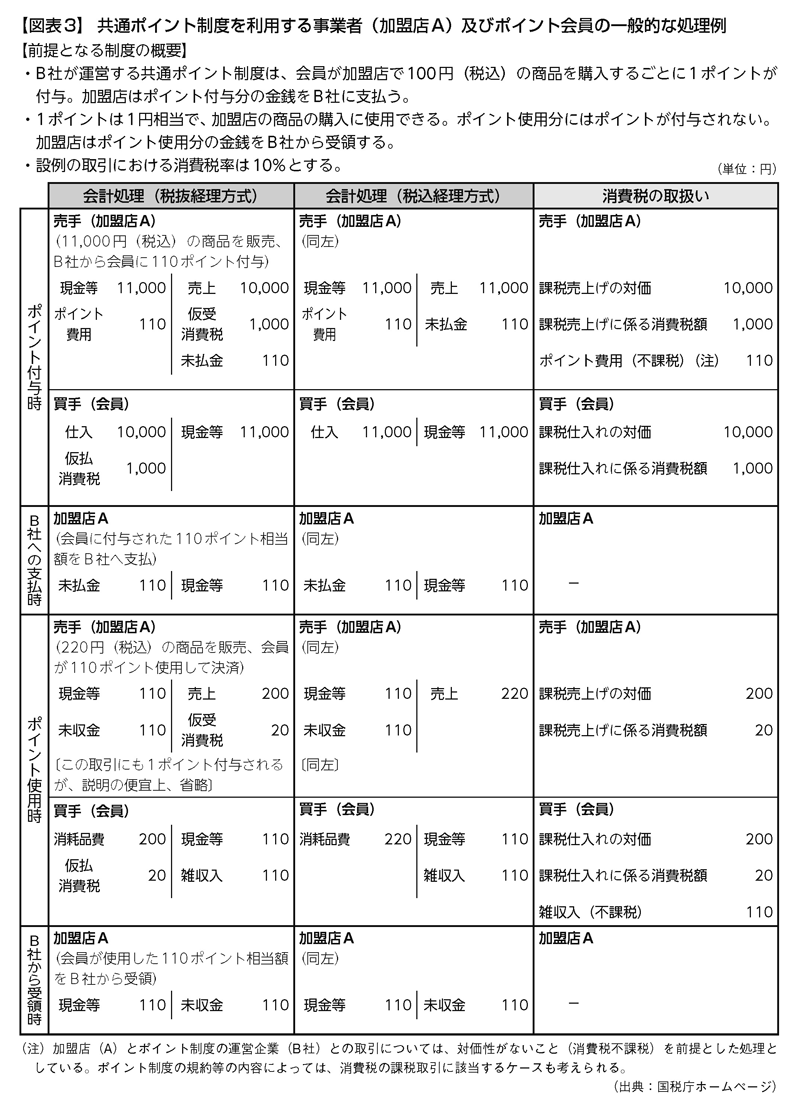
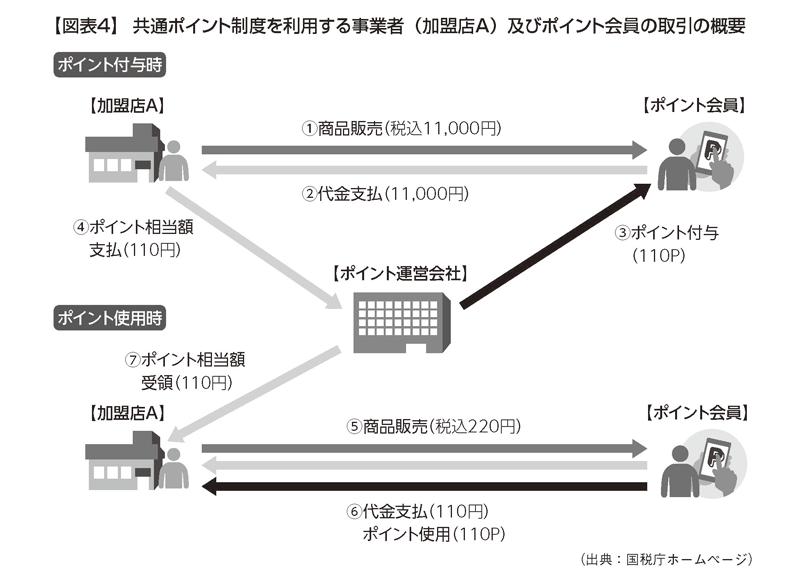
この処理例は、上記1の収益認識会計基準を適用しない中小法人や個人事業者を前提としたものであり、上記1の「収益認識基準による場合の取扱いの例」とは異なり、法人税と消費税の収益認識のタイミングは一致する。
図表3によれば、加盟店と顧客(ポイント会員)の会計処理及び消費税の取扱いは以下のとおりとなる(下記の①〜⑦は図表4の取引の概要図(以下「概要図」)の①〜⑦と一致)。
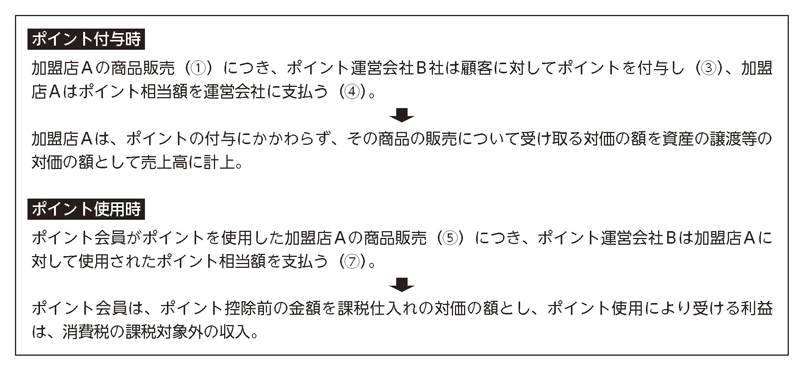
ポイント運営会社と加盟店の取引
ここで注意したいのが、加盟店Aと運営会社B社との間の取引の取扱いだ。図表3の表の下の注意書きには、「(注)加盟店(A)とポイント制度の運営企業(B社)との取引については、対価性がないこと(消費税不課税)を前提とした処理としている。ポイント制度の規約等の内容によっては、消費税の課税取引に該当するケースも考えられる。」とある。これは、法的性質に応じた判断が必要になることを示している。
具体的には、加盟店Aが運営会社B社に支払うポイント負担金の取扱いについて(概要図の④)、債権債務の精算、つまりB社が負担する将来の支払債務に備える金銭をA社が負担する性格のもの(B社にとっては預り金又は仮受金の性格を有するもの)であり不課税とされるケースと、B社のポイント制度の提供に対して支払うもの、つまり役務提供の対価(課税仕入れ)とされるケースがあるということである。後者の場合には、販売促進費などとして経理処理されるようだ。
実際、この取扱いを巡り国税当局と納税者との間で争いになった事例が存在する。過去の裁決では、前頁のとおり、加盟店Aが運営会社Bに支払うポイント負担金(概要図の④)は対価性がある(課税売上げ)と判断され、運営会社Bが加盟店Aに支払うポイント相当額(概要図の⑦)は対価性なし(不課税)と判断されたケースが見られる。
【請求人(ポイント運営会社)が受け取るポイント負担金(概要図の④)の取扱い→課税売上げとされたケース】
| 平成28年5月27日裁決(大裁(諸)平成27年第61号) |
| 提携法人から支払を受ける金員(本件金員)は、請求人が行うポイント還元の原資であることから、役務の提供の対価には該当しないとする請求人の主張に対し、審判所は、提携法人からの依頼により顧客にポイントを付与し、その付与したポイントに基づき行う決済額からの割引が「役務の提供」に該当することは明らかであり、仮に、本件金員にポイント還元の原資の側面があったとしても、本件金員は、当該役務提供を条件として提携法人から請求人に支払われたという対応関係があるものと認めることができると判断した。 |
【請求人(ポイント運営会社)が支払うポイント相当額(概要図の⑦)の取扱い→不課税とされたケース】
| 平成26年7月2日裁決(東裁(諸)平成26年第5号) |
| 請求人が加盟店から使用済みのお買物券を引き取る際に支払った金額(本件支払金額)は、加盟店に対する商品交換業務の委託料であるから課税仕入れに該当するとの請求人の主張に対し、審判所は、本件支払金額の支払は、物品の給付等を行った加盟店に対し、当該物品の給付等の際に顧客が負担しなかった支払債務を請求人が精算したもの、又はポイントとの引換えに顧客に交付された加盟店発行のお買物券(物品切手等の発行)の代金を請求人が支払ったもの(不課税)と判断した。 また、請求人が加盟店にポイントを発行した際に受領した金員には、ポイントの管理業務のほか、加盟店の顧客に対し商品交換を行う業務の対価が含まれているのであって、顧客がポイントとお買物券の交換を選択した場合、加盟店がその商品交換業務を行い、請求人はその交換業務を免れることから、本件支払金額は、商品交換業務の委託料の支払額、すなわち売上げに係る対価の返還等の金額に該当するとの請求人の主張に対しては、審判所は、顧客の有するポイントの回収と引換えにお買物券を引き渡しており、その時点で商品交換の責務を果たしているものと認められる一方、請求人が加盟店に商品交換業務を委託した事実の存在や、請求人と加盟店との間において、請求人が加盟店に対し商品交換業務の履行に対する報酬を支払う旨を合意した事実の存在を認めるに足る証拠もないことから、売上げに係る対価の返還等の金額に該当しないと判断した。 |
ポイント交換の取扱い
ポイント交換については、統一的な見解は公表されていない。ポイント交換に際して受け取るポイント負担金の収受は、預り金の性格を有するもので消費税の課税対象にはならないとする見解がある一方、以下の裁決においても、上記の裁決の考え方と同じように、加盟店から運営会社へのポイント負担金の支払い(概要図の④)は、後払い決済額からの割引という「役務の提供」の対価(課税売上げ)であるとする考え方、及び運営会社から加盟店へのポイント相当額の支払(概要図の⑦)は不課税とする考え方が見られる。
規約等で当事者間の合意内容を明確にすべき
上記のとおり裁決事例はいくつかあるが、結局のところ、法的性質がどのように判断されるかは、各事例の事実関係に応じて異なってくると思われる。
国税当局の担当者によれば、ポイント制度の普及にともなって、この取扱いに関する納税者からの問い合わせも増えているが、規約や契約書、請求書などにおいて当事者間の合意内容が示されておらず、法的性質の判断が困難なケースが多くみられるとのことだ。国税当局は、例えば、役務提供の対価であるとするならば、「システム使用料として(消費税別)」というような文言を記載するなど、規約や契約書等で当事者間の合意内容を明らかにするよう呼びかけている。消費税上の取扱いを巡って国税当局との争いに発展しないよう、規約等で合意内容を明確化しておくべきだろう。
| 平成30年8月21日裁決(大裁(諸)平成30年第6号) |
| 請求人は、請求人が発行した後払方式のカードを利用して会員が加盟各社で商品購入等をする都度、利用金額に応じたポイント(本件ポイント)を付与し、毎月の利用額(後払決済額)を会員に請求する際に、たまったポイントに応じた金額を後払決済額から割り引く(本件ポイント還元)ほか、会員に対し、提携法人のポイントと引換えに、本件ポイントの付与を受けることができるサービス(本件ポイント交換)を行っていた。 審判所は、本件ポイント交換により請求人が提携法人から受領する金員について、本件ポイント交換による本件ポイントの付与に基づく後払決済額からの割引が「役務の提供」に該当し、本件金員は当該役務の提供の対価に当たるとして、本件ポイント交換は「資産の譲渡等」に該当すると判断した。 なお、たまったポイントに応じた金額の後払決済額からの割引(本件ポイント還元)については、本件ポイント相当額を後払決済額から割り引くことにより会員に還元するものであり、後払決済額は、会員が加盟各社において商品購入等を行った対価を請求人が加盟各社に支払ったことによる会員に対する求償権に係るものであり、請求人自らが行った課税資産の譲渡等の対価ではないと判断した。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















