解説記事2021年04月19日 SCOPE 日本ガイシ、海外子会社とのロイヤルティ取引巡り勝訴(2021年4月19日号・№879)
移転価格課税、処分の大部分が取消し
日本ガイシ、海外子会社とのロイヤルティ取引巡り勝訴
日本ガイシ(株)が海外子会社との間で行ったロイヤルティ取引に対する移転価格課税の適法性を巡り争われていた事件で、東京地裁民事51部(清水知恵子裁判長)は令和2年11月26日、原告の請求をほぼ認め課税処分の大部分を取り消した(約58億円)。東京地裁は、残余利益分割法における残余利益の分割要因について、「重要な無形資産以外の利益発生要因についても考慮すべき」という注目の判断を示した。
東京地裁、「超過減価償却費」も残余利益の分割要因に加えるべき
本事案で課税処分の対象となったのは、セラミックス製品の製造等を行う日本ガイシ(株)(原告)が、ディーゼル車用の微粒子除去フィルター(本件製品)の製造を行うポーランド子会社(本件国外関連者)との間で締結した、本件製品の製造に関する特許権やノウハウ等の無形資産の使用に関するライセンス契約に係る取引(国外関連取引)である。国は、無形資産の使用の対価として日本ガイシが受け取るロイヤルティの額が独立企業間価格に満たないとして移転価格税制を適用した(国の算定方法について図表参照)。
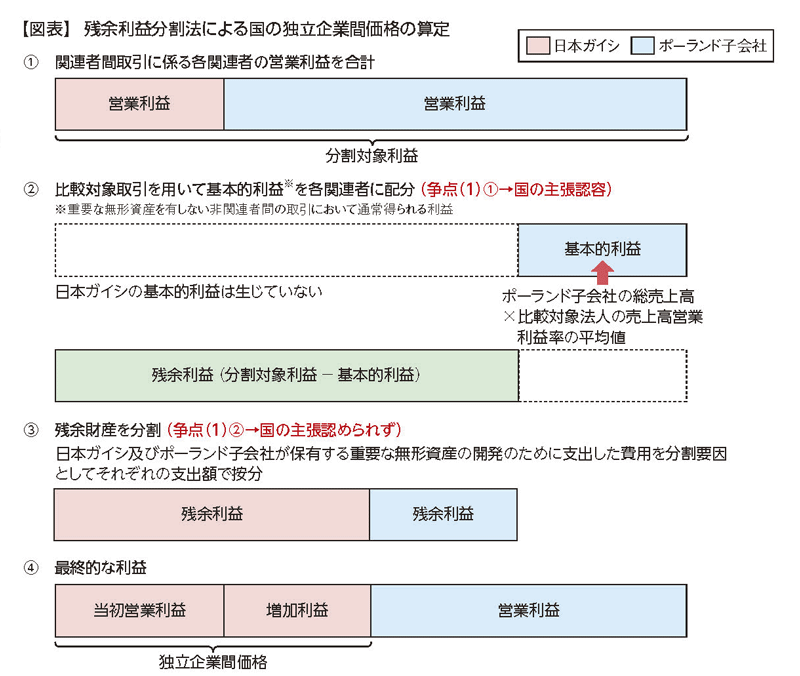
本事案の背景には、ディーゼル車の台数が多いEUにおいて自動車の排ガス規制が強化されていく中で(Euro規制)、その規制基準を満たす有用なものとして本件製品の需要が急増したことがある。
日本ガイシは、Euro規制等による影響などの市場条件や、本件国外関連者による大規模な設備投資により生じた多額の減価償却費等について、(1)基本的利益の算定における比較対象法人の選定に当たり考慮されるべきであること(争点(1)①)、仮に基本的利益の算定方法に誤りがないとした場合には、(2)残余利益の分割要因として考慮されるべきであること(争点(1)②)などを主張した。
これに対し東京地裁は、(1)国の基本的利益の算定は相当であるとして原告の主張を認めなかったが、(2)残余利益の分割については、重要な無形資産の開発に係る原告及び本件国外関連者の各支出額のほかに、本件国外関連者等に係る超過減価償却費を分割要因に加えて配分するのが相当であるとして、原告の主張を一部認めた。
東京地裁は、まず本件超過利益の発生メカニズムについて、①EU市場におけるセラミックス製DPFの需要の急増、②本件国外関連者によるEU市場への早期の参入、③2社寡占状態の継続による高いシェアの維持、④売上高の増大に伴う規模の利益、⑤生産効率の向上を利益発生要因とするものであると指摘した。そして、これらの要因について、原告が主張するように本件の基本的利益の算定において考慮することはできないとしたが、「本件のように重要な無形資産とともに他の複数の利益発生要因が重なり合い、相互に影響しながら一体となって得られた超過利益(残余利益)について、合理的に配分するためには、重要な無形資産以外の利益発生要因に関しても、その寄与の程度の推測にふさわしい要素(分割要因)を適切に考慮すべきである。」との判断を示した。
その上で、「本件設備投資は、本件超過利益をもたらした複数の利益発生要因に関して重要な貢献をしているものと認められるから、本件設備投資に係る減価償却費につき、残余利益の分割要因とするのが相当である。」と結論づけた(そのほかの原告が主張する分割要因は考慮されず)。そして、超過減価償却費を分割要因に加えて残余利益を算定した結果、本件ロイヤルティの額が独立企業間価格を超える年分については課税処分が取り消されることとなった。
この判決を受け、国が令和2年12月9日付で控訴している。また、本件と同様の取引に係る平成23年~27年3月期に係る処分についても東京地裁で係争中となっている。残余利益の分割要因について「重要な無形資産以外の利益発生要因についても考慮すべき」と本事案で示された判断が控訴審やもう一つの地裁案件でも支持されるのか注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















