解説記事2019年11月25日 ニュース特集 速報 デジタル課税「第2の柱」のポイント(2019年11月25日号・№812)
ニュース特集
税負担割合の算定方法次第では所得合算ルールに抵触の恐れ
速報 デジタル課税「第2の柱」のポイント
OECDは11月8日、デジタル課税の「第2の柱(Pillar2)」(ミニマム・タックス)に関する公開討議草案を公表した。
ミニマム・タックスには「所得合算ルール」「軽課税支払ルール」「subject to taxルール」などのルールがあるが、今回は所得合算ルールに絞った内容となっている。
その中では「課税ベースの決定(特に税務・会計数値の差異の調整)」「税率のブレンディング(税負担割合の算定方法)」「適用除外」という3つの論点が示されている。東南アジア等で合法的な税制優遇を受けている日本企業は、これらの論点のうち「税率のブレンディング」と「適用除外」の制度設計次第では、税負担割合の低下及び所得合算ルールへの抵触という形で大きな影響を受けることになる。
本特集では、「第2の柱」における各論点のポイントと企業への影響を解説する。
所得合算ルールでは能動的所得も合算対象に
OECDが検討を進めているデジタル課税には、デジタル課税のうちネクサス及び利得配分に関する国際課税原則の見直しを取り扱う「第1の柱(Pillar1)」と、軽課税国への利益移転に対抗する措置(ミニマム・タックス)である「第2の柱(Pillar2)」があるが、OECDは10月9日に公表した「第1の柱」の公開討議草案(ディスカッション・ドラフト=DD)に続き、第2の柱のDDを11月8日に公表した。
第2の柱であるミニマム・タックスには、主に(1)所得合算ルール、(2)軽課税支払ルール(42頁参照)、(3)subject to taxルール(42頁参照)の3つのルールがある。
今回公表された第2の柱のDDは、上記のうち「所得合算ルール」に絞った内容となっている。所得合算ルールとは、ミニマム税率に達していなければ基本的にその税率まで機械的に課税を行うというものであり、このルールの下では、(適用除外を定めない限り)能動的な所得も含め合算されることになる(図参照)。
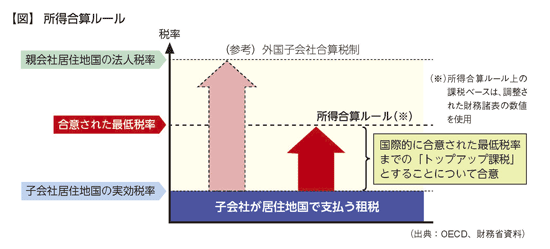
DDでは、所得合算ルールについて、「税務・会計数値の差異の調整」「税率ブレンディング(税負担割合の算定方法)」「適用除外」という3つの論点が提示されている。以下、それぞれの論点について解説する。
論点1 税務・会計数値の差異の調整
年度間の調整を行うことで一時差異による影響を“平準化”
所得合算ルールではまず「課税ベース」をいかに計算するかということが問題になるが、この点についてDDでは、親会社の連結財務諸表(IFRS、USGAAP、JGAAP等)を基礎に算出することが示唆されている。
これは、仮に親会社所在地国の国内税制(CFC税制を含む)に基づいて課税ベースを計算した場合、各国間で課税ベースが異なるため公平性が保てない上に、子会社所得の再計算等の手間がかかるからだ。
とはいえ、そもそも会計数値と税務数値は異なるため、会計数値をそのまま使うわけにはいかない。そこでDDでは、会計数値を基礎に「一定の調整」が必要である旨指摘している。具体的には、まず配当等の永久差異の取扱いを検討した上で(除外すべきものは除外することとする)、次に一時差異(償却方法によるもの、欠損金によるもの、分割払いによるもの、その他)について検討する。
ここでいう一時差異とは、会計と税務における取り扱いの差に起因する期ズレであり、将来加算一時差異も将来減算一時差異もいずれは解消するものである。この点、ミニマム・タックスにおける課税ベースの算定の際、一時差異の調整(会計数値を税務数値に合わせること)を一切行わないとすると、ある事業年度を切り出した場合の数値は、本来あるべき税務数値に比べ、過大または過少に算出されることになる。一方で、個別項目の調整をどこまで行うのかという問題もある。
こうした中、DDでは、一時差異の調整方法として3つのアプローチが提案されている。いずれも、年度間の調整を行うことで一時差異による影響を“平準化”することを意図している。
第1のアプローチは「繰越型」と言えるもの。例えば、子会社がある事業年度でミニマム税率以上の税額を支払っているのであれば、翌年度、ミニマム税率に満たない税額であったとしても、前年度の「超過税額」を繰り越せるという案が出ている。逆にある事業年度において親会社で所得合算ルールが発動され、ミニマム税率に基づく税額を支払った場合には、翌期において所得合算ルールが発動されなければ還付を行う案、また、会計上の損失を「会計上も」繰越控除する案も出ている。
第2のアプローチは、そもそも税効果会計の数値を活用すれば、一時差異による事業年度間のズレを最初から平準化できるのではないかというもの、第3のアプローチは、複数年度の所得金額と支払税額の平均値をとれば、一時差異の影響額は平準化されるのではないかというものである。
企業にとって、複数年度での数値の管理が求められるという点で、第1のアプローチと第3のアプローチは、新たな事務負担を生むことになろう。DDでは、第3のアプローチに関する記述が薄く、第1及び第2のアプローチを中心に検討しているようにも見える。
論点2 税率のブレンディング(税負担割合の算定方法)
各方式への評価は国によってかなりの温度差
ここでは、ミニマム税率と比較する税負担割合をどのように算定するかが論点となるが、この点についてDDでは、「全世界」「国ごと」「事業体ごと」のいずれにより算定すべきか、問題提起を行っている。
このうち最も簡易な方法とされるのが「全世界方式」だ。また、全世界方式は上記の一時差異による歪みもグループ内の数値を集合することで平準化・吸収できるという利点を持ち、さらに高税率国(例えば日本、ドイツ、フランス等)の数値と低税率国(無税国、アイルランド等)の数値をブレンドすることで、税負担割合を高めに見せることができるなどの特長がある。米国のGILTI(グローバル軽課税無形資産所得)と同じとまでは言えないが、近い方式との見方もある。全世界方式は、アイルランドやシンガポールなどが主張しているとされる。
ただし、全世界方式では、ミニマム税率が低いと抜けが生じてしまうことから、「国ごと」または「事業体ごと」にブレンドする方式に比べ、ミニマム税率を高めに設定しなければならない。もっとも、現時点ではミニマム税率の水準は少なくとも表立っては議論になっていない。その背景には、この問題が高度に政治的であることに加え、そもそもブレンド方式が決まらないと税率も決められないという事情がある。
主要国が支持しているのが「国ごと」方式だ。この方式を支持する国は、例えばドイツやフランスといった高税率国と無税国の税率をブレンドする全世界方式に強い違和感を抱いている。ただ、国ごと方式では、ある国の税負担割合を算出する際に、その国から見た国外所得、外国法人税額を除外する作業が必要となるため、全世界方式に比べ事務負担は重くなる。
「事業体ごと」方式は、発想としては現行の外国子会社合算税制に近いが、こちらも仮に国外所得、外国法人税を除くという建付けにした場合には事務負担は増加することになる。外国子会社合算税制との接続を踏まえれば、事業体ごと方式が最も親和性があるとする意見もあるが、DDでは事業体ごと方式を推すような記述は見られない。一方、全世界方式の方が(ミニマム税率が妥当な水準に収まるのであれば)事務負担軽減の観点からは選択肢になり得るとの声もある。
「国ごと」方式については、今のところ企業はかなり消極的な見方を示しており、国外所得、外国法人税を除くことなく、その国に所在する子会社群が計上した所得、税額を単純に積み上げるというやり方でなければ対応できないとの意見も聞かれる。
米国企業はGILTI方式を変えたくないことから揃って全世界方式を推していると言われているが、各方式への評価は国によってかなりの温度差があるのが現状となっている。
論点3 適用除外
日本企業は適用除外求めるも、OECDは安易に適用除外を認めないとの立場
東南アジア等で合法的な税制優遇を受けている日本企業は、いずれのブレンド方式が採用されるかにより、税負担割割合の低下及び所得合算ルールへの抵触という形で大きな影響を受けることになりかねない。こうした中、日本企業からは「一定のカーブアウト(除外)が必要」との声も聞こえてくる。
OECDは、安易に適用除外を認めないことが、途上国が「意に反して」優遇税制を乱発しないことにつながり、それが税率の引下げ競争の歯止めになるとの立場をとっているものの、企業等への配慮からか、DDでは適用除外の考え方が2つ示されている。
1つは「事実及び状況」に基づくきめ細かなカーブアウトである。この方法であれば特定の状況への対応が可能であり、濫用リスクも低い一方、制度の複雑化が懸念されている。
もう1つの方法が、一定の基準に基づく客観的、形式的な適用除外である。GILTIでは、有形資産の一定割合を能動的所得見合いで合算対象から控除しており、こうした措置が念頭にあると見られる。ただし、DDはこの方法について、適用条件を示すためのコンプライアンスコストの増加及び濫用防止措置が必要になると警告している。
日本企業が適用除外を求める方向にあることは間違いないが、いずれの方式を主張するのかは上記「ブレンディング」の程度にも左右されることになる。全世界方式であれば「一定の基準」に基づく形式的な適用除外と親和性があり、事業体ごと方式であれば、個別企業の状況に即したきめ細かなカーブアウトと親和性があるということは言えよう。
12月9日に公聴会、「税率のブレンディング」と「適用除外」が最大の論点に
ここまで述べてきた「課税ベースの決定」「税率のブレンディング」「適用除外」という所得合算ルールの3つの論点のうち、「税務・会計数値の差異の調整」は技術的な論点と言える。一方、「税率のブレンディング」と「適用除外」は、その制度設計によっては、税負担割合の低下及び所得合算ルールへの抵触という形で日本企業に大きな影響を及ぼすことになる。したがって、税負担という観点からは、「税率のブレンディング」と「適用除外」が、当面は第2の柱における最大の論点となろう。
第2の柱に対するパブリックコメントは12月2日に締め切られ、12月9日にパリで公聴会が開催される。特にミニマム税率を決定する上での前提となる「ブレンド方式」に関する議論には注目が集まりそうだ。
なお、軽課税支払ルール、subject to taxルールについては、来年、別途パブリックコメントを実施することが示唆されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















