解説記事2021年10月04日 新会計基準解説 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の概要(2021年10月4日号・№900)
新会計基準解説
実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の概要
企業会計基準委員会 専門研究員 宗延智也
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、2021年8月12日に、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表(脚注1)した。本稿では、本実務対応報告の概要を紹介する。なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、ASBJの見解を示すものではないことをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 本実務対応報告公表の経緯
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)(以下「改正法人税法」という。)において、従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行することとされた。連結納税制度を適用する場合の会計処理及び開示については、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(以下「実務対応報告第5号」という。)及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(以下「実務対応報告第7号」といい、実務対応報告第5号と合わせて「実務対応報告第5号等」という。)を定めていたが、グループ通算制度への移行に伴い、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定める必要が生じたことから、ASBJにおいて検討が行われた。本実務対応報告は、2021年3月に公表した実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表に至ったものである。
なお、税効果会計を適用するにあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)第44項に従って、決算日において国会で成立している税法に規定されている方法に基づいて計算を行う必要があるが、改正法人税法の成立当初においては、グループ通算制度における繰延税金資産の回収可能性等の判断を行うことが困難であるとの意見が聞かれたことから、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「実務対応報告第39号」という。)において、改正前の税法の規定に基づくことができるものとする特例的な取扱いを定めていた。この点、実務対応報告第39号及び実務対応報告第5号等については、本実務対応報告の適用により、廃止することとしている(本実務対応報告第34項)。
Ⅲ グループ通算制度の概要
グループ通算制度は連結納税制度から移行されるものであり、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同様であるとされている。
一方で、制度の簡素化の観点で申告納付の方法が次のように見直されている。
・連結納税制度:企業グループ全体を1つの納税単位とし、親法人がグループ各法人の所得を合算した連結所得に対する法人税の申告納付を行う(図表1参照)。
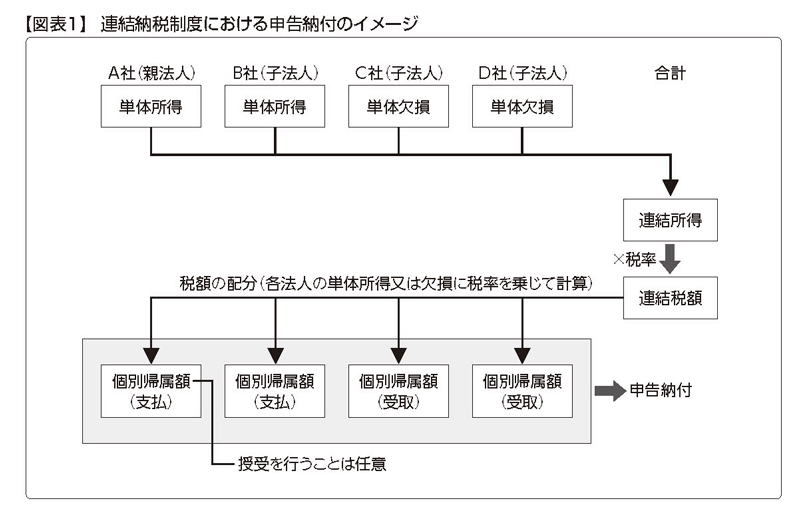
・グループ通算制度:親法人及び各子法人それぞれを納税単位とし、損益通算や欠損金の通算により欠損金や税務上の繰越欠損金を他の法人に配分することによって所得と欠損を通算した上で、親法人及び各子法人それぞれが税額の計算を行い、法人税の申告納付を行う(図表2参照)。
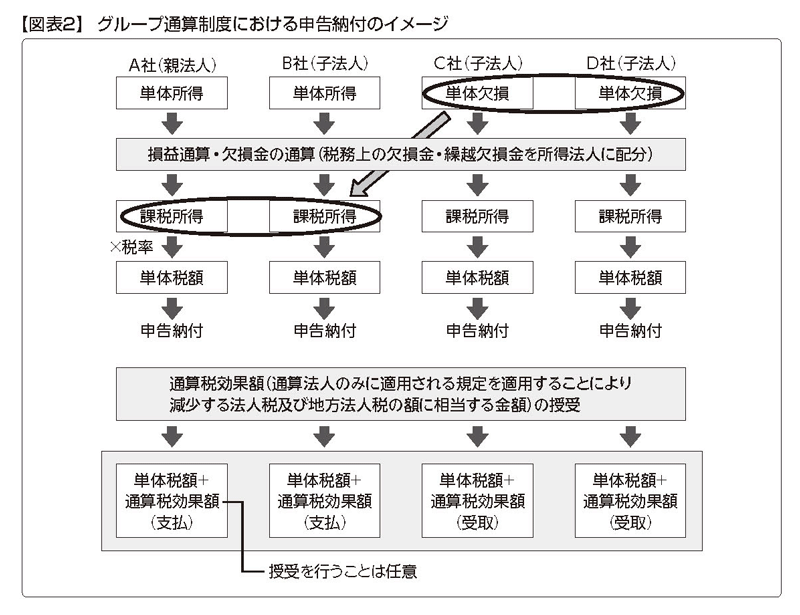
Ⅳ 本実務対応報告の概要
1 範 囲
本実務対応報告は、グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表並びに連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表に適用することとしている(本実務対応報告第3項)。
なお、本実務対応報告は、通算税効果額(脚注2)の授受を行うことを前提として会計処理及び開示を定めており、通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理及び開示については、連結納税制度における取扱いを踏襲するか否かも含め取り扱わないこととしている。これは、連結納税制度における個別帰属額と同様に、通算税効果額は通算会社間で金銭等の授受を行うか否かは任意であるが、連結納税制度においては個別帰属額の授受を行っている場合が多いと考えられ、グループ通算制度においても一般的には通算税効果額の授受を行うことが想定されること、また、通算税効果額の授受を行わない場合の取扱いの検討には一定の困難性があるものと考えられることによるものである。そのため、通算税効果額の授受を行わない場合の具体的な定めは存在せず、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4−3項に定める「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」に該当することになると考えられる(本実務対応報告第3項なお書き並びに第37項及び第38項)。
2 本実務対応報告の基本的な方針
グループ通算制度は、連結納税制度から移行されるものであり、「Ⅲ.グループ通算制度の概要」に記載のとおり、納税申告手続は異なるものの、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じである。そのため、本実務対応報告の開発にあたっては、基本的な方針として、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理及び開示を除き、連結納税制度における実務対応報告第5号等の会計処理及び開示に関する取扱いを踏襲することとしている(本実務対応報告第39項及び第40項)。
なお、実務対応報告第5号等では、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)又は税効果会計基準等(脚注3)で定めのある事項に従う場合でもその旨を記載しているが、本実務対応報告においては、本実務対応報告に定めのあるものを除き法人税等会計基準又は税効果会計基準等の定めに従うこととし、グループ通算制度に特有の会計処理及び開示のみを示すこととしている(本実務対応報告第41項)。
3 法人税及び地方法人税に関する会計処理及び表示
法人税等会計基準は、我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、住民税及び事業税等に関する会計処理及び開示に適用することとしており(法人税等会計基準第2項(1))、グループ通算制度を適用する場合の法人税及び地方法人税についても法人税等会計基準を適用することとしている(本実務対応報告第6項及び第42項)。
一方、通算税効果額については、通算会社間で授受が行われるものであるが、連結納税制度における個別帰属額と同様に法人税に相当する金額であるとされていることから、連結納税制度における個別帰属額の取扱いを踏襲し、個別財務諸表における損益計算書において、当事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしている(本実務対応報告第7項並びに第43項及び第44項)。
また、通算税効果額の表示についても、連結納税制度における個別帰属額の取扱いを踏襲し、法人税及び地方法人税を示す科目に含めて、個別財務諸表における損益計算書に表示し、通算税効果額に係る債権及び債務は、未収入金や未払金などに含めて個別財務諸表における貸借対照表に表示することとしている(本実務対応報告第24項及び第25項並びに第57項及び第58項)。
4 税効果会計に関する会計処理及び表示
(1)税効果会計を適用する上での会計処理の単位
税効果会計を適用する上では、「納税主体」ごとに繰延税金資産及び繰延税金負債の計算を行うことが想定されており、本実務対応報告の適用前における税効果適用指針第4項(1)では、「納税主体」を「納税申告書の作成主体をいい、通常は企業が納税主体となる。ただし、連結納税制度を適用している場合、連結納税の範囲に含まれる企業集団が同一の納税主体となる。」と定義していた。
ここで、納税主体を「納税申告書の作成主体」としつつも、連結納税制度を適用する場合は「納税申告書の作成主体」である連結納税親会社ではなく、企業グループ全体を納税主体としており、納税主体が何を指すのかが必ずしも明らかではなかったと考えられる。
この点、連結納税制度は企業グループの一体性に着目し、企業グループ全体をあたかも1つの法人であるかのように捉えて課税が行われており、連結財務諸表においては「課税される単位」を連結納税主体として税効果会計を適用していたものと考えられる。
一方、グループ通算制度においては、各通算会社が納税申告を行うことから、「納税申告書の作成主体」は各通算会社となるが、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは連結納税制度と同様であるとされており、グループ通算制度を適用する企業グループ全体が「課税される単位」となると考えられる。そのため、本実務対応報告では、連結財務諸表においては、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を1つに束ねた単位」(以下「通算グループ全体」という。)に対して、税効果会計を適用することとしている(本実務対応報告第14項並びに第46項及び第47項)。
(2)繰延税金資産の回収可能性の取扱い
① 個別財務諸表
個別財務諸表における損益計算書においては、通算税効果額を法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしていることから、個別財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっても、他の通算会社からの通算税効果額を考慮することとし、連結納税制度における取扱いを踏襲することとしている(本実務対応報告第50項)。
具体的には、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順において、期末における将来減算一時差異の解消見込額(将来加算一時差異の解消見込額との相殺後)を(ⅰ)一時差異等加減算前通算前所得の見積額、(ⅱ)損益通算による益金算入見積額の順に相殺し、相殺し切れなかった額は、(ⅲ)特定繰越欠損金以外の繰越欠損金として翌年度以降の損金算入のスケジューリングに従って回収が見込まれる金額と相殺することとしている(本実務対応報告第11項及び第51項並びに設例2及び設例3)(図表3参照)。
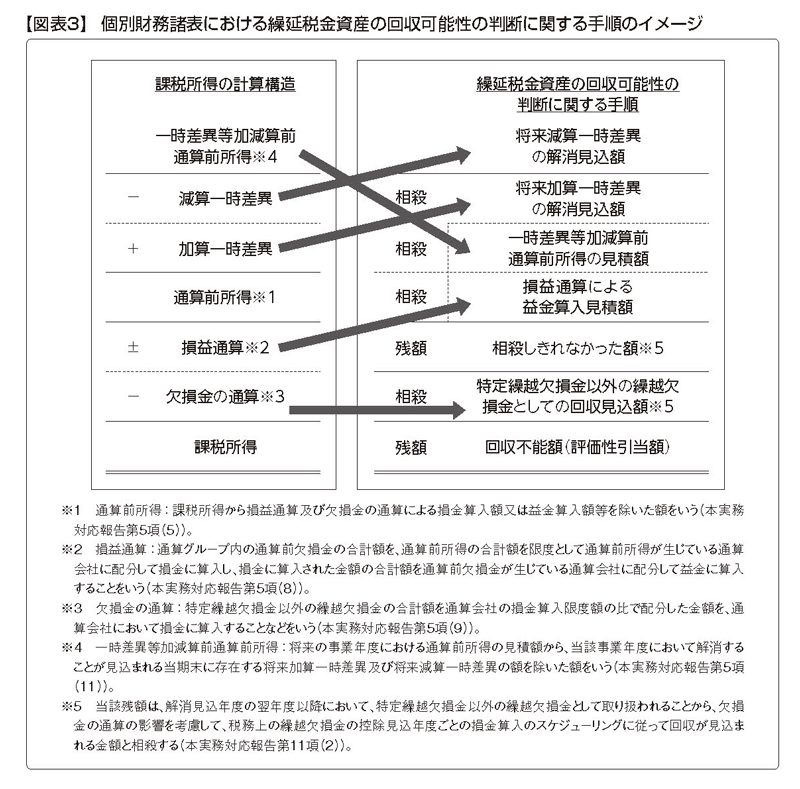
また、企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いにおいても、連結納税制度における取扱いを踏襲し、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性の判断については、通算グループ全体の分類と通算会社の分類のいずれか上位の分類に応じた判断を行うこととしている。なお、通算会社の分類の判定について、連結納税制度の実務では各社における個別所得額のみを用いて判定が行われていたものと考えられることから、グループ通算制度における通算会社の分類は、損益通算や欠損金の通算を考慮せず、自社の通算前所得又は通算前欠損金に基づいて判定することを明確にしている(本実務対応報告第13項及び第52項並びに設例4)。
② 連結財務諸表
連結財務諸表においては、通算グループ全体に対して税効果会計を適用することとしており、法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順や企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについても、通算グループ全体で判断を行うこととしている(本実務対応報告第14項から第17項及び第53項)。
(3)その他の税効果会計に関する会計処理
その他のグループ通算制度に特有の税効果会計に関する会計処理についても、連結納税制度の取扱いを踏襲し、図表4のように取り扱うこととしている。
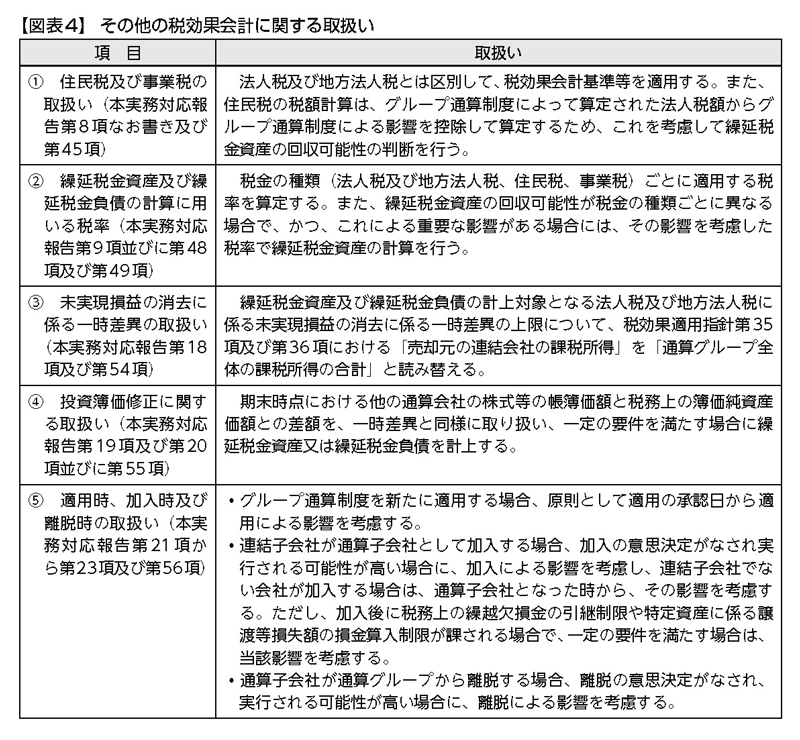
(4)繰延税金資産及び繰延税金負債に関する表示
法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の表示についても、連結納税制度の取扱いを踏襲することとし、個別財務諸表においては、税効果会計基準等の定めに従って、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示し、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺せずに表示することとしている(本実務対応報告第26項及び第59項)。また、連結財務諸表においては、通算グループ全体に対して税効果会計を適用することとしていることから、法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、通算グループ全体の繰延税金資産の合計と繰延税金負債の合計を相殺して表示することとしている(本実務対応報告第27項及び第60項)。
5 注記事項
(1)本実務対応報告の適用に関する注記
実務対応報告第5号では、連結納税制度を適用した場合又は取りやめた場合における最初の連結財務諸表及び個別財務諸表においてその旨を注記することが適当であると考えられるとしていたが、実務においては、多くの企業が適用初年度のみならず、その後の年度においても、重要な会計方針に連結納税制度を適用している旨の注記を行っていた。
グループ通算制度においても、適用開始から取りやめまでの期間において適用していることを示すことが、財務諸表利用者にとって有用となると考えられるため、グループ通算制度を適用した場合又は取りやめた場合に加えて、本実務対応報告により法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理を行っている場合には、その旨を税効果会計に関する注記の内容とあわせて注記することとしている(本実務対応報告第28項及び第61項)。
(2)税効果会計に関する注記
連結財務諸表及び個別財務諸表における税効果会計基準等に定める繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等の注記について、その内訳を税金の種類ごとに注記する必要はないとする連結納税制度における取扱いを踏襲し、法人税及び地方法人税と住民税及び事業税を区分せずに、これらの税金全体で注記することとしている(本実務対応報告第29項及び第62項)。
(3)連帯納付義務に関する注記
連結納税制度における連帯納付義務について、実務対応報告第5号では、通常、連結納税子会社が連帯納付義務を履行する可能性は極めて低いと考えられ、そのような場合には偶発債務の注記を行う必要はないものとしていた。
この点、連結納税制度では子会社が親会社の債務に対する連帯納付義務を負っているのに対して、グループ通算制度では通算子会社だけではなく通算親会社も連帯納付義務を負っている点などの相違があるものの、連帯納付義務は制度に内在する義務であり、グループ通算制度を適用している旨を注記することとしていることから、別途偶発債務としての注記を行う有用性は高くないと考えられ、連帯納付義務について偶発債務としての注記を要しないこととしている(本実務対応報告第30項及び第64項)。
(4)連結納税制度における取扱いを踏襲しなかった注記事項
① 税金の種類ごとに回収可能性が異なる場合の注記
実務対応報告第7号では、連結納税制度における取扱いとして、繰延税金資産から控除された金額(評価性引当額)について、税金の種類によって回収可能性が異なる場合には、税金の種類を示して注記することが望ましいとしていた。しかし、評価性引当額を税金の種類ごとに開示することによる情報の有用性は限定的であると考えられ、また、連結納税制度における実務において、当該定めに基づき注記を行っている企業はごく少数であることから、注記をすることが望ましいとの記載を踏襲しないこととしている。ただし、税金の種類によって回収可能性が異なる場合に、評価性引当額について税金の種類を示すことを禁止する趣旨ではなく、注記することを妨げるものではない(本実務対応報告第62項なお書き)。
② 個別財務諸表における繰延税金資産に関する注記
連結納税制度について、実務対応報告第7号では、連結納税親会社の個別財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の計上額が、連結財務諸表における回収可能見込額を大幅に上回り、その上回る部分の金額に重要性がある場合には、連結納税親会社の個別財務諸表に追加情報として注記することが必要になるとしていた。
これは、個別財務諸表において計上した繰延税金資産が連結財務諸表において取り崩される場合、個別財務諸表において分配可能額に含まれるものが連結財務諸表では資産性がないものとして扱われる点について、連結納税制度導入当初においては、財務諸表利用者に十分に認識されていないと考えられたことによるものと考えられる。
この点、連結納税制度が導入されてから十数年が経過し仕組みが周知されていると考えられることから、グループ通算制度においては、当該注記は不要であると考えられ、連結納税制度における取扱いを踏襲せず、特段の定めを置かないこととしている(本実務対応報告第63項)。
6 適用時期等
(1)原則適用
本実務対応報告の適用にあたって、実務上、システム対応等の一定の準備期間を要する可能性がある。しかし、税法においては2022年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が適用されることを考慮し、原則適用の時期として、2022年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとしている(本実務対応報告第31項及び第65項)。
(2)早期適用
税効果会計に関する会計処理及び開示については、より早期に企業の実態を適切に反映させる観点から、2022年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の期末の連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができることとしている。なお、十分な周知期間を確保することや、年度内における首尾一貫性を確保することから、四半期会計期間からの早期適用は認めないこととしている(本実務対応報告第31項ただし書き及び第66項)。
(3)経過措置
① 連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合
連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合においては、税制の変更による影響と会計方針の変更による影響があると考えられるが、会計方針の変更による影響については、本実務対応報告は実務対応報告第5号等の会計上の取扱いを踏襲しており、会計方針の変更によって重要な影響は生じないと考えられることから、会計方針の変更による影響はないものとみなすこととし、当該定めを一律に適用することとしている。また、会計方針の変更に関する注記は要しないこととしている(本実務対応報告第32項(1)及び第67項)。
なお、実務対応報告第39号の特例的な取扱いを採用している企業について、本実務対応報告の適用前においては税制の変更による影響が考慮されておらず、本実務対応報告の適用によって考慮することになることから、適用時において、税制の変更による影響を損益等として計上することとなると考えられる(本実務対応報告第67項なお書き)。
② 単体納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合
単体納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合について、通常の適用時の取扱いでは、グループ通算制度の適用の承認があった日を含む年度から、翌事業年度よりグループ通算制度を適用するものとして、税効果会計を適用することとしているが、税法におけるグループ通算制度への移行が行われる年度においては一定の準備期間を要すると考えられることから、当該定めによらず、原則適用及び早期適用の定めに従うこととしている(本実務対応報告第32項(2)及び第68項)。
(4)連結納税制度を適用している企業が単体納税制度に移行する場合
連結納税制度を適用している企業が単体納税制度に移行する場合については、税効果会計基準等の原則的な取扱いに従って会計処理を行うことなどから特段の準備期間は不要と考えられ、グループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出した日の属する会計期間(四半期会計期間を含む。)から、2022年4月1日以後最初に開始する事業年度より単体納税制度を適用するものとして税効果会計を適用することとしている(本実務対応報告第33項及び第69項)。
なお、3月決算を例に、上記の適用時期及び経過措置を示すと図表5のようになる。
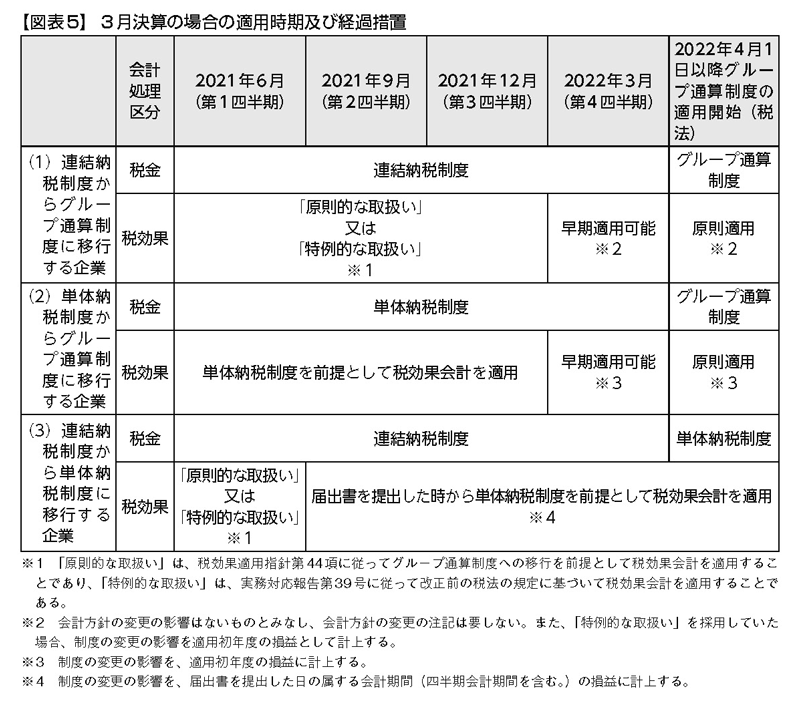
Ⅳ おわりに
本実務対応報告は、グループ通算制度に特有の会計処理及び開示のみを取り扱っていることから、本実務対応報告を確認するにあたっては、法人税等会計基準又は税効果会計基準等の会計処理及び開示の取扱いをあわせて確認いただきたい。また、グループ通算制度への移行に伴って、連結納税制度から取扱いが改正されている点があるが、これらのうち本実務対応報告に定めのないものについては、法人税等会計基準又は税効果会計基準等の定めに従うことになることにご留意頂きたい。
脚注
1 本実務対応報告の全文については、ASBJのウェブサイト
(https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html)を参照のこと。
2 通算税効果額は、損益通算や欠損金の通算などのグループ通算制度に関する法人税法上の規定を適用することによる税額の減少額であり、通算会社間で金銭等の授受が行われることが想定されている。
3 次の会計基準等を合わせて「税効果会計基準等」という。
・企業会計審議会が1998年10月に公表した「税効果会計に係る会計基準」及び同注解
・企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
・税効果適用指針
・企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















