解説記事2021年11月15日 ニュース特集 監査の「質」、会計士法で規律へ(2021年11月15日号・№906)
ニュース特集
上場会社監査事務所登録制度、法制化検討
監査の「質」、会計士法で規律へ
近年、監査法人を大手から中小に変更する上場会社が相次いでいるが、こうした中、「監査の質」の向上を目的とした公認会計士法の改正が検討される方向であることが判明した。
現状、上場会社の監査を行う監査法人が十分な能力・体制を有していることを担保する仕組みとして「上場会社監査事務所登録制度」があるが、十分に機能していないとの指摘がある。そこで金融庁は、公認会計士法を改正し、これを法律に基づく制度として規律することを検討する。
また、同じく公認会計士法の改正により金融庁によるモニタリングも強化され、「虚偽証明に係る監査手続」、すなわち個別の問題事案を金融庁が扱えるようにすることも視野に入れている。
さらに、現在は主に大手及び準大手の監査法人しか受け入れていない監査法人のガバナンス・コードの受け入れを中小監査法人にも求める方向。これに伴い、コードの内容を中小監査法人でも受け入れられるものに改訂することも検討する。改訂後のコードも受け入れられない中小監査法人は上場会社の監査から“退場”させられる可能性もある。そうなれば、こうした監査法人に依存していた上場会社は監査報告書を得ることができなくなり、最悪の場合、上場の維持が難しくなるケースが出てくることもあり得るだろう。
監査報酬の引き上げにより契約解除に誘導も
周知の通り、近年、業績が悪かったり規模が大きくない上場会社を中心に、監査法人を大手から中小に切り替える事例が相次いでおり(本誌750号40頁参照)、これに伴い、上場会社の監査を担う中小規模の監査法人が急増している(図表1参照)。
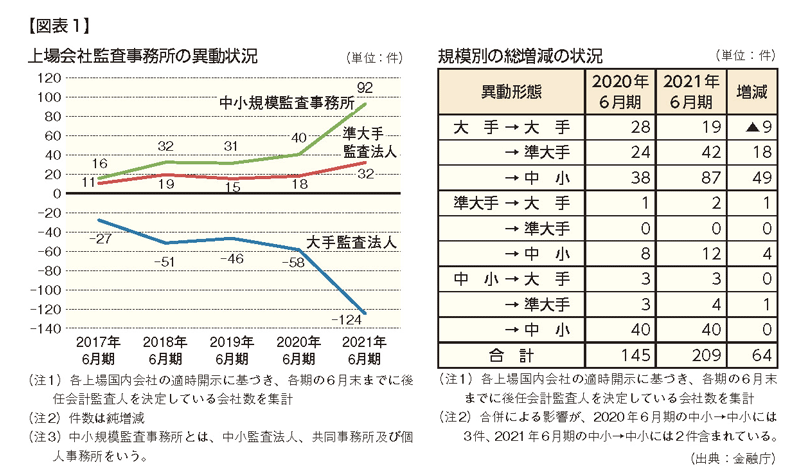
上場会社が監査法人を大手から中小に切り替える大きな目的の一つが、監査報酬の引下げだ。なかには、大手監査法人があえて監査報酬を引き上げることで、不正会計等のリスクがある上場会社を意図的に監査契約解除に誘導しているケースもあると言われている。実際、監査法人を変更した多くの上場会社では監査報酬額が減少している(図表2参照)。
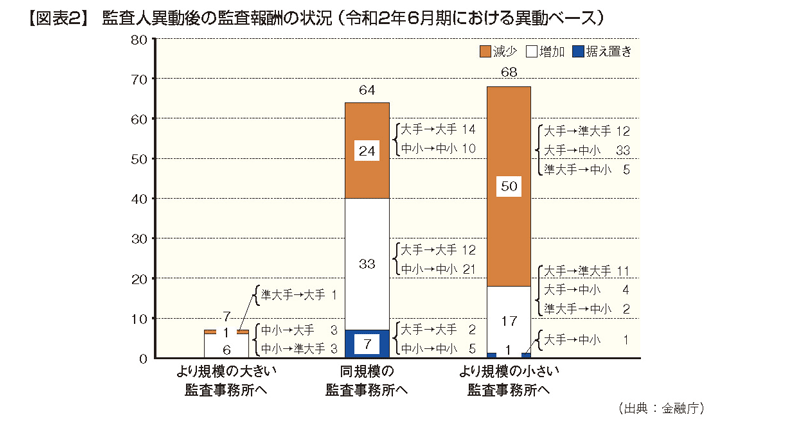
こうした中小監査法人による上場会社の監査の増加に伴い問われているのが、監査の「質」だ。金融庁は、大手監査法人から事監査契約を事実上解除された上場会社が中小監査法人の下で“緩い”監査を受け、結果として不正会計の温床となりかねないことを懸念しているとみられる。
「より高い規律付け」へ法律に基づく枠組みを検討
現状、上場会社の監査を行う監査法人が十分な能力・体制を有していることを担保する仕組みとして、日本公認会計士協会が「品質管理レビュー」を行った上で上場会社監査事務所名簿への登録を認める「上場会社監査事務所登録制度」があり、2021年3月末現在で127事務所が本登録している(準登録事務所(登録審査中)が13事務所)。各証券取引所の有価証券上場規程等では、上場会社の会計監査人は、上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿に登録されている監査事務所でなければならないとされており、また、新規の上場に際しての会計監査人は、上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所又は準登録事務所名簿に登録されている監査事務所のうち、品質管理レビューを受けた監査事務所でなければならない。ただ、この上場会社監査事務所登録制度は十分に機能していないとの指摘がある。
そこで金融庁は、これを法律に基づく制度として規律する方針を打ち出している。金融庁が設置した「会計監査の在り方に関する懇談会」は11月4日、「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理(案)−会計監査の更なる信頼性確保に向けて−」(以下、論点整理(案))を公表したが、その中に下記の記述がある。
【(2)上場会社の監査の担い手に対する規律の在り方(より高い規律付けの検討)】より抜粋
具体的には、現状の自主規制としての上場会社監査事務所登録制度について、登録審査やその後のレビューを通じて監査事務所が上場会社を監査するに十分な能力・態勢を備えていることを担保する規律としての実効性をより高める観点から、法律に基づく制度の枠組みを検討する必要がある。
ここでいう「法律」とは、公認会計士法を指すことが確認されている。
金融庁によるモニタリング強化も公認会計士法の改正で実現
監査の品質強化に向け、論点整理(案)では、会員への指導・監督を行う日本公認会計士協会の自主規制機能の更なる強化を求めているが、それ以上に注目されるのが、金融庁によるモニタリングの強化だ。
現状、金融庁は公認会計士・監査審査会を通じ、監査法人の「業務の運営の状況の検証」を行っているが、今後は「虚偽証明に係る監査手続」についても検証を行えるようにすることを検討する。これは、金融庁が個別の問題事案を扱えるようになることを意味しており、監査法人へのプレッシャーは大幅に強まることになろう。これも公認会計士法の改正により手当されることになる。
このほか論点整理(案)には、中小監査法人の監査の「質」を高めるための具体的な方法の一つとして、監査法人に一定の社員(パートナー)の数を求める意見も出ているとあるが、社員の数を増やすための形式的な合併を招くだけに終わる可能性もあることから、この意見が実現する可能性は低いものとみられる。この点は、「上場会社の監査を行う監査法人への規律付けの観点として適切であるかなお慎重な検討が必要と考えられる」という表現からも読み取ることができる。
中小監査法人にもガバナンス・コードの受入れ求める
また、上場会社を監査する全ての監査法人に対し、監査法人のガバナンス・コード(以下、適宜「コード」という)の受け入れを求める方針も打ち出されている。
現在、コードは主に大手及び準大手の監査法人しか受け入れていない(図表3参照)。
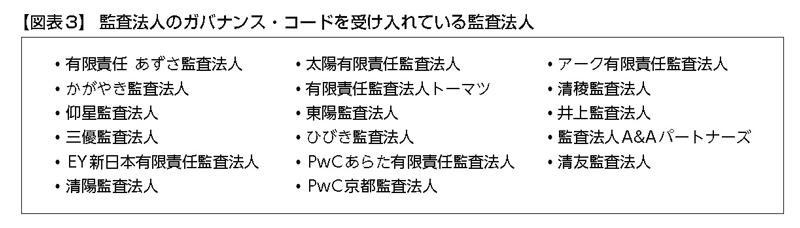
ただ、現状のコードは中小監査法人にはハードルが高いとの指摘もあることを踏まえ、コードの内容を中小監査法人でも受け入れられるものに改訂することも検討されるようだ。
監査法人のローテーションは見送り
監査法人の交代に関連した論点として、監査法人のローテーション制度があるが、同制度について論点整理(案)には下記の記述がある。
【2.「第三者の眼」によるチェック機能の発揮】より抜粋
なお、監査法人の独立性の確保を徹底する観点から監査法人自体を一定期間毎に交代させる「ローテーション制度」の導入については、上記のとおり、日本公認会計士協会において、報酬依存度に基づく新たなルールの導入等を内容とする倫理規則の改訂に向けた作業が行われていることを踏まえ、このルールが監査人の交代に与える影響も見極めながら、引き続き検討されるべきである。
「引き続き検討されるべきである」とはされているものの、これは要するに当面は導入しないことを示していると言って差し支えないだろう。
最悪のケースでは監査報告書を得られなくなる恐れも
これらの措置により、監査の品質に対する中小監査法人へのプレッシャーは大幅に強まることは間違いない。
監査の品質が低いと判断されれば上場会社監査事務所から外されたり、改訂後の監査法人のガバナンス・コードを受け入れられなければ、上場会社の監査から“退場”させられたりする事態も想定される。そうなれば、こうした監査法人に依存していた上場会社は監査報告書を得ることができなくなり、上場が維持できなくなることも考えられる。自社の監査法人の監査の品質が高くないと感じている上場会社は注意が必要だろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























