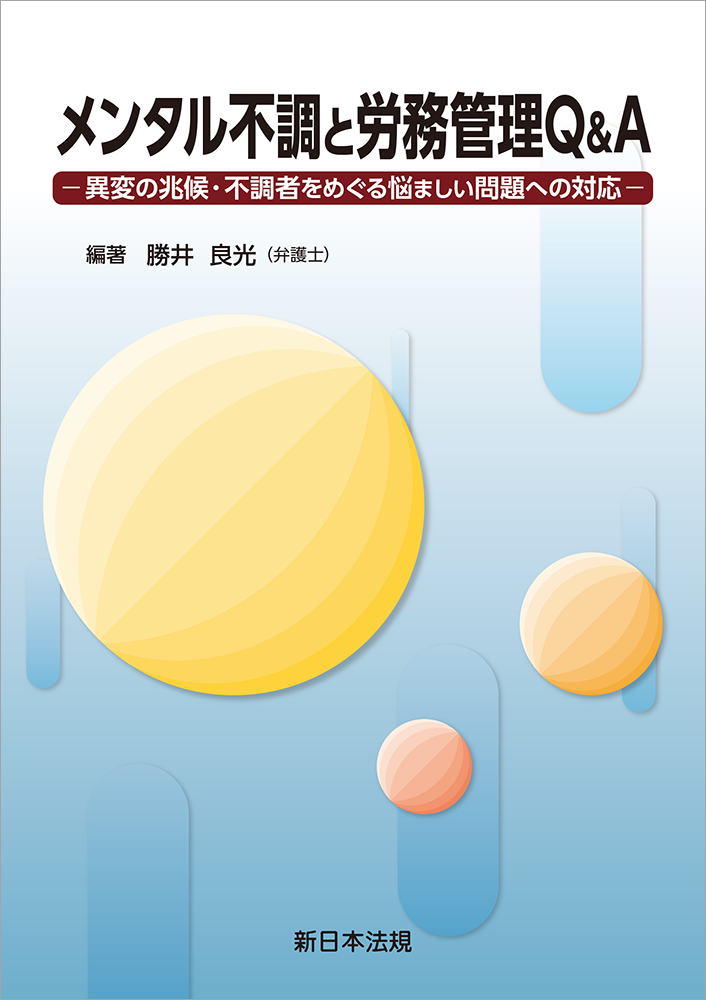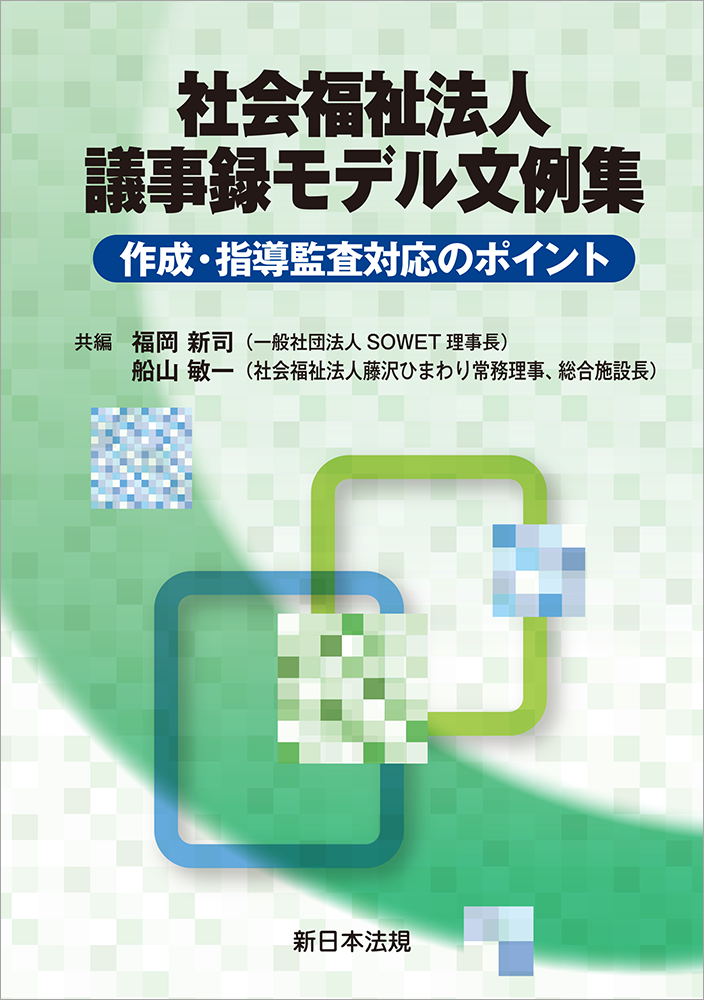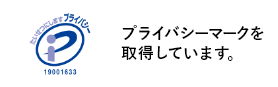解説記事2022年02月14日 ニュース特集 みなし配当の取扱い巡り税理士に3,800万円の賠償責任(2022年2月14日号・№918)
ニュース特集
裁判例や税務当局の見解なし、税理士の判断に“軽率”と指摘
みなし配当の取扱い巡り税理士に3,800万円の賠償責任
東京地方裁判所(金澤秀樹裁判長)で個人の税理士に対して約3,800万円の損害賠償を認める判決があった(令和3年11月11日)。裁判所は、みなし配当の規定の解釈に関する裁判例や税務当局の見解を示した資料などがなかったのであるから、少なくとも原告に対して総合課税の対象となる可能性があることを説明すべきであったとした。申告分離課税が適用できると判断したことに対しては、税務の専門家として「軽率である」と厳しく批判している。
「事業の全部の譲受け」に該当するか否かで税額が大きく異なる
本件は、原告(会社の元代表取締役)が、自身が経営する会社の株式等の資産を同社に売却するに際し、顧問税理士であった被告に対し、株式の売買による収入について申告分離課税を前提とする課税関係となる取引スキームを実行すべきコンサルティング契約を締結していながら、契約上の義務に違反したなどとして債務不履行に基づく損害賠償として約4,300万円の支払いを求めた事案である。
原告は、会社の代表取締役に就任後、役員報酬のほか、本社土地建物についての会社からの賃料収入及び原告自身が購入した不動産の賃料収入を得て、不動産に係る経費や父(前代表取締役)から相続した債務及び原告自身の借入債務を返済していたが、平成20年頃以降、会社の業績が悪化したことから、原告の役員報酬及び本社土地建物の賃料を減額した。
その後、原告は借入金返済の負担が重くなったため、被告の税理士は、借入金の負担から逃れる方法として、原告所有の不動産や株式を会社に買い取ってもらい、原告が会社の役員を退任し、借入金をゼロにすることを提案。被告は、原告に対して提案を実行した場合の税額等の試算を行った。試算を行う上では、資産売却が所得税法施行令64条1項4号(以下「施行令条項」、表1参照)に該当すれば株式売買による収入は譲渡所得として申告分離課税の対象(措法37条の10①)となるが、そうでなければ配当所得とみなされ(所法22条、24条、25条①)、総合課税の対象として税務申告をする必要があり、税額が大幅に異なるものであった。
【表1】施行令条項
| 所得税法25条(配当等とみなす金額)1項 法人(中略)、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。 五 当該法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する(中略)購入による取得その他の政令で定める取得(中略)を除く。) 所得税法施行令61条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)1項 法第25条第1項第5号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 四 事業の全部の譲受け(編注:本件「施行令条項」) |
税理士の調査では明確な結論を発見できず
この点、被告は日本税理士会連合会のデータベースを利用して施行令条項の解釈に関する調査を行ったが、所有する株式全部を売却した場合にまでみなし配当として課税するのはひどいと考える旨が記載された文献1点を除き、明確な結論を示した裁判例や文献を発見することができなかったが、原告が株式のほか、本社土地建物等も会社に売却し、会社の取締役についても退任することは、原告が会社と関係する事業すべてを売却したことになるから、本件資産売却は施行令条項に該当すると判断し、税額の試算を行った。
その後、原告は、株式売買に係る収入が譲渡所得として申告分離課税の対象になるとして確定申告を行ったが、税務署からの要請に基づき、配当所得があったことを前提とする修正申告を行うことになった。一方、税務署は、原告の会社に対しては配当についての源泉徴収を行わず、国に納付しなかったとして不納付加算税等の賦課決定処分を行った。会社は国税不服審判所に対して審査請求を行ったものの、棄却する裁決(平成29年裁決、表2参照)が行われた。
【表2】平成29年裁決
| 東京国税不服審判所は平成29年8月2日、請求人(会社)は自己株式を取得したものの、事業を前代表者から譲り受けたとは認められないから、自己株式の取得は、所得税法施行令61条1項4号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得には該当しないとの判断を示し、請求人は、自己株式の取得の際に支払ったみなし配当に該当する金額について源泉徴収義務を負うことになるとした(東裁(諸)平29−11)。 請求人は、自己株式の取得に際し、株主である前代表者に交付した金銭について、自己株式の取得は、所得税法25条1項に規定するみなし配当が生じない所得税法施行令61条1項4号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得に該当するから、みなし配当は生じないと主張していた。 |
税理士は好意で資産売却を試算と主張
被告の税理士は、原告から相談を受け好意で資産売却に関する試算を行ったものであり、原告とコンサルティング契約を締結した事実はないとしたほか、施行令条項の「事業の全部の譲受け」に該当するかどうか、当時の状況で必要とされる注意を尽くして検討及び調査を行ったなどと主張した(表3、4参照)。
【表3】当事者の主な主張①(被告が、原告との間でコンサルティング契約を締結し、同契約上の善管注意義務に違反したか)
| 原告(会社の元代表取締役) | 被告(税理士) |
| 原告と被告は、被告が①株式を1億5,392万円で売却し、これによる収入につき申告分離課税となるようなスキームを企画提案し、その実現に尽力すること、②土地建物を3億円で売却が実現することができるよう尽力すること、③原告が会社の代表取締役社長及び取締役を退任する際に退職慰労金として8,323万円が支給されるよう尽力するとの内容のコンサルティング契約を締結した。 被告は、コンサルティング契約のうち、上記①を実現するに当たり、専門家としての善管注意義務に基づき、株式売買により原告が得る収入につき申告分離課税となるスキームを実現する義務があり、資産売却が所得税法施行令61条1項4号に該当しないことについて、少なくとも税務署に対する問い合わせ又は国税局の事前照会を行うべきであった。 |
原告と被告がコンサルティング契約を締結した事実はない。 被告は、原告から役員報酬及び土地建物の賃料が減額されたことにより、債務の返済負担が非常に重くなっているとの相談を受けたことから、好意で原告の資産売却に関する試算をし、原告のために会社等との折衝等の協力を行ったが、原告との間で、被告が義務を負うような合意をした事実はない。被告が原告に対して報酬を提案したのは、最終的に資産売却等の取引が実現し、原告が利益を得ることになったため、別途依頼を受けていた平成25年度の税務申告の報酬請求のタイミングで、行った協力行為についての謝礼のような見返りを受け取れないかと考えたものであって、試算や協力行為について委任を受けていたことに基づくものではない。 |
【表4】当事者の主な主張②(被告が資産売却に伴う税額を誤りなく算定すべき義務を負うか及び義務に違反したか)
| 原告(会社の元代表取締役) | 被告(税理士) |
| 被告は、資産売却について、税理士に求められる善管注意義務の下、誤りなく税額を算定するとともに、資産売却が所得税法施行令61条1項4号に該当するかについて十分な法的根拠がないのであれば、資産売却の結果、1億5,000万円が手元に残らない可能性があることを原告に説明する義務があった。 | 資産売却が施行令条項にいう「事業の全部の譲受け」に該当するか否かは、社会通念に従った総合的な判断が求められるべきであり、原告が営む会社に係る事業を全て一体として同社に譲渡することで、会社は事業承継としての枠組みで融資を受けられるという共通認識の下、取引が行われたものであるから、被告の判断には正当性がある。また、平成25年当時、施行令条項について定まった解釈はなく、これを明確に示した文献、通達等の資料はなかったこと、被告は、税理士の調査で用いられるデータサービス及び文献を網羅的に検索し、当時の状況で必要とされる注意を尽くして検討及び調査を行った。 |
コンサルティング契約締結は認められず
裁判所は、被告は会社の顧問税理士であって、原告との間で資産管理契約等を締結したこともなく、原告の個人資産を管理すべき地位にはなかったのであるから、原告のためにその手元に1億5,000万円が確保される内容の資産売却等の計画を立案し、金融機関や会社との交渉を引き受けたのであれば、日常の業務とは別のものとして相応の時間と労力を要し、これに対する報酬を事前に定め、委任の趣旨を明確にするために契約書を作成するのが通常であると指摘。原告と被告との間で報酬についての協議等はなく、契約書等も作成されていないことからすると、原告と被告がコンサルティング契約を締結したとは認められないとした。
税額計算合意は委任契約で善管注意義務あり
次に原告が被告に税額の試算を依頼し、被告が了承したことについて裁判所は、税理士が依頼者との間で一定の事実関係を前提とする申告すべき税額の計算に係る事務をすることを合意した場合には、その合意の性質は委任契約あるいは準委任契約と解されることから善管注意義務を負っているとした。
施行令条項の「事業」は会社法と同義
その上で試算の前提となった資産売却が施行令条項の「事業の全部の譲受け」に該当するかどうかについては、所得税法等には事業譲渡等の意義を定めた規定は存在しないが、会社法467条1項1号ないし4号は事業譲渡等に関して規定しており、「事業」とは一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産であると解されているとし、施行令条項にいう「事業」とは会社法における事業と同義であるとした。
本件における資産売却は、①原告が保有していた本社土地建物及び株式を会社に売却するものであり、他に売却された財産はないこと、②原告は本社土地建物やその他の不動産を賃貸してその収入を得て、自らは会社の代表取締役として勤務していたものであり、本社土地建物及び株式を利用して個人として営業活動を行っていたとは認められないこと、③株式は会社の発行済み株式の4分の1強の割合にすぎず、原告が会社を完全に支配していた事実もないことに照らせば、本件資産が原告個人の営業のために組織化され、有機的一体として機能していたとはおよそ認め難いとして、資産売却が施行令条項に該当するということはできないとの判断を示し、株式売買による収入が申告分離課税の対象となることを前提とする試算は誤りであったとした。
税務の専門家として総合課税の対象となる可能性を説明すべき
また、裁判所は、被告は試算の時点までに施行令条項の適用如何で税額が大きく異なり、試算結果も異なるものとなることを認識していたこと、被告が調査した結果、施行令条項の解釈を明確に示した裁判例、税務当局の見解を示した資料、通説的見解の存在を示す文献等、被告の見解を裏付ける適当な資料を確認することができなかったのであるから、少なくとも原告に対して総合課税の対象となる可能性があることを説明するべきであったと指摘。その上で資産売却が施行令条項に該当することを否定する文献が存在しなかったとしても、「事業の全部の譲受け」との用語からすれば、同じ用語を用いる会社法の解釈を踏まえて判断すべきであることは当然であって、税務の専門家として、施行令条項に該当することについて確度の高い資料がないのに、典型的な事業譲渡とはその内容が異なる資産売却が施行令条項に該当すると判断することは軽率であるといえ、資産売却が施行令条項に該当しなければ原告にとって租税負担が大きくなり、想定外の不利な事態が生じ得る状況であったことに照らせば、税務の専門家としての注意義務を果たしたものとはいえないとした。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -